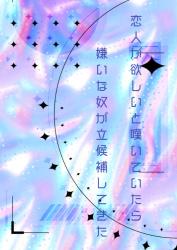終業式が終わるとあっという間に夏休みに入った。
僕は一日中、机に齧りついて漫画を描いている。
幼馴染と転校生の二人分のストーリーを描かなければならないので、時間がいくらあっても足りない。
描くことに集中していると呼吸を忘れてしまうらしく、唯斗くんから「息吸って!」と怒号が飛ぶ。
今日何度目かの注意を受け、唯斗くんは心配そうに眉を寄せた・
「そんなんで一人で大丈夫?」
「平気だよ」
「やっぱ残ろうか」
「ご家族が待ってるんでしょ? 顔見せてあげるのも親孝行だよ」
「でも……」
唯斗くんはすでにパック詰めが済んだキャリーケースを見下ろした。
唯斗くんは今日から東京の実家に帰るのだ。
どうやらおばあさんの体調があまりよくないらしく、入院してしまったらしい。顔を見せにこれないか、とご両親から連絡があったようだ。
でも唯斗くんは僕が無理しないか心配して、ギリギリまで引き伸ばしてくれたみたい。
僕はにっと口角を上げた。
「僕のことは心配しないで。向こうで会おうよ」
「本当に俺で務まるかな」
「唯斗くんはしっかりしてるから、大丈夫だよ!」
唯斗くんには僕のブースの売り子をやってもらう予定だ。
だから次に会えるのは半月後のコミケのときだ。
それまで寂しくなるけど仕方がない。僕のわがままでこれ以上唯斗くんを引き留めて、おばあさんになにかあったら大変だ。
ようやく唯斗くんは納得してくれたようで、渋々とキャップをかぶった。
「藍がそこまで言うなら行って来るよ」
「うん」
「なにかあったらすぐ連絡してね」
「わかった」
「毎日メッセージ送るね」
「そこまでしなくていいよ。遠距離恋愛するカップルじゃないんだから」
唯斗くんがあまりに心配するのでおかしかった。しかもちょっと死亡フラグっぽいし。
僕が笑っていると唯斗くんはぽかんの口を開けた。
「そりゃ心配するよ。大切な……親友なんだから」
「ありがとう」
唯斗くんはやさしいな。日だまりをたっぷり含んだシーツみたいに僕を包んで安心させてくれる。
僕は壁にかけてある時計を見上げた。
「そろそろバスの時間になっちゃうよ」
「あ、本当だ。じゃあコミケでね」
「うん! いってらっしゃい!」
夏の日差しに負けないくらい眩しい笑顔で唯斗くんは実家に帰った。
唯斗くんが帰省して二週間が経った。
その間は散々な日ばかり続く。
慣れない制作作業の連続で僕は疲れ果てていた。元々ネット関連には弱いのに、デジタルで絵を描くなんて無謀なことをしているからだろう。
いつも一枚絵や四コマ漫画みたいな少ないページしか描いていなかったので、いきなり二十ページ二冊はキツい。描いても描いても終わらない。
かなり甘くスケジュールを考えていた。
「これ以上はマズイな」
ずっと徹夜続きなので現実があやふやだ。少しでも気が緩むと線も歪み、トーンはズレ、かなり酷く仕上がってしまっている。
それを直すとまたさらに時間がかかるという悪循環を生んでいた。
八月に入り、コミケまであと十日だ。
焦燥感だけがジリジリと僕を追い詰め、睡魔に負けそうになると悪夢で叩き起こされる。
「しっかりしなくちゃ」
ポンと頬を叩いて、簡易冷蔵庫から栄養ドリンクを取り出した。最後の一本だ。そろそろ買いに行きたいところだけど、そんな余裕はない。
せめてキリがいいところまで終わらせよう。
僕は一気に瓶を煽った。
少しだけ意識がしゃんとする。
作業に戻ろうとタブレットに視線を戻すと机に置いていたスマホが鳴った。
画面を見ると唯斗くんの名前が表示されている。
僕は通話ボタンをタップした。
「……もしもし?」
『調子どう?』
「大丈夫だよ」
『本当?』
「もちろん」
唯斗くんが僕の息遣いすら窺うように押し黙った。
唯斗くんから見えていないと嘘を吐いてしまった。
本当はかなりギリギリだし、二日はまともに寝ていない。かろうじて風呂は入っているけど、髪はパサパサで目元に濃いクマがある。
もし唯斗くんが見たら青ざめてしまうだろう。
でも遠く離れた唯斗くんを安心させたい。
唯斗くんはふうと息を吐いた。
『そろそろSNSで告知しないとマズイんじゃない?』
「あ~そっか。忘れてた」
『サンプル送ってくれたら、俺が作っておこうか?』
「大丈夫。ちゃんとやるよ」
唯斗くんには見えていないのに僕はへらっと笑ってみせた。
しばらく沈黙が続き、僕がペンを動かすシャッシャという音だけになる。
その音に耳を傾けていた唯斗くんの声音に後悔が混じる。
『ごめん、俺が転校生も描いて欲しいって頼んだから無理させてるよね』
「決めたのは僕だよ。ちゃんとスケジュール管理できてなかった僕が悪い」
『俺……漫画のことなんにもわかってなかった。こんなに時間がかかるものだと知らなかったよ』
「それは僕も同じ」
漫画は一コマに数時間かけて描く。でも読まれるのは数秒程度だ。
時間をかけたからといって、読んでくれた人が同じ分だけの時間をかけてくれるわけじゃない。
でもどんなに短い時間でも、その人の心に届いてくれればいいのだ。
楽しいとか面白いだとか、嫌いでもいい。
その人の心に爪痕を残せれば、創作者として嬉しいことはないのだろう。
「唯斗くんと話してたらなんだか元気が出てきた」
『無理してない?』
「平気だよ。いまなら一気に終わらせられそう」
やる気スイッチが押されたようにみるみる活力が湧いてくる。だけど気持ちに比例するように全身が熱くなってきた。
クーラーがついているはずなのに、背中が薄っすらと汗ばんでいる。
でも身体の芯はなぜかひんやりとしていた。クーラーで冷えたのかな?
『藍の顔見たい。ちょっとだけテレビ通話にできる?』
「いいけど……いま、酷い顔してるかも」
『藍の顔はいつも可愛いよ』
「コンタクトの度数合ってないんじゃない?」
『ずっと裸眼だよ。じゃあ切り替えるね』
僕は慌ててスマホをスタンドに立てかけた。最後の悪あがきに前髪をちょっと手櫛で整えるけど、元の顔が大したことないので意味はない。あと栄養ドリンクも画角に入らないように端に寄せた。
画面に映った唯斗くんは実家の自室にいるらしく、黒で統一されたオシャレなベッドや本棚が背後に見える。
髪は毛先だけちょっとカールさせ、ブランドのロゴの入った白いシャツを着ていた。
おばあさんのお見舞いに行っていたのかもしれない。
僕が画面に現れると唯斗くんは目尻をきゅっとさせた。
『やっと藍に会えた』
「毎日メッセージでやり取りしてるでしょ」
『でも顔を見るのは久しぶり。えっと……二週間くらい経つかな。長いな~』
唯斗くんは頬杖をついたまま、大きく口を開けた。授業を怠けている生徒みたいに緩い表情に笑ってしまいそうになる。
けれど僕の頬はうまく動かない。
それに頭が煮えられているようにグツグツしてきた。
唯斗くんは画面を操作している。誰かからメッセージでも来たのかな。
そうすると急に画面がぐるりと変わる。唯斗くんはスマホを持ったまま、部屋を移動しているようだ。
「どうしたの?」
『ちょっと用事を思い出したから動いてるだけ。気にしないで』
「忙しいなら切るよ」
『全然平気。むしろこのままでいさせて欲しい』
唯斗くんの真剣な表情に僕は首を傾げた。邪魔していないならいいかな。僕ももうちょっと唯斗くんと話していたいし。
僕は作業の手を止めて、画面をみつめた。
「おばあさんの具合いはどう?」
『思ったより元気。顔見せに行ってよかったよ』
「きっとおばあさんも唯斗くんに会えて嬉しいんだね」
『そうそう。この前、おばあちゃんが硬いリンゴをそのまま食べたちゃって、入れ歯が抜けちゃったんだよ』
「えぇ!?」
『歯だけがリンゴに噛りついてるの。まじヤバかった』
「それはちょっと見てみたかったかも」
『もう家族全員大笑いでさ』
それからしばらく僕たちは他愛もない話をした。
もっといっぱい話していたいな。
でも栄養ドリンクの効果が切れてきたのか、段々眠くなってくる。
僕が目元を擦っていると、唯斗くんは画面を撫でた。
『ごめん、作業の邪魔してるよね。そろそろ切るよ。またあとでメッセ送るね』
「うん、待ってる」
『じゃあね』
「バイバイ」
通話を切ると部屋の中が一気に静かになった。
まるで森の中に一人取り残されたように物悲しい。
「しっかりやらなくちゃ」
唯斗くんに励ましてもらえたから頑張ろう。
タブレットに視線を戻すとなぜか目の前がぐらりと歪む。これはマズいやつだ。
支えることもできずに僕の額はごんとタブレットの上に落ちた。液晶画面が温かく、瞼の裏が点々と明るい。
「やば……作業、しない……と」
胃の中が洗濯機みたいにぐるぐる回転している。吐き気がせり上がってきたが、えずくだけに終わった。まともに食事をしていないから胃は空っぽだ。
僕はそのまま引きずられるように意識を手放した。
柔らかな背中の感触とひんやりする額に、僕はゆっくりと瞼を開けた。
「目が覚めた?」
「……唯斗くん? 学校、遅刻しちゃう?」
「まだ寝ぼけてるみたいだね」
唯斗くんがふんわりと笑って、僕の額に手のひらを置いた。冷やされたタオルみたいに気持ちいい。
うっとりと目を細めそうになり、僕は机の上に乱雑にある栄養ドリンクの存在に気づいた。
ばっとさっきまでの記憶が流れてくる。
「原稿!」
僕が起き上がると視界がぐらりと歪む。前のめりに倒れそうになり、唯斗くんの逞しい腕が支えてくれた。
「急に起きたらだめだよ。熱があるんだし」
ベッドに寝かせてもらうと身体が鉛のように重たかった。身体の芯は寒いのに、額は薄っすらと汗ばんでいる。
「唯斗くん。東京は? おばあさんはどうしたの?」
唯斗くんとはさっきまでテレビ通話をしていたはずだ。それがどうして寮に帰って来ているのか意味がわからない。
「順番に説明するね」
唯斗くんはベッド横に腰を下ろした。
「藍とテレビ通話して具合いが悪いのがすぐわかった。だから水間にメッセ送って、様子を見て貰ったら部屋で倒れてたんだよ」
「唯斗くんの顔を見たら安心しちゃって」
「んん!」
唯斗くんは喉に異物が入っているかのように大きな咳払いをした。
「俺は電話しながら準備して、すぐこっち来たんだ」
「だから画面が揺れてたんだね」
「そう。水間から倒れてるってきたときは心臓が止まるかと思った」
「心配かけてごめん」
「さっきまで寮監の先生と病院の先生も来てくれてたんだよ。診察中もずっと目を覚まさなくて、このまま死んじゃうんじゃないかって」
膝の上に握られている唯斗くんのこぶしが震えていた。どれほど不安にさせてしまったのか、痛いくらい伝わってくる。
唯斗くんは机に視線を向けた。
「どうしてそんな無理もしてたの?」
「だってなかなか作業が終わらなくて」
「でも身体壊してまでやることじゃないでしょ」
ごもっともな意見だ。
でも僕には描きたい理由があった。
「二人を幸せにできるのは僕だけなんだよ」
「ん?」
「描いてる漫画の二人、いや三人か。それを幸せにも不幸にもできるのは僕だけなんだ。だから生半可なことはしたくなくて」
三人は本気で恋をしているのだ。それに見合うだけの画力をあげたくて、突き動かされるようにペンを走らせていた。
髪の毛一本にも神経を使って描いているのだ。
作品は我が子同然という気持ちがよくわかる。
手塩にかけたキャラクターたちを大切に育ててあげたい。
「だから根詰めて描いてた。大丈夫って嘘吐いたくせに、迷惑かけてごめんね」
「迷惑だとは思ってないけど、嘘吐いたところは反省してもらいたいな」
有無を言わさない笑顔に僕は顔を青ざめながら頷いた。
そこではたと気づく。
「おばあさんは? 東京は?」
「ちゃんと家族に許可取って戻ってきたよ。だから安心して」
やさしく笑ってくれる唯斗くんが部屋にいる。なんだかほっとする。陸に打ち上げられていた魚が海に返してもらえたように活力が漲ってきた。
「あの〜……オレも一応いるんですけど」
シンタが気まずそうに挙手をすると唯斗くんは片眉を跳ねさせる。
いつからシンタがいたのか、扉の前に立っていた。
唯斗くんがぐるりと首を向ける。
「水間、まだいたの。もう大丈夫。あとは俺がやるから」
「ひどっ! これでもすっとんで来て、先生とかに連絡したのはオレなんですけど」
「それは感謝しるよ。さっき東京バナナあげたでしょ」
「なんっか誠意を感じられないんだよな」
シンタは首を捻りながらも、右手にはしっかりと東京バナナの紙袋を持っていた。
だけどシンタの言うこともわかる。なんだか唯斗くんの言い方には棘を感じるのだ。
たくさん話したせいか、再び眠気が襲ってきた。僕がうつらうつらしていると冷たい手が頰に触れてくれる。
視界いっぱいに唯斗くんのやさしい笑顔が映った。
「寝てていいよ。ずっとここにいるから」
「……ん」
唯斗くんの大きな手が頭を撫でてくれる。こんな風に甘やかされるのは子どものとき以来だ。
あまりの気持ちよさに僕は再び夢の世界に落ちていった。
目が覚めるとカーテンの隙間から朝日が差し込んでいた。細い線がまっすぐと唯斗くんの方へ伸びている。
昨日までぺしゃんこだったベッドが規則的に上下していた。布団の隙間から整った寝顔が見えて、唯斗くんが帰ってきてくれたのだと実感できた。
唯斗くんがいる。
ただそれだけで朝の目覚めが何倍も気持ちがいい。
上半身だけ起き上がると驚くほど身体が軽かった。燻っていた熱も引いている。
太陽に向かって芽を伸ばすつくしのように伸びをすると、背骨がボキボキと鳴る。その痛みが思考をすっきりさせてくれた。
肩を回して軽いストレッチをしていると、唯斗くんの布団がもぞりと動く。
「ん……藍?」
「ごめん、起こしちゃった?」
「調子はどう?」
「もう平気」
「元気そうでよかった」
「唯斗くんのお陰だよ」
僕たちは同時にふふっと笑いあった。
僕は再びベッドに横になり、そのまま会話を続けた。
「唯斗くんがこの部屋にいてくれるだけで嬉しい」
「寂しかったの?」
「ちょっと……ううん、すごく寂しかったよ」
「え」
「唯斗くんが来るまでずっと一人だったのに変だよね」
唯斗くんのいない部屋は冷たい深海にいるように静かで、孤独だった。
ずっとそんな暮らしをしていたのに唯斗くんと過ごして、僕は変わってしまったんだ。
「ご家族のことを考えると心苦しいんだけど……唯斗くんが帰ってきてくれて嬉しい」
僕はタオルケットを引き上げて顔の半分を隠した。じわじわと頬が熱くなる。
高二もなってなにを甘えたことを言ってるんだ。
だけど唯斗くんは呆れた様子もなく、にっと口角を上げた。
「そっち行ってもいい?」
「どういうこと?」
「こういうこと!」
ベッドから降りたかと思ったら、唯斗くんはするりと僕のタオルケットの中に潜り込み、ぎゅうと抱きしめてくれた。
シトラスの香りに包まれ、僕の心臓は激しく鳴り始める。
「こ、これは……どういう状況!?」
「親友ならこれくらいするよ」
「シンタとやったことないけど」
「じゃあ水間とは友だちってことだね。これが普通だよ」
「普通?」
「そうだよ」
淀みのないまっすぐな言葉に僕は渋々と頷いた。当たり前ならいっか。いや、いいのか?
疑問はあるけどいまは考えないことにする。だって唯斗くんに触れているだけで幸せな気持ちになれるのだ。
僕は胸板に耳を押しつけて、唯斗くんの心音を聞いた。僕以上に激しく鳴っている。唯斗くんも恥ずかしいのかな。
親友なら普通なのに変なの。
僕はそっと唯斗くんの背中に腕を回した。隙間がないほど密着できると安心するのに、足の裏を擽られたようなそわそわする。
ピコンと頭の中の電球が光った。
「あ、これさーー」
「構図撮るから離れるのはナシだよ」
「……まだなにも言ってない」
「違った?」
「違くないけど」
そんなに僕ってわかりやすいかな。
「前にも似たようなことあったでしょ」
「あ~壁ドンのとき?」
「あんな衝撃なかなか忘れられないよ」
僕の前髪をさらりと撫でる唯斗くんの手つきはやさしい。この手は魔法みたいだ。触れられているだけで段々と眠くなってくる。
「ふぁ……」
「眠くなってきた?」
「ん……でもそれよりお腹すいた」
「いい傾向だね。昨日からほとんど食べてないんでしょ?」
「うん」
昨日というよりここ数日まともに食事をしていない。原稿のことで頭がいっぱいで、空腹を感じなかったのだ。
でもいま胃が空っぽなのがわかる。
そんな感覚を取り戻せたのは唯斗くんがいてくれるからだ。
「食堂あくまであとちょっとだけ、こうしていい?」
「え」
「いまちょっと甘えたい気分」
唯斗くんは黙ってしまった。クーラーの稼働音だけが響く。
一人のときは孤独を嘲笑うかのような音だったのに、いまはそう聞こえない。
不思議だ。唯斗くんといると世界が別物に見える。
「……俺が我慢強いからって試されてるのか。いや、藍はそんなことするタイプじゃないよな」
「唯斗くん?」
もしかして嫌だったのかな。
僕が不安気に顔を上げると苦いものを食べたように唯斗くんは顎に皺を寄せていた。
「……いいよ」
「ありがとう。へへっ、嬉しいな」
僕は食堂が開くまで唯斗くんにぎゅっと抱きしめてもらっていた。
結論から言えば、漫画は間に合わなかった。
中途半端な作品にしたくなかったし、準備不足のまま初めてコミケに参加して周りに迷惑もかけたくない。
お金がもったいない気がしたけど勉強代だと思うしかないだろう。
僕は机にスケッチブックを広げた。
「もっといいネームを作るぞ」
僕が気合いをいれていると唯斗くんが課題ノートから顔を上げた。
「ネームできてなかったの?」
「幼馴染の方はペン入れまで済んでるけど、転校生の方がね」
まだ本人には内緒だけど、転校生キャラはかなり唯斗くんに寄せている。
イケメンでみんなにやさしいけど、受けだけを特別にしてくれる人だ。
だからつい「唯斗くんならどうするかな」と考えてしまって、何度も描き直していた。
唯斗くんは僕のスケッチブックを覗こうと身を捩った。
「ちょっと見たいな」
「だめ。完成したらね」
「いいじゃん。ちょっとだけ」
「だめ」
「ちぇっ」
おもちゃを買ってもらえなかった子どものように唇を尖らせる唯斗くんがちょっとだけかわいい。
「うっす、邪魔するぞ」
「あ、もうそんな時間?」
ノック音とともに入ってきたシンタを見て、僕は壁にかかっている時計を見上げた。時刻は朝の十時を過ぎている。
課題を終わらせるためにシンタが僕たちの部屋に来る約束をしていたのだ。
というかシンタは唯斗くんの課題を写すのが目的だろうけど。
シンタはひょいと紙袋を僕に渡した。
「これ土産」
「ありがとう! あ、僕の好きなお菓子だ」
「それはおばさんが持っていけって」
「なにか言ってた?」
「一日でもいいから帰って来いだってよ」
「う~だよね」
シンタの家と僕の家は隣同士だ。だからなにかと母さんはシンタから僕の様子を訊いているらしい。
置いてあるクッションに座り、シンタは折り畳みテーブルの上に課題を広げた。
「嫌がらず帰ってやればいいのに」
「嫌ってわけじゃないんだけど」
「家族と仲がいいんじゃなかったっけ?」
唯斗くんが目をぱちくりとさせた。
僕が親孝行だよ、と説得して唯斗くんを東京に帰らせたくせに、自分は帰ってないなんて身勝手な奴だと思われてるかもしれない。
「仲はいいんだけどね」
「藍の母ちゃんはインパクトが強い」
シンタは勝手にスナック菓子の封を開けて食べ始めた。コンソメ味が部屋に広がる。
唯斗くんの頭にクエスチョンマークが飛び交っていた。
「どういう系? もしかしてヤバい感じの?」
「簡単に言えばギャルだな」
シンタの答えに僕は頷いた。
「母さんは僕と真逆の性格なんだ。明るくひょうきんで、一度決めたら曲げなくて、気が強い。僕が不登校のときも一人で学校に乗り込んで、大暴れして警察沙汰になったし」
「それは……すごいね」
「たまたま校長先生が母さんの昔の担任だったから大丈夫だったけど、下手してたら傷害罪で捕まってたかもしれなくて」
「それだけ聞くとインパクトは強い」
唯斗くんは頷いているのを見て、僕は肩を落とした。
母さんは家族をとても愛してくれている。小さいときはよく一緒に遊んでくれて、誕生日には大きいホールケーキを作ってくれた。数えきれないほどの楽しい思い出がある。
家族を大切にする母さんだからこそ、不登校の原因がクラスメイトだと知ったときは豹変した。
般若のような形相で授業中の教室に入り、机を片っ端から投げ飛ばしたのだ。いじめの主犯格に詰め寄り、殺伐とした雰囲気だったらしい。
大切にしてくれているからこその衝動だと理解してるけど、僕はそこまでして欲しかったわけじゃないのだ。
唯斗くんはぱんっと手を叩いた。
「俺、藍のお母さんに会ってみたい」
「えぇ! ビックリしちゃうよ?」
「でも藍のことをとても大切にしてるんでしょ」
「そうだけど」
「新学期始まってから一度も帰ってあげないのはさすがに寂しいよ。ほら、親孝行じゃないの」
唯斗くんに言葉を返されてしまえば、言い返す権利は僕にはない。
確かにずっと帰らないというのは、よくない。
「わかった……じゃあ今日帰ろうかな。明日だとひよっちゃいそう」
「そうと決まればすぐに行こう!」
「なんで唯斗くんが乗り気なの?」
「藍のご両親にちゃんと挨拶しておかないと」
わざわざ寮の同室だと挨拶してくれるんだ。唯斗くんはなんて真面目なんだろう。
そそくさと唯斗くんが着替え始めるので、僕も慌てて立ち上がった。
一人ぽつんと残されたシンタはげんなりしている。
「オレが来た意味ってなんなわけ?」
寮からバスと電車を使って三十分ほどの距離に僕の実家がある。
住宅が多くひしめき合う高台で、海も見渡せる静かな住宅地だ。
僕は約半年ぶりに見る玄関扉の前で固まった。
『おにいちゃんのほうがおおきい!』
『早い者勝ちだ!』
『ゆんね、さっきね』
『いいからさっさと食べなさい!』
ちょうど昼食を食べているのだろう。弟妹の争う声とそれを制止する母さんの声が玄関扉を突き抜けている。
情景がまざまざと浮かび、僕は頭を抱えたくなった。
相変わらずうちの家族は落ち着きがない。
僕は隣の唯斗くんを見上げた。
「覚悟はいい?」
「どういう意味?」
中の音が聞こえているだろうに唯斗くんは呑気に笑っている。まだ僕の家のことを全然理解していない。
我が家の状況を熟知しているシンタは、課題をやるからと家に帰った。十中八九逃げたのだ。
よし、ともう一度気合いを入れ直し、僕はインターホンを押した。中で誰が出るかで揉めている声がして、母さんがぴしゃりと怒鳴りつけると水を打ったように静かになる。
『はい』
「えっと、ただいま」
『……藍!?』
ドタドタと廊下を走り、突風のような勢いで扉が開いた。鼻先にびゅんと扉がかすめる。
取っ手を持ったまま母さんは目を見開いた。
「うわっ! 本物!!」
「ニセモノが来るわけないでしょ」
「あんた半年も顔見せなかったじゃない。なに急にどうしたの? またイジメられた?」
「なんでそうなるの」
僕は母さんの斜め上にいく返答に笑ってしまった。
全然変わってない。
根本が黒くなった金髪にキャラクターもののヘアバンドをつけた母さんは、最後に会ったときと変わらず目の前にいた。
懐かしさが胸に広がって、僕を安心させてくれる。
「だれ~? らんにいちゃんだ!」
弟妹たちが怪獣のような足音を響かせて、玄関にぎゅうぎゅうに集まった。
六歳の双子の妹は前に会ったより随分と背が伸びている。二人とも前歯が抜けて歯抜けの笑顔を向けてくれた。
「いま食事中なのにタイミング悪いな」
十歳の弟はぶすっとした顔をしているけど、嬉しさが隠しきれていないのか口元が緩んでいる。こっちも随分と背が伸びて、肌が真っ黒だ。なんだか目線が近い気がする。
僕が順繰りに弟妹たちを見ていると母さんが手を挙げた。
「ちょいちょいちょい待て、藍。そのイケメンはどこの誰でいらっしゃるで候?」
母さんが変な日本語を使い、僕の隣に佇んでいる唯斗くんを見上げた。
今日は仕事が休みだったのだったのか、母さんはすっぴんで眉毛が薄い。しかも部屋着がなぜか僕の中学生のころのジャージだし。
いや、恥ずかしそうに頬を赤く染めないで。母親の女の部分を見せられるほど、恐怖が先にくる。
弟妹たちも唯斗くんに気づき、目をぱちくりとさせていた。
四人の視線を受けた唯斗くんは、爽やかな笑顔を浮かべて、頭を下げている。
「初めまして、藍くんと同室の宇梶唯斗です」
しばらく四人は唯斗くんを見つめたかと思うと同時に口を広げた。
「「「「イケメンがきたぞー!!」」」」
四人の絶叫に隣家のシンタが覗きに来たのは言うまでもない。
「ごめんね、騒がしくて」
「いいよ。すごく楽しいし」
「でも」
「もう土下座はいいから」
僕はフローリングに擦りつけていた顔を上げた。
その唯斗くんはテレビ画面に顔を固定されたまま、やさしい笑顔を浮かべている。両脇には双子が立ち、唯斗くんの髪を結んだり、メイクを施していた。
姉のゆらがぶんぶんと首を振る。
「だめ、このふわふわゴムのほうがギャルっぽい」
「ぜったいこっちいちごだよ」
「ならアイシャドウはみずいろじゃなくてピンクにして。いろあわせないと、へんでしょ」
「ゆいとくんは、ぜったいあおがにあうもん!」
唯斗くんを間に挟み、双子たちの喧嘩が始まってしまった。我が家ではいつものことである。
「ねぇ唯斗兄ちゃん、次はこっちのゲームをしようよ」
マイペースな弟は新しいゲームソフトを出した。人気キャラクターを使ってカーレースをする昔からある定番ゲームだ。
唯斗くんは目尻を下げた。
「いいよ。へぇいま十五まで出てるんだ。俺がやってたときは、十くらいだったのに」
「でもこれ一個前だから、いまは十六だよ」
「そんなにシリーズ続いてるの? まだアヒルいる?」
「ゆいとくん、うごかないで」
「アイシャドウぬるからめ、つむって!」
「ちょっとママのリップないんですけど!!」
みんなの声に負けないくらい襖越しに母さんの怒鳴り声が聞こえる。双子は同時顔を見合わせてしれっと笑った。
妹のゆんの手元には、黒い光沢のあるリップケースが握られている。
僕はそれを奪い、襖の隙間から母さんに返すと「ゆん!」と見事犯人の名前を言い当てた。
さすが母さんだ。
「あ~バレちゃったじゃん。リップどうする?」
「あかいやつしかないよ」
「ねぇ、唯斗兄ちゃん。早くやろうよ」
聖徳太子でも聞き取れないほど、あちこちから弟妹の声が飛び、ロックフェス並みのうるささだ。
僕は再び土下座したくなったが、唯斗くんはふわっと笑っている。
「元気な家族だね」
「ごめん、うるさいでしょ?」
「誰がうるさいってー?」
襖越しでも母さんには聞こえたらしい。それでもリビングに顔を出さないのは、メイクをしているからだ。
イケメンを前にどうにか取り繕うとしているのだろうか。
恥ずかしいからやめて欲しい。
僕ががっくりと肩を落としていると、相変わらず唯我独尊な弟は唯斗くんのシャツを引っ張った。
「ほら、ゲーム始まったよ。早くキャラ選んで」
「ちょっとうごかないで! うまくむすべない」
「め、あけちゃだめだってば」
唯斗くんは弟とゲームをしながら、双子たちのためにマネキンとなってくれている。
かなり器用だ。
あちこちから要求がきても、唯斗くんは嫌な顔一つせずにこやかな笑みを浮かべた。
「ごめんね。アイシャドウ塗り終わったらキャラ選ぶから。頭は動かさないようにするね」
どうしてそんなやさしいんだ。
僕だったら三秒でギブなのに、唯斗くんは懐が大きすぎる。
僕は土下座はやめて、唯斗くんの隣に座った。
「唯斗くんって一人っ子なのに、なんでそんな小さい子の扱いうまいの?」
「よく想像してたからかな〜兄弟がいたらどうなんだろうって」
テレビに向けられた横顔に翳りが見える。ちょっと寂しそうに感じたのは、唯斗くんの痛い部分に触れてしまったせいだろう。
もしかして兄弟がずっと欲しかったのかな。
僕は距離を詰めて、肩同士を触れ合わせた。びくりと唯斗くんの身体が跳ねる。
唯斗くんに抱きしめてもらえたとき、とても安心したのだ。だからいま、それを返したい。
さすがに弟妹たちの前で抱き合えないから、その代わりだ。
アイシャドウが済んだ唯斗くんはゴリゴリギャルメイクを僕に向けた。
双子の妥協案でパープルのアイシャドウが唯斗くんの白い肌に合っている。
僕はふふっと笑った。
「似合ってるよ。すっごいギャル」
「ほんとう~? 嬉しいぃ~」
語尾を伸ばしながら話すとまさにギャルだ。イケメンはどんな化粧でも似合うものらしい。
痺れを切らした弟は「ねぇ」と声を張り上げる。
「唯斗兄ちゃん! 早くキャラ決めてよ~」
「おかおはまえむけて!」
「ごめん、ごめん」
唯斗くんは慌てて顔を正面に向けた。その頰がちょっと赤いのはメイクのせいかな。チークつけすぎじゃないか?
でもこうやってみんなで騒いでいるの楽しいかも。
僕が唯斗くんにくっついたままでいるとゆんに髪を引っ張られた。
「らんにいちゃんも、むすんであげる!」
「僕はいいよ〜って痛い! ちょっとやさしくして!」
「キャハハ」
立ち上がって逃げるとゆんが追いかけてくる。それを見たもうゆらも混ざり、リビングをぐるぐると回った。
「静かにしなさい! 近所迷惑でしょ!!」
襖をがんと開けた母さんの怒鳴り声すらも楽しさに代わり、僕たちはずっと笑っていた。
メイクを済ませた母さんは「夕飯食べていきなさい」とたこ焼き器を準備してくれた。
我が家の定番料理だ。
僕はテーブルの上に新聞紙を敷き詰め、たこ焼き器を置いた。
大きいボールに溢れるほどのタネを作った母さんは、気合いをいれるために腕を捲っっている。
「最初はなにからにする?」
「タコ!」
ゆらとゆんが同時に声をあげ、母さんは白い歯を覗かせた。
「ご注文、ありがとうございます!」
母さんは窪みにタネを注ぎ、小さく切ったタコをいれた。火が通るとクルクル回して、きれいな球体をつくる。
母さんの手際のよさに唯斗くんが「おぉ!」と声をあげた。
「お上手ですね」
「昔たこ焼き屋で働いてたから、こんなもの朝飯前よ」
母さんが得意げだ。褒められて調子に乗って、どっちが子どもだかわからなくなっちゃうじゃないか。
たこ焼き器はいろんなものが作れる。
ホットケーキミックスにすればベビーカステラになるし、オリーブオイルとタコがあればアヒージョにもできる。
それにたこ焼きの中身を餅や明太子、チョコをいれて味変もできるし、最後まで飽きずに食べられるすぐれた食品だ。
僕たちが帰っていることを知った父さんが、仕事帰りにケーキを買ってきてくれた。
「きょうってパーティーみたいだね」
「たのしいね!」
双子が口の周りにソースをいっぱいつけてニコニコと笑っている。その様子に唯斗くんは愛おしそうに目を細めていた。
この雰囲気いいな。
僕の家族の中に唯斗くんがいてくれる。すごく楽しくて、話が尽きなくて、ずっとこの時間が続いて欲しい。
「あら、もうこんな時間じゃない」
母さんが壁掛け時計を見て、小さな悲鳴をあげた。時刻は夜の七時を過ぎている。外出の門限は八時までと決まっているので、そろそろ帰らないとペナルティを喰らう。
楽しい時間はあっという間に過ぎてしまうものだ。
「えぇ~ゆいとくん、かえっちゃうの?」
「いっしょにおふろはいろうよ」
「もう一回ゲームしよ! 今度こそ勝つから!!」
「どうしよう。困ったな」
唯斗くんは僕に助けを求めるように苦笑いを浮かべた。
シンデレラが十二時になったら帰らなければいけないように、時間は限りあるのだ。
「みんな、唯斗くんに迷惑かけないで。じゃあそろそろ帰ろうか」
僕が荷物を取りに行こうとすると「待ちなさい!」と母さんに制された。
「外泊届申請してあげるから、二人とも泊まって行きなさい」
「別にいいよ。寮は近いし」
「いいから泊まりなさい!! 久しぶりに帰ってきたんだから、逃がしやしないよ!」
母さんの細い腕が伸びてきて、僕と唯斗くんの肩を組んだ。ほのかに香る化粧品の匂いが懐かしい。昔はいつもこうやってぎゅっとしてもらってたな。
でも僕は慣れているけど、唯斗くんは蝋燭のようにぴしっとまっすぐ固まってしまっている。
「ちょっと唯斗くんが困ってるじゃん。やめてあげてよ」
「あら、照れちゃったのかしら。私、若く見えるけど四十なの。年下は範囲外だから」
「……そういうの恥ずかしいからやめて」
母さんの冗談に突っ込むのも疲れる。唯斗くんは「ぷはっ」っと息を吹き返して笑った。
「じゃあお言葉に甘えて泊まらせていただきます。親に連絡して、頼んでみます」
「やったー! おふろにはいろう」
「はいろう」
双子がぴょんぴょんと跳ねて喜んでいる。でも唯斗くんは首を振った。
「さすがに女の子と一緒には入れないから、お風呂あがったら一緒にケーキを食べようね」
「はーい!」
いつもは風呂を面倒くさがるのに双子は競うように浴室へと行った。母さんが慌てて追いかけている。
嵐が去ると少しだけ静かだ。
弟と父さんは残っているたこ焼きを食べながら、ぽつぽつと話しているようだ。
僕は唯斗くんに視線を戻した。
「本当に泊まって大丈夫? うち、寝る直前まで騒がしいけど」
「もちろん。すごく楽しいよ」
「ならよかった」
なんだか帰省を嫌がっていた自分が恥ずかしい。
実際に帰ってみるとこうして温かく迎えてもらえて、いつもと変わらない家族の様子に安心する。
「僕の自慢の家族なんだ」
唯斗くんはにっこりを微笑んでくれた。
風呂に入ってからケーキを食べていると、弟たちは船を漕ぎだし、母さんに促されてすぐ眠った。どうやら限界まで遊んで疲れたらしい。
まだ話したそうな母さんを父さんが寝室へと連れて行き、僕と唯斗くんはリビングを引き上げて僕の自室へと向かった。
本来弟と二人部屋だが、今夜は唯斗くんと使わせてもらう。唯斗くんが風呂に入っている間に布団はすでに敷いておいた。
僕は布団の上に座ると唯斗くんはくすぐったそうに笑った。
「やっぱこういう位置になるんだね」
「え?」
僕は敷いた布団を見下ろした。なにか変なところがあっただろうか。
首を傾げていると唯斗くんは口角を上げた。
「寮と同じ位置だよね。俺が藍の右側」
「本当だ! 全然気づかなかったよ」
「自然と刷り込まれちゃうんだろうね」
そう言いながら唯斗くんは僕の左側にちょこんと座った。パジャマは父さんが昔お土産で貰ったアロハシャツで下は僕のジャージだ。
でも裾が足りなくてつんつるてんになっている。
アンバランスな組み合わせだけど、こういうファッションだと言われてしまえば納得できそうだ。
唯斗くんはぐるりと部屋を見回した。
「藍の部屋って感じがする」
「そう?」
「机の上はぐちゃぐちゃなのに、本棚だけはきっちり並べてあるところとか」
「う~よく見てるね」
教科書やノートはいつも机に出しっぱなしだ。
唯斗くんは本棚の一番下にある場所を指さした。
「これってアルバム?」
「そうだけど……見たい?」
「そりゃもちろん」
「あんまり面白いもんじゃないけど……いいよ」
「ありがとう!」
唯斗くんは本棚からアルバムを全部出し、布団に並べた。
母さんは結構マメで兄弟ごとにアルバムを分けてくれている。月日や場所なども細かく書いてあった。
「あ、これ水間でしょ」
唯斗くんが指さした写真は、幼稚園の入園式だ。シンタと隣で映っている。
場所はこのマンションのエントランスのとこだ。見慣れたポストがある。
このときはあまり仲良くなくて、僕は下を向いているし、シンタはカメラマンに向かってガンを飛ばしている。
その様子を見た唯斗くんはくしゃっと笑った。
「小さいときから水間って感じ」
「シンタはほとんど変わってないよ」
唯斗くんは思い出を辿るようにゆっくりとページを捲っている。
「どの藍も可愛いな」
「お世辞でもありがとう」
「お世辞なんてとんでもない。これ全部寮に持って帰ろうよ」
「いらない! こんなの持って帰っても邪魔なだけでしょ」
「寝る前に毎日眺める」
「いりません」
「ちぇっ」
小さいときの僕を見ても楽しくなんてないだろう。
唇を突き出しながらも唯斗くんの顔はアルバムに向けられたままだ。
「これって」
「あぁ……担任のまゆみ先生だよ」
卒園式の日、僕はまゆみ先生に抱っこしてもらいながら大泣きしている写真だ。
「おとなになったらおよめさんになってください」と書いた手紙を渡したのもよく憶えている
「好きだったの?」
「えっと、まぁ」
「じゃあ初恋だったんだね」
唯斗くんの横顔が緩む。まるでそのときの僕を慰めるかのように写真をそっと撫でた。
次のページになると小学校の入学式だ。
ピカピカのランドセルと黄色い帽子をかぶり、シンタと映っている。
このときはだいぶ打ち解け、肩を組んで映っていた。
「ここにも水間がいるんだ」
確かに見返すとシンタは必ずと言っていいほど僕の隣にいる。当たり前過ぎて指摘されるまで気づかなかった。
これじゃシンタのアルバムだと言われても気づかれないかもしれない。
唯斗くんはちょっとだけ眉を寄せている。
「ズルい」
「なにが?」
「こんな可愛い藍を独り占めしていた水間が」
「独り占めって」
僕は腹を抱えて笑ってしまった。
まるで僕を取られて嫉妬しているみたいじゃないか。
僕の反応が面白くなかったのか、唯斗くんの鼻に皺が寄る。
「小学校のとき好きだった子は?」
「いない、かな」
「中学」
「それも……特には」
「まゆみ先生だけってこと?」
「そうだね。あんまり恋愛に興味がなかったかも」
きゅんとしたくなったら漫画やアニメを観れば事足りる。わざわざ自分でしたいなんて思わなかった。
「唯斗くんはどうだったの? すっごいモテてそう」
「期待に添えるほどじゃないよ」
「そうやって謙遜するところが余裕の表れだね」
「ははっ……でも好きな子には振り向いてもらえないんだよね」
「え」
唯斗くんは眉を寄せて、困ったように笑った。すべてを諦めているかの表情は、それだけ唯斗くんが深く想っているのが伝わってくる。
唯斗くんは僕のアルバムをぱたんと閉じた。
「もう遅くなっちゃったし、寝よっか。続きはまた明日」
「……うん」
「おやすみ」
僕がリモコンで明かりを消すとすぐに規則的な寝息がしてきた。疲れていたのかもしれない。
僕は痛む胸にそっと手を置いた。
唯斗くんに好きな人がいる。
その現実をなかなか飲み込めず、その日はなかなか寝つけなかった。