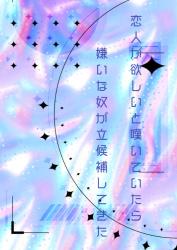期末試験の結果は過去最高得点を叩き出した。お陰で夏休み中の補習は免れ、夏コミに向けて本腰をいれられる。
思う存分漫画に打ち込められるはずなのに、僕は寮の部屋でスケッチブックを前に頭を抱えていた。
受けの相手役を幼馴染するか、転校生するかを決めかねている。
そもそも最初は幼馴染との話にするつもりだった。当て馬として転校生を出したけど、キャラクターを作り込むにつれ、愛着が湧いてしまったのだ。
転校生にも幸せになってもらいたい。
でもそのためには受けとの恋愛がベストだ。
だからといって幼馴染を捨てたくない。
「う~ん……どうしよう」
僕がうんうん唸っているとベッドの上で「これ愛」の新刊を読んでいた唯斗くんが顔をあげた。
「どうしたの?」
「ネームに詰まってて」
「読んでもいい?」
「でもBLだよ?」
「俺がいま読んでるものはなんだと思う?」
漫画の表紙が僕に見えるように掲げた唯斗くんに笑ってしまった。
唯斗くんは僕の本棚にあるBL漫画をすべて読破している。
「でも自分が描いたものを読まれるのはちょっと恥ずかしいかも」
「漫画を読んでもらうために描いてるのに?」
「ネットに投稿するのは相手の顔が見えないからいいんだよ」
友人に見られるのとは羞恥心の大きさが違う。でもシンタだとあまり恥ずかしいとは思わないんだよな。小さいときから一緒にいるし、羞恥心がないからかも。
だからといっていつまでも一人で悩んでいるわけにもいかない。
「水間には読ませるのに?」
唯斗くんの声に険が混じる。心なしか目が鋭いような。もしかして怒ってる?
そりゃ出し惜しみしてるようだし、面白くないよね。
僕はドキドキしながらスケッチブックを唯斗くんに渡した。
「じゃあお願いします」
「うん、しっかり読むね」
唯斗くんは起き上がってスケッチブックを開いた。羽毛みたいに長い睫毛が伏せられ、右から左に眼球が動いている。
この待ってる時間がなんとも言えない。
僕がそわそわしているうちに最後まで読み終わった唯斗くんは、ぱたんとスケッチブックを閉じた。
「すごいよかったよ。受けの子が純粋ですごく可愛い」
「やった!」
「でも……どうして最後は幼馴染とくっつくの? 途中まで当て馬ともいい感じだったよね」
「やっぱり変だよね」
僕は受けの相手を幼馴染にするか、転校生にするかで悩んでいると吐露した。
唯斗くんが目を丸くしている。
「これってもしかして実体験?」
「僕とシンタってこと? まさか、想像もしたくないよ」
母親同士が仲良く、僕とシンタは幼稚園から一緒だ。
お互い何歳までおねしょをしていたか、嫌いな食べ物や好きな食べ物、それから使っているシャンプーだって知っている。
共働きのシンタの両親は帰って来るのが遅い。だからシンタはいつも僕の家で夕飯を食べていたし、何度も一緒に風呂も入っている。
それこそ兄弟のように育ってきたのだ。
シンタのことは好きだが、自分の弟に向ける感情と同じだと断言できる。
唯斗くんはまだ納得していないのか、スケッチブックに視線を落とした。
「これ、描き直す気はない?」
「どこかダメだった?」
「相手が転校生でも悪くないと思う」
「唯斗くんは転校生ものが好きなんだね。でもわかる」
唯斗くんがうちの学校に現れたように、転校生というのもインパクトがある。
席は隣同士で寮は同室になって、試験勉強を一緒にしたりしてーーて、これほとんど僕と唯斗くんのことじゃないか。
まさか僕たちがBLの王道にいるとは思わなかった。
でも「ただしイケメンに限る」という注釈が必要だな。僕では到底相手役を務められない。
唯斗くんは瞳をきらりと光らせた。その奥に闘志が漲っている気がする。
「俺は絶対転校生の方がいいと思う。受けの子を大事にできる素質があるよ」
唯斗くんの目は真剣だ。こんなに僕の漫画のことを思ってくれて嬉しい。
僕は「う~ん」と唸った。
「シンタにも感想聞いてみるね」
「水間にも訊くの」
「うん。僕の作品は全部読んでもらってるから、適切なアドバイスをもらえるかもしれない」
「……そっか」
唯斗くんは僅かに肩を落としたように見えた。そんなに残念に思うことかな?
気分転換に僕と唯斗くんは風呂に向かうことにした。
寮生全員が使うので大浴場は広く、清潔に保たれている。でも時間は夕方の四時から八時までと決められ、どうしても混みあってしまう。
夕食直後は特に混むから、僕は学校から帰ってすぐに入るようにしている。そうすればほぼ貸し切りだ。
このことに気づいたのは去年の冬で、その知識を唯斗くんに教えたらいつの間にか一緒に行く流れになり、いまに至っている。
僕が大浴場の暖簾を潜るとむわりとした土の匂いが鼻をかすめた。
脱衣所には泥だらけの野球部がひしめき合っている。
その中に山岸くんの姿もあり、僕たちを見つけるとぱっと顔を輝かせた。
「唯斗と沢渡じゃん! おまえら、いまから風呂? オレらもなんだ!」
山岸くんは練習着らしい白いシャツを脱いだ。所々泥で汚れている。
唯斗くんが首を傾げた。
「この時間に練習が終わるの珍しいね」
「雲行きが怪しいからって早めに切り上げたんだよ。明日は三回戦だし、体調崩すわけにもいかないからな」
「次も頑張ってね」
「今年も甲子園いくぜ!」
山岸くんはにっと笑い、他の野球部員たちも頷いている。
そっか、もうそんなに勝ち上がってるんだ。山岸くんたちはすごいな。
僕はそそくさと空いているすみに移動した。人はいないけど、カゴの中には衣服が詰め込まれている。誰かが脱いだシャツや靴下が散乱したままだ。
隣に唯斗くんが来てくれ、僕に耳打ちをした。
「藍、ちょっと時間をズラさない?」
「どうして?」
「……混んでるし」
「でもこの後もしばらく似たような状況だと思うよ?」
このぐらい混んでいることなんて普通だ。一年生のときなんて一番ピークの時間に入浴していて、ぎゅうぎゅうだったこともある。
でも最近ほぼ唯斗くんと貸し切りの状態が続いていたから、嫌なのかな。
もしかして唯斗くんはみんなに裸を見られたくないとか?
いつもタオルで下半身を隠していたし、洗うのも最短時間で済ませてすぐに湯船につかっていた。
同じ男だし、そんな恥ずかしがることじゃないのにな。
唯斗くんはどこで鍛えているのか、腹筋は割れてるし腕も張りがあってカッコいい。むしろそのまま下着の広告塔になれると思う。
僕の方がひょろりとして情けない体格なのに。
唯斗くんを見上げると大きな身体で僕をさらにすみに追いやった。
唯斗くんと体格差があるせいで見下されると圧がある。美人の無表情ほど怖いものはない。
「言うこと聞いて」
「でも夕飯の時間遅くなっちゃうよ」
「藍」
「……わかった。じゃあちょっとだけ待つ」
「よろしい」
正解を言い当てた生徒を褒めるように唯斗くんは目尻を下げた。
そんなに裸を見られたくないなら仕方がないね。
ロッカーの脇から山岸くんが顔を覗かせた。
「入らねぇの?」
「俺たちはちょっと待つよ」
「それがいいかもな。野球部は騒がしいし! でもすぐ出てくるよ」
山岸くんはタオルで下半身を隠そうともせず、生まれたままの姿で大浴場に入っていく。
日に焼けていない尻が丸出しだ。
「見ちゃだめ」
目元を大きな手で隠され、視界が奪われる。えっ、と声を上げた。
「これじゃなにも見えないよ!」
「他の奴の裸は見せたくない」
「なにそれ」
僕はおかしくて笑ってしまった。同じ男なんだからみんな付いているものは一緒だ。
心外だったのか唯斗くんの声に不満が混じる。
「そんなに笑うこと?」
「だってみんな男だよ」
「でもさ」
そこで僕ははっと気がついた。
「もしかして僕が腐男子だからって心配してくれてるの?」
「……うん」
つまり唯斗くんが他の人と風呂に入りたくなかったのは僕に気を使ってくれたからなんだ。
的外れな答えに辿り着き、僕はくすっと笑った。
「確かに僕は腐男子だけど、異性愛者だよ」
「え」
手を離されてやっと視界が明るくなった。電灯の光がちょっと眩しい。
僕は何度か瞬きをするとようやく明るさになれてきた。元に戻った視界には口をあんぐりと開けたままの唯斗くんがいる。
そんなに驚くことかな。
「もしかして僕がゲイだと思って心配してくれてたの?」
「あ……うん」
「だから毎日お風呂一緒に来てくれたんだ。僕が暴走しないように」
「いや、そういうわけじゃ」
「ありがとう。本当大丈夫だから」
まさか自分がゲイだと思われているなんて考えもしなかった。
でもちょっとだけ傷つくな。僕がどこでも発情する変態だと思っていたということじゃないか。
ちらっと盗み見みると唯斗くんは口元に手の甲を当てて、ぶつぶつと呟いている。
「俺だけ藍を独占したかっただけなのに」
「独占?」
「……なんでもない」
「そう? あ、だいぶ空いてきたから入ろうか」
さすが運動部は風呂が速い。今度は脱衣所に人がいっぱいいる。
「そうだね。さっさと入ろう」
「うん」
「俺が影になってるから、藍はそこで脱いで」
「どうして?」
「……別に深い理由はないけど」
そう言う唯斗くんはおもちゃを買ってもらえなかった子どものように唇を尖らせている。
ちょっと可愛いな。なんでも言うこと聞いてあげたくなっちゃう。
「わかった。じゃあさっさと着替えるね」
僕は唯斗くんの背中にガードしてもらいながら、服を脱ぎ、腰にしっかりとタオルを巻いた。
その姿をじっと唯斗くんに見られている。貧相な身体って思ってるのかな。やっぱり鍛えた方がいいよね。
「……エロすぎ」
「唯斗くん? 顔真っ赤だけど、もうのぼせた?」
「なんでもない。じゃあ行こうか」
僕が脱いでいる間に唯斗くんも裸になっていた。相変わらず美しい裸体だ。
つい見惚れてしまいそうになり、頭を振った。
さすがにそれはダメだろう。
「藍?」
「早く行こう」
僕は人の少なくなった大浴場へと向かった。
夏休み直前の教室内は騒がしい。どこに行こうかなにをしようか計画している声があちこちから届く。
だけど僕は静かに前の席に座るシンタをみつめていた。ごくりと唾を飲み込むと、シンタはスケッチブックから顔を上げる。
「ネーム結構いいじゃん」
「よかったぁ~」
「でも転校生と途中までいい感じだったのに、急に方向転換した感じがするな」
「やっぱりわかる?」
「だってここ受けが「きみのことは好きだよ」ってはっきり言っちゃってるし」
「だよね‥…唯斗くんにも言われちゃったよ」
僕は机にだらりと突っ伏した。
「転校生のキャラを深掘りしてたら、そっちもいいなと思ってきちゃってるんだ」
けれど結局うまくいかなくて終わってしまう。だったら受けを双子設定にしようか、とも思ったが、それはまた別の話になっちゃうんだよね。
でもそろそろペン入れをしないと納期に間に合わない。
ゆったりとネームを作っていられる時間は、刻一刻と減っている。
シンタは意外そうに眉を上げた。
「ならどっちも描けばいいんじゃね? ほら、ギャルゲとか乙女ゲーとか同じ話だけどくっつくキャラが違ったりするじゃん。そういう感じにすれば?」
「つまり二冊描くってことか」
「好きって思うならどっちもやってみていいと思うけど」
「いいかもしれない」
目から鱗の提案に、僕の頭の中がいろんなアイディアが浮かんでくる。
さすが地球規模にストライクゾーンが広いシンタだ。まさかギャルゲや乙女ゲームまで嗜んでいるとは思わなかった。
でもかなりいいアドバイスかもしれない。欲しいなら二つ手に入れたっていいんだ。
僕がスケッチブックに描き込みをしていると、シャツをパタパタとさせて唯斗くんが登校してきた。
「はぁ〜疲れた」
「お疲れさま、先生見つかった?」
「校庭にいた。まさか花壇の水やりをしてると思わなかったよ」
唯斗くんは日直だからと早く登校したのに、肝心の担任が見つからず日誌を持って来れなかったらしい。登校してからずっと探しているとメッセージがきていた。
「頼まれてた飲み物買っておいたよ」
「サンキュー」
僕からスポーツ飲料水のペットボトルを受け取った唯斗くんは一気に飲んだ。汗をかいているようだし、担任探しは難航していたのだろう。
「おまえら、だいぶ仲良くなってきたよな」
僕と唯斗くんのやり取りを見て、シンタが感慨深く頷いている。
「うん、そうかも」
僕は唯斗くんに笑顔を向けた。彼のお陰で毎日楽しくなったと言っても過言ではない。
「不意打ちやば」
唯斗くんは手の甲で口元を隠してしまった。でも隙間から見える頰がちょっと赤く見える。唯斗くんも僕と同じ気持ちなのかな。そうだったら嬉しい。
シンタはがたんと椅子を鳴らした。
「で、オレが言った案採用する?」
「そうしようかな」
「なんの話?」
「幼馴染だけの話と転校生のだけの話の二つ描くってよ」
「それいいね! 面白そう」
「頑張ってみる」
初めてのコミケ参加で、一冊しかないのも勿体ない気がする。やれることはやろう。大変だと思うけど、絶対楽しい。
「俺も手伝うからなにか言ってね」
「じゃあ……資料集めに付き合ってくれる?」
「いいよ」
唯斗くんが快くオーケーしてくれたことだし、俄然やる気が出てきた。
学校が休みの土曜日、僕は久しぶりに私服に袖を通した。
中学生のときに量販店で買った紺色のポロシャツにベージュのチノパンという無難な服装だ。姉ちゃんの見立てだから変ではないはず。
唯斗くんが持ち込んだ姿見で髪を手ぐして整えれば、準備万端である。
「よし、ちょっと早いけど行こうかな」
僕はショルダーバッグを肩に下げて、部屋を出た。
一歩外に出ると灼熱の太陽が照りつけてくる。あまりの暑さのせいで蝉が沈黙をしているくらいだ。
僕はアスファルトの照り返しに負けそうになりながら、徒歩五分のバス停に向かった。時刻表を見ていたのですぐにバスが来て、十五分ほど揺られると駅に着く。
そこからさらに電車に乗って商業施設の多い都市部へと向かった。
「唯斗くんは……まだかな」
寮から一緒に行こうと思っていたのに僕が起きたときには唯斗くんの姿はなかった。
机の上に書き置きがあり、『現地待ち合わせしよう。十時に駅ね』と書かれていたのだ。
なんでそんなまどろっこしいことをするのだろう。
駅に着くとあまりの人の多さに驚いた。
たぶん東京ほどじゃないけど、ひっきりなしに人の往来がある。キャリーケースや大きなリュックを背負った人ばかりだから観光客なのだろう。
海も近く、大学生と思われる若い男女のグループが海岸行きのバス停で行列をつくっていた。
「えっと……どの辺で待ってようかな」
駅前広場で待ち合わせていたが、人が多すぎて唯斗くんを見つけられるか自信がない。
都市部なんてほとんど行かないから慣れていないのだ。
僕がキョロキョロと見渡していると人だかりができているのに気がついた。
芸能人が来ているのかな。
大通りの脇は商店街になっていて、美味しい名産品が多い。あわびの串焼きやホテタ、いちご飴もあり、たまテレビ撮影をしている。
なんとなく観察していると女の子たちが多い。輪から小作りな頭が見え、サングラスが大きすぎて顔の半分が隠れていた。
明らかに一般人ではないオーラを放っている。
サングラスの男は僕の方を見ると手を振った。
「こっちだよ! ちょっと待ってて」
すいません、と女の子たちに謝りながらサングラス男は僕の方に来た。
おしゃれっぽい水色のシャツと黒の足首が見えるズボンがよく似合っている。派手さはないのに、精錬された高級品のように人目を惹く。
僕がぼんやりしていると「藍?」と名前を呼ばれて、男はサングラスを取った。
「唯斗くん!?」
「そうだよ。なんでそんなに驚いてるの」
「だって芸能人かと思って。女の子に囲まれてたし」
「あぁ……」
唯斗くんの後ろにいる女の子たちはソワソワしながら僕たちの様子を窺っている。
気づいているだろうに唯斗くんはまるで見えないもののように振舞った。
「せっかく待ち合わせしてデートっぽくしたかったんだけど、失敗しちゃったね」
「デ、デデデデデート!?」
ただの資料集めがどうしてデートになるんだ。それに僕と唯斗くんは友だちで、恋人じゃない。
デートって付き合ってるカップルがするものでしょ?
僕がぐるぐる目を回していると唯斗くんはにっと白い歯を覗かせる。
「ここじゃ落ち着かないから行こう。今日は藍のための日だから」
唯斗くんに腕を掴まれて、僕たちは女の子たちから逃げるように走り出した。
唯斗くんはショッピングモールの雑貨屋さんで買ったキャップをかぶると、まるで存在が消えたかのようにピタリと注目されなくなった。帽子ってすごい。
でも顔を隠していても一般人ではないオーラはあるので、すれ違う人はみんな振り返っている。
唯斗くんはサングラスの縁をそっと指で摘まんだ。
「ごめん、迷惑かけたよね」
「そんなことないよ。あんな風に囲まれるシーンって漫画でしか読んだことないから、ビックリしたけど」
「だよね……本当ごめん」
唯斗くんは珍しく落ち込んでしまっている。昨日まで楽しみだと笑ってくれていたのに。
女の子に注目されて、疲れちゃったのかもしれない。
唯斗くんのあまりのモテっぷりを目の当たりにして胸がモヤモヤする。
そりゃこれだけカッコよかったら、みんな好きになっちゃうよね。
でも、なんでだろう。友人が人気で嬉しい気持ちにはなれない。
なぜだか内臓をグルグル掻き混ぜられているように気持ちが悪くなってくる。
もしかして急に走ったから疲れてるのかな。
僕は足を止め、口元を手で押さえた。
「吐きそう」
「え! あ、トイレ行く?」
「そこまでは……平気」
「とりあえずあそこにベンチに座ろうか」
唯斗くんに背中を支えてもらいながら僕はベンチに座った。少しだけ身体はラクになるけど、胸の気持ち悪さは残っている。
唯斗くんが心配そうに僕の顔を覗いた。
「しんどい? 病院行く?」
「ちょっとだけ。なんか胸がグルグルしてる感じなの」
「朝ごはんがもたれてるのかな」
「胃もたれとは違う気がする。ここが気持ち悪い」
僕は胸元をぎゅうっと握った。せっかくの一張羅が皺になってしまうが、なにかに縋っていないと自分が自分でなくなりそうなのだ。
この感覚はあのときと似ている。
期末試験期間中、唯斗くんが山岸くんたちに勉強を教えていたから一人で図書館に来たときだ。
あのとき、どうやって治ったんだっけ。思いだせない。
唯斗くんは眉を寄せたあと、ぱっと顔を輝かせた。
「そういうときは炭酸飲むとすっきりするかも。ちょっと待ってて」
唯斗くんは隣の自販機で炭酸飲料水を買った。蓋を開けてから渡してくれる。
「どーぞ」
「ありがとう」
僕は言われるがまま炭酸を一気に煽った。しゅわしゅわと弾ける泡が喉を通ってくすぐったい。身体をきんと冷やしてくれる。
少しだけラクになった気がした。
「どう?」
「すっきりしてきたかも」
「じゃあもうちょっと休憩しようか」
唯斗くんはブラックコーヒーを買い、隣から香ばしい大人な香りがする。高校生でブラックコーヒーを飲めるなんてすごいな。
缶に口をつける唯斗くんの横顔がきれいだ。遠くを見ている目はどんな形をしているのだろう。サングラスが邪魔でよくわからない。
唯斗くんの視線には家族連れがいた。小さな女の子が母親に手を引かれ、よたよたと歩いている。
それを見つめる唯斗くんの口元はマシュマロのように柔らかくて甘い。
炭酸の泡のようにパチパチと自分の中でなにかが弾ける。
僕はショルダーバックからスケッチブックを出して描き始めた。
唯斗くんはなにも言わない。
僕が描き始めるとただ黙って同じポーズのままでいてくれる。
「できた」
十分ほどで描きあげたスケッチに僕は大きく息を吸った。
「見せて。お~いい感じ」
「いつもありがとう。黙って描かせてくれて」
「そりゃ専属モデルですから」
サングラスを取った唯斗くんの笑顔を見ていると気持ち悪さが薄らいでいく。まるで雨雲の隙間から差し込む陽の光みたいにキラキラが増すのだ。
「でもこの顔、見たことがあるな。あーー」
体育祭で金ぴかのシールを貼ってもらったときだ。あの笑顔はどんなメダルよりも輝き、胸が張り裂けそうなくらいドキドキした。 いまも同じように心音が鳴っている。
さっきまであんなに気持ち悪かったのが嘘のようにすっきりしている。
あのときも唯斗くんの写真を見て、元気になったんだ。
「藍? どうした?」
「唯斗くんの笑顔を見てたら、気持ち悪いの治ったみたい」
「え?」
「ありがとう。僕は唯斗くんの笑った顔が一番の薬なんだ」
「……うわ〜なんだよ、それ。タラシかよ」
唯斗くんは両手で顔を覆ってしまった。
「変なこと言っちゃった?」
「いや、嬉しい。めちゃくちゃ嬉しい。でも自覚してないのが悔しい」
「自覚?」
唯斗くんが言うことは時々難しくてよくわからない。
唯斗くんは缶を両手で挟み、ゆっくりと口を開いた。
「正直、自分の顔を褒められるのってあんまり好きじゃなかったんだよね」
「……僕、いままでたくさん褒めちゃったよ」
「藍に言われると平気。むしろこの顔で生まれてよかったって両親に感謝したいくらいだし」
「でも僕は唯斗くんの顔だけが好きなんじゃないよ。前にも言ったけど、勉強に真剣に取り組んでいるところとか、こうして僕のために時間を使ってくれるやさしいところとか……あげたらキリがないくらい」
次から次へと唯斗くんの好きなところが出てくるので語っていると、唯斗くんはくしゃっと笑った。
「ふはっ、なにそれ。めっちゃ俺のこと好きじゃん」
「もちろん。唯斗くんのこと大好きだよ」
なにを当たり前のことを言っているんだ。いくら資料集めとはいえ、僕は好きでもない人と出かけるほどコミュ力が高いわけではない。
「…………まじ」
「うん」
「俺も藍のこと好きだよ」
「じゃあ今日から親友だね!」
僕の言葉に唯斗くんがズッコケだ。バラエティ番組のひな壇芸人並みに見事である。
コーヒーをこぼさなかったのがプロの技がなせるのだろうか。
「違った?」
「……いや、合ってる。いまは、ね」
「うん!」
僕は炭酸飲料水を一気に煽った。
休憩を終えて、僕たちは書店に向かった。広い店内は細かくジャンルごとに分けられ、外国語の辞書や歴史書などが多くある。
もちろんコミックスや小説も多い。奥にはカフェスペースも隣接しているので、買った本をすぐ読むことができる。
県内一の広い本屋さんだ。
僕は少女漫画の棚に隠れながらBL漫画の背表紙を観察している。
「すごい……あれも、これも読んだことがないものばかりだ」
「いつもどこで漫画買ってるの?」
「姉ちゃんに買ってもらって、それを送ってもらってるんだ」
寮ではネット通販は利用できないけど、家族から送ってもらったものは受け取ることができる。
なにより書店まで電車とバスを使わなくちゃいけないので、ラクな方を取ってしまっていた。
でもたまにはこうして棚を観察するだけで新たな刺激になる。
棚一面に素晴らしい本が宝石のように並んでいた。
あ~見たい見たい見たい。せめてあそこの空気だけでも吸わせて。
僕が葛藤している間に後から来た大学生くらいの若い女性が僕たちのことをチラ見している。
僕はすぐ同士だとピンときた。腐っている者同士、テレパシーで通じ合うのかもしれない。
だから彼女の気持ちがわかる。
「もう出ようか」
「いいの? せっかく来たのに」
「大丈夫」
僕は唯斗くんの背中を押して、店の外へと連れ出した。
「どうしたの?」
「女の人がいたから」
「うん、いたね」
「……僕たちがいたら買うのやめちゃうかもしれないから」
BLは少女漫画とは違う。爽やかな表紙もあれば、エロさを前面に出している作品もある。
だから買うのに勇気がいるし、誰にも見られたくない気持ちを理解できるのだ。
僕が答えると唯斗くんは目を瞬いた。
「藍は本当によく周りが見えてるよね」
「腐った者同士、なんとなくわかるだけだよ」
「そんなことない。模写するときもさ、顔の特徴をよく捉えてるよね。これってよく観察してないとできないことじゃない?」
「まぁそのせいで研究くんってあだ名つけられてたけどね」
僕は慌てて口を押えた。当然唯斗くんには聞こえていて、味の感想に困ったような顔をしている。
唯斗くんがやさしいから、つい心に引っかかっていたことがポロッとこぼれてしまった。
唯斗くんなら聞いてくれるんじゃないかという甘えだ。
でもいまのは嫌味みたいだった。まるで山岸くんたちを責めているみたいじゃないか。
僕だって悪いところはある。黙ってみつめられて模写されてたら、いい気持ちはしないだろう。
唯斗くんは難問に取り組む学者のように難しい顔をしたまま、顎に指をかけた。
「山岸たちにちゃんと謝ってもらう?」
「いいよ、そんなことしなくて」
「でも一歩間違えばイジメでしょ? 水間も知らないってことは影でコソコソしてたことになるし。モヤモヤは残ってるんじゃないの?」
「それは……そうだけど」
「謝ってもらうのが正解ってわけじゃないけどさ、相手の誠意がわかるよ」
唯斗くんは中学でイジメられていた僕のことを気にしてくれているのだろう。当時は逃げることに必死で、相手を弾劾したり謝ってもらおうなんて考えたことがなかった。
僕が我慢すれば丸く収まるのだと思ったのだ。
でも唯斗くんは違うと言う。
それでは僕がずっと劣等感を抱いたままだと気にしてくれているのだ。
唯斗くんは僕の未来を、僕よりも大切に思ってくれている。
「心配してくれてありがとう。唯斗くんがそこまで言ってくれるから、もう充分だよ」
「でも納得できない」
「なんで唯斗くんが拗ねちゃうのさ」
「……そういうんじゃないよ」
「僕はいつも唯斗くんに支えてもらってるね」
「それは俺の方だよ」
「僕はなにもしてないよ?」
「いっぱいしてくれてる」
僕の小指に唯斗くんの小指が絡まる。あの日、唯斗くんとシンタがやっていた指切りに似ているけど違う。
少しでも動いたら離れてしまいそうなほど弱い。
僕は呼吸一つにも気を使いながら、小指から伝わる熱を感じていた。