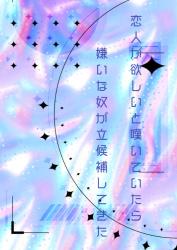中間試験が来週に迫り、僕は机にかじりついて勉強をしている。誘惑まみれの本棚にはカーテンをかけ、タブレットは机の引き出しに封印していた。
でもふと勉強への集中力が途切れる。
「幼馴染か転校生、どっちにしよう」
夏コミの新刊で頭がいっぱいで勉強に集中できていない。
「だめだめ、しっかりしないと」
自分に喝をいれて、再びワークに向き合った。
特に数学が苦手だ。そもそもなにを言っているのか理解できない。日本語で書かれているはずなのに、異世界の古文書のように難解だ。
ちょっとだけ休憩しようかな。
僕は数学のワークとノートを端に避け、金ぴかシールの貼ってあるスケッチブックを出した。ここには新刊のネームを描いている。
キャラクターのプロフィール欄を見返した。
シンタをイメージした幼馴染と唯斗くんをイメージした転校生の二人のラフ画を描いてある。
攻めを幼馴染にするか転校生にするか。それによってストーリーが大きく異なる。
どっちも捨てがたい。
小さいときから一緒にいるから長年の恋心に気づかなかった、というのもいいし、彗星のように現れた転校生にアプローチされまくる溺愛ものもいい。
うんうん唸っていると背後の椅子がぎしりと音をたてた。
「どこかわからないところがあるの? ……漫画描いてたんだ」
「いやっ、これはちょっと休憩しようとしただけで」
「全然進んでないけど」
真っ白なノートを指さされ、僕は苦笑いを浮かべた。全部バレてる。
唯斗くんは僕の白紙ノートをパラパラと捲った。
「もしかして俺がいるから集中できない?」
「そんなことないよ。唯斗くんは静かだし。僕の方がうるさいんじゃない?」
「まさか。藍がいてくれるだけで捗るよ」
こんな独り言ばかり言って迷惑かけているのに、唯斗くんはやさしいな。
でも結局、唯斗くんの勉強を中断させてしまっている。これ以上一緒にいたら迷惑をかけちゃうよね。
僕はノートとワークをかき集めた。
「談話室で勉強してるね」
「え、なんで?」
「唯斗くんの邪魔しちゃってるし」
「だから邪魔じゃないって。あ、教えてあげるから一緒にやろう」
「それじゃ唯斗くんが勉強する時間減っちゃうよ」
「人に教えると俺も理解が深まるから大丈夫」
なんていい人なんだろう。僕に気を使わせないような言葉選びに胸が熱くなる。
「唯斗くんはやさしすぎる」
「藍だけ特別ね」
「僕だけ?」
どういう意味だろうか。
なにかひっかかりを覚えたけど、明確な答えはもらえなかった。
唯斗くんはずっとニコニコしている。
同室だから気を使ってくれたんだよね、きっと。
部屋だと誘惑が多いからと、僕たちは談話室に移動した。普段はゲームをしたり、雑談をする場所だけどさすがに今日は勉強をしている人が多い。
談話室の中央テーブルで野球部が顔を突き合わせて教科書を囲っている。もうすぐ甲子園をかけた大会が始まるので、試験で赤点を取ったらレギュラーから外されるらしい。
だからみんな真剣だ。
僕が来たことに気づいた山岸くんがじろりと睨みつけた。
入学当初から僕がシンタと仲良くしているのをよく思っていないのだ。でも山岸くんはすぐ唯斗くんに気づき、ぱっと笑顔に変わる。
「唯斗! ここの英訳教えて欲しいんだけど」
山岸くんは屈託のない笑顔で手招きをしている。山岸くんとクラスは違うけど、体育祭で走り合ってから唯斗くんと仲良くなったらしい。
「えっと」
唯斗くんは困ったように僕に顔を向けた。行ってもいいのか気にしてくれているのだろう。
僕は大きく頷いた。
唯斗くんは「ごめんね」と口パクをして、山岸くんたちの元へ向かった。
「いいよ。どこ?」
「この長文のやつなんだけどさ」
「ここはThatの使い方がちょっと違うんだよ」
唯斗くんが丁寧に説明していると山岸くんを始めとした野球部が、みんなノートをとっている。
その様子を見ていた他の寮生たちがわらわらと集まりだした。
「オレたちも混ぜて」
「じゃあホワイトボードに書いてもらおう。そしたらみんな見れるじゃん」
部屋の隅にあるホワイトボードを引っ張ってきて、唯斗くんがその前に立ち、サラサラときれいな英文を書いていった。
「ここは単語の使い方がいつもと違ってーー」
まるで授業のように唯斗くんが説明を始めると、あちこちから質問する声が飛ぶ。
唯斗くんは一つずつ丁寧に答えていた。
すごいな、唯斗くんは。いつも彼の周りは人が集まる。
唯斗くんが楽しそうにしている姿にちくりと胸が痛む。少しだけ苦しくなって僕は唾を飲み込んだ。でもなかなか痛みはなくなってくれない。
せっかくみんなで勉強してるのに邪魔しちゃ悪いよね。
僕はそっと談話室を出て行った。
太陽が沈みかかっている橙色の空はきれいだ。イワシ雲が空に浮かび、夕日に反射して幻想的な模様をつくっている。
僕は夕空を眺めながら学校へと向かった。試験勉強期間中は寮生のために図書室が夜の八時まで解放されている。時間が合えば先生に教えてもらえる特典付きだけど、行きたがる生徒は少ない。
案の定、図書室には誰もいなかった。
「あ~暑かった」
僕は額に浮かんだ汗を手の甲で拭い、エアコンのボタンを押した。たった五分しか外を歩いていないのに滝のように汗が流れる。
「さて、勉強するか」
気合いを入れて数学のワークを開いたけど、数字の大波がぐわんと押し寄せてきた。
数字だけならまだしも知らない記号も多い。Xやyじゃない、cosとsinって初めて見るんですけど? 新しいBLの隠語?
授業はちゃんと聞いているしノートもとっている。
だけどこの図がなにを示して、この公式がなんのために使うのかさっぱりわからない。
「あ~だめだ。全然進まないよ」
僕はノートに突っ伏して、泣きそうになった。
そんなとき、唯斗くんの顔が浮かぶ。
「黙って出て行っちゃったから心配してるかな」
唯斗くんは友だちが多い。教室ではいつも輪の中心にいて、みんなを明るく照らしてくれる太陽みたいな存在だ。
やさしくて、勉強ができて、スポーツ万能な唯斗くんを好きな人は多い。
それが同室ってだけで僕は関わらせてもらえるんだから、ありがたいはずなんだよね。もっと感謝した方がいい。そんなことわかってる。
でもこのモヤモヤする気持ちはなんだろう。
「なんだか吐き気がする」
僕は胃の辺りをぐるりと撫でた。もうすぐ夕食の時間だからお腹が減ってるのかな。
とても勉強する気分にはなれず、僕はポケットからスマホを出して画面フォルダを見返した。
唯斗くんと体育祭で一緒に撮ったものや、海岸掃除、初めてポーズをとってくれたものまでとどんどん遡っていく。
「これ懐かしいな」
唯斗くんに壁ドンして欲しいと頼んだ写真が出てきた。恥ずかしそうに両目を瞑っているのがなんとも可愛らしい。
ゆっくりスライドさせると目をキラキラとさせて笑う唯斗くんがいた。
世界で一番美しい宝石を散りばめたように画面が光りで溢れている。
この笑顔は万人を魅了させるだろう。きっとこの写真を元にして描いた絵はたくさんの評価を得られる。
でもなぜか僕はペンを取る気になれなかった。
「この笑顔、誰にも見せたくないな」
ぽつりとこぼれた言葉に自分でも驚いた。
どうしてそんなこと思うのだろうか。
自分の気持ちが雲のようにふわふわで形がわからない。
確かなのはこの笑顔だけは自分だけのものにしたいってことだけ。
僕はその写真をお気に入りフォルダにしまった。そうすればいつでも見返せられる。
窓から夕陽が差し込んできてノートに長い影が落ちた。ちょうど図書室は海側に面しているので、水平線に沈む太陽がよく見える。
海鳥が飛んでいる影や漁船も見えた。
穏やかだけどどこか哀愁が漂う景色を見ると、僕の心臓は縄で縛られたみたいに苦しくなる。
中学三年のとき、僕はイジメられていた。理由はわからない。
学校にも行かず、部屋に籠もったっきり塞ぎ込んでいた。
まだ実家にいたので海は遠い。でも僕の家は高台にあるマンションだったので、水平線に沈む夕陽はよく見えた。
夕焼けを見ていると辛かった気持ちが蘇る。
なにをしてもクスクスと笑われ、教師に指されて発言すると休み時間では僕の口真似大会が開催された。
シンタが何度もやめろと庇ってくれたけど、いじめの矛先がシンタに向きそうで怖かった。
だから僕は不登校を選んだ。
家族は心配して、毎日僕が元気になりそうなものを持ってきてくれた。
映画、パズル、手芸や音楽、ペーパークラフトなどありとあらゆるものを貢いで、励ましてくれたのだ。
けれど当時の僕は心が死んでしまっていた。なにかを楽しむ心の空白がなかったのだ。
まるで人形になったかのように、感情を表に出せなかった。
でもある日、姉ちゃんがBL漫画を貸してくれた。
その運命の出会いが僕を変えたのだ。
男同士の胸キュンストーリーにハラハラしたり、じれったくなったりと心がジェットコースターのように激しく動く。
新刊を読みたい気持ちだけで暗闇からぱっと抜け出せたのだ。
気持ちが上向きになり僕は再び絵を描き始めた。
そして勉強にも取り組んだ。授業に遅れてしまった分、家庭教師に来てもらって遅れを取り戻したのだ。
寮のある海南高校を選んだのは、自立した姿を両親に見せて安心させたから。
最初は反対されたけど、何度も説得してどうにか寮暮らしをさせてもらえている。
昔のことを思い出すと辛いこともあったけど、同時に家族の温かみを実感させてくれた。
この夕暮れにはそんな思いが詰まっている。
「だからちょっと寂しくなっちゃうのかな」
気持ち悪さと寂寥感で僕の目尻には薄っすらと涙が浮かんだ。指の腹で拭えばすぐに乾いてしまうのに、そうすることができなかった。
「唯斗くん……」
心細いときに浮かんだ顔は唯斗くんの笑顔だ。さっそく写真を見返すと吐き気はなくなり、少しずつ気力が湧いてくる。
どんな特効薬よりも効くらしい。
でもね、写真だけじゃなくてそばにいて欲しいな。自分から離れたくせに莫迦だよね。
夕陽を眺めていると段々と瞼が重たくなってきて、僕は目を瞑った。
海面から顔を出すようにふっと意識が戻る。図書室に誰かいる気配がする。もしかして見回りの先生かな。
でもまだ寝ていたい。
僕が瞼を閉じたままでいると頬をぷにっと突かれた。楽しそうな笑い声までする。
「ふふっ、よく寝てる」
「ん……」
「起きて〜そろそろ図書室閉めるってよ」
肩を揺さぶられて僕はゆっくりと身体を起こした。
「……唯斗くん? もう朝?」
「まだ寝ぼけてるのね、この子は」
息子に飽きれた母親のような唯斗はなおも僕の頬を突いている。
少しずつ頭が覚醒してきた。
「やばっ、寝ちゃってた!」
壁にかかっている時計を見ると夜の七時五十分をさしていた。窓の外は日がすっかり沈み、暗い海が見える。
慌てている僕に唯斗くんはぷっと吹き出した。
「何時間寝てたの?」
「わかんない。二時間くらい?」
「ほとんど勉強してないじゃん」
「うぅ~どうしよう」
勉強するつもりで来たのに、睡眠学習と言い訳できないほどがっつり寝てた。昨日の夜はいつも通りに寝たはずだったのにな。
唯斗くんの長い指が僕の頬を刺した。
「頰に痕ついてるよ」
「え、よだれ?」
「違うよ。なんか線みたいなやつ」
「どこ!?」
僕がペタペタと顔を触っていると「ここだよ」と唯斗くんの大きな手のひらに片頬が包まれた。指の腹が僕の頬に触れる。
唯斗くんの睫毛の際がわかるほど近づかれ、僕は目をぱちくりとさせた。
「そんなに変な痕?」
「猫のヒゲみたいで可愛い」
「なにそれ」
どうやら髪の毛を巻き込んで寝ていたらしく、頬を触ると小さなおうとつがあった。それが猫のヒゲだと揶揄われているのだろう。
笑っていた唯斗くんの表情が途端に曇る。
「……泣いてたの?」
「え?」
「目元がちょっと赤い」
親指の腹で目元を撫でられると擽ったくて、僕は肩を竦めた。
「ちょっと昔のこと思い出しちゃって」
「辛かったの?」
「うん……でももう平気」
へらっと笑ってみせた。でも唯斗くんは釣られてくれない。
僕は明るい笑顔の唯斗くんが見たくて、もっと口角を上げてみせる。
だけど唯斗くんは笑ってくれない。むしろどんどん暗くなってしまう。
頰に添えられた手がゆっくり離れてしまい、僕は指の行方を目で追った。
その指が僕の頭にぽんと乗せられる。
「訊いたらだめかな?」
「情けない話だから」
「じゃあ俺も情けない話する」
「唯斗くんに情けないところってあるの?」
「むしろ情けないとこばっかだよ」
「そう見えないけど」
唯斗くんはカッコよくて運動ができて頭がよくて友だちが多い。なんでも持ってるスーパーヒーローみたいな人だ。
そんな完璧超人な唯斗くんに情けないところがあるなんて想像できない。
「俺から話そうか」
背筋をピンと伸ばした唯斗くんはまっすぐ前を見ている。凛とした横顔が三日月みたいにキレイなのに、長い睫毛に伏せられた瞳に暗い影が落ちた。
「俺はここに逃げてきたんだ」
唯斗くんは眉を寄せ、苦しさに喘ぐように息を吐いた。
「詳しくは言えないけど、求められることと自分がやりたいことが違ったんだ。で、苦しくなって逃げてきた。情けないでしょ」
「……そんなことないよ」
「山岸たちみたいに夢を追って来たんじゃない。俺は夢を捨ててここにいるんだ」
痛みに耐えるように唯斗くんの口元が歪んだ。
もしかして唯斗くんはずっと疎外感を味わっていたのだろうか。
甲子園を目指す野球部や全国制覇を掲げているサッカー部を見て、負い目を感じていたのかもしれない。
じゃなきゃ「逃げてきた」なんて言葉は出てこないだろう。
僕は心のどこかで唯斗くんのことを二次元のように考えていた。
頭がよくて、運動ができて、友だち想い。まるで絵に描いたような優等生に唯斗くんを当てはめて満足していた。
でもそうじゃない。
唯斗くんだって悩んで、苦しくて立ち止まってしまうときだってある。
僕と同じ生きてる人間なんだ。
話し終えた唯斗くんは、いつも通りやさしい笑みに戻った。
「じゃあ次は藍ね」
「……面白い話じゃないよ」
「藍のことはなんでも知りたい」
まっすぐに向けられる瞳に魅せられて僕は口を開いた。
中学でイジメられて不登校になったと話すと、唯斗くんの眉間に小山ができている。
「どうしてそんな……酷い」
「ん~僕ってちょっとのんびりしてるし、変わってるからウザかったのかもね」
現に高校ではシンタと唯斗くん以外の友人はいない。
「そんなこと思ったことないけど」
「唯斗くんはやさしい人だからだよ。ね、情けない話でしょ?」
こんなつまらない話を聞かせてしまって空気がどんどん悪くなってしまいそうだ。
僕は手早くノートを片付けて立ち上がった。
「そろそろ学校閉まるし、寮に帰ろう」
「まだ訊いてない」
立ち上がろうとする僕の腕を唯斗くんに掴まれてしまった。おずおずと座ると、唯斗くんの膝とこつんと当たる。
「……どうして一人でここに来たの?」
「唯斗くんがみんなと勉強してたから、邪魔しちゃ悪いって思って」
「それだけ?」
「それだけだよ」
「俺はズルい人間だから、ある言葉を藍に言わせようとしてる。わかる?」
「どういう意味?」
唯斗くんがズルい人間ってどういう意味だろう。キツネのようににやっと口角をあげるだけで、僕の問いに答えてくれない。
唯斗くんは僕の両隣に手をついて立ち上がった。小さな檻に閉じ込められてしまう。
顔を上げるとポロシャツのボタンが額に当たり、隙間から艶めかしい鎖骨が見える。僕は慌てて下を向いた。
「さっきさ、俺が他の奴と話してるのを見てどう思ったの?」
「どうって……それは」
寂しかった、とこぼすと唯斗くんは小さく息を飲んだ。
「どうして寂しかったの?」
「なにそれ連想ゲーム?」
「そうだよ。ね、どうして?」
唯斗くんの声が芯を持って僕の胸に届く。嘘を吐くことを許さないと意志が感じられた。
唯斗くんの吐息が髪に触れ、僕の全身から汗が噴き出してくる。恥ずかしい。この状況はいったいなんだろう。
考えなきゃいけないのに唯斗くんの匂いにあてられて、頭がクラクラしてくる。
唯斗くんはさらに続けた。
「『これ恋』で似たようなことがあったよね。攻めが女子と付き合おうとして、受けがツンツンしててさ」
「あ~うん。嫉妬しちゃうんだよね」
「漫画だとわかるんだ」
「どういう意味?」
再び顔を上げると唯斗くんと距離が近くて鼻先同士がぶつかる。桜色の唇があと少しの距離にあり、首を伸ばしたら届いてしまいそうだ。
顔じゅうがどんどん熱くなっていく。まともに考えることができず、僕は目を回していた。
「じゃあ考えてみて。もし水間だったらどう? みんなと勉強してて、どう思う?」
「シンタは相変わらず人気者だなぁとしか」
「でも俺が他の奴と話していたら嫌なんだ」
「……そうなのかも。ごめん、性格悪いよね。こういうところが僕ってダメなのかな」
唯斗くんが誰と仲良くしようが彼の自由だ。それを寂しいからと自分に縛りつける権限は、僕にはない。
同室だし、席も隣同士で自然と仲良くなったけど、それは唯斗くんが僕にやさしくしてくれるからだ。自惚れていいはずがない。
「どうしてそう卑屈に考えちゃうのかな」
唯斗くんは呆れた顔をしながら、僕の肩に額を置いた。小さな頭がすっぽりとおさまる。
いつも嗅いでいるシャンプーの匂いが濃く感じた。
「俺はもっと藍と仲良くなりたい」
「ぼ、僕も!」
「俺はちょっと意味が違うけどね」
「意味が違う?」
それってどういうことだろうか。
考えようとして窓に視線を向けてはっとした。
「てかこのポーズいいな。写真に撮りたい」
「この状況でよく漫画のことを考えられるね」
「窓越しに薄く反射してるの見える? すごい素敵だよ。あ~誰か通りがからないかな」
「絶対撮らせたくない」
唯斗くんは呆気なく僕の肩から離れてしまった。でもまだ匂いが残っていて、僕の胸の鼓動が速くなる。
空が群青色に染まっていた。小さな星が点々とのぼっている。波打つ音がざわわと聞こえた。
さっきまで寂しかった気持ちが嘘のように軽い。唯斗くんに話したお陰だろう。
「話を聞いてくれて、聞かせてくれてありがとう。唯斗くんも同じなんだってわかって、ちょっと元気だな」
「どういたしまして」
「唯斗くんのこと、たくさん知れて嬉しい」
「じゃあもっと仲良くなること、する?」
意味深に口角を上げる唯斗くんに僕はドキドキしながら頷いた。
「仲良くなるってこういうことか」
「なにを想像してたの、藍は」
「別に……」
僕はぶうと唇を尖らせ、手元のノートに視線を移した。
唯斗くんの「仲良くなる」は毎日勉強をすることらしい。
昼休みや放課後、休みの日も付きっきりで勉強をみてくれる。
お陰で授業中に指されても過度に緊張しないようになった。
昼休みに僕と唯斗くんが勉強をしていると前の席のシンタも加わる。といってもシンタは頭がよく、通学中の電車やバスの中で教科書を読めば覚えられるのだ。
だからシンタは僕が問題を解いているのをただじっと眺めている。見るだけで覚えられるなんて特殊能力を持つファンタジーのキャラみたいで羨ましい。
唯斗くんはシャープペンの先で教科書を指した。
「そこはこっちの公式を使って……そうそう。だいぶ理解できてきたね」
「唯斗くんの教え方が上手だからだよ。まさかこんなに自分が勉強できるようになるなんて信じられない」
「ここ受験するときはどうしたの?」
「そのときは必死になってやったな〜たまたま得意な問題ばかり出たし、ラッキーだったかも」
「こいつ、昔から運だけはいいんだよ」
シンタが顎をしゃくって僕をさした。唯斗くんが目をくりっとさせている。
「他にもあるの?」
「ドッジボールで最後まで当てられなかったり、くじ引きでよく一等当たるよな。あとは道で倒れてたじいさんを助けたら、うちの市長で表彰されたり」
「へぇ〜すごい」
「たまたまね」
運だけでここまできたようなものだ。自分の実力ではない。
周りに恵まれているのもそうだ。シンタは小学校からずっと一緒だし、前に同室だった子もいい人だった。唯斗くんは僕にとてもやさしい。
「唯斗〜ちょっと英語でわかんないところあるんだけどさ」
隣のクラスである山岸くんがズカズカと教室に入り、唯斗くんの席にまで来た。後ろには三人ほど坊主がいるから野球部なのだろう。
山岸くんがシンタに気づくと目を丸くさせている。
「お、水間じゃん。珍しく勉強してんの?」
「オレをそこら辺のヤツらと一緒にすんな」
「どんだけ天才なんだよ」
山岸くんはニカッと歯を覗かせた。夏の青空のようにからっとした笑顔だ。
山岸くんがシンタを慕っているのがよくわかる。
「ごめん、いま藍の数学みてるんだ」
「は?」
唯斗くんが断ると山岸くんはじっと僕を見た。
この感覚はよく覚えている。
僕が人気者のシンタと仲良くしていると、よく思わない人がいた。そのときに向けられる目に似ている。
山岸くんは僕のノートを覗いて、さっと教室を出て行った。後ろにいた三人も首を傾げながら続いていく。
もしかして僕がいるから嫌になっちゃったんだろうか。
「僕は一人でも大丈夫だよ。山岸くんたちをみてあげて」
「俺が監視してないとまた絵を描くでしょ」
「シンタに見ててもらうよ」
「おい、オレを巻き込むな。まだ死にたくない」
シンタがぶるぶると首を横に振った。そんなに僕の勉強を見るのが嫌なのかな。ちょっと傷つくんですけど。
唯斗くんはじろりとシンタを睨みつけたあと、僕に笑顔を向けた。
「いまは藍優先だから」
唯斗くんの言葉にかぁと頰が熱くなる。山岸くんを差し置いて僕を優先してもらっていいのだろうか。
やっぱり僕は運がいいのかもしれない。
「じゃあ数学ならいいだろ?」
山岸くんたちは英語の教科書から数学の教科書とワークに変わり、戻ってきた。
確かに英語と数学を別々に教えるより、唯斗くんの負担は少ないかもしれない。
「でも」
唯斗くんは困惑している。さすがに向こうが融通を効かせたのに何度も断るのは気が引けるのだろう。
「い、いいよ! 一緒にやろう」
僕は上擦らないように言うと山岸くんは目を見開いた。そしてにっと笑顔を向けてくれる。
「沢渡、サンキュー!」
「僕の名前知ってるの?」
「そりゃ有名人じゃん」
「え?」
「人の顔をじっと見てくる、二組の研究くんだろ」
僕が目を丸くしているとシンタも知らなかったようでぽかんとしている。
「だって人の顔をいつも観察してるだろ。話しかけるわけでもなく、なんか研究されてるみたいって入学当時から話題だったじゃん」
悪気のない山岸くんの笑顔に、僕は相槌を打つことすらできなかった。
中学のときと同じだ。
「俺たちは遊んでやってるのに、どうして沢渡は大事にするんだ」といじめのリーダーの子に責められたのだ。
もしかして僕がずっとみんなのことを見てて気持ち悪いから避けられていたのだろうか。
足が震える。いますぐ逃げ出したい。
でもそれじゃ中学のころと変わらないじゃないか。
僕は大きく息を吸った。
「……嫌な思いをさせてごめん。実は絵の参考にしてて」
「へぇ見せて!」
「これなんだけど」
僕は引き出しに入っているスケッチブックを出した。最初はクラスメイトを参考にして描かせてもらっていたけど、ページが進むにつれ唯斗くんばかりになる。
それを見た山岸くんが感嘆の声をあげた。
「うまっ! なにこれ、プロ?」
「……漫画家目指してるんだ」
「これならなれるじゃん! あ、オレもいる!」
山岸くんがめくったページには野球部の練習風景を描かせてもらっている。ボールを投げる山岸くんや、走り込みをしている部員がページいっぱいに埋まっている。
「てかなんで男しかいないんだ?」
びくりと肩が跳ねた。さすがにBLを描いていると知られたらマズイ。
「男子校なんだから男しかいないだろ」
「それもそっか」
シンタの助け舟に山岸くんは頷いた。結構単純なのかもしれない。
山岸くんはパラパラとページを捲り、太い眉を寄せた。
「でも勝手にスケッチするのは肖像権とかやばくね?」
「はい……仰る通りです。本当にすいません。これも処分します」
「描いた人にはちゃんと許可取ればいいんじゃね? オレは別に構わねぇよ」
な、と山岸くんが振り返ると野球部の三人が頷いている。
そんな簡単にいいのだろうか。僕が勝手に描いた張本人のくせに心配になってしまう。
「むしろこんなイケメンに描いてくれるなら喜ぶ奴が多そう」
「そうかな?」
「うん、いいと思う!」
にっと笑う山岸くんにうっかり泣いてしまいそうになった。
でも唯斗くんは難解な問題にぶつかったような顔をしている。
僕と目が合うとぱっと笑顔に戻った。
「藍の専用モデルは俺だけだから、他の人はもう描かないでよ」
ちょっと拗ねたような唯斗くんが可愛くて、僕は笑ってしまった。