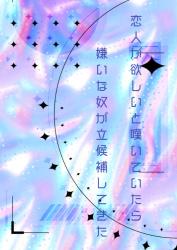五月下旬に体育祭が始まった。
一般公開されないし、家族も来場できないからむさ苦しい男たちの雄叫びだけが青空に響き渡っている。
けれど宇梶くんが出場すると黄色い歓声に変わった。
「きゃー! 唯斗ー!!」
「こっち向いてー!」
唯斗くんがグラウンドに登場しただけで、アイドルのコンサートのような盛り上がりである。声変わりの済んだ裏声がそこかしこに響いていた。
しかも宇梶くんの存在は他学年も知っているようで、龍の咆哮のような音量だ。
学校の裏が海でよかった。これが住宅街だったら騒音問題になっていただろう。
僕が校庭に視線を向ける救護テント側のスタート位置に宇梶くんの姿が見えた。猛々しい声援に手を振って応えている。
次は百メートル走、最終レースだ。
宇梶くんと同じレーンには、各運動部で俊足の選手が揃えられている。
特に野球部エースピッチャーの山岸くんが頭一つ分抜いて速いらしい。
だからといってそう簡単に負けるつもりはないのだろう。
他の選手たちもみんな引き締まった顔をして、負けてたまるかとオーラを出していた。
メラメラと闘志が燃え上がっている様子を目に焼きつけ、僕は応援席に座りペンを走らせている。
隣のシンタは呆れた様子だ。
「ここでも描くのかよ」
「こんなシーンめったにないからね! あ、シンタは写真撮ってよ」
「なんでオレが」
文句を言いながらもシンタはしっかりスマホを構えてくれる、
スタートラインに立つ宇梶くんに目を奪われる。指定の体操服すら完璧に着こなし、王者の登場に相応しく赤いハチマチが風に靡いていた。
「いちについて……よーい」
パンッと銃声音と共に選手たちが一斉に走り出す。拮抗状態だったが、コースの半分を過ぎると二人が飛び出てくる。
宇梶くんと山岸くんだ。宇梶くんが珍しく苦しそうな表情をしている。でもそれよりも彼の走るフォームに見惚れた。
なんて美しいんだろう。背筋がピンと伸び、前に繰り出す足の筋肉のハリが彫刻品のようだ。
僕は目を走らせながら描き殴った。隣のシンタはパシャパシャと連写をしてくれている。
ゴール直前に宇梶くんが一歩リードし、前のめりになってテープを切った。
どっと歓声が沸く。
一位の証拠に宇梶くんは係の人から金ぴかのシールを胸元に貼られていた。
「おおおおぉ!! さすが、唯斗!」
クラスメイトが唯斗くんに賛辞を送っている。うちの学年で一番速い山岸くんに勝ったのだから当然だろう。
僕は一通り描き終えると、一位の旗の前で座っている宇梶くんをやっと冷静に眺めることができる。
「すごっ……」
「へぇ〜宇梶やるじゃん」
シンタがぴゅうと口笛を吹いた。
去年までならシンタが学年一速かったが、肘の怪我により激しい運動は控えている。その横顔に少しだけ悔しさが混じっているのを見逃さなかった。
宇梶くんと本気で走ってみたかったんだろうな。
宇梶くんのお陰で、赤組に得点が入ったけど、白組との差は歴然としている。
三学年をクラスごとに縦割りで紅白に分けられているので、三年生からの野次がすごい。みんな元は運動部だから、例え体育祭でも負けるのは嫌なのだろう。
僕の背中にじっとりとした汗が浮かんだ。
「どうだった?」
応援席に戻ってきた宇梶くんが僕の隣に座った。
あれだけ白熱した走りをしたというのに、宇梶くんは額に小粒の汗を浮かべているだけだ。息も乱れていない。
宇梶くんは体操服の襟を伸ばし乱暴に額を拭うと鍛えられた腹筋がよく見える。
――パシャッ
僕の反対側を見るとシンタが宇梶くんを撮っていた。
「ナイス、シンタ! いまのやつ、写真に欲しいと思ってたんだよね」
「おまえの考えてることなんて手に取るようにわかるからな」
「ありがとう!」
僕がシンタのスマホ画面を覗き込んでいると、こつんと額にデコピンをされた。
「俺の走りはどうだった?」
下唇を突き出してちょっと不機嫌そうな宇梶くんがじろりと僕を見下ろしている。その顔もいいな、写真に撮りたい。
でもいまはきっとそんなことをしちゃだめなんだろう。それくらいわかっている。
「一位おめでとう! すっっっっごくカッコよかったよ! フォームが機械みたいに揃ってて」
「……機械?」
「一切の乱れがないところがすごい。あと筋肉のハリとかも最高だった〜」
なんで僕の眼球には録画機能がついていないんだろう。それがあればいつでも宇梶くんの走りをリピートできるのに。
「もう一回言って」
「筋肉のハリが最高!」
「じゃなくてもっと前」
「すっっっごくカッコよかったよ?」
「ん」
宇梶くんは頰をちょっとだけ赤らめて、手の甲で口元を隠してしまった。急にどうしたんだろう。もしかしてあんなスピードで走ったから気分が悪くなったのかな。
『続きましては借り物・障害物競争です。選手の方は入場口に並んでください』
放送が流れて僕は顔をあげた。
「あ、僕たちの番だ」
「そうだな、行くか」
シンタが立ち上がったので僕もついて行こうとすると、体操服を引っ張られた。振り返ると宇梶くんがにっと白い歯を覗かせている。
「頑張ってね」
「転ばないようにするよ」
僕はへらっと笑ってみせた。運動全般苦手だけど、宇梶くんに応援してもらえたから頑張るしかない。
僕とシンタが列と前後になって座る。
「おい、藍。宇梶見てみな」
僕が首を伸ばすと応援席から宇梶くんが手を振っているのが見える。青空に届きそうなほど腕が長い。でも誰に振っているのだろう。
これで僕が振り返して、本当はシンタだったりしたら恥ずかしくて競技どころではなくなってしまう。
「シンタに手を振ってるんだよ」
「なら確かめてみるか」
シンタも腕を伸ばして振ると宇梶くんは腕をクロスさせて、首まで振っている。
「ほら、オレじゃないだろ」
「でも」
「いいから」
シンタに促されるまま僕が小さく手を振り返すと宇梶くんはぱっと笑ってくれた。
その笑顔を見ていると萎んでいた気持ちが息を吹き返す。頑張って、と応援してもらえたし気合い入れよう。
「お、次オレか。行って来る」
「無理しないでね」
「ん」
銃声が鳴るとシンタはジョギングのようなペースで走り出した。平均台や網くぐりをすいすいと泳ぐ魚のような滑らかさで終わらせていく。
あっという間に障害物を終え、ゴール手前に置いてある箱までたどり着いた。そこには人や物のお題が書かれたメモが入っていて、お題と一緒にゴールしなければならないのだ。
シンタはメモを読むとまっすぐ応援席へと走って行った。
「坊主の人、来てー!」
シンタが声をかけると野球部がわらわらと集まりだした。
「一人でいいって! なんで全員来るんだよ!!」
シンタが怒っているのに誰一人抜けようとはしない。一、二年で総勢五十人ほど集まり、赤組も白組も関係なく、みんなで肩を組んでゴールテープを切った。
「なんだよこれ〜」
「最高!」
なぜか全生徒から拍手をもらい、シンタは恥ずかしそうに応援席に戻って行った。
クラスのみんなからも声をかけられ、照れくさそうに後頭部を搔いている。
いいものを見せてもらったな。
でもあんな盛り上がったあとにやるのはハードルが高くない?
僕がスタートラインに立つと宇梶くんは長い腕で丸をつくってくれた。意味はわからないけど頑張れってことかな。
「いちについて、よーい……」
パンッと音と共に僕は飛び出した。といっても運動ができないメンバーが揃っているので全体的にモタモタしている。
平均台は落ちるし、網には引っかかって靴は脱げる選手が続出している。かくゆう僕も体操服が網に引っかかってしまった。
けれど頑張って走っているので、絶賛一位をキープしている。
ようやく最後まできて、僕は箱に手を突っ込んだ。お題はなんだろう。変なものじゃなきゃいいな。
紙を広げて僕は首を傾げた。
「好きなもの……?」
好きなものってなんだろう。BL漫画? いや、さすがにあり得ない。でもそれ以外に好きなものがぱっと思い浮かばなかった。
「早くしろー!」
「沢渡、なにしてるんだよ!」
僕が考え込んでいる間に他の選手たちはお目当てのものに走っている。いけない、このままだとビリになってしまう。
「沢渡ー! おいで!!」
宇梶くんがぴょんと跳ねながら僕を呼んでくれている。
吸い寄せられるように応援席に向かった。
「お題なんだったの?」
「好きなものって……どうしよ。寮に戻って漫画は取りに行けないし」
歓声の中に僕への野次が聞こえ、頭がぐちゃぐちゃになる。早くしなきゃ。でもどうしよう。こんなもの適当でもいいだろ。わかっているのに身体が動かない。
宇梶くんが僕の肩を撫でてくれ、はっと顔を上げた。
「沢渡は俺のこと……好き?」
「えっ、うん。そりゃもちろん」
イケメンでやさしくて、僕の趣味に付き合ってくれる宇梶くんを嫌いになる方が難しいだろう。
「よし! じゃあいいね!!」
宇梶くんは流れるように僕の膝裏に手を差し込み軽々と持ち上げた。
いわゆるお姫様抱っこというやつだ。
「宇梶くん!?」
「この方が速い」
僕を担いだまま宇梶くんは走りだし、すでにゴールへと向かっていた選手を次々に抜いていった。
僕への非難の声が奇声に変わる。
宇梶くんはそのままゴールテープを切った。
「やった、一位だよ!」
宇梶くんの顔の周りにキラキラと光の粒子が見える。スローモーションのように宇梶くんの表情が移り変わる瞬間がわかった。
もっと見ていたい。この笑顔を閉じ込めておきたい。
胸が高鳴って痛いくらい拍動している。僕は胸を押さえて、じっと宇梶くんを見返した。
「……沢渡?」
「あ、あぁ……ごめん。ぼうっとしてて」
「俺に見惚れてくれてるのかと思った」
「えぇ!」
確かにそうだけど、こんな間近で言われると照れる。
一位の列に並ぶとようやく降ろしてもらえた。地面の感触にほっとする。
「一位のシールもらったよ」
宇梶くんは金ピカのシールを僕の袖に付けてくれた。
僕は体操服を引っ張って、まじまじとシールを見下ろした。一位と中央に書かれ、それを囲うように王冠が描かれている。
一位なんて生まれて初めてだ。
同じものが宇梶くんの胸元にも光っている。
「お揃いだね」
白い歯を覗かせる宇梶くんの笑顔に目が離せなかった。
まだ胸がドキドキしている。
体育祭から一週間経ったというのに、スケッチブックの表紙に貼った金ピカのシールを見ると宇梶くんの笑顔を思い出してしまう。
すごく、カッコよかった。
でも宇梶くんは芸能人並みに美しい顔面だし、ドキドキするのは自然なことだろう。
僕はベッドの上でゴロリと寝返りを打ち、宇梶くんの方を向いた。
宇梶くんは僕に背中を向けて机に向かっている。課題が出ていたからそれをやっているのかな。それとも明日の授業の予習だろうか。
宇梶くんの成績はよく、頭脳明晰、運動神経抜群と最早完全無欠の超人だ。
宇梶くんがシャープペンを走らせるシャッシャという音だけが部屋に響く。ときどき息を吐いて、問題に悩んでいるようだ。
後ろ姿なのが惜しい。
どんな顔で勉強に取り組んでいるのかな。クラスの席は隣だけど、見ていると描きたくなってしまうから見ないようにしてる。でもいまならいいかな。
起き上がろうとするとポンと通知が鳴り、僕はスマホを手に取った。創作アカウント用のアドレスにメールがきたらしい。
「え~と……な、夏コミに受かった! うそ、やった!!」
僕は小さな子どもみたいにベッドの上を跳ねた。まさか受かるなんて思ってもみなかったのだ。
無名な上に実質一人しかファンがいないのに本を出せる? 夢じゃないよね?
不安はあるけど、それよりも嬉しさの方が何倍も上回る。
「なにかいいことでもあったの?」
「あ、ごめんね。勉強の邪魔しちゃって」
「ちょうど終わったし平気だよ」
宇梶くんが振り返ると椅子がぎしりと鳴る。
「あのね、コミケに受かったの!」
「漫画とかアニメのイベントみたいなやつ?」
一般人の認識はやはりこういうものなのだろう。
僕は大きく頷いた。
「アニメや漫画の二次創作や自作の漫画や小説、企業が限定グッズを販売する即売会だよ」
僕が鼻息荒く説明するけど、宇梶くんはあまりわかってなさそうだ。でも「よかったね」と笑ってくれる。
一息に説明したので酸欠になり、僕は大きく息を吸った。お陰で少しだけ冷静になれる。
だから現実がしっかりと見えた。
「でも僕の本を買ってくれる人っているのかな。実質見てくれる人は一人だけだし」
初めてのイラストが万バズしたとはいえ、そのあとは一人だけだ。告知をしても実際に手に取ってくれるだろうか。
僕はスマホでSNSのアカウントを立ち上げた。やっぱりどのイラストも閲覧数は三のまま増えていない。
画面を覗いた宇梶くんが首を傾げる。
「それなんだけどさ、これ鍵付きになってない?」
「え?」
「ほら、俺のアカウントから見ると沢渡があげたイラストにモザイクがかかって、鍵マークがついてるでしょ?」
僕が宇梶くんのスマホを覗くと、確かに僕のペンネームである「サワリーラン」のメディア欄には鍵マークがついていた。
というか投稿そのものが見えないようになっている。
「本当だ。全然気づかなかった」
「しかも四桁の数字を入力しないと見れない仕様になってるよ。パスワードのヒントは誕生日って書いてあるけど……設定した覚えある?」
「あ~そう言われるとそうかも」
万バズしたイラストだけど、あまりに反響が大きくて怖くなって消したのだ。
しばらくしてから投稿し直したけど、そのときうっかり鍵をつけてしまったのかもしれない。
僕はインターネット関連には疎い。このSNSアカウントもシンタに教えてもらいながら作ったのだ。そういうシンタも野球ばかりしてたからネットに強いわけではない。
「プロフィール欄の設定ってとこからパスワード解除ってやれば大丈夫だよ」
宇梶くんに言われるがまま操作するとメディア欄の鍵マークが消えた。
瞬く間に♯創作BLで投稿したイラストの閲覧数が増えていく。
「どんどん伸びる! 宇梶くん、ありがとう!」
「どういたしまして」
「てかどうして僕のアカウント知ってるの? 教えたっけ?」
「あ~水間くんに訊いたよ」
「そっか。なんか恥ずかしいな」
へらっと笑うと宇梶くんは嬉しそうに笑ってくれた。
また、あの表情だ。
体育祭で「お揃いだね」と言ってくれたときと同じ笑顔をしている。この顔はどういう嬉しいの顔なんだろう。
僕はカメラを起動させて、宇梶くんの顔を撮った。画面いっぱいに宇梶くんの笑顔がおさまっている。
「ちょっと勝手に撮らないでよ」
「でもいい顔してたから……だめ?」
「ぐっ……俺がその顔に弱いと知ってやってるの?」
「ん?」
「……いいよ。じゃあその代わり、俺のことを唯斗って呼んで。俺も藍って呼ぶから」
「それ等価交換じゃないよね!?」
「なら写真は消してもらう」
「え~」
宇梶くんの顔は真剣だ。あまり見たことがない怒ったような顔をしている。
せっかく撮れた写真を消したくない。でも「唯斗」って呼び捨てにするのは恥ずかしい。
「唯斗、くんじゃだめ?」
「それでもいいよ」
「よかった。じゃあこの写真は大切にするね、唯斗くん!」
唯斗くんはなぜか頭を抱えてしまったので、僕は首を傾げた。
あんまり呼ばれたくなかった? もしかして滑舌が悪いのかな?
「あ〜破壊力やばすぎ」
唯斗くんはぶつぶつと言っていたけど、僕にはよくわからなかった。
学校から徒歩十分程度のところに海がある。
海開きが始まる前に全校生徒でゴミ拾いをするという年間行事があるのだ。
まだ梅雨とは思えないほどの日差しが降り注ぎ、粘度のある汗がじっとりと僕の頬を伝う。
立ち止まって顎に溜まった汗を拭っていると、シンタが大声をあげた。
「あ、またペットボトルじゃん。もう何回目だよ」
トングでペットボトルを拾ったシンタは、手持ちの袋に入れた。僕も隣に落ちている缶を拾って、袋に入れる。
海はきれいなのに砂浜にはあり得ないほどのゴミがあるのだ。毎年地域住民や海南の生徒がゴミ拾いをしているけど、年々増えている気がする。
「くそっ……なんで毎年毎年こんなことやらなくちゃいけねぇんだよ」
キャップを取って汗を拭ったシンタは朝から文句ばかりだ。その気持ちはわかるけど、病気以外の欠席は内申に響くのでズル休みはできない。
日光を含んだ砂浜は熱い。それに海藻が腐ったような悪臭を放っている。
とても環境がいいとは言えない。
なにより僕は暑さに弱く、膝に手をついた。
「確かに……しんどいよね」
「顔真っ赤だそ。大丈夫か?」
「ヘーキ。たまには運動しないと」
僕は高校に入学してからというものの、ペンより重いものを持たない生活をしている。運動不足なのは自覚しているので、こういうときに動かないとマズイ。
「藍、具合い悪い?」
僕が立ち止まっていると唯斗くんが戻って来てくれた。
事務のおばちゃんから借りたツバの大きい麦わら帽子をかぶった唯斗くんは、日焼けしないように長袖長ズボンのジャージを着ている。とても暑そうだ。
でも汗が日差しを反射して宝石みたいに輝いていて、イケメンだと得だなと思ってしまう。
「大丈夫だよ〜」
「じゃあこれ貸してあげる」
唯斗くんは自分の首につけていたネッククーラーを貸してくれた。もちろんこれも事務のおばちゃんから借りたらしい。イケメンは至れり尽くせりだ。
首にかけてもらうとひんやりとして気持ちいい。あんなに火照っていた身体が瞬時に冷えるのがわかる。
「ありがとう。少しラクになった」
「あと十分で休憩だから無理しないでね」
そう言って笑いかけてくれる唯斗くんの美しさに目を覆いたくなった。
麦わら帽子とジャージに軍手という姿なのに、背景に海があるからなんでも絵になってしまう。
BLをこよなく愛する腐男子として、美しいものには目がない。イケメンは国宝だし、きゅるんとした可愛い男の子は常にSPがついて護られるべきだとすら思う。
唯斗くんのお陰で元気出てきた。
僕たちが再びゴミ拾いを始めると、波打ち際ではしゃいでいるグループが目についた。二人で追いかけっこしてきゃっきゃと声をあげている。
「待って〜私の運命!」
「それって「恋はじ」?」
「そうそう! ショート動画でバズってたよな」
グループはゴミ拾いもせずにはしゃぎ、巡回していた教務主任の先生に怒られていた。
その様子を眺めていると隣の唯斗くんが固まっていることに気づく。
「唯斗くん……? どうかした?」
「……いや、なんでもない」
あんまりそうには見えないけど。もしかして熱中症かな。でも具合いが悪そうには見えない。
ちょっと話題を変えてみよう。
「「恋はじ」ってなんだろ。ドラマかな?」
「「初めての恋を始めませんか」。通称「恋はじ」で、現役高校生の恋愛リアリティ番組だな」
さすが地球規模にストライクゾーンが広いシンタだ。まさかそんな番組まで網羅しているとは思わなかった。
でも高校生の恋愛リアリティ番組なんてものがあるんだ。学校内だけじゃだめなのかな。
「いまってそんなのあるんだね」
「ネットで検索するとすぐ観れるぜ」
シンタがスマホを取り出してサイトを見せてくれた。男女八人が一週間ほど旅に出て、運命の相手を見つけるものらしい。
両想いになったら二人で帰り、振られたら一人で帰る。プロフィールを見たら僕たちと同世代の男女ばかりだ。
みんなモデルやインフルエンサーらしく、顔面偏差値が高い。男の子も少女漫画顔負けの美男子揃いで、これは女子受けもよさそうだ。
先月で「恋はじ」が三期目に入り、メンバーはすべて入れ替わっているとのことだ。
「へぇ〜こんな世界があるんだね」
「同じ世界だよ」
「別世界って感じ……唯斗くん、大丈夫?」
ずっと黙ったままの唯斗くんは僕が声をかけるとやっと動き出した。
でも関節が錆びついているように動きがぎこちない。心なしか笑顔が無理している感じがする。
「もしかして具合い悪い?」
「いや、大丈夫。ちょっと嫌なこと思い出しただけ」
「そっか。無理しないでね」
「うん」
でもその日の唯斗くんはなかなか元気になってくれず、疲れたのか夜はすぐに眠ってしまった。
一体、どうしちゃったんだろう。