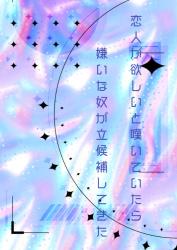宇梶くんはものの二日で完璧にクラスに溶け込んだ。あたかも最初からいたように教室の中心にいて、昼休みのいまはクラスメイトと楽しそうに話している。
僕はそんな宇梶くんを盗み見ながらペンを走らせた。
宇梶くんが笑うと少し尖った犬歯が見える。目尻が下がるのでゴールデンレトリバーを彷彿とさせた。
瞬きもせずに宇梶くんの表情を頭の中で記憶して、手早くスケッチブックに描く。
うん、かなりいい感じだ。
でもちょっと物足りない。
クラスメイトと話しる自然体の宇梶くんもいいけど、それだとボーイズがラブする感じではないんだよな。
「でさ~唯斗、聞いてよ」
「なに?」
クラスメイトの一人が宇梶くんの肩を組み、甘えるように首をもたげている。
そうだよ、それそれ!
シャープペンを握る指に力が入る。じゃれ合い最高です。ありがとう、クラスメイト! 名前はごめん、わかりません。
ほら、二年に進級したばかりだし?
でもめちゃくちゃ感謝してます!
肩を組まれた宇梶くんは平然と会話をしている。すごい。一切のテレがない。あれが陽キャの普通なのだろうか。
僕が鼻息荒く描き殴っているとスケッチブックに影が入った。
「それって盗撮にならないのか? いや、盗模写っていうのか」
前の席のシンタが僕の手元を覗いている。スケッチブックには隙間がないほど宇梶くんの絵で溢れていた。
僕は得意げにふふんと鼻を鳴らす。
「実は本人に許可もらったんだ」
「てことは腐男子だってことは」
「まぁいろいろあってバレちゃった」
「大方、自爆したんだろ」
鋭い。さすが幼馴染だ。
「でも宇梶くん、引かなかったんだ。僕の絵を気に入ってくれたみたいで、見せる代わりにモデルを引き受けてくれたし」
「藍の絵は上手いもんな」
「そう言ってくれるのシンタと宇梶くんだけだよ」
「二人に増えてよかったじゃん」
「うん」
評価が欲しくて描いているわけじゃないけど、褒められるとやっぱり嬉しい。モチベーションが上がる。
「夏コミ受かったら新作漫画描こうと思ってるんだ」
「話は決めた?」
「まだ。でもなんとなくの構想はあるけど」
「じゃあパニックホラーでよろしく」
シンタはコンビニの菓子パンを一口食べ、スマホに視線を落とした。
電子書籍で漫画を読んでいるのだろう。ちらりと見えた絵はグロテスクなホラーものだった。
よくそんなものを読みながら食事ができるな。
僕は視界にいれないように背中を引いた。怖いのは苦手だ。
「嫌だよ、そんな話。僕はきゅんとして甘酸っぱいものが好きなんだから」
「好きそう。いかにもって感じだよな」
「どういう意味?」
えくぼを浮かべるシンタの笑い方にむっとした。どうせ恋愛未経験の童貞だと莫迦にしているのだろう。自分も同じくせに。
「二人でなんの話をしてるの?」
席に戻ってきた宇梶くんは僕とシンタの顔を交互にみやっている。
僕とシンタは目配せをして、同時に首を傾げた。
「えっと……なんだろう?」
「パニックホラーBL」
「それはシンタが勝手に言ってるだけでしょ」
「いや、絶対流行るって」
「そんなの描けないよ」
「なんかいい感じに暗くして、線多く描けばいいんじゃね」
「適当だな」
僕が鼻白んでいると宇梶くんは目を丸くさせている。
「沢渡と水間って仲いいね」
「幼稚園からの幼馴染なんだ」
僕が答えると宇梶くんは「でも水間は通いじゃなかった?」とさらに驚いている。
シンタは口元のパン屑を乱暴に拭った指で僕をさした。
「こいつ、BL漫画描きたいからって入寮したんだぜ」
「えっ、そうなの?」
僕はすかさず首を振った。
「自立するために寮にしたんだ。ま、兄弟が多くて一人になりたかったのもあるけど。ここから電車とバスで三十分くらいの距離だよ」
「じゃあほとんど地元ってことか」
「宇梶くんはどうしてこんな田舎に来たの? 親の仕事の都合とか?」
「うん……まぁそんな感じ」
宇梶くんは困ったように笑った。頬もちょっと力がはいっているし、あんまり触れて欲しくない話題なのかもしれない。
「水間は沢渡のBL漫画のこと知ってるんだ」
「まあな。昔から描いた漫画とか絵とか見せられてきたし。その延長って感じだな」
「シンタは大雑把で偏見ないから、BLでも読んでもらえるんだよね。あと、いろんな漫画とか読んでるから結構いいアドバイスをしてくれるんだよ」
僕はシンタの守備範囲が広く、どんなジャンルも読むという話をしていると宇梶くんはちょっとだけ眉を寄せた。
「今度から俺も読ませてもらってもいい?」
「え、でもBLだよ」
「俺もそういうの偏見ないし。なんならちょっと気になるくらい」
「そうなんだ! なら僕のオススメ漫画を貸すよ」
「ありがとう。じゃあ寮に帰ってからの約束ね」
宇梶くんが長い小指を差し出してきたので驚いた。まさかBLシュチュによくある指切りげんまんですか!
まさかリアルでお目にかかれるとは思わず、鼻息が荒くなる。
「ちょっと待って。シンタが宇梶くんと指切りして」
「なんでだよ」
「写真撮る」
「なんでオレがそんなことしなくちゃーー」
「いいから! お願い!!」
僕が拝むとシンタは「面倒くせぇな」と言いながら宇梶くんの小指に絡めてくれている。
一瞬宇梶くんの顔が固まった気がしたけど気のせいかな。
「視線お願いします」
二人がこっちを見た瞬間、僕は素早く写真を撮った。正面から一枚と上から一枚。逆サイドに回って一枚と合計三枚撮った。
シンタはスポーツマンらしく骨格がしっかりしていて、ガタイがいい。でも目はきりっとした細めで猫っぽい。
対する宇梶くんは王子様のような華やかさがある。
違ったタイプのイケメンなので、二人の絵面は砂糖と塩のようにお互いのよさを引き立てている。
「ありがとう、二人とも!」
「……うん」
宇梶くんががっくりと肩を落としているのが気になったけど、僕はすぐにスケッチブックを開いて二人の絵を描き始めた。
「はぁ〜疲れた。あ、いっけない」
僕はベッドにダイブしてつい独り言をこぼしてしまった。まだ一人だったときの癖が抜けていない。
慌てて口を押えてカーテンに視線を向けると、宇梶くんの抑えきれない笑い声が聞こえてくる。
「ふふっ、沢渡といると楽しいな」
「ごめん、うるさいよね」
「平気。てかもっと話したいからカーテン取ってもいい?」
「えぇ!?」
「だめ?」
「僕と話してて楽しいの?」
「もちろん。じゃあカーテン取っちゃうよ」
カラカラと音を立てて僕と宇梶くんを隔てていたカーテンは取り払われた。いつの間にか宇梶くんは部屋着のスウェットに着替えている。
僕はまだ制服のままだ。
「着替えるの早いね」
「ブレザーって肩凝るからすぐ着替えるようにしてるんだ」
「確かに。でも着替えるのも面倒くさくない?」
「すぐやればいいんだよ」
「宇梶くんはしっかりしてるなぁ」
僕は着替える気力を養うためにタブレットを取って絵を描き始めた。
いまは宇梶くんが椅子に座ってくれている絵に色を塗っている最中だ。
「描いてるとこ見てもいい?」
「どうぞ」
宇梶くんは僕のベッドに腰掛けてタブレットを覗いた。
宇梶くんの髪は黒いのにキラキラしている。肌も艷やかで陶器のようにキレイなんだよな。
お風呂上りに化粧水やら乳液やらを塗っているし、かなり肌にはこだわりがあるっぽい。
僕は完成図を頭に思い描きながら、色を変えたり付け加えたりする。
「すご、こんな風にできるんだ」
「面白い?」
「どんどん絵が生きてくる感じがする」
「生きてくる……いい表現だなぁ」
命を吹き込む神様になったような気分で僕は作業に没頭した。
「できた!」
僕は出来上がった絵を宇梶くんに見せた。制服で座っているが、ただそれだけではおもしろくない。ニヒルな笑みを浮かべ、下僕を見下ろしているような貫禄を出している。
王子様然とした宇梶くんとは違った趣向にした。
「すご……自分じゃないみたい」
「ちょっとイメージと真逆にしてみたんだ。裏家業の親玉っぽい感じで」
「確かにそう見える」
「これ、SNSにあげたらマズイよね。制服がもろうちのだってバレるし」
「確かにそれはマズイかも」
「じゃあ勿体ないけど、このままお蔵入りだな」
「あのさ……この絵、もらってもいい?」
「いいけど」
「やった。待ち受けにする」
メッセージアプリで送ると、宇梶くんはさっそくロック画面に設定してくれた。
「めっちゃ嬉しい。大事にする」
「喜んでもらえてよかった」
宇梶くんは本当にいい人だ。僕の絵をこんなにも褒めてくれる。
「じゃあさ、ちょっとお願いしたいポーズがあるんだけど」
「なに?」
「足を開いて座って、太ももに肘をついて手を組んで欲しい」
「こう?」
「そうそれ! 親玉感増してる! 待って、写真撮るから」
宇梶くんを見ていると泉のようにアイディアが浮かんでくる。しかもそれを的確に再現してくれるので、自然と熱が入ってしまう。
僕たちは風呂の時間まで写真を撮っていた。
腐男子を隠さなくていいといありがたい状況に、風呂から出た僕は本棚にBL漫画を戻している。
僕がいそいそと整理をしていると、ストレッチをしていた宇梶くんが僕の隣に腰を下ろした。
「う、うわぁ……」
お風呂上りで上気している頬にまだ濡れている髪が合わさって色っぽい。Tシャツの隙間から覗く鎖骨がこれまたいい役割を果たしている。
高校生とは思えない色香にクラクラしそうだ。
僕の目が釘付けになっているとも気づかず、宇梶くんは本棚を眺めた。
「結構持ってるんだね」
「これでも一部だよ。残りは姉ちゃんの家に送ってる」
「実家じゃないの?」
「うちは弟と妹がいるから。僕がいない間に見られたら大変だし。でも姉ちゃんは腐女子だし、都内で一人暮らししてるから大丈夫なんだ」
なにしろ僕の師匠は姉ちゃんだ。BLというジャンルを教えてもらって感謝している。
「家族と仲いいんだね」
「うん! 宇梶くんは兄弟いる?」
「一人っ子」
「あ〜そんな感じする」
「わがままってこと?」
「どっちかっていうと自分のルールがしっかりあるって感じかな」
帰ってきてすぐ着替えるところがまさにそうだ。風呂上がりに化粧水を塗ったり、ストレッチをしたりとこだわりが強い。
「よく人のこと見てるんだね」
「なんとなくだよ。嫌な思いさせたらごめん」
「沢渡はすぐ謝る」
「癖になってるのかも。こんなオタクが生きててすいませんって感じで」
「卑屈すぎ」
くつくつと笑う宇梶くんはひまわりのように明るい。きっと僕みたいな偏屈になることなく、周りから愛される人生を送っているのだろう。
一通り笑い終わると宇梶くんは本棚に視線を戻した。
「そういえば約束した本は?」
「忘れてた。『これ愛』ね!」
僕は「これが僕たちの愛の話」の漫画を出した。
「どういう話なの?」
「これ幼馴染の二人なんだけど、ずっと両片思いをしてるのにお互い気づかなくて。諦めようとした攻めが彼女をつくってーーおっとこれ以上言ったらネタバレになっちゃうね。初心者でも読みやすいし、むずきゅん必須だよ」
「へぇ~」
僕の説明を聞いた宇梶くんは、裏表紙のあらすじをじっくりと読んでくれている。
自分の性癖を暴露してるようで恥ずかしいな。
未成年だから過激なシーンがない作品しか持ってないけど、普通にキスはするし、抱き合ったりもしている作品もある。
宇梶くんは抵抗ないかな。
棚に差さっている他の漫画の裏表紙も読んでから宇梶くんは口を開いた。
「沢渡は幼馴染モノが好きなの?」
「うん! 王道はいいよね。幼馴染故に長く一緒にいるから自分の気持ちに気づかなくて~すれ違って~なんてしちゃたり。「そうじゃないよ」と突っ込みながらハラハラする」
同性同士の葛藤があるからこそBLはいいのだ。それに幼馴染要素も加わると鬼に金棒だ。無敵すぎる設定である。
最初に思いついた人に賞をあげたいくらいだ。
宇梶くんは「これ恋」を抜き取った。
「敵情視察にもなりそうだし、これ借りておくよ」
「敵情視察?」
にこっと笑う宇梶くんに釣られて、僕もへらっと笑った。イケメンは笑うだけで許される。
「実は僕、将来BL漫画家になりたくて漫画も描いてるんだ。いま告白シーンをどうしようか迷ってて……宇梶くんはいままでどういう告白シチュがよかった?」
「えぇ!?」
悲鳴をあげる宇梶くんに驚いてしまった。顔が真っ赤である。
「宇梶くんのことだから、いままでたくさん告白されてきたと思って訊いちゃったんだけど……そっか。相手のこともあるから言えないよね。軽率でした」
「いや、そんなことはないけど……じゃあ俺の理想でもいい?」
「もちろん!」
宇梶くんは細い指を顎にかけ、しばらく考えてくれていた。
「放課後の誰もいない教室かな。なんか特別感があるし」
「王道だね!」
それもいいな。シチュエーションはすぐに浮かぶけど、ありきたりすぎる。あともう一押しが欲しい。
ぐるぐる考えているとぱっと閃いた。
「壁ドンだ!」
「ちょっと古くない?」
「使い古されてるからこそ定番と呼ぶんだよ」
「そうなの?」
宇梶くんは頭の上に「?」マークをたくさん浮かばせている。
リアルでやったらカツアゲみたいだけど、二次元だと別なのだ。
「ってことで壁ドンやってもらってもいい?」
「いま? ここで?」
「うん。あ、嫌だった?」
「……嫌じゃないけど」
「よかった。じゃあこの椅子にスマホを置いて……僕はここに立つから壁ドンをお願いします」
「うん」
僕が壁側に立つと宇梶くんは正面に来てくれた。頬がりんごのように真っ赤だ。どうやら照れているらしい。
僕相手に恥ずかしがる必要なんてないのにな。
「タイマーかけるね。五秒でいっか」
僕がスマホのボタンを押して戻ると宇梶くんが腕を伸ばした。宇梶くんの端正な顔が近づく。
だけどなぜか両目はぎゅっと瞑っていた。
ーーパシャ
「撮れたね。どれどれ」
僕が画面を確認していると、宇梶くんは頭を抱えてしゃがみ込んでしまっている。
「大丈夫?」
「……思ったより恥ずかしい」
「宇梶くんでも照れることがあるんだね」
「沢渡は堂々としてて、へこむよ」
「これ見て元気出して。結構きれいに撮れてるよ」
下からのアングルなので宇梶くんの腕の長さがより際立つ。
目は瞑ってしまっているけど、恥ずかしさが滲み出ていい。
俺様ちっくに壁ドンするのも悪くないけど、照れくささが混じってるとむずきゅん具合いが増す。
でも相手役が僕じゃなかったらよかったんだけどな。
こればっかりは仕方がない。
自分の顔は見ないことにしよう。
僕はもう一度スマホを椅子に立て掛けた。
「横からと、あと正面からも撮っていい?」
「まだ撮るの?」
「迷惑だったならシンタに頼むけど」
「頑張らせていただきます」
「そう? よかった~」
「いつもは水間と撮ってるの?」
「まさか。シンタは絡みの写真は嫌がるんだよね。だからいつもフリーの写真探してるの」
でもフリーの素材って探すの結構面倒なんだよね。著作権とか肖像権とかトレース問題とか色々あるし。
僕が愚痴をこぼすと宇梶くんは力強く頷いた。
「これから絡みの写真は俺とだけ撮ろう」
「いいの?」
「他の人とは撮っちゃだめだよ」
「ありがとう。宇梶くんはやさしいな」
僕が犯罪者にならないか気にしてくれているのかな。
まだ出会って二日しか経っていないのに宇梶くんはなんて友達思いなのだろう。
「じゃあせっかくだからハグの写真もいい? いい感じのフリー素材がないんだよね」
「え……」
宇梶くんはさらに顔を真っ赤にさせた。さすがに調子乗りすぎたかな。
やっぱり同性同士で抱き合うのは気分がよくないよね。
やめようか、と言いかけると宇梶くんは犬みたいに首を振った。
「が、頑張る……いくよ」
「はーい」
宇梶くんは顎に皺を寄せながらもハグをしてくれた。温かい。それにすごくいい匂いがする。お風呂上りだからシャンプーか。花のような上品な香りだ。
「すごくいい匂いするね。これってシャンプー?」
「えっ……あ、うん。昔もらったやつで」
「いい匂い〜宇梶くんに合ってる」
王子様の雰囲気がある宇梶くんのために誂えた香りみたいだ。
背中に回された宇梶くんの腕が小刻みに震えている。
「それより写真は?」
「ごめん、忘れてた。タイマーやるからちょっと離してもらっていい?」
「あぁ」
宇梶くんの腕からするりと抜けて、僕はタイマーをセットして、写真におさめた。
「う〜ん……身体が離れてるから微妙だな。もうちょっとくっついてもらっていい?」
写真を確認すると宇梶くんと僕の間には人一人が入れそうな空間ができている。さすがにこれは不格好だ。
だけの宇梶くんはあまり乗り気ではないみたい。
「あ〜うん」
「無理しなくていいよ? こんなオタクとハグなんて……」
「無理なんてしてないから! よし、もう大丈夫」
宇梶くんは赤い顔のまま、ぎゅっと目を瞑った。そこまで覚悟をさせて申し訳ない。
もうこの際、さっさと終わらせてしまった方が宇梶くんのためだろう。
「じゃあ撮るよ〜」
僕はもう一度タイマーボタンを押して宇梶くんの背中に腕を回した。
宇梶くんも僕の腰を抱いてくれ、ぎゅっと密着してくれる。
思ったより宇梶くんの身体に厚みがあった。細いと思っていたけどしっかりと鍛えているんだな。
顔を上げると宇梶くんがちょっと怒ったような嬉しいような、色んな感情が混ざったような顔をしていた。
いま、宇梶くんはなにを考えているんだろう。
パシャッと音がすると驚くほどの速さで宇梶くんは離れた。
僕が写真を確認すると、イメージ通りにうまく撮れていた。
「ばっちり! じゃあ次は……」
「まだあるの?」
宇梶くんは辟易していたけど、最後まで僕の言う通りに絡みの写真を撮ってくれた。
すごくいい人だ!
宇梶くんが協力してくれたお陰で熱が入ってしまい、僕は徹夜で壁ドンの絵を描きあげた。
宇梶くんが真っ赤にしている顔が、うぶさがあっていい。台詞を言わせるなら絶対噛ませたいな。
登校する前にイラストをSNSに投稿して、昼休みに確認したけど閲覧数は三のままだった。
渾身の作品なのにどうしてだろう。
「あ~僕のなにがだめなのかな」
眠気と疲労で重たい溜息を吐くと、前の席のシンタが振り返る。
「どした?」
「今朝のイラスト、見てくれたよね?」
「あぁ、よかったよ。恥ずかしそうに壁ドンするのが妙にリアル。あれって宇梶?」
「よくわかったね」
「おまえの絵は昔から見てるからな」
似せて描いたつもりはなかったんだけど、見てる人には気づかれちゃうんだな。宇梶くんだと気づかれないように本人にも言われてるし、ちゃんとしないと。
つまり僕の画力が足りないってことなのかな。へこむ。
はぁとまた溜息がこぼれた。
「どうして閲覧数増えないんだと思う?」
「やっぱまたバズりたい?」
「そうじゃないけど、一人でも多くの人に届いて欲しいなって」
僕のイラストを見て元気になってくれる人がいたら嬉しい。
そうするためには、たくさんの人の目に留まらないとだめだ。
「せっかく宇梶くんが身を削って協力してくれてるのに、結果が出てないと申し訳ないよ」
「別にやらせとけばいいんじゃね」
「やっぱシンタやって」
「絡みは嫌だ。オレとおまえだなんて事故だろ」
「わかるけどさ。さすがに申し訳なくなってくる」
眠気もあるせいか考えがマイナスの方に引っ張られてしまう。実質一しかない閲覧数は、まるで僕の価値を表しているようだ。
「沢渡、具合いが悪いの?」
僕があまりにへこたれているから、宇梶くんが心配して席に戻って来てくれたらしい。
話を途中で抜けてしまったのか、宇梶くんのいつメンに睨まれているような気がする。
宇梶くんに早く戻って欲しくて笑顔を貼りつけた。
「大丈夫。ちょっと寝不足なだけ」
「夜遅くまで絵描いてたもんね。完成したんでしょ?」
「そうなんだけどね」
「なにか悩み事?」
なおも宇梶くんは問いかけてくれている。ついに椅子に座ってしまい、完全に僕の話を聞く流れになってしまった。
あぁ、いつメンたちの視線が痛い。怖くて前を向けられないよ。
「大丈夫だから、宇梶くんはみんなのところに戻ってよ」
「どうして俺を除け者にするの?」
「そういうわけじゃないけど」
「水間の方が話しやすいってこと?」
ん~なんか変な風に話がこじれてしまいそうだ。
僕は諦めて白状することにした。
「イラストを投稿してるアカウントがあるんだけど、閲覧数が全然伸びないんだ」
僕はSNSサイトのホーム画面を見せた。メディア欄には♯創作BLのイラストで溢れているが、閲覧数は軒並み三である。
「せっかく宇梶くんが協力してくれてるのに結果出せなくてごめんね」
「これって……」
「僕の絵に足りないものがわかった?」
「沢渡のイラストは完璧だよ」
「そう?」
すっきりしない宇梶くんの表情が気になったけど、それよりも閲覧数の少なさに落ち込み、僕は何度目かの重たい溜息を吐いた。