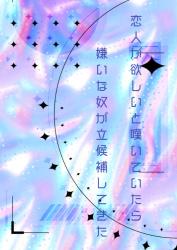僕の通う海南大学附属高等学校は男子高校である。校名通り海に面した田舎町にあり、寮暮らしと通いの生徒が半々いる。僕は前者だ。
土地がありあまるほどあるので校庭や体育館が広い。それを有効活用しようと実績のある講師を定期的に呼び、運動部が強い。遠方からわざわざ入学してくる人もいるほどだ。
自ずと寮生は運動部ばかり集まり、僕のような陰キャはほとんどいない。
僕は壁と窓に挟まれながら、一人で夕食を食べていた。
金目鯛の煮物を口に運び、身がほろりと溶ける。あとから甘じょっぱさが追いかけてきて、絶妙なハーモニーを奏でた。
「美味しい」
入寮して二年目だが、僕は毎日食堂の美味しさに感動している。漁師になったOBから獲れたての魚を食堂に卸してもらっているらしい。
ありがとう、食堂のおばちゃん、漁師さん。
でも感謝の気持ちが風船みたいにしぼんでしまう。
学食に向かう途中で寮監の先生に会い、明日転校してくる子と同室になると告げられたのだ。
高一の夏前に同室だった子が家の用事で転校してしまい、僕はそれから約十か月間、二人部屋を一人で使わせてもらっている。
そのため部屋は自分の好きなもので埋め尽くしていた。
本棚にはBL漫画を並べ、好きなBL作品のポスターを貼り、しまいには自分がいつでも絵を描けるようにホーム画面がBLアニメのタブレットを出しっぱなしにしている。
僕にとっての三種の神器だ。これらが揃っているから寮で孤独でも耐えられている。
でも同室の子ができるなら、もう好きなときに漫画やアニメが観られないのだ。
腐男子が同室となったら転校生は怖いだろう。BLをこよなく愛する僕だけど、恋愛対象は女の子だ。ゲイではない。
でも腐男子というだけで警戒させてしまうだろう。
明日同室になる子はどんなかな。先生の口ぶりから運動部ではなさそうだけど、詳しいことを訊く前に先生は学校へ戻ってしまったのだ。
寮の部屋は同学年と決まっているので僕と同じ二年生のはず。海しかないこんな田舎町に運動部以外の目的なんてあるのかな。
BL的展開だとモデルのようなイケメンが来るのが定番だ。そして仲良くなって恋仲になるーーうん、悪くない。次回作のネタにしようかな。
でもここで注釈が入る。
ただし僕の顔がイケメンに限る、だ。
僕の髪は一度も染めたことのないのにボサボサだし、やぼったい眉にきりっとつりあがった目はいかにも陰キャの極みだ。おまけに背も一七一センチと低い。
誰がどう見ても陰キャを極めた男だ。
せめて転校生くんに不快な思いはさせないようにしなきゃ。食事を終えたらすぐ掃除に取りかかろう。
味を堪能しつつも僕はしっかりご飯をかき込んだ。
洋服をきれいに畳み、クローゼットに入れて僕は額の汗を拭った。だいぶ片付いてきている。
「ちょっと休憩しよう」
ベッドに寝転がりながら僕はネットサーフィンを始めた。♯創作BLというタグを巡る未知と出会いの冒険の旅である。
「渚先生の更新まだか。あ、この作家さん初めて見るな」
誰も聞いていないことをいいことに、僕は独り言が多い。小学校からの幼馴染であるシンタによく注意されてしまうほどだ。でも一人でいるときくらい好きにしたい。
定期巡回を終えて、僕はマイページに飛んだ。昨日投稿したばかりのイラストの閲覧数を確認して肩を落とす。
「……やっぱり全然伸びてない」
僕が投稿した絵は黒髪でクールな男と可愛い系の男が海辺で抱き合っている絵だ。我ながらいい出来栄えだと思っていたけど、閲覧数は三と記されている。
「一人は僕で、もう一人はたぶんシンタかな。あと一人は流れの人かな」
僕は毎週のようにイラストを公開しているけど、閲覧数は決まって三。つまり僕とシンタ以外に見ている人が一人だけいることになる。
誰が見てくれているのかわからないけど、毎回同じ人ではないだろう。たまたまタイムラインに流れてタップしてくれたに違いない。
「黒髪攻めってもう古いのかな。う〜ん、でも僕は結構好きなんだけど。それとも構図がだめなのかな?」
僕はうんうん唸りながら自分のイラストを眺めた。
昔から外で遊ぶよりから絵を描くのが好きで、中学生のときに姉の影響でBLにハマって以来ずっと描いている。
将来はBL漫画家になることを夢みて、漫画やイラストをSNSに投稿していた。
でも評価がないとさすがにへこむ。褒められたくて描いているわけじゃないけど、まるで僕なんて存在はいらないと言われているような疎外感があるのだ。
だけど一度だけバズったことがある。きっとはあれは運がよかっただけなんだろうな。
そりゃBL大航海時代だし、僕が描かなくてももっと素敵な作品はある。
でも僕は自分が描いたものを、誰かの心に届いて欲しい。
「閲覧数が実質一だと無理か」
BL漫画家も夢のまた夢のその先の夢くらいまで遠い。
「これで大方片付いたかな。ってもうすぐ消灯時間だ。早く寝よう」
僕は電気を消して、ベッドに潜った。
明日からは新学期が始まる。
二年はどんなクラスになるだろう。不安はあるけど、考えても仕方がない。
懸念はすぐにBL妄想に上書きされた。
僕が二年四組の教室の前に立つと、活気のある声に気後れしそうになる。どうして運動部の人は声が大きいのだろう。
僕は後ろのドアからこっそりと入り、黒板に書かれている席順を確認して窓際の一番後ろの席に座った。
「よ、藍。今年も一緒だな」
唯一の友人である水間慎太郎ーー通称シンタが僕の前に座りにえくぼを浮かべた。
「よろしく〜。今年もシンタと一緒でよかった」
「相変わらずボッチ貫いてるもんな」
「好きでボッチでいるわけじゃないよ」
「まぁこの学校だと藍みたいなのは過ごしにくいよな」
シンタは同情的な目を僕に向けた。
クラスメイトの七割はなにかしらの運動部に所属している。明るく活発で、太陽の下にいると生き生きするような人の中で、僕みたいなオタクは異質だろう。
シンタも小学生のときから野球をやっていて、スポーツ推薦を勝ち取り海南に進学した。
でも去年肘を大怪我してしまい、手術をした。日常生活に支障はないけど、もう二度とボールは投げられないと宣告され、野球部を退部している。
本人曰く「バケモンばかりの部活だったからかっこよく辞められてよかったよ」と言ってるけど、本当は辛いのだろう。
僕の前では臆面にも出さない。
そのいじらしさが理想の攻めである。弱い部分を見せないでぐっと堪えるけど、受けの前だけではちょっと弱気な姿を見せちゃうのもいいな。
これもネタにしよう。
「また変な妄想してるだろ」
「べ、別に!」
「全部声に出てるからな」
「嘘!?」
にっと白い歯を覗かせるシンタはいたずらっ子のように笑った。その笑顔に僕を蔑む様子はない。
シンタはストライクゾーンが地球規模並みに広いのでBL漫画だけでなく、少女漫画、青年漫画、ホラー、百合などあらゆるジャンルに手を出している。漫画に限らず、アニメ、映画、バラエティ番組も網羅していた。
見識が広いのでよく僕の漫画やイラストを見て感想をくれる。
「一昨日あげてたやつよかったよ。相変わらず黒髪攻め好きだな」
「だってカッコよくない?」
「まぁわからんでもないな」
「でももう好きに描けなくなりそうだよ」
「なんで?」
「今日転校生が来るんだって。僕の同室になるみたいで」
「あ〜オレ、そいつ見たかも」
「え!? どんな人だった?」
「すぐわかるよ」
シンタがもったいぶっているとチャイムが鳴ってしまった。
僕がそわそわしていると担任が教室に入ってきて騒がしい声がしんと静かになる。
白髪交じりの担任がぐるりと教室を見渡した。
「今日から転校生が来るから仲良くしろよ。入ってきて」
担任が廊下に声をかけるとがらりと扉が開いた。その瞬間、教室全体が息を飲んだ。
サラサラと音を奏でそうな黒髪に利発そうな眉が覗く。陶器のように白い肌はくすみ一つない。細面の中に神様により作られたパーツが絶妙な形で配置されている。
この辺ではお目にかかれないイケメンの登場にみんなぽかんと口を開けていた。
唯一事前に見たらしいシンタだけは僕を振り返り、にやっと笑っている。
クラスメイトの視線を受けて、転校生は少しだけ顎を引いた。
「東京から来ました宇梶唯斗です。わからないことばかりなので、色々教えてください。よろしくお願いします」
低く張りのある声が教室の隅々にまで響き渡る。宇梶くんは腰をきっちりと曲げて礼儀正しいお辞儀をした。
静まり返った教室の様子に、宇梶くんは助けを求めるように先生を見ている。困っている顔すらカッコいい。
ここに女子がいたら黄色い悲鳴が轟いただろう。残念なことに男子しかいない教室はイケメンの登場に処理が追いつかないらしい。
だが担任は淡々としている。
「席は……沢渡の隣でいいな。移動教室のとき場所を教えてやれよ」
「ええ!」
「なんだ、沢渡。嫌なのか」
「いや……そうではなくて」
「寮の部屋も同室だからな。しばらく面倒みてやれ」
寮監でもある担任の言葉に僕は目を剥いた。このイケメンと二十四時間ずっと過ごさなくちゃいけないの? なにこれ罰ゲーム?
黒板の方から宇梶くんが歩いてくる。制服のブレザーの靡き方すら計算されつくしているように美しい。そこに皺ができるからスタイルがよく見えるのか。
僕は絵を描きたい衝動をぐっと堪えた。そんなことしたらオタクだとバレてしまう。でもせっかくだから目に焼きつけようとじっと宇梶くんの制服をみつめていた。
「えっと、沢渡でいいのかな。これからよろしくね」
ウエスト部分に皺が入って、光がやや右上から当たるからここに影ができるのか。肩のラインもいいな。てかこの身体つきは鍛えてるよね。背も高いし、顔も小さい。
でも驚くべきなのは足の長さだ。内臓どこに入ってるの?
ただの変哲もない制服なのに宇梶くんが着ると一流のファッションデザイナーの作品みたい。
「あの……沢渡?」
「わっ!」
宇梶くんのご尊顔に覗き込まれて僕はひっくり返り、椅子から転げ落ちた。ホームルーム中の担任から「静かにしろよ」と注意を受けてしまった。
クラスメイトがクスクスと笑っている。
恥ずかしくて顔が熱い。
そんな僕に宇梶くんは心配そうに眉を寄せた。
「急に声かけてごめんね。もしかして具合い悪い?」
「全然そんなことなくて……すいません、ぼうっとしてて」
「よかった」
「はい……。あの、沢渡藍です」
「宇梶唯斗です。これからよろしくね」
宇梶くんは顔だけでなく、性格もいいらしい。
こんな僕にまでやさしい笑顔を向けてありがたいけれど、あまりの眩しさに目が焼かれてしまいそうだ。
ホームルームが終わると体育館に移動して始業式が行われる。
体育館へと向かう途中、さっそく宇梶くんの周りには陽キャの多いサッカー部員が集まっていた。弾丸のようにスピード感のあるトークを繰り広げている。
「東京って芸能人がウロウロしてるってまじ?」
「俺はあまり見かけたことがないな。でも横浜に行ったとき、ドラマの撮影現場を見たことがあるよ」
「渋谷はよく行ってた?」
「騒がしいところは苦手で。あ、でも新宿はおばあちゃんちが近いからよく行く」
「東京人って感じだな!」
僕は宇梶くんたちの後ろを歩いているので自然と会話が耳に入ってしまう。
初対面ばかりに囲まれても、宇梶くんはリラックスした様子で笑っている。人見知りをしないタイプなんだろう。
あんな風にすぐ打ち解けられててすごい。
やっぱり人生のスタートラインから違うんだろうな。
僕がのんびり歩いていると隣のシンタが肩を叩いてきた。
「転校生どう?」
「いままで一度も見たことがないレベルの顔面偏差値だね」
「まさにBL展開じゃん。イケメンの転校生が同室って」
「そうだけど」
まさに僕が妄想していた通りだ。
だがもちろん僕と宇梶くんが恋愛に発展することはない。そんなこと想像することすらおこがましいだろう。
こういうとき、僕の顔がめちゃくちゃ可愛かったら妄想しがいがあったのにな。
「せめてスケッチさせて欲しい。まさに次描きたいタイプの攻め様なんだよね」
宇梶くんの目元はクールな印象があるのに笑うと親しみやすさが出るのだ。きっと目尻がきゅっと絞まるからだろう。
冷たそうに見えて、やさしい愛嬌のある男。
宇梶くんはまさに僕が求めていた攻め様だ。
「じゃあスケッチさせてって言えば?」
「これから二年間同室になるのに、そんなキモいこと言えるわけないだろ」
「キモイって自覚あるんだ」
「自分の立場くらい理解してるよ」
「ねぇ沢渡くん」
「ひいい!」
突然宇梶くんがくるりと振り返り、名前を呼ばれて驚いてしまった。
僕が変な悲鳴をあげたから宇梶くんは目を丸くしている。
さっきまで宇梶くんの周りいたサッカー部員の姿がない。
体育館の前に生活指導の先生がいて、どうやらサッカー部の子たちは慌てて着崩した制服を直しているらしい。
だから一人になった宇梶くんが僕に声をかけてくれたのだとようやく理解できた。
理解できたからといって冷静になれるわけではない。
僕はどくどくと脈打つ心臓を手で押さえた。
急に宇梶くんのご尊顔を向けられ、平静でいられるはずがない。声をかけるときは心の準備が欲しい。
でもこんな距離で顔を見れる機会なんて、そうそうないだろう。
僕はじっと宇梶君の顔を見上げた。
睫毛長いな。あ、二重のとこに前髪の毛先が挟まっちゃってる。
それだけ二重がぱっちりしてるってことなんだろうな。
いますぐ模写したい。
「……沢渡?」
「あ、ごめん。なに?」
「まだ寮の鍵もらってないから、今日一緒に帰ってもいいかな?」
「え、僕?」
「だめだった?」
お伺いを立てるように上目遣いされてしまい、僕は下唇を噛んだ。なんてあざとい! カッコよさの中に可愛さを合わせるなんて無敵じゃないか。
あぁ〜模写したい、模写したい、模写したい!!
「藍、声に出てるぞ」
シンタにそっと耳打ちをされて、僕は慌てて口を押えた。気持ちが暴走しちゃうとどうにも止められない。
僕は落ち着かせるようにゆっくりと息を吐いた。
「わかった」
「じゃあ放課後よろしくね」
宇梶くんは制服を直したサッカー部員たちとともに体育館へと入って行った。ほのかにシトラスの香りが残る。
匂いまでオシャレとは侮れないな。
始業式のあとは教室に戻り、帰りのホームルームをやって下校になる。
校門でシンタと別れ、僕と宇梶くんは寮へと向かった。寮は学校から歩いて五分ほどの立地にある。
寮には学食や大風呂、トレーニングルームまで揃い結構広い。一、二年生は二人部屋、希望すれば三年生から一人部屋になれる。
僕は宇梶くんに寮内を簡単に案内して、部屋に向かった。すでに寮母さんの手によって宇梶くんの荷物が届いている。
でも段ボールが二箱だけだ。
「荷物少ないね」
「最低限の服があればいっかなって。あとは必要になったら買えばいいし」
「コンビニまで三十分かかるよ」
「嘘!?」
「ちなみにカラオケや映画に行くならバスで駅まで行って、そこから電車に乗らないと」
「……そうなんだ」
あまりの田舎っぷりに宇梶くんが絶句している。
「ちょっと油断してたかも」
「東京に住んでたら考えられないでしょ?」
「いや、これは完全に俺が下調べしてなかったせい」
そこで怒ったりしないのが意外だった。前に同室の子は千葉から来た人で、海南高周りになにもなくて叫んでいたのに。
都会の人は不便で仕方がないのだろう。
僕がじっと宇梶くんを見つめていると、長い前髪をかき混ぜた。
「逆になにもなくてよかったかも」
「そう?」
「自然豊かで、すぐ好きになれると思う」
宇梶くんなりにいいところを見つけようとしてくれているらしい。
僕も海南は田舎で海しかないし、閉塞的だけど結構好きだ。
気に入ってくれると嬉しいな。
宇梶くんは部屋をぐるりと見回した。
「部屋結構広いんだね」
「二人部屋だからね。机とベッドとカラーボックスは備え付けだけど、もし足りなかったら他にも持ってきて大丈夫だよ」
「ありがとう。あ、でもクローゼットは共同なんだね……段ボール多くない?」
「あぁ、ちょっと片付けが追いつかなくてそこにしまっているんだ」
僕は慌てて段ボールに覆いかぶさった。この中に僕のお宝たちを避難させている。見られるわけにはいかない。
へらっと笑いながら僕は段ボールを後ろに隠すと、宇梶くんは首を傾げている。
じっとりと背中に汗が伝う。元はオタク部屋だったと気づかれていないよな。
僕は話を逸らすことにした。
「カーテンで部屋を区切れてプライバシーは守られるけど、うるさかったら遠慮なく言ってね」
「俺もうるさかったら言ってね」
「これから二年間よろしく」
「こちらこそ」
手を差し出されたので驚いた。関節が細く、指が長い。爪が桜貝みたいだ。
「キレイだな」
「え?」
つい声に出してしまっていた。慌てて口を押える。
「ご、ごめん。」
「それは構わないけど……なんか変だった?」
「変というより美し過ぎて」
「ん?」
「宇梶くんみたいなカッコいい人初めて見たからつい魅入っちゃって……ごめん、ジロジロ見られて気持ち悪いよね」
初対面なのに挙動が変過ぎた。いくら理想の攻め様だと言っても限度がある。
「あ~そっか」
宇梶くんは困ったように笑っていた。もしかしてイケメンと言われ慣れ過ぎて、誉め言葉として受け取ってもらえないのかもしれない。
「あ、でもただカッコいいだけじゃなくて立ち振る舞いもいいなって」
僕は一度唇を湿らせた。
「背筋がピンといつも伸びてるし、お辞儀武士みたい決まってて。そういう所作も含めてカッコいいわけで……」
段々なにが言いたいのかわからなくなってきた。頭の中が出口を求めてグルグルしてくる。
「つ、つまり宇梶くんは理想の攻め様なんです!」
「……攻め、様?」
「あっ……その」
言っちゃった! 宇梶くんドン引きしてるよ! さっきまでやさしい笑顔だったのに片頬が引き攣っている。
「沢渡は……腐男子ってこと?」
理解力の早い宇梶くんはどうやらすべてを察してしまったらしい。
これ以上は誤魔化せないだろう。
僕は観念して後ろに隠していた段ボールを開けた。中には秘蔵のBL漫画がみっちりと詰まっている。
「僕は腐男子です」
英語の例文みたいに答えてしまった。これはペンです、みたいな。
僕は供物を神に捧げるように段ボールを差し出すと、宇梶くんは一冊取り出した。
「『これが僕たちの愛の話』?」
「あ、これは高校生同士のピュアラブなんだよ! ここ! この告白シーンとか最高じゃない? 攻めの顔に夕焼けの影が入るけど、受けの方は明るいの。つまり受けが攻めとの恋を諦めないっていうことを示唆してて……」
僕が一息に話しているのを宇梶くんは呆然としている。またやってしまった。僕ってどうしてこうなんだろう。
一度失敗したくせに懲りていないらしい。
「本当ごめん。こんな気持ち悪い奴と同室は嫌でしょ? 部屋変えてもらえるように先生に頼んで来るよ」
「待って!」
立ち上がろうとする僕のブレザーを宇梶くんが掴んだ。ぐいと身体が傾き、宇梶くんの端正な顔が近づく。
「全然嫌じゃない」
一語一句に感情を込められているのか、胸にしっかりと届いた。宇梶くんの黒豆みたいな目には嫌悪感がない。
ただただ美しい宝石のように輝いている。あまりの眩しさに驚いて、僕は顔を伏せた。
「……無理しないでいいよ」
「無理じゃない」
「僕のこと気持ち悪くないの?」
「そんなこと思わないよ」
「……なんでそんなにいい人なの!」
僕は感動して泣きそうになってしまった。こんな自分語りの多いオタクの僕を気持ち悪いと思わない人なんているんだ。
もしかして宇梶くんの前世は女神だったのだろうか。なるほどだからこんなに容姿が整っているんだな。
「じゃ、じゃあ! 宇梶くんを模写してもいい?」
「ん?」
宇梶くんは首を傾げて、はっとした。腐男子を引かないという話から、興奮し過ぎたせいで一気に話が飛んでしまっている。
僕は小さく息を吐いた。
「読むだけじゃなくて、僕はBL漫画やイラストも描いてるんだ。で、次描きたい新作の攻め様が宇梶くんのイメージとピッタリ合うから、描きたいなぁって」
「つまりモデルってこと?」
「そう! 顔は宇梶くんと雰囲気は似せるけど、別人で描くし」
「ん~どうしようかな。ちょっと確認取らないと」
「そうだよね。親御さんも心配になっちゃうよね」
また先走ってしまった。僕が肩を落としてしゅんとしていると、宇梶くんは小さく笑った。
「そんなに落ち込むとこ?」
「だって本当に宇梶くんは素晴らしいんだよ。笑うと目尻がきゅっとするところも、犬歯がちょっと尖ってるところも素敵だし」
「よく見てるね」
「引力みたいに惹きつけられちゃうんだよ」
「引力……」
「ごめん、また気持ち悪いこと言ってたね」
僕ってどうして失敗を学ばないんだろう。罪を白状する罪人のように惨めな気分だ。
「それならお試しで一枚描いてもらっていい?」
「いいの?」
「沢渡のイラストがどういうものか見てみたいし」
「じゃあここに座って、足組んでもらっていい? それでちょっと勝気な顔して」
「こう?」
勉強椅子が王様の座る煌びやかな玉座に変わる。不適に笑う顔がドSらしく見えた。
目を潤ませる僕を見て、宇梶くんがぎょっとしている。
「どうしたの?」
「宇梶くんのご両親に感謝してる」
「なんで、また」
「だってこんな立派な宇梶くんを産み育ててくださったんだもん。あ~お金があったらお祝いを送って差し上げたい」
「それはやめて」
ドン引きしているだろうに宇梶くんはくしゃっと笑った。笑うとちょっと子どもっぽい。
僕はスケッチブックとペンを持ってきて、さっそく描かせてもらった。
実物を前に緊張するけど、それもすぐなくなる。無心でペンを走らせた。
「できた」
「見てもいい?」
「もちろん」
僕がスケッチブックを渡すと宇梶くんはふさふさの睫毛を見開いた。
「すごい上手だね」
「モデルがいいから」
僕は恥ずかしさを隠すように後頭部を掻いた。
「あれ……もしかして」
「ん?」
「他にも絵はある?」
「タブレットにいっぱいあるよ」
僕は机に置きっぱなしにしているタブレットを起動させた。
下絵はアナログで描いて、ペン入れや色つけはタブレットでしているのだ。
フォルダを開き、いままで描いたイラストを宇梶くんが食い入るように見ている。
「これって」
「あぁ、懐かしいな」
僕がSNSのアカウントを始めて最初に投稿したイラストだ。
黒髪のスポーツ少年の攻めと両性的な可愛さの受けが肩を組んでいるだけのもの。
なぜかイラストの評判がよく、万バズというものをした初めての作品だ。
しばらくしてから宇梶くんは口を開いた。
「やっぱり……」
「ごめん、気持ち悪かった?」
「そんなことない。あまりにキレイだったら見惚れてた」
「えぇ〜褒めすぎだよ」
褒められ慣れていないので宇梶くんの賛辞がじっくりと僕の身体に染み込む。きっと顔はデレデレしているだろう。
「もしよかったらこれからも絵を見せてもらってもいい? その代わりにモデルでもなんでもやるよ」
「親御さんに確認しなくて平気?」
「これくらいなら大丈夫だと思う。あと俺の名前は絶対出さないでね」
「もちろん。約束するよ」
僕が親指を立てると宇梶くんは同じポーズをしてくれた。ノリがいい。
「でも夢みたい。宇梶くんのこと、これから描いてもいいなんて」
「俺も嬉しいよ」
にこっと笑う顔すら絵になる。さっきまで我慢してたけど、もう好きに描いていいんだ。
新たな出会いの春に僕は心から感謝をした。