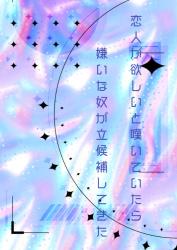年が明けて新学期に入ると慌ただしく修学旅行が始まった。
本来なら十月に行く予定だけど、運動部の全国大会と日程が被ってしまい、一月に延期されたのだ。
ついこの前東京に行ったばかりだけど、観光はしていないので僕は楽しみにしていた。
「見て! あんなにビルが小さいよ」
僕たちはスカイツリーに登り、展望デッキで都内を見下ろしている。三百六十度ガラス張りなのでどこからでも景色が楽しめる。
でもどこを見渡しても海は見えない。ビル、ビル、ビルばかりだ。
逆にそれが新鮮で僕がはしゃいでいると唯斗くんは長い指を窓に向けた。
「向こう側に小さく東京タワーがあるのわかる?」
「えっと……あぁ、あれだね! ちっちゃい~」
「そこはこれから行く浅草寺だよ。雷門で有名なやつ」
「さすが東京っ子だね」
僕が関心しているとシンタがニヤニヤしながら僕の肩を叩いた。
「兄貴、全部パンフレットに書いてありやすぜ」
シンタが見せてくれたパンフレットには見たままの景色がイラストで描かれ、どこになにがあるのか詳しく説明書きされている。
唯斗くんが驚くほどの素早さでシンタからパンフレットを奪い、後ろに隠した。
少し怒ったように眉を顰めてシンタを睨みつけている。
「しょうがないだろ。住んでるとどこになにがあるとかあんまり意識しないんだから」
「もしかしてわざわざ調べてくれたの?」
「ちょっとだけね」
「ありがとう! お陰ですごく勉強になるよ」
地元なのに唯斗くんは手間暇かけて調べてくれたんだ。その行為が嬉しい。
きっと僕たちを楽しませようとしてくれたんだろうな。
だけどシンタはずっとニヤニヤ笑みは崩れない。もしかして違ったのかな。
「はい、集合〜お昼食べに行きますよ」
担任の合図に僕たちはぞろぞろとエレベーター前に並んだ。自然と班で固まり、僕と唯斗くん、シンタ、クラスメイトの二人の五人グループが一か所に集まる。
他のクラスもいるし、観光客も多い。ちょうど昼前なので、エレバーター乗り場の前は降りようとする人たちで溢れていた。
でも僕がぶつからないように唯斗くんが長い腕でガードしてくれている。それに気づくと自然と頬が下がった。
王子様みたいだ。
僕の頬がだらしがなく垂れ下がっていると唯斗くんは首を傾げた。
「楽しい?」
「うん!」
「この前は観光できなかったもんね」
「唯斗くんちにお邪魔できたのも貴重な体験だったよ」
唯斗くんのお母さんから了解を得られて転校をしなかったから、こうして一緒に修学旅行に行けるのだ。
あの日、勇気を出してよかった。
「仲良しカップル。オレも会話に入れろよ」
「カ、カカカカップルって」
「違うのか?」
シンタのまっすぐな目に僕は俯いた。唯斗くんと付き合っていることは秘密だ。
僕だけならいいけど、唯斗くんまで変な目で見られて欲しくない。
なにより休業中とはいえ、唯斗くんはモデルなのだ。悪い評判に繋がるのではないかと気が気ではない。
「ほら、あそこも新婚カップルだぜ」
シンタが顎で指した先は隣のクラスの二人だ。
可愛らしいタイプの子とスポーツ青年らしい絵に描いたようなイケメンカップルだ。
男子校という特殊な環境化の中、男同士で付き合う人は結構いるらしい。なんとなく噂には聞いていたけど、ちゃんと見たのは初めてだった。
「カップル、いるんだね」
「そりゃいるだろ。修学旅行といえば定番じゃん」
シンタの莫迦にするようなニュアンスに僕はむぅと唇を尖らせた。
「でも男同士だし」
「それだとだめなの?」
「だめじゃ……ないけど。シンタは偏見ないの?」
「オレがあるように見えるか?」
シンタはえくぼを浮かばせた。
宇宙規模にストライクゾーンが広く、少女漫画からホラー作品まで幅広くなんでも愛する男に「偏見」という価値観はないらしい。
「僕が難しく考えてたのかな」
「まぁ相手はコイツだしな」
シンタが隣を見上げると唯斗くんは眉を寄せた。
「幼馴染だからって藍に気安く触らないで」
「お〜こわっ」
しっしとシンタを追いやり、唯斗くんは僕の肩に腕を回した。
「あ〜ラブラブだ」
シンタがニヤニヤと笑いながら僕たちを指差していると、唯斗くんが片頬を上げた。
「羨ましいんだろ」
「くそっ〜〜!! 絶対可愛い彼女作っておまえらに自慢してやるからな!」
「そういうのを負け犬の遠吠えって言うんだよ」
「なにぃ!?」
唯斗くんの煽りに、シンタはぷんぷんと怒りだしてしまった。
シンタがこんなに怒るのは珍しい。わりと淡泊なタイプなので意外だった。
唯斗くんとはよっぽど馬が合うのかもしれない。
シンタがプリプリしているのを尻目に、唯斗くんは僕の耳元に唇を寄せた。
「俺たちの邪魔をする水間が悪いんだよね」
「もう唯斗くんったら」
咎めるつもりが声に甘さが混じってしまう。
僕は恋人をとことん甘やかしたいタイプらしい。
でもずっとそういうわけにはいかない。
ここは東京で、唯斗くんのことを知っている人がたくさんいる。変な言動をして、噂がたったら文化祭のときと同じことになる。
幸い、唯斗くんの所属事務所が声明を出してくれたおかげで出待ちされなくなり、唯斗くんの私物が盗られることはなくなった。
けれど同じことが二度と起こらないとも限らない。
注意に注意を重ねるぐらいがちょうどいいと思う。
「こんなことやって付き合ってるのが世間にバレたらどうするの?」
「別にいいよ」
「そういうわけにはいかないでしょ」
「来年は受験もあるし、モデルはまだ休むつもり。そのうちみんな俺のことなんて忘れるよ。だから、ね」
俺に集中して、と鼓膜を響かせるので僕の背筋を甘く震わせた。
ソラマチのレストランでランチをして、僕たちは浅草寺まで歩いて移動した。お参りをしたり仲見世通りを歩いたりしているだけでも楽しい。
地元にはない、日本古来の風景に胸が高鳴る。
お土産店を物色しているとシンタが大きな目をくりっとさせた。
「お、着物レンタルできるみたいだな」
「本当だ。きれいだね」
店内にいた女子大生くらいの人たちがピンクやオレンジなどの着物を着ていた。
壁に貼ってあるポスターによると二階で着物のレンタルと着付けをやってくれるらしい。
でも値段を見てビックリした。高校生が気軽に出せる値段ではない。
「結構高いね」
「くそ~着てみたかったな」
悔しそうなシンタを見て、唯斗くんは笑った。
「このあとすぐ移動だから時間も厳しいんじゃない?」
「残念。唯斗くんの着物姿、写真に撮りたかった」
きっとすごく似合ってるだろうな。背も高いし、頭が小さいからすらっとしてかっこいいはず。
あ、でもあまりに似合い過ぎるから人が集まっちゃうかも。やっぱ却下。でも見たい欲も我慢できない。
僕がポスターの前で腕を組んでいると唯斗くんはぽんと手を叩いた。
「じゃあ今度来たときにレンタルしよう」
「今度?」
「卒業旅行とか春休みでもいいけど、また一緒に来よう」
「うん!」
約束ができると嬉しい。これから続く未来を唯斗くんは僕と一緒にいたいと思ってくれているんだと実感できる。
「おっと、危ない」
僕は腕を引かれて唯斗くんの胸の中にぽすんとおさまった。ふわりと香るシトラスの香りに頬が熱くなる。
「え、なに?」
「外国の人とぶつかりそうだったから。ほら、藍って可愛いサイズだから見えづらいのかも」
「どうせ小さいですよ」
唯斗くんの身長は見上げるほど大きいけど、僕は平均以下だ。家族みんな小さいから小人家族だとシンタには揶揄われている。
唯斗くんは僕の頭に頬をぐりぐりと当てた。
「でもこのくらいのサイズの方が抱き心地がいいよ」
「ちょっと唯斗くん! みんな見てる!!」
「いいよ、そんなの」
唯斗くんには羞恥心というものがないらしい。恋人になって初めて知った。それとも普通のカップルは所かまわずベタベタするものだろうか。
確かにBL漫画では定番なシチュだけど、これは現実なのだ。やっぱりおかしいだろう。
でも跳ねのけることができない。だって唯斗くんに触れられると嬉しいのだ。
「あー! またイチャついてる! 逮捕だ、逮捕!!」
「またうるさい奴が来たよ」
「新婚カップル刑事の登場だ!」
「なにそれ」
呆れる唯斗くんに対し、シンタは歯茎をむき出しにして喚いている。犬がじゃれ合っているように見えるから、なんだかんだと仲がいいのだろう。
それから僕たちはバスに乗って博物館を見学してからホテルに向かった。
「藍と二人部屋がよかったな」
「でも三人って新鮮だから楽しいよ」
僕の言葉に唯斗くんは曖昧に頷いた。
本音は僕も二人きりがよかったけど、シンタとの三人部屋も魅力的だ。
班ごとに部屋割りは決められ、僕たちは二人部屋と三人部屋に別れている。同じグループの二人が気を使ってくれたのかもしれない。
部屋はかなり広く、ベッドが二つと床に布団が一組ある和洋折衷な造りだ。い草の匂いが新鮮で、めいいっぱい吸い込むとほっとする。
大浴場には入ることは禁止され、備え付けのバスルームを使うよう学校で決められていた。だけど洗面所や風呂はかなり狭く、一人はいるのがやっとだろう。
悪ふざけをしないよう先生たちが選んだのかもしれない。
荷解きを終えたシンタは備え付けの椅子に座り、僕と唯斗くんを順番に視線を向けた。
「寝る場所どうする?」
「俺と藍が布団。水間はベッドね」
「おまえたち、オレがいるのにおっぱじめるつもりか?」
げんなりした様子のシンタに僕は慌てて首を振った。
「布団に二人は狭いよ。公平にじゃんけんで決めよう!」
「狭くないよ」
「じゃんけん!」
「……わかった」
唯斗くんは唇を尖らせた。もしかして布団で寝る方がよかったのかな。
「水間はグーだけ出してね」
「なんでだよ」
「藍と一緒に寝たいからに決まってるじゃん」
さも当然とばかりの唯斗くんに僕とシンタは開いた口が塞がらなかった。あまりに横柄すぎる。
シンタはやれやれといった感じで首を左右に振った。
「小学生かよ」
「なんとでも言えばいい。じゃあ最初はグー」
「待て待て待て」
「じゃんけん……ポン!」
唯斗くんはパーで僕とシンタはチョキを出した。唯斗くんの一人負けである。
僕のチョキを見て、シンタが腹を抱えて笑い出した。
「なんで藍までチョキ出してんだよ」
「咄嗟だったからつい」
「策士策に溺れるってやつだな」
シンタがニヤっと笑うとパーのままの唯斗くんは小刻みに肩を震わせている。
「もう一回!」
「男らしくない奴だな」
「三回勝負だし」
「いつ決めたんだよ」
シンタは呆れながらも結局じゃんけんに付き合ってあげたが、唯斗くんに全勝していた。
「宇梶、じゃんけん弱すぎだろ」
「……うっさい」
「あ~あ、拗ねちゃって。オレ、先風呂入るわ」
シンタは風呂道具を持って浴室へと向かった。ぱたんと扉が閉まると唯斗くんと二人っきりだ。
唯斗くんはまだ拗ねているのか大きな背中が丸っこくなっている。ダンゴムシみたいで可愛いな。
「唯斗くん」
僕が名前を呼んで腕を広げると畳の上で縮こまっていた唯斗くんがおずおずと手を伸ばしてくれる。
指先を絡めると引っ張られ、僕は唯斗くんの上に乗っかった。
おもちゃを買ってもらえなかった子どものように不貞腐れた唯斗くんは、僕と目を合わせようともしない。罰が悪いのだろうか。
でもずっとこのままは嫌だな。
「じゃんけん弱くても大好きだよ」
「それ地雷」
「ごめん、なんか可愛くて」
運動も勉強もできるのに、じゃんけんが異常に弱すぎるギャップがいい。
慰めたつもりだったけど逆効果だったみたいだ。
せっかくの二人きりの時間だから楽しみたいな。
僕たちは隙あらば寮でイチャイチャしていた。手を繋いだり、抱き合ったり、膝の上に座らせてもらったり。
キスも何回もしている。
いまは二人きりだけど、シンタがいつ風呂から出てくるかわからない。
だからといってせっかくのチャンスを無駄にしたくない。
僕は唯斗くんの胸元に額を擦りつけた。
「やっと二人きりだね」
「藍も二人になりたかったの?」
「当たり前だよ。シンタといるのも楽しいけど、唯斗くんとの時間も大切にしたいんだ」
「はぁ、なんで藍はそんなにいい子なの」
唯斗くんがやさしく髪を撫でてくれる。僕のツボを的確に突いてくるので気持ちよくて欠伸が漏れた。
「藍は撫でるとすぐ眠くなる」
「だって安心できるんだもん」
「あ~可愛すぎる。これ我慢するなっていうのが無理だよ」
僕が顔をあげて、触れるだけのキスをすると唯斗くんは頬を真っ赤にさせた。
「ちょっ、え!? いま、藍からキスしてくれた?」
「大きい声出さないで。シンタに聞こえちゃう」
「いま見逃してた。もう一回して!」
「シンタ戻ってきちゃうから」
洗面所の方へと視線を向けるとまだシャワーの音がしている。いつも烏の行水なのに珍しい。
「水間は当分戻って来ないよ」
「なんでわかるの?」
唯斗くんはにやっと片頬を上げた。
「あいつは空気が読めるからね」
なんだかんだといいながら、シンタのことを信用しているんだ。やっぱり二人とも仲がいい。
「だからもう一回!」
「待ち構えられると恥ずかしいよ」
「じゃあ俺からするね」
撫でてくれていた手が頬に添えられ、上を向かせられると唇が重なった。角度を変えながらちゅっと可愛らしい音をたてているうちに、思考が微睡む。
僅かな隙間ににゅるりと舌が入り、僕は瞼を開けた。
唯斗くんは悪戯っ子のように微笑んでいる。
唾液を絡ませる激しい口づけに僕の目尻に涙が浮かんだ。気持ちよすぎて離れたくない。
やっぱり二人部屋にすればよかったかも。
数秒堪能したあと、唯斗くんはちゅっと音をたてて離れた。
「これ以上は歯止め効かなくなるからおしまい」
「……うん」
「あ~その顔は反則」
一体僕はどんな変な顔をしているんだ。ペタペタと頬を触ると唯斗くんは眉を寄せている。
「寮に帰ってきてからのお楽しみにしようね」
囁かれた言葉が鼓膜に甘く響き、僕は小さく頷いた。
二日目は屋根なし観光バスに乗って都内を巡り、国会議事堂や博物館を見学した。
修学旅行と言ってもお遊びではない。帰ったらレポートを提出しなければならないから、真剣に取り組まないと評価してもらえないのでみんな真剣だ。
でもお昼を終えると班ごとの自由時間になる。
「じゃあ電車に乗って、ドームシティに向かうか」
班長であるシンタの言葉に班の全員が頷いた。自由時間は遊園地で遊ぶと事前に決めていたのだ。
僕が修学旅行で一番楽しみにしていた場所である。
「目的地の案内は宇梶に任せる」
「はいはい」
シンタは偉そうに唯斗くんに指示している。でも土地勘のないシンタより唯斗くんの方が頼りになるのは事実だ。
一度来たことがある東京駅だけど、路線が違うとまったく別の駅のように見える。掲示板を見ても読めない線ばかりだ。常磐線ってなんて読むんだろう。
唯斗くんは僕たちを中央線ホームに案内してくれ、電車を待った。
平日の昼間なのに混んでいる。
シンタが時刻表を見て、声を上げた。
「電車が五分おきにくる、だと?」
「地元じゃ一本逃したら三十分はこないのにね」
「東京やば」
さすが日本の首都である。
「電車きたよ」
唯斗くんに声をかけられて僕たちは慌てて電車に乗り込んだ。座るほどの余裕はないけど、思ったより混んでいない。
「藍はここね」
唯斗くんは扉のすぐ横のスペースに僕を招き入れた。その前に唯斗くんが壁のように立ってくれる。
こうやって気を使ってくれるところにきゅんとしてしまう。恩着せがましくないところにもときめく。
でも、と心に翳りがさす。
やっぱり慣れてるのかな。キスも初めてとは思えないほど上手だったし。僕はいまだに息継ぎの仕方もわからなくて、酸欠になりそうなのにな。
ずきり、と胸の奥が痛む。
僕は未だに唯斗くんが出演していた恋愛リアリティ番組「はじ恋」は未視聴だ。だって女の子にやさしくしている唯斗くんを見たら、嫉妬で画面を叩き割ってしまうかもしれない。
きっと当時はすごくモテていたんだろうな。いまでもその人気が衰えていないところを見ると、ガチ恋ファンが多かったのかもしれない。
それに唯斗くんはゲイだと言っている。もしかして男の恋人がいた期間があったんじゃないか。
あ~だめだ。せっかく楽しみにしてた遊園地なのに嫌なこと考えちゃってる。
僕がふぅと短く息を吐くと唯斗くんが顔を近づけてきた。
「疲れた?」
「……あ、ううん。大丈夫」
僕がへらっと笑うと右頬を摘まれた。ぷにぷにと柔らかさを堪能され、横に引っ張られる。
「ふぁひふんの」
「言いたいことがあるなら言ってよ」
「なにもないよ」
嫉妬なんてみっともない。心の器が小さいのがバレてしまう。
ただでさえ僕は冴えない男だ。勉強も運動もできないし、得意なのは絵を描くだけ。それも賞を取るほど上手いわけでもない。
なんの取り柄もない僕が一日でも長く唯斗くんに好かれるためには、多少の我慢は必要なのだ。
次の駅で停車すると髪がミルクティー色の女の子が乗ってきた。唯斗くんを一目見て、ぱっと花が咲いたような笑顔になる。
「唯斗じゃん! 偶然〜なんでこんなとこいるの?」
「……久しぶり」
唯斗くんは女の子に気づくと、貼りつけたような笑顔を浮かべる。その表情からあまり会いたくなかったのだと察した。
女の子は寒さを感じないのかショートパンツを履いている。すらりと伸びる足がまっすぐキレイで自慢なのだろう。目鼻立ちがはっきりしているかなりの美人だ。
明らかに次元が違う。
東京にいる人ってみんなこんな美形ばかりなのだろうか。
「あれってRINAじゃない?」
「てか隣にいるのかじゆーじゃん!」
「まじ! てことは番組終わってから付き合ったの? どういうこと?」
車内で居合わせた同年代くらいの女の子たちが唯斗くんとRINAさんの存在に気づき、騒ぎ始めた。
これはかなりマズイのではないか。
だけどRINAさんはまるで見せつけるように唯斗くんの腕に身体を寄せた。
「せっかくうちらいい感じだったのにさ〜なんで途中離脱しちゃったの?」
「体調崩したからさ」
「でもここにいるってことはもう元気なんでしょ?」
「……悪いけど、いま友だちといるんだ」
RINAさんはようやく僕たちの存在に気づいたらしく、目をぱちくりとさせた。
「この田舎者って感じの人たちが唯斗の友だち?」
「いま修学旅行中なんだよ」
「修学旅行が東京? どんな山奥から来たの」
RINAさんは僕たちを小馬鹿にするように笑った。隣のシンタは不機嫌そうに眉を寄せる。他の二人は縮こまってしまった。
RINAさんはさらに続ける。
「田舎者は放っておいて渋谷行こうよ。今日ね、はじ恋メンバーで会うって約束しててさ」
「行かない」
「みんな唯斗に会いたがってるよ。いいじゃん、行こう」
「離して」
唯斗くんが絡まれた腕を払うとRINAさんは鋭い視線を僕に向ける。
「あんたからも言いなさいよ。唯斗に行って来いって」
「え、でも」
「唯斗とあんたたち、全然釣り合ってないよ!」
僕はがんと頭を殴られたような衝撃を受けた。
自分でも釣り合っていないとわかっている。
でもそれを他人に指摘されるとより明確な形となって、僕の胸を深く突き刺した。
僕が俯くと唯斗くんが一歩前に出る。
「釣り合うとかなにそれ」
「だって唯斗は私たちといるのが合うに決まってる!」
「俺は自分がいたい人たちといる」
「だから私の方がーー」
「じゃあそうやって自分の釣り合う人といればいいだろ。俺を巻き込まないでくれ」
ちょうど電車が駅に着いた。扉が開くと唯斗くんに腕を引かれる。
「みんな、降りよう」
「ちょっと……!」
RINAさんがすかさず唯斗くんの腕を掴もうとしたけど、唯斗くんはさっと躱した。
RINAさんは呆気に取られたのか、そのまま立ち尽くし電車は動き出した。電車から巻き起こる風が僕たちの間をすり抜けていく。
「ごめん、降りる駅間違えちゃった」
いつもみたいに笑っているのに唯斗くんの瞳には仄暗さが潜んでいた。
僕たちは予定通りに遊園地に来て、たくさんのアトラクションに乗った。唯斗くんは楽しそうにしていたけど、それがから元気なことくらいすぐわかる。
ホテルに戻り、シンタは気を利かせてくれたのか他の部屋に行ってくれた。
唯斗くんは机に向かい、もう今日のレポートをまとめている。その一心不乱な背中は僕を拒否していた。
なにも聞かないで欲しい。そう語っている。
きっとこのままでも唯斗くんとの関係は壊れないだろう。いままで通り楽しくて幸せな時間を過ごせる。
でもそれじゃだめだ。
僕はただ唯斗くんと楽しいことをしたいんじゃない。辛いときも支えたいから一緒にいると決めたんだ。
ゆっくりと唯斗くんの近くに寄り、空いた椅子を引き寄せた。
「唯斗くん」
「藍もレポートまとめる?」
「昼のことだけどさ」
「あぁごめん。嫌な思いをさせたよね」
僕は首を振った。
「唯斗くんが僕たちといるって言ってくれて嬉しかった」
「……当然じゃん」
「でもRINAさんを悲しませてよかったの?」
「それは」
唯斗くんはシャープペンを置いた。その指先が少し震えている。
「RINAとは相手役としてあてがわれたんだ」
ゆっくりと語り始める唯斗くんに僕は耳を傾けた。
「「はじ恋」は恋愛リアリティを謳ってるけど、実際は大まかな台本があるんだ。こういう場面では相手役の子を呼び出して二人きりになるように、とか」
僕は「はじ恋」を観ていないからどういうものかわからない。けれどそれは唯斗くんの思っていたものとは全然違ったのだろう。
「RINAはずっとあんな感じでさ。他の女の子を裏でいびってたり、別の男ともいい感じになってて。それがわかってるのに好きなフリしなきゃいけないんだよ。俺はゲイで女の子を好きになることなんてないのに」
「そっか、辛いこと話してくれてありがとう」
僕は唯斗くんの手を握った。指先が氷のように冷たい。
きっと唯斗くんが一番深く傷ついているところを見せてくれたのだ。
ゲイであるのに女の子を好きなフリをしくちゃいけないこと。
仕事を途中で放り出してしまったこと。
ずっと悩んできたのだ。
それが辛くなって海南に逃げてきたと言っていたけど、影のように付きまとっていたのかもしれない。
僕はなにもできない。唯斗くんが抱えている痛みの半分も理解できていないだろう。
それでもそばに寄り添いたい。
だって誰よりも大好きなんだから。
釣り合わないんだったら、釣り合うための努力をしたい。
「おいで」
僕が両腕を広げると唯斗くんがぽんと胸の中に入ってきてくれた。サラサラの髪を撫でてあげると強張っていた唯斗くんの身体の力が抜けていく。
「唯斗くんはいっぱい頑張ってるから、いい子いい子してあげる」
「……藍がいてくてよかった」
背中に回された腕に力が入る。僕もぎゅっとしがみついた。わずかな隙間も許せないくらい唯斗くんとくっついていたい。
「あ〜これ以上ダメだ」
「ん?」
「藍を押し倒したくなる」
顔を上げた唯斗くんの両目は情欲を含んでいた。意味を理解して、僕の頭がボンッと音を立てる。
「じゃあ離れよ」
「やだ。もうちょっと」
「……なにもしないからね?」
「わかってる」
そう言われると僕も変な気分になってきてしまう。修学旅行中でよかった。もし寮だったらどうなっていたか。
ガタッと音がして振り返ると扉の前にシンタが立っていた。
「あ〜わりぃ。邪魔するつもりじゃなかったんだけど。その、トランプ取りに来てさ」
シンタが気まずそうに頰を搔いている。僕は恥ずかしさのあまりにベッドにダイブした。
「いいところだったのに邪魔するなよ」
「だからわざとじゃないって」
唯斗くんとシンタが言い合いをしているけど、僕は恥ずかしくて顔を出せそうもない。
布団の中でモダモダしていると上に重さを感じる。
「ほら、出てきておいで」
「むーりー!」
「照れちゃって可愛い」
「……おまえらいつもそんな感じなのかよ」
呆れた様子のシンタの顔が浮かぶ。恥ずかしくて見られたくない。
だってオムツを履いていたときから一緒なのだ。いわば家族に恋人とイチャイチャしていたところを見られたと同じ。平静でいられるはずがない。
「じゃあ……」
唯斗くんがばっと布団を引っ張って中に入ってきた。
「これなら見られないから恥ずかしくないね」
「これはこれで恥ずかしいよ!」
僕の不満は聞き入れてもらえず、唯斗くんはしばらく笑っていた。