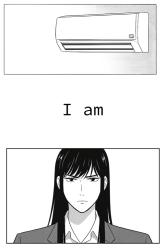帝の御陵に絵を描け──。
清麻呂からその命を聞いた日の夜、俺は眠れなかった。
畳の上に横になっても、胸の奥がざわついて、どうにも落ち着かない。
推しの絵を描いていたら、千三百年前の帝に召し出される。
そんな話があってたまるか、と令和の俺なら笑い飛ばしていただろう。
だが、今の俺は笑えなかった。これは現実だ。逃げられない。
翌朝、清麻呂に連れられて御陵へ向かった。
都の喧騒を離れ、丘陵地帯へ入ると、空気がひんやりと変わった。
「照夫、緊張しておるか」
「……はい」
「無理もない。だが、いましの筆は帝が選ばれた。胸を張るがよい」
胸を張る──そんな簡単な話ではない。
俺はただ、推しの絵を描いていただけだ。
それが、帝の墓に刻まれるなど、どう考えても分不相応だ。
やがて、御陵の入口が見えた。
外見は質素な墳丘だが、近づくにつれ、空気が重くなる。
清麻呂が松明を灯し、俺を促した。
中は狭く、暗く、静かだった。松明の火が壁に揺れ、影が踊る。石棺が置かれる予定の空間に辿り着いた。
この空間の高さは1mぐらいだろうか。俺と清麻呂の二人がかがんでやっと入れる狭い空間だ。
「ここに、帝が眠られる」
清麻呂の声は低く、厳かだった。
「そして、この壁の面に──」
清麻呂は西側の壁を指した。
「『新しい学館のおなごたち』を描くのだ」
その言葉を聞いた瞬間、胸の奥が熱くなった。
推しを描く。
だが、これはファンアートではない。
帝の墓だ。歴史に残る壁画だ。
「……本当に、俺でいいんですか」
思わず漏れた声に、清麻呂は笑った。
「照夫。いまし以外に誰が描けよう。あの絵を見た者は皆、口を揃えて言った。“濃き淡きをしっかりつけられていて、姿や凛としての出で立ちや素にして晴れやかなりし”とな」
濃淡をしっかりつけられていて立体感も出ており素晴しい──
令和で、AGの絵を描いていたときに言われた言葉と同じだった。
俺は壁に手を触れた。
冷たく、ざらついている。
ここに、推しの姿を描くのか。
「……やります」
気づけば、そう口にしていた。
清麻呂は満足げに頷いた。
「では、まずは巡りに帯びて行きよ。あの女子たちの姿を、余すところなく見てくるがよい。帝の御陵は十年の計りだ。いましには一年、習作に費やす時を与える」
一年──
推しの全国ツアーに帯同する一年。
胸が高鳴った。
こうして俺は、画材を背負い、「新しい学館のおなごたち」の巡業に同行することになった。
* * *
巡業の初日は、東国の大きな集落だった。
広場には簡素な舞台が組まれ、村人たちがざわざわと集まってくる。
子どもたちは走り回り、老人たちは腰を下ろし、若者たちは興味深そうに舞台を見つめていた。
やがて、楽が鳴った。
太鼓の低い響きが地面を震わせ、笛の音が空気を切り裂く。
その瞬間、四人が舞台に現れた。
白い衣が風をはらみ、髪が揺れ、足が地を打つ。
跳ねる。
回る。
止まる。
組む。
笑う。
睨む。
そして、歌う、踊る。
そのすべてが、ひとつの物語のように流れていった。身体そのものが表現だ。
四人の動きは、ただの舞ではなかった。
足を踏み鳴らす音、袖が風を切る音、息を吸う音までもが、ひとつの楽曲のように響いていた。
村人たちは最初こそ戸惑っていたが、やがて目を見開き、息を呑み、ついには手を叩き始めた。
子どもたちは笑い、若者たちは声を上げ、老人たちでさえ身を乗り出していた。
俺は、その光景を夢中で描いた。
跳ね上がる足の角度。
衣が翻る瞬間の影。
笑ったときの頬の柔らかさ。
四人が組み合った時の堅牢さ。
鋭い眼差しの奥にある火。
描いても描いても、描き足りなかった。
巡業は続いた。
北国では、冷たい風が舞台を吹き抜けた。
四人はその風をものともせず、むしろ風を味方につけるように舞った。
袖が大きく揺れ、髪が乱れ、雪のような白い衣が夜空に浮かび上がった。
西の港町では、潮の匂いが漂う中、漁師たちが酒を片手に声を上げた。
四人の舞は荒々しい海のようで、観客の熱気は波のように押し寄せた。
演技が終わってお開きだというのに観客たちは帰らない、拍手が続く。
すると四人は再度舞台に立ち、泳ぐように舞いながらもう一曲を演じた。
南の温暖な地では、花が舞台に投げ込まれた。
四人はそれを拾い、振り回し、投げ返し、笑いながら舞った。
観客は泣き、笑い、叫び、まるで祭りのようだった。
どの地でも、四人は圧倒的だった。
清麻呂は、焚き火のそばで静かに言った。
「照夫、いまし……楽しんでおるな」
「はい。……正直、こんなに胸が熱くなるとは思いませんでした」
「いましの筆は、日に日に冴えておる。巡りが終わる頃には、壁の画の構えの図も見えてこよう」
清麻呂の言葉は、どこか誇らしげだった。
一年が過ぎた頃、俺の手元には数百枚の習作が残っていた。
四人の笑顔、舞、歌う姿、跳ねる姿──どれも、俺の魂の一部のようだった。
そして、都へ戻る日が来た。
巡業の最後の夜、四人は舞台の上で深く一礼した。
観客は立ち上がり、手を叩き続けた。
その音は、夜空に吸い込まれ、どこまでも響いていった。
俺は胸の奥が熱くなり、目頭がじんとした。
──ありがとう。
心の中で、そっと呟いた。
* * *
俺は凝灰岩に漆喰が均一に塗られた壁の前に立った。
学館の一室が工房として与えられた。ここで描いた壁を石室へ運んで組み立てるのだ。
俺の担当する壁は約1m四方の正方形だ。光を柔らかく反射している。
「照夫、いよいよだな」
壁に手を掛けて立つ清麻呂が言った。
俺は深く息を吸い、壁の前に一歩進めた。
一年間、描き続けた四人の姿が脳裏に浮かぶ。
跳ねる瞬間の足の角度。
袖が風を切る軌跡。
笑ったときの頬の影。
鋭い眼差しの奥にある火。
「……描きます」
そう言うと、清麻呂は満足げに頷いた。
「絵の具えはすべて揃えてある。白、黒、赤、青、の色石を砕き、膠を混ぜ、色を作るのはたやすくはない。だが、いましならば扱える」
壁画制作は、想像以上に過酷だった。
壁画制作は俺以外にも、四神(青龍、白虎、朱雀、玄武)を担当する絵師がいて、それぞれ与えられた工房で精を出している。
壁も数枚用意されている。よって失敗は許されているのだが、壁を用意するのも大変なようだ。都からも見渡せる「ふたかみやま」と呼ばれる山で産出する白石(凝灰岩)を切り出してくるそうだ。
石工たちが鑿で叩いて平らに加工して、砥石を使って表面を滑らかにしてくれる。その上に漆喰を塗る。これがキャンバスだ。
絵具は乾きやすく、少しでも迷えば線が滲む。顔料は均一に混ざらず、色が安定しない。筆は硬く、思うように動かない。
他の絵師たちとも一緒に食事などして情報を交換し合う。筆の入れ方のコツや絵具の色の配合方法を試し合った。
特に朱雀の難度が高いらしく、絵師が追加されて二人体制で製作している。
こうして俺たちは悪戦苦闘しながらも、筆を走らせるたびに、それぞれの想いが壁に宿っていく。
まるで、彼女たちや四神がそこに生きているかのように。
清麻呂は毎日のように見に来ては、静かに頷いた。
「照夫……見事だ。いましの筆は、魂を写す」
その言葉を聞くたびに、胸の奥が熱くなった。
だが同時に、ある感覚が静かに広がっていった。
──俺はもう、現代には戻れない。
令和の生活。
工作機械メーカーでの仕事。
ハンバーガー。ラーメン。コーヒー。
スマホ。ネット。
AGファンクラブの仲間たち。
rocky、かさんどら。
新しい学校のリーダーズのライブ。あの夜の熱気。
すべてが、遠い夢のように思えた。
筆を握る手が震えた。
だが、それは恐怖ではなかった。
「飛鳥で生きる」
その覚悟が、静かに胸に落ちた。
壁画制作は数ヶ月に及んだ。
最後の一筆を置いたとき、俺は壁に手を当てた。
「……ありがとう」
誰に向けた言葉か、自分でも分からなかった。
清麻呂は深く頷いた。
「照夫。いましは、帝の御心に応えた。誇るがよい」
帝への報告を終えると、俺は清麻呂に遑を申し出た。
「しばらく……寺に戻りとうございます」
清麻呂は静かに頷いた。
「よい。いましはよく務めた。あとは、好きに生きよ」
寺へ戻る道は、巡業の旅とは違い、静かだった。
風の音、鳥の声、土の匂い──すべてが懐かしかった。
寺に着くと、子どもたちが駆け寄ってきた。
「てるお!」
「帰ってきたのか!」
和尚は変わらぬ穏やかな笑みで迎えてくれた。
「照夫よ。よう戻ったな」
畑の匂い。
土の感触。
井戸水の冷たさ。
藁の寝床の軋む音。
すべてが温かかった。
こうして俺は、再び寺での生活に戻った。
野良仕事をし、子どもたちに字を教え、静かな日々を過ごした。
俺は、ここ飛鳥で生きていく。
脚注:
◆凝灰岩…火山の噴火で放出された火山灰や火山砂(粒径4mm以下)が地面や水底に積もり、固まってできた堆積岩の一種。軽くて軟らかく、加工が容易なため、古墳時代からの石棺、現代の建材として広く利用される。白色、灰色、緑色などがあり、熱に強い特徴を持つ。
◆四神…中国の神話に由来し、天の東西南北の四方位を司る霊獣。東の青龍、西の白虎、南の朱雀、北の玄武が邪気を遮断して幸運を呼び込むとされ、古墳の守護神として尊ばれている。
◆奈良県・二上山…奈良県葛城市と大阪府南河内郡太子町にまたがる山。標高517mの雄岳と標高474mの雌岳の2つの頂を有する。千数百万年前、二上山地域では活発な火山活動が繰り広げられていたため、二上山と周辺の地質は、溶岩や火砕流堆積物などで形成されている。万葉集でも「うつそみの人なるわれや明日よりは二上山を弟世とわが見む(大来皇女)」と詠まれている。
《つづく》
清麻呂からその命を聞いた日の夜、俺は眠れなかった。
畳の上に横になっても、胸の奥がざわついて、どうにも落ち着かない。
推しの絵を描いていたら、千三百年前の帝に召し出される。
そんな話があってたまるか、と令和の俺なら笑い飛ばしていただろう。
だが、今の俺は笑えなかった。これは現実だ。逃げられない。
翌朝、清麻呂に連れられて御陵へ向かった。
都の喧騒を離れ、丘陵地帯へ入ると、空気がひんやりと変わった。
「照夫、緊張しておるか」
「……はい」
「無理もない。だが、いましの筆は帝が選ばれた。胸を張るがよい」
胸を張る──そんな簡単な話ではない。
俺はただ、推しの絵を描いていただけだ。
それが、帝の墓に刻まれるなど、どう考えても分不相応だ。
やがて、御陵の入口が見えた。
外見は質素な墳丘だが、近づくにつれ、空気が重くなる。
清麻呂が松明を灯し、俺を促した。
中は狭く、暗く、静かだった。松明の火が壁に揺れ、影が踊る。石棺が置かれる予定の空間に辿り着いた。
この空間の高さは1mぐらいだろうか。俺と清麻呂の二人がかがんでやっと入れる狭い空間だ。
「ここに、帝が眠られる」
清麻呂の声は低く、厳かだった。
「そして、この壁の面に──」
清麻呂は西側の壁を指した。
「『新しい学館のおなごたち』を描くのだ」
その言葉を聞いた瞬間、胸の奥が熱くなった。
推しを描く。
だが、これはファンアートではない。
帝の墓だ。歴史に残る壁画だ。
「……本当に、俺でいいんですか」
思わず漏れた声に、清麻呂は笑った。
「照夫。いまし以外に誰が描けよう。あの絵を見た者は皆、口を揃えて言った。“濃き淡きをしっかりつけられていて、姿や凛としての出で立ちや素にして晴れやかなりし”とな」
濃淡をしっかりつけられていて立体感も出ており素晴しい──
令和で、AGの絵を描いていたときに言われた言葉と同じだった。
俺は壁に手を触れた。
冷たく、ざらついている。
ここに、推しの姿を描くのか。
「……やります」
気づけば、そう口にしていた。
清麻呂は満足げに頷いた。
「では、まずは巡りに帯びて行きよ。あの女子たちの姿を、余すところなく見てくるがよい。帝の御陵は十年の計りだ。いましには一年、習作に費やす時を与える」
一年──
推しの全国ツアーに帯同する一年。
胸が高鳴った。
こうして俺は、画材を背負い、「新しい学館のおなごたち」の巡業に同行することになった。
* * *
巡業の初日は、東国の大きな集落だった。
広場には簡素な舞台が組まれ、村人たちがざわざわと集まってくる。
子どもたちは走り回り、老人たちは腰を下ろし、若者たちは興味深そうに舞台を見つめていた。
やがて、楽が鳴った。
太鼓の低い響きが地面を震わせ、笛の音が空気を切り裂く。
その瞬間、四人が舞台に現れた。
白い衣が風をはらみ、髪が揺れ、足が地を打つ。
跳ねる。
回る。
止まる。
組む。
笑う。
睨む。
そして、歌う、踊る。
そのすべてが、ひとつの物語のように流れていった。身体そのものが表現だ。
四人の動きは、ただの舞ではなかった。
足を踏み鳴らす音、袖が風を切る音、息を吸う音までもが、ひとつの楽曲のように響いていた。
村人たちは最初こそ戸惑っていたが、やがて目を見開き、息を呑み、ついには手を叩き始めた。
子どもたちは笑い、若者たちは声を上げ、老人たちでさえ身を乗り出していた。
俺は、その光景を夢中で描いた。
跳ね上がる足の角度。
衣が翻る瞬間の影。
笑ったときの頬の柔らかさ。
四人が組み合った時の堅牢さ。
鋭い眼差しの奥にある火。
描いても描いても、描き足りなかった。
巡業は続いた。
北国では、冷たい風が舞台を吹き抜けた。
四人はその風をものともせず、むしろ風を味方につけるように舞った。
袖が大きく揺れ、髪が乱れ、雪のような白い衣が夜空に浮かび上がった。
西の港町では、潮の匂いが漂う中、漁師たちが酒を片手に声を上げた。
四人の舞は荒々しい海のようで、観客の熱気は波のように押し寄せた。
演技が終わってお開きだというのに観客たちは帰らない、拍手が続く。
すると四人は再度舞台に立ち、泳ぐように舞いながらもう一曲を演じた。
南の温暖な地では、花が舞台に投げ込まれた。
四人はそれを拾い、振り回し、投げ返し、笑いながら舞った。
観客は泣き、笑い、叫び、まるで祭りのようだった。
どの地でも、四人は圧倒的だった。
清麻呂は、焚き火のそばで静かに言った。
「照夫、いまし……楽しんでおるな」
「はい。……正直、こんなに胸が熱くなるとは思いませんでした」
「いましの筆は、日に日に冴えておる。巡りが終わる頃には、壁の画の構えの図も見えてこよう」
清麻呂の言葉は、どこか誇らしげだった。
一年が過ぎた頃、俺の手元には数百枚の習作が残っていた。
四人の笑顔、舞、歌う姿、跳ねる姿──どれも、俺の魂の一部のようだった。
そして、都へ戻る日が来た。
巡業の最後の夜、四人は舞台の上で深く一礼した。
観客は立ち上がり、手を叩き続けた。
その音は、夜空に吸い込まれ、どこまでも響いていった。
俺は胸の奥が熱くなり、目頭がじんとした。
──ありがとう。
心の中で、そっと呟いた。
* * *
俺は凝灰岩に漆喰が均一に塗られた壁の前に立った。
学館の一室が工房として与えられた。ここで描いた壁を石室へ運んで組み立てるのだ。
俺の担当する壁は約1m四方の正方形だ。光を柔らかく反射している。
「照夫、いよいよだな」
壁に手を掛けて立つ清麻呂が言った。
俺は深く息を吸い、壁の前に一歩進めた。
一年間、描き続けた四人の姿が脳裏に浮かぶ。
跳ねる瞬間の足の角度。
袖が風を切る軌跡。
笑ったときの頬の影。
鋭い眼差しの奥にある火。
「……描きます」
そう言うと、清麻呂は満足げに頷いた。
「絵の具えはすべて揃えてある。白、黒、赤、青、の色石を砕き、膠を混ぜ、色を作るのはたやすくはない。だが、いましならば扱える」
壁画制作は、想像以上に過酷だった。
壁画制作は俺以外にも、四神(青龍、白虎、朱雀、玄武)を担当する絵師がいて、それぞれ与えられた工房で精を出している。
壁も数枚用意されている。よって失敗は許されているのだが、壁を用意するのも大変なようだ。都からも見渡せる「ふたかみやま」と呼ばれる山で産出する白石(凝灰岩)を切り出してくるそうだ。
石工たちが鑿で叩いて平らに加工して、砥石を使って表面を滑らかにしてくれる。その上に漆喰を塗る。これがキャンバスだ。
絵具は乾きやすく、少しでも迷えば線が滲む。顔料は均一に混ざらず、色が安定しない。筆は硬く、思うように動かない。
他の絵師たちとも一緒に食事などして情報を交換し合う。筆の入れ方のコツや絵具の色の配合方法を試し合った。
特に朱雀の難度が高いらしく、絵師が追加されて二人体制で製作している。
こうして俺たちは悪戦苦闘しながらも、筆を走らせるたびに、それぞれの想いが壁に宿っていく。
まるで、彼女たちや四神がそこに生きているかのように。
清麻呂は毎日のように見に来ては、静かに頷いた。
「照夫……見事だ。いましの筆は、魂を写す」
その言葉を聞くたびに、胸の奥が熱くなった。
だが同時に、ある感覚が静かに広がっていった。
──俺はもう、現代には戻れない。
令和の生活。
工作機械メーカーでの仕事。
ハンバーガー。ラーメン。コーヒー。
スマホ。ネット。
AGファンクラブの仲間たち。
rocky、かさんどら。
新しい学校のリーダーズのライブ。あの夜の熱気。
すべてが、遠い夢のように思えた。
筆を握る手が震えた。
だが、それは恐怖ではなかった。
「飛鳥で生きる」
その覚悟が、静かに胸に落ちた。
壁画制作は数ヶ月に及んだ。
最後の一筆を置いたとき、俺は壁に手を当てた。
「……ありがとう」
誰に向けた言葉か、自分でも分からなかった。
清麻呂は深く頷いた。
「照夫。いましは、帝の御心に応えた。誇るがよい」
帝への報告を終えると、俺は清麻呂に遑を申し出た。
「しばらく……寺に戻りとうございます」
清麻呂は静かに頷いた。
「よい。いましはよく務めた。あとは、好きに生きよ」
寺へ戻る道は、巡業の旅とは違い、静かだった。
風の音、鳥の声、土の匂い──すべてが懐かしかった。
寺に着くと、子どもたちが駆け寄ってきた。
「てるお!」
「帰ってきたのか!」
和尚は変わらぬ穏やかな笑みで迎えてくれた。
「照夫よ。よう戻ったな」
畑の匂い。
土の感触。
井戸水の冷たさ。
藁の寝床の軋む音。
すべてが温かかった。
こうして俺は、再び寺での生活に戻った。
野良仕事をし、子どもたちに字を教え、静かな日々を過ごした。
俺は、ここ飛鳥で生きていく。
脚注:
◆凝灰岩…火山の噴火で放出された火山灰や火山砂(粒径4mm以下)が地面や水底に積もり、固まってできた堆積岩の一種。軽くて軟らかく、加工が容易なため、古墳時代からの石棺、現代の建材として広く利用される。白色、灰色、緑色などがあり、熱に強い特徴を持つ。
◆四神…中国の神話に由来し、天の東西南北の四方位を司る霊獣。東の青龍、西の白虎、南の朱雀、北の玄武が邪気を遮断して幸運を呼び込むとされ、古墳の守護神として尊ばれている。
◆奈良県・二上山…奈良県葛城市と大阪府南河内郡太子町にまたがる山。標高517mの雄岳と標高474mの雌岳の2つの頂を有する。千数百万年前、二上山地域では活発な火山活動が繰り広げられていたため、二上山と周辺の地質は、溶岩や火砕流堆積物などで形成されている。万葉集でも「うつそみの人なるわれや明日よりは二上山を弟世とわが見む(大来皇女)」と詠まれている。
《つづく》