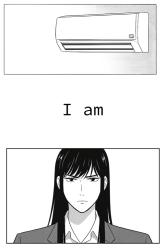都での暮らしにも、ようやく慣れてきた頃だった。
学館での仕事は相変わらず山のようにあったが、俺はそれを淡々とこなしていった。
紙の質は悪く、筆は硬く、墨はすぐに乾く。それでも、令和での事務仕事に比べれば、どこか懐かしい作業だった。
ある日、清麻呂がふと俺の机の上を見て言った。
「照夫、その絵は……いましが描いたのか?」
机の端に置いていた紙切れには、学館の書生たちを軽くデフォルメした落書きがあった。
癖で描いたものだ。見られるとは思っていなかった。
「ええ、まあ……ちょっとした息抜きで」
清麻呂は紙を手に取り、しばらく眺めたあと、静かに言った。
「妙な味わいがあるな。そなたの筆は、字だけではないようだ」
その言葉が、後にとんでもない方向へ転がっていくとは、この時は思いもしなかった。
──そして、運命の日が来た。
年に一度の宮中の宴。学館の役人も招かれる大きな行事だ。
俺は清麻呂に連れられ、広間の隅に控えていた。
やがて、楽が鳴り、四人の女性が舞台に現れた。
白い衣をまとい、髪を高く結い、足取りは軽やか。歌い、踊り、笑い、跳ねる。
その姿を見た瞬間、胸が締めつけられた。
──ああ。
これは……新しい学校のリーダーズだ。
令和の記憶が、鮮やかに蘇った。
MVの光、ライブの熱気、ファンクラブの仲間たちの声。
すべてが一気に押し寄せてきた。
「清麻呂様、あの四人……名は?」
思わず尋ねると、清麻呂は首をかしげた。
「名か? いや、特に決まってはおらぬ。学館にも通っておったがな。和歌が得意で、舞も上手い。宮中でも人気の娘たちよ」
俺は思わず口をついて出た。
「新しい学館の……」
清麻呂が続けた。
「新しい学館のおなごたち、か。ふむ、悪くない」
その場にいた者たちが一斉に頷いた。
「確かに、あの女子たちにふさわしい名だ」
「新しい学館のおなごたち……覚えやすい」
こうして、四人組はいつしか誰からも「新しい学館のおなごたち」と呼ばれるようになった。
翌日、俺は試しに彼女たちの姿を絵に描いてみた。
だが、気づけば本気になっていた。線を引く手が震え、影をつける指先が熱を帯びる。
完成した絵を清麻呂に見せると、彼は目を見開いた。
「……これは、見事だ」
その絵は瞬く間に学館中に広まり、やがて宮中へ、そして都中へと広がった。
人々は口々に言った。
「新しい学館のおなごたちを、ここまで美しく描ける者がいたとは」
「この絵よ、どこか異なる国の香りがする」
そしてついに、その評判は帝の耳にも届いた。
帝はもともと「新しい学館のおなごたち」の大の贔屓だったらしい。
清麻呂が呼び出され、こう告げられたという。
「その絵を描いた者に、余から命を下す」
数日後、清麻呂は俺を呼び出した。
「照夫。いましに、重大な命が下った」
清麻呂の声はいつになく厳かだった。
「帝の御陵の壁面に、『新しい学館のおなごたち』を描け、との仰せである」
息が止まった。
まさか、自分の“推し”を、千三百年前の帝の墓に描くことになるとは──
夢にも思わなかった。
《つづく》
学館での仕事は相変わらず山のようにあったが、俺はそれを淡々とこなしていった。
紙の質は悪く、筆は硬く、墨はすぐに乾く。それでも、令和での事務仕事に比べれば、どこか懐かしい作業だった。
ある日、清麻呂がふと俺の机の上を見て言った。
「照夫、その絵は……いましが描いたのか?」
机の端に置いていた紙切れには、学館の書生たちを軽くデフォルメした落書きがあった。
癖で描いたものだ。見られるとは思っていなかった。
「ええ、まあ……ちょっとした息抜きで」
清麻呂は紙を手に取り、しばらく眺めたあと、静かに言った。
「妙な味わいがあるな。そなたの筆は、字だけではないようだ」
その言葉が、後にとんでもない方向へ転がっていくとは、この時は思いもしなかった。
──そして、運命の日が来た。
年に一度の宮中の宴。学館の役人も招かれる大きな行事だ。
俺は清麻呂に連れられ、広間の隅に控えていた。
やがて、楽が鳴り、四人の女性が舞台に現れた。
白い衣をまとい、髪を高く結い、足取りは軽やか。歌い、踊り、笑い、跳ねる。
その姿を見た瞬間、胸が締めつけられた。
──ああ。
これは……新しい学校のリーダーズだ。
令和の記憶が、鮮やかに蘇った。
MVの光、ライブの熱気、ファンクラブの仲間たちの声。
すべてが一気に押し寄せてきた。
「清麻呂様、あの四人……名は?」
思わず尋ねると、清麻呂は首をかしげた。
「名か? いや、特に決まってはおらぬ。学館にも通っておったがな。和歌が得意で、舞も上手い。宮中でも人気の娘たちよ」
俺は思わず口をついて出た。
「新しい学館の……」
清麻呂が続けた。
「新しい学館のおなごたち、か。ふむ、悪くない」
その場にいた者たちが一斉に頷いた。
「確かに、あの女子たちにふさわしい名だ」
「新しい学館のおなごたち……覚えやすい」
こうして、四人組はいつしか誰からも「新しい学館のおなごたち」と呼ばれるようになった。
翌日、俺は試しに彼女たちの姿を絵に描いてみた。
だが、気づけば本気になっていた。線を引く手が震え、影をつける指先が熱を帯びる。
完成した絵を清麻呂に見せると、彼は目を見開いた。
「……これは、見事だ」
その絵は瞬く間に学館中に広まり、やがて宮中へ、そして都中へと広がった。
人々は口々に言った。
「新しい学館のおなごたちを、ここまで美しく描ける者がいたとは」
「この絵よ、どこか異なる国の香りがする」
そしてついに、その評判は帝の耳にも届いた。
帝はもともと「新しい学館のおなごたち」の大の贔屓だったらしい。
清麻呂が呼び出され、こう告げられたという。
「その絵を描いた者に、余から命を下す」
数日後、清麻呂は俺を呼び出した。
「照夫。いましに、重大な命が下った」
清麻呂の声はいつになく厳かだった。
「帝の御陵の壁面に、『新しい学館のおなごたち』を描け、との仰せである」
息が止まった。
まさか、自分の“推し”を、千三百年前の帝の墓に描くことになるとは──
夢にも思わなかった。
《つづく》