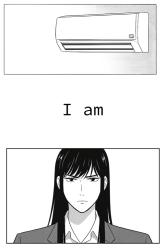横手川 照夫、五十四歳。富山県在住。仕事は工作機械メーカーのエンジニア。
特に出世欲もなく、かといって不満があるわけでもない。淡々とした日々を積み重ねて、気づけば五十を過ぎていた。
そんな俺の生活が変わったのは、ある夜のことだった。
YouTubeでなんとなく流れてきた動画──女性四人組のダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」のMVを、ふとクリックした。
最初の数秒で、胸を撃ち抜かれた。
四人の動きはキレがあり、表情は自由と個性に溢れ、どこか懐かしくて、どこか新しくて、気づけば再生ボタンを何度も押していた。
「……なんだこれ。すげえな」
その日から、俺の生活は少しずつ変わり始めた。
MVを見漁り、ライブ映像を探し、気づけばファンクラブにも入っていた。
ファンクラブでのハンドルネームは「スーツアーマー」とした。
ガンダム好きの俺らしい名前だ。
それに加えて、会社員なのでスーツ。そして我が社は自衛隊向けの装甲車の外板を曲げる大型プレスブレーキを製造販売している。
装甲=アーマー──まあ、中年のダジャレみたいなものだ。
だが、意外と気に入っている。自分の本名は好きではないし。
ファンクラブの交流サイトでは、同じAGファンの仲間たちが毎日のように書き込みをしていた。
おっと、AGというのは、ATARASHII GAKKO!の略称だ。海外進出時のネームらしい。
その中でも特に仲良くなったのが、「rocky」というハンドルネームの男性だ。
年齢も住む場所も違うのに、AGの話になると、まるで昔からの友人のように話が弾んだ。
「スーツアーマーさん、今日の配信見ました?」
「見た見た。あの振り付け、すごかったな」
「ですよね!あれ絶対ライブでやりますよ」
そんなやり取りが、いつの間にか日課になっていた。
交流サイトには、ファンアートを描く人たちも多かった。
AGのメンバーを可愛く描いたり、ライブのワンシーンを再現したり、どれも愛にあふれていた。
パステル調のかわいらしいAGのイラストを描く「かさんどら」さんが、ライブで会ってみたら男性だったのには驚いたが。てっきり女性かと思い込んでいた。
俺は絵なんて描いたことがなかった。美術の成績はいつも「2」か、定期試験で頑張った甲斐があってよくて「3」。センスなんて、あるわけがない。
それでも──描いてみたくなった。
AGを好きになってから、胸の奥にずっと灯っていた熱のようなものが、どうしても形にしたかった。
最初の絵はひどいものだった。顔はゆがみ、手は棒のようで、rockyとかさんどらに見せたら笑われるだろうと思った。
だが、rockyは言った。
「スーツアーマーさん、これ……めっちゃいいですよ。なんか“好き”が伝わってくる絵です」
かさんどらは「スツマーさんのかーいーでちゅ~💖(*´ε`*)チュッチュ」
……正直、どう返せばいいのか分からなかったが、悪い気はしなかった。
そこから俺は、毎晩のように絵を描いた。色鉛筆や用具も揃えてみた。仕事から帰って、夕飯を食べて、風呂に入って、机に向かってペンを握る。
線は少しずつ滑らかになり、影のつけ方も覚え、気づけば交流サイトでも褒められるようになっていた。
「スーツアーマーさん、上達早すぎません?」
「雪も溶けるほど🫠あちちな熱量ですなぁ」
「It's so beautiful!」
「完成おめでとうございまーす&お疲れさまでしたぁ😄」
「(^▽^)/少年並みの集中力!✨素晴らすぃ!(⌒∇⌒)」
「すっかり画伯🦊🫶描くたびに成長を感じれてお父さん嬉しいよ🙌」
「濃淡をしっかりつけられていて立体感も出ており素晴らしい仕上がり👏見習いたいと思います。」
「これだからガノタは」
「素晴らしすぎて、言葉が出ません〜!スーツアーマーさんが絵に向き合う真剣な眼差しや、描ききった瞬間の嬉しそうな目尻まで、つい想像してしまいます。」
「わぁオリジナリティ溢るる💙」
そんなやり取りが、俺の毎日を明るくした。
気づけば、AGは俺の人生に“彩り”を与えていた。
ガンダムだけが趣味だった俺の世界に、新しい色が増えた。
五十を過ぎて、こんなふうに胸が躍る青春の日々が来るとは思っていなかった。
またライブの開催が待ち遠しくなった。よし、遠征費も稼がないとな、しっかり働くぞ!
──この時の俺は、まさか自分が千三百年前の飛鳥で筆を握ることになるなんて、夢にも思っていなかった。
特に出世欲もなく、かといって不満があるわけでもない。淡々とした日々を積み重ねて、気づけば五十を過ぎていた。
そんな俺の生活が変わったのは、ある夜のことだった。
YouTubeでなんとなく流れてきた動画──女性四人組のダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」のMVを、ふとクリックした。
最初の数秒で、胸を撃ち抜かれた。
四人の動きはキレがあり、表情は自由と個性に溢れ、どこか懐かしくて、どこか新しくて、気づけば再生ボタンを何度も押していた。
「……なんだこれ。すげえな」
その日から、俺の生活は少しずつ変わり始めた。
MVを見漁り、ライブ映像を探し、気づけばファンクラブにも入っていた。
ファンクラブでのハンドルネームは「スーツアーマー」とした。
ガンダム好きの俺らしい名前だ。
それに加えて、会社員なのでスーツ。そして我が社は自衛隊向けの装甲車の外板を曲げる大型プレスブレーキを製造販売している。
装甲=アーマー──まあ、中年のダジャレみたいなものだ。
だが、意外と気に入っている。自分の本名は好きではないし。
ファンクラブの交流サイトでは、同じAGファンの仲間たちが毎日のように書き込みをしていた。
おっと、AGというのは、ATARASHII GAKKO!の略称だ。海外進出時のネームらしい。
その中でも特に仲良くなったのが、「rocky」というハンドルネームの男性だ。
年齢も住む場所も違うのに、AGの話になると、まるで昔からの友人のように話が弾んだ。
「スーツアーマーさん、今日の配信見ました?」
「見た見た。あの振り付け、すごかったな」
「ですよね!あれ絶対ライブでやりますよ」
そんなやり取りが、いつの間にか日課になっていた。
交流サイトには、ファンアートを描く人たちも多かった。
AGのメンバーを可愛く描いたり、ライブのワンシーンを再現したり、どれも愛にあふれていた。
パステル調のかわいらしいAGのイラストを描く「かさんどら」さんが、ライブで会ってみたら男性だったのには驚いたが。てっきり女性かと思い込んでいた。
俺は絵なんて描いたことがなかった。美術の成績はいつも「2」か、定期試験で頑張った甲斐があってよくて「3」。センスなんて、あるわけがない。
それでも──描いてみたくなった。
AGを好きになってから、胸の奥にずっと灯っていた熱のようなものが、どうしても形にしたかった。
最初の絵はひどいものだった。顔はゆがみ、手は棒のようで、rockyとかさんどらに見せたら笑われるだろうと思った。
だが、rockyは言った。
「スーツアーマーさん、これ……めっちゃいいですよ。なんか“好き”が伝わってくる絵です」
かさんどらは「スツマーさんのかーいーでちゅ~💖(*´ε`*)チュッチュ」
……正直、どう返せばいいのか分からなかったが、悪い気はしなかった。
そこから俺は、毎晩のように絵を描いた。色鉛筆や用具も揃えてみた。仕事から帰って、夕飯を食べて、風呂に入って、机に向かってペンを握る。
線は少しずつ滑らかになり、影のつけ方も覚え、気づけば交流サイトでも褒められるようになっていた。
「スーツアーマーさん、上達早すぎません?」
「雪も溶けるほど🫠あちちな熱量ですなぁ」
「It's so beautiful!」
「完成おめでとうございまーす&お疲れさまでしたぁ😄」
「(^▽^)/少年並みの集中力!✨素晴らすぃ!(⌒∇⌒)」
「すっかり画伯🦊🫶描くたびに成長を感じれてお父さん嬉しいよ🙌」
「濃淡をしっかりつけられていて立体感も出ており素晴らしい仕上がり👏見習いたいと思います。」
「これだからガノタは」
「素晴らしすぎて、言葉が出ません〜!スーツアーマーさんが絵に向き合う真剣な眼差しや、描ききった瞬間の嬉しそうな目尻まで、つい想像してしまいます。」
「わぁオリジナリティ溢るる💙」
そんなやり取りが、俺の毎日を明るくした。
気づけば、AGは俺の人生に“彩り”を与えていた。
ガンダムだけが趣味だった俺の世界に、新しい色が増えた。
五十を過ぎて、こんなふうに胸が躍る青春の日々が来るとは思っていなかった。
またライブの開催が待ち遠しくなった。よし、遠征費も稼がないとな、しっかり働くぞ!
──この時の俺は、まさか自分が千三百年前の飛鳥で筆を握ることになるなんて、夢にも思っていなかった。