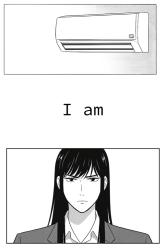こうしてこの寺での暮らしが二年を過ぎた頃、俺の名は村を越えて広がり始めた。
最初は里長が、俺の書いた帳面を近隣の村に見せたことがきっかけだった。
「この字を書いたのは誰だ」と、別の村の長が尋ねたらしい。
やがて、この地方を治める豪族の耳にも届いた。
豪族の館に呼ばれ、穀倉の記録や家人の名簿を清書したこともある。
豪族は俺の筆を見て、目を細めて言った。
「異国の者かと思うてたが、そなたはあやしな手を持つ」
あやしの意味はおそらく不思議という意味だろう、でも、褒められているのは分かった。
評判というものは、思っているよりも早く遠くへ飛んでいく。
そしてついに、都から使いが来た。
その日、寺の門前に立っていたのは、見たこともないほど立派な衣をまとった男だった。
腰には飾り金具のついた帯、足元は革の靴。村の誰とも違う。
「照夫殿であるか」
男は俺の名を、驚くほど正確に発音した。
「朝廷よりの仰せである。学館の長、大田 清麻呂様が、そなたを召し出される」
同席していた和尚は深く頷き、静かに言った。
「都へ上るがよい。そなたの筆は、ここに留めておくには惜しい」
胸の奥がざわついた。
ここでの暮らしに慣れ、村の人々にも受け入れられ、ようやく居場所ができたと思っていた。
だが、また世界が動き出す。
「……分かりました」
そう答えるしかなかった。
出立の日、村の人々が寺の前に集まっていた。
子どもたちは俺の袖をつかみ、「てるお、もう帰ってこないのか」と泣きそうな顔をした。
里長は腕を組み、いつもの無愛想な表情のまま「都でも恥をかかぬようにな」と言った。
それが精一杯の激励なのだろう。
和尚は、門の前で静かに手を合わせた。
「照夫よ。都は広うて深い。だが、そなたならば迷わぬ」
迷わぬ──その言葉が胸に刺さった。
俺は三年前、草原で立ち尽くしたまま、何も分からず迷っていた。
あの頃の俺を思えば、今の俺は確かに変わったのかもしれない。
荷といえば、粗末な布袋ひとつ。
筆と墨と、寺で分けてもらった少しの食糧。
それだけを背負い、俺は村を後にした。
振り返ると、村の屋根が夕日に照らされていた。
藁の匂い、土の匂い、子どもたちの笑い声。
すべてが、もう遠ざかっていく。
都までは十日間の道のりだった。
近くのコンビニに行くときでさえも車を運転していた俺だが、この二年間はとにかくどこへ行くにしても徒歩だ。おかげで健脚になった俺だが、それでも十日も歩き続けるのはかなりつらかった。
カレンダーが無いので季節は風景で判断するしかない。桜の花がすでに散って青い葉が茂っているので初夏の頃だと思う。
山道を越えた。木々の間を抜ける風は冷たく、鳥の声がやけに澄んで聞こえた。
川沿いを歩いた。川幅は広く、村の小川とは比べものにならない。それだけ広くて大きな川なのに端から端まで澄みきっている。美しさに感動する。
途中の集落では、俺の訛りを珍しがる者もいたが、誰も深くは詮索しなかった。
こうして十日後に、道が開けた先に、巨大な建物が見えた。
瓦屋根が陽光を反射し、まるで別世界のように輝いている。
──これが都か。
胸の奥がざわついた。
村とは違う、圧倒的な人の気配があった。
学館に案内されると、そこは寺とは比べものにならないほど広かった。
書物が積まれ、役人たちが忙しなく行き交っている。
「照夫と申すか」
声の方を見ると、一人の男が立っていた。
四十前後だろうか。鋭い目つきだが、どこか柔らかさもある。
これが大田清麻呂だった。
「そなたの筆、すでに聞き及んでおる。字が読め、書けると」
俺がうなずくと、大田は満足げに頷いた。
「ならば、しばらく我がもとで働くがよい。学館の事務は山のようにある」
その言い方は、命令というよりも期待に近かった。
こうして俺は、都での生活を始めることになった。
村とは違い、都は絶えず音がしていた。
市場の呼び声、役人たちの足音、寺の鐘の響き。
夜になっても、どこかで人の声が聞こえる。
学館では、朝から晩まで文書の整理に追われた。
紙は粗く、筆は硬く、墨はすぐに乾く。
「照夫殿、そなたの手は実に早い」
書生たちは驚き、時に羨ましそうに俺を見た。
PC操作よりも実は手作業の方が得意なのかもしれないと自分がいちばん驚いた。
都の一年は、村の三年よりも早く過ぎていった。
それほどに、毎日が新しく、慌ただしく、そして刺激に満ちていた。
最初は里長が、俺の書いた帳面を近隣の村に見せたことがきっかけだった。
「この字を書いたのは誰だ」と、別の村の長が尋ねたらしい。
やがて、この地方を治める豪族の耳にも届いた。
豪族の館に呼ばれ、穀倉の記録や家人の名簿を清書したこともある。
豪族は俺の筆を見て、目を細めて言った。
「異国の者かと思うてたが、そなたはあやしな手を持つ」
あやしの意味はおそらく不思議という意味だろう、でも、褒められているのは分かった。
評判というものは、思っているよりも早く遠くへ飛んでいく。
そしてついに、都から使いが来た。
その日、寺の門前に立っていたのは、見たこともないほど立派な衣をまとった男だった。
腰には飾り金具のついた帯、足元は革の靴。村の誰とも違う。
「照夫殿であるか」
男は俺の名を、驚くほど正確に発音した。
「朝廷よりの仰せである。学館の長、大田 清麻呂様が、そなたを召し出される」
同席していた和尚は深く頷き、静かに言った。
「都へ上るがよい。そなたの筆は、ここに留めておくには惜しい」
胸の奥がざわついた。
ここでの暮らしに慣れ、村の人々にも受け入れられ、ようやく居場所ができたと思っていた。
だが、また世界が動き出す。
「……分かりました」
そう答えるしかなかった。
出立の日、村の人々が寺の前に集まっていた。
子どもたちは俺の袖をつかみ、「てるお、もう帰ってこないのか」と泣きそうな顔をした。
里長は腕を組み、いつもの無愛想な表情のまま「都でも恥をかかぬようにな」と言った。
それが精一杯の激励なのだろう。
和尚は、門の前で静かに手を合わせた。
「照夫よ。都は広うて深い。だが、そなたならば迷わぬ」
迷わぬ──その言葉が胸に刺さった。
俺は三年前、草原で立ち尽くしたまま、何も分からず迷っていた。
あの頃の俺を思えば、今の俺は確かに変わったのかもしれない。
荷といえば、粗末な布袋ひとつ。
筆と墨と、寺で分けてもらった少しの食糧。
それだけを背負い、俺は村を後にした。
振り返ると、村の屋根が夕日に照らされていた。
藁の匂い、土の匂い、子どもたちの笑い声。
すべてが、もう遠ざかっていく。
都までは十日間の道のりだった。
近くのコンビニに行くときでさえも車を運転していた俺だが、この二年間はとにかくどこへ行くにしても徒歩だ。おかげで健脚になった俺だが、それでも十日も歩き続けるのはかなりつらかった。
カレンダーが無いので季節は風景で判断するしかない。桜の花がすでに散って青い葉が茂っているので初夏の頃だと思う。
山道を越えた。木々の間を抜ける風は冷たく、鳥の声がやけに澄んで聞こえた。
川沿いを歩いた。川幅は広く、村の小川とは比べものにならない。それだけ広くて大きな川なのに端から端まで澄みきっている。美しさに感動する。
途中の集落では、俺の訛りを珍しがる者もいたが、誰も深くは詮索しなかった。
こうして十日後に、道が開けた先に、巨大な建物が見えた。
瓦屋根が陽光を反射し、まるで別世界のように輝いている。
──これが都か。
胸の奥がざわついた。
村とは違う、圧倒的な人の気配があった。
学館に案内されると、そこは寺とは比べものにならないほど広かった。
書物が積まれ、役人たちが忙しなく行き交っている。
「照夫と申すか」
声の方を見ると、一人の男が立っていた。
四十前後だろうか。鋭い目つきだが、どこか柔らかさもある。
これが大田清麻呂だった。
「そなたの筆、すでに聞き及んでおる。字が読め、書けると」
俺がうなずくと、大田は満足げに頷いた。
「ならば、しばらく我がもとで働くがよい。学館の事務は山のようにある」
その言い方は、命令というよりも期待に近かった。
こうして俺は、都での生活を始めることになった。
村とは違い、都は絶えず音がしていた。
市場の呼び声、役人たちの足音、寺の鐘の響き。
夜になっても、どこかで人の声が聞こえる。
学館では、朝から晩まで文書の整理に追われた。
紙は粗く、筆は硬く、墨はすぐに乾く。
「照夫殿、そなたの手は実に早い」
書生たちは驚き、時に羨ましそうに俺を見た。
PC操作よりも実は手作業の方が得意なのかもしれないと自分がいちばん驚いた。
都の一年は、村の三年よりも早く過ぎていった。
それほどに、毎日が新しく、慌ただしく、そして刺激に満ちていた。