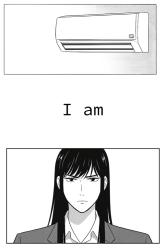寺に案内されると、和尚は俺を本堂の隅に座らせ、湯気の立つ椀を差し出した。
中身は、米とも粥ともつかない白いどろりとしたものだった。
味はほとんどしなかったが、空腹だった俺には十分すぎるほど温かかった。
「名は、なんと申す」
和尚がゆっくりとした口調で尋ねた。
俺は自分の名前を告げたが、和尚は一度では聞き取れなかったようで、
「てう……お?」
と首をかしげた。
その発音が妙に可笑しくて、思わず笑ってしまった。どうやら「る」が発音しにくいようだ。
その夜は、寺の片隅で藁の上に横になった。
硬くて、湿っていて、寝返りを打つたびに軋む。
眠れるわけがなかった。眠れないまま天井を見つめていると、ふと気づいた。
──いつか帰れるのだろうか。
その考えが胸に重く沈んだが、不思議と恐怖はなかった。
むしろ、現実感のないまま、ただ受け入れるしかないという諦めに近い感情だった。
こうして、俺は寺に住みつくようになった。
薪を割り、水を汲み、畑を耕し、夜になったら寝る。
寺での暮らしは、思っていたよりも静かで、そして忙しかった。
朝はまだ薄暗いうちに鐘の音で起こされる。
冷たい井戸水で顔を洗い、薪を割り、畑に出て土をいじる。
昼は寺に出入りする子どもたちに混じって、和尚の手伝いをしながら言葉を覚えた。
最初は、聞き取れる単語の方が少なかった。なんというか、子音が少ない気がする。
特にラ行がほとんど「あいうえお」みたいな発音をする。
ハ行は「ふぁ・ふぃ・ひゅ・ふぇ・ふぉ」と発音する。HよりFなのだろう。
そして極め付けがカ行だ。「くゎ・くぃ・くぅ・けぇ・くぉ」と聞こえる。
鳥は「とい」、川は「くゎあ」。もちろん、目の前に鳥や川があっての会話をしているときなので分かるは分かるのだが。
それでも山はやまだし、稲はいねだし、当たり前のことなのだがこんな太古の時代でも日本語はすでに日本語なんだな、と感心してしまう。でも魚は「うお」と言う、「さかな」と言う人はいない。
こうして、和尚の話すゆっくりとした口調と、子どもたちの素朴な言い回しは、俺の耳に少しずつ馴染んでいった。
和尚が日課とする読経の経典を見ると、やっぱりなかなか読みづらい字体だった。そもそも平仮名がまったくない。
ああ、これ博物館で見たやつだ……スマホで調べられないのが、こんなに不便だとは。
そこに興味を示している俺を見て、和尚が「経に意を感じるのか?」と尋ねてきた。
「なんて書いてあるのかなと思いまして。これは『びくに』だと思うのですが」
比丘尼の字に指をさして答えてみた。
続けて優婆夷の字に、
「ですが、これは……なんでしょうかね、ゆうばい? ゆばい?」
和尚は「字が読めるのか」と驚いた顔をした。
そして、紙とも布ともつかない、ざらついた薄い板のようなものと筆を持ってきた。
俺はただ自分の名前を書いてみた。照夫。
和尚はますます目を丸くしながらも、何度も頷きながら、
「これ珍しきことよ」
と呟いた。
そうか、この時代、識字率は相当低いわけだ。
俺は決して学校の成績は良い方ではなかったし、せっかく入った大学もつまらなくなって二年生の時に中退してしまった。
だけど、字が読み書きできるというだけで、この日から村の人たちにとって俺は特別な存在になった。
寺での暮らしがひと月を過ぎた頃、村の里長が寺を訪れた。
「この者、字を書けるという者か」
里長は俺の書いた文字をじっと見つめ、やがて深く頷いた。
「村のしるしをつける者が欲しいのだ。手伝いてくれぬか」
『しるし』とは帳面のことらしい。(発音は「しうし」と聞こえる、村は「むあ」と聞こえる)
帳面といっても、収穫した穀物の量や、村人の名前、貸し借りの記録を、粗末な紙に筆で書きつけるだけのものだ。
だが、村人たちは俺が筆を動かすたびに感心したように息を呑んだ。
「字だ」「字を書いておる」
「なんと、きれいな字を書くもんだ」
「こんなに早く書けうのか」
その反応に、俺は少し照れた。
ただの中年男の、普通の字なのに。そもそも筆を使い慣れていないのに。
まさか義務教育と、高校の時のいけ好かなかった国語教師に感謝する日がやってくるとは思っていなかった。
寺に戻ると、和尚が静かに笑った。
「いまし、もうすっかり村の者よの」
『いまし』とは、貴方、という意味だ。
その言葉を聞いた瞬間、胸の奥がじんわりと温かくなった。
この村の人たちは純朴で、寛容で、おおらかだ。
脚注:
◆比丘尼(びくに)…仏教における出家し戒律を守って修行する女性僧侶(尼僧)のこと。サンスクリット語「bhikṣuṇī(ビクシュニー)」の音写。
◆優婆夷(うばい)…仏教における在家の女性信者のこと。サンスクリット語「upāsikā(ウパーシカー)」の音写。
中身は、米とも粥ともつかない白いどろりとしたものだった。
味はほとんどしなかったが、空腹だった俺には十分すぎるほど温かかった。
「名は、なんと申す」
和尚がゆっくりとした口調で尋ねた。
俺は自分の名前を告げたが、和尚は一度では聞き取れなかったようで、
「てう……お?」
と首をかしげた。
その発音が妙に可笑しくて、思わず笑ってしまった。どうやら「る」が発音しにくいようだ。
その夜は、寺の片隅で藁の上に横になった。
硬くて、湿っていて、寝返りを打つたびに軋む。
眠れるわけがなかった。眠れないまま天井を見つめていると、ふと気づいた。
──いつか帰れるのだろうか。
その考えが胸に重く沈んだが、不思議と恐怖はなかった。
むしろ、現実感のないまま、ただ受け入れるしかないという諦めに近い感情だった。
こうして、俺は寺に住みつくようになった。
薪を割り、水を汲み、畑を耕し、夜になったら寝る。
寺での暮らしは、思っていたよりも静かで、そして忙しかった。
朝はまだ薄暗いうちに鐘の音で起こされる。
冷たい井戸水で顔を洗い、薪を割り、畑に出て土をいじる。
昼は寺に出入りする子どもたちに混じって、和尚の手伝いをしながら言葉を覚えた。
最初は、聞き取れる単語の方が少なかった。なんというか、子音が少ない気がする。
特にラ行がほとんど「あいうえお」みたいな発音をする。
ハ行は「ふぁ・ふぃ・ひゅ・ふぇ・ふぉ」と発音する。HよりFなのだろう。
そして極め付けがカ行だ。「くゎ・くぃ・くぅ・けぇ・くぉ」と聞こえる。
鳥は「とい」、川は「くゎあ」。もちろん、目の前に鳥や川があっての会話をしているときなので分かるは分かるのだが。
それでも山はやまだし、稲はいねだし、当たり前のことなのだがこんな太古の時代でも日本語はすでに日本語なんだな、と感心してしまう。でも魚は「うお」と言う、「さかな」と言う人はいない。
こうして、和尚の話すゆっくりとした口調と、子どもたちの素朴な言い回しは、俺の耳に少しずつ馴染んでいった。
和尚が日課とする読経の経典を見ると、やっぱりなかなか読みづらい字体だった。そもそも平仮名がまったくない。
ああ、これ博物館で見たやつだ……スマホで調べられないのが、こんなに不便だとは。
そこに興味を示している俺を見て、和尚が「経に意を感じるのか?」と尋ねてきた。
「なんて書いてあるのかなと思いまして。これは『びくに』だと思うのですが」
比丘尼の字に指をさして答えてみた。
続けて優婆夷の字に、
「ですが、これは……なんでしょうかね、ゆうばい? ゆばい?」
和尚は「字が読めるのか」と驚いた顔をした。
そして、紙とも布ともつかない、ざらついた薄い板のようなものと筆を持ってきた。
俺はただ自分の名前を書いてみた。照夫。
和尚はますます目を丸くしながらも、何度も頷きながら、
「これ珍しきことよ」
と呟いた。
そうか、この時代、識字率は相当低いわけだ。
俺は決して学校の成績は良い方ではなかったし、せっかく入った大学もつまらなくなって二年生の時に中退してしまった。
だけど、字が読み書きできるというだけで、この日から村の人たちにとって俺は特別な存在になった。
寺での暮らしがひと月を過ぎた頃、村の里長が寺を訪れた。
「この者、字を書けるという者か」
里長は俺の書いた文字をじっと見つめ、やがて深く頷いた。
「村のしるしをつける者が欲しいのだ。手伝いてくれぬか」
『しるし』とは帳面のことらしい。(発音は「しうし」と聞こえる、村は「むあ」と聞こえる)
帳面といっても、収穫した穀物の量や、村人の名前、貸し借りの記録を、粗末な紙に筆で書きつけるだけのものだ。
だが、村人たちは俺が筆を動かすたびに感心したように息を呑んだ。
「字だ」「字を書いておる」
「なんと、きれいな字を書くもんだ」
「こんなに早く書けうのか」
その反応に、俺は少し照れた。
ただの中年男の、普通の字なのに。そもそも筆を使い慣れていないのに。
まさか義務教育と、高校の時のいけ好かなかった国語教師に感謝する日がやってくるとは思っていなかった。
寺に戻ると、和尚が静かに笑った。
「いまし、もうすっかり村の者よの」
『いまし』とは、貴方、という意味だ。
その言葉を聞いた瞬間、胸の奥がじんわりと温かくなった。
この村の人たちは純朴で、寛容で、おおらかだ。
脚注:
◆比丘尼(びくに)…仏教における出家し戒律を守って修行する女性僧侶(尼僧)のこと。サンスクリット語「bhikṣuṇī(ビクシュニー)」の音写。
◆優婆夷(うばい)…仏教における在家の女性信者のこと。サンスクリット語「upāsikā(ウパーシカー)」の音写。