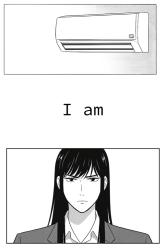これで三回目の夏が終わりに近づいてきたわけだが、夏がこんなにも涼しいとは改めて感心する。
俺は気候学者でもないのでその理由は分からないけれど、二酸化炭素やメタンなどの温室効果ガスが少ないからだと思う。
一方で、この三年でようやく味のしない飯にも慣れた。最初の頃は、塩気のなさに泣きそうになったものだ。
当時は味の濃いものが美味しいと感じていただけなのかもしれない。今では素材そのものの味を感じることに気付いている自分がいる。
慣れたといえば、ここの人たちの話すのがやけにゆっくりだということも。
最初はイライラしたが、三年も経つと、この間の長さが心地よくなる。
とにかく匂いが濃い。人の汗、土、煙、獣。
最初はむせ返ったが、今ではこれが日常の匂いだ。
こうして振り返ってみると、本当にここに来た当初は戸惑うことが多かった。
あの日のことを、どう説明すればいいのか今でもわからない。
雷が落ちたわけでも、光に包まれたわけでもない。気づいたら、ただそこにいた。
見慣れない草原の真ん中で、立ちすくんでいただけだった。
彷徨い歩いていると、集落に出くわした。
俺の姿を見つけた子どもたちが、屈託なく近づいてくる。
「ここはいったいどこなんだ。教えてくれ」
だが、村の子どもたちは俺の話すことに首を傾げた。
そんな俺も、子どもたちの話す言葉に首をかしげた。
日本語であるのは確かなのだが、言葉が分からない。
古い言い回しなのか、訛りなのか、それとも俺の頭がおかしくなったのか。
とにかく、まともに会話が成立しなかった。
それでも子どもたちは俺を怖がるでもなく、ただ珍しいものを見るような目でじっと見つめていた。
そのうちの一人が、俺の手を引っ張った。どこへ行くのかも分からないまま、されるがままについていった。
村の中は、土と煙の匂いが混ざり合い、家々は低く、屋根は藁で覆われていた。
人々は俺を見ると、驚くでもなく、ただ「また変なのが来た」という顔をするだけだった。
子どもたちに連れていかれた先は、小高い丘の上にある寺だった。
寺といっても、俺が知っているような立派な伽藍ではない。
木の柱がむき出しで、風が吹けば軋むような、質素な建物だった。
子どもたちは境内に入ると、奥に向かって大声で呼んだ。
「おしょーさまー! へんなひとー!」
その呼び声に応えるように、奥から一人の男が現れた。
白い髭を胸まで伸ばし、ゆっくりとした足取りで近づいてくる。
その目は、俺を見ても一切動じていなかった。
「ほう……これはまた、珍しき人かな」
その声は低く、落ち着いていて、どこかすべてを見透かしているようだった。
俺が何を言えばいいのか迷っていると、和尚はまるで俺の心を読んだかのように続けた。
「言葉が通じぬか。無理もない。そなた、遠きところから来たのであろう?」
遠きところ──その言い方が、妙にしっくりきた。
俺は思わずうなずいた。
和尚はそれを見て、まるで当たり前のことを確認しただけのように言った。
「ならば、しばらくここで休むがよい。よそより来る者は、まず心を落ち着けねばならぬ」
驚くほど自然に、俺を受け入れた。
この瞬間、俺は悟った。
──時代が違う、と。
俺は気候学者でもないのでその理由は分からないけれど、二酸化炭素やメタンなどの温室効果ガスが少ないからだと思う。
一方で、この三年でようやく味のしない飯にも慣れた。最初の頃は、塩気のなさに泣きそうになったものだ。
当時は味の濃いものが美味しいと感じていただけなのかもしれない。今では素材そのものの味を感じることに気付いている自分がいる。
慣れたといえば、ここの人たちの話すのがやけにゆっくりだということも。
最初はイライラしたが、三年も経つと、この間の長さが心地よくなる。
とにかく匂いが濃い。人の汗、土、煙、獣。
最初はむせ返ったが、今ではこれが日常の匂いだ。
こうして振り返ってみると、本当にここに来た当初は戸惑うことが多かった。
あの日のことを、どう説明すればいいのか今でもわからない。
雷が落ちたわけでも、光に包まれたわけでもない。気づいたら、ただそこにいた。
見慣れない草原の真ん中で、立ちすくんでいただけだった。
彷徨い歩いていると、集落に出くわした。
俺の姿を見つけた子どもたちが、屈託なく近づいてくる。
「ここはいったいどこなんだ。教えてくれ」
だが、村の子どもたちは俺の話すことに首を傾げた。
そんな俺も、子どもたちの話す言葉に首をかしげた。
日本語であるのは確かなのだが、言葉が分からない。
古い言い回しなのか、訛りなのか、それとも俺の頭がおかしくなったのか。
とにかく、まともに会話が成立しなかった。
それでも子どもたちは俺を怖がるでもなく、ただ珍しいものを見るような目でじっと見つめていた。
そのうちの一人が、俺の手を引っ張った。どこへ行くのかも分からないまま、されるがままについていった。
村の中は、土と煙の匂いが混ざり合い、家々は低く、屋根は藁で覆われていた。
人々は俺を見ると、驚くでもなく、ただ「また変なのが来た」という顔をするだけだった。
子どもたちに連れていかれた先は、小高い丘の上にある寺だった。
寺といっても、俺が知っているような立派な伽藍ではない。
木の柱がむき出しで、風が吹けば軋むような、質素な建物だった。
子どもたちは境内に入ると、奥に向かって大声で呼んだ。
「おしょーさまー! へんなひとー!」
その呼び声に応えるように、奥から一人の男が現れた。
白い髭を胸まで伸ばし、ゆっくりとした足取りで近づいてくる。
その目は、俺を見ても一切動じていなかった。
「ほう……これはまた、珍しき人かな」
その声は低く、落ち着いていて、どこかすべてを見透かしているようだった。
俺が何を言えばいいのか迷っていると、和尚はまるで俺の心を読んだかのように続けた。
「言葉が通じぬか。無理もない。そなた、遠きところから来たのであろう?」
遠きところ──その言い方が、妙にしっくりきた。
俺は思わずうなずいた。
和尚はそれを見て、まるで当たり前のことを確認しただけのように言った。
「ならば、しばらくここで休むがよい。よそより来る者は、まず心を落ち着けねばならぬ」
驚くほど自然に、俺を受け入れた。
この瞬間、俺は悟った。
──時代が違う、と。