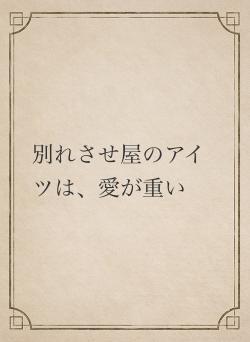もし、この歌声が誰かに届いたなら…
僕らは一生幸せなんだろうな
高校生になったら、もっと毎日がキラキラ輝くと思っていた。
だけど実際の高校生活は、気が合うとまではいえない友達や最低限の会話を交わすクラスメイトに囲まれ、1日の大半を机に向かい、ただただ毎日が過ぎていくだけ。もちろん、彼女がいるなんて夢のまた夢だ。
委員会が長引いた放課後。人のいない靴箱に着いた僕は、靴を手にしながら外を見た。大きな雨粒が地面を激しく叩きつけ、勢いよく跳ね返っている。あれは確実に靴の中までぐしょぐしょになるレベルだ。
「少し待てば小雨になるかなぁ…」
そう呟いた僕は昇降口から出て、傘を広げず軒下で立ち止まった。
大雨で野球部やサッカー部が室内で練習しているため、外は誰もいなくて、まるで世界に自分1人しかいないような気分になる。
雨はそんなに好きじゃないけど、雨音は好きだ。すごく癒される。
ワイヤレスイヤホンを片方だけ耳に付け、選択したメドレーを流し始めた。雨の日に、雨の歌を聴きたくなるのは僕だけじゃないと思う。この曲を聴き終えたら、ずぶ濡れ覚悟で大人しく帰ろう。
そんなことを考えながら、歌を口ずさんでいた。後半のサビを口に出した瞬間、誰かの歌声が重なった。
ーえっ…。
雨の激しい音とイヤホンから流れる音で、近づく足音に気付けなかった。自分のこの声が聞かれていたなんて思いもしなかった。
勢いよく隣を見ると、見覚えのある男子生徒がいる。
「その曲良いよな!」
そう爽やかな笑顔で言ってきたのは、隣のクラスの椎名くんだ。
「う、うん…」
言葉を交わすのは初めてのはず。そもそも僕の存在なんか知らないはずなのに、タメ口で話しかけてきたということは…もしかして僕のこと知ってたのかな?
「雨すごいなー。止むの待ってんの?」
「あ…うん、小雨にならないかなって」
「しばらくはならねぇと思うぞ、この雨は」
「そう…だよね。…帰ろうかな。椎名くんもこれから帰るの?」
「うん。あのさ、帰る前にもっかい歌ってよ」
「…え?」
「さっきの歌でもいいし、違う曲でもいいからさ」
「…あっ…え…な、なんで!?」
椎名くんからのまさかのお願いに軽くパニックになってしまう。
「知念の歌声、ちゃんと聴きたいから」
…あ、僕の名前知ってるんだ。
僕を見る椎名くんの目があまりに真っ直ぐで、断れなかった。
横に並んだまま前を向き、降り続く雨を見ている。そんな状況で、僕は今から椎名くんのために歌う。声のボリュームはどのくらいにすればいいんだろう、ワンフレーズだけ歌えばいいのか、次に流れてくる曲でいいのかな…。鼓動が激しくなりそうだったが、雨音のおかげでリラックスできている。
目を閉じ、小さく息を吐き、歌い始めた。まるで別世界にいるような不思議な感覚になってくる。
1番を歌い終わり「…これでいい?」と聞いた僕に椎名くんは目を輝かせている。
「めっちゃ上手いじゃん!!歌声すげぇ綺麗だし。え、やば」
人に褒められるなんて久しぶりで、頬が真っ赤になりそうだ。
「あ、ありがとう…」
「俺も歌うの好きなんだよ。…なぁ、後夜祭で一緒に歌わない?」
「…」
え…今、なんて言われた?
「…後夜祭?」
「そう!文化祭の後に、生徒だけが体育館に集まってやる後夜祭。希望して、選ばれたらみんなの前でダンスしたり、演奏したり出来るんだってさ」
全校生徒の前で歌う!?…いやいや、無理無理!そもそも椎名くんと僕が一緒に歌うなんて…。
「ま、考えといて。とりあえず、明日の昼休み教室行くから!じゃ、お疲れー」
僕の返事を聞かず、傘を差した椎名くんは1人校門に向かい歩いて行く。
その後ろ姿を見ながら、今さら鼓動が激しくなってくる。人前で歌ったのは、何年振りだろう…。
次の日の昼休み。本当に僕のいる教室にやって来た椎名くんは、ドアから大きな声で呼びかける。
「知念いるー?…あ、いた!」
椎名くんの目当てが僕なことに周りのクラスメイトはざわつき始め、一緒にお弁当を食べている友達も、何で?という顔で見てきた。
僕は急いで椎名くんの所へ駆け寄った。
「あの、椎名くん…他の場所でもいいかな?」
「うん、いいよ!」
人のいない校舎裏に着き、椎名くんは勢いよく話しかけてくる。
「2学期になってすぐに後夜祭の希望者を募るらしいんだよ。んで、中間テスト前に実行委員会によるオーディションがあって、無事通過できたら後夜祭で歌えるってわけ」
「そうなんだ。…椎名くんは、後夜祭で歌いたいって思ってたの?」
「うん!バンドのボーカルでもいいと思ってたけど、楽器出来るメンバー集めんの大変そうだし、それに昨日の知念の歌声聴いたら、びびびっときちゃったんだよ。2人で体育館のステージで歌ってんのが頭に浮かんだ」
「…。」
「つーわけで、よろしくな、知念!」
「あのさ…何で僕なの?その…仲の良い友達を誘えばいいと思うんだけど…」
「知念歌上手いし、せっかく出るなら中途半端じゃなくて、本気で歌いたいじゃん。それにさ…俺と知念だって仲良くなる可能性あるだろ?」
「え…」
椎名くんと僕は正反対だ。いつも友達に囲まれて賑やかな椎名くん。上辺だけの友達付き合いで影を潜めている僕。爽やかで、カッコよくて、背の高い椎名くん。眼鏡で地味で、背が低い僕。椎名くんの中身はよく知らないけど、こんな大人しい根暗な僕とは違うに決まってる。だから…だから仲良くなれるわけないのに、椎名くんがあまりに純粋にそう言ってくれたから、ほんの少しだけ光が見えたんだ。
「…よろしくお願いします…」
差し出した僕の右手を椎名くんは強く握った。
「最高の時間にしような!」
何の迷いもない笑顔を見せた椎名くん。
その瞬間、僕の平凡な毎日が大きく変わる音がした。