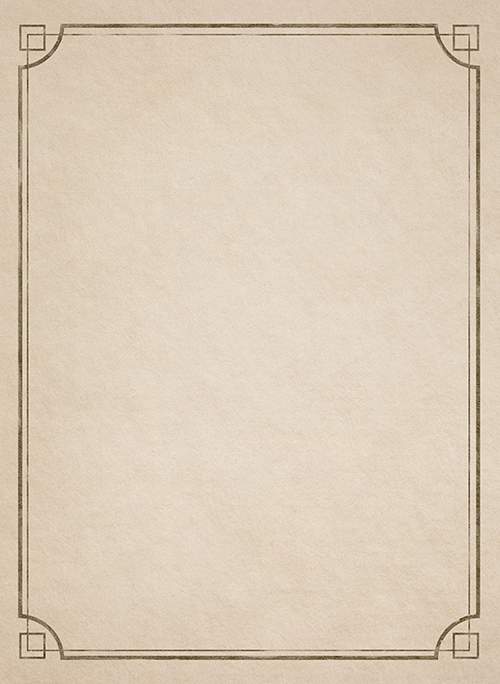5章
私は今、まさに正念場に立たされている。
「この子が、竜馬の婚約者なのね……」
目の前にいらっしゃる神城さんのご両親へ、挨拶をしている最中だった。
急遽、神城さんのお屋敷で暮らすことになったものの、目まぐるしく変わる現実に私の心は全く追いついていない。 呆然とする間もなく、こうして神城家の当主夫妻と対面することになってしまったのだ。
つい先ほど、実家で嵐のような婚約報告を済ませたばかりなのに。
このスピード感には困惑を通り越して目眩すら覚えるが、今の私にはそれ以上に切実な悩みがあった。
(神城さんのご両親に、婚約者として認めてもらえるだろうか……)
私はあやかし界では名を知られた存在だ。もちろん、最悪の意味で。
物心ついた時から「鬼龍院の無能」と蔑まれ、家族や一族のみならず、多くのあやかしから忌み嫌われて生きてきた。
そんな、誰からも望まれない無能な娘が、あろうことか一族の誇りである息子の隣に立つ。親であれば、到底許しがたい不名誉に感じるはずだ。
「両親は優しいから、きっと認めてくれる」
神城さんはそう言って私を励ましてくれたけれど、とてもそうは思えなかった。
彼の言葉を疑っているわけではない。ただ、私はこれまでの人生で「愛される」という経験をあまりにも知らなすぎた。
これでもかというほど嫌われ、拒絶される痛みに慣れきってしまった私の心は、神城さんのご両親までもが私を冷たく突き放す光景を、勝手に描き出してしまう。
不安と恐怖で指先まで氷のように冷たくなり、体はカチコチに強張ったまま、ただ運命の裁定を待つことしかできなかった。
しかし、時間はすぐに過ぎていくもので、あっという間にご両親と対面することとなった。
神城家の使用人に案内された部屋に入るとそこには二人の男女がいた。
(この人達が神城さんの両親……)
お母様は、どこか亡き母を彷彿とさせる慈愛に満ちた美貌の持ち主。対して、お父様は彫刻のように峻厳な面持ちで、現当主としての圧倒的な霊圧が、肌を刺すような威圧感となって部屋を満たしている。
二人は私を一瞥した瞬間、わずかに目を見開いた。けれど、すぐに冷徹なほど凪いだ表情に戻り、私の目の前へと歩み寄る。
「あなたが、竜馬の連れてきた玲花さんね」
お母様の声は、先ほどまでの柔らかな空気とは一変し、氷のような冷ややかさを帯びていた。
(やっぱり……歓迎なんて、されていないんだ)
逃げ出したいほどの不安に襲われ、背中を冷たい汗が伝う。
「は、初めまして……。鬼龍院 玲花と申します……っ」
声の震えを必死に抑え、持てる限りの勇気を振り絞って深々と頭を下げた。
そんな私の痛々しい姿を値踏みするように見つめ、お母様は小さく、けれど重みのある溜息を吐いた。
「まさか、こんな子が息子の婚約者だなんてね……」
突き放すような言葉に、私の心臓はさらに激しく脈打つ。
お母様は鋭く、射抜くような真剣な眼差しに変わり、私に問いを突きつけた。
「ねぇ、玲花さん。あなたは、本気でうちの息子を一生大事にできるの?」
その問いに、私は石のように硬直してしまった。
神城さんを、大事に……。
私たちは今日出会ったばかりで、互いの歩んできた道も、心の奥底も、まだ何も知らないに等しい。そんな真っ白な状況で、果たして彼を愛し、守り抜くと誓えるのだろうか。
喉の奥が乾き、答えに窮して俯いてしまう私を、お母様はじっと見つめ、静かに言葉を重ねた。
「即座に答えられないようでは、息子の婚約者として認めるわけにはいかないわね」
お母様の突き放すような一言に、視界が真っ白に染まった。
どうしよう。このままでは、神城さんの隣にいることさえ許されない。
焦れば焦るほど言葉は喉に張り付き、私はただ、救いを求めるように視線を泳がせることしかできなかった。
追い打ちをかけるように、今度はお父様が地を這うような低い声で問いを重ねる。
「……君は、なぜ竜馬の婚約者になったんだ?」
その峻烈な眼差しに射抜かれ、私はもはや飾る言葉も見つからず、心のままをありのままに吐き出した。
「神城さんが……私を、見つけてくださったからです」
その瞬間、室内の空気が凍りついたかのように、ご両親は揃って絶句した。
「つまり、ただ婚約を申し込まれたから、流されるままに承諾したと……そういうことか?」
お父様の表情は、先ほどよりもさらに険しく、底知れぬ圧を帯びていく。
確かに、客観的に見ればその通りかもしれない。始まりは、彼からの唐突な求婚だった。
でも、私はただ「流された」わけじゃない。
(違う……。理由がそれだけなら、私は今、ここにいない)
胸の奥で、小さな、けれど確かな想いが熱を帯びていた。
「違います! 私は……神城さんと、お互いに愛し、愛される存在になりたくて、婚約者になる道を選んだんです」
私はまだ、神城さんのことを何ひとつ知らないに等しい。
それでも、この人と共に歩み、幸せになりたいと――生まれて初めて、心の底からそう願ってしまったのだ。
私の剥き出しの本心が届いたのだろうか。張り詰めていた空気がふっと緩み、ご両親は顔を見合わせると、先ほどまでの厳格さが嘘のような、柔和な微笑みを私に向けた。
「そう……あなたはちゃんと、自分の意志で竜馬を想ってくれているのね」
「これからのあいつを、どうか頼む。末永く仲良くしてやってくれ」
その言葉に、ようやく理解した。お二人は私を試していたのだということを。
張り詰めていた糸が切れ、安堵から一気に肩の力が抜けてしまった。
「私の方こそ……認めてくださり、本当にありがとうございます。お父様、お母様」
これからの未来を預けてくださった感謝を込めて、私は再び深々と頭を下げた。すると、お母様が弾んだ声で私を制した。
「もうっ、玲花ちゃんったら! そんなに畏まらなくていいのよ。これからは気軽に『お母さん』って呼んでちょうだい!」
「えっ、ええと……お、お母さんっ」
「あらぁ! なんて可愛いのっ!!」
お母様の口調が、さっきまでとはまるで別人のような…… でも、最初の直感通り、本当はとても温かくて情に厚い方なのだと分かって胸が熱くなった。
この家なら、きっとすぐに馴染める。
そう確信して嬉しさが込み上げ、お母様と楽しく言葉を交わしていた、その時だった。
「……母さん、玲花をあまり困らせないでくれ」
背後から伸びてきた神城さんの腕が、私の肩を優しく、けれど独占するようにぐいっと抱き寄せた。
「母さん、父さん。玲花に自己紹介するのを忘れているぞ」
神城さんの呆れたような指摘に、お二人は「あっ!」と弾かれたように顔を見合わせた。
どうやら、お二人ともどこか抜けたところがあるのかもしれない……あはは。でも、その意外な人間味に思わず頬が緩んでしまう。
「ごめんなさいね! 念願の娘ができるって知って、舞い上がっちゃって。私は神城 凛よ。今日からよろしくね、玲花ちゃん!」
「私は神城家現当主、神城 紫苑だ。妻が騒がしくてすまないね。玲花さん、至らぬ息子だが、これからよろしく頼む」
先ほどまでの威厳はどこへやら、お二人は柔らかな微笑みを浮かべて一礼してくださった。
(良かった……。お二人とも、本当に温かくて素敵なお父様とお母様だ)
「はい! 私からも、これからどうぞよろしくお願いします」
こうして、私は神城家のご両親から正式に婚約者として認めていただくことができた。
これまで、実の家族とは決して結ぶことのできなかった絆。けれど、このお二人となら、何でも笑って話し合えるような、本当の「家族」になれるかもしれない。
心の底から、そう願わずにはいられなかった。
「さあ、遠慮しないでたくさん食べてね!」
婚約の挨拶を終え、すっかり打ち解けたお母様――凛さんと、今はお茶会の真っ最中だ。傍らには神城さんと紫苑さんの姿もあり、 和やかな時間が流れている。
お母様がテーブルを埋め尽くさんばかりに用意してくれたお菓子の山を前に、私は夢見心地で手を伸ばした。
実家にいた頃、お菓子はいつも目の毒でしかなかった。薫だけが優雅にティータイムを楽しむ姿を、私はただ遠くから羨望の眼差しで見つめるしかなかったのだ。いつしか「私には縁のないもの」と諦めていた甘い宝石たちが、今は私のために用意されている。
「……美味しい」
お母様が厳選したお菓子は、どれも頬が落ちそうなほど絶品で、芳醇な紅茶の香りと完璧に調和していた。
私が一口食べるごとに目を輝かせていると、お母様は嬉しそうに「これも、あれも」と次々に新しいお菓子を勧めてくれる。
その様子は、まるでお腹を空かせた雛にせっせと餌を運ぶ親ツバメのよう。
誰の目から見ても微笑ましく、愛に満ちたその光景に、私はかつて味わったことのない幸福を噛み締めていた。
楽しい時間は瞬く間に過ぎ、神城さんから「そろそろ休もうか」と声をかけられた。
ふと時計に目をやると、お茶会を始めてからいつの間にか二時間が経過している。心から満たされるひとときを過ごすと、時はこれほどまでに速く駆け抜けていくものなのだと、身を以て知った気がした。
名残惜しさはあったけれど、明日も学園がある。お母さんはよほど楽しんでくれたのか、「またお休みの日にやりましょうね」と、ひときわ明るい声で約束を交わしてくれた。
身支度を整え、ご両親に挨拶をしてから、神城さんに連れられて自室へと向かう。
改めて見渡す神城家の屋敷は、言葉を失うほど規格外の広さだった。
現代最強のあやかし一族と謳われる神城家。その居城とも呼べる屋敷は、私の実家の三倍はあろうかという壮麗な造りで、想像の限界を遥かに超えていた。
迷路のような廊下を神城さんの背中を追って歩き、ようやく部屋に辿り着いた時には、三分は経っていたのではないかと思うほどだ。
「ここが、君の部屋だ」
案内された室内は、ゆったりとしたソファやテーブルが設えられ、中央には吸い込まれそうなほど大きなベッドが鎮座していた。それでいて装飾は清楚で品が良く、初めて訪れた場所とは思えないほど、私の心にしっくりと馴染む落ち着いた空気に満ちていた。
「どうだ、玲花。気に入ってくれたか?」
神城さんは、私の反応を伺うように少し心配そうな面持ちで尋ねてきた。
「はい、とっても素敵です……!」
抑えきれない喜びが声に乗り、つい興奮気味に答えてしまう。私のそんな様子を見て、彼はようやく「よかった」と安堵したように胸を撫でおろした。
けれど、直後に猛烈な羞恥心がこみ上げてきた。私は逃げるように顔を俯かせる。
(恥ずかしい……。はしゃぎすぎて、はしたないって思われちゃったかな)
顔が火照り、耳の先まで赤くなっていくのが自分でも分かった。けれど、神城さんはそんな私を笑ったりせず、ただ温かな眼差しで見つめてくれていた。
「それじゃあ、また明日。今日は大変な一日だったからな、ゆっくり休んでくれ」
どこまでも優しい彼の気遣いが、心に染み渡る。
「はい。ありがとうございます。おやすみなさい、神城さん」
彼が部屋を出て、扉が静かに閉まる。その瞬間、私は吸い寄せられるように広大なベッドへと倒れ込んだ。
「……つ、疲れたぁ……」
今日一日を振り返れば、あまりに多くのことが起こりすぎた。神城さんからの突然の求婚に始まり、目まぐるしく変わっていく環境。今日からこの屋敷で暮らすことになったけれど、まだ夢の中にいるようで、実感が追いつかない。
(少しずつ、慣れていけばいいよね……)
心地よいシーツの感触に包まれながら、溜まりに溜まっていた疲労が重まぶたを押し下げていく。
視界の端で、鮮やかな青い蝶がひらひらと優雅に舞っている。
ここは……夢の中なのだろうか。
神城家の壮麗な屋敷とはまた違う、深く澄んだ夜空。そこには淡い月明かりが宿り、辺りを神秘的な光に染め上げていた。目の前に佇む一本の桜の木を、数多の青い蝶が囲むように舞う。まるで現世のものとは思えないほど幻想的な光景に、私は一瞬で心を奪われてしまった。
何かに導かれるように周囲を見渡すと、少し離れた場所に、見慣れた屋敷の影が立っていた。
(……あそこは、鬼龍院の本邸だわ)
長年過ごした家を、見間違えるはずがない。けれど、なぜ夢にまであの場所が出てくるのだろう。
戸惑いながらも屋敷の近くに立つ人影を凝視した瞬間、心臓が跳ねた。
そこにいたのは、亡くなった私のお母さんだった。
お母さんは私に気づくと、生前と変わらない、陽だまりのような優しく穏やかな笑顔を向けてくれる。
もしかして、私をこの場所に呼んだのはお母さんなの?
けれど、一体どうして――。
そう問いかけようとした、その時だった。
「―――――」
お母さんの唇がかすかに動き、何かを囁いている。
けれど、その声はあまりに小さく、夜の静寂(しじま)に溶けてしまってこちらまでは届かない。
「お母さん、今なんて――」
問いかけようと一歩踏み出した瞬間、突風とともに激しい桜吹雪が視界を遮った。
「わっ……!」
思わず腕で顔を覆い、固く目を閉じる。
数秒して風が止み、恐るおそる目を開けると、そこにはお母さんだけでなく、険しい表情をしたお父さんの姿もあった。
二人の腕の中には、布に包まれた小さな赤ん坊。
(あれは……私?)
赤ん坊の私を抱きかかえたお母さんは、必死の形相でお父さんに食い下がっていた。
「待ってください、樹様!!」
静寂を切り裂くような悲痛な叫び。お父さんを引き止めるお母さんの瞳には、これまでに見たこともないような決死の覚悟が宿っていた。
けれど、お父さんはお母さんを顧みることさえせず、冷徹な横顔のまま吐き捨てる。
「なんだ、菫。玲花のことで話すことなど、もう何一つない」
聞く耳持たぬと言わんばかりの、拒絶。
私は生まれたその瞬間から霊力を宿さず、この頃にはすでに「無能」の烙印を押されていたのだ。
「玲花には、霊力こそありません。けれど、この子にはきっと――」
母の必死の訴えも、父の苛立ちを募らせるだけだった。父は忌々しげに、まだ赤ん坊である私を鋭く射抜くように睨みつける。
「霊力を継承しなかった玲花に、一体何の価値がある。それ以外に、この家に必要なものなど何一つない」
非情な断定に、母は言葉を失い、絶望に身を震わせた。
それを見た父は、心底興味を失ったと言わんばかりに鼻で笑い、冷たく言い捨てる。
「もういい。そんな無能に構っている暇はない。私は薫のところへ行く」
母の心を踏みにじるような言葉を残し、父は背を向けて去っていった。
静まり返った庭に一人取り残された母は、腕の中の私を見つめ、今にも消え入りそうな声で、悲しみの色に染まった呟きを漏らした。
「ごめんね、玲花……。お母さんのせいで、あなたをこんなに苦しめてしまって……」
(いいえ、お母さん。謝らなきゃいけないのは、私の方だよ)
私が霊力を持って生まれなかったせいで、お母さんまで肩身の狭い思いをさせてしまった。
それなのに、お母さんは私に数えきれないほどの愛情を注いでくれた。
だから、自分を責めないで。
私はお母さんと一緒にいられるだけで、それだけで十分に幸せだったんだから。
けれど、届かぬ想いを虚空に残したまま、母は遠い目をして、さらに話を続けた。
「でもね、玲花。あなたには、本当は特別な力が宿っているのよ」
お母さんの口から飛び出した衝撃的な言葉に、私は理解が追いつかず、ただ呆然と立ち尽くした。
特別な……力?
そんなもの、あるはずがない。霊力を持たずに生まれた私は、あやかしたちが当たり前のように操る「能力」を何ひとつ使うことができない。今日まで「無能」として生きてきたことが、何よりの証拠だ。
けれど、お母さんの瞳は真っ直ぐに私を見つめ、確信に満ちた声を紡ぎ続ける。
「いい、玲花。あなたはあと数年もすれば――覚醒が訪れるわ」
途中の言葉は風の音にかき消され、聞き取ることができなかった。けれど、私の耳に「覚醒」という単語だけが、異様な重みを持って突き刺さる。
覚醒……。その言葉は一体、何を意味しているのだろう。
「だから、玲花……。お願い、どうかこの残酷な世界で、独りでも生き抜いて」
そう言って、お母さんの瞳から大粒の涙が零れ落ちる。
「お母さん!」
私はたまらず彼女のもとへ駆け寄ろうとした。けれど、行く手を阻むように再び猛烈な桜吹雪が吹き荒れる。
先ほどよりも遥かに激しい嵐に足元を掬われ、一歩も前に進むことができない。
「お母さん! 行かないで!」
喉が千切れんばかりに叫んだ私の声が届いたのか、お母さんは最後に一度だけこちらを振り返った。
その顔には、すべてを包み込むような、慈愛に満ちた微笑みが浮かんでいる。
必死に手を伸ばし、その温もりに触れようとしたけれど――。
「はっ……。ここは、自分の部屋……?」
弾かれたように上体を起こし、周囲を見渡す。そこにあるのは、昨日案内された神城家の、あの清楚で落ち着いた部屋だった。
本当に、不思議な夢だった。
赤ちゃんの頃の記憶なんてひとかけらもないのに、夢の中で触れた空気や母の涙は、恐ろしいほどに生々しく、熱を持っていた。
(お母さんが言っていた、あの言葉……)
『覚醒』。
肝心な前後の言葉は聞き取れなかったけれど、その単語だけが心臓の奥に深く突き刺さっている。
覚醒なんて、霊力を持たない私には縁のない言葉のはず。一体何が起きるというのか、あの断片的な会話だけではまるで見当もつかない。
「……また、お母さんに会えるかな」
もし次があるのなら、今度こそ逃さずに問いかけてみたい。
「玲花、起きたか?」
不意に部屋の外から神城さんの落ち着いた声が響き、私は思考を現実に引き戻された。
「はっ、はい! 今行きます!」
慌てて返事をして扉を開けると、そこにはすでに完璧に制服を着こなした神城さんが立っていた。朝の清廉な光を浴びる彼は、直視できないほどに神々しく、その圧倒的な美貌の破壊力に息が止まりそうになる。
(……朝からこれは、心臓がもたない。慣れるまでに相当な時間がかかりそう……)
私は高鳴る胸を抑えながら、自分も早く準備を整えようと、急いで制服に着替え始めた。
「おはよう、玲花ちゃん!」
リビングに足を踏み入れると、お母様が眩い笑顔で迎えてくれた。キッチンからは食欲をそそる香りが漂い、私のために朝食を支度してくれていたようだ。お父様は現当主としての職務のため、一足先に仕事へ向かったという。
今日から「神城竜馬の婚約者」として学園へ通う――。その事実は、誇らしさよりも底知れない不安を私に抱かせた。
神城家の重厚な車に揺られ、学園へと向かう車内。
「緊張しているのか?」
隣に座る神城さんの問いに、私は小さくコクリと頷いた。脳裏には、昨日の婚約宣告の際に向けられた、射抜くような憎悪の眼差しが焼き付いて離れない。
私の強張った様子を察したのか、神城さんはそっと、けれど力強く私の手を握りしめた。
「大丈夫だ。玲花に手を出した者は、二度と日の目を見られないようにしてやるから」
春の陽だまりのような微笑みを浮かべながら、背筋が凍るような台詞を口にする神城さん。私はただ、引き攣ったような苦笑いを返すことしかできなかった。昨日、私の家族にも同じような脅しをかけていたけれど……きっと、冗談に違いない。そもそも、私という人間にそこまでしてもらう価値なんて、あるはずがないのだから。
けれど、彼の掌の温もりは、確実に私の不安を溶かしていった。
「ありがとうございます、神城さん」
この人が隣にいてくれるのなら、どんな荒波も越えていけるかもしれない。そんな淡い期待が胸に灯る。
やがて学園に到着し、神城さんにエスコートされながら車を降りる。
その瞬間、登校中の生徒たちの視線が一斉にこちらへ突き刺さり、校門前は、まるで時が止まったかのような静寂と驚愕に包み込まれた。
「あれって神城様……!? 隣にいるの、本当にあの鬼龍院の無能なの!?」
「嘘でしょ、本当に婚約者にするなんて信じられない……」
校門をくぐった瞬間、辺りは蜂の巣をつついたような騒ぎになった。
困惑のさざめきに混じって、鋭い刃のような悪意が私の鼓膜を突き刺す。
「どうせ、あんな無能が選ばれるなんて……汚い手でも使って神城様をたぶらかしたに決まってるわ」
「あり得ない。どうせ一時の気まぐれよ。すぐに捨てられて婚約破棄されるのがオチね」
その言葉が聞こえた瞬間、隣を歩く神城さんの体温が、一気に零度まで下がった気がした。
恐る恐る隣を見上げると、そこには美しい顔を般若のように歪ませ、今にもその生徒たちを噛み殺しそうな形相で睨みつける彼の姿があった。
「……あの連中、今すぐこの世から消してしまおうか」
低く、地を這うような死神の囁き。冗談には聞こえないその響きに、私は血の気が引く思いで慌てて彼の腕に縋りついた。
「だ、大丈夫ですから! 神城さんがこうして側にいてくれるだけで、私は十分なんです! ほら、行きましょう、神城さん!」
必死の説得が届いたのか、神城さんは私を見つめると、先ほどまでの殺気が嘘のような、とろけるほど甘く柔らかな表情へと一変した。
「……そうか。玲花がそこまで言うなら、今は堪えよう。だが、もし何かあればいつでも俺の名前を呼べ。いいな?」
「は、はい……分かりましたっ」
神城さんのあまりの豹変ぶりに戸惑いながらも、ひとまずはクラスメイトたちの命(?)の危機を回避できたことに、私は胸をなでおろした。
それから、神城さんはわざわざ教室の前まで送ってくれてから自分の教室へ向かった。
神城さんは二年生だから学園では離れてしまう。
教室に入ると皆さん、私を好奇的な目で見つめてくる。
「玲花さんだ。まさか本当に神城様の婚約者に選ばれるなんてっ」
「凄いよね。でも、これでCクラスの虐めも少しは減るんじゃない?」
まさか一日でこれ程、評価が変わるなんて。
周囲の羨望のまなざしが、今の私には何より痛い。
神城さんという輝かしい方の隣に、無能な私が立つ。それがどれほど彼に泥を塗る行為か、皆さんは分かっていない。
喜ぶべきことなのに、胸にあるのは祝福への感謝ではなく、彼を貶めてしまうことへの申し訳なさばかりだった。
皆さんは羨ましいって言うけど、私には到底喜べない。
神城さんの隣に私が並ぶのは、彼にとってマイナスでしかないから。
私みたいな無能が、彼の評価を汚してしまう……そう思うと、ただただ苦しいだけだった。
はぁっと誰にも気付かれないようにため息を吐いた。
そんな時だった。
「おはよう!玲花ちゃん!!」
大きな声が聞こえて振り返ると唯一の友達である冬美が抱きついてきた。
「冬美!おはよう」
「聞いたよ、玲花ちゃん!!あの、神城さんの婚約者になったなんてすごいじゃん!!」
「そう、かな」
「どうしたの? なんか元気がなさそうだけど……悩み事があるなら私が聞くよ!」
冬美の真っ直ぐな優しさに、凍えていた胸がじんわりと解けていく。「冬美と友達で本当に良かった」――心の底からそう実感した。
「実はね……」
震える声で、私は自分の内側を語り始めた。誰かに心の内をさらけ出すのは初めてで、拒絶されるのが怖くて指先が震えたけれど、冬美は一言も挟まず、真剣な眼差しで私の言葉を拾い集めてくれた。
話し終えた瞬間、視界が少し明るくなった気がした。「誰かに頼る」という選択肢が、これほど自分を楽にしてくれるなんて。
語り終えた私に、冬美は深く頷き、私の心に寄り添った確かな答えを返してくれた。
「確かに、霊力の差はどうしようもない事実かもしれない」
「やっぱり、そうだよね……」
「でもね、玲花ちゃんは誰よりも優しくて気遣いができる。頭だってすごく良いじゃない。なら、その強みを使って神城さんの支えになればいい。それって立派な役割だよ」
「でも、それだけじゃ私の存在価値なんて……」
「それでいいんだよ。人は誰だって完璧じゃない。神城さんにだって不得意なことや、誰にも言えない悩みがあるはず。だからこそ、二人の得意なことで補い合えばいいんだよ」
「冬美……」
その言葉が、暗く沈んでいた私の心に一筋の光を投げかけた。
ずっと「足りないもの」ばかり数えていたけれど、私にも彼に差し出せるものがあるのかもしれない。冬美の真っ直ぐな言葉に、ようやく深く長い眠りから呼び覚まされたような心地がした。
神城さんの支えになる。そんな大それたこと、今の私にはまだ夢物語かもしれない。
霊力のなさはどうしようもないけれど、それ以外の場所でなら、いつか彼の役に立てる日が来るかもしれない。
誰も認めてくれなくていい。ただ、彼にとって少しでも意味のある存在になれたなら。
密かな、けれど確かな決意を瞳に宿すと、冬美が包み込むような笑顔を見せてくれた。
「その様子なら、もう心配いらないかな」
「うん……冬美、本当にありがとう」
親友に背中を押してもらうことが、これほど救いになるなんて。重く沈んでいた心が、今は驚くほど軽やかだった。
悩みが晴れたとはいえ、まだ何も成し遂げたわけではない。
けれど、この学園で学び、自分を磨き、いつか胸を張って神城さんの隣に立ちたい。
空っぽだった私の学園生活に、今、鮮やかな「目標」と「希望」が宿った。
ようやく「生きる理由」を見つけた気がした。
自分の存在を憎むことしかできなかった灰色の人生。
そんな私の世界に光を灯してくれたのは、紛れもなく彼だった。
―これから先、私は多くの喜びを噛み締め、時に痛みを知り、そして本当の「愛」を知っていくことになる。
運命の歯車が、静かに、けれど力強く回り出す。
――それは、遠くない未来に綴られる、新しい物語
私は今、まさに正念場に立たされている。
「この子が、竜馬の婚約者なのね……」
目の前にいらっしゃる神城さんのご両親へ、挨拶をしている最中だった。
急遽、神城さんのお屋敷で暮らすことになったものの、目まぐるしく変わる現実に私の心は全く追いついていない。 呆然とする間もなく、こうして神城家の当主夫妻と対面することになってしまったのだ。
つい先ほど、実家で嵐のような婚約報告を済ませたばかりなのに。
このスピード感には困惑を通り越して目眩すら覚えるが、今の私にはそれ以上に切実な悩みがあった。
(神城さんのご両親に、婚約者として認めてもらえるだろうか……)
私はあやかし界では名を知られた存在だ。もちろん、最悪の意味で。
物心ついた時から「鬼龍院の無能」と蔑まれ、家族や一族のみならず、多くのあやかしから忌み嫌われて生きてきた。
そんな、誰からも望まれない無能な娘が、あろうことか一族の誇りである息子の隣に立つ。親であれば、到底許しがたい不名誉に感じるはずだ。
「両親は優しいから、きっと認めてくれる」
神城さんはそう言って私を励ましてくれたけれど、とてもそうは思えなかった。
彼の言葉を疑っているわけではない。ただ、私はこれまでの人生で「愛される」という経験をあまりにも知らなすぎた。
これでもかというほど嫌われ、拒絶される痛みに慣れきってしまった私の心は、神城さんのご両親までもが私を冷たく突き放す光景を、勝手に描き出してしまう。
不安と恐怖で指先まで氷のように冷たくなり、体はカチコチに強張ったまま、ただ運命の裁定を待つことしかできなかった。
しかし、時間はすぐに過ぎていくもので、あっという間にご両親と対面することとなった。
神城家の使用人に案内された部屋に入るとそこには二人の男女がいた。
(この人達が神城さんの両親……)
お母様は、どこか亡き母を彷彿とさせる慈愛に満ちた美貌の持ち主。対して、お父様は彫刻のように峻厳な面持ちで、現当主としての圧倒的な霊圧が、肌を刺すような威圧感となって部屋を満たしている。
二人は私を一瞥した瞬間、わずかに目を見開いた。けれど、すぐに冷徹なほど凪いだ表情に戻り、私の目の前へと歩み寄る。
「あなたが、竜馬の連れてきた玲花さんね」
お母様の声は、先ほどまでの柔らかな空気とは一変し、氷のような冷ややかさを帯びていた。
(やっぱり……歓迎なんて、されていないんだ)
逃げ出したいほどの不安に襲われ、背中を冷たい汗が伝う。
「は、初めまして……。鬼龍院 玲花と申します……っ」
声の震えを必死に抑え、持てる限りの勇気を振り絞って深々と頭を下げた。
そんな私の痛々しい姿を値踏みするように見つめ、お母様は小さく、けれど重みのある溜息を吐いた。
「まさか、こんな子が息子の婚約者だなんてね……」
突き放すような言葉に、私の心臓はさらに激しく脈打つ。
お母様は鋭く、射抜くような真剣な眼差しに変わり、私に問いを突きつけた。
「ねぇ、玲花さん。あなたは、本気でうちの息子を一生大事にできるの?」
その問いに、私は石のように硬直してしまった。
神城さんを、大事に……。
私たちは今日出会ったばかりで、互いの歩んできた道も、心の奥底も、まだ何も知らないに等しい。そんな真っ白な状況で、果たして彼を愛し、守り抜くと誓えるのだろうか。
喉の奥が乾き、答えに窮して俯いてしまう私を、お母様はじっと見つめ、静かに言葉を重ねた。
「即座に答えられないようでは、息子の婚約者として認めるわけにはいかないわね」
お母様の突き放すような一言に、視界が真っ白に染まった。
どうしよう。このままでは、神城さんの隣にいることさえ許されない。
焦れば焦るほど言葉は喉に張り付き、私はただ、救いを求めるように視線を泳がせることしかできなかった。
追い打ちをかけるように、今度はお父様が地を這うような低い声で問いを重ねる。
「……君は、なぜ竜馬の婚約者になったんだ?」
その峻烈な眼差しに射抜かれ、私はもはや飾る言葉も見つからず、心のままをありのままに吐き出した。
「神城さんが……私を、見つけてくださったからです」
その瞬間、室内の空気が凍りついたかのように、ご両親は揃って絶句した。
「つまり、ただ婚約を申し込まれたから、流されるままに承諾したと……そういうことか?」
お父様の表情は、先ほどよりもさらに険しく、底知れぬ圧を帯びていく。
確かに、客観的に見ればその通りかもしれない。始まりは、彼からの唐突な求婚だった。
でも、私はただ「流された」わけじゃない。
(違う……。理由がそれだけなら、私は今、ここにいない)
胸の奥で、小さな、けれど確かな想いが熱を帯びていた。
「違います! 私は……神城さんと、お互いに愛し、愛される存在になりたくて、婚約者になる道を選んだんです」
私はまだ、神城さんのことを何ひとつ知らないに等しい。
それでも、この人と共に歩み、幸せになりたいと――生まれて初めて、心の底からそう願ってしまったのだ。
私の剥き出しの本心が届いたのだろうか。張り詰めていた空気がふっと緩み、ご両親は顔を見合わせると、先ほどまでの厳格さが嘘のような、柔和な微笑みを私に向けた。
「そう……あなたはちゃんと、自分の意志で竜馬を想ってくれているのね」
「これからのあいつを、どうか頼む。末永く仲良くしてやってくれ」
その言葉に、ようやく理解した。お二人は私を試していたのだということを。
張り詰めていた糸が切れ、安堵から一気に肩の力が抜けてしまった。
「私の方こそ……認めてくださり、本当にありがとうございます。お父様、お母様」
これからの未来を預けてくださった感謝を込めて、私は再び深々と頭を下げた。すると、お母様が弾んだ声で私を制した。
「もうっ、玲花ちゃんったら! そんなに畏まらなくていいのよ。これからは気軽に『お母さん』って呼んでちょうだい!」
「えっ、ええと……お、お母さんっ」
「あらぁ! なんて可愛いのっ!!」
お母様の口調が、さっきまでとはまるで別人のような…… でも、最初の直感通り、本当はとても温かくて情に厚い方なのだと分かって胸が熱くなった。
この家なら、きっとすぐに馴染める。
そう確信して嬉しさが込み上げ、お母様と楽しく言葉を交わしていた、その時だった。
「……母さん、玲花をあまり困らせないでくれ」
背後から伸びてきた神城さんの腕が、私の肩を優しく、けれど独占するようにぐいっと抱き寄せた。
「母さん、父さん。玲花に自己紹介するのを忘れているぞ」
神城さんの呆れたような指摘に、お二人は「あっ!」と弾かれたように顔を見合わせた。
どうやら、お二人ともどこか抜けたところがあるのかもしれない……あはは。でも、その意外な人間味に思わず頬が緩んでしまう。
「ごめんなさいね! 念願の娘ができるって知って、舞い上がっちゃって。私は神城 凛よ。今日からよろしくね、玲花ちゃん!」
「私は神城家現当主、神城 紫苑だ。妻が騒がしくてすまないね。玲花さん、至らぬ息子だが、これからよろしく頼む」
先ほどまでの威厳はどこへやら、お二人は柔らかな微笑みを浮かべて一礼してくださった。
(良かった……。お二人とも、本当に温かくて素敵なお父様とお母様だ)
「はい! 私からも、これからどうぞよろしくお願いします」
こうして、私は神城家のご両親から正式に婚約者として認めていただくことができた。
これまで、実の家族とは決して結ぶことのできなかった絆。けれど、このお二人となら、何でも笑って話し合えるような、本当の「家族」になれるかもしれない。
心の底から、そう願わずにはいられなかった。
「さあ、遠慮しないでたくさん食べてね!」
婚約の挨拶を終え、すっかり打ち解けたお母様――凛さんと、今はお茶会の真っ最中だ。傍らには神城さんと紫苑さんの姿もあり、 和やかな時間が流れている。
お母様がテーブルを埋め尽くさんばかりに用意してくれたお菓子の山を前に、私は夢見心地で手を伸ばした。
実家にいた頃、お菓子はいつも目の毒でしかなかった。薫だけが優雅にティータイムを楽しむ姿を、私はただ遠くから羨望の眼差しで見つめるしかなかったのだ。いつしか「私には縁のないもの」と諦めていた甘い宝石たちが、今は私のために用意されている。
「……美味しい」
お母様が厳選したお菓子は、どれも頬が落ちそうなほど絶品で、芳醇な紅茶の香りと完璧に調和していた。
私が一口食べるごとに目を輝かせていると、お母様は嬉しそうに「これも、あれも」と次々に新しいお菓子を勧めてくれる。
その様子は、まるでお腹を空かせた雛にせっせと餌を運ぶ親ツバメのよう。
誰の目から見ても微笑ましく、愛に満ちたその光景に、私はかつて味わったことのない幸福を噛み締めていた。
楽しい時間は瞬く間に過ぎ、神城さんから「そろそろ休もうか」と声をかけられた。
ふと時計に目をやると、お茶会を始めてからいつの間にか二時間が経過している。心から満たされるひとときを過ごすと、時はこれほどまでに速く駆け抜けていくものなのだと、身を以て知った気がした。
名残惜しさはあったけれど、明日も学園がある。お母さんはよほど楽しんでくれたのか、「またお休みの日にやりましょうね」と、ひときわ明るい声で約束を交わしてくれた。
身支度を整え、ご両親に挨拶をしてから、神城さんに連れられて自室へと向かう。
改めて見渡す神城家の屋敷は、言葉を失うほど規格外の広さだった。
現代最強のあやかし一族と謳われる神城家。その居城とも呼べる屋敷は、私の実家の三倍はあろうかという壮麗な造りで、想像の限界を遥かに超えていた。
迷路のような廊下を神城さんの背中を追って歩き、ようやく部屋に辿り着いた時には、三分は経っていたのではないかと思うほどだ。
「ここが、君の部屋だ」
案内された室内は、ゆったりとしたソファやテーブルが設えられ、中央には吸い込まれそうなほど大きなベッドが鎮座していた。それでいて装飾は清楚で品が良く、初めて訪れた場所とは思えないほど、私の心にしっくりと馴染む落ち着いた空気に満ちていた。
「どうだ、玲花。気に入ってくれたか?」
神城さんは、私の反応を伺うように少し心配そうな面持ちで尋ねてきた。
「はい、とっても素敵です……!」
抑えきれない喜びが声に乗り、つい興奮気味に答えてしまう。私のそんな様子を見て、彼はようやく「よかった」と安堵したように胸を撫でおろした。
けれど、直後に猛烈な羞恥心がこみ上げてきた。私は逃げるように顔を俯かせる。
(恥ずかしい……。はしゃぎすぎて、はしたないって思われちゃったかな)
顔が火照り、耳の先まで赤くなっていくのが自分でも分かった。けれど、神城さんはそんな私を笑ったりせず、ただ温かな眼差しで見つめてくれていた。
「それじゃあ、また明日。今日は大変な一日だったからな、ゆっくり休んでくれ」
どこまでも優しい彼の気遣いが、心に染み渡る。
「はい。ありがとうございます。おやすみなさい、神城さん」
彼が部屋を出て、扉が静かに閉まる。その瞬間、私は吸い寄せられるように広大なベッドへと倒れ込んだ。
「……つ、疲れたぁ……」
今日一日を振り返れば、あまりに多くのことが起こりすぎた。神城さんからの突然の求婚に始まり、目まぐるしく変わっていく環境。今日からこの屋敷で暮らすことになったけれど、まだ夢の中にいるようで、実感が追いつかない。
(少しずつ、慣れていけばいいよね……)
心地よいシーツの感触に包まれながら、溜まりに溜まっていた疲労が重まぶたを押し下げていく。
視界の端で、鮮やかな青い蝶がひらひらと優雅に舞っている。
ここは……夢の中なのだろうか。
神城家の壮麗な屋敷とはまた違う、深く澄んだ夜空。そこには淡い月明かりが宿り、辺りを神秘的な光に染め上げていた。目の前に佇む一本の桜の木を、数多の青い蝶が囲むように舞う。まるで現世のものとは思えないほど幻想的な光景に、私は一瞬で心を奪われてしまった。
何かに導かれるように周囲を見渡すと、少し離れた場所に、見慣れた屋敷の影が立っていた。
(……あそこは、鬼龍院の本邸だわ)
長年過ごした家を、見間違えるはずがない。けれど、なぜ夢にまであの場所が出てくるのだろう。
戸惑いながらも屋敷の近くに立つ人影を凝視した瞬間、心臓が跳ねた。
そこにいたのは、亡くなった私のお母さんだった。
お母さんは私に気づくと、生前と変わらない、陽だまりのような優しく穏やかな笑顔を向けてくれる。
もしかして、私をこの場所に呼んだのはお母さんなの?
けれど、一体どうして――。
そう問いかけようとした、その時だった。
「―――――」
お母さんの唇がかすかに動き、何かを囁いている。
けれど、その声はあまりに小さく、夜の静寂(しじま)に溶けてしまってこちらまでは届かない。
「お母さん、今なんて――」
問いかけようと一歩踏み出した瞬間、突風とともに激しい桜吹雪が視界を遮った。
「わっ……!」
思わず腕で顔を覆い、固く目を閉じる。
数秒して風が止み、恐るおそる目を開けると、そこにはお母さんだけでなく、険しい表情をしたお父さんの姿もあった。
二人の腕の中には、布に包まれた小さな赤ん坊。
(あれは……私?)
赤ん坊の私を抱きかかえたお母さんは、必死の形相でお父さんに食い下がっていた。
「待ってください、樹様!!」
静寂を切り裂くような悲痛な叫び。お父さんを引き止めるお母さんの瞳には、これまでに見たこともないような決死の覚悟が宿っていた。
けれど、お父さんはお母さんを顧みることさえせず、冷徹な横顔のまま吐き捨てる。
「なんだ、菫。玲花のことで話すことなど、もう何一つない」
聞く耳持たぬと言わんばかりの、拒絶。
私は生まれたその瞬間から霊力を宿さず、この頃にはすでに「無能」の烙印を押されていたのだ。
「玲花には、霊力こそありません。けれど、この子にはきっと――」
母の必死の訴えも、父の苛立ちを募らせるだけだった。父は忌々しげに、まだ赤ん坊である私を鋭く射抜くように睨みつける。
「霊力を継承しなかった玲花に、一体何の価値がある。それ以外に、この家に必要なものなど何一つない」
非情な断定に、母は言葉を失い、絶望に身を震わせた。
それを見た父は、心底興味を失ったと言わんばかりに鼻で笑い、冷たく言い捨てる。
「もういい。そんな無能に構っている暇はない。私は薫のところへ行く」
母の心を踏みにじるような言葉を残し、父は背を向けて去っていった。
静まり返った庭に一人取り残された母は、腕の中の私を見つめ、今にも消え入りそうな声で、悲しみの色に染まった呟きを漏らした。
「ごめんね、玲花……。お母さんのせいで、あなたをこんなに苦しめてしまって……」
(いいえ、お母さん。謝らなきゃいけないのは、私の方だよ)
私が霊力を持って生まれなかったせいで、お母さんまで肩身の狭い思いをさせてしまった。
それなのに、お母さんは私に数えきれないほどの愛情を注いでくれた。
だから、自分を責めないで。
私はお母さんと一緒にいられるだけで、それだけで十分に幸せだったんだから。
けれど、届かぬ想いを虚空に残したまま、母は遠い目をして、さらに話を続けた。
「でもね、玲花。あなたには、本当は特別な力が宿っているのよ」
お母さんの口から飛び出した衝撃的な言葉に、私は理解が追いつかず、ただ呆然と立ち尽くした。
特別な……力?
そんなもの、あるはずがない。霊力を持たずに生まれた私は、あやかしたちが当たり前のように操る「能力」を何ひとつ使うことができない。今日まで「無能」として生きてきたことが、何よりの証拠だ。
けれど、お母さんの瞳は真っ直ぐに私を見つめ、確信に満ちた声を紡ぎ続ける。
「いい、玲花。あなたはあと数年もすれば――覚醒が訪れるわ」
途中の言葉は風の音にかき消され、聞き取ることができなかった。けれど、私の耳に「覚醒」という単語だけが、異様な重みを持って突き刺さる。
覚醒……。その言葉は一体、何を意味しているのだろう。
「だから、玲花……。お願い、どうかこの残酷な世界で、独りでも生き抜いて」
そう言って、お母さんの瞳から大粒の涙が零れ落ちる。
「お母さん!」
私はたまらず彼女のもとへ駆け寄ろうとした。けれど、行く手を阻むように再び猛烈な桜吹雪が吹き荒れる。
先ほどよりも遥かに激しい嵐に足元を掬われ、一歩も前に進むことができない。
「お母さん! 行かないで!」
喉が千切れんばかりに叫んだ私の声が届いたのか、お母さんは最後に一度だけこちらを振り返った。
その顔には、すべてを包み込むような、慈愛に満ちた微笑みが浮かんでいる。
必死に手を伸ばし、その温もりに触れようとしたけれど――。
「はっ……。ここは、自分の部屋……?」
弾かれたように上体を起こし、周囲を見渡す。そこにあるのは、昨日案内された神城家の、あの清楚で落ち着いた部屋だった。
本当に、不思議な夢だった。
赤ちゃんの頃の記憶なんてひとかけらもないのに、夢の中で触れた空気や母の涙は、恐ろしいほどに生々しく、熱を持っていた。
(お母さんが言っていた、あの言葉……)
『覚醒』。
肝心な前後の言葉は聞き取れなかったけれど、その単語だけが心臓の奥に深く突き刺さっている。
覚醒なんて、霊力を持たない私には縁のない言葉のはず。一体何が起きるというのか、あの断片的な会話だけではまるで見当もつかない。
「……また、お母さんに会えるかな」
もし次があるのなら、今度こそ逃さずに問いかけてみたい。
「玲花、起きたか?」
不意に部屋の外から神城さんの落ち着いた声が響き、私は思考を現実に引き戻された。
「はっ、はい! 今行きます!」
慌てて返事をして扉を開けると、そこにはすでに完璧に制服を着こなした神城さんが立っていた。朝の清廉な光を浴びる彼は、直視できないほどに神々しく、その圧倒的な美貌の破壊力に息が止まりそうになる。
(……朝からこれは、心臓がもたない。慣れるまでに相当な時間がかかりそう……)
私は高鳴る胸を抑えながら、自分も早く準備を整えようと、急いで制服に着替え始めた。
「おはよう、玲花ちゃん!」
リビングに足を踏み入れると、お母様が眩い笑顔で迎えてくれた。キッチンからは食欲をそそる香りが漂い、私のために朝食を支度してくれていたようだ。お父様は現当主としての職務のため、一足先に仕事へ向かったという。
今日から「神城竜馬の婚約者」として学園へ通う――。その事実は、誇らしさよりも底知れない不安を私に抱かせた。
神城家の重厚な車に揺られ、学園へと向かう車内。
「緊張しているのか?」
隣に座る神城さんの問いに、私は小さくコクリと頷いた。脳裏には、昨日の婚約宣告の際に向けられた、射抜くような憎悪の眼差しが焼き付いて離れない。
私の強張った様子を察したのか、神城さんはそっと、けれど力強く私の手を握りしめた。
「大丈夫だ。玲花に手を出した者は、二度と日の目を見られないようにしてやるから」
春の陽だまりのような微笑みを浮かべながら、背筋が凍るような台詞を口にする神城さん。私はただ、引き攣ったような苦笑いを返すことしかできなかった。昨日、私の家族にも同じような脅しをかけていたけれど……きっと、冗談に違いない。そもそも、私という人間にそこまでしてもらう価値なんて、あるはずがないのだから。
けれど、彼の掌の温もりは、確実に私の不安を溶かしていった。
「ありがとうございます、神城さん」
この人が隣にいてくれるのなら、どんな荒波も越えていけるかもしれない。そんな淡い期待が胸に灯る。
やがて学園に到着し、神城さんにエスコートされながら車を降りる。
その瞬間、登校中の生徒たちの視線が一斉にこちらへ突き刺さり、校門前は、まるで時が止まったかのような静寂と驚愕に包み込まれた。
「あれって神城様……!? 隣にいるの、本当にあの鬼龍院の無能なの!?」
「嘘でしょ、本当に婚約者にするなんて信じられない……」
校門をくぐった瞬間、辺りは蜂の巣をつついたような騒ぎになった。
困惑のさざめきに混じって、鋭い刃のような悪意が私の鼓膜を突き刺す。
「どうせ、あんな無能が選ばれるなんて……汚い手でも使って神城様をたぶらかしたに決まってるわ」
「あり得ない。どうせ一時の気まぐれよ。すぐに捨てられて婚約破棄されるのがオチね」
その言葉が聞こえた瞬間、隣を歩く神城さんの体温が、一気に零度まで下がった気がした。
恐る恐る隣を見上げると、そこには美しい顔を般若のように歪ませ、今にもその生徒たちを噛み殺しそうな形相で睨みつける彼の姿があった。
「……あの連中、今すぐこの世から消してしまおうか」
低く、地を這うような死神の囁き。冗談には聞こえないその響きに、私は血の気が引く思いで慌てて彼の腕に縋りついた。
「だ、大丈夫ですから! 神城さんがこうして側にいてくれるだけで、私は十分なんです! ほら、行きましょう、神城さん!」
必死の説得が届いたのか、神城さんは私を見つめると、先ほどまでの殺気が嘘のような、とろけるほど甘く柔らかな表情へと一変した。
「……そうか。玲花がそこまで言うなら、今は堪えよう。だが、もし何かあればいつでも俺の名前を呼べ。いいな?」
「は、はい……分かりましたっ」
神城さんのあまりの豹変ぶりに戸惑いながらも、ひとまずはクラスメイトたちの命(?)の危機を回避できたことに、私は胸をなでおろした。
それから、神城さんはわざわざ教室の前まで送ってくれてから自分の教室へ向かった。
神城さんは二年生だから学園では離れてしまう。
教室に入ると皆さん、私を好奇的な目で見つめてくる。
「玲花さんだ。まさか本当に神城様の婚約者に選ばれるなんてっ」
「凄いよね。でも、これでCクラスの虐めも少しは減るんじゃない?」
まさか一日でこれ程、評価が変わるなんて。
周囲の羨望のまなざしが、今の私には何より痛い。
神城さんという輝かしい方の隣に、無能な私が立つ。それがどれほど彼に泥を塗る行為か、皆さんは分かっていない。
喜ぶべきことなのに、胸にあるのは祝福への感謝ではなく、彼を貶めてしまうことへの申し訳なさばかりだった。
皆さんは羨ましいって言うけど、私には到底喜べない。
神城さんの隣に私が並ぶのは、彼にとってマイナスでしかないから。
私みたいな無能が、彼の評価を汚してしまう……そう思うと、ただただ苦しいだけだった。
はぁっと誰にも気付かれないようにため息を吐いた。
そんな時だった。
「おはよう!玲花ちゃん!!」
大きな声が聞こえて振り返ると唯一の友達である冬美が抱きついてきた。
「冬美!おはよう」
「聞いたよ、玲花ちゃん!!あの、神城さんの婚約者になったなんてすごいじゃん!!」
「そう、かな」
「どうしたの? なんか元気がなさそうだけど……悩み事があるなら私が聞くよ!」
冬美の真っ直ぐな優しさに、凍えていた胸がじんわりと解けていく。「冬美と友達で本当に良かった」――心の底からそう実感した。
「実はね……」
震える声で、私は自分の内側を語り始めた。誰かに心の内をさらけ出すのは初めてで、拒絶されるのが怖くて指先が震えたけれど、冬美は一言も挟まず、真剣な眼差しで私の言葉を拾い集めてくれた。
話し終えた瞬間、視界が少し明るくなった気がした。「誰かに頼る」という選択肢が、これほど自分を楽にしてくれるなんて。
語り終えた私に、冬美は深く頷き、私の心に寄り添った確かな答えを返してくれた。
「確かに、霊力の差はどうしようもない事実かもしれない」
「やっぱり、そうだよね……」
「でもね、玲花ちゃんは誰よりも優しくて気遣いができる。頭だってすごく良いじゃない。なら、その強みを使って神城さんの支えになればいい。それって立派な役割だよ」
「でも、それだけじゃ私の存在価値なんて……」
「それでいいんだよ。人は誰だって完璧じゃない。神城さんにだって不得意なことや、誰にも言えない悩みがあるはず。だからこそ、二人の得意なことで補い合えばいいんだよ」
「冬美……」
その言葉が、暗く沈んでいた私の心に一筋の光を投げかけた。
ずっと「足りないもの」ばかり数えていたけれど、私にも彼に差し出せるものがあるのかもしれない。冬美の真っ直ぐな言葉に、ようやく深く長い眠りから呼び覚まされたような心地がした。
神城さんの支えになる。そんな大それたこと、今の私にはまだ夢物語かもしれない。
霊力のなさはどうしようもないけれど、それ以外の場所でなら、いつか彼の役に立てる日が来るかもしれない。
誰も認めてくれなくていい。ただ、彼にとって少しでも意味のある存在になれたなら。
密かな、けれど確かな決意を瞳に宿すと、冬美が包み込むような笑顔を見せてくれた。
「その様子なら、もう心配いらないかな」
「うん……冬美、本当にありがとう」
親友に背中を押してもらうことが、これほど救いになるなんて。重く沈んでいた心が、今は驚くほど軽やかだった。
悩みが晴れたとはいえ、まだ何も成し遂げたわけではない。
けれど、この学園で学び、自分を磨き、いつか胸を張って神城さんの隣に立ちたい。
空っぽだった私の学園生活に、今、鮮やかな「目標」と「希望」が宿った。
ようやく「生きる理由」を見つけた気がした。
自分の存在を憎むことしかできなかった灰色の人生。
そんな私の世界に光を灯してくれたのは、紛れもなく彼だった。
―これから先、私は多くの喜びを噛み締め、時に痛みを知り、そして本当の「愛」を知っていくことになる。
運命の歯車が、静かに、けれど力強く回り出す。
――それは、遠くない未来に綴られる、新しい物語