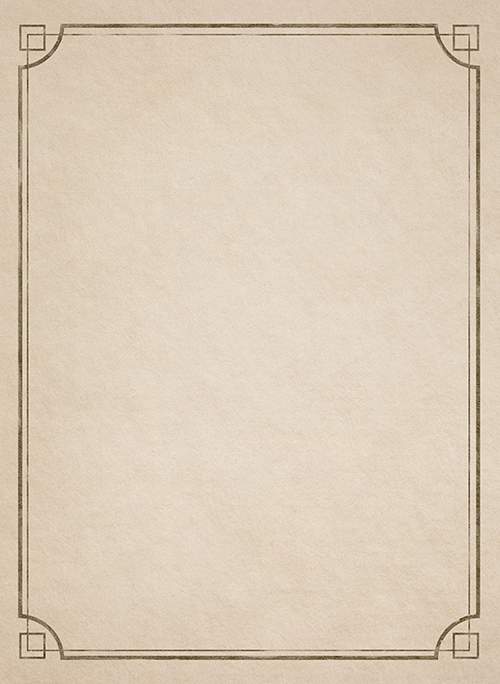3章
昨日から、日本随一の名門校・エトワール学園での日々が始まった。
そして今日は、待ちに待った初めての授業。
胸の奥が少しだけきゅっと震えるような緊張はあるけれど、それ以上に、抑えきれない高揚感が全身を満たしている。
日本トップクラスの秀才が集うこの学園の講義は、並大抵の難易度ではないと聞き及んでいた。
けれど、だからこそ、そこで教鞭を執る先生方もまた、当代随一の知性を誇る人達ばかり。
入学が決まるずっと前から、私はこの学園の教壇から放たれる「知の輝き」に、強い憧れを抱き続けてきたのだ。
昨夜からずっと、この瞬間を心待ちにしていた。
これから始まる未知なる学びへの期待に、私は静かに胸を躍らせている。
学園に着いて教室の中に入る。
早く着いてしまったのか、教室には誰も居なかった。
「まだHRまで時間があるし……図書館にでも行こうかな?」
昨日入学したばかりだというのに、私は早くもこの学園の図書館に心を奪われてしまった。
名門校の威信を象徴するかのようなその場所は、圧倒的な広さと奥行きを誇っている。内装はまるで外国の古城を彷彿とさせる意匠で統一されており、どこかロマンチックな情趣が漂っていた。
けれど、私が何よりもこの場所に心惹かれた理由は、その外観以上に、視界を埋め尽くす圧倒的な蔵書の数だった。
昨日は時間に余裕がなく、一冊しか読むことが出来なかった。
でも、読みたい本がまだまだ山のようにある。
私は荷物を速やかに教室に置き、図書館に向かった。
暫くは図書館で本を読み、楽しい時間を過ごした。
HRの三十分前の予鈴が鳴り、私は教室に戻った。
私が姿を現したその瞬間、教室の空気が一変した。
まるで示し合わせたかのように、クラスメイトたちの冷ややかな視線が一斉に私へと突き刺さる。
静寂を切り裂くようにして聞こえてきたのは、隠そうともしない悪意に満ちた囁き声だった。
「見て、鬼龍院の無能。」
「本当だ。朝から不快なもの見ちゃった。」
「最悪っ」
そんなクラスメイトの声に、心が苦しくなる。
悲しい気持ちになりつつも私が無能と言うことは事実。
なので、文句を言わずに諦める。
席に座ると私の唯一の友達、冬美が声をかけてくれた。
「玲花ちゃん…大丈夫?」
心配そうに聞く彼女の優しさに心の苦しみが少なくなった。
「ええ、心配してくれてありがとう。冬美」
「そっか、なら良かったっ」
その後も冬美は私が安心するように面白い話を沢山してくれた。
(本当に……良いお友達を持ったなぁ)
他のクラスメイトとは仲良くできそうにないが冬美が居てくれるだけで充分だ。
HRが終わり、図書館から借りてきた本を読み始める。
すると、慌てた様子の生徒が教室に入った。
「皆、聞いてくれ!急報だ!!あの鬼龍院 薫様が、学園代表候補生である鏡見 楓様の婚約者に選ばれたぞ!!」
その生徒が弾んだ声で叫ぶやいなや、教室内には凄まじい衝撃が走った。
「えっ、本当!?」「あの鏡見様の……?」
「嘘っ、あの楓様が婚約者を!?」
「はぁ〜、薫様…羨ましい」
「薫さんって、あの無能の妹さんでしょ?」
「双子なのに大違い」
と、驚きと興奮が混じり合ったざわめきが波紋のように広がり、静寂だった空間は一瞬にして熱狂の渦に呑み込まれていった。
悪気など微塵もない、純粋な賞賛や事実を告げる言葉。それがかえって鋭い刃となって、私の胸を容赦なく抉ってくる。
「玲花ちゃん……」
冬美が私を見て、心配そうな声を出す。
「ごめんね。少し…外の空気を吸ってくるねっ」
教室を満たす熱狂と、自分を切り裂くような視線。 その空気に耐えきれなくなった私は、弾かれたように席を立ち、教室を飛び出した。
縋るような思いで辿り着いた中庭で、周囲に誰もいないことを確認し、ようやく深く震える息を吐き出す。
昨日、事実を知ったときからこうなることは分かっていた。覚悟していたはずだった。 それでも、心に直接流れ込んでくる疎外感と痛みに耐えきれず、私は無様に逃げ出してしまったのだ。
「……戻らなきゃ」
いつまでもここに留まっているわけにはいかない。すぐにチャイムが鳴り、授業が始まってしまう。
それに冬美も心配しているはず。
重い足取りを引きずるようにして、私は再び、あの息の詰まる校舎へと向かうために振り返った。
すると、一人の男子生徒がいた。
よく見てみるとその人は昨日の入学式で学園代表候補生の一人、神城 竜馬さんだった。
私は誰も居ないと思っていたので驚いて、体が動かない。
(もしかして…見られていた?)
自分の情けない姿を見られていた。その事実に気づいた瞬間、猛烈な羞恥心がこみ上げ、顔が燃えるように熱くなる。
視線を向けると、神城さんは驚愕に目を見開いたまま、立ち尽くす私をまっすぐに見つめていた。まるで見てはいけないものを見てしまったかのようなその表情に、私はさらなる居たたまれなさを感じ、その場に縫い付けられたようになってしまった。
沈黙が流れた後、神城さんがようやく何かを言いかけようと唇を動かした。
てっきり、私の情けない姿を咎められるのだと身構えたけれど、彼から零れ出たのは意外な言葉だった。
「……君の名前は?」
なぜ今、そんなことを聞くのだろう。予想だにしない問いかけに、私はさらに当惑し、言葉を失ってしまった。
「…鬼龍院 玲花です」
私が名前を告げると、神城さんは迷いのない足取りで距離を詰め、私の手を優しく、けれど逃がさないという強い意志を込めて握りしめた。
「玲花……君は今から、私の婚約者だ」
あまりに唐突で、常軌を逸したその宣告。心臓が跳ね上がるのを通り越し、私はただ石像のように硬直してしまった。
私が、あの神城さんの婚約者に?
頭が理解を拒絶し、喉の奥が張り付いたように声が出ない。
「……っ、すみません!」
こみ上げてきたのは喜びではなく、正体の知れない恐怖だった。私は弾かれたように彼の手を振り払い、無我夢中でその場を逃げ出した。
あの神城さんを置き去りにしたのだ。後になって、とんでもない失礼をしてしまったという申し訳なさが溢れてきたけれど、あの時の私には、一刻も早くその場から消え去ることしか考えられないほど、心の余裕が失われていた。
「鬼龍院の無能」と蔑まれているこの私が、あの方――神城家の次期当主様と結ばれるなんて。
そんなこと、天地がひっくり返ってもあり得るはずがない。
もし、この出来事が家族の耳に届いたら……。
その瞬間に脳裏を掠めた恐ろしい結末に、私は思考を強制的に打ち切った。
これ以上考えたら、恐怖で立っていられなくなる。私は震える肩を抱きしめ、ただひたすらに、その予感から逃れるように頭を振った。
授業が終わり、待望の昼休みが訪れた。
私は冬美と机を並べ、お弁当を広げながら午前中の授業の話題に花を咲かせる。
「流石は名門校」と誰もが口を揃えるだけあって、講義のスピードは驚くほど速く、ついていくだけで精一杯だった。けれど、教え方は驚くほど明快で、決して勉強が得意とは言えない私の頭にも、知識がすうっと吸い込まれるように馴染んでいく。
この質の高い学びの中に身を置けるのなら、これからはもっと勉強に打ち込めそうな気がする。
今日という一日が、未知の知識に触れる喜びを教えてくれた。
私は今、これからの学園生活が楽しみで仕方がなくなっている。
ご飯を食べ終わり、冬美と図書館へ向かおうとしていたその時だった。
「全校生徒に連絡します。5限目の授業は急遽、全校集会に変更になります。繰り返します――」
急遽、5限目の授業が全校集会に変更されるという通達があった。
初めての講義をあれほど心待ちにしていただけに、肩透かしを食らったような、小さく溜息をつきたくなるような残念な気持ちが胸をかすめた。でも、仕方が無いことなので心の中で渋々、了解の返事をする。
そして昼休みが終わり、全校集会のため講堂に向かった。
入るのは初めてでは無いがやっぱり凄いっ
何度見ても驚きが隠せない。
暫くはこのままだけど少しずつ頑張って慣れていこう。
座席に座り、全校生徒が集まるのを待つ。
それまでの間、たくさんの声が聞こえてきた。
「ねぇ、あれ見てよ。鬼龍院の無能よ。」
「本当だ。薫様の引き立て役じゃない。」
「よくこの学園に来れたよね。霊力が無いのに」
「きっと薫様のついででしょ」
耳に飛び込んでくる言葉のほとんどは、私を容赦なく見下し、嘲笑う内容ばかりだった。
どうやらこの話は同学年に留まらず、全校生徒の知るところとなっているらしい。
上級生までもが、私に蔑みの視線を投げかけては、隣の生徒とひそひそと耳打ちを交わしている。
同じ学年どころか、面識のない先輩方にまで醜態が知れ渡っていたなんて……。
耐え難い羞恥と、締め付けられるような苦しさで、胸が張り裂けてしまいそうだった。
針のむしろに座らされているような絶望的な時間。
けれど、やがて全校生徒の入場が完了し、ようやくその地獄のような「品定め」の時間が幕を閉じた。
「只今より全校集会を執り行います。」
教頭先生の声が静かな講堂に響く。
その声にはかすかな緊張が感じ取れる。
(どうして教頭先生が緊張しているの?)
「ここで、学園代表候補生・神城 竜馬からのお話です」
教頭先生の呼び込みと共に、神城さんが静かに壇上へと上がった。
その場に立つだけで空気を支配してしまう、浮世離れした美しさ。周囲の女子生徒たちは、瞬く間に心奪われた「恋する乙女」の表情を浮かべ、うっとりと彼を仰ぎ見ている。
けれど、私にはそんな余裕など微塵もなかった。
脳裏を離れないのは、今朝のHR前に彼から突きつけられた、あの唐突な婚約宣告のこと。
神城さんの姿を目前にして、言葉にできないほど不吉な不安が、波のように押し寄せてくる。
(……嫌な予感がする)
心臓が警鐘を鳴らすように激しく打ち鳴らされ、その予感は、残酷なまでの確信となって的中してしまった。
「今日集まってもらったのは他でもない……俺の婚約者を見つけたからだ!!」
神城さんの婚約宣言が放たれた瞬間、広大な講堂は割れんばかりの驚愕と、底知れぬ困惑の渦に呑み込まれた。
周囲が騒然とする中、私はただ、逃げるように深く顔を俯かせることしかできなかった。
嫌な予感は、最悪の形で現実のものとなってしまった。
(嘘……本当に、言っちゃったんだ……)
「婚約者を見つけた」――その一言が、私の逃げ場を容赦なく奪い去る。
心臓は痛いほどに脈打ち、耳の奥で自分の鼓動がうるさく響いていた。
「えっ、どういうこと!? 神城様が、ご自分で婚約者を見つけたって……」
「もしかして、私だったりして……?」
どこからか聞こえてくる女生徒たちの期待に満ちたさざめき。それが私には鋭い刃のように突き刺さり、緊張で肺が潰されそうなほど、呼吸が浅くなっていく。
(……逃げなきゃ。先生を呼んで、ここから連れ出してもらおう)
縋るような思いで顔を上げた瞬間、舞台の上に立つ神城さんと、真っ直ぐに視線がぶつかった。
「――見つけた」
神城さんは低く、けれど確信に満ちた声でそう呟くと、迷いのない足取りで舞台を降りた。
ざわついていた講堂が、彼の異様なまでの気迫に圧され、静まり返っていく。
彼はそのまま真っ直ぐに歩いてくると、震える私の目の前でぴたりと足を止めた。
周囲の生徒たちは、一体何が起きているのか理解が追いつかず、ただ石像のように硬直している。
私は心臓の音が耳元で鳴り響き、もはや呼吸を保つのがやっとだった。
そんな私を射抜くような強い眼差しで見つめ、彼はついに、その唇を開いた。
「鬼龍院 玲花。――君こそが、俺の婚約者だ」
静寂を切り裂くようなその宣言。
次の瞬間、講堂は地鳴りのような驚愕と、底知れぬ困惑の渦に包み込まれた。
「な、何が起こっているの……?」
「神城様があの『鬼龍院の無能』と婚約!? そんな馬鹿なことがあっていいわけないわ!」
「こんなこと前代未聞だぞ……!」
怖い。周囲から飛んでくる、刃物のような視線が。
皆がどんな顔で私を蔑んでいるのかを想像するだけで恐ろしくて、私は再び深く顔を俯かせた。
(……気のせいであってほしい。何かの間違いだと言って)
けれど、目の前で私を射抜く、神城さんのあまりに真剣な眼差しがそれを許さない。
逃れようのない現実として、悟らざるを得なかった。彼が全校生徒の前で宣言した「婚約者」とは、間違いなくこの私なのだと。
今はただ、押し寄せる恐怖と底知れぬ不安に、心が千切れそうなほど苦しい。
どうしよう。もし、このことを薫が両親に言ってしまったら。
「……っ」
想像しただけで、背筋に凍るような悪寒が走り、止まらない震えが全身を支配した。
(……でも、それもすべて、本当に婚約者になってしまったらの話だよね)
ならば、ならなければいい。
そもそも私のような「無能」が、神城さんの隣に立つなど相応しくないし、その立場はあまりにも荷が重すぎる。 彼ほどの御方なら、もっと家柄も才能も優れた、相応しい相手がいるはずだ。
婚約を白紙に戻すなら、今、この瞬間しかない。
「あの、神城さん……っ!」
意を決して、拒絶の言葉を口にしようとした、その時だった。
ふわりと、足が地を離れる浮遊感に襲われる。
「え……?」
視界が揺れ、気がついた時には、神城さんの端正な顔が目の前にあった。
至近距離で射抜くような瞳に見つめられ、私はあまりの美しさに心臓が跳ね、思わず視線を泳がせてしまう。
どうやら私は、神城さんに「お姫様抱っこ」をされているらしい。
名門校の講堂という公の場で、神城様が取ったあまりに大胆で独占的な行動。
静まり返っていた周囲は、再び火がついたような騒音と、絶叫に近いどよめきに包み込まれた。
「神城様があんな無能をお姫様抱っこするなんて!?」
「信じられない……絶対に許せない」
周囲から突き刺さる嫉妬と怨嗟の声に、私は身をすくませる。けれど、それ以上に「今この状況」が耐えがたいほど恥ずかしく、思考は真っ白に塗りつぶされていった。
お願いだから、今すぐ降ろしてほしい。そう叫びたかったけれど、ふと見上げた神城さんの横顔があまりにも幸福そうで、拒絶の言葉は喉の奥に張り付いて消えた。
神城さんは私を抱いたまま悠然と舞台へ戻り、全校生徒を見下ろして朗々と告げた。
「これから玲花は俺の婚約者だ。貴様ら、彼女への接し方にはくれぐれも気をつけろ」
次の瞬間、彼の纏う空気が一変した。今まで見たこともないような、凍てつくほど冷酷な顔がそこにはあった。
「もし、俺の玲花を傷つける者がいれば……その命はないと思え」
その低く、底知れぬ殺意を孕んだ響きに、私を含めた全校生徒が蛇に睨まれた蛙のように震え上がった。 容姿端麗な彼が放つ凄絶な威圧感は、言葉を失わせるほどの迫力に満ちている。
「以上だ。一クラスずつ、速やかに教室へ戻れ」
彼の独壇場となった講堂には、静まり返った恐怖と、消えることのない波乱の予感だけが重く沈殿していた。
そして、その後、神城さんに抱えられたまま連れて行かれたのは、選ばれた「学園代表候補生」のみが入室を許される特別な専用室だった。
一歩足を踏み入れれば、そこは教室とは別世界の贅を尽くした空間。広々とした室内には上質なソファーやデスクはもちろん、専用のシャワー室やベッドまで完備されており、そのあまりの浮世離れした光景に、私は腰が抜けてしまいそうだった。
神城さんは壊れ物を扱うような手つきで、私を柔らかなソファーへと座らせてくれた。
私が少しずつ呼吸を整え、落ち着くのを待ってから、彼は静かに口を開いた。
「まずは……あんな大勢の前で、いきなり婚約者だなんて宣言してしまって、本当にすまなかった」
神城さんは真っ直ぐに私を見つめ、深々と頭を下げた。
そこに悪気などは微塵も感じられず、ただひたすらに、私を困らせてしまったことへの申し訳なさが滲んでいる。
けれど、ホームルームの前にあんなふうに逃げ出して、彼の話をきちんと聞こうとしなかった私の方にも非はあるはずだ。
「いいえ、気にしないでください。……大丈夫ですから」
私が努めて穏やかにそう返すと、神城さんの表情がぱあっと、春の陽だまりのように明るくなった。
(……可愛い)
あんなに凛々しい男性に対して、こんな感想を抱くのは失礼かもしれない。
けれど、今の彼からは先ほど壇上で見せたような威圧感は消え去り、包み込むような優しい空気が部屋を満たしていた。 そのあまりのギャップが、私の強張っていた心を少しずつ解きほぐしていく。
「あの……私を、婚約者にするというのは……」
今日一日、頭の片隅でずっと渦巻いていた疑問を、震える声で口にした。
神城さんは、名門・神城家の次期当主。若くして「最強」と謳われる、あまりにも眩しい存在だ。本来なら、私のような者が言葉を交わすことさえ許されない、雲の上の人のはず。
あやかしたちの羨望を一身に集める彼が、なぜよりによって、こんな「無能」な私を婚約者に選んだのか。どうしても、理解の範疇を超えていた。
「ああ、そうだが? 何か問題でもあったか?」
神城さんは至極当然のことのように問い返してきたけれど、私からすれば問題しかない。
あやかしの世界では、子孫に強大な力を継承させるため、互いの霊力が釣り合う者同士で結ばれるのが鉄則だ。神城家のような至高の血筋であれば、その縛りはなおさら厳格なはず。
私には、彼と並び立てるような力なんて一欠片もない。
一族を挙げて反対されるのは目に見えているのに、なぜあえて、茨の道でしかない私への求婚を選んだのだろうか。
「でも……私は神城さんに相応しくないです」
心の奥底に溜まっていた本音を、そのまま口にした。
すると、神城さんはそれまでの柔和な表情を一変させ、不機嫌そうに眉を顰めた。
(もしかして、怒らせてしまった……?)
余計なことを言って不快にさせてしまったのではないかと、私は血の気が引く思いで狼狽する。
そんな私の焦りをよそに、神城さんは音もなく隣へと移動し、至近距離から私の顔を覗き込んできた。
燃えるような紅い瞳に射抜かれ、捕らえられた小鳥のように心臓が跳ねる。
「玲花は俺に相応しい。それに、俺は玲花に惚れて婚約を申し込んだんだ」
(私に、惚れて……?)
思考が真っ白に染まり、言葉の意味が上手く脳に届かない。
神城さんのような、天に愛されたかのような御方なら、微笑むだけで誰をも虜にしてしまうだろう。
けれど、私には誰かの心を惹きつけるような魅力も、愛される資格もないはずなのに。
分かっている。これは何かの間違いか、私の聞き違いだ。
そう自分に言い聞かせようとするのに、熱を帯びた彼の眼差しが、私の震える心を逃がしてはくれなかった。
「玲花。俺でよかったら、俺の婚約者になってほしい」
胸の奥が熱くなる。そんな風に求められたのは、生まれて初めてだった。
どうしよう。神城さんの隣にいたい、そんな大それた願いが、心の隅で小さな産声を上げる。
けれど、私が彼の隣に立てば、数えきれないほどの迷惑をかけてしまうだろう。「無能」な私が婚約者だなんて、彼の輝かしい経歴に泥を塗ることにならないだろうか。
葛藤に揺れ、答えを出せずに立ち尽くす私を、彼は包み込むような眼差しで見つめた。
「玲花、大丈夫だ。何があっても、俺が必ず君を守るから」
まるで見透かされたかのように、一番欲しかった言葉を差し出してくれる。その温かさに触れた瞬間、頑なだった私の心が、静かに解けていくのを感じた。
(優しい……。この人を、信じてみたい)
「……よろしくお願いします」
絞り出すような声でそう告げた。
神城さんの婚約者になる道は、きっと険しい。周囲の冷ややかな目や、あの家族との軋轢――不安を数え上げればきりがない。
でも、もう一人で震えるのは嫌だ。
本当は、ずっと自分の居場所を求めていた。
この人が、こんな私を愛そうとしてくれるように。
私も、誰かを心から愛せる自分になりたい。
私の了承の言葉を聞いた瞬間、神城さんは今日一番の子供のように無邪気で眩しい笑顔を見せた。
「ありがとう……っ! 玲花、約束する。これから一生、君を幸せにしてみせるよ」
熱のこもった誓いと共に、彼は私を力強く、それでいて壊れ物を慈しむような優しさで抱きしめた。
彼の腕の中から伝わってくる確かな鼓動と体温。それに呼応するように、私の冷え切っていた胸の奥も、じんわりと柔らかな熱で満たされていく。
神城さんの婚約者という立場になれば、想像もつかないような逆風が吹き荒れ、酷い目に遭うこともあるかもしれない。
けれど、今はただ、この温もりを信じていたい。
初めて自分を必要としてくれたこの人の手を、離さずにいてみよう。そう、静かに心に決めた。
[side 神城]
今日、俺は運命の出逢いをした。
苛立ちを鎮めるため、あてどなく中庭を彷徨っていた時のことだ。
この学園という場所が、俺は反吐が出るほど嫌いだった。群がってくる連中はどいつもこいつも、卑屈な笑みを浮かべて俺に媚を売る。
結局、誰も俺自身を見てなどいない。
ただ、神城家の次期当主という肩書きと、他を圧倒する霊力という「価値」に群がっているだけだ。
もしも俺に、この強大な力がなかったら――。
奴らは手のひらを返したように、Cクラスの連中へ向けるような冷酷な蔑みを俺にぶつけるだろう。
霊力の多寡だけで人間の価値が決まる。そんな歪んだ理屈が支配するこの世界は、あまりに滑稽で、吐き気がするほど不自然だ。
行き場のない怒りが胸の奥で煮え繰り返る。けれど、この衝動を叩きつける場所などどこにもなかった。
学園に来れば、嫌でもそんな腐った現実を突きつけられる。
だから一年生の頃はほとんど不登校だったし、今だって、出席日数の帳尻を合わせるためだけに、重い足取りで校門をくぐる日々だ。
今日も、相変わらずの媚びへつらう生徒や教師どもの態度に胃が焼けるような不快感を覚え、人目のつかないこの中庭へと逃げ込んできたのだった。
しかし、誰もいないはずの中庭に一人の先客がいた。
背を向けていたため、その表情までは窺い知れない。ただ、陽光を透かす長いブラウンの髪が、風に揺れて美しく輝いていた。
その静寂の中に、不意に微かな啜り泣きが混じる。
なぜ、彼女が泣いているのかは分からない。
けれど、必死に嗚咽を押し殺し、肩を震わせて泣くその背中は、見ているこちらが息苦しくなるほど痛々しかった。
見ず知らずの他人のはずなのに、なぜか胸の奥を鋭く締め付けられるような感覚に襲われ、俺は声をかけることもできず、ただ遠くから彼女を見守ることしかできなかった。
どれほどの時間が流れただろうか。
やがて、絶え絶えだった泣き声が止んだ。
彼女はゆっくりと立ち上がり、意を決したようにこちらを振り向いた。
その瞬間、俺の心臓は大きく跳ね上がった。
長い髪に縁取られたその素顔は、想像を絶するほどに美しかった。
艶やかなブラウンの髪に、潤みを帯びた桜色の瞳。守ってあげたくなるような愛らしさと、凛とした気品を併せ持つその美貌に、俺の胸はかつてない速さで脈打ち始める。
張り詰めた緊張の中、今まで感じたことのない、突き抜けるような歓喜が全身を駆け巡った。
その瞬間、自分でも驚くほどはっきりと悟った。
俺は、この少女に恋をしたのだ。
一目惚れなんて、夢想家の語る絵空事だと思っていた。 だが出逢ってしまった今、初めて理解した。恋とは、これほどまでに単純で、抗いようのない衝動なのだと。
対する彼女はといえば、俺の存在に気づくと、弾かれたように驚愕の表情で固まっていた。
泣き腫らした顔を見られ、おまけに見知らぬ男が背後に立っていたのだ。 恐怖を抱かせたのではないかと、嫌われることへの怯えが胸を掠める。まだ、言葉さえ交わしていないというのに。
「……君、名前は?」
気づいた時には、思考を追い越して言葉が溢れていた。
案の定、彼女は困惑を隠しきれないといった様子で、呆然と俺を見つめている。
初対面の男にいきなり名を聞かれる不気味さは、自分でもよく分かっていた。
けれど、止められなかった。
得体の知れない焦燥感に突き動かされるように、俺はただ、彼女という存在を、その名を、心の底から知りたいと渇望していた。
「……鬼龍院、玲花です」
しばらくの沈黙の後、消え入りそうなほど小さな、けれど凛とした鈴の音のような声が返ってきた。その一言が、乾ききっていた俺の心に、驚くほど鮮やかな歓喜をもたらした。
その名は、聞き覚えがあった。
名門・鬼龍院家に生まれながら、霊力を持たぬ「異端の子」。あやかしの世界でその名を知らぬ者はいない。
けれど、誰が想像できただろうか。
噂に聞く「無能」が、これほどまでに清らかで、目を離せなくなるほど素敵な少女だったなんて。
あやかし共は、霊力の多寡でしか価値を測れない節穴ばかりだ。そんな歪んだ尺度でしか見られない世界で、彼女がどれほどの孤独と痛みを抱えてきたか。
(なぜ、もっと早く見つけられなかったんだ)
胸を締め付けるような後悔が、どす黒い塊となってせり上がってくる。
けれど、もう絶望させるような真似はさせない。
俺が、彼女のすべてを肯定し、世界の悪意から遮断してみせる。
「玲花……君は今から、俺の婚約者だ」
唐突すぎる宣言に、彼女の時が止まる。
たとえ、この命を賭してでも。
これからは俺が、君の盾となり、帰るべき場所になると誓おう。
彼女が去った後、俺は焦燥感に突き動かされるようにして、すぐさま全校集会の手筈を整えた。
あんな強引な真似をすれば玲花を困らせてしまうことは分かっていたが、一刻も早く彼女が「俺のもの」だと世間に知らしめなければ、誰かに奪われてしまいそうで正気ではいられなかったのだ。
強引に終わらせた集会の後、俺は彼女を抱きかかえたまま、学園代表候補生にのみ許された聖域へと連れ去った。
そこで改めて、大勢の前で晒し者にしてしまった非礼を心から詫び、彼女の許しを請うた。
緊張の糸が切れるような沈黙の後、玲花は静かに、俺の婚約を受け入れてくれた。
その瞬間、視界が歪むほどの歓喜が押し寄せ、不覚にも涙が溢れそうになった。
「……っ、ありがとう」
愛しさが限界を超え、俺は彼女を壊れ物を扱うように、けれど二度と離さないという決意を込めて強く抱きしめた。
絶望に染まっていた俺の人生に、今、たった一筋の、けれど何よりも眩い光が差し込んだのだ。
この生涯を賭けて、俺はこの光を――玲花を守り抜くと、胸の奥で熱く誓った。
昨日から、日本随一の名門校・エトワール学園での日々が始まった。
そして今日は、待ちに待った初めての授業。
胸の奥が少しだけきゅっと震えるような緊張はあるけれど、それ以上に、抑えきれない高揚感が全身を満たしている。
日本トップクラスの秀才が集うこの学園の講義は、並大抵の難易度ではないと聞き及んでいた。
けれど、だからこそ、そこで教鞭を執る先生方もまた、当代随一の知性を誇る人達ばかり。
入学が決まるずっと前から、私はこの学園の教壇から放たれる「知の輝き」に、強い憧れを抱き続けてきたのだ。
昨夜からずっと、この瞬間を心待ちにしていた。
これから始まる未知なる学びへの期待に、私は静かに胸を躍らせている。
学園に着いて教室の中に入る。
早く着いてしまったのか、教室には誰も居なかった。
「まだHRまで時間があるし……図書館にでも行こうかな?」
昨日入学したばかりだというのに、私は早くもこの学園の図書館に心を奪われてしまった。
名門校の威信を象徴するかのようなその場所は、圧倒的な広さと奥行きを誇っている。内装はまるで外国の古城を彷彿とさせる意匠で統一されており、どこかロマンチックな情趣が漂っていた。
けれど、私が何よりもこの場所に心惹かれた理由は、その外観以上に、視界を埋め尽くす圧倒的な蔵書の数だった。
昨日は時間に余裕がなく、一冊しか読むことが出来なかった。
でも、読みたい本がまだまだ山のようにある。
私は荷物を速やかに教室に置き、図書館に向かった。
暫くは図書館で本を読み、楽しい時間を過ごした。
HRの三十分前の予鈴が鳴り、私は教室に戻った。
私が姿を現したその瞬間、教室の空気が一変した。
まるで示し合わせたかのように、クラスメイトたちの冷ややかな視線が一斉に私へと突き刺さる。
静寂を切り裂くようにして聞こえてきたのは、隠そうともしない悪意に満ちた囁き声だった。
「見て、鬼龍院の無能。」
「本当だ。朝から不快なもの見ちゃった。」
「最悪っ」
そんなクラスメイトの声に、心が苦しくなる。
悲しい気持ちになりつつも私が無能と言うことは事実。
なので、文句を言わずに諦める。
席に座ると私の唯一の友達、冬美が声をかけてくれた。
「玲花ちゃん…大丈夫?」
心配そうに聞く彼女の優しさに心の苦しみが少なくなった。
「ええ、心配してくれてありがとう。冬美」
「そっか、なら良かったっ」
その後も冬美は私が安心するように面白い話を沢山してくれた。
(本当に……良いお友達を持ったなぁ)
他のクラスメイトとは仲良くできそうにないが冬美が居てくれるだけで充分だ。
HRが終わり、図書館から借りてきた本を読み始める。
すると、慌てた様子の生徒が教室に入った。
「皆、聞いてくれ!急報だ!!あの鬼龍院 薫様が、学園代表候補生である鏡見 楓様の婚約者に選ばれたぞ!!」
その生徒が弾んだ声で叫ぶやいなや、教室内には凄まじい衝撃が走った。
「えっ、本当!?」「あの鏡見様の……?」
「嘘っ、あの楓様が婚約者を!?」
「はぁ〜、薫様…羨ましい」
「薫さんって、あの無能の妹さんでしょ?」
「双子なのに大違い」
と、驚きと興奮が混じり合ったざわめきが波紋のように広がり、静寂だった空間は一瞬にして熱狂の渦に呑み込まれていった。
悪気など微塵もない、純粋な賞賛や事実を告げる言葉。それがかえって鋭い刃となって、私の胸を容赦なく抉ってくる。
「玲花ちゃん……」
冬美が私を見て、心配そうな声を出す。
「ごめんね。少し…外の空気を吸ってくるねっ」
教室を満たす熱狂と、自分を切り裂くような視線。 その空気に耐えきれなくなった私は、弾かれたように席を立ち、教室を飛び出した。
縋るような思いで辿り着いた中庭で、周囲に誰もいないことを確認し、ようやく深く震える息を吐き出す。
昨日、事実を知ったときからこうなることは分かっていた。覚悟していたはずだった。 それでも、心に直接流れ込んでくる疎外感と痛みに耐えきれず、私は無様に逃げ出してしまったのだ。
「……戻らなきゃ」
いつまでもここに留まっているわけにはいかない。すぐにチャイムが鳴り、授業が始まってしまう。
それに冬美も心配しているはず。
重い足取りを引きずるようにして、私は再び、あの息の詰まる校舎へと向かうために振り返った。
すると、一人の男子生徒がいた。
よく見てみるとその人は昨日の入学式で学園代表候補生の一人、神城 竜馬さんだった。
私は誰も居ないと思っていたので驚いて、体が動かない。
(もしかして…見られていた?)
自分の情けない姿を見られていた。その事実に気づいた瞬間、猛烈な羞恥心がこみ上げ、顔が燃えるように熱くなる。
視線を向けると、神城さんは驚愕に目を見開いたまま、立ち尽くす私をまっすぐに見つめていた。まるで見てはいけないものを見てしまったかのようなその表情に、私はさらなる居たたまれなさを感じ、その場に縫い付けられたようになってしまった。
沈黙が流れた後、神城さんがようやく何かを言いかけようと唇を動かした。
てっきり、私の情けない姿を咎められるのだと身構えたけれど、彼から零れ出たのは意外な言葉だった。
「……君の名前は?」
なぜ今、そんなことを聞くのだろう。予想だにしない問いかけに、私はさらに当惑し、言葉を失ってしまった。
「…鬼龍院 玲花です」
私が名前を告げると、神城さんは迷いのない足取りで距離を詰め、私の手を優しく、けれど逃がさないという強い意志を込めて握りしめた。
「玲花……君は今から、私の婚約者だ」
あまりに唐突で、常軌を逸したその宣告。心臓が跳ね上がるのを通り越し、私はただ石像のように硬直してしまった。
私が、あの神城さんの婚約者に?
頭が理解を拒絶し、喉の奥が張り付いたように声が出ない。
「……っ、すみません!」
こみ上げてきたのは喜びではなく、正体の知れない恐怖だった。私は弾かれたように彼の手を振り払い、無我夢中でその場を逃げ出した。
あの神城さんを置き去りにしたのだ。後になって、とんでもない失礼をしてしまったという申し訳なさが溢れてきたけれど、あの時の私には、一刻も早くその場から消え去ることしか考えられないほど、心の余裕が失われていた。
「鬼龍院の無能」と蔑まれているこの私が、あの方――神城家の次期当主様と結ばれるなんて。
そんなこと、天地がひっくり返ってもあり得るはずがない。
もし、この出来事が家族の耳に届いたら……。
その瞬間に脳裏を掠めた恐ろしい結末に、私は思考を強制的に打ち切った。
これ以上考えたら、恐怖で立っていられなくなる。私は震える肩を抱きしめ、ただひたすらに、その予感から逃れるように頭を振った。
授業が終わり、待望の昼休みが訪れた。
私は冬美と机を並べ、お弁当を広げながら午前中の授業の話題に花を咲かせる。
「流石は名門校」と誰もが口を揃えるだけあって、講義のスピードは驚くほど速く、ついていくだけで精一杯だった。けれど、教え方は驚くほど明快で、決して勉強が得意とは言えない私の頭にも、知識がすうっと吸い込まれるように馴染んでいく。
この質の高い学びの中に身を置けるのなら、これからはもっと勉強に打ち込めそうな気がする。
今日という一日が、未知の知識に触れる喜びを教えてくれた。
私は今、これからの学園生活が楽しみで仕方がなくなっている。
ご飯を食べ終わり、冬美と図書館へ向かおうとしていたその時だった。
「全校生徒に連絡します。5限目の授業は急遽、全校集会に変更になります。繰り返します――」
急遽、5限目の授業が全校集会に変更されるという通達があった。
初めての講義をあれほど心待ちにしていただけに、肩透かしを食らったような、小さく溜息をつきたくなるような残念な気持ちが胸をかすめた。でも、仕方が無いことなので心の中で渋々、了解の返事をする。
そして昼休みが終わり、全校集会のため講堂に向かった。
入るのは初めてでは無いがやっぱり凄いっ
何度見ても驚きが隠せない。
暫くはこのままだけど少しずつ頑張って慣れていこう。
座席に座り、全校生徒が集まるのを待つ。
それまでの間、たくさんの声が聞こえてきた。
「ねぇ、あれ見てよ。鬼龍院の無能よ。」
「本当だ。薫様の引き立て役じゃない。」
「よくこの学園に来れたよね。霊力が無いのに」
「きっと薫様のついででしょ」
耳に飛び込んでくる言葉のほとんどは、私を容赦なく見下し、嘲笑う内容ばかりだった。
どうやらこの話は同学年に留まらず、全校生徒の知るところとなっているらしい。
上級生までもが、私に蔑みの視線を投げかけては、隣の生徒とひそひそと耳打ちを交わしている。
同じ学年どころか、面識のない先輩方にまで醜態が知れ渡っていたなんて……。
耐え難い羞恥と、締め付けられるような苦しさで、胸が張り裂けてしまいそうだった。
針のむしろに座らされているような絶望的な時間。
けれど、やがて全校生徒の入場が完了し、ようやくその地獄のような「品定め」の時間が幕を閉じた。
「只今より全校集会を執り行います。」
教頭先生の声が静かな講堂に響く。
その声にはかすかな緊張が感じ取れる。
(どうして教頭先生が緊張しているの?)
「ここで、学園代表候補生・神城 竜馬からのお話です」
教頭先生の呼び込みと共に、神城さんが静かに壇上へと上がった。
その場に立つだけで空気を支配してしまう、浮世離れした美しさ。周囲の女子生徒たちは、瞬く間に心奪われた「恋する乙女」の表情を浮かべ、うっとりと彼を仰ぎ見ている。
けれど、私にはそんな余裕など微塵もなかった。
脳裏を離れないのは、今朝のHR前に彼から突きつけられた、あの唐突な婚約宣告のこと。
神城さんの姿を目前にして、言葉にできないほど不吉な不安が、波のように押し寄せてくる。
(……嫌な予感がする)
心臓が警鐘を鳴らすように激しく打ち鳴らされ、その予感は、残酷なまでの確信となって的中してしまった。
「今日集まってもらったのは他でもない……俺の婚約者を見つけたからだ!!」
神城さんの婚約宣言が放たれた瞬間、広大な講堂は割れんばかりの驚愕と、底知れぬ困惑の渦に呑み込まれた。
周囲が騒然とする中、私はただ、逃げるように深く顔を俯かせることしかできなかった。
嫌な予感は、最悪の形で現実のものとなってしまった。
(嘘……本当に、言っちゃったんだ……)
「婚約者を見つけた」――その一言が、私の逃げ場を容赦なく奪い去る。
心臓は痛いほどに脈打ち、耳の奥で自分の鼓動がうるさく響いていた。
「えっ、どういうこと!? 神城様が、ご自分で婚約者を見つけたって……」
「もしかして、私だったりして……?」
どこからか聞こえてくる女生徒たちの期待に満ちたさざめき。それが私には鋭い刃のように突き刺さり、緊張で肺が潰されそうなほど、呼吸が浅くなっていく。
(……逃げなきゃ。先生を呼んで、ここから連れ出してもらおう)
縋るような思いで顔を上げた瞬間、舞台の上に立つ神城さんと、真っ直ぐに視線がぶつかった。
「――見つけた」
神城さんは低く、けれど確信に満ちた声でそう呟くと、迷いのない足取りで舞台を降りた。
ざわついていた講堂が、彼の異様なまでの気迫に圧され、静まり返っていく。
彼はそのまま真っ直ぐに歩いてくると、震える私の目の前でぴたりと足を止めた。
周囲の生徒たちは、一体何が起きているのか理解が追いつかず、ただ石像のように硬直している。
私は心臓の音が耳元で鳴り響き、もはや呼吸を保つのがやっとだった。
そんな私を射抜くような強い眼差しで見つめ、彼はついに、その唇を開いた。
「鬼龍院 玲花。――君こそが、俺の婚約者だ」
静寂を切り裂くようなその宣言。
次の瞬間、講堂は地鳴りのような驚愕と、底知れぬ困惑の渦に包み込まれた。
「な、何が起こっているの……?」
「神城様があの『鬼龍院の無能』と婚約!? そんな馬鹿なことがあっていいわけないわ!」
「こんなこと前代未聞だぞ……!」
怖い。周囲から飛んでくる、刃物のような視線が。
皆がどんな顔で私を蔑んでいるのかを想像するだけで恐ろしくて、私は再び深く顔を俯かせた。
(……気のせいであってほしい。何かの間違いだと言って)
けれど、目の前で私を射抜く、神城さんのあまりに真剣な眼差しがそれを許さない。
逃れようのない現実として、悟らざるを得なかった。彼が全校生徒の前で宣言した「婚約者」とは、間違いなくこの私なのだと。
今はただ、押し寄せる恐怖と底知れぬ不安に、心が千切れそうなほど苦しい。
どうしよう。もし、このことを薫が両親に言ってしまったら。
「……っ」
想像しただけで、背筋に凍るような悪寒が走り、止まらない震えが全身を支配した。
(……でも、それもすべて、本当に婚約者になってしまったらの話だよね)
ならば、ならなければいい。
そもそも私のような「無能」が、神城さんの隣に立つなど相応しくないし、その立場はあまりにも荷が重すぎる。 彼ほどの御方なら、もっと家柄も才能も優れた、相応しい相手がいるはずだ。
婚約を白紙に戻すなら、今、この瞬間しかない。
「あの、神城さん……っ!」
意を決して、拒絶の言葉を口にしようとした、その時だった。
ふわりと、足が地を離れる浮遊感に襲われる。
「え……?」
視界が揺れ、気がついた時には、神城さんの端正な顔が目の前にあった。
至近距離で射抜くような瞳に見つめられ、私はあまりの美しさに心臓が跳ね、思わず視線を泳がせてしまう。
どうやら私は、神城さんに「お姫様抱っこ」をされているらしい。
名門校の講堂という公の場で、神城様が取ったあまりに大胆で独占的な行動。
静まり返っていた周囲は、再び火がついたような騒音と、絶叫に近いどよめきに包み込まれた。
「神城様があんな無能をお姫様抱っこするなんて!?」
「信じられない……絶対に許せない」
周囲から突き刺さる嫉妬と怨嗟の声に、私は身をすくませる。けれど、それ以上に「今この状況」が耐えがたいほど恥ずかしく、思考は真っ白に塗りつぶされていった。
お願いだから、今すぐ降ろしてほしい。そう叫びたかったけれど、ふと見上げた神城さんの横顔があまりにも幸福そうで、拒絶の言葉は喉の奥に張り付いて消えた。
神城さんは私を抱いたまま悠然と舞台へ戻り、全校生徒を見下ろして朗々と告げた。
「これから玲花は俺の婚約者だ。貴様ら、彼女への接し方にはくれぐれも気をつけろ」
次の瞬間、彼の纏う空気が一変した。今まで見たこともないような、凍てつくほど冷酷な顔がそこにはあった。
「もし、俺の玲花を傷つける者がいれば……その命はないと思え」
その低く、底知れぬ殺意を孕んだ響きに、私を含めた全校生徒が蛇に睨まれた蛙のように震え上がった。 容姿端麗な彼が放つ凄絶な威圧感は、言葉を失わせるほどの迫力に満ちている。
「以上だ。一クラスずつ、速やかに教室へ戻れ」
彼の独壇場となった講堂には、静まり返った恐怖と、消えることのない波乱の予感だけが重く沈殿していた。
そして、その後、神城さんに抱えられたまま連れて行かれたのは、選ばれた「学園代表候補生」のみが入室を許される特別な専用室だった。
一歩足を踏み入れれば、そこは教室とは別世界の贅を尽くした空間。広々とした室内には上質なソファーやデスクはもちろん、専用のシャワー室やベッドまで完備されており、そのあまりの浮世離れした光景に、私は腰が抜けてしまいそうだった。
神城さんは壊れ物を扱うような手つきで、私を柔らかなソファーへと座らせてくれた。
私が少しずつ呼吸を整え、落ち着くのを待ってから、彼は静かに口を開いた。
「まずは……あんな大勢の前で、いきなり婚約者だなんて宣言してしまって、本当にすまなかった」
神城さんは真っ直ぐに私を見つめ、深々と頭を下げた。
そこに悪気などは微塵も感じられず、ただひたすらに、私を困らせてしまったことへの申し訳なさが滲んでいる。
けれど、ホームルームの前にあんなふうに逃げ出して、彼の話をきちんと聞こうとしなかった私の方にも非はあるはずだ。
「いいえ、気にしないでください。……大丈夫ですから」
私が努めて穏やかにそう返すと、神城さんの表情がぱあっと、春の陽だまりのように明るくなった。
(……可愛い)
あんなに凛々しい男性に対して、こんな感想を抱くのは失礼かもしれない。
けれど、今の彼からは先ほど壇上で見せたような威圧感は消え去り、包み込むような優しい空気が部屋を満たしていた。 そのあまりのギャップが、私の強張っていた心を少しずつ解きほぐしていく。
「あの……私を、婚約者にするというのは……」
今日一日、頭の片隅でずっと渦巻いていた疑問を、震える声で口にした。
神城さんは、名門・神城家の次期当主。若くして「最強」と謳われる、あまりにも眩しい存在だ。本来なら、私のような者が言葉を交わすことさえ許されない、雲の上の人のはず。
あやかしたちの羨望を一身に集める彼が、なぜよりによって、こんな「無能」な私を婚約者に選んだのか。どうしても、理解の範疇を超えていた。
「ああ、そうだが? 何か問題でもあったか?」
神城さんは至極当然のことのように問い返してきたけれど、私からすれば問題しかない。
あやかしの世界では、子孫に強大な力を継承させるため、互いの霊力が釣り合う者同士で結ばれるのが鉄則だ。神城家のような至高の血筋であれば、その縛りはなおさら厳格なはず。
私には、彼と並び立てるような力なんて一欠片もない。
一族を挙げて反対されるのは目に見えているのに、なぜあえて、茨の道でしかない私への求婚を選んだのだろうか。
「でも……私は神城さんに相応しくないです」
心の奥底に溜まっていた本音を、そのまま口にした。
すると、神城さんはそれまでの柔和な表情を一変させ、不機嫌そうに眉を顰めた。
(もしかして、怒らせてしまった……?)
余計なことを言って不快にさせてしまったのではないかと、私は血の気が引く思いで狼狽する。
そんな私の焦りをよそに、神城さんは音もなく隣へと移動し、至近距離から私の顔を覗き込んできた。
燃えるような紅い瞳に射抜かれ、捕らえられた小鳥のように心臓が跳ねる。
「玲花は俺に相応しい。それに、俺は玲花に惚れて婚約を申し込んだんだ」
(私に、惚れて……?)
思考が真っ白に染まり、言葉の意味が上手く脳に届かない。
神城さんのような、天に愛されたかのような御方なら、微笑むだけで誰をも虜にしてしまうだろう。
けれど、私には誰かの心を惹きつけるような魅力も、愛される資格もないはずなのに。
分かっている。これは何かの間違いか、私の聞き違いだ。
そう自分に言い聞かせようとするのに、熱を帯びた彼の眼差しが、私の震える心を逃がしてはくれなかった。
「玲花。俺でよかったら、俺の婚約者になってほしい」
胸の奥が熱くなる。そんな風に求められたのは、生まれて初めてだった。
どうしよう。神城さんの隣にいたい、そんな大それた願いが、心の隅で小さな産声を上げる。
けれど、私が彼の隣に立てば、数えきれないほどの迷惑をかけてしまうだろう。「無能」な私が婚約者だなんて、彼の輝かしい経歴に泥を塗ることにならないだろうか。
葛藤に揺れ、答えを出せずに立ち尽くす私を、彼は包み込むような眼差しで見つめた。
「玲花、大丈夫だ。何があっても、俺が必ず君を守るから」
まるで見透かされたかのように、一番欲しかった言葉を差し出してくれる。その温かさに触れた瞬間、頑なだった私の心が、静かに解けていくのを感じた。
(優しい……。この人を、信じてみたい)
「……よろしくお願いします」
絞り出すような声でそう告げた。
神城さんの婚約者になる道は、きっと険しい。周囲の冷ややかな目や、あの家族との軋轢――不安を数え上げればきりがない。
でも、もう一人で震えるのは嫌だ。
本当は、ずっと自分の居場所を求めていた。
この人が、こんな私を愛そうとしてくれるように。
私も、誰かを心から愛せる自分になりたい。
私の了承の言葉を聞いた瞬間、神城さんは今日一番の子供のように無邪気で眩しい笑顔を見せた。
「ありがとう……っ! 玲花、約束する。これから一生、君を幸せにしてみせるよ」
熱のこもった誓いと共に、彼は私を力強く、それでいて壊れ物を慈しむような優しさで抱きしめた。
彼の腕の中から伝わってくる確かな鼓動と体温。それに呼応するように、私の冷え切っていた胸の奥も、じんわりと柔らかな熱で満たされていく。
神城さんの婚約者という立場になれば、想像もつかないような逆風が吹き荒れ、酷い目に遭うこともあるかもしれない。
けれど、今はただ、この温もりを信じていたい。
初めて自分を必要としてくれたこの人の手を、離さずにいてみよう。そう、静かに心に決めた。
[side 神城]
今日、俺は運命の出逢いをした。
苛立ちを鎮めるため、あてどなく中庭を彷徨っていた時のことだ。
この学園という場所が、俺は反吐が出るほど嫌いだった。群がってくる連中はどいつもこいつも、卑屈な笑みを浮かべて俺に媚を売る。
結局、誰も俺自身を見てなどいない。
ただ、神城家の次期当主という肩書きと、他を圧倒する霊力という「価値」に群がっているだけだ。
もしも俺に、この強大な力がなかったら――。
奴らは手のひらを返したように、Cクラスの連中へ向けるような冷酷な蔑みを俺にぶつけるだろう。
霊力の多寡だけで人間の価値が決まる。そんな歪んだ理屈が支配するこの世界は、あまりに滑稽で、吐き気がするほど不自然だ。
行き場のない怒りが胸の奥で煮え繰り返る。けれど、この衝動を叩きつける場所などどこにもなかった。
学園に来れば、嫌でもそんな腐った現実を突きつけられる。
だから一年生の頃はほとんど不登校だったし、今だって、出席日数の帳尻を合わせるためだけに、重い足取りで校門をくぐる日々だ。
今日も、相変わらずの媚びへつらう生徒や教師どもの態度に胃が焼けるような不快感を覚え、人目のつかないこの中庭へと逃げ込んできたのだった。
しかし、誰もいないはずの中庭に一人の先客がいた。
背を向けていたため、その表情までは窺い知れない。ただ、陽光を透かす長いブラウンの髪が、風に揺れて美しく輝いていた。
その静寂の中に、不意に微かな啜り泣きが混じる。
なぜ、彼女が泣いているのかは分からない。
けれど、必死に嗚咽を押し殺し、肩を震わせて泣くその背中は、見ているこちらが息苦しくなるほど痛々しかった。
見ず知らずの他人のはずなのに、なぜか胸の奥を鋭く締め付けられるような感覚に襲われ、俺は声をかけることもできず、ただ遠くから彼女を見守ることしかできなかった。
どれほどの時間が流れただろうか。
やがて、絶え絶えだった泣き声が止んだ。
彼女はゆっくりと立ち上がり、意を決したようにこちらを振り向いた。
その瞬間、俺の心臓は大きく跳ね上がった。
長い髪に縁取られたその素顔は、想像を絶するほどに美しかった。
艶やかなブラウンの髪に、潤みを帯びた桜色の瞳。守ってあげたくなるような愛らしさと、凛とした気品を併せ持つその美貌に、俺の胸はかつてない速さで脈打ち始める。
張り詰めた緊張の中、今まで感じたことのない、突き抜けるような歓喜が全身を駆け巡った。
その瞬間、自分でも驚くほどはっきりと悟った。
俺は、この少女に恋をしたのだ。
一目惚れなんて、夢想家の語る絵空事だと思っていた。 だが出逢ってしまった今、初めて理解した。恋とは、これほどまでに単純で、抗いようのない衝動なのだと。
対する彼女はといえば、俺の存在に気づくと、弾かれたように驚愕の表情で固まっていた。
泣き腫らした顔を見られ、おまけに見知らぬ男が背後に立っていたのだ。 恐怖を抱かせたのではないかと、嫌われることへの怯えが胸を掠める。まだ、言葉さえ交わしていないというのに。
「……君、名前は?」
気づいた時には、思考を追い越して言葉が溢れていた。
案の定、彼女は困惑を隠しきれないといった様子で、呆然と俺を見つめている。
初対面の男にいきなり名を聞かれる不気味さは、自分でもよく分かっていた。
けれど、止められなかった。
得体の知れない焦燥感に突き動かされるように、俺はただ、彼女という存在を、その名を、心の底から知りたいと渇望していた。
「……鬼龍院、玲花です」
しばらくの沈黙の後、消え入りそうなほど小さな、けれど凛とした鈴の音のような声が返ってきた。その一言が、乾ききっていた俺の心に、驚くほど鮮やかな歓喜をもたらした。
その名は、聞き覚えがあった。
名門・鬼龍院家に生まれながら、霊力を持たぬ「異端の子」。あやかしの世界でその名を知らぬ者はいない。
けれど、誰が想像できただろうか。
噂に聞く「無能」が、これほどまでに清らかで、目を離せなくなるほど素敵な少女だったなんて。
あやかし共は、霊力の多寡でしか価値を測れない節穴ばかりだ。そんな歪んだ尺度でしか見られない世界で、彼女がどれほどの孤独と痛みを抱えてきたか。
(なぜ、もっと早く見つけられなかったんだ)
胸を締め付けるような後悔が、どす黒い塊となってせり上がってくる。
けれど、もう絶望させるような真似はさせない。
俺が、彼女のすべてを肯定し、世界の悪意から遮断してみせる。
「玲花……君は今から、俺の婚約者だ」
唐突すぎる宣言に、彼女の時が止まる。
たとえ、この命を賭してでも。
これからは俺が、君の盾となり、帰るべき場所になると誓おう。
彼女が去った後、俺は焦燥感に突き動かされるようにして、すぐさま全校集会の手筈を整えた。
あんな強引な真似をすれば玲花を困らせてしまうことは分かっていたが、一刻も早く彼女が「俺のもの」だと世間に知らしめなければ、誰かに奪われてしまいそうで正気ではいられなかったのだ。
強引に終わらせた集会の後、俺は彼女を抱きかかえたまま、学園代表候補生にのみ許された聖域へと連れ去った。
そこで改めて、大勢の前で晒し者にしてしまった非礼を心から詫び、彼女の許しを請うた。
緊張の糸が切れるような沈黙の後、玲花は静かに、俺の婚約を受け入れてくれた。
その瞬間、視界が歪むほどの歓喜が押し寄せ、不覚にも涙が溢れそうになった。
「……っ、ありがとう」
愛しさが限界を超え、俺は彼女を壊れ物を扱うように、けれど二度と離さないという決意を込めて強く抱きしめた。
絶望に染まっていた俺の人生に、今、たった一筋の、けれど何よりも眩い光が差し込んだのだ。
この生涯を賭けて、俺はこの光を――玲花を守り抜くと、胸の奥で熱く誓った。