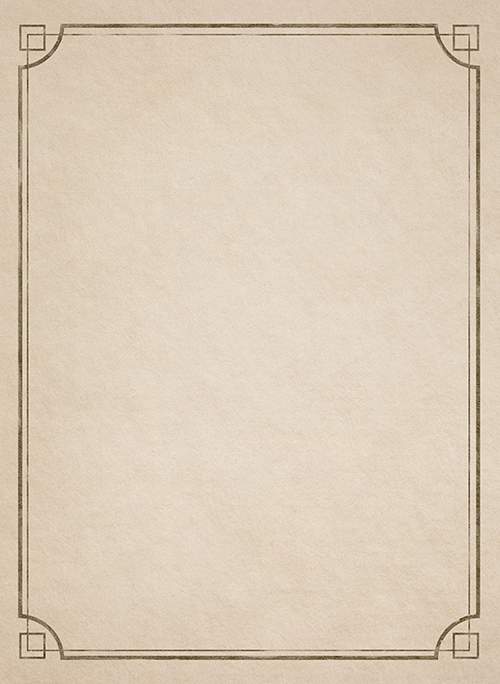2章
鬼龍院家の無能と呼ばれ、一族の汚点として嫌われ続けていた私。
しかし、十歳の誕生日の日に謎の声が聞こえてから生きてみようと思うようになった。
それから苦しい日々を耐え抜いてきた。
そんな私は十五歳になり、超エリート学園・エトワール学園に入学することとなった。
鬼龍院家の無能と言われ、私と関わろうとする人はほとんど居なかった。
でも、そんな私にも友達ができた。
名前は雪乃 冬美。属性は雪女族。
彼女は能力は素晴らしいものだが霊力が低いためそもそも操ることができなかったらしい。
その為、一族から役立たずと言われ虐げられてきたそうだ。
同じような境遇に置かれた私達はすぐに仲良くなることができた。
そんな彼女と友達になり良い学園生活が始まると楽しみになった。
「只今から、エトワール学園高等部の入学式を執り行います」
前にいる教頭先生の声と共に講堂の生徒が一斉に立ち上がる。
そして、教頭先生の合図と一緒にお辞儀をする。
今日は入学初日なので、この入学式が終わったら下校になる。
入学式には保護者も参加できるようだが私の両親は見当たらない。
目線を他のクラスの方に向けるとAクラスの保護者席に座る両親が居た。
どうやら妹の薫の様子を見に来たらしい。
私の双子の妹の薫は、鬼龍院家でも誇られるほどの霊力を持ち合わせている。
そのお陰か、一族から大切にされてきた。
それは両親も同じだった。
今日の入学式も私なんか眼中に無い。
きっと薫の輝かしい入学式を見に来たのだ。
両親は薫を見て、笑みを浮かべていた。
そんな微笑ましい家族の姿が私の胸を苦しめる。
霊力がある。たったそれだけのことでこんなにも待遇が違う。
(薫は良いな。両親から愛されていて。)
私はお母さん以外の人は誰も愛してくれなかった。
お父さんも継母も…一族の者も。皆、私を気持ち悪がった。
それが、悲しかった。私はただ、愛されたかった。
それだけなのに……無能の私には愛される権利すらなかった。
「ここで、二人の学園代表候補に挨拶をしてもらう」
そんな教頭先生の声で私の意識は現実に戻った。
もう、こんなに進んでいたんだ。
この後は学園代表候補の挨拶を聞いて、入学式は終わりだ。
学園代表候補……それはこの学園の代表になる可能性のある生徒の事。
今、教頭先生が二人と言っていたのでその二人で学園代表の座を取り合っているのだろう。
このエトワール学園では学園代表と言うものがある。
しかし、学園代表になれるのは学園で一人のみ。
それもあやかしだけだ。
学園代表になるには多くの条件が必要だと聞いたことがある。
まずは今言った、あやかしであること。
次に成績が10位以内に入っている者。
そして、あやかし特性である霊力量と能力が優れている者。
その他にも沢山ある条件に当てはまる者のみが学園代表になれる。
こんな鬼畜すぎる条件でも学園代表を目指している者は多い。
何故なら進路で役立つからだ。
元々、この学園はエリート学園として名高い学園だ。
そんな学園の代表生徒は喉から手が出るほど欲しい存在だ。
しかも、学園代表の生徒には特別な権限が使えると聞く。
だからこそ、この学園のあやかし達は学園代表になろうとしている者が多いようだ。
そんな学園代表候補である二人の生徒の挨拶。
私も興味深く、講堂に視線を向ける。
「学園代表候補生、鏡見 楓」
名前を呼ばれ、舞台に上がる一人の生徒。
この人が、学園代表候補生の内の一人…?
その人は美しく洗礼されたされた容姿だった。
そんな彼に何人もの女生徒が顔を赤らめていた。
しかも、鏡見家の人間なんてっ
鏡見家……それはあやかしの頂点に立てると言われているほどの実力を持つ一族。
彼らは、鬼龍院家と同じようにあやかし界の世界を支えており、またその特別な力で政権にまで進出したあやかしの憧れの一族。
でも、だからこそ彼が学園代表候補生に選ばれた理由が分かった。
そんな強い一族の出で有能な彼が選ばれない方がおかしいだろう。
「ー新入生の皆様、この度は入学おめでとうございます。この学園は他の学校よりも厳しく難しいですがこの学園の生徒であることを
自覚して日々、励むように務めて下さい。」
入学を祝っていると言う言葉とは裏腹に感情の籠もっていない声。
冷たい表情と声でただ台本のセリフを読むかのように祝いの言葉を述べているように見えた。
挨拶が終わり、舞台を降りた鏡見さん。
「あ〜、楓さん…かっこよかった」
近くに座っている女生徒から声がした。
「分かる...あんな綺麗な人、誰でも恋するよね」
「まぁ、無能の私達には関係ないことだよ」
「……っそうだね」
小声でコソコソと話す女生徒たち。
その会話が耳に入る。
話を聞くに鏡見さんは相当、女生徒から人気なようだ。
鏡見さんが降りた後、直ぐに教頭先生が次の生徒の名前を呼ぶ。
「学園代表候補生、神城 竜馬」
名前を呼ばれた男子生徒が舞台に上がる。
その姿を見た瞬間、講堂にいる全生徒が彼に釘付けとなった。
漆黒を纏う髪に、見た者全員を魅了する紅い瞳。
遠目から見ても分かる綺麗な人。
あまりの美しさにこの場に居る者ははっと息を呑む。
その場の空気は、彼の一瞥(いちべつ)だけで甘い熱を帯びた。周囲の女子生徒たちは一様に、射抜かれたような衝撃に頬を染め、恋に落ちた瞬間の顔で彼を仰ぎ見ていた
でも、そうなるのも頷けるほど彼は美しい。
舞台に上がり、マイクを持ち、スピーチを始める神城さん。
その姿すら様になっていて魅了される。
「新入生の皆さん。入学おめでとうございます。私達、在校生一同は皆さんの入学を心から歓迎しています」
短めの挨拶を終えて、舞台を降りた。
それにしても、さっきの学園代表候補生の神城さん。
彼もまた、鬼龍院家や鏡見家と同じようにあやかし界を支えてきた一族だ。
神城家……その昔、あやかしの神の側近をしていたと言われる一族。
神に仕えていたお礼に莫大な霊力を授けられたと言い伝えられている。
今やあやかし界で一番強いと言われている。
彼はそんな神城家の次期当主だ。
霊力量が多く、能力も優秀なものだと言われている。
この学園は、私が思った以上にすごい学園かもしれない。
まさか、あやかし界の最強と言われる3つの一族の人間が集まっているなんてっ。
あまりの衝撃に、心臓の音が耳元まで響くようだった。
波風を立てず、誰にも気付かれない空気として、この学園生活をやり過ごそう――。そう固く心に誓った。
そして入学式も終わり、教室に戻った。
この後は予定がなく各自解散となっている。
周りを見ると他の子達はクラスメイト同士で話していた。
私は冬美と話したかったが先に帰ってしまった。
今朝のこともあってクラスメイトには話しかけにくい。
私は折角なので図書館に行こうと思う。
こんなにも大きな学園なのだ、図書館もきっと大きくてたくさんの蔵書があるはず。
考えるだけでもワクワクしてしまう。
物心ついた時から、私の隣にいてくれたのは本だけだった。本だけが私の逃げ場所であり、唯一の友だった。 家族に疎まれ、愛の乾きに耐えてきた私が、虐げられた日々の中で、今日まで命を繋ぎ止めてこられたのは本という救いがあったからだ。
頁(ページ)をめくっている間だけは、剥き出しの傷口がふさがるような、穏やかな幸福に浸ることができた。そこにはいつも、私が焦がれてやまない理想の世界が広がっていた。
そんな場所が現実にあればいいと何度願っただろう。結局、その夢が叶うことはなかったけれど、今も本だけは私の無二の理解者であり、本が教えてくれた温もりは、今も私の心を静かに支え続けている。
「凄いっ、こんな図書館がこの世にあるなんて...」
図書館に足を踏み入れた瞬間、思わず「あ……」と小さな感嘆が漏れた。
目の前に広がっていたのは、視界の端から端までを埋め尽くす、圧倒的なまでの本の連なり。
天を仰ぐほど高い書架が迷宮のように続き、これまで目にしてきたどの図書室とも比較にならない、膨大な知の集積がそこにはあった。
これほどの規模を誇る場所は、国内を探しても他にはないだろう。
物語の中でしか許されないような夢の光景に、私は一瞬、自分がどこにいるのかさえ忘れてしまいそうになった。
取り敢えずこの図書館の中を探索してみよう。
壁に貼られた館内マップで目的地を定め、歩き出す。
どこを向いても、視界に飛び込んでくるのは背表紙の列ばかり。これほどの蔵書に囲まれているのなら、私の学園生活の大半は、間違いなくこの場所で費やされることになるだろう。
ほんの少し歩き回っただけで、好奇心をそそる本が次々と見つかった。
「今日は、この中でも特に気になるものを一冊だけ……」
そう自分に言い訳をして、本を手に取る。
今、家に帰ったところで、妹の薫の入学祝いのために家族は出払っているはずだ。少しぐらい帰宅が遅れたところで、誰も気に留めないし、咎められることもないだろう。
静寂に包まれた空間で、私は手にした本のページを、そっとめくり始めた。
「ふうっ...この本、とても素敵だったな」
少しだけと思って読んでいたらいつの間にか一冊を読み上げていた。
いつの間にか、あれほど明るかった館内には夜の気配が忍び寄り、影が長く伸びている。
慌てて図書館を出て時計を見るともう18時だった。
「もうこんな時間...急がないとっ」
私の帰りが遅いことを心配する者なんて、あの家には一人もいない。むしろ、このまま私が消えてしまった方が、彼らにとっては都合が良いはずだ。
それなのに、なぜ私はこんなに焦っているのだろう。
それはただ、家族が戻る前に山積みの家事を片付けておかなければならないから。
家には数人の使用人がいるけれど、彼らは何一つ動こうとせず、面倒な仕事はすべて私に押し付けている。私が今すぐ帰って立ち働かなければ、家族の不興を買い、家の中が回らなくなってしまうのだ。
ただでさえ『無能』な私は、置かせてもらっている身なのだ。
せめて家事くらいは完璧にこなさなければ、ここにいる資格さえない。
それに、こうして立ち働いている間だけは、無価値な私でも少しは誰かの役に立てているような気がした。
もちろん、それがただの思い込みであり、独りよがりの自己満足に過ぎないことは分かっている。
けれど、汚れを落とし、家を整えていく達成感だけが、私の荒んだ心をかろうじて真っさらにしてくれるのだ。
逸る心で家路を急ぎ、ようやく辿り着いた邸宅には、皮肉にもすでに明々と灯りがともっていた。
(帰ってきてたんだ。)
両親が戻る前にすべてを終わらせておかなければ、容赦のない拳が飛んでくる。
その恐怖が背筋を駆け抜け、家の中に灯る明かりを見た瞬間、私の足は鉛のように重くすくんでしまった。
「...ただいま」
扉を開けて小さな声で帰りを知らせる。
この後、両親が怒って殴られると思う体が動かない。
そんな私に使用人が気づいて両親がいる部屋のほうへ行った。
するとその部屋からこちらに向けてお父さんの怒声が聞こえた。
「玲花!!早くこちらに来なさい!!」
私はその声に怯えながらも恐る恐るお父さんたちがいる部屋に入る。
「お父さん...ごめんなさい。只今、戻りました」
私は部屋に入ってすぐに頭を下げて謝った。
少ししてから顔をあげるとお父さんに継母.....そして薫がいた。
「全く、無能のくせに家事をサボるなんて...何処までも役立たずね」
「まぁ、お姉ちゃんが役立たずなのは昔からじゃん。」
二人は私を見るや激しい罵声を浴びせてきた。
けれど、遅れた私が悪いのだから、反論の言葉など一言も持ち合わせていない。
これ以上場の空気が冷え冷えと凍りつかないよう、私はただ、泥を呑み込むような心地で固く口を閉ざし、嵐が過ぎ去るのを待つしかなかった。
「はぁ、本当にお前は何のために生まれてきたのやら……」
父が吐き捨てたその言葉は、鋭い刃となって私の胸の奥深くを突き刺した。
突き落とされたような衝撃に、心臓がじりじりと焼けるように痛む。
(本当に……お父さんの言う通りだ)
反論する言葉も、自分を擁護する理屈も何ひとつ浮かばない。
暗い奈落の底を見つめるような心地で、私は自問せずにはいられなかった。
私は、一体何のために生まれてきたんだろう。
祝福されることもなく、誰にも望まれず、ただこうして罵倒を受け止めるためだけに、今日まで息をしてきたのだろうか。
「お前なんかに関係ない話だが、薫がどうしても伝えときたいと言ってな」
(えっ…薫が。どうしたんだろう。私のことを嫌っている薫が私に伝えたいことって……。)
「実は、私……あの鏡見 楓さまの婚約者になったの!」
鏡見 楓って今日紹介されていた学園代表候補生のっ。
薫は今日、初めて会ったばかりだろうにどうやったら婚約者になったのだろう。
「今日、家に帰ろうとしたらね、たまたま楓さまに会って。私の霊力を見て婚約を交わしたのよ」
そっか…どうして学園に入ったばかりの薫が婚約者になったのか分からなかったがそういうことね。
薫は鬼龍院家の女の子の中で一番霊力量が多くて能力も優秀だ。
そんな薫が婚約者になってくれたら鏡見家も安泰だろう。
「入学式初日であの鏡見様の婚約者になれるなんて。薫は本当に凄い子ね。私達の自慢の娘よ。」
両親は、薫が鏡見家の婚約者に選ばれたことが、誇らしくて仕方ないようだ。その顔には、隠しきれない歓喜の色が浮かんでいる。
それもそのはずだ。国内有数の名門である鏡見家が、我が鬼龍院の娘を娶るとなれば、一族の将来は盤石なものとなる。
しかも、その相手は鏡見家の中でも至高の才を誇ると謳われる、鏡見 楓さん。
類まれなる力を持つ二人が結ばれ、その血を引く子が生まれれば、計り知れない霊力量を宿した傑物が誕生するに違いない。
そうなれば、鬼龍院の一族は今以上に強固な権勢を誇り、揺るぎない地位を築くことになるだろう。両親は薫が鏡見家の婚約者になってくれたのがとても嬉しいようだ。
「はぁ……薫はこれほどまでの大役を果たしたというのに、玲花、あんたは本当に救いようがないわね。無能で、何の役にも立たない。……いっそ、生まれてこなければ良かったのに」
継母が私に向ける言葉には、剥き出しの棘があった。私を見据えるその瞳は、汚物でも見るかのような深い嫌悪に濁っている。
「まあまあ、お母様。そんなに怒らないで。落ち着いて?」
その時、薫が継母の手にそっと自分の手を重ね、鈴を転がすような優しい声で宥めた。すると、つい先ほどまで煮え繰り返るような怒りを撒き散らしていた継母の表情が、魔法にでもかかったかのようにみるみると機嫌が良い方へと変わっていく。
継母の凍てつくような悪意を、薫の存在だけが鮮やかに溶かしていく。その対照的な光景を、私はただ透明な空気として、黙って見つめることしかできなかった。
「そうね。今日は薫のお祝いの日だものね。」
薫の行動で機嫌が良くなった継母は私を見る。
さっきよりも優しい眼差しになっていて安堵する。
「もう話すことが無いから、さっさと家事をして寝なさい」
継母は私に命令した後、こちらを一切見ることが無かった。
私は三人の邪魔をしないように静かに襖を閉めた。
良かった。
いつもならこのまま殴られていたが今日は機嫌が良くて殴られずに済んだ。
恐れていた事態が起きずに安心して肩の力が抜けた。
そして着替えを済ませた後、すぐに家事に取り掛かった。