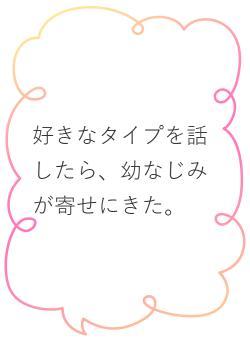「猪狩くん。先ほど投票の結果、我がクラスが文化祭でやる劇の演目は文芸部の日向脚本の“傾国の姫に異世界転生!~ホラーゲームは苦手なのになぜか無双してます~”に決まったんだけどもね」
「いや、俺も居たから知っているが……」
放課後の教室。帰ろうと思った瞬間、見計らったように現れた月島に咄嗟に身構える俺。
──一体どんな用件だ。
──わざわざ説明口調で念押しして……絶対ろくなことじゃない。
「一晩で脚本を書き上げて来た日向の熱量と、みくりんのお姫様衣装が見られるという期待に押され投票した俺たちだが……」
「配役決めは明日だぞ。姫宮の了承を得ずに決めるんじゃない」
「残念ながら我々は脚本担当の日向含め──ホラーゲームの方はプレイ経験がない」
「異世界転生の方は誰か経験があるのか?」
「そこでだ、猪狩くん!」
俺の突っ込みを無視した月島がここで差し出してきたのは、白い横長の封筒から飛び出た二枚の紙。何かのチケットのようだ、と書いてある文字を読んで後悔した。【ホラー×謎解き!?リアル脱出ゲーム】……先週一緒に行こうと誘われ、断った記憶がある。
「君には我がクラスの代表として、ホラーの世界観を学んで来てもらいたい!」
「だから、俺は怖いのは苦手だと……」
「おだまり!!」
改めて辞退しようとすれば、問答無用で学ランのポケットにねじ込まれるチケットたち。
「なぁにが怖いのは苦手、だ!お前の見た目ならむしろホラーの方が逃げるわ!!」
「あっ、ちょっ」
「それ今日までなんだから絶対行けよ!」
「月島は行かないのか!?」
「今日は夜までバイトっ」
言いながら月島は物凄い速さで去っていく。ポケットから封筒を取り出し、俺はため息を吐いた。
──本当に、怖いのはダメなんだが……。
僅かな希望も見えないような暗い室内、恐怖を掻き立てるBGM、命の危機を抱かせることに特化した仕掛けの数々──……想像するだけで背筋が凍る。
──これはお化け屋敷とはまた違うようだが……密室で怖い思いをさせられるのに変わりはない。
──こっちもバイトで行けなかったことにしてしまおうか。でもあの感じだと、月島は俺が月曜休みなのを知ってるようだし……。
「あ、猪狩くん」
途方にくれ、ぼんやりとチケットを眺めていると誰かがやってくる。帰りのHRが終わるのと同時に宿題のプリントを提出しに行った姫宮が戻って来たのだ。
「姫宮……」
「それ、何かのチケット?」
隣で俺の手元を覗き込もうとする姫宮に見えやすいよう、少し紙を傾ける。
「リアル脱出ゲームか。確か猪狩くんのバイト先のショッピングモールでやってたね」
「あ、ああ。文化祭でやる劇の演目は決まったが、『ホラーゲームは誰もプレイ経験がないから学んでこい』と月島に渡された」
「ホラーゲーム“は”?」
「異世界転生の経験者はいるらしい」
「っ、あははは!」
何気ない俺の冗談に、大口を開けて笑う姫宮。偶然とはいえ外で話す機会が多かったせいか、いつの間にか学校の中でも素を見せてくれるようになった。
「なるほどね。で、チケットが二枚あるんだ」
ひとしきり笑ったあと話を戻す姫宮に「ああ」と頷く。
「これから誰か誘うの?」
「いや……当てがないから一枚は諦めて、俺だけ行こうかと」
「そっか……」
俺の返事に少し考える素振りを見せた後、姫宮は再び口を開いた。
「じゃあそのチケット、二枚とも俺がもらおうか」
「えっ、姫宮が?」
「うん。猪狩くんホラー系苦手でしょ?世界観学ぶってことなら俺でも良いだろうし、地元の知り合い誘えば誰かしら来てくれるから」
「……」
こちらとしては願ってもない申し出だが……身代わりにするようで罪悪感が湧く。姫宮だってホラーが苦手かもしれないのに。
「まぁ俺、リアル脱出ゲームって行ったことないからどうなるかは謎だけど」
「あ、あの」
「ん?」
「姫宮さえ良ければ、俺たち二人で行かないか?」
震える手を押さえ込んでそう切り出せば、ただでさえもぱっちりとした姫宮の目がさらに丸くなった。
「俺と猪狩くんで?」
「脱出ゲーム自体は月島と行ったことあるから役に立てると思う」
「でも、結構怖そうだよ?」
「こ、怖いのは嫌だが……姫宮と一緒なら頑張れる」
言い終わってハッとする。か弱くて守ってあげたくなる雰囲気の子だったらともかく、見るからに頑丈そうな俺がこんなこと言うのはただただ情けない。少し顔を上げただけの姫宮とばっちり視線が合うほどの俯き加減だし、恐怖のあまり涙目になってる気もする。
──相手が月島だったら『気持ち悪いこと言ってないでさっさと行け!』と一喝される場面だ。
──姫宮にそんな突き放され方したら立ち直れない……。
なんて俺の不安をよそに、姫宮はゆるりとまぶたの力を抜いて微笑んでいた。軽く首を傾げる仕草も相まって少女漫画のワンシーン(もちろんヒロインのところ)を切り取ったみたいだ。
「そんな可愛いこと言われたら、連れてかないわけにはいかないね」
「……っ」
だけど実際口から出たのは同じ少女漫画でも、ヒロインの相手役のような台詞だった。
──ま、また可愛いって言った……!
『可愛い子が可愛い子と戯れてる』
この前の土曜日、姫宮の妹の瑠璃葉ちゃんと俺が話していた時にも似たようなことを言われた。そういう扱いに密かな憧れがあった俺にとっては夢のような出来事で──、でも間違いなくネタの類だから舞い上がらないように気を付けていたのに。もはやこれは、軽率に同じ冗談を繰り返す姫宮の方に問題がある。
「じゃ、猪狩くんの決意が鈍らないうちに行こっか」
俺の心情などつゆ知らず、さっさと自分の鞄を持ってきて歩き出す姫宮の背中を、恨めしく眺めることしか出来なかった。
◇◇
「──本当に、申し訳ない……」
俺のバイト先があるショッピングモールでは定期的に様々なイベントが開催されていて、今姫宮と来ているリアル脱出ゲームもそのうちのひとつだ。
受付と簡単な説明を済ませ、靴を脱いで入るタイプの密室に閉じ込められてから約十分後。低い天井のせいか少し圧迫感のあるここには脱出するための鍵を探すべく動き回る姫宮と──その気配を感じながら端に体育座りし、ぎゅっ、と両目を瞑る俺。
──こんなに怖いとは思わなかった……!
「俺の存在意義がない……」
「いやいや、さっきの謎は猪狩くんが解いてくれなかったら詰んでたよ」
入室するなり目に飛び込んできた女性の幽霊の映像に大絶叫した俺はすっかり戦意喪失していたが、『終わるまで目瞑ってて良いよ。謎解きだけ読むから手伝って』という姫宮の気遣いのおかげでかろうじてリタイアせずにいた。
「あ。今、絶対に目開けないで」
「わ、分かった」
「うわやば。よくこんな仕掛け作ったな……」
俺に念押しした後、素の姫宮が小さくぼやく。一体どんなことになっているんだ……。
「またこういう無茶ぶりされたらすぐに俺呼んで。特に苦手なものとかないから、今日みたいに付き合えると思う」
次に発せられたのは俺に宛てたものだ。壁際でカチャカチャ音がするから、謎解きをしながら話しているのが容易に想像できる。
「……ありがとう……」
姿は見えないが、すぐ近くにある姫宮の気配は俺より小柄なことを忘れそうなくらい頼もしい。しかも──……。
「泣き叫んでみっともないところ見せたのに……笑わないんだな」
「笑うわけないよ。可愛いとは思っちゃったけど」
「まっ、またそんな……」
相変わらずカチャカチャ鳴らすなか姫宮が悪びれず言うものだから、しっかり目を瞑りつつ声を張り上げる俺。
「いい加減その冗談やめてくれっ。俺の見た目であんな情けない悲鳴を上げて……可愛いわけがないだろう!」
「冗談なんかじゃないよ」
「うっ……」
渾身の訴えを短く返されてさすがに怯む。どうして姫宮はこんなに頑ななんだ。俺が“可愛い”だなんて、誰の共感も得られないだろうに。
「……あれ……?」
そこで突然、閉じた瞼の向こうで控えめに揺れていた照明が陰った。壁際で姫宮がずっと鳴らしていたカチャカチャ音も聞こえなくなり、俺は一人にされてしまったのかと不安が襲う。いてもたってもいられなくなり、それまでぎゅっと閉じていた両目をおそるおそる開いた瞬間──ここ最近毎日のように見ていた端正な顔が視界のほとんどを占めており呼吸が止まった。
「姫宮っ、ち、近…!」
「猪狩くんは、可愛いって言われるの嫌?」
「え……?」
体育座りする俺の前にしゃがみ顔を覗き込んでくる姫宮は、目が合ったのを確認するとゆっくり口を開く。
「からかってるつもりはなくて、本心だったんだけど……君が嫌ならもう絶対に言わない」
「あ、あの」
「教えて?猪狩くんの気持ち」
今の姫宮は学ラン姿で、学校で“みくりん”と呼ばれ愛でられてる時と同じなのに低い声音とか……冷静にこちらを見据える眼差しが決定的に違う。これをはぐらかすのは無理だと本能が悟った。
「……じゃない」
「ん?」
「嫌じゃ、ない。ずっと言われてみたかったから……むしろ嬉しい」
ここまで言って良いのだろうか。姫宮の背後の画面には物凄い形相でこちらに手を伸ばす幽霊がばっちり確認出来るけど、怖がる余裕がない。
「でも俺は今まで可愛いなんて言われたことないし、月島たちに聞かれたら姫宮が馬鹿にされる……」
“姫”の感性って結構アレなんだなと、鼻で笑う月島が目に浮かぶ。俺のせいで姫宮がネタにされたら──考えるだけで目頭が熱くなる。
「俺はそんなの気にしない」
だけど姫宮は本当に気にしていないようで、眼前を遮る自分の前髪を雑にかき上げながら事もなげに言う。
「ホラー苦手なのに劇のためにってここまで来て、怖いの頑張って我慢してる猪狩くん可愛いよ。『姫宮と一緒なら頑張れる』って涙目で言ってきたのもすごく可愛くて──俺以外にはやらないでほしいって思った」
「そ、それは言い過ぎだ……!」
「照れると目を合わせてくれなくなるところも可愛い」
「……っ」
タガが外れたように“可愛い”を連発する姫宮に困り果ててしまう。それすら嫌じゃないと、向こうは知っている分なお質が悪い。とはいえこれが続くと心臓がもたない……そう悩み始めた頃、姫宮の後ろの画面が弾けたように消え、扉の鍵がガチャッ、という音と共に回るのが見えた。
「あ、鍵開いたね。さっき送った答えが合ってたみたい」
「終わったのか……」
申し訳程度についていた証明が眩しいくらいに明るくなり、それを合図に姫宮が離れていく。少し名残惜しいと思ってしまったのは黙っておこう……。
「お兄さんめっちゃ叫んでましたねー」
「怖いのダメなのにお疲れ様でした!」
序盤の俺の大絶叫を姫宮のものだと勘違いしたらしい二人の若い女性スタッフが、そちらに声をかけている。しかし姫宮はあれは自分じゃないと訂正せず、「ほんと怖かったですー」と軽く笑いながら退場ゲートから出て行く。
「あの人メロ……!インステ聞きに行く!?」
「私ら仕事中なんだからやめようよ……。なんか怖そうな人が付いてるし」
ひそひそ声が指す“怖そうな人”とは俺のことだろうが──直前に大量摂取した“可愛い”のおかげだろうか、全く傷つくことはなかった。