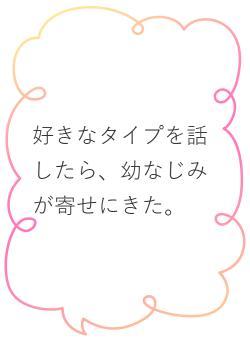──やはり、休日はどこも混むな……。
土曜日。バイト先で偶然姫宮に会った日から二日経っており、それ以来の出勤だった。火村さんのことだけが気がかりだったが……店に入った俺を見つけるなりすぐ一昨日の件を謝ってくれ、仕事ぶりも格段に良くなったことでいつもより効率良くホールを回せた。そして時間は午後三時。無事退勤した俺は一人、ショッピングモールの中を歩いている。
──姫宮の毅然とした対応に思うところがあったのだろうか。火村さんはちゃんと切り替えが出来てすごいな。
──それに比べて、俺は。
俺のバイト先のファミレスが入っているレストラン街とは違う階のフードコート。遅めの昼食を取ろうと買ったたこ焼きを携えて席を探しながらも、相変わらず頭を離れないのは学校では(おそらく)俺しか知らない姫宮の外の顔。
──あの時の姫宮は堂々としていてかっこ良かった。
──俺も、自分の見た目を考えればああいう風に振る舞うべきなのだろう。
出来ればもっとあっちの姫宮とも話がしてみたいが、このショッピングモールでバイトを始めてから一年、一昨日まで会うことはなかった。自宅がここに近い俺とは違って、あっちはたまたま立ち寄っただけなのかもしれない。
「……くん、猪狩くんっ」
外での自分を月島たちに知られるのが嫌みたいだから、仮に姫宮が今日もここにいて俺を見かけたとしても気づかないふりをされる可能性もある。──なんて考えた次の瞬間、俺は目を見開いた。数歩先の席に座った姫宮が、こちらに手を振っていたのだ。
「姫宮……!」
「席探してたよね?良かったら座って」
「ど、どうも……」
隣の椅子に置いていた荷物をさっとどけて座るところを作ってくれた姫宮に軽く会釈して、ありがたく座らせてもらう。俺を見かけたとしてもスルーされるかと思いきや実際はそんなことなかった。嬉しい予想外に思わず口角が上がる。
「今日もバイト?」
「ああ。さっき終わったんだ」
たこ焼きが乗ったトレーをテーブルに着地させたところで、姫宮の向かい側の椅子にちょこん、と座る小さな影に気づいた。幼稚園でいうと年中さんくらいの女の子だ。
「姫宮、彼女は?」
「俺……ごほん、僕の妹。ルリ、兄ちゃんのお友達だよ」
紹介のすぐ後に続く、「こんにちは!」という元気な声。
「ひめみや るりは!5さいですっ」
「宝石の瑠璃に、葉っぱって書いて瑠璃葉っていうの」
「瑠璃葉ちゃんか……ちゃんと挨拶出来て偉いな。俺は猪狩 雄一、十七歳だ」
姫宮の補足を受けてから、なるべく目線が合うように上半身を屈めて「こんにちは」と返した俺に見せた満足そうな笑顔は、当たり前と言えばそれまでだが兄の姫宮によく似ている。
「瑠璃葉ちゃん、俺もここで一緒に食べて良いか?」
「うんっ、良いよ!」
「ありがとう」
時間的に姫宮兄妹はおやつを食べていたんだろう。瑠璃葉ちゃんの前にあるアイス屋さんのカップの中身は空っぽだった。
「ゆーいちくん見て!猫さんだよっ」
「ん?あ、これって……」
興奮した様子の瑠璃葉ちゃんが指さす前髪には猫ちゃんモチーフのクリップが留まっている。一昨日の朝、月島が姫宮にプレゼントしていたものだ。
「みっくんがくれたの!」
「みっくん……?ああ、お兄ちゃんのことか」
「あとこっちのぷっくりシールと……このノートもみっくんが選んでくれた!」
ここと同じ階にあったはずの雑貨屋の袋を取り出し、ひとつひとつ手に持ち一生懸命説明してくれている姿はとても可愛い。前髪クリップは姫宮が買った物ではないが、俯く隣を見るに言及しない方が良さそうだ。
「優しいお兄ちゃんだな」
「うん!ルリ、みっくんのこと大好きっ」
「ルリ。アイス食べ終わってるならあっち行ってきな」
大好きと言われ僅かに目尻を染めた姫宮が『あっち』と促したのは、狭い通路を渡ってすぐのところにあるキッズスペース。
「はぁい!ごちそうさまでしたっ」
「クリップ刺さったら危ないから外して行きな」
姫宮の声掛けに素直に頷いた瑠璃葉ちゃんは、前髪クリップをテーブルに置いてから遊びに行く。
「彼女あそこのヘビーユーザーだから。今日も気持ちよく昼寝してたのに、早く連れてけって叩き起こされた」
「ふはっ」
瑠璃葉ちゃんがキッズスペースに入るのを確認した姫宮が冗談めかしてそう言うものだから、つい吹き出してしまう。ということは……姫宮も俺と同じでこのショッピングモールの近くに住んでいて、今まで会わなかった方が不思議なのか。
「俺にも妹がいるが、あれだけ年齢が離れていれば余計に可愛いだろう」
「ほんとそう。なんでも買ってあげたくなっちゃって、バイト代いくら溶かしたことか」
「シールもノートも姫宮が選んだと言っていたが、さすがセンスが良いな」
「……そんなことないよ」
俺の感想の少し後に、罰の悪そうな姫宮の声が返ってくる。
「今まで月島くんたちにもらったプレゼントはぜんぶ瑠璃葉にあげてて、反応見てたらなんとなく好みが分かってきたってだけ」
「そうなのか?」
「うん。俺──ん”んっ、僕自身、最近まで“可愛い”とは無縁だったし」
意外だと思いながら、今日の姫宮の服装を見てみる。淡いピンクのトレーナーとゴールドのワンポイントが付いた華奢なネックレス。それらだけ見れば学校でのイメージと大差ないが、ワイドパンツだったか?デニムで出来たダボっとしたズボンや飾り気のない真っ黒なスニーカーを合わせた全体を見れば確かに、可愛いとは真逆の印象を受ける。
「中学時代は瑠璃葉の誕生日に変なものあげて泣かせちゃったこともあって」
「なるほど……」
話しながらも姫宮は、瑠璃葉ちゃんがどの辺りで遊んでいるかを常に気にかけている。一昨日バイト先で会った時は無糖のコーヒーを嗜んでいたようだが、今脇に置いてあるカップからは甘い香りがした。
「高校で“姫”なんて呼ばれて最初はうざ──嫌だったけど、今はあの子が心から喜ぶ物を選べるようになったから感謝してる。……プレゼント瑠璃葉に横流ししてるの、月島くんたちには内緒にしてくれると嬉しい」
「それはもちろん」
テーブルの上に置かれた前髪クリップを手に取って言う姫宮に俺は頷く。
「わざわざ触れ回ることじゃないからな。あと……今は別に素でも良い。休みの日くらいは自然体でいてくれ」
学校では自分のことを“僕”と呼ぶ姫宮だが、会話中何度か取り繕っているところから察するにおそらく本当の一人称は“俺”だ。クラスメイトがいるからなんて気を張らず、ありのままで過ごしてほしい。
「……分かった」
キッズスペース内で滑り台の順番を待つ瑠璃葉ちゃんに意識を向けつつ、ちらりと俺を見る姫宮。
「優しいよね、猪狩くんって。一昨日も俺の私服見たのに学校でネタにしなかったし」
「ネタ……?」
「例えばこっそり撮った写真拡散して、『“姫”の私服イメージと違い過ぎて草』とか」
「そ、そんなことするわけない」
確かに初めて姫宮の私服を見た時、学校とは随分印象が違うとは思った。でも。
「容姿だけ見て勝手に役回りを決め、それにそぐわなければ馬鹿にする……なんておかしいだろう。少なくとも俺は絶対にしない」
俺自身、臆病な性格に合わない体格のせいで散々な目に合ってきた。今の口ぶりからすると姫宮も、俺と似たような経験があるんじゃないか。
「一昨日バイト先で会った時から、俺は姫宮みたいな男を目指すべきだと思っていた。だから今日こうして話せて嬉しい」
「えっ、猪狩くんはそのままで良いよ」
さっきも少し考えていたことを口にした途端、姫宮が意外そうな声を上げる。
「優しくて穏やかで人の嫌がることは絶対しない、今の猪狩くんが素敵だよ」
「そんな……」
前から思ってたとばかりにすらすら言われるとくすぐったい。瑠璃葉ちゃんが少し遠くで遊んでくれていて良かった、姫宮の注意がそちらに逸れることで熱くなった顔を見られずに済む。
「……ゆーいちくんっ!」
と、噂をすればじゃないが、滑り台を終えキッズスペースから出て来た瑠璃葉ちゃんが兄ではなくなぜか俺を呼びながらやってくる。
「たこ焼き冷める前に食べなさいっ」
「あ、忘れてた……。それを言いに来てくれたのか?」
「そーだよぉ」
俺の問いに瑠璃葉ちゃんは大きく頷く。姫宮がずっと見守っていたように、彼女の方もこっちを気にしてくれていたのか。
「ルリが食べさせてあげるねっ」
「い、いや……自分で食べるから大丈夫だ」
「また忘れちゃうからだめ!」
「そんなことはない……はず……」
瑠璃葉ちゃんに詰められたじたじになる俺を眺めていた姫宮が、「ふふ」と口元を綻ばせる。
「良いね。可愛い子が可愛い子と戯れてる」
「……え?」
唖然とする俺の視線の先には、素知らぬ顔でラテを啜る姫宮。
“可愛い子”。
一人は間違いなく瑠璃葉ちゃんのことだ。その瑠璃葉ちゃんと戯れているというもう一人の可愛い子とは──学校で言おうものなら大爆笑が起きるだろうが──状況的に俺しかいない。だけど、え、そんなまさか。可愛いなんて、幼い頃すら言われたことないのに。
「はいゆーいちくんっ、あーん!」
瑠璃葉ちゃんが箸を上手に使って食べさせてくれたたこ焼きは、まだ少しだけ温かった。