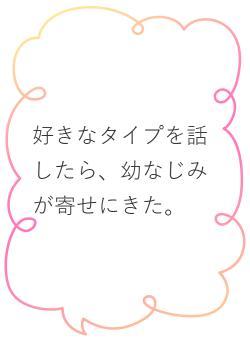バイト先の大型ショッピングモール内のファミレスは夕飯の時間には少し早いものの、買い物ついでに寄ったと思われる客で賑わっていた。始めはただ戸惑うだけだったが一年近くやれば慣れたもので、今日も忙しく働いていた──けど。
「猪狩さーんっ、オーダーミスしちゃいましたぁ……!」
そう言って慌ただしくパントリーに入って来たのは、新人スタッフの火村さん。俺はデザートを仕上げる手は動かしつつ、彼女の方へ目線をやる。
「どんなミスだ?」
「これなんですけど、ミニサイズとXLサイズを間違ってオーダー通しちゃったみたいでっ」
気づいてからすぐ両手に抱えて運んで来たのだろう。“これ”と見せられたのは、数人がかりでも完食に苦戦しそうな巨大なシーフードピザ。
「ピザ用のオーブンは今フル稼働してるし、作り直すにも時間がかかるな……」
「どうしましょう……」
「まずお客様に謝罪と、事情の説明をしてきてくれ。俺もデザートを配膳したら行く」
「えっ、私が謝るんですか!?」
「えっ?」
自分が謝ることをまったく想定していなかったような火村さんの反応に、こちらも素っ頓狂な声が口を突く。
「オーダーミスしたのは君なんだよな……?」
「そうですけどぉ、ちょっと怖そうなお客様だから行きたくないですっ。ほらあの黒いパーカーの人!」
促される形でホールを覗くと、該当の客は細身の後ろ姿しか見えないが確かに近寄りがたい雰囲気をしていた。
「でも、ちゃんと謝らないと……」
「じゃー猪狩が代わりに謝れば?」
俺と火村さんの声を聞きつけてか、調理担当の大学生がキッチンから顔を出す。
「お前が火村ちゃんの教育係なんだからさ」
「だから俺も火村さんに付いて行こうと」
「うちで一番若い子を怖いお兄さんとこ行かせるの?トラウマになったらどうすんだよ」
「そんな……」
いくら教育係だって、代わりに謝罪なんて高校生バイトの領分を完全に超えている。それに俺だって彼女とひとつしか年が変わらないし、怖いと思うのも同じだ。……だけど口にしたら『そんなデカい図体で何言ってんだ』って笑われるに決まっている。
「……分かった。今回は俺が謝ってくる」
「ありがとうございまーす。デザートの方は私が行っときますんで!」
「ったく、グチグチ言わないで最初から行ってやれよ」
まだ店長も社員さんも来そうにないし、これ以上抵抗しても無駄だろう。渋々頷いた途端、火村さんは結構な勢いをつけてピザを台に置き、キッチンの大学生は俺にギリギリ聞こえる声量で呟いてから舌打ちをした。
──やっぱり、こういうのが俺の役回りなのか。
もし俺が火村さんや──学校の姫宮みたいに小柄で華奢で、守ってあげたくなるような容姿だったら、あの大学生の反応も別のものになっただろうか。
「申し訳ございません、お客様。ご注文いただいたピザですがサイズを間違ってしまっ……」
空想に耽っていてもしかたがない、現実で待っているお客様がいるんだ。
さっき教えられたテーブルへ向かい、意を決して絞り出した謝罪の続きは……見覚えのあり過ぎる顔を前に息と一緒に飲み込んでしまった。
「猪狩くん?」
袖に金色の刺繍が入った、黒地でゆったりサイズのパーカー。
ツヤがあり、きちんと手入れされているのだと一目で分かるけど無造作に放置された髪。そこから覗く、ピアスと思われる無骨な銀色。
学校とは随分印象が違うが──ひとり用の席でドリンクバーのホットコーヒー片手にきょとん、と俺を見るライトブラウンの瞳は間違いなく、クラスメイトの姫宮 美来璃のものだ。
「姫宮……」
「びっくりした。ここでバイトしてたんだね」
「あ、ああ。えっと、実は注文してもらったピザのサイズを間違えてしまって……作り直しに時間がかかるんだ。カットして出すことも出来るが、メニューの写真とかなり異なるしトッピングも違うものに……」
状況を飲み込んで次に口を開いた時、知り合いだという安心感からかいつもの話し方になってしまった。しかし姫宮は「ウエイター姿似合うね」と笑っていて、俺の口調はもちろんオーダーミスについても怒ってなさそうだ。
「基本の具材さえ合ってればそれでも全然良いよ」
「本当に申し訳ない、すぐに切って持って来るからもう少し待っててくれ」
「猪狩くんが注文間違えたわけじゃないでしょ?気にしないで」
「……ありがとう」
快く了承してくれた上に優しいフォローまでくれた姫宮に感謝を伝え、温かいうちに届けなければとパントリーへ戻る。ピザのカットを済ませて早速持って行こうとすれば、デザートの配膳を終えた火村さんが目の前に立ちはだかっていた。
「あのお客様、猪狩さんの知り合いですかぁ?」
「ああ。卓に行くまで気づかなかったが、彼は俺が通う高校のクラスメイトなんだ」
「ふぅん……」
火村さんは少し考える素振りを見せた後、俺が持っていたピザを目にも留まらぬ速さで取り上げる。
「火村さん?」
「次は私が行きます!話してるの見てたんですけど思ったより怖くなさそうだったし、あの人が猪狩さんに笑いかけてるとこめっちゃメロくなかったですか!?私もアレ浴びたいんでちゃんと謝ってきますっ」
──また“メロい”か。
今朝優姫も言っていたが、メロいとは一体なんなんだ……?あと、笑いかけてほしいから謝りに行くというのは違うんじゃないか。色々突っ込みたいことが浮かぶ間にも、火村さんは早足で姫宮のいる卓へ行ってしまう。
「大変お待たせいたしましたっ、ご注文のシーフードピザです!」
心配になった俺は、周りの空いたテーブルを片付けながら様子を伺う。いつあの笑みを見けられるかと期待に満ちた火村さんの横顔と、皿が置きやすいようにかコーヒーを端に寄せる姫宮の手元が見えた。
「オーダーミスしちゃってすみませんでしたぁ。私ちょっとこういうとこあって……猪狩さんにも迷惑かけてばっかりで」
謝るだけじゃなく何やら話を広げようとする火村さんに、客に身の上相談する気かと目を疑った……その時だった。
「ほんとだよ」
学校ではまず聞いたことのない姫宮の低い声が耳を掠めて、紙ナプキンを補充していた手が止まる。笑顔を浴びる?つもりが逆に突き放されてしまった火村さんも、少しフリーズした後「え?」と戸惑いをあらわにしていた。
「代わりを行かせといて今さら何しに来たの?俺の友達をあまり困らせないでくれる」
「……っ」
数分前に俺に『気にしないで』と言ってくれた時とはまるで違う姫宮のそっけない対応に面食らったであろう火村さんは、無言で裏へ走っていく。一刻も早く彼女のフォローを、とテーブルの片づけを切り上げたところでレジが混み始めたことに気づき、俺はひとまずそちらを優先することにした。
示し合わせたように次々とやってくるお客様の会計をこなし、あと少しで一段落するという場面で来た最後のひとりは姫宮だ。
「さっきの子、大丈夫?」
受け取った伝票を俺が入力している間、姫宮はレジ横で販売しているお菓子を物色しながら言う。
「泣かせちゃったかも」
「時間前に帰ってしまったみたいだが……週に一度はあることだから大丈夫だ」
「毎週そんなことあったら経営側は大丈夫じゃなさそう」
「一応、この後社員さんに連絡しておく」
「さすが、慣れてるね」
苦笑を浮かべた姫宮が「これもください」とキャラメルを持ってくる。会計をぴったり済ませてレシートといっしょに渡すと──なぜかそれだけ俺の手元に押し戻された。
「これは……?」
「猪狩くんにご褒美」
「ご褒美?」
スーパーやコンビニで見かける物よりひと回りほど小さいキャラメルの箱。バイトが終わるまでユニフォームのポケットに隠しておくにはちょうど良さそうなサイズだ。
「俺……じゃない、僕、学校以外だとこんな感じだからさ。遠目で見た時怖かったでしょ」
「うっ……」
不意の問いかけは図星だっただけに咄嗟に否定が出来なかった。だけど姫宮に気を悪くした様子はない。
「なのに勇気出して来てくれた猪狩くんすごいと思う。よく頑張りました」
身長は姫宮より俺の方が二十センチ近く高いものの、上目遣いではなくしっかりと頭を上げ視線を合わせてくれている。ゆるりと目を細めるところは学校でもよく見るが、愛くるしいイメージのあれとは違い、今は凛々しいというか……精悍という言葉が似合う。
──姫宮はこんな顔もするのか。
──……俺が怖がっていたことに気づいた上で、茶化すことなく労わってくれた。
「じゃ、ごちそうさまでした」
長居は無用とばかりに、ひら、と手を振りながらこちらに背を向ける姫宮。それを「ありがとうございました……」と見送る俺の手には、もらったばかりのキャラメルの箱が握られていた。
◇◇
「劇やるなら絶対異世界ファンタジーだって!世界を統べる女神の役とか、みくりんにぴったりだろ!?」
「いーや、俺は敢えて正統派を推すね。ジュリエット役のみくりんこそ、全人類が求める姿だっ」
姫宮の意外な一面を知った、次の日の学校。
約三カ月後に開催される文化祭で劇をやることになった俺たちのクラスは、LHRの時間を使い演目決めをしている。
「だからお前たち……姫宮の意見を聞けと言ってるだろう」
「まあ、みんな楽しそうだし」
例によって本人の意志を無視して進める月島たちに苦言を呈するが、姫宮はもう諦めているようだ。……そんな彼を隣に、内心ソワソワする俺。
──改めてお礼を言った方が良いのだろうか。
昨日のバイトは、姫宮が客として来なければただ理不尽な目に合って終わっていた。会計の時に『ご褒美』ともらったキャラメルはまだ残っていて、今はお守りのように俺の通学用の鞄に忍ばせている。
しかし、『昨日はありがとう』だなんて言ってるのを月島たちに聞かれたら面倒なことになりそうだ……と何気なく隣を見ると──いつからかこちらに顔を向けていた姫宮と視線がかち合った。
「──しぃ」
「……っ」
俺が何を考えていたか、姫宮に伝わったらしい。
そこだけ見ても端正な顔立ちが伺い知れる口元に人差し指を当て、囁くように言う姿に心臓が跳ねる。……昨日のことを口止めされて怖かったとか、そういうことじゃない。
『顔とか性格が良過ぎてメロメロになるみたいな……』
『あの人が猪狩さんに笑いかけてるとこめっちゃメロくなかったですか!?』
たびたび耳にしたものの意味が分からずにいた“メロい”が、今やっと理解出来た気がした。