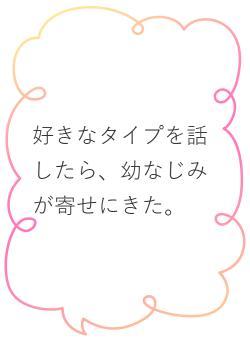「優姫、外に立ってるのお前の彼氏じゃないか?」
「えっ、もう来てる!?」
洗面所にいる妹にリビングから声をかければ、弾かれたようにこちらへやって来る。
「ほんとだ、急かさないで待ってくれてるとか今日もメロ過ぎ……!」
「メロ……?」
窓の外を覗きながら鞄と──紙袋に入った大荷物を持つ妹の口から出た、聞き馴染みのない言葉に首を傾げる俺。
「メロンみたいだ……という意味か?」
「ちがくて、顔とか性格が良過ぎてメロメロになるみたいな……時間ないから後でちゃんと教えてあげる!行ってきますっ」
「行ってらっしゃい。気を付けろよ」
バタバタと忙しなく玄関を出て行く妹が窓の向こうに見える。それを出迎えた俺と同じくらいの背丈の男が、付き合って三カ月経つという彼氏だそうだ。
「おはよ!」
「はよ。荷物今日の家庭科で使うやつ?持つよ」
「あ、ありがとう……!」
「あと段差あるから手、掴まって」
「さすがに慣れてるから大丈夫だよっ」
リビングの窓は換気のために開け放してあったので、落ち着いた彼氏とくすぐったそうな妹の話し声が丸聞こえだ。
──相変わらず、大切にされているようだ。
さて俺もそろそろ支度しなければとリビングを出た時、ひとつの思いが過ぎる。
──羨ましい。
──俺も、優姫みたいに扱われたら。
包容力があり、さりげなく守ってくれる彼氏。その慈しみを受け取るにふさわしい、小柄で愛らしい妹。
夢見心地で洗面台の鏡の前に立つけれど──そこに映った愛らしいとは対極のところにある体格と顔つきが、お前には無理な話だと吐き捨てていた。
◇◇
「よぉ猪狩!しばらく見ない間にまたデカくなったなっ」
「昨日も学校で会っただろう」
「相変わらず屈強な佇まい……。殴り合い挑まれたら勝てない」
「そんなこと挑まない。お前は俺をなんだと思っているんだ……」
妹を見送ってから約一時間後。
登校し教室に入った俺の顔を見るなり好き勝手なことを言う友人たちに、思わずため息が出る。
──“屈強”。
俺・猪狩 雄一の見た目を一言で表すとそうらしい。
高校二年生にして180は優に超える身長、がっしりした肩幅、体質なのか日々の生活の中で自然と付いてしまった厚い筋肉──見た目だけで言えばその評価に間違いはない。クセが出ないよう短く切った黒髪と、赤ん坊の頃からだという鋭い目つきのせいもあると思う。
「猪狩ー、ホラー系脱出ゲームのチケットもらったから一緒に行こうぜ!ここにいる全員誘ったんだけど振られちゃってさぁ」
「行かない。前にも言ったが、俺は怖いのは苦手だ」
「お前までそういうこと言う!つかそのガタイで怖いの苦手は嘘だろっ」
「ちょっ……通してくれ月島」
「うるせー!行くって言うまで絶対退かねぇからな!!」
一年生から同じクラスで親しくしている月島は基本良い奴だがこういう時は少し鬱陶しい。俺は今来たばかりだから鞄くらいは置かせてほしい……と言おうとしたところで、すぐ後ろから人の気配がした。
「やめなよ月島くん」
背中越しだったが、俺の行く手を阻む月島を咎める声で誰だかすぐに分かった。
「猪狩くん困ってるでしょ?」
隣に並んだ時に鼻を掠めたのはシャンプーだろうか、今年同じクラスになるまで男子校で嗅ぐとは思っていなかった華やかな香り。
「おはよ、猪狩くん」
左下から俺の顔を覗き込み、ふわりと笑いかけてくれたのはクラスメイトの姫宮 美来璃。
身長は本人曰く165センチで、しっかりした作りの学ランの上から見ても分かるほど華奢な身体。ぱっちりと開いた、向こう側が見えそうなくらい透き通った印象のライトブラウンの瞳を、その密度をものともせずに上向いたまつ毛が彩っている。耳より少し長いくらいの淡い茶色の髪はさらさらしていて、窓から差す日の光を浴びて煌めいていた。
ここは男子校で、姫宮も例に漏れず男子なのだが……この容姿ならばある日突然『本当は女だ』と打ち明けられても容易に信じることが出来る。
「おはよう、姫み──」
「みくりんーっ!おはよう!!」
「“姫”が来たぞー!」
「うぉおお!!」
今日唯一まともに挨拶してくれた姫宮に答えようとしたけど、俺の目の前からあっさり退いた月島を筆頭に教室に居たクラスメイトが一斉に歓声を上げたことで遮られた。
「姫、チョコ食べる?」
「今日も可愛い。優勝」
「全宇宙の“男子校の姫”がここに集ったとしてもみくりんが一番だよ……!」
「そうそう、みくりんに似合いそうな前髪クリップ買って来たんだよ俺!」
教壇の前にある自分の机に着き、鞄を置いた姫宮を男たちが囲む。時折呼ばれている“姫”というのは名字から取られたあだ名ではなく、今みたいに大勢に愛でられている様が御伽噺に出てくる“お姫様”のようだから……らしい。
「月島、クリップはどっち付けんの?」
「絶っ対に猫。白くてふわふわなとことかみくりんっぽいし!」
「……ほんとだ、めっちゃ似合う!」
「姫とふわふわの親和性ヤバいなっ」
月島が姫宮に買ってきたという前髪を留める用のクリップは、わんこモチーフと猫ちゃんモチーフのふたつセットだった。
「おい」
無許可で姫宮の前髪を留めて盛り上がる周りに見かねた俺は、月島たちが陣取る前の方へ早足で向かう。
「勝手に着けるのも良くないがせめて好みを聞いてやれ。姫宮が犬派だったらどうするんだ」
「こんな目つきの悪い犬、みくりんが選ぶわけないだろっ」
「つか猪狩は教壇登んなっ。ただでさえもデカいのに威圧感半端ないから!」
姫宮の机の周りは入る隙がなかったので、仕方なく教壇に上がって注意したものの一蹴された。結局月島は残ったわんちゃんのクリップを回収し、姫宮には問答無用で猫ちゃんのクリップが宛がわれてしまう(どうでも良いが、俺が心の中でわんちゃん猫ちゃんなんて言ってるのがこいつらに知られたら鼻で笑われるに違いない)。
「猪狩くん、僕はどっちも可愛いと思ってたから気にしないで?」
「姫宮がそう言うなら……」
「クリップありがとう月島くん。最近よくこういうのくれるけど、どこで買ってるの?」
「よくぞ聞いてくれました!家の近くに良い感じの雑貨屋が出来てさぁ──」
前髪にクセを付けないためか緩めに留め直されたクリップは確かに、月島の話を興味深そうに聞くあどけない横顔に似合っている。しかし姫宮が毎日のようにもらうプレゼントはちゃんと相手の好みを考えたのか疑わしい物ばかりで、つい俺が口を挟んでしまうが……本人はさほど気にしていないようだ。
「月島、そろそろ着替えなきゃじゃね?」
「あ、マジだ。みくりんっ、体育はそのクリップ付けたまま出てな!」
数分して、壁にかかった時計を見た月島たちが姫宮から離れて行く。今日の一時間目は体育だから早めにジャージに着替えるつもりなんだろう、俺もそれに続くべく教壇を下りようとした瞬間──下まで割と高さがあることに気づき、転がり落ちたらどうしようという不安に駆られる。
「猪狩くん」
そんな俺の心中を知ってか知らずか、下側からさっと手を差し出してくれたのは──……まさかの姫宮だった。
「良かったら掴まって」
「あ、ありがとう……」
月島たちに見られたら絶対からかわれると一瞬迷ったが、思い切ってその細長い手指を取れば存外安定感があり簡単に降りれた。離れながらもう一度礼を言う俺に、満足そうに笑う姫宮。
少し恥ずかしいが、嬉しい。彼氏が迎えに来た時の優姫もこんな気持ちだったのだろうか。
──出来ることなら、こんな感じでさりげなくリードしてくれる男性と付き合いたい。
──でも、叶わない願いだ。
席に戻るなり、躊躇いなく学ランを脱ぎジャージに着替えようとする姫宮からなんとなく目を逸らして思う。
本当は俺だって大事に扱われたい。それこそ、御伽噺に出て来るお姫様みたいに。……だけど体格から考えれば俺は明らかに守る側で、自分よりずっと小柄な姫宮に手を貸してもらうのは情けないことなのだ。
「今日の体育なんだっけ?」
「バスケのミニゲーム」
「猪狩いるチームの勝ち確じゃん」
「じゃあ一番先に体育館着いた奴が猪狩獲得ってことで!」
いつの間にか上下ジャージに着替えた月島たちが、そんなことを話しながら朝のHRが始まるのを待っている。
──アイツらには悪いが、今日はバイトもあるしほどほどでやらせてもらおう。
──信じてもらえなさそうだけど、球技は苦手だし。
そう心に決めた直後校内に響いた予鈴に、まだ着替えてなかった俺は慌てて自分の机に戻るのだった。