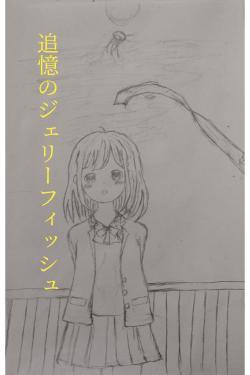「中川優花さんだよね?よろしく!」
席替えで今さっき隣の席になった伊波くんが私に向かって声をあげる。
「あ、うん。よろしく」
それに驚いた私は、その様子に怖気付きながら、小さく返事をした。
それに対してまた伊波くんは冷たいなーなんて言っていたけれど、私はにこっとわらって心の内を誤魔化しておいた。
別にいつもと何も変わらない。ただ無難に、静かに毎日をやり過ごす。今の私に与えられた使命はそれだけだ。
もう、誰にも失望なんてされたくないから――
一日の授業が全て終わり、帰りの挨拶を済ませて、私は校舎を出た。
部活には入っていないから、ほかの部の子達の練習を横目に駐輪場へと向かう。放課後の騒々しさを後ろに背負いながら、私は鍵を自転車に突き刺して右に回した。
――カシャン
鍵の解ける音が二重になって耳に聞こえてきた気がして、ふと顔を上げると目の前にくすっと笑った顔の伊波くんがいた。
「全然気づかねえの」
私はぎょっとした。伊波くんは誰にでも喋りかけるタイプの人だから、気まぐれで目の前にいる私に話しかけたのだろう。でも、私はあまり話すのが得意ではないから、正直なところこうして伊波くんに話しかけられるのはなんだかとても苦しかった。
私がなんて答えようか考えていると、それを察したのか
「じゃあ俺今からカラオケ行くから帰るわ」
と言っていきなり自転車を漕いで学校を出ていった。
それに安堵しながら、私もゆっくりと家までの道をたどっていく。
見上げた先の空には、大きな羽のような形の雲が辺り一面を覆っていた。
「ただいま」
「おかえり。もう晩御飯できてるから」
「うん」
母と淡白な会話を交わして、何とか夕飯の席に着く。
「いただきます」
重ね合わせた手のひらを引き剥がし、勢いよく箸と茶碗を掴み取る。
「優花」
白米ををかきこんでいると、近くに座っていた父に喋りかけられた。
「優花はほんとにもうやらなくていいの?高校からでも部活でやり直したらいいんじゃない」
そう言って見せられたのは、プールが一面に描かれた一枚のチラシ。
3年前のこの時期、私は続けてきた水泳を辞めた。
両親はまだ続けた方がいいと言ってくれていたけれど、私はあの子の期待に応えられなくて、向けられる失望の目に、耐えられなかった。
――「俺、優花の泳ぎ好きなんだよね」
3年前のあの時、同じスイミングスクールに通っていたナツが喋りかけてきた。ナツという呼び方は、出会ってすぐに私がつけたあだ名。
「速いのもそうなんだけど、こう、水の中の優花ってなんかめっちゃ強くて、うおおおおっ!て見てる俺まで燃え上がってくんの」
「ふっ。なにそれ、いきなり褒めてそれかよ!褒めるならちゃんと褒めて!」
あまりの物言いに、思わず吹き出してしまった。
「いや、めっちゃ褒めてる!本気で褒めてるから!」
必死に弁明するナツがまた面白くて、辺りには私の笑い声が響き渡った。
そうして少し話が途切れたところで、ナツはすうっと息を吸って、
「だから、俺応援してる。全国行くの期待してるから」
といつになく落ち着いた面持ちで私を応援してくれた。その言葉に、私はなんだか心が締まるような気がした。
「ありがとう。頑張るね。ナツは緊張で震えて失格くらいが関の山かな。あ、ごめんその前にナツ市大会で終わりか」
「失格が関の山ってなんだよ!俺だって地区大会はいける実力あるから!」
今はなんだか思いっきり笑っていたくて、ついナツをからかってしまう。
「うそうそ。ナツも頑張ってよ?」
少しおどけたようすでナツを励ます。
「おう!一緒に頑張ろうな!」
そう言ってナツが拳をこちらに差し出してきたので、それにグーを作って重ね合わせる。ナツの手は私の手よりも随分と大きかった。
しかし、最後のチャンスである地方大会で、標準タイムに0.2秒届かず、私は全国大会への出場権を逃した。
控え室でばかみたいに泣き喚く私を彼はじっと見ていた。それからゆっくりと私に近寄ってきて、"もう優花は頑張ったから大丈夫だよ"と言ってくれた。
きっと彼は優しさで私に声をかけてくれたのだと思う。けれど、その優しさが余計に涙腺を刺激して、何も言い出せなかったのを覚えている。
それから少しして、私は水泳をやめてしまった。大会後もしばらくの間は練習で彼と会う機会もあったけれど、話しかけることも話しかけられることもなかった。きっと、私の結果と態度に呆れたのだと思う。
結局、あの日せっかく応援に来てくれていた彼に、何も言えずに関係は途絶えてしまった。
――「優花?」
当時のことを思い出していたら、父に怪訝そうに顔を覗き込まれた。掌に不快感を覚え、見ると酷く汗で滲んでいる。
「もうほんとに、やらなくていいから…」
「ねえゆうかー!!」
登校してクラスに入った途端、友達の美来が騒がしい様子でこちらに駆けてきた。
「どうしたのそんなに慌てて」
聞くと、美来は嬉しそうに笑んで、喋り始めた。
「来週の祝日ね中谷くんのグループ3人と遊びに行くことになって、こっちも何人か誘うって言ってあるから優花も行かない?」
「んー、他に誰か誘う?」
「今のとこ優花しか誘わないつもり。1人は流石に無理だけどライバルは増やしたくないし」
美来は中谷くんに気があると言っていたから、そのことだと思う。けれどその言い方だと私がどん臭くて絶対ライバルにはならないって意味なのだろうか。もしそうなら行きたくないななんて思ったり、でも断ったら雰囲気悪くなるかななんて考えたりしていると、真正面から美来が早く早くと決断を迫ってきた。
「んーーー」
(やっぱり断れば良かったかも…)
楽しそうに喋る美来と中谷くんを横目に見ながらそう思う。あの後、結局美来に押し切られて行くことにしてしまった。しかも他にいるのは中谷くんグループの伊波くんと服部くんだけだから喋る相手もいない。
そうしてしばらくお祭り会場の浜辺を歩いていくと、屋台と人の量がだんだんと増えてきて、お祭りらしい雰囲気が漂ってきた。
私はやけくそになって、近くにあったベビーカステラを買って口に放り込んでいた。
すると突然、中谷くんが伊波くんと服部くんの方に近寄ってきて、何やら三人でコソコソと話している。
話し終えるや否や、二人はガッツポーズで中谷くんを送り出す。中谷くんは酷く緊張していて、それを察したのか美来も何だか落ち着かない様子だった。離れていった二人を見届けると、今度は伊波くんが服部くんに向かってなにか喋っている。
聞き耳を立てると服部くんが俺ぼっちじゃんとか何とかぼやいているのが聞こえてきた。
なんの話しをしているのだろうと考えていると伊波くんがちらりとこちらに目をやった。
「中川!ついてきて」
そういうと伊波くんはなんの躊躇いもなく私の手を取った。
「えっ!?」
あまりに突然のことで、私は抵抗する暇もなく、伊波くんの手に引っ張られてしまう。
「ごめん服部!帰ってきたら奢ってやるからベビーカステラでも食べといてくれー!!」
それだけを言い残して、私と伊波くんは夕日の落ちる方へと走っていく。
「何なの伊波くん」
少し行ったところで私が聞くと、伊波くんはぴたりと止まって、何だか懐かしい笑顔でこちらを向いた。
「俺のこと誰かわかる?」
「いや、誰ってクラスメイトの伊波く…」
そこで蘇った記憶に、思わず声を漏らす。
「え…ナツ…?」
名前を呼んだ瞬間、まるで時が止まったように、辺り一帯が凪いだ。
「そうだよ。全然気づかねえの」
「え、え、うそ、」
混乱する様子の私に構うことなくナツは喋り続ける。
「なんか急に水泳来なくなっちゃうし。高校入学したらなんか同じクラスにいるし。俺のこと覚えてなかったし」
「いや、だって、あの時私、ナツに呆れられたと思ってたから…あとナツ雰囲気変わりすぎだもん、髪の毛も体型も、メガネまで。それに、名前だってナツとしか呼んでなかったから…」
「呆れるなんてそんなわけねえじゃん。俺ずっと優花に憧れてきたんだぞ」
「そう、だったんだ…」
言いたいことがありすぎて、次から次へと言葉が口からついてでる。けれど、今一番に言わなければいけないことがなにかくらいは私にもわかる。
荒れる心を落ち着かせて、ゆっくりと海風を吸い込む。
「あの時はごめん。あと、ありがとう」
「俺も、あの後もっとちゃんと話せばよかった。ごめん」
私の中では安堵が溢れかえって、それが目の中に水滴となって溜まっていってしまった。
その私を見て、ナツが思いっきり私を抱きしめた。
ぎゅうううって苦しいくらいの力で抱きしめた。
「俺、優花のことめっちゃすごくて強いやつだと思ってたけど、俺より全然弱いじゃねえか…」
ナツの懐かしい温もりに、凍って動かなくなっていた私の心は溶かされて、いよいよ涙が止まらなくなってしまった。
それからしばらくして、たまたま隣を通った大人に今の様子を見られてしまった私は、ナツを突き放して誤魔化すようにベビーカステラを全て口の中に放り込んだ。
そして思いっきり飛び上がって。
海に飛び込んだ。
「え、ちょ、ゆうか!」
酷く慌てる様子のナツに向かって
「ナツみたいに暑苦しいやつめー!」
と大声で叫んでやった。
「ゆうかー!!」
プールサイドから私を呼ぶ声が飛んでくる。きらりと光った茶髪に小さくガッツポーズをみせて、気合を入れる。目の前には、青空をそのまま映し出したような、真っ青な水面が一面に広がっていた。
「ピーー!」
用意の笛が、辺りに鳴り響く。ゆっくりとスタート台に乗って、向こう側のゴールを見渡す。
私は、今日からまた新しいスタートを切るんだ。
「take your mark」
席替えで今さっき隣の席になった伊波くんが私に向かって声をあげる。
「あ、うん。よろしく」
それに驚いた私は、その様子に怖気付きながら、小さく返事をした。
それに対してまた伊波くんは冷たいなーなんて言っていたけれど、私はにこっとわらって心の内を誤魔化しておいた。
別にいつもと何も変わらない。ただ無難に、静かに毎日をやり過ごす。今の私に与えられた使命はそれだけだ。
もう、誰にも失望なんてされたくないから――
一日の授業が全て終わり、帰りの挨拶を済ませて、私は校舎を出た。
部活には入っていないから、ほかの部の子達の練習を横目に駐輪場へと向かう。放課後の騒々しさを後ろに背負いながら、私は鍵を自転車に突き刺して右に回した。
――カシャン
鍵の解ける音が二重になって耳に聞こえてきた気がして、ふと顔を上げると目の前にくすっと笑った顔の伊波くんがいた。
「全然気づかねえの」
私はぎょっとした。伊波くんは誰にでも喋りかけるタイプの人だから、気まぐれで目の前にいる私に話しかけたのだろう。でも、私はあまり話すのが得意ではないから、正直なところこうして伊波くんに話しかけられるのはなんだかとても苦しかった。
私がなんて答えようか考えていると、それを察したのか
「じゃあ俺今からカラオケ行くから帰るわ」
と言っていきなり自転車を漕いで学校を出ていった。
それに安堵しながら、私もゆっくりと家までの道をたどっていく。
見上げた先の空には、大きな羽のような形の雲が辺り一面を覆っていた。
「ただいま」
「おかえり。もう晩御飯できてるから」
「うん」
母と淡白な会話を交わして、何とか夕飯の席に着く。
「いただきます」
重ね合わせた手のひらを引き剥がし、勢いよく箸と茶碗を掴み取る。
「優花」
白米ををかきこんでいると、近くに座っていた父に喋りかけられた。
「優花はほんとにもうやらなくていいの?高校からでも部活でやり直したらいいんじゃない」
そう言って見せられたのは、プールが一面に描かれた一枚のチラシ。
3年前のこの時期、私は続けてきた水泳を辞めた。
両親はまだ続けた方がいいと言ってくれていたけれど、私はあの子の期待に応えられなくて、向けられる失望の目に、耐えられなかった。
――「俺、優花の泳ぎ好きなんだよね」
3年前のあの時、同じスイミングスクールに通っていたナツが喋りかけてきた。ナツという呼び方は、出会ってすぐに私がつけたあだ名。
「速いのもそうなんだけど、こう、水の中の優花ってなんかめっちゃ強くて、うおおおおっ!て見てる俺まで燃え上がってくんの」
「ふっ。なにそれ、いきなり褒めてそれかよ!褒めるならちゃんと褒めて!」
あまりの物言いに、思わず吹き出してしまった。
「いや、めっちゃ褒めてる!本気で褒めてるから!」
必死に弁明するナツがまた面白くて、辺りには私の笑い声が響き渡った。
そうして少し話が途切れたところで、ナツはすうっと息を吸って、
「だから、俺応援してる。全国行くの期待してるから」
といつになく落ち着いた面持ちで私を応援してくれた。その言葉に、私はなんだか心が締まるような気がした。
「ありがとう。頑張るね。ナツは緊張で震えて失格くらいが関の山かな。あ、ごめんその前にナツ市大会で終わりか」
「失格が関の山ってなんだよ!俺だって地区大会はいける実力あるから!」
今はなんだか思いっきり笑っていたくて、ついナツをからかってしまう。
「うそうそ。ナツも頑張ってよ?」
少しおどけたようすでナツを励ます。
「おう!一緒に頑張ろうな!」
そう言ってナツが拳をこちらに差し出してきたので、それにグーを作って重ね合わせる。ナツの手は私の手よりも随分と大きかった。
しかし、最後のチャンスである地方大会で、標準タイムに0.2秒届かず、私は全国大会への出場権を逃した。
控え室でばかみたいに泣き喚く私を彼はじっと見ていた。それからゆっくりと私に近寄ってきて、"もう優花は頑張ったから大丈夫だよ"と言ってくれた。
きっと彼は優しさで私に声をかけてくれたのだと思う。けれど、その優しさが余計に涙腺を刺激して、何も言い出せなかったのを覚えている。
それから少しして、私は水泳をやめてしまった。大会後もしばらくの間は練習で彼と会う機会もあったけれど、話しかけることも話しかけられることもなかった。きっと、私の結果と態度に呆れたのだと思う。
結局、あの日せっかく応援に来てくれていた彼に、何も言えずに関係は途絶えてしまった。
――「優花?」
当時のことを思い出していたら、父に怪訝そうに顔を覗き込まれた。掌に不快感を覚え、見ると酷く汗で滲んでいる。
「もうほんとに、やらなくていいから…」
「ねえゆうかー!!」
登校してクラスに入った途端、友達の美来が騒がしい様子でこちらに駆けてきた。
「どうしたのそんなに慌てて」
聞くと、美来は嬉しそうに笑んで、喋り始めた。
「来週の祝日ね中谷くんのグループ3人と遊びに行くことになって、こっちも何人か誘うって言ってあるから優花も行かない?」
「んー、他に誰か誘う?」
「今のとこ優花しか誘わないつもり。1人は流石に無理だけどライバルは増やしたくないし」
美来は中谷くんに気があると言っていたから、そのことだと思う。けれどその言い方だと私がどん臭くて絶対ライバルにはならないって意味なのだろうか。もしそうなら行きたくないななんて思ったり、でも断ったら雰囲気悪くなるかななんて考えたりしていると、真正面から美来が早く早くと決断を迫ってきた。
「んーーー」
(やっぱり断れば良かったかも…)
楽しそうに喋る美来と中谷くんを横目に見ながらそう思う。あの後、結局美来に押し切られて行くことにしてしまった。しかも他にいるのは中谷くんグループの伊波くんと服部くんだけだから喋る相手もいない。
そうしてしばらくお祭り会場の浜辺を歩いていくと、屋台と人の量がだんだんと増えてきて、お祭りらしい雰囲気が漂ってきた。
私はやけくそになって、近くにあったベビーカステラを買って口に放り込んでいた。
すると突然、中谷くんが伊波くんと服部くんの方に近寄ってきて、何やら三人でコソコソと話している。
話し終えるや否や、二人はガッツポーズで中谷くんを送り出す。中谷くんは酷く緊張していて、それを察したのか美来も何だか落ち着かない様子だった。離れていった二人を見届けると、今度は伊波くんが服部くんに向かってなにか喋っている。
聞き耳を立てると服部くんが俺ぼっちじゃんとか何とかぼやいているのが聞こえてきた。
なんの話しをしているのだろうと考えていると伊波くんがちらりとこちらに目をやった。
「中川!ついてきて」
そういうと伊波くんはなんの躊躇いもなく私の手を取った。
「えっ!?」
あまりに突然のことで、私は抵抗する暇もなく、伊波くんの手に引っ張られてしまう。
「ごめん服部!帰ってきたら奢ってやるからベビーカステラでも食べといてくれー!!」
それだけを言い残して、私と伊波くんは夕日の落ちる方へと走っていく。
「何なの伊波くん」
少し行ったところで私が聞くと、伊波くんはぴたりと止まって、何だか懐かしい笑顔でこちらを向いた。
「俺のこと誰かわかる?」
「いや、誰ってクラスメイトの伊波く…」
そこで蘇った記憶に、思わず声を漏らす。
「え…ナツ…?」
名前を呼んだ瞬間、まるで時が止まったように、辺り一帯が凪いだ。
「そうだよ。全然気づかねえの」
「え、え、うそ、」
混乱する様子の私に構うことなくナツは喋り続ける。
「なんか急に水泳来なくなっちゃうし。高校入学したらなんか同じクラスにいるし。俺のこと覚えてなかったし」
「いや、だって、あの時私、ナツに呆れられたと思ってたから…あとナツ雰囲気変わりすぎだもん、髪の毛も体型も、メガネまで。それに、名前だってナツとしか呼んでなかったから…」
「呆れるなんてそんなわけねえじゃん。俺ずっと優花に憧れてきたんだぞ」
「そう、だったんだ…」
言いたいことがありすぎて、次から次へと言葉が口からついてでる。けれど、今一番に言わなければいけないことがなにかくらいは私にもわかる。
荒れる心を落ち着かせて、ゆっくりと海風を吸い込む。
「あの時はごめん。あと、ありがとう」
「俺も、あの後もっとちゃんと話せばよかった。ごめん」
私の中では安堵が溢れかえって、それが目の中に水滴となって溜まっていってしまった。
その私を見て、ナツが思いっきり私を抱きしめた。
ぎゅうううって苦しいくらいの力で抱きしめた。
「俺、優花のことめっちゃすごくて強いやつだと思ってたけど、俺より全然弱いじゃねえか…」
ナツの懐かしい温もりに、凍って動かなくなっていた私の心は溶かされて、いよいよ涙が止まらなくなってしまった。
それからしばらくして、たまたま隣を通った大人に今の様子を見られてしまった私は、ナツを突き放して誤魔化すようにベビーカステラを全て口の中に放り込んだ。
そして思いっきり飛び上がって。
海に飛び込んだ。
「え、ちょ、ゆうか!」
酷く慌てる様子のナツに向かって
「ナツみたいに暑苦しいやつめー!」
と大声で叫んでやった。
「ゆうかー!!」
プールサイドから私を呼ぶ声が飛んでくる。きらりと光った茶髪に小さくガッツポーズをみせて、気合を入れる。目の前には、青空をそのまま映し出したような、真っ青な水面が一面に広がっていた。
「ピーー!」
用意の笛が、辺りに鳴り響く。ゆっくりとスタート台に乗って、向こう側のゴールを見渡す。
私は、今日からまた新しいスタートを切るんだ。
「take your mark」