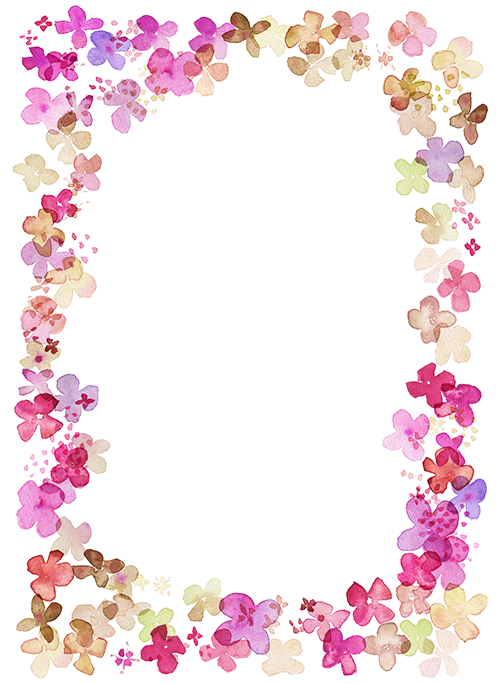『あなたに、会いたい。』
***
チリン
と、いつもの鈴の音が聞こえた。
「今日も来たの?」
私が窓を開けると、彼女は私の膝の上に乗ってきた。
「ほんと、毛並みがいいねぇ。」
彼女を撫でながら呟く。
「みにゃぁ…」
彼女が気持ちよさそうに鳴いて、すりすりと擦り寄ってくる。
「今夜も月が綺麗だね。」
彼女も私の言葉に賛成するように一鳴きした。
「もうすぐ、流星群がくるらしいよ?」
彼女は首を傾げて、小さく、可愛らしい声で鳴いた。
その愛おしい鳴き声に思わず彼女を抱き寄せる。
「ねぇ、そっちでは元気してるの?」
彼女に聞いてみる。
私の声なんて聞いていないような素振りで、彼女が私の腕からすり抜けて、リビングの方に歩いていく。
「どうしたの?」
そう言いながら立ち上がって、彼女についていく。
振り返ると暗い部屋には、パソコンの画面が爛々と光っていた。
***
彼女が初めてここに来たのは大体3ヶ月前くらいのこと。
星空が輝き、満月が光り輝いていた夜。
いつものように窓辺でパソコンの作業をしていた時に、チリンと鈴の音が聞こえてきた。
不思議に思って窓を引き上げると、そこには闇に沈み込むように黒猫が座っていた。
「こんばんわ。」
私が声をかけると、返事をするように小さく鳴いて、そのまま家に入り込んできた。
彼女には首輪が付いていて、何かが書いてあるプレートがついていた。
よく見ると、彼女の名前と住所が書いてあった。
彼女の名前は『みみ』というそうだ。
とっても可愛らしい名前だ。
そのプレートをひっくり返せば、
「この子はよく外に行くので、来たら遊んでやってください。」
と、飼い主からのメッセージがあった。
みみちゃんはお行儀良くおすわりをして、私がその情報を得るまで待っていた。
みみちゃんはまるで私の家に来たことがあるような足取りで、すぐさまキッチンへ向かった。
「ミルク?」
冷蔵庫の前で止まったみみちゃんは、頷くようににゃあと鳴いた。
冷蔵庫から牛乳を取り出し、飲みやすそうなお皿に注ぐ。
「冷たいままで大丈夫?」
そう声をかけると、みみちゃんはお皿の前に立ち尽くしたので、マグカップに注ぎ直した牛乳を電子レンジにかける。
その牛乳を再度お皿に入れて床に置く。
するとみみちゃんが近づいて、恐る恐る舌をつけた。
「んにゃっ」
みみちゃんの小さな叫びが聞こえる。
「猫舌なの?」
私の声を無視するようにそっぽを向いてしまう。
たしかに、少し熱すぎたかもしれない。
冷たい牛乳と混ぜながら、生ぬるいと感じるところまで調整して、みみちゃんを呼ぶ。
「みみちゃん、飲む?」
私の声に反応するように耳がぴくっと動き、牛乳を飲みにやってきた。
ぴちゃぴちゃとみみちゃんが牛乳を飲む音が響く。
ひとり暮らしには広すぎるリビングが、より一層みみちゃんの存在を際立たせていた。
***
そんな3ヶ月前の出会いを思い出しながら暗い部屋を出て、リビングについたみみちゃんはソファに飛び乗った。
そして、私を呼ぶように可愛らしい声で鳴く。
その声に惹きつけられるように私は、ソファにゆっくりと腰掛ける。
あぁ。こうして、誰かとこの大きなソファに座るのは何年ぶりなんだろう。
懐かしい思い出が蘇ってきそうで、咄嗟に頬を叩く。
私は、そんなことをしている場合じゃない。
前を向かなきゃ。過去を振り返らず、進まなきゃ。
謎に頬を叩いた私を、みみちゃんは見つめていた。
その、青く光る瞳で。
***
「みみちゃん?そろそろ寝るよ?」
みみちゃんとソファでドラマを見て、夕ご飯を食べて、お風呂に入って…と一通り夜すべきことは終わらせた。
みみちゃんは大抵一緒に寝るが、朝になるといなくなっている。
みみちゃんは多い時で週に1回、少ない時で1ヶ月に1回程度現れる。
それも、私の仕事が少なく、比較的余裕のある時に。
そんなことを考えていると、みみちゃんが足元を通り過ぎた。
これで4回目だ。
なんだか、今日のみみちゃんは落ち着きがない。
家の中をあちこち歩き回って、何かを探している様子だ。
もしかして、あれを探しているのだろうか。
うちには比較的大きいタンスがある。
その前には小さなラグが敷いてあって、みみちゃんはよくそのラグの上にいた。
でも、そのタンスはもう入れる物もなくなり、明日の粗大ゴミに出そうと玄関に置いてある。
「みみちゃん、タンス探してる?」
聞いてみると頷くように一鳴きした。
「ごめんね、もう粗大ゴミに出しちゃうんだ。ラグならあっちのお部屋にあるから、許してくれる?」
「にゃっ!」
みみちゃんは拒絶するように強く鳴いた。
「タンスなら、玄関にあるよ?」
みみちゃんはピクっと耳を反応させ、玄関に走った。
そんなみみちゃんを追いかけると、一番下の段を開けようと前足で引っ掻いていた。
「ここに何かあるの?」
ここ掘れワンワンみたいな感じで何かがあるんだと思った私は、一番下の段を開ける。
でも、中身は空っぽで、何も無かった。
「何も無いからしめちゃうよ?」
タンスの中に入り込んでしまったみみちゃんに声をかける。
持ち上げようとしてもみみちゃんは暴れて、タンスから出ようとしない。
そして、タンスの上の方を引っ掻き始めた。
「みみちゃん、引っ掻いちゃダメだよ?」
優しくなだめるも、みみちゃんはやめてくれない。
思わずタンスを覗き込むと、1つの封筒が張り付いていた。
もう黄ばんでいて、かなり古いもののように思える。
封筒をひっくり返すと、宛名の欄には私の名前が書かれていた。
その字は懐かしくて、私がずっと求めていた字で。
これが何なのかを知る前に、涙が頬をつたった。
***
私には夫がいた。でも、その夫のことを『元』旦那と呼べるかなんて、分からない。
だって、もう死んでしまったのだから。
彼は優しい人だった。誰にでも、等しく接する素敵な人だった。
そんなところに、私は心を惹かれた。
付き合ってからも、結婚してからも、彼の誠実さは変わらず、私を一途に愛してくれていた。
『墨ちゃんのこと、一生幸せにする。』
『ほんとに村井にしちゃっていいの?霧ヶ丘って苗字かっこいいのに。』
結婚する時も、私が霧ヶ丘という苗字を気に入ってるのを気にしてくれた。
でも私は、彼と一緒の苗字になりたかった。
村井墨って、なんだか名前の並びが素朴で可愛らしかった。
『もうちょっと安定したら可愛い娘か息子が欲しいね。きっと墨ちゃんに似て、元気で明るい子だよ。』
私は元気で可愛い娘が欲しいと、ことあるごとに言っていた。
『墨ちゃん、ずっと愛してるよ。おやすみ。』
この言葉は毎晩の、寝る前の合言葉だった。
きっと彼は今も、愛してくれていると、私は信じている。
彼がこの世から消えたのは、ほんの一瞬の出来事だった。
あのトラックの運転手を、何度恨んだか分からない。
小さな男の子が飛び出したのを助け、夫は代わりに死んだ。
夫が、男の子を助けたヒーローのように報道されることが悔しくて、本当に悔しくてたまらなかった。
男の子のことは恨まなかった。だってその子は、青信号なことを確認してから走り出したのだもの。
だから私の怒りも恨みも悔しさも、全てがトラックの運転手に向いた。
あいつは飲酒運転をしていた。
事件後1週間ほど経って、刑務所に呼ばれ、あいつからの謝罪があるかと思いきや突然の面会拒否。
そこから6年。1度たりとも謝られたことはない。
こんな胸の苦しさを、どうやって紛らわせるのか。
そんなの分かりっこなかった。
夫がいなくなってから、ずっと厳しい生活が続いた。
生きる希望なんて、到底どこにもなかった。
苦しさからか、難聴が再発した。
小学5年生の時に罹った難聴は、高校に上がる頃には治っていたが、再発の恐れがあると言われていた。
いちばん恐れていたそれが、現実になったのだ。
また、補聴器で暮らす日々に逆戻りだ。
私は、夫が戻ってくるならば耳も声も口も、何もかも差し出すというのに。
***
涙でぼやける視界の奥の、黄ばんだ封筒を見つめる。
綺麗に、整った字があった。
『村井墨様、もしくは霧ヶ丘墨様へ』
あぁ、この字は。
多分、いいや絶対。
私の夫、村井良二のものだ。
***
チリン
と、いつもの鈴の音が聞こえた。
「今日も来たの?」
私が窓を開けると、彼女は私の膝の上に乗ってきた。
「ほんと、毛並みがいいねぇ。」
彼女を撫でながら呟く。
「みにゃぁ…」
彼女が気持ちよさそうに鳴いて、すりすりと擦り寄ってくる。
「今夜も月が綺麗だね。」
彼女も私の言葉に賛成するように一鳴きした。
「もうすぐ、流星群がくるらしいよ?」
彼女は首を傾げて、小さく、可愛らしい声で鳴いた。
その愛おしい鳴き声に思わず彼女を抱き寄せる。
「ねぇ、そっちでは元気してるの?」
彼女に聞いてみる。
私の声なんて聞いていないような素振りで、彼女が私の腕からすり抜けて、リビングの方に歩いていく。
「どうしたの?」
そう言いながら立ち上がって、彼女についていく。
振り返ると暗い部屋には、パソコンの画面が爛々と光っていた。
***
彼女が初めてここに来たのは大体3ヶ月前くらいのこと。
星空が輝き、満月が光り輝いていた夜。
いつものように窓辺でパソコンの作業をしていた時に、チリンと鈴の音が聞こえてきた。
不思議に思って窓を引き上げると、そこには闇に沈み込むように黒猫が座っていた。
「こんばんわ。」
私が声をかけると、返事をするように小さく鳴いて、そのまま家に入り込んできた。
彼女には首輪が付いていて、何かが書いてあるプレートがついていた。
よく見ると、彼女の名前と住所が書いてあった。
彼女の名前は『みみ』というそうだ。
とっても可愛らしい名前だ。
そのプレートをひっくり返せば、
「この子はよく外に行くので、来たら遊んでやってください。」
と、飼い主からのメッセージがあった。
みみちゃんはお行儀良くおすわりをして、私がその情報を得るまで待っていた。
みみちゃんはまるで私の家に来たことがあるような足取りで、すぐさまキッチンへ向かった。
「ミルク?」
冷蔵庫の前で止まったみみちゃんは、頷くようににゃあと鳴いた。
冷蔵庫から牛乳を取り出し、飲みやすそうなお皿に注ぐ。
「冷たいままで大丈夫?」
そう声をかけると、みみちゃんはお皿の前に立ち尽くしたので、マグカップに注ぎ直した牛乳を電子レンジにかける。
その牛乳を再度お皿に入れて床に置く。
するとみみちゃんが近づいて、恐る恐る舌をつけた。
「んにゃっ」
みみちゃんの小さな叫びが聞こえる。
「猫舌なの?」
私の声を無視するようにそっぽを向いてしまう。
たしかに、少し熱すぎたかもしれない。
冷たい牛乳と混ぜながら、生ぬるいと感じるところまで調整して、みみちゃんを呼ぶ。
「みみちゃん、飲む?」
私の声に反応するように耳がぴくっと動き、牛乳を飲みにやってきた。
ぴちゃぴちゃとみみちゃんが牛乳を飲む音が響く。
ひとり暮らしには広すぎるリビングが、より一層みみちゃんの存在を際立たせていた。
***
そんな3ヶ月前の出会いを思い出しながら暗い部屋を出て、リビングについたみみちゃんはソファに飛び乗った。
そして、私を呼ぶように可愛らしい声で鳴く。
その声に惹きつけられるように私は、ソファにゆっくりと腰掛ける。
あぁ。こうして、誰かとこの大きなソファに座るのは何年ぶりなんだろう。
懐かしい思い出が蘇ってきそうで、咄嗟に頬を叩く。
私は、そんなことをしている場合じゃない。
前を向かなきゃ。過去を振り返らず、進まなきゃ。
謎に頬を叩いた私を、みみちゃんは見つめていた。
その、青く光る瞳で。
***
「みみちゃん?そろそろ寝るよ?」
みみちゃんとソファでドラマを見て、夕ご飯を食べて、お風呂に入って…と一通り夜すべきことは終わらせた。
みみちゃんは大抵一緒に寝るが、朝になるといなくなっている。
みみちゃんは多い時で週に1回、少ない時で1ヶ月に1回程度現れる。
それも、私の仕事が少なく、比較的余裕のある時に。
そんなことを考えていると、みみちゃんが足元を通り過ぎた。
これで4回目だ。
なんだか、今日のみみちゃんは落ち着きがない。
家の中をあちこち歩き回って、何かを探している様子だ。
もしかして、あれを探しているのだろうか。
うちには比較的大きいタンスがある。
その前には小さなラグが敷いてあって、みみちゃんはよくそのラグの上にいた。
でも、そのタンスはもう入れる物もなくなり、明日の粗大ゴミに出そうと玄関に置いてある。
「みみちゃん、タンス探してる?」
聞いてみると頷くように一鳴きした。
「ごめんね、もう粗大ゴミに出しちゃうんだ。ラグならあっちのお部屋にあるから、許してくれる?」
「にゃっ!」
みみちゃんは拒絶するように強く鳴いた。
「タンスなら、玄関にあるよ?」
みみちゃんはピクっと耳を反応させ、玄関に走った。
そんなみみちゃんを追いかけると、一番下の段を開けようと前足で引っ掻いていた。
「ここに何かあるの?」
ここ掘れワンワンみたいな感じで何かがあるんだと思った私は、一番下の段を開ける。
でも、中身は空っぽで、何も無かった。
「何も無いからしめちゃうよ?」
タンスの中に入り込んでしまったみみちゃんに声をかける。
持ち上げようとしてもみみちゃんは暴れて、タンスから出ようとしない。
そして、タンスの上の方を引っ掻き始めた。
「みみちゃん、引っ掻いちゃダメだよ?」
優しくなだめるも、みみちゃんはやめてくれない。
思わずタンスを覗き込むと、1つの封筒が張り付いていた。
もう黄ばんでいて、かなり古いもののように思える。
封筒をひっくり返すと、宛名の欄には私の名前が書かれていた。
その字は懐かしくて、私がずっと求めていた字で。
これが何なのかを知る前に、涙が頬をつたった。
***
私には夫がいた。でも、その夫のことを『元』旦那と呼べるかなんて、分からない。
だって、もう死んでしまったのだから。
彼は優しい人だった。誰にでも、等しく接する素敵な人だった。
そんなところに、私は心を惹かれた。
付き合ってからも、結婚してからも、彼の誠実さは変わらず、私を一途に愛してくれていた。
『墨ちゃんのこと、一生幸せにする。』
『ほんとに村井にしちゃっていいの?霧ヶ丘って苗字かっこいいのに。』
結婚する時も、私が霧ヶ丘という苗字を気に入ってるのを気にしてくれた。
でも私は、彼と一緒の苗字になりたかった。
村井墨って、なんだか名前の並びが素朴で可愛らしかった。
『もうちょっと安定したら可愛い娘か息子が欲しいね。きっと墨ちゃんに似て、元気で明るい子だよ。』
私は元気で可愛い娘が欲しいと、ことあるごとに言っていた。
『墨ちゃん、ずっと愛してるよ。おやすみ。』
この言葉は毎晩の、寝る前の合言葉だった。
きっと彼は今も、愛してくれていると、私は信じている。
彼がこの世から消えたのは、ほんの一瞬の出来事だった。
あのトラックの運転手を、何度恨んだか分からない。
小さな男の子が飛び出したのを助け、夫は代わりに死んだ。
夫が、男の子を助けたヒーローのように報道されることが悔しくて、本当に悔しくてたまらなかった。
男の子のことは恨まなかった。だってその子は、青信号なことを確認してから走り出したのだもの。
だから私の怒りも恨みも悔しさも、全てがトラックの運転手に向いた。
あいつは飲酒運転をしていた。
事件後1週間ほど経って、刑務所に呼ばれ、あいつからの謝罪があるかと思いきや突然の面会拒否。
そこから6年。1度たりとも謝られたことはない。
こんな胸の苦しさを、どうやって紛らわせるのか。
そんなの分かりっこなかった。
夫がいなくなってから、ずっと厳しい生活が続いた。
生きる希望なんて、到底どこにもなかった。
苦しさからか、難聴が再発した。
小学5年生の時に罹った難聴は、高校に上がる頃には治っていたが、再発の恐れがあると言われていた。
いちばん恐れていたそれが、現実になったのだ。
また、補聴器で暮らす日々に逆戻りだ。
私は、夫が戻ってくるならば耳も声も口も、何もかも差し出すというのに。
***
涙でぼやける視界の奥の、黄ばんだ封筒を見つめる。
綺麗に、整った字があった。
『村井墨様、もしくは霧ヶ丘墨様へ』
あぁ、この字は。
多分、いいや絶対。
私の夫、村井良二のものだ。