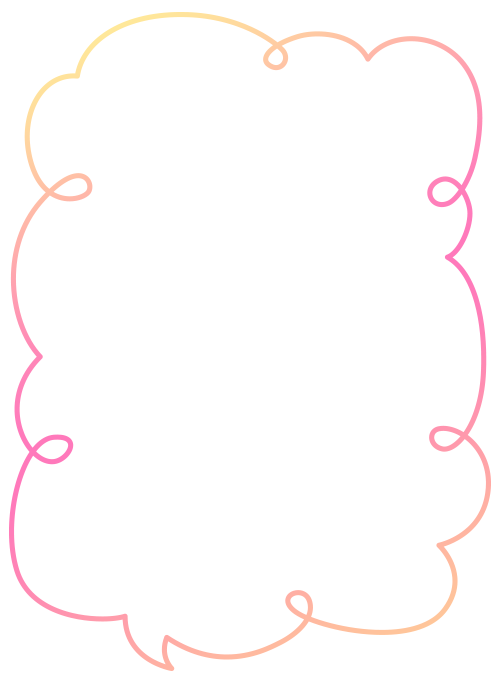星を見に行こう、なんて言っても早々見に行けるものではない。流星群が見れる、なんて騒がれても東京は明るすぎて、天体観測をするには向かない。星を見るにしても、真夜中に夜空を見上げて、星が瞬いているのを確認するだけで精一杯だ。
「あー……やっぱり見えないよねぇ」
比較的灯りも少なく、閑静な場所に立つこの寮でさえ星を見るには向かない。去年は事務所の企画のコンセプトが天体観測だったから、撮影での地方に行ってこの時期は天体観測をした覚えがある。あの時の奏はとても嬉しそうだったのを覚えている。
「ほら、夜とは言え蒸し暑いんだから飲め」
「ありがと~」
水筒に作ったのは、去年から奏が気に入ってくれているオレンジティーだ。それを奏に手渡せば、喉が渇いていたのか一気に飲み干してしまった。
もう一杯注いでやれば、はにかみながら奏が空を見上げる。
「今年も光輝くんと星、見たかったんだ」
「俺も、出来るなら見たかったな」
雲一つない空、とは言えないが真夜中の夜空には月とまばらな雲しか浮いていない。きっと此処が都会ではなければ星が見えていたのかもしれない。
「目には見えないけど、きっと星が瞬いているんだろうなぁ……」
空に向かって手を伸ばす衛は何処から悲しげで、目を離せば寄り掛かかる柵から身を乗り出してしまいそうで怖い。そんなことはしない、とわかっているけれど、何処かに行ってしまいそうで思わず奏の腕を掴んでしまう。
「光輝くん?」
「わ、悪い」
「……心配かけちゃった?」
「少しだけな」
奏は俺の手を取ると、優しく指を絡めてくれた。
ふふふ、と嬉しそうに顔を綻ばせ、とろりとした甘やかな笑みを浮かべる。
「連れて行かれそうなほど俺は大層な人物じゃないよ」
「……どうだかな」
「あ、やさぐれ光輝くんだ」
奏が何かに連れて行かれてしまうんじゃないかと不安になることは多々ある。それこそ目に見えるものなら対処が出来るが、きっと奏を連れて行こうとするのは目に見えないものだろう。
今、俺達の頭上に広がる夜空のように。
今ももしかしたら緩やかにその手を衛に伸ばしているんじゃないかと不安になってしまう。
「光輝くんはたまに凄く迷子みたいな顔するよね」
「……そんなことはない」
「ううん、あるよ。俺も同じだったからわかる」
奏は俺と手を繋いだまま、再び柵の前に立つ。今度は俺と横並びになっている。
「俺もね、光輝くんに見つけてもらうまでは迷子だったと思うんだ」
すっ、と奏が指差すほうには高層ビルの灯りがキラキラと光っている。それはまるで去年見たような星の輝きに似ている。夜空から何処かへ落ちた星も瞬いて、消えた。
遠くに見える灯りもふとした拍子に消えて、その存在がなかったことになる。それに何故か物悲しさを覚えてしまう。
「星も瞬いている間は綺麗だ、って言われるけれど輝き続けないといけないのは大変だと思うんだ」
「そう、だな」
「……けれどね、瞬いている星は夜空から落ちる時に最期はたくさんの人に希望を与えてくれるんだ」
「流れ星か」
「うん。俺はね、もっと輝きたいって願って、自ら流れてきた星に見つけてもらって、此処まで来れた」
えへへ、といつものように笑っているけれど、その瞳はとても真剣で、何も言えなくなる。
そのまま黙っていれば奏が言葉を続ける。
「星に願いを、なんて俺は少し疑ってたけれどキラキラ光る星が俺のところに来てくれたから信じざるを得ないよね」
強く握り締められた手に、少しだけ安堵してしまう。奏の言葉を正しく理解出来ているのかわからないが、きっと奏なりに俺に執着心を持ってくれているのだと思いたい。
「光輝くん、まだ輝いててね」
「一緒じゃないと無理だぞ?」
「ふふ、いつまでも隣にいれるのなら」
今度は俺からも手を握り返し、奏の顔を見る。
変わらず微笑んでいて、何を考えているのかわからない。藤村衛の思考を、世界観を正しく理解出来ることは出来ないのかもしれないが、こうして言葉の端々で表して、歩み寄ろうとしてくれているのがわかる。
「けれど、流れ星でロマンチックな話にさせないところが奏らしいな?」
「そ、そうかな?」
「ああ。普通はロマンチックになるものだろ」
何というか、半ば心中のような、そうでないような。不思議で独特な言い回しは嫌いではない。
瞬いては落ちる、なんて栄枯盛衰のようで不吉ではあるが終わりがあるから何でも美しいのかもしれない。永遠に続くものなどない、そうわかっていて奏は永遠を何処か望んでいる。
矛盾していて、愛おしい。
「流れ星かぁ…うーん……」
「何かあるか?」
「メロディが降ってくる……兆しもない」
「残念だな」
それでも奏の瞳に映る街の灯りはやはり星のようだ。瞬きをしても、確かに浮かぶ小さな夜空に俺も笑みが浮かんでしまう。
「え、何か楽しいことあった?」
「いや、な。俺も奏に影響されているんだな、と思ってな」
そんな考え、奏と出逢う前はなかった。
瞳に浮かぶ灯りが小さな夜空ならば、奏の頭の中は大宇宙だ。未知の世界で、誰も解明出来ていない。
「とりあえず、奏」
「なぁに?」
「口開けろ」
「んむ、え、何? わっ、え?」
どうせ星は見えないだろうと思って、奏のご機嫌とりのために買っておいた小さな星を奏の口の中に放り込む。口に放り込まれたものの正体に気付いたのか、がりがりと小気味の良い音が静かな屋上に響く。
「星、食べちゃいました」
そう言って、また開かれた口に星を投げ込む。
全く……本当にロマンも情緒もない。
それでも、奏が愛おしいと思うのは惚れた弱みと言うやつなのだろう。
それに、目の前に広がるのが本物の夜空で、天体観測さえ出来ていればお得意の言い回しでロマンチックなことにもなるのだろうから。
だから今年はこれで良いのかもしれない。
「来年は綺麗な星空が観たいな」
「来年と言わず、プラネタリウムでも行くか?」
「……それも良いかも、なんて思ってしまう」
「今日が全く情緒がないんだから、人工の星でも我慢してくれ」
プラネタリウムに行った時は少しはそれらしいことをしたい、なんて俺のわがままなのだろうか。
けれど奏がそういうのも満更ではないことを俺は知っている。
俺が奏の流れ星なら、奏も俺の願いを叶えてくれた流れ星だ。突然俺の目の前に現れて、願いを叶えるだけでなく、俺にたくさんのことを教えてくれた。変化と呼ぶのか、退化と呼ぶのかはわからないが俺はこれで良いと思っている。
人並みの感情に左右されるのも、悪くはないと思える。俺にもこんな感情があったのか、と喜ぶことのほうが多い。
「奏」
「はい?」
「大好きだぞ」
「……突然口説くの、やめてください」
恥ずかしいです、と消え入りそうな声で言われてしまえば、もっと意地悪をしたくなる。
「奏はどうだ?」
「ちょ、やめ、光輝くん!」
「言うまで離さない」
「うぅ~」
逃さないように、落ちてなどいかないように。
まだまだ俺の隣にいてもらわないと困るから、腕に閉じ込めてキツく抱き締める。
暑くて、ふざけるたびに汗が滲むけれど、後で2人で風呂に入れば良いだけの話だ。
「もう! 好きです、大好きです!」
「投げやりだな?」
「うぅ~」
星に願いをかけなくても、目に見えない何かが其処にあっても、確かに愛おしい存在は目の前にいる。それだけで、良いのかもしれない。
目に見えないものが奏を連れて行こうとしても、奏の手を引き、連れて行かせないようにすればいい。
「奏、もう暑いから部屋に帰らないか?」
「……変なことしないでね」
「変なことはしないさ」
ただ、誰にも連れて行かれないように腕の中に閉じ込めるだけだ、とは言わない。
そんな想いを胸に秘めながら少し汗ばんだ奏の手を引き、俺達は部屋に戻ったのだった。
俺だけがこの流れ星の正体を知っていたらいいのだから。