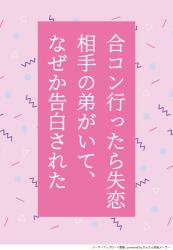「今日が最後の夜ですね」
部屋の真ん中に立った榊原が、自分のベッドを見つめてぽつりと言った。
明日の朝、榊原は空港に向かう。そしてアメリカに発つ。
荷造りはほとんど終わっていて、部屋の半分は妙にがらんとしていた。
俺は自分のベッドに座り、榊原の背中を見ていた。
「俺さ……お前が、いちいち歯みがきは洗面所でしろってうるさかったの、すげぇうざかった」
「は?」
榊原がぱっと振り返った。
俺は構わず続けた。
「お前のマグカップ使っただけでぎゃあぎゃあ言うのも、あと仲良くなる前に俺が写真撮ろうとしたら睨んでくるのも、部屋で俺のこと無視するのも、すげぇ嫌だった」
「え、……それ、今日言います?」
「だって、お前、……行っちゃうじゃん。今日言わなきゃいつ言うんだよ」
肝心なことは言えなくて、余計なことはすらすらと口を出て行く。
だから、次の言葉を言うのに、すごくすごく時間がかかった。
ゆっくりと立ち上がる。
「……俺、お前のこと、好きだよ」
やっと声にして、そのまま目を見開いている榊原にキスをした。
「好き。……榊原が好き」
一瞬だけ、互いの唇が触れて、離れる。
榊原はよほど驚いているのか、しばらく固まっていた。
「な、なんでそっちから一線越えてくんだよ……」
めずらしく榊原の声が裏返っている。
「ア、アンタのことを思って、こっちがどれだけ手ぇ出すの我慢してたと思ってるんですか!」
俺は開き直るように言い返した。
「出せばいいだろ。最後なんだから。何発ヤったって、明日にはバイバイだよ」
「……マジでクソだな、アンタ」
「それでも、……お前は好きだって言ってくれた。お前なら、もっといい奴たくさんいるのに、……だけど、俺が好きって言ってくれただろ」
榊原を見上げる。
「……今日だけでいいから。そしたら、俺……お前のこと、一生応援できるから」
「……」
「テレビでお前の活躍を見たら、『俺のこと好きだったやつだ』って過去のことにしてやるから……だから」
泣きそうになって、ぜったい涙を流さないように唇を噛んだ。
言葉が続かない。喉が詰まる。
息を吸って、もう一度榊原を見据えた。
「お願い。今日だけ……俺のそばにいて――」
次の瞬間、乱暴に引き寄せられた。
背中が壁にぶつかる。榊原の顔が近づいてきて、唇が重なった。
さっき俺がした軽いキスとは違う。
深くて、熱くて、息ができない。
「もう、知るかよ」
「……っ、ん……」
「ぜんぶ、手ぇ出してやるから」
榊原が俺の頬を両手で包んだ。
「後悔、しないでくださいよ」
「……しない、……ふっ、んぅ……」
また唇が重なった。
今度は優しくて、でも切なくて。
転がるように、ベッドに倒れ込んだ。服を脱がされ、肌が重なる。
榊原の体温。榊原の匂い。榊原の声。
ぜんぶぜんぶ忘れないように。
*
朝日が差し込んで、目が覚めた。
体が重い。あちこちが痛い。
ぼんやりした頭で考えて、一気に記憶が蘇った。
榊原に告白して、キスして、それから——。
「……っ」
慌てて体を起こそうとして、シーツがはだける。自分の体が目に入って、かぁっと頬が熱くなった。
首筋、鎖骨、胸元。
赤い痕だらけだ。
たくさんの、キスマーク。榊原が昨日の夜、最初は強気に笑いながら、その後は泣きそうな顔でつけたキスマーク。
昨夜のことはぜんぶ俺の妄想じゃなかった。
「起きました?」
声がして、顔を上げた。
榊原が俺のベッドの縁に座っていた。もう私服に着替えている。出発の準備は万端らしい。
「……いつから起きてたの」
「けっこう前から」
「……ずっと見てたのかよ」
「見てました」
「……変態」
「それは今日の俺じゃなくて、昨日の俺に言うべき言葉でしょ」
榊原が笑って、俺の髪を梳く。
朝日に照らされた顔が、やっぱりかっこいい。
「水野先輩、体は?」
「平気……」
「じゃあ、……心は?」
そんな心配そうな顔をしないでほしい。
「ぜんぜん平気。お前とヤッてすっきりした」
最後くらい、笑顔で送り出したい。
そう決めて、俺は無理やり笑った。
*
空港は人でごった返していた。
榊原の見送りには、藤堂を始めとするバスケ部の連中や、寮の連中、それに久我も来ていた。
「榊原、頑張れよー!」
「NBA行ったらサインくれよな。メルカリで売る」
「……売るなよ」
「ぜってー覚えてろよ、俺たちのこと!」
みんなが口々に声をかける。
泣いている奴もいて、久我もめちゃくちゃ号泣している。
「久我先輩、泣きすぎでしょ」
「だってさぁ……お前がいなくなるの寂しいだろうがよぉ……」
「……まぁ、俺もちょっと寂しいっすけど」
「ちょっとかよ!」
榊原が照れくさそうに笑った。
俺は少し離れたところで、その様子を見ていた。
泣けなかった。泣いたら、止まらなくなりそうで。
ちゃんと見送らなきゃ。笑顔で送り出さなきゃ。
「先輩」
榊原が近づいてきた。
「……おう」
「そろそろ行きます、俺」
「……うん」
わかってる。わかってるけど、足が動かない。
行かないでほしい。でも、行ってほしい。複雑な気持ちがぐるぐる回る。
「元気でな」
「先輩も」
「ちゃんとメシ食えよ」
「大丈夫ですよ」
「無理すんなよ」
「わかってます」
「……榊原」
「はい」
「……好きだったよ、俺」
小さい声で言った。榊原にだけ届くように。
ちゃんと過去にできるはずだ。きっと。
涙がもう溢れて止まらないけれど、胸が痛くてたまらないけれど、それでも。
榊原が目を丸くして、それからけらけらと笑い出す。
「ありがとうございます。……アンタのそのすげぇムカつく発言で、より覚悟が決まりました」
「……え?」
その瞬間、抱きしめられた。息が止まる。ざわっと寮の連中たちが息を呑んだのが体感で伝わった。
「水野先輩、付き合いましょう。俺と」
耳元でささやかれた榊原の言葉。
「……は?」
俺の声じゃない、久我の声だ。
「俺が付き合おうって言ったら、アンタの人生まるごと変えてしまうから、すげぇ悩みました」
抱きしめられたまま、榊原の真剣な声を聞く。
「……ビビってかなり遅くなって、本当にすみません。でも、ようやく覚悟が決まったんで、先輩の人生ごと俺に背負わせてください」
榊原が真剣な目で俺を見た。
「俺と、遠距離恋愛してください」
「……え」
「付き合ってください、先輩」
頭が真っ白になった。
付き合う。遠距離恋愛。俺と、榊原が。
「……む、無理だよ!」
久我たちは、いまだ驚いたように俺たちを見ている。
「無理じゃないです」
「だ、だって、俺……お前の夢、邪魔したくない……!」
「邪魔じゃないですって、むしろ先輩がいたら、何倍も、何十倍も、がんばれます」
「ア、アメリカと日本だよ! 会えねぇじゃん!」
「会いに来ます。電話もできるし、ビデオ通話だってあんだろ」
「でも……」
「でもじゃない」
榊原が俺の腰を強く引き寄せる。
「昨日、先輩が好きって言ってくれて、すげぇ嬉しかった」
「……」
「……俺、アンタの気持ち知らないまま行くとこだった」
「……」
「アンタが俺を好きなら、なんの問題があるんですか? ちゃんと付き合いたいんです。中途半端は嫌だ」
俺は動揺しながら榊原を見た。
プレイ中の時みたいな、本気な目。
「バスケも先輩も、どっちも諦めねぇから。両方、手に入れます」
「……そんな器用なこと」
「やれますよ。だって、この俺がやるって決めたんで」
榊原が俺の頬に手を添えた。
「先輩は俺を信じてくれないんですか」
「……し、信じてないわけじゃない」
「じゃあ、付き合ってください」
「……」
「あと、そこの人たち、ぼけっと見てねぇで、援護射撃してもらえますか?」
榊原が久我たちに言い放つと、久我が涙を拭きながら、困ったように頭を掻いた。
「え、えーと……さ、榊原は、めちゃくちゃバスケ上手い……」
「もっとほかにないんスか……」
「俺あるわ。水野先輩とのツーショット、スマホのロック画面にしてます。かわいいとこあるでしょ」
「えっ……そうなの?」
「藤堂、お前ぜってぇ殺す」
「援護射撃しろって言ったのそっちだろ」
周りから笑い声が上がった。榊原の耳が少しだけ赤くなっている。
「榊原、料理できるよな」
「後輩の面倒見もいい!」
「でも水野には甘えっぱなしだろ。見ててめっちゃおもろかったわ」
「それな、水野の前では赤ちゃんだからこいつ」
「つうか俺、榊原に勉強教えてもらって赤点回避した」
「俺も」
「俺もー」
次々と声が上がる。
「赤ちゃんはいいとして……先輩、聞きました? 俺、けっこうな優良物件ですよ」
榊原が俺に向き直った。
「頼みますから、いいよって言ってください」
さっきまで強気だった目が、少しだけ不安そうに揺れている。
「……ほんとに、俺で……いいの?」
「いいに決まってるでしょ」
「俺、重いよ。毎日連絡したくなるし、声聞きたくなるし」
「いいですよ。俺も毎日連絡します」
「……寂しいって言っちゃうかも」
「言ってください。俺も言いますから」
榊原が笑った。
優しい笑顔。俺だけに見せてくれる笑顔。
「……わかった」
俺は涙を拭いて、榊原を見た。俺だって、覚悟を決めたから。
「俺も頑張る。だから……付き合おう、榊原」
「……はい」
榊原が嬉しそうに笑った。
顔が熱い。心臓がうるさい。
周りからヒューヒューと冷やかしの声が聞こえる。
「マジかよ」
「おめでとー!」
「榊原、お前ってやる奴だと思ってたけど、まさかこう来るとは」
「うちの水野を泣かすなよー!」
「……当たり前じゃないですか」
寮の連中が大騒ぎしている。
恥ずかしい。恥ずかしいけど、嬉しい。
「……なんでわざわざ空港で、……ほんとお前ってばか」
「ばかでいいですよ。俺なりに色々と考えた結果なんで。水野先輩お人好しだから、人前だと断りにくくなるでしょ? あと時間もギリギリにすれば、いいよって言う確率が上がる」
「「「「「……うっわ、こいつ最低!!!!」」」」」
満場一致の声に、俺はぷはっと噴き出してしまった。
榊原は無視を決め込んでいるのか、腕を緩めて、俺と向き合う。
「行ってきます」
「……行ってこい」
「毎日連絡しますから」
「……うん、俺も」
榊原が手を振って、ゲートに向かっていく。
何度も振り返りながら、少しずつ遠くなっていく。
俺は手を振り続けた。
見えなくなるまで、ずっと。
「……行っちゃったな」
隣で久我が言った。
「うん」
まだ心臓がドキドキしている。
「なんとなくこうなる気はしてたわ」
「……うそつけ」
「遠距離、大変だと思うけどさ」
「……うん」
「お前らなら、絶対大丈夫だよ。あいつ、お前のことめちゃくちゃ好きだし」
「……うん」
「気持ち悪いくらい」
「……うん」
藤堂も隣に来た。
「最後まで手のかかる奴で、すみません」
「……ほんとにな」
ズボンのポケットに入れていたスマホが震えた。
榊原からのメッセージだった。
『水野先輩、俺もう寂しい』
思わず笑った。
すぐに返信を打つ。
『俺も』
すぐに既読がついて、返事が来た。
『ちゅき』
また笑った。泣きそうになりながら。
『俺もちゅき』
送信して、スマホを胸に当てた。俺はすでに後悔していた。
俺の返事を待って不安そうにしているあいつの顔を、写真に収めてやればよかった。
おわり
好かれている後輩と別室になりました。
部屋の真ん中に立った榊原が、自分のベッドを見つめてぽつりと言った。
明日の朝、榊原は空港に向かう。そしてアメリカに発つ。
荷造りはほとんど終わっていて、部屋の半分は妙にがらんとしていた。
俺は自分のベッドに座り、榊原の背中を見ていた。
「俺さ……お前が、いちいち歯みがきは洗面所でしろってうるさかったの、すげぇうざかった」
「は?」
榊原がぱっと振り返った。
俺は構わず続けた。
「お前のマグカップ使っただけでぎゃあぎゃあ言うのも、あと仲良くなる前に俺が写真撮ろうとしたら睨んでくるのも、部屋で俺のこと無視するのも、すげぇ嫌だった」
「え、……それ、今日言います?」
「だって、お前、……行っちゃうじゃん。今日言わなきゃいつ言うんだよ」
肝心なことは言えなくて、余計なことはすらすらと口を出て行く。
だから、次の言葉を言うのに、すごくすごく時間がかかった。
ゆっくりと立ち上がる。
「……俺、お前のこと、好きだよ」
やっと声にして、そのまま目を見開いている榊原にキスをした。
「好き。……榊原が好き」
一瞬だけ、互いの唇が触れて、離れる。
榊原はよほど驚いているのか、しばらく固まっていた。
「な、なんでそっちから一線越えてくんだよ……」
めずらしく榊原の声が裏返っている。
「ア、アンタのことを思って、こっちがどれだけ手ぇ出すの我慢してたと思ってるんですか!」
俺は開き直るように言い返した。
「出せばいいだろ。最後なんだから。何発ヤったって、明日にはバイバイだよ」
「……マジでクソだな、アンタ」
「それでも、……お前は好きだって言ってくれた。お前なら、もっといい奴たくさんいるのに、……だけど、俺が好きって言ってくれただろ」
榊原を見上げる。
「……今日だけでいいから。そしたら、俺……お前のこと、一生応援できるから」
「……」
「テレビでお前の活躍を見たら、『俺のこと好きだったやつだ』って過去のことにしてやるから……だから」
泣きそうになって、ぜったい涙を流さないように唇を噛んだ。
言葉が続かない。喉が詰まる。
息を吸って、もう一度榊原を見据えた。
「お願い。今日だけ……俺のそばにいて――」
次の瞬間、乱暴に引き寄せられた。
背中が壁にぶつかる。榊原の顔が近づいてきて、唇が重なった。
さっき俺がした軽いキスとは違う。
深くて、熱くて、息ができない。
「もう、知るかよ」
「……っ、ん……」
「ぜんぶ、手ぇ出してやるから」
榊原が俺の頬を両手で包んだ。
「後悔、しないでくださいよ」
「……しない、……ふっ、んぅ……」
また唇が重なった。
今度は優しくて、でも切なくて。
転がるように、ベッドに倒れ込んだ。服を脱がされ、肌が重なる。
榊原の体温。榊原の匂い。榊原の声。
ぜんぶぜんぶ忘れないように。
*
朝日が差し込んで、目が覚めた。
体が重い。あちこちが痛い。
ぼんやりした頭で考えて、一気に記憶が蘇った。
榊原に告白して、キスして、それから——。
「……っ」
慌てて体を起こそうとして、シーツがはだける。自分の体が目に入って、かぁっと頬が熱くなった。
首筋、鎖骨、胸元。
赤い痕だらけだ。
たくさんの、キスマーク。榊原が昨日の夜、最初は強気に笑いながら、その後は泣きそうな顔でつけたキスマーク。
昨夜のことはぜんぶ俺の妄想じゃなかった。
「起きました?」
声がして、顔を上げた。
榊原が俺のベッドの縁に座っていた。もう私服に着替えている。出発の準備は万端らしい。
「……いつから起きてたの」
「けっこう前から」
「……ずっと見てたのかよ」
「見てました」
「……変態」
「それは今日の俺じゃなくて、昨日の俺に言うべき言葉でしょ」
榊原が笑って、俺の髪を梳く。
朝日に照らされた顔が、やっぱりかっこいい。
「水野先輩、体は?」
「平気……」
「じゃあ、……心は?」
そんな心配そうな顔をしないでほしい。
「ぜんぜん平気。お前とヤッてすっきりした」
最後くらい、笑顔で送り出したい。
そう決めて、俺は無理やり笑った。
*
空港は人でごった返していた。
榊原の見送りには、藤堂を始めとするバスケ部の連中や、寮の連中、それに久我も来ていた。
「榊原、頑張れよー!」
「NBA行ったらサインくれよな。メルカリで売る」
「……売るなよ」
「ぜってー覚えてろよ、俺たちのこと!」
みんなが口々に声をかける。
泣いている奴もいて、久我もめちゃくちゃ号泣している。
「久我先輩、泣きすぎでしょ」
「だってさぁ……お前がいなくなるの寂しいだろうがよぉ……」
「……まぁ、俺もちょっと寂しいっすけど」
「ちょっとかよ!」
榊原が照れくさそうに笑った。
俺は少し離れたところで、その様子を見ていた。
泣けなかった。泣いたら、止まらなくなりそうで。
ちゃんと見送らなきゃ。笑顔で送り出さなきゃ。
「先輩」
榊原が近づいてきた。
「……おう」
「そろそろ行きます、俺」
「……うん」
わかってる。わかってるけど、足が動かない。
行かないでほしい。でも、行ってほしい。複雑な気持ちがぐるぐる回る。
「元気でな」
「先輩も」
「ちゃんとメシ食えよ」
「大丈夫ですよ」
「無理すんなよ」
「わかってます」
「……榊原」
「はい」
「……好きだったよ、俺」
小さい声で言った。榊原にだけ届くように。
ちゃんと過去にできるはずだ。きっと。
涙がもう溢れて止まらないけれど、胸が痛くてたまらないけれど、それでも。
榊原が目を丸くして、それからけらけらと笑い出す。
「ありがとうございます。……アンタのそのすげぇムカつく発言で、より覚悟が決まりました」
「……え?」
その瞬間、抱きしめられた。息が止まる。ざわっと寮の連中たちが息を呑んだのが体感で伝わった。
「水野先輩、付き合いましょう。俺と」
耳元でささやかれた榊原の言葉。
「……は?」
俺の声じゃない、久我の声だ。
「俺が付き合おうって言ったら、アンタの人生まるごと変えてしまうから、すげぇ悩みました」
抱きしめられたまま、榊原の真剣な声を聞く。
「……ビビってかなり遅くなって、本当にすみません。でも、ようやく覚悟が決まったんで、先輩の人生ごと俺に背負わせてください」
榊原が真剣な目で俺を見た。
「俺と、遠距離恋愛してください」
「……え」
「付き合ってください、先輩」
頭が真っ白になった。
付き合う。遠距離恋愛。俺と、榊原が。
「……む、無理だよ!」
久我たちは、いまだ驚いたように俺たちを見ている。
「無理じゃないです」
「だ、だって、俺……お前の夢、邪魔したくない……!」
「邪魔じゃないですって、むしろ先輩がいたら、何倍も、何十倍も、がんばれます」
「ア、アメリカと日本だよ! 会えねぇじゃん!」
「会いに来ます。電話もできるし、ビデオ通話だってあんだろ」
「でも……」
「でもじゃない」
榊原が俺の腰を強く引き寄せる。
「昨日、先輩が好きって言ってくれて、すげぇ嬉しかった」
「……」
「……俺、アンタの気持ち知らないまま行くとこだった」
「……」
「アンタが俺を好きなら、なんの問題があるんですか? ちゃんと付き合いたいんです。中途半端は嫌だ」
俺は動揺しながら榊原を見た。
プレイ中の時みたいな、本気な目。
「バスケも先輩も、どっちも諦めねぇから。両方、手に入れます」
「……そんな器用なこと」
「やれますよ。だって、この俺がやるって決めたんで」
榊原が俺の頬に手を添えた。
「先輩は俺を信じてくれないんですか」
「……し、信じてないわけじゃない」
「じゃあ、付き合ってください」
「……」
「あと、そこの人たち、ぼけっと見てねぇで、援護射撃してもらえますか?」
榊原が久我たちに言い放つと、久我が涙を拭きながら、困ったように頭を掻いた。
「え、えーと……さ、榊原は、めちゃくちゃバスケ上手い……」
「もっとほかにないんスか……」
「俺あるわ。水野先輩とのツーショット、スマホのロック画面にしてます。かわいいとこあるでしょ」
「えっ……そうなの?」
「藤堂、お前ぜってぇ殺す」
「援護射撃しろって言ったのそっちだろ」
周りから笑い声が上がった。榊原の耳が少しだけ赤くなっている。
「榊原、料理できるよな」
「後輩の面倒見もいい!」
「でも水野には甘えっぱなしだろ。見ててめっちゃおもろかったわ」
「それな、水野の前では赤ちゃんだからこいつ」
「つうか俺、榊原に勉強教えてもらって赤点回避した」
「俺も」
「俺もー」
次々と声が上がる。
「赤ちゃんはいいとして……先輩、聞きました? 俺、けっこうな優良物件ですよ」
榊原が俺に向き直った。
「頼みますから、いいよって言ってください」
さっきまで強気だった目が、少しだけ不安そうに揺れている。
「……ほんとに、俺で……いいの?」
「いいに決まってるでしょ」
「俺、重いよ。毎日連絡したくなるし、声聞きたくなるし」
「いいですよ。俺も毎日連絡します」
「……寂しいって言っちゃうかも」
「言ってください。俺も言いますから」
榊原が笑った。
優しい笑顔。俺だけに見せてくれる笑顔。
「……わかった」
俺は涙を拭いて、榊原を見た。俺だって、覚悟を決めたから。
「俺も頑張る。だから……付き合おう、榊原」
「……はい」
榊原が嬉しそうに笑った。
顔が熱い。心臓がうるさい。
周りからヒューヒューと冷やかしの声が聞こえる。
「マジかよ」
「おめでとー!」
「榊原、お前ってやる奴だと思ってたけど、まさかこう来るとは」
「うちの水野を泣かすなよー!」
「……当たり前じゃないですか」
寮の連中が大騒ぎしている。
恥ずかしい。恥ずかしいけど、嬉しい。
「……なんでわざわざ空港で、……ほんとお前ってばか」
「ばかでいいですよ。俺なりに色々と考えた結果なんで。水野先輩お人好しだから、人前だと断りにくくなるでしょ? あと時間もギリギリにすれば、いいよって言う確率が上がる」
「「「「「……うっわ、こいつ最低!!!!」」」」」
満場一致の声に、俺はぷはっと噴き出してしまった。
榊原は無視を決め込んでいるのか、腕を緩めて、俺と向き合う。
「行ってきます」
「……行ってこい」
「毎日連絡しますから」
「……うん、俺も」
榊原が手を振って、ゲートに向かっていく。
何度も振り返りながら、少しずつ遠くなっていく。
俺は手を振り続けた。
見えなくなるまで、ずっと。
「……行っちゃったな」
隣で久我が言った。
「うん」
まだ心臓がドキドキしている。
「なんとなくこうなる気はしてたわ」
「……うそつけ」
「遠距離、大変だと思うけどさ」
「……うん」
「お前らなら、絶対大丈夫だよ。あいつ、お前のことめちゃくちゃ好きだし」
「……うん」
「気持ち悪いくらい」
「……うん」
藤堂も隣に来た。
「最後まで手のかかる奴で、すみません」
「……ほんとにな」
ズボンのポケットに入れていたスマホが震えた。
榊原からのメッセージだった。
『水野先輩、俺もう寂しい』
思わず笑った。
すぐに返信を打つ。
『俺も』
すぐに既読がついて、返事が来た。
『ちゅき』
また笑った。泣きそうになりながら。
『俺もちゅき』
送信して、スマホを胸に当てた。俺はすでに後悔していた。
俺の返事を待って不安そうにしているあいつの顔を、写真に収めてやればよかった。
おわり
好かれている後輩と別室になりました。