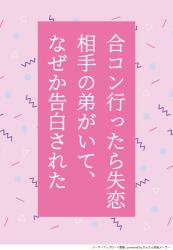それから何日か経った頃、俺と榊原は玄関の掃除当番になった。
最近、あまり眠れていない。
あっちこっちに散らばった来客用のスリッパを、ひとつひとつ揃えて靴箱に入れていく。
黙々と作業をしていると、榊原が口を開いた。
「聞かないんですか、あれ」
「……っ」
「『俺のこと好き?』って、前は毎日聞いてきたのに」
心臓が跳ねた。
俺は榊原を見ないようにして、スリッパを乱暴に靴箱に突っ込んだ。
「うるせぇな、いいから手動かせよ」
言ったあと、しまった、と思った。
俺、人にこんな言い方したことない。
でも、榊原は怒ることなく、けらけらと笑ってみせた。
「どうしたんですか? アンタがそんな風に八つ当たりするとこ、初めて見ました」
「……」
「悩みなら聞きますよ?」
「……おっ!」
お前のせいだろうが!!!!!!
心の中で叫んだ。
留学のことを黙ってたお前のせいで、俺は今こんなにわけのわからない感情になっている。
「あー……もしかして、なんか聞きました? 藤堂あたりから」
榊原の声が、少し真剣になった。
俺は観念して、靴箱に背中を預けた。
「……聞いた」
「……そうですか」
「本当に行くの? アメリカ」
「……行きます」
「そっか」
やっぱり、行ってしまうんだ。
沈黙が落ちる。
玄関には俺たち以外誰もいない。夕暮れの光が、床に長い影を作っていた。
「なんで言ってくれなかったんだよ」
気づいたら、口に出していた。
「俺、お前と同じ部屋なのに。毎日一緒にいたのに」
「…………」
「藤堂は知ってて、俺は知らなかった。……俺には言えなかったってこと?」
榊原が黙った。
その沈黙が、答えだった。
「先輩には……言いづらかったんです」
「なんで」
「なんでって……」
榊原が困ったように笑った。
「アンタが『好きな人』だから」
「…………」
「言ったら、先輩は気を遣うだろうし。俺に優しくしてくれるのが、同情なのかなんなのか、わかんなくなるのも嫌だったし」
「……そ、そんなの」
「わかってます。俺の勝手な言い分だって」
榊原が、俺のほうを見た。
「先輩は、俺がいなくなったら寂しいですか」
その声が、やけに静かだった。
試しているような、でも本心を聞きたいような。
「……寂しいよ」
素直に答えた。
「お前がいなくなったら、すげぇ寂しい」
「…………」
「この部屋に帰ってきても、お前がいないんだろ。朝起きても、お前の顔が見られないんだろ。生意気な態度も、イケメンってわかってるみたいなムカつく笑顔も、もう見られないんだろ」
言葉が止まらなかった。
「それは……やだよ、普通に」
榊原が俺の隣に立つ。
「アメリカ行っても、俺のこと、忘れないでくださいよ」
「……」
忘れられるわけがない。
「俺が将来プロのバスケ選手になって、テレビに出て、女の子にきゃーきゃー言われても」
「……今も言われてんだろ」
「まぁ、そこはいいんですけど」
榊原が真剣な顔になった。
「何年後かわかんないですけど、俺がアンタの目に映ったら、思い出してください。『こいつは俺のこと、しつこいくらい好きだったやつだ』って」
その言葉にカチンときた。
「お前にとっては、……もう過去なのかよ」
「え?」
「『好きだった』って。もう終わったみたいに言うなよ……!」
「いや、そういう意味じゃ——」
「俺、お前の横にいるじゃん! 今、いるじゃん!」
声が大きくなっていた。
自分でも驚くくらい、感情が溢れ出していた。
「お前、勝手に俺の初告白奪っといて、『はい、さようなら』ってそんなのありかよ!」
榊原が固まった。
「初めて……告白されたんですか」
「……うん」
「マジで?」
「マジだよ」
「……ははっ、初めてが俺って、かわいそうに」
「かわいそうじゃない」
俺は榊原を睨んだ。
「全然かわいそうじゃない。むしろ、みんなに自慢してもいいくらいだって……俺は、……思ってる」
榊原が息を呑む。
数秒、沈黙が流れた。
「……アンタ、かわいすぎだろ」
「は?」
「なんなんですか。押し倒していいんですか」
「そっ、それはちょっと……」
「じゃあ、抱きしめるのは?」
榊原が一歩近づいてくる。逃げ場がない。
「……ちょっとくらいなら、いい……かも」
言った瞬間、腕を引かれた。
気づいたら、榊原の胸の中にいた。
大きな体。あったかい。榊原の匂いがする。
心臓の音が聞こえる。俺なのか、榊原なのか。
「……あー、まずい。こういうの、まずいだろ……」
榊原がぶつぶつ言っている。
俺はまたわけがわからないくらい腹が立って、ぎゅうっと榊原の背中のジャージを掴んだ。
「いや、抱き返してくんなよ……。水野先輩、ばかなんですか?」
「……そっちこそばか。先輩には敬語使え」
「今さら……」
ぎゅうぎゅうと抱き返す。その時。
「えっ、ふたりで何してんの?」
明るい声が響いて、俺は現実に引き戻された。
そうだった、ここは玄関だ。めちゃくちゃみんなが通る場所だ。
はっとして離れようとしたけど、榊原は腕を緩めなかった。
「見りゃあわかんでしょ。抱き合ってるんですよ」
へらっと笑って、榊原が宣言した。
振り返ると、ほかにも久我やバスケ部の連中も立っている。
「ぎゃはははは! 水野と榊原が抱き合ってる!」
「なんだなんだ、仲良いな!」
「俺らも混ざろ!」
「団結! 団結!」
バスケ部やらバレー部やら、背の高い野郎どもがわらわらと集まってきて、俺たちをぎゅうぎゅうと囲んだ。
「こんな時になんなんですけど、俺、アメリカに留学することになりました」
さらりと榊原が言う。「うぇっ!?」とか「マジ!?」とか「めでてぇ!」とか、みんな大騒ぎだった。
もみくちゃにされながら、俺はどさくさに紛れて、もっと榊原にくっついた。
榊原はなぜか不機嫌な顔になって、みんなから俺を守るように抱きしめてくる。
なんなんだよ、お前。
もうこれでさよならなんて、言うなよ。
好きだった、なんて言うなよ。
たとえ俺と付き合う気がなくたって、そんなの。聞きたくないんだ、今は。
*
榊原がアメリカに行くことは、あっという間に広まった。
それからの日々は、残り時間が減っていくのをまざまざと感じながら、榊原との日々を過ごした。
意識するなと思えば思うほど、榊原のことが気になる。
同じ部屋で朝まで一緒にいるのが、こんなにもどかしいなんて知らなかった。近いのに、近くない。
夜、ベッドに入ってからも眠れない。
隣のベッドから聞こえる榊原の息。かすかな寝返りの音。
それを聞いているだけで、胸がざわつく。
「……先輩、起きてます?」
暗闇の中で榊原の声がした。
「……起きてる」
「眠れないんですか」
「……まあね。お前は?」
「俺も」
沈黙が流れる。
暗くて顔はよく見えないけど、榊原がこっちを向いているのがわかった。
「……なぁ、先輩」
「んー……?」
「俺の布団来ます? ほら、人肌あると眠れるって言うし」
「……いかない」
「ですよね」
少しの間があった。
「……お前が、こっち来たらいいじゃん」
ぼそりと言う。
「…………はぁぁぁぁぁぁぁ」
長いため息が聞こえた。
そして、ガサガサと布団から出る音。
榊原が俺のベッドに近づいてきて、布団に潜り込んできた。
「……お前でかいから、狭い」
「我慢してくださいよ」
叱りつけるみたいに、布団の中でそっと手を握られた。
大きくてあったかい手。この手でドリブルして、シュートを決める、かっこいい手。この前、俺のことを抱きしめた手。
俺たちはいったい何をしているんだろう。もうわけがわからなくて、考えるのをやめた。
榊原が何も言わないから、俺も何も言わなかった。
指先が絡まる。心臓はさっきの倍うるさくなって、絶対眠れそうにない。
暗闇の中で天井を見つめながら、俺は眠ることを完全に諦めた。
「……しりとりしよ」
「は?」
「眠れないから」
「……いいっすね」
榊原が死んだような声で言った。
俺たちは手を繋いだまま、小声でしりとりを始めた。
りんご、ゴリラ、ラッパ、パンダ、ダンクシュート。
たぶん、三回目の「ル」が回ってきたあたりで、俺は眠りに落ちた。
そして……朝、目が覚めたら、隣に榊原の寝顔があった。
無防備な顔。長いまつげ。少し開いた唇。
近い。近すぎる。
……かっこいいな、と思ってしまう自分がいる。
なんかもう、ダメかもしれない。
榊原の顔を見るたびにドキドキする。
これって、なんなんだろう。
もしかして、俺は榊原のことを——。
考えるのが怖かった。
だって、気づいてしまったら、もう戻れない気がしたから。
もうすぐ榊原はいなくなる。
今さら気づいたって、どうしようもない。
*
「はぁ……」
部屋でひとり、ため息を吐く。
ばかな俺は、また今日もこっそりとバスケ部の練習試合を見に行ってしまった。
試合が終わった後、榊原が他校の女子生徒と話しているのを見た。
かわいい子だった。榊原に話しかけて、スマホを差し出している。たぶん、連絡先を聞いていたんだろう。
榊原は困ったように笑って何かを言い、女の子も笑っていた。断っているのか、受け入れているのか、俺にはわからない。
その時、胸の奥がぎゅっと締め付けられた。
……なんだよ、これ。
榊原が女の子と話してるだけで、あんなにムカつくなんて。
「はぁ……」
もう一度ため息をつく。
もしも俺が榊原と付き合ったら、どうなるんだろう。
あいつを撮った写真を見つめながら、ふとそんなことを考えてしまった。
あいつは生意気だけど、たぶん俺のことを大事にしてくれる。
好きなものを覚えていてくれるし、体調が悪いときは看病してくれるし、俺のSNSの写真だってずっと見ていてくれた。
付き合ったら、きっと幸せにしてくれるんだろうな。
……でも、榊原はアメリカに行くし、さらには最初から俺と付き合うつもりなんてさらさらないのだ。
向こうで関わる人間もめちゃくちゃ多いだろう。俺のことなんてすぐ忘れるに決まってる。
かわいい女の子にも関わるだろう。さっきみたいに連絡先を聞かれることだって、何度もあるだろう。
そのうち、俺以外の誰かを好きになる、確実に。
そう思ったら、ますます胸が痛くて息ができなくなった。
俺はいつから、こんなに榊原のことばかり考えるようになったんだろう。
嫌われてるって気づいた時から?
それともあいつが俺を好きだって気づいた時から?
ガチャッと部屋の扉が開く。
「水野先輩、ただいま」
そんな声とともに、微笑んだ榊原が部屋に入ってきた。
「おかえり……」
……俺はもうだめだ。こいつが好きなんだって、認めるしかない。
榊原の顔を見ただけで、好きだと言ってしまいそうになるのだから。
俺は心の声を押し殺し、いつもの質問をした。
「……俺のこと、好き?」
「会ってすぐそれかよ」
けらけらと笑ったあと、「はい」と榊原が答える。
好きだ、と思う。
でも、言ってどうなる?
榊原はアメリカに行く。俺は日本に残る。
榊原は夢を追いかけてますます忙しくなる。遠距離なんて、無理に決まってる。
だったら、黙っていたほうがいい。
榊原の夢の邪魔なんて、絶対にしたくない。
*
留学まで、あと三日。榊原の部屋の荷物が少しずつ減っていく。
榊原は、前より優しかった。
俺が落ち込んでいるのを察しているのか、さりげなく気を遣ってくれる。
それがまたつらかった。
その日の夜、部屋でぼんやりしていると、榊原が声をかけてきた。
「先輩、ちょっといいですか」
「……なに」
「写真、撮ってほしいんですけど」
「写真?」
榊原がスマホを取り出した。
「俺たちのツーショット。……一枚も持ってないなって気づいて」
俺は目を丸くした。
確かに、俺と榊原の写真なんて一枚もない。
俺はいつも撮る側で、榊原は撮られる側で。二人で写ったことなんて、一度もなかった。
「……いいよ」
「じゃあ、こっち来てください」
榊原が自分のベッドに座って、隣をぽんぽんと叩いた。
俺は少し躊躇してから、榊原の隣に座った。
近い。肩が触れる距離。
榊原がスマホを持ち上げて、インカメラを起動した。
画面に、俺と榊原の顔が並んで映る。
「……なんか照れるわ」
「ちゃんと笑ってくださいよ、先輩。アメリカ行ったら、毎日この写真を見るんですから」
「言ったな? お前、本当に見ろよ」
「やっぱ毎日は言い過ぎかも」
からかうように榊原が笑い、俺も自然と口元が緩んだ。
カシャ、とシャッター音が鳴った。
「……すげぇいいの撮れたわ」
榊原が画面を確認する。
俺も覗き込んだ。
二人とも、笑っていた。
なんだか気恥ずかしくて、でも嬉しくて。
「……めっちゃいい写真」
「でしょ」
榊原が満足そうに言った。
「これ、先輩にも送りますね。忘れないでくださいよ、俺のこと」
「……忘れるわけないだろ」
俺は画面の中の自分たちを見つめた。
泣いてる榊原の写真を勝手に撮ってしまったのが、すべての始まりだった。
そして今、俺たちはふたりで笑ってる写真を撮っている。
なんか、泣きそうだ。
「……榊原」
「はい」
「……頑張れよ、アメリカ行っても」
それしか言えなかった。
本当は、行かないでほしい。ずっとそばにいてほしい。
でも、言えない。言っちゃいけない。
「……はい。頑張ります」
榊原が静かに答えた。
俺たちは並んで座ったまま、しばらく何も言わなかった。
肩が触れている。それだけで、胸がいっぱいだった。
あと三日。
たった三日で、こいつはいなくなる。
言えないまま終わっていく。この夜も、この恋も、終わってしまうんだ、きっと。
最近、あまり眠れていない。
あっちこっちに散らばった来客用のスリッパを、ひとつひとつ揃えて靴箱に入れていく。
黙々と作業をしていると、榊原が口を開いた。
「聞かないんですか、あれ」
「……っ」
「『俺のこと好き?』って、前は毎日聞いてきたのに」
心臓が跳ねた。
俺は榊原を見ないようにして、スリッパを乱暴に靴箱に突っ込んだ。
「うるせぇな、いいから手動かせよ」
言ったあと、しまった、と思った。
俺、人にこんな言い方したことない。
でも、榊原は怒ることなく、けらけらと笑ってみせた。
「どうしたんですか? アンタがそんな風に八つ当たりするとこ、初めて見ました」
「……」
「悩みなら聞きますよ?」
「……おっ!」
お前のせいだろうが!!!!!!
心の中で叫んだ。
留学のことを黙ってたお前のせいで、俺は今こんなにわけのわからない感情になっている。
「あー……もしかして、なんか聞きました? 藤堂あたりから」
榊原の声が、少し真剣になった。
俺は観念して、靴箱に背中を預けた。
「……聞いた」
「……そうですか」
「本当に行くの? アメリカ」
「……行きます」
「そっか」
やっぱり、行ってしまうんだ。
沈黙が落ちる。
玄関には俺たち以外誰もいない。夕暮れの光が、床に長い影を作っていた。
「なんで言ってくれなかったんだよ」
気づいたら、口に出していた。
「俺、お前と同じ部屋なのに。毎日一緒にいたのに」
「…………」
「藤堂は知ってて、俺は知らなかった。……俺には言えなかったってこと?」
榊原が黙った。
その沈黙が、答えだった。
「先輩には……言いづらかったんです」
「なんで」
「なんでって……」
榊原が困ったように笑った。
「アンタが『好きな人』だから」
「…………」
「言ったら、先輩は気を遣うだろうし。俺に優しくしてくれるのが、同情なのかなんなのか、わかんなくなるのも嫌だったし」
「……そ、そんなの」
「わかってます。俺の勝手な言い分だって」
榊原が、俺のほうを見た。
「先輩は、俺がいなくなったら寂しいですか」
その声が、やけに静かだった。
試しているような、でも本心を聞きたいような。
「……寂しいよ」
素直に答えた。
「お前がいなくなったら、すげぇ寂しい」
「…………」
「この部屋に帰ってきても、お前がいないんだろ。朝起きても、お前の顔が見られないんだろ。生意気な態度も、イケメンってわかってるみたいなムカつく笑顔も、もう見られないんだろ」
言葉が止まらなかった。
「それは……やだよ、普通に」
榊原が俺の隣に立つ。
「アメリカ行っても、俺のこと、忘れないでくださいよ」
「……」
忘れられるわけがない。
「俺が将来プロのバスケ選手になって、テレビに出て、女の子にきゃーきゃー言われても」
「……今も言われてんだろ」
「まぁ、そこはいいんですけど」
榊原が真剣な顔になった。
「何年後かわかんないですけど、俺がアンタの目に映ったら、思い出してください。『こいつは俺のこと、しつこいくらい好きだったやつだ』って」
その言葉にカチンときた。
「お前にとっては、……もう過去なのかよ」
「え?」
「『好きだった』って。もう終わったみたいに言うなよ……!」
「いや、そういう意味じゃ——」
「俺、お前の横にいるじゃん! 今、いるじゃん!」
声が大きくなっていた。
自分でも驚くくらい、感情が溢れ出していた。
「お前、勝手に俺の初告白奪っといて、『はい、さようなら』ってそんなのありかよ!」
榊原が固まった。
「初めて……告白されたんですか」
「……うん」
「マジで?」
「マジだよ」
「……ははっ、初めてが俺って、かわいそうに」
「かわいそうじゃない」
俺は榊原を睨んだ。
「全然かわいそうじゃない。むしろ、みんなに自慢してもいいくらいだって……俺は、……思ってる」
榊原が息を呑む。
数秒、沈黙が流れた。
「……アンタ、かわいすぎだろ」
「は?」
「なんなんですか。押し倒していいんですか」
「そっ、それはちょっと……」
「じゃあ、抱きしめるのは?」
榊原が一歩近づいてくる。逃げ場がない。
「……ちょっとくらいなら、いい……かも」
言った瞬間、腕を引かれた。
気づいたら、榊原の胸の中にいた。
大きな体。あったかい。榊原の匂いがする。
心臓の音が聞こえる。俺なのか、榊原なのか。
「……あー、まずい。こういうの、まずいだろ……」
榊原がぶつぶつ言っている。
俺はまたわけがわからないくらい腹が立って、ぎゅうっと榊原の背中のジャージを掴んだ。
「いや、抱き返してくんなよ……。水野先輩、ばかなんですか?」
「……そっちこそばか。先輩には敬語使え」
「今さら……」
ぎゅうぎゅうと抱き返す。その時。
「えっ、ふたりで何してんの?」
明るい声が響いて、俺は現実に引き戻された。
そうだった、ここは玄関だ。めちゃくちゃみんなが通る場所だ。
はっとして離れようとしたけど、榊原は腕を緩めなかった。
「見りゃあわかんでしょ。抱き合ってるんですよ」
へらっと笑って、榊原が宣言した。
振り返ると、ほかにも久我やバスケ部の連中も立っている。
「ぎゃはははは! 水野と榊原が抱き合ってる!」
「なんだなんだ、仲良いな!」
「俺らも混ざろ!」
「団結! 団結!」
バスケ部やらバレー部やら、背の高い野郎どもがわらわらと集まってきて、俺たちをぎゅうぎゅうと囲んだ。
「こんな時になんなんですけど、俺、アメリカに留学することになりました」
さらりと榊原が言う。「うぇっ!?」とか「マジ!?」とか「めでてぇ!」とか、みんな大騒ぎだった。
もみくちゃにされながら、俺はどさくさに紛れて、もっと榊原にくっついた。
榊原はなぜか不機嫌な顔になって、みんなから俺を守るように抱きしめてくる。
なんなんだよ、お前。
もうこれでさよならなんて、言うなよ。
好きだった、なんて言うなよ。
たとえ俺と付き合う気がなくたって、そんなの。聞きたくないんだ、今は。
*
榊原がアメリカに行くことは、あっという間に広まった。
それからの日々は、残り時間が減っていくのをまざまざと感じながら、榊原との日々を過ごした。
意識するなと思えば思うほど、榊原のことが気になる。
同じ部屋で朝まで一緒にいるのが、こんなにもどかしいなんて知らなかった。近いのに、近くない。
夜、ベッドに入ってからも眠れない。
隣のベッドから聞こえる榊原の息。かすかな寝返りの音。
それを聞いているだけで、胸がざわつく。
「……先輩、起きてます?」
暗闇の中で榊原の声がした。
「……起きてる」
「眠れないんですか」
「……まあね。お前は?」
「俺も」
沈黙が流れる。
暗くて顔はよく見えないけど、榊原がこっちを向いているのがわかった。
「……なぁ、先輩」
「んー……?」
「俺の布団来ます? ほら、人肌あると眠れるって言うし」
「……いかない」
「ですよね」
少しの間があった。
「……お前が、こっち来たらいいじゃん」
ぼそりと言う。
「…………はぁぁぁぁぁぁぁ」
長いため息が聞こえた。
そして、ガサガサと布団から出る音。
榊原が俺のベッドに近づいてきて、布団に潜り込んできた。
「……お前でかいから、狭い」
「我慢してくださいよ」
叱りつけるみたいに、布団の中でそっと手を握られた。
大きくてあったかい手。この手でドリブルして、シュートを決める、かっこいい手。この前、俺のことを抱きしめた手。
俺たちはいったい何をしているんだろう。もうわけがわからなくて、考えるのをやめた。
榊原が何も言わないから、俺も何も言わなかった。
指先が絡まる。心臓はさっきの倍うるさくなって、絶対眠れそうにない。
暗闇の中で天井を見つめながら、俺は眠ることを完全に諦めた。
「……しりとりしよ」
「は?」
「眠れないから」
「……いいっすね」
榊原が死んだような声で言った。
俺たちは手を繋いだまま、小声でしりとりを始めた。
りんご、ゴリラ、ラッパ、パンダ、ダンクシュート。
たぶん、三回目の「ル」が回ってきたあたりで、俺は眠りに落ちた。
そして……朝、目が覚めたら、隣に榊原の寝顔があった。
無防備な顔。長いまつげ。少し開いた唇。
近い。近すぎる。
……かっこいいな、と思ってしまう自分がいる。
なんかもう、ダメかもしれない。
榊原の顔を見るたびにドキドキする。
これって、なんなんだろう。
もしかして、俺は榊原のことを——。
考えるのが怖かった。
だって、気づいてしまったら、もう戻れない気がしたから。
もうすぐ榊原はいなくなる。
今さら気づいたって、どうしようもない。
*
「はぁ……」
部屋でひとり、ため息を吐く。
ばかな俺は、また今日もこっそりとバスケ部の練習試合を見に行ってしまった。
試合が終わった後、榊原が他校の女子生徒と話しているのを見た。
かわいい子だった。榊原に話しかけて、スマホを差し出している。たぶん、連絡先を聞いていたんだろう。
榊原は困ったように笑って何かを言い、女の子も笑っていた。断っているのか、受け入れているのか、俺にはわからない。
その時、胸の奥がぎゅっと締め付けられた。
……なんだよ、これ。
榊原が女の子と話してるだけで、あんなにムカつくなんて。
「はぁ……」
もう一度ため息をつく。
もしも俺が榊原と付き合ったら、どうなるんだろう。
あいつを撮った写真を見つめながら、ふとそんなことを考えてしまった。
あいつは生意気だけど、たぶん俺のことを大事にしてくれる。
好きなものを覚えていてくれるし、体調が悪いときは看病してくれるし、俺のSNSの写真だってずっと見ていてくれた。
付き合ったら、きっと幸せにしてくれるんだろうな。
……でも、榊原はアメリカに行くし、さらには最初から俺と付き合うつもりなんてさらさらないのだ。
向こうで関わる人間もめちゃくちゃ多いだろう。俺のことなんてすぐ忘れるに決まってる。
かわいい女の子にも関わるだろう。さっきみたいに連絡先を聞かれることだって、何度もあるだろう。
そのうち、俺以外の誰かを好きになる、確実に。
そう思ったら、ますます胸が痛くて息ができなくなった。
俺はいつから、こんなに榊原のことばかり考えるようになったんだろう。
嫌われてるって気づいた時から?
それともあいつが俺を好きだって気づいた時から?
ガチャッと部屋の扉が開く。
「水野先輩、ただいま」
そんな声とともに、微笑んだ榊原が部屋に入ってきた。
「おかえり……」
……俺はもうだめだ。こいつが好きなんだって、認めるしかない。
榊原の顔を見ただけで、好きだと言ってしまいそうになるのだから。
俺は心の声を押し殺し、いつもの質問をした。
「……俺のこと、好き?」
「会ってすぐそれかよ」
けらけらと笑ったあと、「はい」と榊原が答える。
好きだ、と思う。
でも、言ってどうなる?
榊原はアメリカに行く。俺は日本に残る。
榊原は夢を追いかけてますます忙しくなる。遠距離なんて、無理に決まってる。
だったら、黙っていたほうがいい。
榊原の夢の邪魔なんて、絶対にしたくない。
*
留学まで、あと三日。榊原の部屋の荷物が少しずつ減っていく。
榊原は、前より優しかった。
俺が落ち込んでいるのを察しているのか、さりげなく気を遣ってくれる。
それがまたつらかった。
その日の夜、部屋でぼんやりしていると、榊原が声をかけてきた。
「先輩、ちょっといいですか」
「……なに」
「写真、撮ってほしいんですけど」
「写真?」
榊原がスマホを取り出した。
「俺たちのツーショット。……一枚も持ってないなって気づいて」
俺は目を丸くした。
確かに、俺と榊原の写真なんて一枚もない。
俺はいつも撮る側で、榊原は撮られる側で。二人で写ったことなんて、一度もなかった。
「……いいよ」
「じゃあ、こっち来てください」
榊原が自分のベッドに座って、隣をぽんぽんと叩いた。
俺は少し躊躇してから、榊原の隣に座った。
近い。肩が触れる距離。
榊原がスマホを持ち上げて、インカメラを起動した。
画面に、俺と榊原の顔が並んで映る。
「……なんか照れるわ」
「ちゃんと笑ってくださいよ、先輩。アメリカ行ったら、毎日この写真を見るんですから」
「言ったな? お前、本当に見ろよ」
「やっぱ毎日は言い過ぎかも」
からかうように榊原が笑い、俺も自然と口元が緩んだ。
カシャ、とシャッター音が鳴った。
「……すげぇいいの撮れたわ」
榊原が画面を確認する。
俺も覗き込んだ。
二人とも、笑っていた。
なんだか気恥ずかしくて、でも嬉しくて。
「……めっちゃいい写真」
「でしょ」
榊原が満足そうに言った。
「これ、先輩にも送りますね。忘れないでくださいよ、俺のこと」
「……忘れるわけないだろ」
俺は画面の中の自分たちを見つめた。
泣いてる榊原の写真を勝手に撮ってしまったのが、すべての始まりだった。
そして今、俺たちはふたりで笑ってる写真を撮っている。
なんか、泣きそうだ。
「……榊原」
「はい」
「……頑張れよ、アメリカ行っても」
それしか言えなかった。
本当は、行かないでほしい。ずっとそばにいてほしい。
でも、言えない。言っちゃいけない。
「……はい。頑張ります」
榊原が静かに答えた。
俺たちは並んで座ったまま、しばらく何も言わなかった。
肩が触れている。それだけで、胸がいっぱいだった。
あと三日。
たった三日で、こいつはいなくなる。
言えないまま終わっていく。この夜も、この恋も、終わってしまうんだ、きっと。