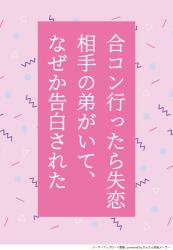――付き合ってほしいとか、そういうのは思ってないです。
一週間前、榊原はそう言った。
お互いに、普通に接する。
それが、俺と榊原の間で交わした約束だった。
でも、――普通ってなんだっけ。
榊原に「好き」って言われてから、俺の中の「普通」がぐらぐらと揺れていた。
「先輩、醤油とって」
「え、あ、うん」
食堂で向かいに座った榊原に話しかけられて、俺は慌てて醤油を渡した。
指先が触れた。そんな些細なことで、ばかみたいに心臓が跳ねる。
「……なんですか」
「な、なんでもない……」
榊原が怪訝そうな顔をしている。
俺は誤魔化すように味噌汁をすすった。
……ダメだ。全然普通じゃない、俺のほうが。
榊原は俺を避けなくなった。
食堂で向かいに座るし、談話室でも隣にいる。部屋でも普通に話す。
でも、以前と何かが決定的に違うことに気づいていた。
榊原が俺を見る目が、前よりずっと優しい。
それに気づくたびに、俺の心臓は勝手に騒ぎ出すのだ。
「なぁ、榊原」
俺は榊原にこっそりと声をかける。
「はい」
「お前、俺のこと……好きなんだよな?」
榊原が箸を止めた。
少し離れた席では、陽キャの久我が中心となって、ゲラゲラとさわがしく話をしている。
榊原は周りの様子を確認してから、呆れたように息を吐く。
「アンタ、それ今日だけで三回目ですよ」
「いやだって……」
「昨日も五回は聞かれた気がするんですけど」
「そんなに聞いてないだろ!」
「聞いてます」
榊原がじとっとした目で俺を見る。
たしかに聞いた……かもしれない。
いや、だって仕方ないじゃないか。イケメンの榊原が、どこにでもいるようなモブの俺を好きとか、未だに信じられるわけがない。
「好きですよ。むかつくくらい、かなり」
さらっと言われて、息が止まりそうになる。俺は、今日三回もこんなことを繰り返していた。
「……そ、そっか」
「そっか、じゃないですよ。いい加減、慣れろよな」
「なっ、慣れるわけないだろ……!」
小声で叫ぶと、榊原がふっと笑った。
その笑顔がまた心臓に悪くて、俺は味噌汁を一気に飲み干した。熱い。
*
その日の夜、俺は部屋で課題をやっていた。……けれど、集中できるわけもなく、隣で筋トレをしている榊原の存在をすぐ近くに感じている。
「……水野先輩」
筋トレをし終わったのか、榊原が不意に口を開いた。
「えっ?」
「ひとつ、アンタに謝らなきゃいけないことがあって」
榊原がじっと俺を見下ろす。
「謝る?」
「はい。単刀直入に言いますけど、先輩のSNS、中学の時からずっと見てました」
「……は?」
「写真用のアカウント。見つけて、ずっとフォローしてました」
俺は目を丸くした。
え、マジで?
「フォロワーに『SS』っていません?」
「SS? ……いる! けっこう前からいいねくれる人! 毎回反応してくれるから、めっちゃありがたいなって……!」
言いかけて、気づいた。
SS。榊原昴のイニシャル。
「……もしかして、お前?」
「うん、俺」
榊原はあっさりとそう言って、部屋着で額の汗を拭う。
「中学の時にアカウント作って、ずっと見てました。先輩の写真、ぜんぶ保存してます」
「ぜ、ぜんぶ!?」
「気持ち悪いでしょ。わかってます」
「気持ち悪くはないって……」
ないけど、衝撃がすごい。
あのSSって、榊原だったんだ、毎回いいねくれてた……。
「すみません。ストーカーみたいで」
「いや……」
「ずっと言おうと思ってたんですけど、タイミングなくて。……でも、隠したままいんのも違うかなって」
「…………」
「引きますよね」
俺は頭を抱えた。
榊原の執着が、想像以上にすごかった。中学からって、三年以上前からってことだろ。
「俺のこと好きすぎじゃ……」
「だから、そうだって言ってんだろ。それくらい、俺は先輩に執着してるってことです」
榊原が開き直ったように言った。
その顔は平然としていて、俺のほうが顔が熱くなっていく。
「でもまぁ、気持ち悪かったらブロックしてください。消えますんで」
「き、消えるなよ、ばか!」
「…………いいんですか、俺に見られてても」
「いいよ。……SSさんからの……じゃなくて、お前からのいいね、けっこう励みになってたんだよ。知らなかったけど」
榊原が、少しだけ意外そうな顔をしたあと、すぐに笑って「ほんとお人好しだな」とつぶやいた。
*
——好きですよ、先輩。
榊原の言葉が、頭から離れない。そりゃあ何度も聞いた俺も悪いけど、授業中も、部活中も、ふとした瞬間に思い出してしまう。
そのたびに顔が熱くなって、集中できなくなる。
これじゃあ俺のほうがおかしくなってんだろ……。
放課後、俺はバスケ部の練習を見に行った。
写真部の仕事があるわけじゃない。ただ、榊原を見たかっただけだ。
……我ながら、だいぶやばい気がする。
体育館の端っこで、俺はコートを眺めていた。
榊原が走り回っている。ドリブル、パス、シュート。どの動きも綺麗で、目が離せない。
斜め前では、バスケ部の誰かの彼女なのか、他校の女子たちが榊原や藤堂を見てきゃあきゃあ騒いでいる。
……わかる。あいつら、かっこいいもんな。特に、……榊原が。
練習の休憩時間、榊原が体育館から出てきた。
俺を見つけて、怪訝そうな顔をする。
「先輩、なんでいるんですか」
「いや、お前の練習見に来た」
「見に来たって……写真部の活動じゃないですよね」
「うん。ただの応援」
「……応援て」
榊原がぽかんとした顔をしている。
なんかおかしいこと言ったか?
流れた沈黙が怖くなって、俺はぼそっと本音を漏らした。
「お前、今日もシュート決まりまくっててかっこよかったね」
「……どうも」
「なんか……」
「……ん?」
「なんか最近、……お前から目が離せなくて困る」
素直にそう言ったら、榊原が固まった。
数秒の沈黙のあと、榊原が顔を背ける。明らかに耳が赤い。
「……困るのはこっちですよ。そういうの、やめてください」
「え、なんで」
「俺が勘違いするだろ」
俺を見ないようにしながら、榊原が続ける。
「先輩がそうやって普通に褒めてくれんの、すげぇ嬉しいですけど。いちいち期待すんのだるいんで、やめてもらえますか」
「……き、期待って、なに」
「…………わかんだろ、普通に」
「だ、だって! お前が付き合うつもりないって言ったんだろ!」
「だから困るって言ってんですよ」
榊原が苛立ったように言った。
俺も少しムッとする。
「……じゃあ褒めないほうがいいの?」
「そうじゃなくて」
「お前の応援しちゃダメなの?」
「だからそうじゃなくて……」
「じゃあなんだよ」
「…………」
榊原が黙った。
気まずい沈黙が流れる。
「……やだ」
「は?」
「お前を褒めないとか、応援しないとか、やだ。俺はお前のこと応援したいし、かっこいいって思ったらぜったい言いたい」
榊原が目を見開いた。
俺も自分で何言ってるのかよくわからなくなってきた。でも、止まらない。
「お前が困るのは知らない。俺は言いたいから言う」
「……アンタ、なんなんすか」
「知らない」
俺たちは睨み合うように見つめ合った。
数秒後、榊原がふっと力を抜いた。
「……あー、ほんと負けるわ。水野先輩ってガチで嫌」
「き、嫌いになった?」
「なんねぇよ。好きだよ」
「……うん、よ――」
よかった。そう言おうとして、はっとして言葉を止めた。
なんだよ、よかったって。
「……まぁ、とにかく……応援、あざした」
「おう」
「嬉しかったです。……クソだるいけど」
最後に意地悪くそう付け足して、榊原はまた体育館に戻っていった。
だるいなんて言って、顔はすごくにやけていたから、たぶんやっぱり……あいつは俺を好きなんだと思う。
*
その夜、榊原より先に部屋に戻って、シャワーを浴び終わった時のことだ。
俺はパンツ一枚で、タオルで髪を拭きながら部屋に戻った。
——そこに、榊原が立っていた。
「うわっ、ビビった!」
「……っ」
榊原が、固まった。
俺を見て、目を見開いている。その視線が、俺の体をなぞるように動いた。
首筋、鎖骨、胸元、腹筋——。
「……な、なんだよ」
「いや……」
「貧相な体で悪かったな」
「……言ってねぇだろ」
榊原が、ぐっと視線を逸らした。
耳が赤くなっているのがわかる。
「先輩、一応俺、アンタのこと好きなんで」
「……う、……うん?」
「そういう格好で目の前うろつかれると困るっていうか……。マジでこっちの勝手な言い分ですけど、油断しないでもらえますか」
俺は急に自分の格好が恥ずかしくなって、慌ててタオルを体に巻きつけた。
「わ、悪い。着替える」
「……そうしてください」
榊原が、俺を見ないようにしながらベッドのほうへ歩いていった。
俺は急いでクローゼットからTシャツとスウェットを引っ張り出して、着替えた。
心臓がうるさい。
今の榊原の視線、やけに熱かった。
俺の体を見て、あんな顔するんだ。あんな声出すんだ。
……俺のこと、本当に好きなんだ。
わかってたはずなのに、改めて性的な衝動を突きつけられると、なんか……すごくドキドキする。
「……着替えた」
「ああ……はい」
榊原はこっちを見ないようにして、ベッドに座ってスマホをいじっている。
俺は自分のベッドに腰を下ろして、榊原のほうを見た。
「……俺のこと、まだ好き?」
榊原が大きな声を出して笑った。心底、おもしろいと言うように。
「意外と欲しがりなんですね、先輩って」
「べっ、別にそういうわけじゃ……」
「好きだよ、先輩」
照れずに、まっすぐ言ってくる。
こいつ、なんでそんな平気な顔で言えるんだ。
「……お前って、前の彼女にも、そうやって好き好き言ってたのかよ」
「好き好き……。つうか、前の彼女は聞いてこなかったですよ。アンタみたいに一日何回も」
「……ごめん」
「謝んなくていいです」
榊原が困ったように微笑む。
「アンタが聞きたいなら、いくらでも言います」
「…………」
「好きです、水野先輩」
まっすぐな目で、そう言われた。
心臓がうるさい。顔が熱い。
……なんで俺、こんなにドキドキしてるんだ。お前に付き合う気がないのは知ってるのに。
*
榊原は最近、部屋のシャワーじゃなくて大浴場を使うことが増えていた。うちの寮には各部屋にシャワーがついているけど、大浴場もある。
たぶん榊原は俺を気遣っているのだろう。
その夜。
榊原が大浴場に行っている間、ドアがノックされた。
開けると、藤堂が立っていた。
「水野先輩、今ちょっといいですか。榊原、風呂で今いないっスよね」
「いないけど……どうした?」
「あいつがいないとこで話したくて。廊下、出て来てもらえます? ここならあいつが来てもすぐわかるし」
藤堂の表情がいつもと違う。にやにやした感じがない。
俺は廊下に出て、ドアを閉めた。
「榊原のことなんですけど……」
「……うん」
「あいつ、先週監督に呼び出されたの知ってます?」
「いや、知らない。……なんかあったの?」
「留学の話です」
「……りゅっ、留学!?」
思いもよらなかった単語が耳に届き、俺は固まった。
「はい。アメリカの強豪校からスカウトが来てて。前から話は進んでたんですけど、受け入れ先が正式に決まったみたいです」
「…………ア、アメリカ」
「たぶん、二ヶ月後には出発するかもって」
二ヶ月後。
あと六十日あるかないかだ。
「向こうの高校で経験積んで、大学リーグを目指すらしいです。NBAのスカウトって大学の試合を見に来るんで、そこで活躍すればプロへの道も開けるっていう」
「……そう、なんだ」
「あいつの実力なら、マジでNBA行けるかもしんないですから」
「……そ、そっか」
「もしかして、榊原から聞いて……」
「……ない」
頭が真っ白になる。聞いてない。榊原から、一度だって。
「あー……やっぱ言ってなかったんスね、あいつ」
藤堂が気まずそうに頭を掻いた。
「たぶん、言いづらかったんだと思います。先輩には特に……」
藤堂が言葉を濁す。たぶん藤堂は榊原が俺を好きなことを知っているんだと思った。
「すみません、俺が先に言っちゃって。でも、先輩には知っといてほしくて。あいつ絶対自分からは言わねぇだろうし」
「…………」
「あ、榊原には俺から聞いたって言わないでくださいね。殺されるんで」
藤堂は軽く手を挙げて、自分の部屋のほうへ戻っていった。
俺は廊下に立ったまま、しばらく動けなかった。
榊原がいなくなる。
この学校から。この寮から。俺の隣から。
二ヶ月後に。
廊下の奥から、風呂上がりの榊原が歩いてくるのが見えた。
濡れた髪。上気した頬。俺を見つけて、不思議そうに首を傾げる。
「先輩、なんで廊下にいるんですか」
「……い、いや、なんでも」
先に部屋に戻り、ベッドに飛び込んで頭から布団を被った。
なんで、言ってくれなかったんだよ。
胸の奥が軋むように痛い。
俺には何も求めてないって、そういうことだったのか。
最初から、お前は……。
俺の前からいなくなるつもりだったんだ。
一週間前、榊原はそう言った。
お互いに、普通に接する。
それが、俺と榊原の間で交わした約束だった。
でも、――普通ってなんだっけ。
榊原に「好き」って言われてから、俺の中の「普通」がぐらぐらと揺れていた。
「先輩、醤油とって」
「え、あ、うん」
食堂で向かいに座った榊原に話しかけられて、俺は慌てて醤油を渡した。
指先が触れた。そんな些細なことで、ばかみたいに心臓が跳ねる。
「……なんですか」
「な、なんでもない……」
榊原が怪訝そうな顔をしている。
俺は誤魔化すように味噌汁をすすった。
……ダメだ。全然普通じゃない、俺のほうが。
榊原は俺を避けなくなった。
食堂で向かいに座るし、談話室でも隣にいる。部屋でも普通に話す。
でも、以前と何かが決定的に違うことに気づいていた。
榊原が俺を見る目が、前よりずっと優しい。
それに気づくたびに、俺の心臓は勝手に騒ぎ出すのだ。
「なぁ、榊原」
俺は榊原にこっそりと声をかける。
「はい」
「お前、俺のこと……好きなんだよな?」
榊原が箸を止めた。
少し離れた席では、陽キャの久我が中心となって、ゲラゲラとさわがしく話をしている。
榊原は周りの様子を確認してから、呆れたように息を吐く。
「アンタ、それ今日だけで三回目ですよ」
「いやだって……」
「昨日も五回は聞かれた気がするんですけど」
「そんなに聞いてないだろ!」
「聞いてます」
榊原がじとっとした目で俺を見る。
たしかに聞いた……かもしれない。
いや、だって仕方ないじゃないか。イケメンの榊原が、どこにでもいるようなモブの俺を好きとか、未だに信じられるわけがない。
「好きですよ。むかつくくらい、かなり」
さらっと言われて、息が止まりそうになる。俺は、今日三回もこんなことを繰り返していた。
「……そ、そっか」
「そっか、じゃないですよ。いい加減、慣れろよな」
「なっ、慣れるわけないだろ……!」
小声で叫ぶと、榊原がふっと笑った。
その笑顔がまた心臓に悪くて、俺は味噌汁を一気に飲み干した。熱い。
*
その日の夜、俺は部屋で課題をやっていた。……けれど、集中できるわけもなく、隣で筋トレをしている榊原の存在をすぐ近くに感じている。
「……水野先輩」
筋トレをし終わったのか、榊原が不意に口を開いた。
「えっ?」
「ひとつ、アンタに謝らなきゃいけないことがあって」
榊原がじっと俺を見下ろす。
「謝る?」
「はい。単刀直入に言いますけど、先輩のSNS、中学の時からずっと見てました」
「……は?」
「写真用のアカウント。見つけて、ずっとフォローしてました」
俺は目を丸くした。
え、マジで?
「フォロワーに『SS』っていません?」
「SS? ……いる! けっこう前からいいねくれる人! 毎回反応してくれるから、めっちゃありがたいなって……!」
言いかけて、気づいた。
SS。榊原昴のイニシャル。
「……もしかして、お前?」
「うん、俺」
榊原はあっさりとそう言って、部屋着で額の汗を拭う。
「中学の時にアカウント作って、ずっと見てました。先輩の写真、ぜんぶ保存してます」
「ぜ、ぜんぶ!?」
「気持ち悪いでしょ。わかってます」
「気持ち悪くはないって……」
ないけど、衝撃がすごい。
あのSSって、榊原だったんだ、毎回いいねくれてた……。
「すみません。ストーカーみたいで」
「いや……」
「ずっと言おうと思ってたんですけど、タイミングなくて。……でも、隠したままいんのも違うかなって」
「…………」
「引きますよね」
俺は頭を抱えた。
榊原の執着が、想像以上にすごかった。中学からって、三年以上前からってことだろ。
「俺のこと好きすぎじゃ……」
「だから、そうだって言ってんだろ。それくらい、俺は先輩に執着してるってことです」
榊原が開き直ったように言った。
その顔は平然としていて、俺のほうが顔が熱くなっていく。
「でもまぁ、気持ち悪かったらブロックしてください。消えますんで」
「き、消えるなよ、ばか!」
「…………いいんですか、俺に見られてても」
「いいよ。……SSさんからの……じゃなくて、お前からのいいね、けっこう励みになってたんだよ。知らなかったけど」
榊原が、少しだけ意外そうな顔をしたあと、すぐに笑って「ほんとお人好しだな」とつぶやいた。
*
——好きですよ、先輩。
榊原の言葉が、頭から離れない。そりゃあ何度も聞いた俺も悪いけど、授業中も、部活中も、ふとした瞬間に思い出してしまう。
そのたびに顔が熱くなって、集中できなくなる。
これじゃあ俺のほうがおかしくなってんだろ……。
放課後、俺はバスケ部の練習を見に行った。
写真部の仕事があるわけじゃない。ただ、榊原を見たかっただけだ。
……我ながら、だいぶやばい気がする。
体育館の端っこで、俺はコートを眺めていた。
榊原が走り回っている。ドリブル、パス、シュート。どの動きも綺麗で、目が離せない。
斜め前では、バスケ部の誰かの彼女なのか、他校の女子たちが榊原や藤堂を見てきゃあきゃあ騒いでいる。
……わかる。あいつら、かっこいいもんな。特に、……榊原が。
練習の休憩時間、榊原が体育館から出てきた。
俺を見つけて、怪訝そうな顔をする。
「先輩、なんでいるんですか」
「いや、お前の練習見に来た」
「見に来たって……写真部の活動じゃないですよね」
「うん。ただの応援」
「……応援て」
榊原がぽかんとした顔をしている。
なんかおかしいこと言ったか?
流れた沈黙が怖くなって、俺はぼそっと本音を漏らした。
「お前、今日もシュート決まりまくっててかっこよかったね」
「……どうも」
「なんか……」
「……ん?」
「なんか最近、……お前から目が離せなくて困る」
素直にそう言ったら、榊原が固まった。
数秒の沈黙のあと、榊原が顔を背ける。明らかに耳が赤い。
「……困るのはこっちですよ。そういうの、やめてください」
「え、なんで」
「俺が勘違いするだろ」
俺を見ないようにしながら、榊原が続ける。
「先輩がそうやって普通に褒めてくれんの、すげぇ嬉しいですけど。いちいち期待すんのだるいんで、やめてもらえますか」
「……き、期待って、なに」
「…………わかんだろ、普通に」
「だ、だって! お前が付き合うつもりないって言ったんだろ!」
「だから困るって言ってんですよ」
榊原が苛立ったように言った。
俺も少しムッとする。
「……じゃあ褒めないほうがいいの?」
「そうじゃなくて」
「お前の応援しちゃダメなの?」
「だからそうじゃなくて……」
「じゃあなんだよ」
「…………」
榊原が黙った。
気まずい沈黙が流れる。
「……やだ」
「は?」
「お前を褒めないとか、応援しないとか、やだ。俺はお前のこと応援したいし、かっこいいって思ったらぜったい言いたい」
榊原が目を見開いた。
俺も自分で何言ってるのかよくわからなくなってきた。でも、止まらない。
「お前が困るのは知らない。俺は言いたいから言う」
「……アンタ、なんなんすか」
「知らない」
俺たちは睨み合うように見つめ合った。
数秒後、榊原がふっと力を抜いた。
「……あー、ほんと負けるわ。水野先輩ってガチで嫌」
「き、嫌いになった?」
「なんねぇよ。好きだよ」
「……うん、よ――」
よかった。そう言おうとして、はっとして言葉を止めた。
なんだよ、よかったって。
「……まぁ、とにかく……応援、あざした」
「おう」
「嬉しかったです。……クソだるいけど」
最後に意地悪くそう付け足して、榊原はまた体育館に戻っていった。
だるいなんて言って、顔はすごくにやけていたから、たぶんやっぱり……あいつは俺を好きなんだと思う。
*
その夜、榊原より先に部屋に戻って、シャワーを浴び終わった時のことだ。
俺はパンツ一枚で、タオルで髪を拭きながら部屋に戻った。
——そこに、榊原が立っていた。
「うわっ、ビビった!」
「……っ」
榊原が、固まった。
俺を見て、目を見開いている。その視線が、俺の体をなぞるように動いた。
首筋、鎖骨、胸元、腹筋——。
「……な、なんだよ」
「いや……」
「貧相な体で悪かったな」
「……言ってねぇだろ」
榊原が、ぐっと視線を逸らした。
耳が赤くなっているのがわかる。
「先輩、一応俺、アンタのこと好きなんで」
「……う、……うん?」
「そういう格好で目の前うろつかれると困るっていうか……。マジでこっちの勝手な言い分ですけど、油断しないでもらえますか」
俺は急に自分の格好が恥ずかしくなって、慌ててタオルを体に巻きつけた。
「わ、悪い。着替える」
「……そうしてください」
榊原が、俺を見ないようにしながらベッドのほうへ歩いていった。
俺は急いでクローゼットからTシャツとスウェットを引っ張り出して、着替えた。
心臓がうるさい。
今の榊原の視線、やけに熱かった。
俺の体を見て、あんな顔するんだ。あんな声出すんだ。
……俺のこと、本当に好きなんだ。
わかってたはずなのに、改めて性的な衝動を突きつけられると、なんか……すごくドキドキする。
「……着替えた」
「ああ……はい」
榊原はこっちを見ないようにして、ベッドに座ってスマホをいじっている。
俺は自分のベッドに腰を下ろして、榊原のほうを見た。
「……俺のこと、まだ好き?」
榊原が大きな声を出して笑った。心底、おもしろいと言うように。
「意外と欲しがりなんですね、先輩って」
「べっ、別にそういうわけじゃ……」
「好きだよ、先輩」
照れずに、まっすぐ言ってくる。
こいつ、なんでそんな平気な顔で言えるんだ。
「……お前って、前の彼女にも、そうやって好き好き言ってたのかよ」
「好き好き……。つうか、前の彼女は聞いてこなかったですよ。アンタみたいに一日何回も」
「……ごめん」
「謝んなくていいです」
榊原が困ったように微笑む。
「アンタが聞きたいなら、いくらでも言います」
「…………」
「好きです、水野先輩」
まっすぐな目で、そう言われた。
心臓がうるさい。顔が熱い。
……なんで俺、こんなにドキドキしてるんだ。お前に付き合う気がないのは知ってるのに。
*
榊原は最近、部屋のシャワーじゃなくて大浴場を使うことが増えていた。うちの寮には各部屋にシャワーがついているけど、大浴場もある。
たぶん榊原は俺を気遣っているのだろう。
その夜。
榊原が大浴場に行っている間、ドアがノックされた。
開けると、藤堂が立っていた。
「水野先輩、今ちょっといいですか。榊原、風呂で今いないっスよね」
「いないけど……どうした?」
「あいつがいないとこで話したくて。廊下、出て来てもらえます? ここならあいつが来てもすぐわかるし」
藤堂の表情がいつもと違う。にやにやした感じがない。
俺は廊下に出て、ドアを閉めた。
「榊原のことなんですけど……」
「……うん」
「あいつ、先週監督に呼び出されたの知ってます?」
「いや、知らない。……なんかあったの?」
「留学の話です」
「……りゅっ、留学!?」
思いもよらなかった単語が耳に届き、俺は固まった。
「はい。アメリカの強豪校からスカウトが来てて。前から話は進んでたんですけど、受け入れ先が正式に決まったみたいです」
「…………ア、アメリカ」
「たぶん、二ヶ月後には出発するかもって」
二ヶ月後。
あと六十日あるかないかだ。
「向こうの高校で経験積んで、大学リーグを目指すらしいです。NBAのスカウトって大学の試合を見に来るんで、そこで活躍すればプロへの道も開けるっていう」
「……そう、なんだ」
「あいつの実力なら、マジでNBA行けるかもしんないですから」
「……そ、そっか」
「もしかして、榊原から聞いて……」
「……ない」
頭が真っ白になる。聞いてない。榊原から、一度だって。
「あー……やっぱ言ってなかったんスね、あいつ」
藤堂が気まずそうに頭を掻いた。
「たぶん、言いづらかったんだと思います。先輩には特に……」
藤堂が言葉を濁す。たぶん藤堂は榊原が俺を好きなことを知っているんだと思った。
「すみません、俺が先に言っちゃって。でも、先輩には知っといてほしくて。あいつ絶対自分からは言わねぇだろうし」
「…………」
「あ、榊原には俺から聞いたって言わないでくださいね。殺されるんで」
藤堂は軽く手を挙げて、自分の部屋のほうへ戻っていった。
俺は廊下に立ったまま、しばらく動けなかった。
榊原がいなくなる。
この学校から。この寮から。俺の隣から。
二ヶ月後に。
廊下の奥から、風呂上がりの榊原が歩いてくるのが見えた。
濡れた髪。上気した頬。俺を見つけて、不思議そうに首を傾げる。
「先輩、なんで廊下にいるんですか」
「……い、いや、なんでも」
先に部屋に戻り、ベッドに飛び込んで頭から布団を被った。
なんで、言ってくれなかったんだよ。
胸の奥が軋むように痛い。
俺には何も求めてないって、そういうことだったのか。
最初から、お前は……。
俺の前からいなくなるつもりだったんだ。