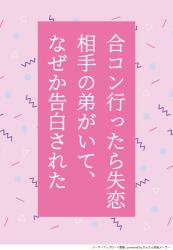【榊原Side】
——もしかして、俺のこと好きなんじゃない?
水野先輩の声が、頭の中で何度も響いている。
談話室を飛び出して、俺は寮の裏庭にいた。誰もいない暗がりで、壁にもたれかかって空を見上げる。
心臓がうるさい。さっきからずっと、おかしいくらいに脈打っている。
「……ふざけんな」
吐き捨てるように呟いた。
好き? 俺が? あの人のことを?
んなわけねぇだろ。
俺はあの人のことが嫌いだ。あの人がのんきに俺の泣いた写真をSNSに載せてから、ずっとそう思ってきた。
あの人と同じ高校に入って、ますます嫌いになった。
あの人の、自分を犠牲にしてまで誰にでも優しくするところが嫌いだ。
くだらない冗談を言ってへらへら笑っているところが嫌いだ。
久我先輩たちに気安く触られても気づかないで、へらへらしているところが嫌いだ。
俺がガン見していることにも気づかないで、上半身裸でうろつきやがって——。
「…………」
待て。
今、俺、なんて思った?
頭を抱える。
落ち着け。冷静になれ。
俺は水野先輩のことが嫌いだ。ずっとそう思ってきただろ。中学の時に泣いている写真を撮られて以来、ずっと。
ずっと――って、……え、俺ってキモすぎない?
先輩の言うとおり、たしかにあの写真の俺は豆粒みたいに小さかった。友人に「泣いた写真撮られたんだけど……マジうぜぇ」って見せた時も、「お前だって誰もわかんねぇよ」と軽くあしらわれていた。
それをわざわざ根に持って、何年も「嫌い」だと思い続けるのは——普通に考えて、……キモくね?
そもそも、本当に嫌いな相手のことを、こんなに目で追うか?
本当に嫌いな相手の看病をするか?
本当に嫌いな相手が他の奴と話しているだけで、こんなにイライラするか?
意味わかんねぇ。
「……くそ」
ポケットの中のスマホが震えた。画面を見ると、藤堂からのLINEだった。
『どこいんの? こっちの部屋、来いよ』
同じバスケ部で、小学校からの腐れ縁。俺のことを一番よく知っている友人。
……いや、今は誰とも話したくない。
無視しようとしたけど、すぐに次のメッセージが来た。
『水野先輩と何かあった? お前らが談話室でなんかあったらしいって、もう寮中で噂になってるぞ』
舌打ちする。この寮、噂が広まるのが早すぎるだろ。
返信を打とうとして、指が止まった。なんて返せばいいかわからない。
結局、既読だけつけてスマホをポケットに戻した。
数分後、裏庭に足音が近づいてきた。
「やっぱここにいた」
藤堂だった。俺の隣に来て、同じように壁にもたれかかる。
「……なんで来んだよ」
「お前が来いっつっても来ないからだろ。で、何があったんだよ」
「なんもねぇよ」
「嘘つけ。……どうせ水野先輩絡みだろ」
「なんだよ、『どうせ』って」
「いや、お前、あの人のことになると毎回妙にガキみたいなことするから」
藤堂が遠慮なく俺の顔を覗き込んでくる。うざい。こいつ、昔からこういう奴だ。
「……先輩に、変なこと言われた」
「変なこと?」
「……俺が水野先輩のこと好きなんじゃないかって」
言った瞬間、藤堂が「え」という顔をした。そしてしばらく黙って考え込んでから、「あー……」と声を出す。
「……お前、それで逃げ出してきたの?」
「逃げ出したんじゃねぇし、腹立っただけだし」
「はぁ……やっぱ、そういうことか」
「……は?」
「前からお前のこと怪しいとは思ってたんだよ。水野先輩に対してだけ明らかに態度おかしいし……でも、まさか本人が気づいてないとは思わなかったから、黙ってたんだけど」
「…………」
「図星突かれて動揺したってことは——お前、水野先輩のこと好きなんだろ」
藤堂が呆れたように言い切った。
「色々繋がったわ。最近のお前、水野先輩の話するとき、めちゃくちゃ楽しそうだもん」
「……楽しそうって、俺が?」
「うん。『今日も先輩がうぜぇ』とか言いながら、顔にやけてんの。気持ち悪いくらい」
「にやけてねぇし」
「にやけてる。つーか、お前が誰かの話をあんなにするの、初めて見たわ」
藤堂が腕を組んで続ける。
「食堂でも先輩のそばに座るし、談話室でも先輩の近くにいるし。そもそも、1年の時から、他の奴が先輩と楽しそうに話してるとすげぇ不機嫌になってたじゃん」
「……それはあの人がいちいち視界に入って、ウザいからだろ!」
「勝手に目で追ってんのは誰だよ」
「……うっ」
「先輩が風邪ひいた時、授業サボってまで看病してたよな?」
「サボってない……」
「体育ん時も、数学ん時も、『腹痛い~~』って言って授業抜けてたの俺知ってるけど、まだ続ける?」
「…………」
言い返せなかった。
「あとさぁ、お前ずっと誰かのSNS見てるよな」
「……」
「中学の時からだろ。スマホに通知来るたびにすげぇ速さで開いて、気持ち悪いくらいじっと見てたじゃん」
「……」
「……あれ、水野先輩のアカウントみてたんじゃねぇの?」
「…………」
「図星かよ。お前、わかりやす」
けらけらと笑われて、頬が少しだけ熱くなる。
「……俺、あの人のこと」
「うん」
「……好き、なのかよ」
「俺が知るかよ! 自分の気持ちくらい自分で考えろ! ……でもまぁ、客観的に見て完全に好きだと思うけど」
「…………」
頭の中がぐちゃぐちゃだ。
好き? 俺が、水野先輩のことを?
認めたら、何かが変わってしまう気がして怖かった。
でも——。
「一目惚れしたんだよ、お前。水野先輩に」
「なっ!? ……男にひとめぼれとか!」
「あるだろ? ……おいおい、令和の時代にその説明からしなきゃいけねぇの?」
逃げ場がなくなって、小さくつぶやいた。
「そんなん言ったら……俺、マジで……好き、なのかも……水野先輩のこと……」
「はぁ……榊原さぁ、……ほんと本命に対して不器用すぎじゃない? ガチで赤ちゃんレベルだわ……」
「……赤ちゃん」
「それなりに彼女いたことあるくせに、本命童貞かよ」
「……本命童貞」
「ダサすぎ」
「……ダサすぎ」
頭の中に衝撃が走る。
確かに、中学の時も高校の時も、彼女がいたことはある。告白されて、まぁいいかって付き合って、なんとなく続いて、なんとなく別れた。
でも、誰といても、こんなにもどかしくて腹が立つ気持ちになったことはなかった。
心臓がうるさくなることも、目で追ってしまうことも、腹が立つのにそばにいたいと思うことも。
……あの人の前だと、全部、全部全部全部全部おかしくなる。
「……あー、くそ」
髪をくしゃくしゃとかき混ぜた。
認めたくなかった。でも、もう誤魔化せない。
思い返せば、全部あの人のことばかりだ。
「…………マジかよ」
呆然と呟いた。
俺、水野先輩のことが好きだ。
嫌いだと思ってたのは、好きすぎてどうしていいかわからなかったから……なんて藤堂の言うようにダサすぎる。
「やっと自覚した?」
藤堂が呆れた声を出す。
「で、どうすんの?」
「……どうすんのって」
「告白すんの? しねぇの?」
告白。
その単語が、やけに重く響いた。
「……しても意味ねぇだろ」
「なんで」
「俺、もうすぐアメリカ行くかもしれねぇし」
「バスケ留学の話? まだ決まってないだろ」
「でも、行く可能性は高い。そしたら遠距離になるし……それに、先輩は男だし」
「男とか関係ある? 好きなんだろ?」
藤堂は俺の顔をじっと見て、ため息をついた。
「榊原ん中にさ、今まで『自分が男を好きになる』っていう発想がなかったんだろ?」
「……あったよ。授業でもやったし、別に俺は――!」
「……なんだよ」
「わかんねぇ……」
「はぁ? つうか、難しく考えんなよ。実際のお前の心と、お前の中の認識がバラバラだっただけなんだから。少しずつ合わせていけよ、赤ちゃん」
「……」
「ったく。言い訳ばっか考えやがって。ほんとお前らしくねぇわ。怖いだけじゃん。振られるのが」
ぐっと言葉に詰まる。
「まぁ、お前の人生だから好きにすればいいけどさ」
藤堂がへらっと笑って、俺の肩を叩いた。
「後悔しねぇようにな。アメリカ行くなら、なおさら」
「…………」
「水野先輩だって、お前のこと気にかけてると思うけどな。……恋愛感情って感じではねぇけど」
「……ねぇのかよ」
「ははっ、そこはお前ががんばれよ」
それだけ言って、藤堂は寮の中に戻っていった。
俺は一人残されて、暗い空を見上げる。
どうやら俺は水野先輩のことが、好き……らしい。
今さら気づいても、どうすればいいかわからない。
ふと、中学の頃のことを思い出した。
南陽中対青葉中戦。あの日、俺たちは負けた。
悔しくて、情けなくて、人に見られたくなくて体育館の端で泣いていた。
ふと顔を上げたら、青葉中の制服を着て、にこにこ笑っている男が見えた。今日一日、カメラを構えて、ずっとへらへらと笑い続けていた男だ。またカメラを構え、喜びに溢れる選手たちを撮っている。
どうしようもなく苛立ちを感じた。ほかにも笑っている奴らがいたのに、あの人の笑顔だけが妙に頭に残っていた。
数日後、SNSであの試合の写真を見つけた。
試合の様子を撮影した写真の隅に、小さく映り込んでいる俺。泣いている顔まではわからないけど、俺にはすぐに自分だとわかった。
投稿したのは青葉中写真部の公式アカウントで、写真のクレジットには「撮影:写真部 3年 水野詠太」と書いてあった。
——あいつだ。
あの日、写真部と書かれたカードを首から下げて、カメラを構えていたのはあいつだけだ。奴の顔が、鮮明に蘇ってきた。
にこにこ笑っていた顔。
ムカついた。すげぇムカついた。泣いてるところを撮られたから? それもあるけど、それだけじゃない気がした。あの顔が頭にこびりついて離れないことが、無性に腹立たしかった。
青葉中、写真部で検索をしたら、すぐにそれらしきアカウントが見つかった。こんなふうにすぐ検索できるなんて、まったく危機感がない。
写真専用のアカウントらしく、風景や街並み、たまにちょっとしたつぶやきが並んでいる。
どんな奴なのか気になって、投稿を遡って見た。
変な写真が多かった。
おそらく誰かが忘れていったであろう、公園のベンチにある片方だけの手袋とか。
誰かがガードレールの上にきれいに並べた、どんぐり五個とか。
どれも別になんてことない写真だ。なのに、あの先輩が撮ったと思ったら、なぜか気になってしょうがなかった。
写真の合間には、日常のつぶやきも混ざっていた。
『ゆで卵作ろうとしてレンジで爆発させた。二度とやらない』とか。
『傘三本目なくした。俺に傘を持たせるな』とか。
『カラスに横断歩道で道を譲られた。お前が先に行けよ』とか。
くだらない。ほんとにくだらねぇ日常。
それから、なんとなく水野先輩のアカウントを見るようになった。
練習でうまくいかなかった日とか、授業中に眠くなった時とか、なんの気なしにアカウントを開いて、新しい投稿を眺める。
そのうち通知を設定して、先輩が投稿したらすぐに見るようになった。だって、ムカつくから。
あいつのことは嫌いだけれど……でも、写真だけは認めてやらなくもない。
そんなことを生意気に思いながら、俺は先輩の投稿を見続けた。
たまに水野先輩が写っている写真があると、何度も見返した。
友達にいたずらで撮られたのか、へらっと眉毛を下げて笑っている。
こいつは俺の泣いている写真を撮ったムカつく奴。
本当に、本当に、ムカつく奴。
俺の志望校は、最初から決まっていた。
バスケの強豪校で、ずっと行きたかった高校だ。
ある日、水野先輩のアカウントを見ていたら、短いメッセージが投稿された。
『第一高校、受かった』
——俺が行きたい高校と同じだ。
心臓が跳ねた。
その時は「最悪」だと思った。あんな奴……泣いてる俺の写真を堂々と載せるデリカシーのない奴と同じ高校なんて、ついてない。そう思ったはずだった。
……なのに、なんで俺はあんなにスマホを握りしめていたんだろう。
俺が第一高校に受かった。入学式の日。
寮の前で、俺はあの顔をすぐに見つけた。
二年近く経っても、忘れるわけがなかった。こっちは毎日先輩のSNSを見ているのだ。
また心臓がぎゅっと掴まれたみたいになった。
——あの人だ。
でも、あの写真に俺が映り込んでいたことなんて、本人は気づいてすらいなかった。
先輩は俺を見て、にこにこ笑ってこう言った。
「お、バスケがうまい榊原だよな? 俺は水野、二年。よろしくなー!」
呼吸が速くなる。
直感的にやっぱりこいつのことが嫌いだ、と思った。振り回されたくない。関わりたくない。どうしてこんなにムカつくんだ、と。
「……あー、くそ。考えんのやめよ」
頭を振って、立ち上がる。
いつまでも思い出に浸っていても、どうしようもない。
とりあえず、部屋に戻らないと。
*
部屋に戻ったのは、消灯時間ギリギリだった。
できることなら朝まで外にいたかったけど、そういうわけにもいかない。覚悟を決めてドアを開ける。
「——あ」
水野先輩が、ベッドの上に座っていた。
俺の顔を見た瞬間、慌てたように立ち上がる。
「お、おかえり……」
「…………」
心臓がうるさい。
さっき自覚したばかりの感情が、胸の中で暴れている。
先輩の顔を見るだけで、こんなにどうしようもなくなるなんて。
「あの、さ。さっきは……その」
先輩がもじもじしながら、何か言おうとしている。
たぶん、謝ろうとしているんだろう。俺が怒って出ていったから。
「……すみません。俺が悪かったです。気にしないでください」
「え……?」
俺は先輩の顔を見ないようにして、自分のベッドに向かった。
「え、あの、榊原——」
「眠いんで。寝ます」
そっけなく言って、ベッドに腰を下ろす。
その時、廊下からノックの音がした。
「昴先輩、いますか?」
同じバスケ部の1年、山本の声だった。
俺は反射的に立ち上がって、ドアを開ける。
「……どした」
「あ、すみません、昴先輩! 明日の朝練の集合時間、三十分早まったって……連絡回ってきたから伝えに来たっす!」
「あー、了解。わざわざありがとな」
自分でも驚くくらい、普通の声が出た。
山本に向かって軽く笑って見せると、山本は「また明日、よろしくお願いします!!」と礼儀よく頭を下げて去っていった。
ドアを閉めて振り返ると、水野先輩が目を丸くして俺を見ていた。
「…………なんですか」
「いや……お前、今めっちゃ優しく笑ってたなって」
「は?」
「……俺の前でもそういう顔しろよ。……なぁんて、こういうこと言うからダメなんだよな、俺」
……心臓が痛い。
アンタの前だと、普通になんかできないんだよ。
好きだって自覚する前からずっと、アンタの前でだけ俺はおかしくなる。
俺はベッドに戻って、先輩に背を向けた。
「あ、あのさ、榊原。さっきのことなんだけど」
「……もういいですから。俺が悪かったんで」
「いや、ちゃんと俺にも謝らせろよ! ……冗談で変なこと言って、ほんとごめんな。怒らせるつもりはなかったんだ」
先輩の声が、申し訳なさそうに背中に降ってくる。
……違う。
怒ってなんかない。
むしろ逆だ。図星すぎて、どうしていいかわからなくなっただけだ。
でも、そんなこと言えるわけがない。
「……大丈夫ですから、ほんとに」
「そ、そっか……」
先輩の声が、少しだけ安堵したように聞こえた。
良かった、と小さく呟く声が聞こえて、また胸がぎゅっと締め付けられる。
「じゃあ、その……おやすみ」
「……おやすみなさい」
部屋の電気が消えた。
暗闇の中、俺は目を開けたまま天井を見つめていた。
すぐ隣に、好きな人がいる。
なのに、何も言えない。何もできない。
さっき山本には普通に笑えたのに、この人の前だと顔すらまともに見られない。
藤堂の言葉が、頭の中でリフレインする。
——それなりに彼女いたことあるくせに、本命童貞かよ
「…………」
暗闇の中、小さくため息をつく。
隣のベッドから、先輩の寝息が聞こえてきた。もう寝たのかよ、早ぇな。
……いや、俺が眠れねぇだけか。
寝返りを打って、先輩のほうを見る。
暗くてよく見えないけど、布団の膨らみがかすかに上下しているのがわかった。
なんかすげぇ……かわいいかも。
その姿を見ているだけで、心臓がうるさくなる。
告白なんて、できるわけがない。
……俺ってマジで、本命童貞じゃん。
誰にも聞こえないように心の中で呟いて、俺は布団を頭まで被った。
——もしかして、俺のこと好きなんじゃない?
水野先輩の声が、頭の中で何度も響いている。
談話室を飛び出して、俺は寮の裏庭にいた。誰もいない暗がりで、壁にもたれかかって空を見上げる。
心臓がうるさい。さっきからずっと、おかしいくらいに脈打っている。
「……ふざけんな」
吐き捨てるように呟いた。
好き? 俺が? あの人のことを?
んなわけねぇだろ。
俺はあの人のことが嫌いだ。あの人がのんきに俺の泣いた写真をSNSに載せてから、ずっとそう思ってきた。
あの人と同じ高校に入って、ますます嫌いになった。
あの人の、自分を犠牲にしてまで誰にでも優しくするところが嫌いだ。
くだらない冗談を言ってへらへら笑っているところが嫌いだ。
久我先輩たちに気安く触られても気づかないで、へらへらしているところが嫌いだ。
俺がガン見していることにも気づかないで、上半身裸でうろつきやがって——。
「…………」
待て。
今、俺、なんて思った?
頭を抱える。
落ち着け。冷静になれ。
俺は水野先輩のことが嫌いだ。ずっとそう思ってきただろ。中学の時に泣いている写真を撮られて以来、ずっと。
ずっと――って、……え、俺ってキモすぎない?
先輩の言うとおり、たしかにあの写真の俺は豆粒みたいに小さかった。友人に「泣いた写真撮られたんだけど……マジうぜぇ」って見せた時も、「お前だって誰もわかんねぇよ」と軽くあしらわれていた。
それをわざわざ根に持って、何年も「嫌い」だと思い続けるのは——普通に考えて、……キモくね?
そもそも、本当に嫌いな相手のことを、こんなに目で追うか?
本当に嫌いな相手の看病をするか?
本当に嫌いな相手が他の奴と話しているだけで、こんなにイライラするか?
意味わかんねぇ。
「……くそ」
ポケットの中のスマホが震えた。画面を見ると、藤堂からのLINEだった。
『どこいんの? こっちの部屋、来いよ』
同じバスケ部で、小学校からの腐れ縁。俺のことを一番よく知っている友人。
……いや、今は誰とも話したくない。
無視しようとしたけど、すぐに次のメッセージが来た。
『水野先輩と何かあった? お前らが談話室でなんかあったらしいって、もう寮中で噂になってるぞ』
舌打ちする。この寮、噂が広まるのが早すぎるだろ。
返信を打とうとして、指が止まった。なんて返せばいいかわからない。
結局、既読だけつけてスマホをポケットに戻した。
数分後、裏庭に足音が近づいてきた。
「やっぱここにいた」
藤堂だった。俺の隣に来て、同じように壁にもたれかかる。
「……なんで来んだよ」
「お前が来いっつっても来ないからだろ。で、何があったんだよ」
「なんもねぇよ」
「嘘つけ。……どうせ水野先輩絡みだろ」
「なんだよ、『どうせ』って」
「いや、お前、あの人のことになると毎回妙にガキみたいなことするから」
藤堂が遠慮なく俺の顔を覗き込んでくる。うざい。こいつ、昔からこういう奴だ。
「……先輩に、変なこと言われた」
「変なこと?」
「……俺が水野先輩のこと好きなんじゃないかって」
言った瞬間、藤堂が「え」という顔をした。そしてしばらく黙って考え込んでから、「あー……」と声を出す。
「……お前、それで逃げ出してきたの?」
「逃げ出したんじゃねぇし、腹立っただけだし」
「はぁ……やっぱ、そういうことか」
「……は?」
「前からお前のこと怪しいとは思ってたんだよ。水野先輩に対してだけ明らかに態度おかしいし……でも、まさか本人が気づいてないとは思わなかったから、黙ってたんだけど」
「…………」
「図星突かれて動揺したってことは——お前、水野先輩のこと好きなんだろ」
藤堂が呆れたように言い切った。
「色々繋がったわ。最近のお前、水野先輩の話するとき、めちゃくちゃ楽しそうだもん」
「……楽しそうって、俺が?」
「うん。『今日も先輩がうぜぇ』とか言いながら、顔にやけてんの。気持ち悪いくらい」
「にやけてねぇし」
「にやけてる。つーか、お前が誰かの話をあんなにするの、初めて見たわ」
藤堂が腕を組んで続ける。
「食堂でも先輩のそばに座るし、談話室でも先輩の近くにいるし。そもそも、1年の時から、他の奴が先輩と楽しそうに話してるとすげぇ不機嫌になってたじゃん」
「……それはあの人がいちいち視界に入って、ウザいからだろ!」
「勝手に目で追ってんのは誰だよ」
「……うっ」
「先輩が風邪ひいた時、授業サボってまで看病してたよな?」
「サボってない……」
「体育ん時も、数学ん時も、『腹痛い~~』って言って授業抜けてたの俺知ってるけど、まだ続ける?」
「…………」
言い返せなかった。
「あとさぁ、お前ずっと誰かのSNS見てるよな」
「……」
「中学の時からだろ。スマホに通知来るたびにすげぇ速さで開いて、気持ち悪いくらいじっと見てたじゃん」
「……」
「……あれ、水野先輩のアカウントみてたんじゃねぇの?」
「…………」
「図星かよ。お前、わかりやす」
けらけらと笑われて、頬が少しだけ熱くなる。
「……俺、あの人のこと」
「うん」
「……好き、なのかよ」
「俺が知るかよ! 自分の気持ちくらい自分で考えろ! ……でもまぁ、客観的に見て完全に好きだと思うけど」
「…………」
頭の中がぐちゃぐちゃだ。
好き? 俺が、水野先輩のことを?
認めたら、何かが変わってしまう気がして怖かった。
でも——。
「一目惚れしたんだよ、お前。水野先輩に」
「なっ!? ……男にひとめぼれとか!」
「あるだろ? ……おいおい、令和の時代にその説明からしなきゃいけねぇの?」
逃げ場がなくなって、小さくつぶやいた。
「そんなん言ったら……俺、マジで……好き、なのかも……水野先輩のこと……」
「はぁ……榊原さぁ、……ほんと本命に対して不器用すぎじゃない? ガチで赤ちゃんレベルだわ……」
「……赤ちゃん」
「それなりに彼女いたことあるくせに、本命童貞かよ」
「……本命童貞」
「ダサすぎ」
「……ダサすぎ」
頭の中に衝撃が走る。
確かに、中学の時も高校の時も、彼女がいたことはある。告白されて、まぁいいかって付き合って、なんとなく続いて、なんとなく別れた。
でも、誰といても、こんなにもどかしくて腹が立つ気持ちになったことはなかった。
心臓がうるさくなることも、目で追ってしまうことも、腹が立つのにそばにいたいと思うことも。
……あの人の前だと、全部、全部全部全部全部おかしくなる。
「……あー、くそ」
髪をくしゃくしゃとかき混ぜた。
認めたくなかった。でも、もう誤魔化せない。
思い返せば、全部あの人のことばかりだ。
「…………マジかよ」
呆然と呟いた。
俺、水野先輩のことが好きだ。
嫌いだと思ってたのは、好きすぎてどうしていいかわからなかったから……なんて藤堂の言うようにダサすぎる。
「やっと自覚した?」
藤堂が呆れた声を出す。
「で、どうすんの?」
「……どうすんのって」
「告白すんの? しねぇの?」
告白。
その単語が、やけに重く響いた。
「……しても意味ねぇだろ」
「なんで」
「俺、もうすぐアメリカ行くかもしれねぇし」
「バスケ留学の話? まだ決まってないだろ」
「でも、行く可能性は高い。そしたら遠距離になるし……それに、先輩は男だし」
「男とか関係ある? 好きなんだろ?」
藤堂は俺の顔をじっと見て、ため息をついた。
「榊原ん中にさ、今まで『自分が男を好きになる』っていう発想がなかったんだろ?」
「……あったよ。授業でもやったし、別に俺は――!」
「……なんだよ」
「わかんねぇ……」
「はぁ? つうか、難しく考えんなよ。実際のお前の心と、お前の中の認識がバラバラだっただけなんだから。少しずつ合わせていけよ、赤ちゃん」
「……」
「ったく。言い訳ばっか考えやがって。ほんとお前らしくねぇわ。怖いだけじゃん。振られるのが」
ぐっと言葉に詰まる。
「まぁ、お前の人生だから好きにすればいいけどさ」
藤堂がへらっと笑って、俺の肩を叩いた。
「後悔しねぇようにな。アメリカ行くなら、なおさら」
「…………」
「水野先輩だって、お前のこと気にかけてると思うけどな。……恋愛感情って感じではねぇけど」
「……ねぇのかよ」
「ははっ、そこはお前ががんばれよ」
それだけ言って、藤堂は寮の中に戻っていった。
俺は一人残されて、暗い空を見上げる。
どうやら俺は水野先輩のことが、好き……らしい。
今さら気づいても、どうすればいいかわからない。
ふと、中学の頃のことを思い出した。
南陽中対青葉中戦。あの日、俺たちは負けた。
悔しくて、情けなくて、人に見られたくなくて体育館の端で泣いていた。
ふと顔を上げたら、青葉中の制服を着て、にこにこ笑っている男が見えた。今日一日、カメラを構えて、ずっとへらへらと笑い続けていた男だ。またカメラを構え、喜びに溢れる選手たちを撮っている。
どうしようもなく苛立ちを感じた。ほかにも笑っている奴らがいたのに、あの人の笑顔だけが妙に頭に残っていた。
数日後、SNSであの試合の写真を見つけた。
試合の様子を撮影した写真の隅に、小さく映り込んでいる俺。泣いている顔まではわからないけど、俺にはすぐに自分だとわかった。
投稿したのは青葉中写真部の公式アカウントで、写真のクレジットには「撮影:写真部 3年 水野詠太」と書いてあった。
——あいつだ。
あの日、写真部と書かれたカードを首から下げて、カメラを構えていたのはあいつだけだ。奴の顔が、鮮明に蘇ってきた。
にこにこ笑っていた顔。
ムカついた。すげぇムカついた。泣いてるところを撮られたから? それもあるけど、それだけじゃない気がした。あの顔が頭にこびりついて離れないことが、無性に腹立たしかった。
青葉中、写真部で検索をしたら、すぐにそれらしきアカウントが見つかった。こんなふうにすぐ検索できるなんて、まったく危機感がない。
写真専用のアカウントらしく、風景や街並み、たまにちょっとしたつぶやきが並んでいる。
どんな奴なのか気になって、投稿を遡って見た。
変な写真が多かった。
おそらく誰かが忘れていったであろう、公園のベンチにある片方だけの手袋とか。
誰かがガードレールの上にきれいに並べた、どんぐり五個とか。
どれも別になんてことない写真だ。なのに、あの先輩が撮ったと思ったら、なぜか気になってしょうがなかった。
写真の合間には、日常のつぶやきも混ざっていた。
『ゆで卵作ろうとしてレンジで爆発させた。二度とやらない』とか。
『傘三本目なくした。俺に傘を持たせるな』とか。
『カラスに横断歩道で道を譲られた。お前が先に行けよ』とか。
くだらない。ほんとにくだらねぇ日常。
それから、なんとなく水野先輩のアカウントを見るようになった。
練習でうまくいかなかった日とか、授業中に眠くなった時とか、なんの気なしにアカウントを開いて、新しい投稿を眺める。
そのうち通知を設定して、先輩が投稿したらすぐに見るようになった。だって、ムカつくから。
あいつのことは嫌いだけれど……でも、写真だけは認めてやらなくもない。
そんなことを生意気に思いながら、俺は先輩の投稿を見続けた。
たまに水野先輩が写っている写真があると、何度も見返した。
友達にいたずらで撮られたのか、へらっと眉毛を下げて笑っている。
こいつは俺の泣いている写真を撮ったムカつく奴。
本当に、本当に、ムカつく奴。
俺の志望校は、最初から決まっていた。
バスケの強豪校で、ずっと行きたかった高校だ。
ある日、水野先輩のアカウントを見ていたら、短いメッセージが投稿された。
『第一高校、受かった』
——俺が行きたい高校と同じだ。
心臓が跳ねた。
その時は「最悪」だと思った。あんな奴……泣いてる俺の写真を堂々と載せるデリカシーのない奴と同じ高校なんて、ついてない。そう思ったはずだった。
……なのに、なんで俺はあんなにスマホを握りしめていたんだろう。
俺が第一高校に受かった。入学式の日。
寮の前で、俺はあの顔をすぐに見つけた。
二年近く経っても、忘れるわけがなかった。こっちは毎日先輩のSNSを見ているのだ。
また心臓がぎゅっと掴まれたみたいになった。
——あの人だ。
でも、あの写真に俺が映り込んでいたことなんて、本人は気づいてすらいなかった。
先輩は俺を見て、にこにこ笑ってこう言った。
「お、バスケがうまい榊原だよな? 俺は水野、二年。よろしくなー!」
呼吸が速くなる。
直感的にやっぱりこいつのことが嫌いだ、と思った。振り回されたくない。関わりたくない。どうしてこんなにムカつくんだ、と。
「……あー、くそ。考えんのやめよ」
頭を振って、立ち上がる。
いつまでも思い出に浸っていても、どうしようもない。
とりあえず、部屋に戻らないと。
*
部屋に戻ったのは、消灯時間ギリギリだった。
できることなら朝まで外にいたかったけど、そういうわけにもいかない。覚悟を決めてドアを開ける。
「——あ」
水野先輩が、ベッドの上に座っていた。
俺の顔を見た瞬間、慌てたように立ち上がる。
「お、おかえり……」
「…………」
心臓がうるさい。
さっき自覚したばかりの感情が、胸の中で暴れている。
先輩の顔を見るだけで、こんなにどうしようもなくなるなんて。
「あの、さ。さっきは……その」
先輩がもじもじしながら、何か言おうとしている。
たぶん、謝ろうとしているんだろう。俺が怒って出ていったから。
「……すみません。俺が悪かったです。気にしないでください」
「え……?」
俺は先輩の顔を見ないようにして、自分のベッドに向かった。
「え、あの、榊原——」
「眠いんで。寝ます」
そっけなく言って、ベッドに腰を下ろす。
その時、廊下からノックの音がした。
「昴先輩、いますか?」
同じバスケ部の1年、山本の声だった。
俺は反射的に立ち上がって、ドアを開ける。
「……どした」
「あ、すみません、昴先輩! 明日の朝練の集合時間、三十分早まったって……連絡回ってきたから伝えに来たっす!」
「あー、了解。わざわざありがとな」
自分でも驚くくらい、普通の声が出た。
山本に向かって軽く笑って見せると、山本は「また明日、よろしくお願いします!!」と礼儀よく頭を下げて去っていった。
ドアを閉めて振り返ると、水野先輩が目を丸くして俺を見ていた。
「…………なんですか」
「いや……お前、今めっちゃ優しく笑ってたなって」
「は?」
「……俺の前でもそういう顔しろよ。……なぁんて、こういうこと言うからダメなんだよな、俺」
……心臓が痛い。
アンタの前だと、普通になんかできないんだよ。
好きだって自覚する前からずっと、アンタの前でだけ俺はおかしくなる。
俺はベッドに戻って、先輩に背を向けた。
「あ、あのさ、榊原。さっきのことなんだけど」
「……もういいですから。俺が悪かったんで」
「いや、ちゃんと俺にも謝らせろよ! ……冗談で変なこと言って、ほんとごめんな。怒らせるつもりはなかったんだ」
先輩の声が、申し訳なさそうに背中に降ってくる。
……違う。
怒ってなんかない。
むしろ逆だ。図星すぎて、どうしていいかわからなくなっただけだ。
でも、そんなこと言えるわけがない。
「……大丈夫ですから、ほんとに」
「そ、そっか……」
先輩の声が、少しだけ安堵したように聞こえた。
良かった、と小さく呟く声が聞こえて、また胸がぎゅっと締め付けられる。
「じゃあ、その……おやすみ」
「……おやすみなさい」
部屋の電気が消えた。
暗闇の中、俺は目を開けたまま天井を見つめていた。
すぐ隣に、好きな人がいる。
なのに、何も言えない。何もできない。
さっき山本には普通に笑えたのに、この人の前だと顔すらまともに見られない。
藤堂の言葉が、頭の中でリフレインする。
——それなりに彼女いたことあるくせに、本命童貞かよ
「…………」
暗闇の中、小さくため息をつく。
隣のベッドから、先輩の寝息が聞こえてきた。もう寝たのかよ、早ぇな。
……いや、俺が眠れねぇだけか。
寝返りを打って、先輩のほうを見る。
暗くてよく見えないけど、布団の膨らみがかすかに上下しているのがわかった。
なんかすげぇ……かわいいかも。
その姿を見ているだけで、心臓がうるさくなる。
告白なんて、できるわけがない。
……俺ってマジで、本命童貞じゃん。
誰にも聞こえないように心の中で呟いて、俺は布団を頭まで被った。