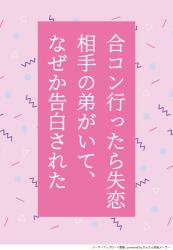停電の夜を境に、俺と榊原の関係は少しずつ変わっていった。
といっても、劇的に仲良くなったわけじゃない。榊原は相変わらず素っ気ないし、俺に対してだけ態度がでかいし、「アンタのこと嫌いです」そう堂々と言ってくる。でも、前みたいにほとんど無視するようなことはなくなった。
朝、「おはよう」と言えば「……す」と消え入りそうだった返事が「……おはようございます」になった。たったそれだけのことなのに、俺はちょっと嬉しくなってしまう。単純な男だ。
「先輩、それ俺のマグカップなんですけど」
「え、マジ? ごめんごめん」
「……アンタさぁ」
「……ちゃんと洗うって!」
「……」
「怒んなよー、イケメーン!」
こんな会話ができるようになっただけで、俺は十分だと思っていた。
嫌われていると思っていた相手と、普通に話せる。それがこんなに嬉しいなんて、自分でも意外だった。
変わったのは俺たちの関係だけじゃない。
俺自身の、榊原を見る目も変わっていた。
陽キャで、人気者で、誰にでも(俺以外に)優しいイケメン。そう思っていた榊原昴は、実はめちゃくちゃ根に持つタイプで、好き嫌いが激しくて、俺にだけは素直になれないっていうか、故意に素直にならない不器用な奴だった。
……なんだよ、それ。普通にかわいいじゃん。
いや、かわいいっていうのは語弊があるな。面白い奴、っていう意味で。
*
五月に入って、寮内の空気も落ち着いてきた頃。
俺は写真部の活動で、バスケ部の練習試合を撮影することになった。
「うっわ、榊原やっぱすげぇな……」
ファインダー越しに見る榊原は、普段悪態をついている生意気な後輩とは別人みたいだった。
コート上を縦横無尽に駆け回り、鮮やかなドリブルで相手を抜き去る。ジャンプシュートのフォームは綺麗で、放たれたボールは吸い込まれるようにゴールへ入っていく。
かっこいい。
純粋にそう思った。同時に、シャッターを切る指が止まらなかった。
「水野先輩、……榊原くんのことばかり撮ってないですか?」
隣で見ていた写真部の後輩に指摘されて、俺は慌ててカメラを下ろした。
「いや、あいつが一番動きがいいからさ。絵になるっていうか」
「確かにかっこいいですもんね、榊原くん」
「だろ?」
なぜか誇らしげに答えてしまった自分に気づいて、俺は内心で首を傾げた。
……なんで俺がドヤ顔してんだ。
試合が終わった後、俺は体育館の入り口で榊原を待っていた。
別に深い意味はない。ただ、いい写真が撮れたから見せてやろうと思っただけだ。
「……なんでいるんですか」
汗だくの榊原が、怪訝そうな顔で俺を見下ろしてくる。身長差があるから、自然と俺が見上げる形になってちょっとむかつく。
「いや、写真見てもらいたくて。お前のやつ、結構いいの撮れたからさー。安心しろよ、今度は泣いてるやつじゃねぇから」
「……は?」
榊原の眉間にしわが寄った。あ、やべ。地雷だったかも。中学の時のトラウマ的に、俺の写真は嫌なのかもしれない。
「あ、いや、別に無理にとは言わないんだけどさ……」
「……見せてください」
「や、やっぱやめとこっかな……」
「いいから、見せろって言ってんだろ」
有無を言わさない雰囲気を醸し出した榊原。俺は気圧されて、カメラのモニターを榊原に向けた。
シュートを放つ瞬間の写真。ドリブルで相手を抜き去る瞬間。チームメイトとハイタッチする瞬間。
榊原は無言で一眼レフの画面を変えていく。その横顔からは、何を考えているのか読み取れない。
「……まぁ、悪くないんじゃないですか」
「お、褒められた。珍しい」
俺は気を良くして、他の写真も見せることにした。
「あ、これも見てくれよ。同じ試合で撮ったやつ」
画面を進めて、別の写真を見せる。バスケ部の三年、俺の友人でもあり、同じクラスでもある村瀬がスリーポイントを決めた瞬間のショットだ。
「村瀬もかっこよく撮れたわ。さすが三年、貫禄あるよな。こいつ普段はけっこう大人しめなのに、ボール持つとすげぇかっこいいんだよな」
「…………」
榊原の表情が、すっと冷めた。
「……水野先輩、他の人間も撮ってるんですか」
「そりゃ、写真部だし。色んな瞬間を撮っちゃうよね! 瞬間を切り取っちゃうよね!」
「…………」
俺の態度がウザかったのか、榊原はあからさまに不機嫌になっている。怒った顔もかっこいいから、やっぱちょっとむかつくけど。
「おい、なんだよ。なんで怒ってんの?」
「別に怒ってないです」
「はい、また出ました~、別に~」
「……うぜぇな」
明らかに怒っている。
相変わらず器が小さい榊原なんか気にせず、にこにこしながら画面を榊原の写真に戻した。榊原はどれもいい表情をしている。
「……でもやっぱさ、お前がいちばん格好いいわ」
正直な感想だった。村瀬も悪くないけど、榊原の躍動感は別格だ。被写体としてすげぇ絵になる。
「…………」
隣を見ると、何を考えているのか、榊原がそっぽを向いていた。
耳がほんのり赤くなっているような……?
「……別に、そういうお世辞、言わなくていいですから」
「事実を言ってんの! お世辞じゃねぇの!」
「……アンタのこと嫌いだし、褒められても別にうれしくないです」
そう言いながらも、榊原の口元がわずかに緩んでいる気がした。
なんだよ、まったく。ほんと素直じゃねぇなぁ。
*
それからも、榊原の態度はよくわからなかった。
相変わらず素っ気ないくせに、なぜか俺のそばにいることが増えた。
食堂で俺が一人で飯を食っていると、いつの間にか向かいに座っている。俺が寮の談話室でほかの3年と騒いでいると、隣のソファに陣取ってつまらなそうにスマホをいじっている。
話しかけても「別に」「普通です」「関係ないでしょ、アンタには」と素っ気ない返事しかしないくせに、俺が席を立つと目で追ってくる。
「……お前さ、なんで俺のそばにいんの?」
「は? 何言ってるんですか? たまたまですけど」
「毎回たまたまなわけねぇだろ」
「ほんとうるせぇな……先輩こそ、なんで俺のこといちいち気にすんですか」
「お前が気になるようなことするからだろ……」
まったく、わけがわからない。
嫌いなんだか、嫌いじゃないんだか。
その日の夜、俺が部屋でパソコン作業をしていると、榊原が眉間に皺を寄せて話しかけてきた。
「……先輩、体調悪いんですか」
「え? 別に普通だけど」
「顔色悪いですよ、アンタ」
「そうか?」
自分ではまったくわからない。むしろ絶好調だ。最近、部活で資料作りを手伝っていたり、後輩の部誌のチェックを頼まれたりで、寝不足気味だったのは事実だけれど。
「今日はもう寝たほうがいいんじゃないですか」
「んー、でもこれ明日までだしなぁ」
「それ、水野先輩の仕事なんですか」
「いや、写真部の田中に頼まれて……」
「……アンタって、本当自分のこと後回しにしますよね。すげぇばか」
「へ?」
「他人の仕事ばっか引き受けて、体壊してたら意味ねぇだろうが。そういうとこマジでムカつくんですよ」
榊原がそう言って、俺のパソコンを勝手に閉じた。
「は!? お前何して——!」
「そんなの、アンタじゃなくて本人がやればいいでしょ。寝ろよ、いい加減」
俺はむっとして、榊原に閉じられてしまったパソコンを再び開いた。
「いや、でもさぁ……田中だって忙しいんだよ」
「そうですか、へー、よかったですね」
「……なっ、なんだよ、その態度!」
「話しかけないでください。俺はアンタと違って今から寝るんで」
俺に背中を向けてベッドに入った榊原を、唖然として見つめる。
マジで……ほんとなんなんだよ、こいつ。でも、バスケ部のエースだしな……眠れなかったら可哀想だよな。俺は静かに電気を消し、こそこそと音を立てないようにパソコンを打つのだった。
*
そんなことがあって次の日。
朝起きた途端、めちゃくちゃ嫌な予感がした。頭がガンガンして、体が鉛みたいに重い。熱を測ったら三十八度五分あった。
「……マジか~~」
最悪だ。今日は写真部のミーティングがあるのに。
「どうしたんですか……」
気づいたら、呆れたような顔をした榊原が俺のベッドの横に立っていた。
「あー……ちょっと熱出たっぽい。悪い、うつすかもしんないから近寄んないほうがいいかも」
「ほんとばかなんですか。あれだけ寝ろって言ったのに」
「……それを言うなよ! こっちだって気まずいんだからさぁ!」
「わかりましたから、もう黙っててください」
榊原がそう言って、俺の額に手を当てた。あまりに予想外の行動にびっくりして押し黙る。榊原に触られるなんて、初めてかも……。
「結構、熱ありますね。今日は一日寝てください」
「でも、ミーティングが……」
「俺が連絡しときます。写真部の誰に言えばいいですか」
「え、いや、そこまでしてもらわなくても……」
「いいから教えてください。担任にも言っておきますんで、アンタはちゃんと大人しくしててくださいよ」
「……あ、うん」
結局、俺は榊原に押し切られる形で一日寝ていることになった。
榊原は授業の合間に様子を見に来てくれて、スポーツドリンクやゼリー飲料を差し入れてくれた。冷えピタを額に乗せてくれたり、汗をかいた俺のために着替えを用意してくれたり。
正直、急に優しすぎて、めちゃくちゃ怖い。
昼過ぎ、どんどんと勢いよくドアをノックする音がした。
「はーい……」
起き上がろうとして、くらくらとめまいがする。やっぱり熱があると普通に辛い。
榊原の言うとおりにしておけばよかったかも……なんて思っても後悔先に立たずだ。
「水野ー! 生きてるかー!」
ドアが開いて、久我が顔を覗かせた。その後ろには同じクラスの村瀬と写真部の田中もいる。
「おいおい、マジで顔色悪いじゃん。大丈夫か?」
「あー……みんな来てくれたんだ。ちょっと熱出ちゃって……。田中、悪いけど、今日のミーティング無理だわ……」
「聞いたよ。榊原が直接、教室来てくれてさ。『水野先輩が熱出したんで、写真部に伝えてもらえますか』って」
村瀬が苦笑しながら言った。
「あいつ、にこにこしながら丁寧に説明してくれてさ。マジで何してもイケメンだよな~」
「え、にこにこ? 榊原が?」
「そうそう。愛想いいし、さすが陽キャって感じ」
にこにこ……かぁ。俺の前だと絶対そんな顔しないんだけど。
「とりあえず、ゼリーとかプリンとか買ってきたから。食えそうなもの食っとけよ」
田中が見舞いの品らしき袋を持ち上げた。
「ありがとな、田中……あ、そうだ、資料終わらしといたから」
「うわー助かる! マジで無理させてごめんな、水野!」
「いいって全然、それより内容とか説明したほうがいいよな? ちょっと待って、今、説明す――」
「何言ってんだよ。お前が今やることじゃねぇだろ」
久我が呆れたように笑った。
「そうそう。あとは自分でできるから。……つうか、ほんとにいつもありがとな、水野」
「……なんだよ、田中。そんな改まんなよ」
「田中の言うとおりだよ……。水野がいてくれるとみんな明るくなるしさ、いないとやっぱさみしい」
「え……村瀬まで……なに、嬉しい……」
「そうそう、水野いねーとつまんねぇよ。だから、風邪をさっさと治すように」
久我がそう言って、俺の尻をパシパシと手で叩いた。田中と村瀬もにこにこしながら、それぞれが俺の肩と背中を撫でている。
なんだかんだ、いい友達を持ったなぁと思っていた、その時、ドアが勢いよく開いた。
「お、イケメン登場」
制服姿の榊原だ。
「久我先輩……それに田中先輩も村瀬先輩も……。わざわざお見舞いですか?」
一瞬だけ鋭い視線を俺によこした榊原は、久我たちに向かって、にこやかに笑っている。……めっちゃ愛想いいじゃん。
「そう、見舞い。榊原はもしかして、水野の看病してくれてんの?」
「……一応、同室なんで」
部屋に入ってきた榊原の手には、購買のレジ袋が握られていた。榊原は久我ににっこりと笑い、かと思うと俺のほうをちらりと見て、すっと表情を消した。
「……先輩、なんで起き上がってるんですか。寝てろって言ったでしょうが」
「いや、みんなが来てくれたから……」
「はぁ……ほんとアンタって言うこと聞かないですよね」
俺にだけ、急にそっけない。コントみてぇだな、とぼうっとする頭の中でのんきに思う。
久我は目を丸くして、田中たちと顔を見合わせていた。
「えっと、榊原。俺らもうちょっといていい? 水野と話したくて——」
「すいません、先輩方。大変申し訳ないんですけど、水野先輩、熱あるんで、そろそろ安静にしとかないと」
榊原がにこにこしながら言った。
笑顔なのに、有無を言わさない雰囲気がある。久我は対抗するように爽やかに笑って、榊原を見据えた。
「榊原、お前大変だろ。俺らが水野の面倒見るから。どれどれ、水野くん、お前どんだけ熱が――」
久我が俺の首筋に手を伸ばそうとした瞬間、榊原がなぜか久我の手首をぐっと掴んだ。
「ありがとうございます。でも、先輩たちまで風邪ひいたら、大変なので」
にこにこしながら言っているけど、榊原は久我の手首を掴んだまま離さない。え、なんで?
久我はおもしろいおもちゃでも見るように「そっか」と笑顔を浮かべた。
「お見舞いの品は預かりますね」
にこにこしながら、田中たちを玄関のほうへ誘導していく。その手際の良さに、田中たちは抵抗する暇もないようだ。
「えっ、ちょ、榊原……?」
「また元気になったら、ゆっくり話してあげてください。今日は本当にすみません」
「お、おう……」
「じゃ、じゃあな水野、お大事に……!」
田中は困惑した様子で、村瀬は完全に気圧されてオロオロしている。久我はまだ面白がっているようで、俺のほうを振り返って、にやにやと手を振った。
「ま、また来るわ」
「じゃあな……」
「ゆっくり休めよー、水野」
ドアが閉まった瞬間、また榊原の笑顔が消えた。
「何、突っ立ってんですか。早く布団に入ってもらえますか?」
「……お前、俺の友達追い出すなよ」
「追い出してません。丁重に帰ってもらっただけです」
「同じだろ……つーか、さっきまでめっちゃにこにこしてたじゃん! 俺の前でもにこにこしろよ!」
「……先輩の前でにこにこする意味ないでしょ」
「えー……」
意味がわからなくて、俺は首を傾げた。
榊原は俺を見ずに、コンビニの袋からスポーツドリンクを取り出している。
「ほら、さっさとベッドに行って、水分とってください。さっきより顔色悪いですよ」
「あ、ああ……ありがと」
差し出されたペットボトルを受け取りながら、俺は榊原の横顔を見つめた。
……なんで、あんなにムキになって追い出したんだろう。
俺の友達が来たのが、そんなに気に入らなかったのか?
不思議に思ってじっと見つめていると、榊原が露骨に顔をしかめてぶつぶつ言い始めた。
「……俺はただ、病人のそばでわいわいやられたら迷惑だと思っただけです。それ以上の意味はないですから」
「ふーん……」
「その目やめてください。気持ち悪いんで」
「その目って、どんな目だよ」
俺は笑いながら、スポーツドリンクを飲んだ。
榊原は相変わらず不機嫌そうな顔で、久我たちが置いていってくれたお見舞いの品を整理し始めた。
「……ゼリーとプリン、どっちがいいですか」
「ゼリー!」
「わかりました」
なんだかんだ言いながら、こうやって世話を焼いてくれる。
ほんと、榊原って——変な奴。
*
夕方。薬のせいか、ずっと悪夢を見ていた。その合間に、何度か榊原が来てくれた気がするけど、授業中の時間だったので、きっとそれも俺の夢だと思う。
体にじんわりと嫌な汗をかきながら、ベッドから起き上がった。
このまま治んなかったらどうしよう、なんて漠然とばかみたいな不安に襲われていた時、榊原がまた様子を見に来てくれた。
「また来たの、お前」
「来ちゃ悪いですか。……それより熱、どうですか。測ってください」
渡された体温計を脇に挟んでいると、ピピピッと高い音が鳴る。
「お、見て。ちょっと下がった。三十七度八分」
榊原が無言で俺の頬に手を当てる。
その大きな手の感触に、すごくほっとしている自分がいた。それもたぶん、熱のせいだ、きっと。
「なぁ、榊原」
「なんですか」
「お前、俺のこと嫌いじゃなかったっけ」
「…………」
熱で朦朧としている俺は、思ったことをそのまま口にしている。
「嫌いな奴が風邪ひいたって、放っておけばいいじゃん」
「……放っておけないのは、アンタのほうだろ」
「んー……?」
「……先輩は嫌いですけど、今は病人なんで」
榊原はそう言いながら、俺の額の冷えピタを取り替えた。
「寝てください。……また来ますから」
「うん。ありがとな、榊原」
「……」
「なぁ、榊原」
「……なんですか」
「はやく、……帰って、きて」
眠気に勝てず、ゆっくりと目を閉じる直前、榊原が何か言った気がした。
でも、熱のせいでよく聞こえなくて、俺はそのまま眠りに落ちた。
*
数日後、すっかり体調も完全復活して普段の生活に戻った。
俺は相変わらず榊原のことを考えていた。
あいつはすぐに俺を嫌いだと言うけれど、絶対嫌いじゃない気がする。
むしろ、かなり気にかけてくれているっぽい。停電の夜から関係が変わって、風邪の看病までしてくれた仲だ。
なのに、本人は絶対に認めない。「嫌いだっつってんだろ」って押し通してくる。
その日の夕方。
俺は談話室で久我と話をしていた。
「水野、最近榊原とめっちゃ仲よくない?」
「……仲いい、のかなぁ」
「前より全然いいだろ。食堂でもいっつも一緒にいるし、部屋でも話してんだろ?」
「まぁ、前よりはマシになったけどさ……」
俺がそう言うと、久我はニヤニヤしながら俺の肩を叩いた。
「榊原ってさ、ほんとお前にだけ態度違うよな」
「……まぁな」
榊原の名誉のため、俺が泣いたあいつの写真を撮ってしまったことは言わなかった。
「つーか、この前お見舞い行った時もすごかったよな」
久我が思い出したように言った。
「あいつ、俺らにはにこにこしてんのに、お前にだけ塩対応だったじゃん。めっちゃウケたわ」
「ウケてないで、なんとかしてくれよ……」
「しかも、すげぇ自然に俺らを追い出したし。村瀬なんか『あれ絶対嫉妬だよな……?』って怯えてたぞ」
「……え、嫉妬?」
意味がわからなくて、俺は首を傾げた。
「嫉妬って、何が?」
「いや、だからお前に対しての——」
「俺に? なんで榊原が俺に嫉妬すんだよ。あいつ俺より顔もいいしバスケも上手いし身長も高いじゃん。勝てる要素ゼロだろ」
「……お前、マジで言ってんの?」
「え? マジだけど?」
久我が呆れたような顔で俺を見た。
「榊原はお前のこと、自分で面倒見たかったんだろ」
「え、どういうこと?」
「だから——」
久我が何か言いかけた時、談話室のドアが開いた。
榊原だった。
俺たち……というか俺を見るなり、その表情に不機嫌さが宿る。
「……何ですか。じろじろ見ないでくださいよ、水野先輩」
「見てねえって。久我と話してただけ」
「はぁ、そうですか」
榊原はそれだけ言って、俺の隣にどかっと座った。しかも、なぜか久我との間に割り込むような形で。
「……榊原、なんでそこに座るんだよ。先輩の俺が狭くなってるでしょ! よく見なさいよ!」
「別に大丈夫でしょ」
「いやいやいや」
「アンタが退ければいいだろ」
「……はぁ!?」
俺たちの会話を聞いていた久我が、苦笑しながら立ち上がった。
「じゃ、俺そろそろ行くわ。邪魔しちゃ悪いしな」
「邪魔……? なんの?」
意味深に笑って、久我は去っていった。
残された俺と榊原の間に、微妙な沈黙が流れる。
「……お前、なんで来たの」
「散歩です」
「嘘つけ」
俺はため息をついて、榊原の顔を覗き込んだ。
こうして近くで見ると、本当に整った顔をしている。睫毛が長くて、肌が綺麗で、唇の形も良い。
……こんなイケメンが、なんで俺なんかにこだわるんだろう。
つうか、さっき久我が言ってた「自分で面倒見たかった」って、どういう意味だ?
まさか、とは思うけど——。
「榊原ってさぁ」
「なんすか」
「もしかして、俺のこと好きなんじゃない?」
軽い冗談のつもりだった。
いつものように「は? 何言ってんですか。ほんとアンタはキモいな。そういうとこが嫌いなんですよ」なぁんて、百倍の悪口を返されると思っていた。
でも。
「…………」
榊原が、固まった。
顔から表情が消えて、まるで石像みたいになっている。
「……えっ、榊原?」
「…………なんつった、今?」
低い声だった。
今まで聞いたことないくらい、低くて冷たい声。
「誰がアンタなんか……。ふざけんなよ」
榊原がそう吐き捨てて、立ち上がった。
「ま、待てって! ごめん、冗談だから」
「……冗談で済むかよ」
「お、おい……榊原!」
榊原は振り返りもせずに、談話室を出ていった。
ドアが乱暴に閉まる音が、やけに大きく響いた。
「…………え?」
俺は呆然と、閉まったドアを見つめていた。
やべ、怒らせた。めっちゃ怒らせた。
……でも、怒りすぎじゃね!? なんであんなに怒ってんだよ!
冗談で「好きなんじゃない?」って言っただけなのに。
「えー……」
もしかして、またあいつと距離ができちゃったりして……。
俺は頭を振って、その考えを追い払った。
きっと、からかわれたのがいつもみたいに気に食わなかっただけだ。あいつのプライドはエベレスト級に高そうだし。
……うん、そうに違いない。きっと大したことないはず。
「そう、だよな?」
不安を打ち消すように、心の中でつぶやく。でも、榊原の強張った横顔が、なぜか頭から離れなかった。
とにかく……今日の夜、またふたりきりになったら、榊原にちゃんと謝らないと。
といっても、劇的に仲良くなったわけじゃない。榊原は相変わらず素っ気ないし、俺に対してだけ態度がでかいし、「アンタのこと嫌いです」そう堂々と言ってくる。でも、前みたいにほとんど無視するようなことはなくなった。
朝、「おはよう」と言えば「……す」と消え入りそうだった返事が「……おはようございます」になった。たったそれだけのことなのに、俺はちょっと嬉しくなってしまう。単純な男だ。
「先輩、それ俺のマグカップなんですけど」
「え、マジ? ごめんごめん」
「……アンタさぁ」
「……ちゃんと洗うって!」
「……」
「怒んなよー、イケメーン!」
こんな会話ができるようになっただけで、俺は十分だと思っていた。
嫌われていると思っていた相手と、普通に話せる。それがこんなに嬉しいなんて、自分でも意外だった。
変わったのは俺たちの関係だけじゃない。
俺自身の、榊原を見る目も変わっていた。
陽キャで、人気者で、誰にでも(俺以外に)優しいイケメン。そう思っていた榊原昴は、実はめちゃくちゃ根に持つタイプで、好き嫌いが激しくて、俺にだけは素直になれないっていうか、故意に素直にならない不器用な奴だった。
……なんだよ、それ。普通にかわいいじゃん。
いや、かわいいっていうのは語弊があるな。面白い奴、っていう意味で。
*
五月に入って、寮内の空気も落ち着いてきた頃。
俺は写真部の活動で、バスケ部の練習試合を撮影することになった。
「うっわ、榊原やっぱすげぇな……」
ファインダー越しに見る榊原は、普段悪態をついている生意気な後輩とは別人みたいだった。
コート上を縦横無尽に駆け回り、鮮やかなドリブルで相手を抜き去る。ジャンプシュートのフォームは綺麗で、放たれたボールは吸い込まれるようにゴールへ入っていく。
かっこいい。
純粋にそう思った。同時に、シャッターを切る指が止まらなかった。
「水野先輩、……榊原くんのことばかり撮ってないですか?」
隣で見ていた写真部の後輩に指摘されて、俺は慌ててカメラを下ろした。
「いや、あいつが一番動きがいいからさ。絵になるっていうか」
「確かにかっこいいですもんね、榊原くん」
「だろ?」
なぜか誇らしげに答えてしまった自分に気づいて、俺は内心で首を傾げた。
……なんで俺がドヤ顔してんだ。
試合が終わった後、俺は体育館の入り口で榊原を待っていた。
別に深い意味はない。ただ、いい写真が撮れたから見せてやろうと思っただけだ。
「……なんでいるんですか」
汗だくの榊原が、怪訝そうな顔で俺を見下ろしてくる。身長差があるから、自然と俺が見上げる形になってちょっとむかつく。
「いや、写真見てもらいたくて。お前のやつ、結構いいの撮れたからさー。安心しろよ、今度は泣いてるやつじゃねぇから」
「……は?」
榊原の眉間にしわが寄った。あ、やべ。地雷だったかも。中学の時のトラウマ的に、俺の写真は嫌なのかもしれない。
「あ、いや、別に無理にとは言わないんだけどさ……」
「……見せてください」
「や、やっぱやめとこっかな……」
「いいから、見せろって言ってんだろ」
有無を言わさない雰囲気を醸し出した榊原。俺は気圧されて、カメラのモニターを榊原に向けた。
シュートを放つ瞬間の写真。ドリブルで相手を抜き去る瞬間。チームメイトとハイタッチする瞬間。
榊原は無言で一眼レフの画面を変えていく。その横顔からは、何を考えているのか読み取れない。
「……まぁ、悪くないんじゃないですか」
「お、褒められた。珍しい」
俺は気を良くして、他の写真も見せることにした。
「あ、これも見てくれよ。同じ試合で撮ったやつ」
画面を進めて、別の写真を見せる。バスケ部の三年、俺の友人でもあり、同じクラスでもある村瀬がスリーポイントを決めた瞬間のショットだ。
「村瀬もかっこよく撮れたわ。さすが三年、貫禄あるよな。こいつ普段はけっこう大人しめなのに、ボール持つとすげぇかっこいいんだよな」
「…………」
榊原の表情が、すっと冷めた。
「……水野先輩、他の人間も撮ってるんですか」
「そりゃ、写真部だし。色んな瞬間を撮っちゃうよね! 瞬間を切り取っちゃうよね!」
「…………」
俺の態度がウザかったのか、榊原はあからさまに不機嫌になっている。怒った顔もかっこいいから、やっぱちょっとむかつくけど。
「おい、なんだよ。なんで怒ってんの?」
「別に怒ってないです」
「はい、また出ました~、別に~」
「……うぜぇな」
明らかに怒っている。
相変わらず器が小さい榊原なんか気にせず、にこにこしながら画面を榊原の写真に戻した。榊原はどれもいい表情をしている。
「……でもやっぱさ、お前がいちばん格好いいわ」
正直な感想だった。村瀬も悪くないけど、榊原の躍動感は別格だ。被写体としてすげぇ絵になる。
「…………」
隣を見ると、何を考えているのか、榊原がそっぽを向いていた。
耳がほんのり赤くなっているような……?
「……別に、そういうお世辞、言わなくていいですから」
「事実を言ってんの! お世辞じゃねぇの!」
「……アンタのこと嫌いだし、褒められても別にうれしくないです」
そう言いながらも、榊原の口元がわずかに緩んでいる気がした。
なんだよ、まったく。ほんと素直じゃねぇなぁ。
*
それからも、榊原の態度はよくわからなかった。
相変わらず素っ気ないくせに、なぜか俺のそばにいることが増えた。
食堂で俺が一人で飯を食っていると、いつの間にか向かいに座っている。俺が寮の談話室でほかの3年と騒いでいると、隣のソファに陣取ってつまらなそうにスマホをいじっている。
話しかけても「別に」「普通です」「関係ないでしょ、アンタには」と素っ気ない返事しかしないくせに、俺が席を立つと目で追ってくる。
「……お前さ、なんで俺のそばにいんの?」
「は? 何言ってるんですか? たまたまですけど」
「毎回たまたまなわけねぇだろ」
「ほんとうるせぇな……先輩こそ、なんで俺のこといちいち気にすんですか」
「お前が気になるようなことするからだろ……」
まったく、わけがわからない。
嫌いなんだか、嫌いじゃないんだか。
その日の夜、俺が部屋でパソコン作業をしていると、榊原が眉間に皺を寄せて話しかけてきた。
「……先輩、体調悪いんですか」
「え? 別に普通だけど」
「顔色悪いですよ、アンタ」
「そうか?」
自分ではまったくわからない。むしろ絶好調だ。最近、部活で資料作りを手伝っていたり、後輩の部誌のチェックを頼まれたりで、寝不足気味だったのは事実だけれど。
「今日はもう寝たほうがいいんじゃないですか」
「んー、でもこれ明日までだしなぁ」
「それ、水野先輩の仕事なんですか」
「いや、写真部の田中に頼まれて……」
「……アンタって、本当自分のこと後回しにしますよね。すげぇばか」
「へ?」
「他人の仕事ばっか引き受けて、体壊してたら意味ねぇだろうが。そういうとこマジでムカつくんですよ」
榊原がそう言って、俺のパソコンを勝手に閉じた。
「は!? お前何して——!」
「そんなの、アンタじゃなくて本人がやればいいでしょ。寝ろよ、いい加減」
俺はむっとして、榊原に閉じられてしまったパソコンを再び開いた。
「いや、でもさぁ……田中だって忙しいんだよ」
「そうですか、へー、よかったですね」
「……なっ、なんだよ、その態度!」
「話しかけないでください。俺はアンタと違って今から寝るんで」
俺に背中を向けてベッドに入った榊原を、唖然として見つめる。
マジで……ほんとなんなんだよ、こいつ。でも、バスケ部のエースだしな……眠れなかったら可哀想だよな。俺は静かに電気を消し、こそこそと音を立てないようにパソコンを打つのだった。
*
そんなことがあって次の日。
朝起きた途端、めちゃくちゃ嫌な予感がした。頭がガンガンして、体が鉛みたいに重い。熱を測ったら三十八度五分あった。
「……マジか~~」
最悪だ。今日は写真部のミーティングがあるのに。
「どうしたんですか……」
気づいたら、呆れたような顔をした榊原が俺のベッドの横に立っていた。
「あー……ちょっと熱出たっぽい。悪い、うつすかもしんないから近寄んないほうがいいかも」
「ほんとばかなんですか。あれだけ寝ろって言ったのに」
「……それを言うなよ! こっちだって気まずいんだからさぁ!」
「わかりましたから、もう黙っててください」
榊原がそう言って、俺の額に手を当てた。あまりに予想外の行動にびっくりして押し黙る。榊原に触られるなんて、初めてかも……。
「結構、熱ありますね。今日は一日寝てください」
「でも、ミーティングが……」
「俺が連絡しときます。写真部の誰に言えばいいですか」
「え、いや、そこまでしてもらわなくても……」
「いいから教えてください。担任にも言っておきますんで、アンタはちゃんと大人しくしててくださいよ」
「……あ、うん」
結局、俺は榊原に押し切られる形で一日寝ていることになった。
榊原は授業の合間に様子を見に来てくれて、スポーツドリンクやゼリー飲料を差し入れてくれた。冷えピタを額に乗せてくれたり、汗をかいた俺のために着替えを用意してくれたり。
正直、急に優しすぎて、めちゃくちゃ怖い。
昼過ぎ、どんどんと勢いよくドアをノックする音がした。
「はーい……」
起き上がろうとして、くらくらとめまいがする。やっぱり熱があると普通に辛い。
榊原の言うとおりにしておけばよかったかも……なんて思っても後悔先に立たずだ。
「水野ー! 生きてるかー!」
ドアが開いて、久我が顔を覗かせた。その後ろには同じクラスの村瀬と写真部の田中もいる。
「おいおい、マジで顔色悪いじゃん。大丈夫か?」
「あー……みんな来てくれたんだ。ちょっと熱出ちゃって……。田中、悪いけど、今日のミーティング無理だわ……」
「聞いたよ。榊原が直接、教室来てくれてさ。『水野先輩が熱出したんで、写真部に伝えてもらえますか』って」
村瀬が苦笑しながら言った。
「あいつ、にこにこしながら丁寧に説明してくれてさ。マジで何してもイケメンだよな~」
「え、にこにこ? 榊原が?」
「そうそう。愛想いいし、さすが陽キャって感じ」
にこにこ……かぁ。俺の前だと絶対そんな顔しないんだけど。
「とりあえず、ゼリーとかプリンとか買ってきたから。食えそうなもの食っとけよ」
田中が見舞いの品らしき袋を持ち上げた。
「ありがとな、田中……あ、そうだ、資料終わらしといたから」
「うわー助かる! マジで無理させてごめんな、水野!」
「いいって全然、それより内容とか説明したほうがいいよな? ちょっと待って、今、説明す――」
「何言ってんだよ。お前が今やることじゃねぇだろ」
久我が呆れたように笑った。
「そうそう。あとは自分でできるから。……つうか、ほんとにいつもありがとな、水野」
「……なんだよ、田中。そんな改まんなよ」
「田中の言うとおりだよ……。水野がいてくれるとみんな明るくなるしさ、いないとやっぱさみしい」
「え……村瀬まで……なに、嬉しい……」
「そうそう、水野いねーとつまんねぇよ。だから、風邪をさっさと治すように」
久我がそう言って、俺の尻をパシパシと手で叩いた。田中と村瀬もにこにこしながら、それぞれが俺の肩と背中を撫でている。
なんだかんだ、いい友達を持ったなぁと思っていた、その時、ドアが勢いよく開いた。
「お、イケメン登場」
制服姿の榊原だ。
「久我先輩……それに田中先輩も村瀬先輩も……。わざわざお見舞いですか?」
一瞬だけ鋭い視線を俺によこした榊原は、久我たちに向かって、にこやかに笑っている。……めっちゃ愛想いいじゃん。
「そう、見舞い。榊原はもしかして、水野の看病してくれてんの?」
「……一応、同室なんで」
部屋に入ってきた榊原の手には、購買のレジ袋が握られていた。榊原は久我ににっこりと笑い、かと思うと俺のほうをちらりと見て、すっと表情を消した。
「……先輩、なんで起き上がってるんですか。寝てろって言ったでしょうが」
「いや、みんなが来てくれたから……」
「はぁ……ほんとアンタって言うこと聞かないですよね」
俺にだけ、急にそっけない。コントみてぇだな、とぼうっとする頭の中でのんきに思う。
久我は目を丸くして、田中たちと顔を見合わせていた。
「えっと、榊原。俺らもうちょっといていい? 水野と話したくて——」
「すいません、先輩方。大変申し訳ないんですけど、水野先輩、熱あるんで、そろそろ安静にしとかないと」
榊原がにこにこしながら言った。
笑顔なのに、有無を言わさない雰囲気がある。久我は対抗するように爽やかに笑って、榊原を見据えた。
「榊原、お前大変だろ。俺らが水野の面倒見るから。どれどれ、水野くん、お前どんだけ熱が――」
久我が俺の首筋に手を伸ばそうとした瞬間、榊原がなぜか久我の手首をぐっと掴んだ。
「ありがとうございます。でも、先輩たちまで風邪ひいたら、大変なので」
にこにこしながら言っているけど、榊原は久我の手首を掴んだまま離さない。え、なんで?
久我はおもしろいおもちゃでも見るように「そっか」と笑顔を浮かべた。
「お見舞いの品は預かりますね」
にこにこしながら、田中たちを玄関のほうへ誘導していく。その手際の良さに、田中たちは抵抗する暇もないようだ。
「えっ、ちょ、榊原……?」
「また元気になったら、ゆっくり話してあげてください。今日は本当にすみません」
「お、おう……」
「じゃ、じゃあな水野、お大事に……!」
田中は困惑した様子で、村瀬は完全に気圧されてオロオロしている。久我はまだ面白がっているようで、俺のほうを振り返って、にやにやと手を振った。
「ま、また来るわ」
「じゃあな……」
「ゆっくり休めよー、水野」
ドアが閉まった瞬間、また榊原の笑顔が消えた。
「何、突っ立ってんですか。早く布団に入ってもらえますか?」
「……お前、俺の友達追い出すなよ」
「追い出してません。丁重に帰ってもらっただけです」
「同じだろ……つーか、さっきまでめっちゃにこにこしてたじゃん! 俺の前でもにこにこしろよ!」
「……先輩の前でにこにこする意味ないでしょ」
「えー……」
意味がわからなくて、俺は首を傾げた。
榊原は俺を見ずに、コンビニの袋からスポーツドリンクを取り出している。
「ほら、さっさとベッドに行って、水分とってください。さっきより顔色悪いですよ」
「あ、ああ……ありがと」
差し出されたペットボトルを受け取りながら、俺は榊原の横顔を見つめた。
……なんで、あんなにムキになって追い出したんだろう。
俺の友達が来たのが、そんなに気に入らなかったのか?
不思議に思ってじっと見つめていると、榊原が露骨に顔をしかめてぶつぶつ言い始めた。
「……俺はただ、病人のそばでわいわいやられたら迷惑だと思っただけです。それ以上の意味はないですから」
「ふーん……」
「その目やめてください。気持ち悪いんで」
「その目って、どんな目だよ」
俺は笑いながら、スポーツドリンクを飲んだ。
榊原は相変わらず不機嫌そうな顔で、久我たちが置いていってくれたお見舞いの品を整理し始めた。
「……ゼリーとプリン、どっちがいいですか」
「ゼリー!」
「わかりました」
なんだかんだ言いながら、こうやって世話を焼いてくれる。
ほんと、榊原って——変な奴。
*
夕方。薬のせいか、ずっと悪夢を見ていた。その合間に、何度か榊原が来てくれた気がするけど、授業中の時間だったので、きっとそれも俺の夢だと思う。
体にじんわりと嫌な汗をかきながら、ベッドから起き上がった。
このまま治んなかったらどうしよう、なんて漠然とばかみたいな不安に襲われていた時、榊原がまた様子を見に来てくれた。
「また来たの、お前」
「来ちゃ悪いですか。……それより熱、どうですか。測ってください」
渡された体温計を脇に挟んでいると、ピピピッと高い音が鳴る。
「お、見て。ちょっと下がった。三十七度八分」
榊原が無言で俺の頬に手を当てる。
その大きな手の感触に、すごくほっとしている自分がいた。それもたぶん、熱のせいだ、きっと。
「なぁ、榊原」
「なんですか」
「お前、俺のこと嫌いじゃなかったっけ」
「…………」
熱で朦朧としている俺は、思ったことをそのまま口にしている。
「嫌いな奴が風邪ひいたって、放っておけばいいじゃん」
「……放っておけないのは、アンタのほうだろ」
「んー……?」
「……先輩は嫌いですけど、今は病人なんで」
榊原はそう言いながら、俺の額の冷えピタを取り替えた。
「寝てください。……また来ますから」
「うん。ありがとな、榊原」
「……」
「なぁ、榊原」
「……なんですか」
「はやく、……帰って、きて」
眠気に勝てず、ゆっくりと目を閉じる直前、榊原が何か言った気がした。
でも、熱のせいでよく聞こえなくて、俺はそのまま眠りに落ちた。
*
数日後、すっかり体調も完全復活して普段の生活に戻った。
俺は相変わらず榊原のことを考えていた。
あいつはすぐに俺を嫌いだと言うけれど、絶対嫌いじゃない気がする。
むしろ、かなり気にかけてくれているっぽい。停電の夜から関係が変わって、風邪の看病までしてくれた仲だ。
なのに、本人は絶対に認めない。「嫌いだっつってんだろ」って押し通してくる。
その日の夕方。
俺は談話室で久我と話をしていた。
「水野、最近榊原とめっちゃ仲よくない?」
「……仲いい、のかなぁ」
「前より全然いいだろ。食堂でもいっつも一緒にいるし、部屋でも話してんだろ?」
「まぁ、前よりはマシになったけどさ……」
俺がそう言うと、久我はニヤニヤしながら俺の肩を叩いた。
「榊原ってさ、ほんとお前にだけ態度違うよな」
「……まぁな」
榊原の名誉のため、俺が泣いたあいつの写真を撮ってしまったことは言わなかった。
「つーか、この前お見舞い行った時もすごかったよな」
久我が思い出したように言った。
「あいつ、俺らにはにこにこしてんのに、お前にだけ塩対応だったじゃん。めっちゃウケたわ」
「ウケてないで、なんとかしてくれよ……」
「しかも、すげぇ自然に俺らを追い出したし。村瀬なんか『あれ絶対嫉妬だよな……?』って怯えてたぞ」
「……え、嫉妬?」
意味がわからなくて、俺は首を傾げた。
「嫉妬って、何が?」
「いや、だからお前に対しての——」
「俺に? なんで榊原が俺に嫉妬すんだよ。あいつ俺より顔もいいしバスケも上手いし身長も高いじゃん。勝てる要素ゼロだろ」
「……お前、マジで言ってんの?」
「え? マジだけど?」
久我が呆れたような顔で俺を見た。
「榊原はお前のこと、自分で面倒見たかったんだろ」
「え、どういうこと?」
「だから——」
久我が何か言いかけた時、談話室のドアが開いた。
榊原だった。
俺たち……というか俺を見るなり、その表情に不機嫌さが宿る。
「……何ですか。じろじろ見ないでくださいよ、水野先輩」
「見てねえって。久我と話してただけ」
「はぁ、そうですか」
榊原はそれだけ言って、俺の隣にどかっと座った。しかも、なぜか久我との間に割り込むような形で。
「……榊原、なんでそこに座るんだよ。先輩の俺が狭くなってるでしょ! よく見なさいよ!」
「別に大丈夫でしょ」
「いやいやいや」
「アンタが退ければいいだろ」
「……はぁ!?」
俺たちの会話を聞いていた久我が、苦笑しながら立ち上がった。
「じゃ、俺そろそろ行くわ。邪魔しちゃ悪いしな」
「邪魔……? なんの?」
意味深に笑って、久我は去っていった。
残された俺と榊原の間に、微妙な沈黙が流れる。
「……お前、なんで来たの」
「散歩です」
「嘘つけ」
俺はため息をついて、榊原の顔を覗き込んだ。
こうして近くで見ると、本当に整った顔をしている。睫毛が長くて、肌が綺麗で、唇の形も良い。
……こんなイケメンが、なんで俺なんかにこだわるんだろう。
つうか、さっき久我が言ってた「自分で面倒見たかった」って、どういう意味だ?
まさか、とは思うけど——。
「榊原ってさぁ」
「なんすか」
「もしかして、俺のこと好きなんじゃない?」
軽い冗談のつもりだった。
いつものように「は? 何言ってんですか。ほんとアンタはキモいな。そういうとこが嫌いなんですよ」なぁんて、百倍の悪口を返されると思っていた。
でも。
「…………」
榊原が、固まった。
顔から表情が消えて、まるで石像みたいになっている。
「……えっ、榊原?」
「…………なんつった、今?」
低い声だった。
今まで聞いたことないくらい、低くて冷たい声。
「誰がアンタなんか……。ふざけんなよ」
榊原がそう吐き捨てて、立ち上がった。
「ま、待てって! ごめん、冗談だから」
「……冗談で済むかよ」
「お、おい……榊原!」
榊原は振り返りもせずに、談話室を出ていった。
ドアが乱暴に閉まる音が、やけに大きく響いた。
「…………え?」
俺は呆然と、閉まったドアを見つめていた。
やべ、怒らせた。めっちゃ怒らせた。
……でも、怒りすぎじゃね!? なんであんなに怒ってんだよ!
冗談で「好きなんじゃない?」って言っただけなのに。
「えー……」
もしかして、またあいつと距離ができちゃったりして……。
俺は頭を振って、その考えを追い払った。
きっと、からかわれたのがいつもみたいに気に食わなかっただけだ。あいつのプライドはエベレスト級に高そうだし。
……うん、そうに違いない。きっと大したことないはず。
「そう、だよな?」
不安を打ち消すように、心の中でつぶやく。でも、榊原の強張った横顔が、なぜか頭から離れなかった。
とにかく……今日の夜、またふたりきりになったら、榊原にちゃんと謝らないと。