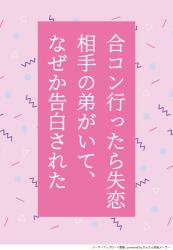桜舞い散る四月。高三になったばかりの春。
俺は寮の掲示板の前で固まっていた。
新学期恒例の部屋割り発表だった。1年間慣れ親しんだ相部屋の相手が変わるのは寂しいけれど、それも寮生活の醍醐味だ。新しい出会いがあるかもしれないし、意外な奴と気が合うかもしれない。そう前向きに考えていた。なのに。
「…………マジか」
305号室:3年 水野詠太・2年 榊原昴
自分の名前の横に並んだ名前を、三度見した。
えー、まさかあいつじゃねぇよな。違うだろ。違うに決まってる。
思わず現実逃避していた。
けれど、この学校に榊原昴という名前の人間は一人しかいない。
バスケ部のエースで、入学当初からかなりの注目を集めていた二年生。
平凡な俺なんかとは違い、すらりと背が高くて、整った顔立ちで、誰にでも人当たりがいい人気者。完全なる陽キャの一軍男子。
ここは男子校だけど、もしも女子生徒がいたら、めちゃくちゃモテるんだろうな、というタイプの後輩。
——で、なぜか俺のことを嫌っている後輩。
「あー……」
思わず天を仰ぐ。
別にいじめられているわけでも、嫌がらせをされているわけでもない。ただ、榊原は俺に対してだけあからさまに態度が違う。目を合わせない。話しかけても素っ気ない。必要最低限の返事しかしない。
最初は気のせいかと思っていた。でも、決定的だったのは一年前。たまたま寮の廊下を歩いていたとき、榊原が友人たちと話しているのが聞こえてしまったのだ。
『榊原ってさぁ、バスケはばかうめぇし、顔は整ってるし、……俺、時々お前に惚れそうになるときあるわ』
『は? やめろ……気持ちわりぃな』
『そうは言ってもさぁ、お前誰にでも優しいじゃん。イケメンでカースト1位なくせに』
『カーストとか意味わかんねぇ……つうか、俺にも無理な奴いるし——』
『え、誰……?』
『水野先輩。あの人だけは無理。好きじゃない』
『あの水野先輩!? お前、なんでだよ!? めっちゃいい人じゃん!』
『……俺は、そう思わない』
あのときの衝撃は今でも忘れられない。
なんで? なんて、俺がいちばん聞きたかった。
心当たりがまったくなかったのだ。榊原と個人的に話したことなんてほとんどない。
ちなみに俺は、中学の時から一方的に榊原を知っていた。バスケの天才がいると噂になっていて、まだあいつが中2だったころ、母校の対戦相手として実際にプレーを見たこともある。
高校に入ってからしゃべったのは数回だけ。しかもその時には、すでに榊原は俺を避けていた。
「よりによって榊原かぁ……」
嫌われているのに関わっていくほど図太くない。……いや、ちょっとは図太いかもしれないけど。
でも、さすがに同室では交流を避けられない。
「水野、おはよ——ってどうした、朝から死んだザリガニみたいな顔して」
後ろから声をかけてきたのは、同学年の久我悠人だった。俺よりも整った爽やかな笑顔で、俺の肩に腕を回してくる。
「死んだザリガニはちくちく言葉だろ……」
「あはは、ごめんって! てか、部屋割り見た? 俺、今年は斉藤と同室だったわー!」
「あ、そう……」
「水野は?」
俺は無言で掲示板を指さした。久我は俺の名前を探して、その横を見て、「あー……」と微妙な声を出した。
「榊原な……。あいつ、お前のこと苦手っぽいもんな」
「苦手っていうか、……たぶん嫌いなんだよ、俺のこと」
「え~~、でも理由わかんないんだろ? そうだ! これを機会に聞いてみたらいいじゃん」
「なんて聞くんだよ……」
久我はからからと笑いながら、「まぁ、なんとなるって!」と俺の尻をぎゅっと掴んでくる。いつものスキンシップを軽くあしらいながら、「どうっすっかなぁ……」とつぶやいた。
「大丈夫っしょ。水野コミュ力クソ高いし」
「……コミュ力でどうにかなる問題じゃない気がする」
「大丈夫大丈夫。それより飯いこうぜ、腹減った」
強引に食堂へ引っ張られながら、まぁなんとかなるか……と頭の中でつぶやいた。それより、腹減ったし。
俺はそうしてのんきに昼食のメニューを考え始めたのだった。
*
その日の夕方。段ボールを抱えて新しい部屋の前に立った。なんか急に緊張してきたかも……。
305号室。
ドアの前で深呼吸をする。別に怖いことなんてない。一緒の部屋になるだけだ。必要以上に関わらなければいい。今までだってそうしてきたじゃないか。
——でも。
正直に言えば、ちょっとだけ期待している自分もいた。同室になったことをきっかけに、仲良くなれるかもしれない。榊原が俺を嫌っている理由がわかるかもしれない。もし誤解があるのなら解けるかもしれない。
そんな甘いことを考えながら、ドアを開けた。
「……失礼しまーす——」
部屋の中には、すでに榊原がいた。
右側のベッドに腰かけて、スマホをいじっている。夕暮れの柔らかな光が部屋に満ちて、その端正な横顔を照らしていた。
——やっぱ、顔がいいな。
一瞬、場違いなことを思った。いや、事実だから仕方ない。榊原昴はめちゃくちゃイケメンなのだ。俺、こういう顔の造形がすごく好きなんだよな……。
そんなことを考えていると、榊原が冷たい視線を向けてくる。
「あ、えっと。知ってると思うけど、俺は三年の水野詠太な。榊原……、今日からよろしくな」
なるべく自然に声をかける。
「……どうも」
それだけ言って、またスマホに目を落とす。
うん、知ってた。そういう反応なのは知ってた。
俺は気にしないふりをして、入口側のベッドに荷物を置いた。今年一年、この部屋で暮らすことになる。榊原がどれだけ塩対応でも、こっちまで気まずくしていたら生活できない。
「いやー、ラッキーだわ。実を言うと、305号室、狙ってたんだよね」
「……」
「ここってほかの部屋よりちょっとでけーしさ」
「……」
「あと隣がいねぇから、騒げるし、あんま周りに気を使わなくていいじゃん? やったー」
「……」
「……なんてな」
……部屋の中には、思い切り気を使う相手がいますけどねぇ、とは言わない。
荷解きをしながら、ちらちらと榊原の様子を窺う。相変わらずスマホを見ているけれど、なんとなく空気が張り詰めている気がする。俺がいるから居心地悪いんだろうな、と思うと申し訳なくなった。
「あのさ、榊原」
「……なんですか」
「俺、写真撮るの好きでさ……それで中学からずっと写真部なんだけど、まぁそれはいいとして……部屋で機材いじったりすることもあるんだわ。だから、うざかったら言って」
「……別に」
「あと、たまに夜更かししてパソコンで作業とかするから、明かりが気になったら——」
「そんなのどうでもいいんで、あんま話しかけないでください」
唐突に、榊原が言った。
顔を上げてこちらを見ている。整った眉がわずかに寄せられていて、明らかに不機嫌な顔だった。
「……は?」
「俺、先輩と馴れ合うつもりないんで」
はっきりと、そう言われた。
さすがにちょっとへこんだ。面と向かって言われると、思っていたよりダメージがでかい。
「……そっか。わかった」
俺はそれだけ言って、荷解きに戻った。
わかったって口にしたけれど、全然わかってなかった。
なんで俺、こんな仕打ち受けなきゃいけないんだろう。心当たりがないぶん、余計にへこむ。
その夜、俺は自分のベッドに潜り込みながら、反対側で眠っているらしい榊原の背中を眺めていた。
広い背中だ。バスケで鍛えているからだろう、Tシャツ越しでも筋肉の付き方がわかる。
嫌われている相手なのに、どうしても目で追ってしまう。顔が好みなのが悪い。いや、男が好きってわけじゃないけど。
「…………はぁ」
小さく溜息をついて、目を閉じた。
先は長い。卒業まで、この調子なのかと思うと想像していた以上に気が重かった。
*
——あれから二週間が経った。
状況は相変わらずだった。榊原は俺に対して必要最低限の会話しかしない。おはようと言えば「……す」と聞こえるか聞こえないかの返事。おやすみと言っても無言。たまに目が合うと、すぐに逸らされる。
俺は俺なりに歩み寄ろうとした。朝起きたら「今日も頑張ろうな」と声をかけてみたり、夜はお茶を淹れて「飲む?」と聞いてみたり。
全部、素っ気なく断られた。
何がそんなに気に食わないんだろう。俺、お前に何かしたっけ。……聞いても答えてくれない気がするけど。
そんなことを考えながら、夜、部屋で課題をやっていた時。突然ぶつん、と電気が落ちた。
「うわっ」
「は?」
驚いたふたりの声が重なる。真っ暗になった部屋の中、慌ててスマホを探った。榊原は自分のベッドにいるはずだ。
「榊原、大丈夫か?」
「……いや、別に」
暗闇の中、スマホのライトをつける。照らされた榊原の顔は、相変わらず不機嫌そうだった。
窓の外を見ると、寮全体が暗くなっているようだった。近くの街灯も消えている。
「停電か……」
「みたいっスね」
スマホで調べると、近くの変電所でトラブルがあり、このあたり一帯が停電していることがわかった。
そして廊下の方からどたどたと足音が聞こえてくる。
「マジかよ! お前らー! 復旧まで5時間くらいかかるんだってー!」
「は? 課題できないじゃん! やろうと思ってたのに、できないじゃん!」
「ぎゃははは! わざとらしー!」
「水野、榊原、停電ってことだから、よろしく! じゃあなー!」
部屋の扉を開けるまでもなく、騒がしい声がまた遠ざかっていく。非常灯のぼんやりした明かりの中、寮生たちがスマホを片手にわいわいやっているのが想像できた。
「5時間か……。さすがにやることないな」
俺はベッドに座り直した。課題は諦めるしかない。暗い中で本を読むわけにもいかないし、スマホのバッテリーも温存したい。
榊原も同じことを考えたのか、スマホのライトを消した。
月明かりだけが部屋を照らす中、沈黙が満ちる。
窓から見える空は晴れていて、星がよく見えた。普段は明かりが邪魔で見えない星が、今夜はくっきりと輝いている。
綺麗だな、と思った。写真を撮りたいけど、スマホじゃ限界がある。一眼レフ……は部室だ。
「……先輩」
不意に、榊原が口を開いた。俺は榊原から話しかけてくれたことに浮かれ、食い気味に「なに?」と返事をする。
「……なんで写真、撮ってるんですか」
意外な質問だった。こいつ、俺のこと興味ないんじゃなかったのか。
「あー、前も言ったけど、普通に好きなんだよね……。一瞬を切り取れる感じが良くて」
「ふうん……」
「体育祭とか文化祭とかスポーツとか、そういうイベントの写真撮るのも好きだし、何気ない日常を切り取るのも好き」
「…………」
榊原は何も言わなかった。でも、聞いている気配はある。
せっかくだから、俺はもう少し踏み込んでみることにした。
「なぁ、榊原」
「……なんすか」
「お前さ、なんで俺のこと嫌ってるわけ?」
直球で聞いた。暗闇で何も見えなくても、榊原が息を呑んだ気配を察する。
「……別に」
「はい出ました~、別に~。別にじゃわかんないだろ。俺さ、お前になんかした覚えないんだけど」
顔も見えないような状態だからか、不思議と強気になれた。榊原の隙のない綺麗な顔を前にしたら、ビビってこんなふうには聞けなかっただろう。
「心当たりないのに嫌われても困るじゃん? 足が臭いから〜とか、見た目がキモいから〜とか、理由くらい教えてくれよ」
なるべく冗談っぽく、陽気に聞いた。しばらく沈黙したあと、榊原が低い声で言う。
「やっぱ、覚えてないんすね」
「お、覚えてないって、どういう……」
「……昔、アンタに泣いてる写真撮られたんですよ」
「は?」
まったく心当たりがなかった。
「中学の時です。南陽中対青葉中戦。バスケの試合で負けて、泣いてたとこ」
「いや、俺そんなの——」
「撮ってたでしょ。試合のあと、カメラ持ってウロウロして、俺の写真撮って……しかも、その写真、アンタの学校のSNSに上げてただろ」
口を開けたまま、記憶を探る。写真部の活動として、撮った写真をSNSにあげていたのは本当だけれど……。
「……もしかして、あれか? うちの学校が勝った試合の写真?」
「……」
「待って、マジで俺、お前なんか撮ってない」
「映ってましたよ、たしかに」
榊原の声が低くなる。
「俺が泣いてるとこ」
……マジで?
そんな写真あったっけ。俺は記憶を必死に辿った。あの試合の時、榊原はかなり活躍していたけれど、最終的にうちの中学が勝ったのを覚えている。
俺は勝ったことをかなり喜んでいて、写真をたくさん撮っていた。……その時、負けた相手校の選手が映り込んでいたような気がしなくもない。でも、メインは自分の学校の選手たちで……。
「……ちょっと待って、確認する」
スマホで我が母校――青葉中のSNSを漁る。中学三年の時の投稿。南陽中対青葉中戦。撮影・三年水野詠太と書かれた投稿。
あった。
うちのチームが勝って喜んでいる写真。その端っこに……いた。豆粒みたいに小さく、顔を押さえている選手が映っていた。
「こ、これ、だよな……?」
「見せないでください。マジで腹立つんで」
榊原が顔を背けた。スマホの明かりで照らされた榊原の頬が、少しだけ赤くなっているような。
「いや、お前……! これ、ほぼ見えないじゃん!」
泣いているのはかろうじてわかるが、おそらく榊原だとは誰もわからないだろう。
「見えますよ」
「見えない見えない。拡大してもギリわからないレベルだって」
「でも写ってる」
「いや、あー……まぁ、……写ってるけどさぁ」
「……むかつく。やっぱアンタは俺のこと、全然覚えてなかったんですね」
榊原の声が、拗ねたように低くなった。
「ずっと、そっちから言ってくるの待ってたんですよ。自分から言うの、シャクだし」
……えっ。
俺は、目の前で不貞腐れている後輩を見つめた。
陽キャで、人気者で、誰にでも優しいイケメン。そう思っていた榊原昴が——こんな些細なことで、ずっと根に持っていた?
「お前……」
「なんすか」
「器、ちっさ!」
思わず笑ってしまった。声を出して、腹を抱えて笑った。
「笑ってんじゃねぇよ」
「いや、だって……お前、そんなことでずっと俺のこと嫌ってたの? マジで?」
「そんなことってなんすか。俺にとっては大事なことなんですけど」
「いやごめん、確かに勝手に撮ったのは悪かった。でも本当に気づかなかったんだよ。お前の顔なんか、あの時全然見てなかったし」
「…………」
榊原が黙った。なんか、余計に怒らせた気がする。
「違う違う、そうじゃなくて。俺、あのとき自分の学校のことしか見てなかったから。お前のこと意識して撮ったわけじゃないんだって」
「……わかりました」
「本当にごめんな。……でもさ、お前、マジで器小さいな。あははは!」
「……うるせぇよ」
榊原がむすっとした声で言う。でも、さっきまでのピリピリした空気はなくなっていた。
「一応先輩だからって黙ってましたけど、この際だから言わせてもらっていいですか」
「お、なに?」
「アンタのこと、他にもムカつくとこいっぱいあるんで」
「えっ、まだあるの?」
「アンタの、自分よりみんなを優先するとこ。ムカつきます」
「……それ悪いこと、……なのかな?」
「あと、くだんねぇ冗談言ってへらへら笑ってんのもムカつく」
「俺の冗談そんなつまんない……?」
「あと、俺のこと避けてるくせに、みんなにはにこにこ優しくしやがって」
「いや待て待て、避けてたのそっち——」
「あと、異常なくらい美味しそうにご飯食べるとこ」
「飯を美味そうに食って何が悪いんだよ!」
「あと、久我先輩にいっつも尻撫でられてんの、あれセクハラっすよ。なんで気づいてないんですか、腹立つな」
「……え、あれセクハラなの?」
久我のスキンシップが多いのは知っていたけど、あれって普通じゃなかったのか。いや、普通だろ……。
「あと、今日も部屋で上半身裸になってウロウロしてましたよね? ちょっと意識足りなすぎじゃないですか」
「あー……ごめん、見苦しかった?」
俺は自分の腹を見下ろした。榊原みたいに鍛えられた体じゃないから、確かに見せられたものではないかもしれない。
「いや、そうじゃなくて——いやらしい目で見るやつとかもいると思うんで」
「……えっ」
「だから、気をつけたほうがいいって言ってるんです」
榊原が早口で捲し立てる。
……なんだよ、いやらしい目って。
「ははっ、お前、変なやつだな」
「……は?」
「いや、なんか、面白いなって。お前のそういうとこ、全然知らなかった」
「別に知らなくていいです」
「やば、ウケる」
いつまでも笑っている俺に、榊原が低い声で言った。
「ケンカ売ってんすか?」
「売ってない売ってない。……ていうかさ、お前、俺にだけそういう態度なの、なんで?」
「……さあ」
「他のやつにはめっちゃ愛想いいのに」
「先輩には、なんか……そういうのできないんですよ」
ぼそっと、榊原がそう言った。
月明かりの中、だんだんと目が慣れてきて、榊原の横顔が見えた。照れているような、困っているような、複雑な表情。
——なんだよそれ。
嫌われてると思ってたのに。ずっと、俺だけが一方的に距離を置かれてると思ってたのに。
そうじゃなかったのかもしれない。
少なくとも、今は……完全に嫌っている感じじゃない……と思う。
「……まぁいいや。とりあえず、今日からまたよろしくな、榊原」
「…………」
「返事しろっつの。俺、お前と仲良くなりたいんだよ。せっかく同室になったんだし」
「……別に。勝手にすればいいじゃないんすか」
素っ気ない返事。でも、さっきまでと声のトーンが違う気がした。
その夜、停電が復旧したのは深夜二時だった。
それまでの数時間、俺たちはぽつぽつと他愛ない話をした。榊原が入部しているバスケ部のこと、互いの先生のこと、寮の飯で何が好きか、なんて本当に他愛もないこと。
榊原は相変わらず素っ気なかったけれど、最初の頃よりずっと言葉を返してくれるようになった。
——なんだ、話せるじゃん。
俺は少しだけ嬉しくなって、その夜は前より軽くなった心で眠りについたのだった。
俺は寮の掲示板の前で固まっていた。
新学期恒例の部屋割り発表だった。1年間慣れ親しんだ相部屋の相手が変わるのは寂しいけれど、それも寮生活の醍醐味だ。新しい出会いがあるかもしれないし、意外な奴と気が合うかもしれない。そう前向きに考えていた。なのに。
「…………マジか」
305号室:3年 水野詠太・2年 榊原昴
自分の名前の横に並んだ名前を、三度見した。
えー、まさかあいつじゃねぇよな。違うだろ。違うに決まってる。
思わず現実逃避していた。
けれど、この学校に榊原昴という名前の人間は一人しかいない。
バスケ部のエースで、入学当初からかなりの注目を集めていた二年生。
平凡な俺なんかとは違い、すらりと背が高くて、整った顔立ちで、誰にでも人当たりがいい人気者。完全なる陽キャの一軍男子。
ここは男子校だけど、もしも女子生徒がいたら、めちゃくちゃモテるんだろうな、というタイプの後輩。
——で、なぜか俺のことを嫌っている後輩。
「あー……」
思わず天を仰ぐ。
別にいじめられているわけでも、嫌がらせをされているわけでもない。ただ、榊原は俺に対してだけあからさまに態度が違う。目を合わせない。話しかけても素っ気ない。必要最低限の返事しかしない。
最初は気のせいかと思っていた。でも、決定的だったのは一年前。たまたま寮の廊下を歩いていたとき、榊原が友人たちと話しているのが聞こえてしまったのだ。
『榊原ってさぁ、バスケはばかうめぇし、顔は整ってるし、……俺、時々お前に惚れそうになるときあるわ』
『は? やめろ……気持ちわりぃな』
『そうは言ってもさぁ、お前誰にでも優しいじゃん。イケメンでカースト1位なくせに』
『カーストとか意味わかんねぇ……つうか、俺にも無理な奴いるし——』
『え、誰……?』
『水野先輩。あの人だけは無理。好きじゃない』
『あの水野先輩!? お前、なんでだよ!? めっちゃいい人じゃん!』
『……俺は、そう思わない』
あのときの衝撃は今でも忘れられない。
なんで? なんて、俺がいちばん聞きたかった。
心当たりがまったくなかったのだ。榊原と個人的に話したことなんてほとんどない。
ちなみに俺は、中学の時から一方的に榊原を知っていた。バスケの天才がいると噂になっていて、まだあいつが中2だったころ、母校の対戦相手として実際にプレーを見たこともある。
高校に入ってからしゃべったのは数回だけ。しかもその時には、すでに榊原は俺を避けていた。
「よりによって榊原かぁ……」
嫌われているのに関わっていくほど図太くない。……いや、ちょっとは図太いかもしれないけど。
でも、さすがに同室では交流を避けられない。
「水野、おはよ——ってどうした、朝から死んだザリガニみたいな顔して」
後ろから声をかけてきたのは、同学年の久我悠人だった。俺よりも整った爽やかな笑顔で、俺の肩に腕を回してくる。
「死んだザリガニはちくちく言葉だろ……」
「あはは、ごめんって! てか、部屋割り見た? 俺、今年は斉藤と同室だったわー!」
「あ、そう……」
「水野は?」
俺は無言で掲示板を指さした。久我は俺の名前を探して、その横を見て、「あー……」と微妙な声を出した。
「榊原な……。あいつ、お前のこと苦手っぽいもんな」
「苦手っていうか、……たぶん嫌いなんだよ、俺のこと」
「え~~、でも理由わかんないんだろ? そうだ! これを機会に聞いてみたらいいじゃん」
「なんて聞くんだよ……」
久我はからからと笑いながら、「まぁ、なんとなるって!」と俺の尻をぎゅっと掴んでくる。いつものスキンシップを軽くあしらいながら、「どうっすっかなぁ……」とつぶやいた。
「大丈夫っしょ。水野コミュ力クソ高いし」
「……コミュ力でどうにかなる問題じゃない気がする」
「大丈夫大丈夫。それより飯いこうぜ、腹減った」
強引に食堂へ引っ張られながら、まぁなんとかなるか……と頭の中でつぶやいた。それより、腹減ったし。
俺はそうしてのんきに昼食のメニューを考え始めたのだった。
*
その日の夕方。段ボールを抱えて新しい部屋の前に立った。なんか急に緊張してきたかも……。
305号室。
ドアの前で深呼吸をする。別に怖いことなんてない。一緒の部屋になるだけだ。必要以上に関わらなければいい。今までだってそうしてきたじゃないか。
——でも。
正直に言えば、ちょっとだけ期待している自分もいた。同室になったことをきっかけに、仲良くなれるかもしれない。榊原が俺を嫌っている理由がわかるかもしれない。もし誤解があるのなら解けるかもしれない。
そんな甘いことを考えながら、ドアを開けた。
「……失礼しまーす——」
部屋の中には、すでに榊原がいた。
右側のベッドに腰かけて、スマホをいじっている。夕暮れの柔らかな光が部屋に満ちて、その端正な横顔を照らしていた。
——やっぱ、顔がいいな。
一瞬、場違いなことを思った。いや、事実だから仕方ない。榊原昴はめちゃくちゃイケメンなのだ。俺、こういう顔の造形がすごく好きなんだよな……。
そんなことを考えていると、榊原が冷たい視線を向けてくる。
「あ、えっと。知ってると思うけど、俺は三年の水野詠太な。榊原……、今日からよろしくな」
なるべく自然に声をかける。
「……どうも」
それだけ言って、またスマホに目を落とす。
うん、知ってた。そういう反応なのは知ってた。
俺は気にしないふりをして、入口側のベッドに荷物を置いた。今年一年、この部屋で暮らすことになる。榊原がどれだけ塩対応でも、こっちまで気まずくしていたら生活できない。
「いやー、ラッキーだわ。実を言うと、305号室、狙ってたんだよね」
「……」
「ここってほかの部屋よりちょっとでけーしさ」
「……」
「あと隣がいねぇから、騒げるし、あんま周りに気を使わなくていいじゃん? やったー」
「……」
「……なんてな」
……部屋の中には、思い切り気を使う相手がいますけどねぇ、とは言わない。
荷解きをしながら、ちらちらと榊原の様子を窺う。相変わらずスマホを見ているけれど、なんとなく空気が張り詰めている気がする。俺がいるから居心地悪いんだろうな、と思うと申し訳なくなった。
「あのさ、榊原」
「……なんですか」
「俺、写真撮るの好きでさ……それで中学からずっと写真部なんだけど、まぁそれはいいとして……部屋で機材いじったりすることもあるんだわ。だから、うざかったら言って」
「……別に」
「あと、たまに夜更かししてパソコンで作業とかするから、明かりが気になったら——」
「そんなのどうでもいいんで、あんま話しかけないでください」
唐突に、榊原が言った。
顔を上げてこちらを見ている。整った眉がわずかに寄せられていて、明らかに不機嫌な顔だった。
「……は?」
「俺、先輩と馴れ合うつもりないんで」
はっきりと、そう言われた。
さすがにちょっとへこんだ。面と向かって言われると、思っていたよりダメージがでかい。
「……そっか。わかった」
俺はそれだけ言って、荷解きに戻った。
わかったって口にしたけれど、全然わかってなかった。
なんで俺、こんな仕打ち受けなきゃいけないんだろう。心当たりがないぶん、余計にへこむ。
その夜、俺は自分のベッドに潜り込みながら、反対側で眠っているらしい榊原の背中を眺めていた。
広い背中だ。バスケで鍛えているからだろう、Tシャツ越しでも筋肉の付き方がわかる。
嫌われている相手なのに、どうしても目で追ってしまう。顔が好みなのが悪い。いや、男が好きってわけじゃないけど。
「…………はぁ」
小さく溜息をついて、目を閉じた。
先は長い。卒業まで、この調子なのかと思うと想像していた以上に気が重かった。
*
——あれから二週間が経った。
状況は相変わらずだった。榊原は俺に対して必要最低限の会話しかしない。おはようと言えば「……す」と聞こえるか聞こえないかの返事。おやすみと言っても無言。たまに目が合うと、すぐに逸らされる。
俺は俺なりに歩み寄ろうとした。朝起きたら「今日も頑張ろうな」と声をかけてみたり、夜はお茶を淹れて「飲む?」と聞いてみたり。
全部、素っ気なく断られた。
何がそんなに気に食わないんだろう。俺、お前に何かしたっけ。……聞いても答えてくれない気がするけど。
そんなことを考えながら、夜、部屋で課題をやっていた時。突然ぶつん、と電気が落ちた。
「うわっ」
「は?」
驚いたふたりの声が重なる。真っ暗になった部屋の中、慌ててスマホを探った。榊原は自分のベッドにいるはずだ。
「榊原、大丈夫か?」
「……いや、別に」
暗闇の中、スマホのライトをつける。照らされた榊原の顔は、相変わらず不機嫌そうだった。
窓の外を見ると、寮全体が暗くなっているようだった。近くの街灯も消えている。
「停電か……」
「みたいっスね」
スマホで調べると、近くの変電所でトラブルがあり、このあたり一帯が停電していることがわかった。
そして廊下の方からどたどたと足音が聞こえてくる。
「マジかよ! お前らー! 復旧まで5時間くらいかかるんだってー!」
「は? 課題できないじゃん! やろうと思ってたのに、できないじゃん!」
「ぎゃははは! わざとらしー!」
「水野、榊原、停電ってことだから、よろしく! じゃあなー!」
部屋の扉を開けるまでもなく、騒がしい声がまた遠ざかっていく。非常灯のぼんやりした明かりの中、寮生たちがスマホを片手にわいわいやっているのが想像できた。
「5時間か……。さすがにやることないな」
俺はベッドに座り直した。課題は諦めるしかない。暗い中で本を読むわけにもいかないし、スマホのバッテリーも温存したい。
榊原も同じことを考えたのか、スマホのライトを消した。
月明かりだけが部屋を照らす中、沈黙が満ちる。
窓から見える空は晴れていて、星がよく見えた。普段は明かりが邪魔で見えない星が、今夜はくっきりと輝いている。
綺麗だな、と思った。写真を撮りたいけど、スマホじゃ限界がある。一眼レフ……は部室だ。
「……先輩」
不意に、榊原が口を開いた。俺は榊原から話しかけてくれたことに浮かれ、食い気味に「なに?」と返事をする。
「……なんで写真、撮ってるんですか」
意外な質問だった。こいつ、俺のこと興味ないんじゃなかったのか。
「あー、前も言ったけど、普通に好きなんだよね……。一瞬を切り取れる感じが良くて」
「ふうん……」
「体育祭とか文化祭とかスポーツとか、そういうイベントの写真撮るのも好きだし、何気ない日常を切り取るのも好き」
「…………」
榊原は何も言わなかった。でも、聞いている気配はある。
せっかくだから、俺はもう少し踏み込んでみることにした。
「なぁ、榊原」
「……なんすか」
「お前さ、なんで俺のこと嫌ってるわけ?」
直球で聞いた。暗闇で何も見えなくても、榊原が息を呑んだ気配を察する。
「……別に」
「はい出ました~、別に~。別にじゃわかんないだろ。俺さ、お前になんかした覚えないんだけど」
顔も見えないような状態だからか、不思議と強気になれた。榊原の隙のない綺麗な顔を前にしたら、ビビってこんなふうには聞けなかっただろう。
「心当たりないのに嫌われても困るじゃん? 足が臭いから〜とか、見た目がキモいから〜とか、理由くらい教えてくれよ」
なるべく冗談っぽく、陽気に聞いた。しばらく沈黙したあと、榊原が低い声で言う。
「やっぱ、覚えてないんすね」
「お、覚えてないって、どういう……」
「……昔、アンタに泣いてる写真撮られたんですよ」
「は?」
まったく心当たりがなかった。
「中学の時です。南陽中対青葉中戦。バスケの試合で負けて、泣いてたとこ」
「いや、俺そんなの——」
「撮ってたでしょ。試合のあと、カメラ持ってウロウロして、俺の写真撮って……しかも、その写真、アンタの学校のSNSに上げてただろ」
口を開けたまま、記憶を探る。写真部の活動として、撮った写真をSNSにあげていたのは本当だけれど……。
「……もしかして、あれか? うちの学校が勝った試合の写真?」
「……」
「待って、マジで俺、お前なんか撮ってない」
「映ってましたよ、たしかに」
榊原の声が低くなる。
「俺が泣いてるとこ」
……マジで?
そんな写真あったっけ。俺は記憶を必死に辿った。あの試合の時、榊原はかなり活躍していたけれど、最終的にうちの中学が勝ったのを覚えている。
俺は勝ったことをかなり喜んでいて、写真をたくさん撮っていた。……その時、負けた相手校の選手が映り込んでいたような気がしなくもない。でも、メインは自分の学校の選手たちで……。
「……ちょっと待って、確認する」
スマホで我が母校――青葉中のSNSを漁る。中学三年の時の投稿。南陽中対青葉中戦。撮影・三年水野詠太と書かれた投稿。
あった。
うちのチームが勝って喜んでいる写真。その端っこに……いた。豆粒みたいに小さく、顔を押さえている選手が映っていた。
「こ、これ、だよな……?」
「見せないでください。マジで腹立つんで」
榊原が顔を背けた。スマホの明かりで照らされた榊原の頬が、少しだけ赤くなっているような。
「いや、お前……! これ、ほぼ見えないじゃん!」
泣いているのはかろうじてわかるが、おそらく榊原だとは誰もわからないだろう。
「見えますよ」
「見えない見えない。拡大してもギリわからないレベルだって」
「でも写ってる」
「いや、あー……まぁ、……写ってるけどさぁ」
「……むかつく。やっぱアンタは俺のこと、全然覚えてなかったんですね」
榊原の声が、拗ねたように低くなった。
「ずっと、そっちから言ってくるの待ってたんですよ。自分から言うの、シャクだし」
……えっ。
俺は、目の前で不貞腐れている後輩を見つめた。
陽キャで、人気者で、誰にでも優しいイケメン。そう思っていた榊原昴が——こんな些細なことで、ずっと根に持っていた?
「お前……」
「なんすか」
「器、ちっさ!」
思わず笑ってしまった。声を出して、腹を抱えて笑った。
「笑ってんじゃねぇよ」
「いや、だって……お前、そんなことでずっと俺のこと嫌ってたの? マジで?」
「そんなことってなんすか。俺にとっては大事なことなんですけど」
「いやごめん、確かに勝手に撮ったのは悪かった。でも本当に気づかなかったんだよ。お前の顔なんか、あの時全然見てなかったし」
「…………」
榊原が黙った。なんか、余計に怒らせた気がする。
「違う違う、そうじゃなくて。俺、あのとき自分の学校のことしか見てなかったから。お前のこと意識して撮ったわけじゃないんだって」
「……わかりました」
「本当にごめんな。……でもさ、お前、マジで器小さいな。あははは!」
「……うるせぇよ」
榊原がむすっとした声で言う。でも、さっきまでのピリピリした空気はなくなっていた。
「一応先輩だからって黙ってましたけど、この際だから言わせてもらっていいですか」
「お、なに?」
「アンタのこと、他にもムカつくとこいっぱいあるんで」
「えっ、まだあるの?」
「アンタの、自分よりみんなを優先するとこ。ムカつきます」
「……それ悪いこと、……なのかな?」
「あと、くだんねぇ冗談言ってへらへら笑ってんのもムカつく」
「俺の冗談そんなつまんない……?」
「あと、俺のこと避けてるくせに、みんなにはにこにこ優しくしやがって」
「いや待て待て、避けてたのそっち——」
「あと、異常なくらい美味しそうにご飯食べるとこ」
「飯を美味そうに食って何が悪いんだよ!」
「あと、久我先輩にいっつも尻撫でられてんの、あれセクハラっすよ。なんで気づいてないんですか、腹立つな」
「……え、あれセクハラなの?」
久我のスキンシップが多いのは知っていたけど、あれって普通じゃなかったのか。いや、普通だろ……。
「あと、今日も部屋で上半身裸になってウロウロしてましたよね? ちょっと意識足りなすぎじゃないですか」
「あー……ごめん、見苦しかった?」
俺は自分の腹を見下ろした。榊原みたいに鍛えられた体じゃないから、確かに見せられたものではないかもしれない。
「いや、そうじゃなくて——いやらしい目で見るやつとかもいると思うんで」
「……えっ」
「だから、気をつけたほうがいいって言ってるんです」
榊原が早口で捲し立てる。
……なんだよ、いやらしい目って。
「ははっ、お前、変なやつだな」
「……は?」
「いや、なんか、面白いなって。お前のそういうとこ、全然知らなかった」
「別に知らなくていいです」
「やば、ウケる」
いつまでも笑っている俺に、榊原が低い声で言った。
「ケンカ売ってんすか?」
「売ってない売ってない。……ていうかさ、お前、俺にだけそういう態度なの、なんで?」
「……さあ」
「他のやつにはめっちゃ愛想いいのに」
「先輩には、なんか……そういうのできないんですよ」
ぼそっと、榊原がそう言った。
月明かりの中、だんだんと目が慣れてきて、榊原の横顔が見えた。照れているような、困っているような、複雑な表情。
——なんだよそれ。
嫌われてると思ってたのに。ずっと、俺だけが一方的に距離を置かれてると思ってたのに。
そうじゃなかったのかもしれない。
少なくとも、今は……完全に嫌っている感じじゃない……と思う。
「……まぁいいや。とりあえず、今日からまたよろしくな、榊原」
「…………」
「返事しろっつの。俺、お前と仲良くなりたいんだよ。せっかく同室になったんだし」
「……別に。勝手にすればいいじゃないんすか」
素っ気ない返事。でも、さっきまでと声のトーンが違う気がした。
その夜、停電が復旧したのは深夜二時だった。
それまでの数時間、俺たちはぽつぽつと他愛ない話をした。榊原が入部しているバスケ部のこと、互いの先生のこと、寮の飯で何が好きか、なんて本当に他愛もないこと。
榊原は相変わらず素っ気なかったけれど、最初の頃よりずっと言葉を返してくれるようになった。
——なんだ、話せるじゃん。
俺は少しだけ嬉しくなって、その夜は前より軽くなった心で眠りについたのだった。