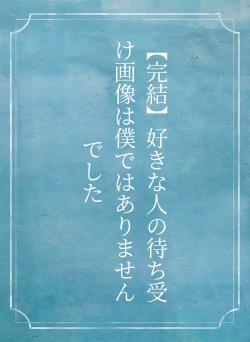【人見孝仁side】
俺があの日、あの路地裏を通りかかったのは本当に偶然だった。
部活を辞めたことで放課後はかなり時間に余裕が出来たことで始めたアルバイト先に向かっている最中の出来事だった。アルバイトと言っても高校生の初めてのアルバイト先で確実に上位TOP3には入るであろうコンビニとかではなく、駅の近くにある個人経営の古い書店だ。
アルバイト先にこの書店を選んだ理由は二つ。
一つは業務内容が楽そうだったからだ。個人経営の書店なだけあって、本の品揃えも御世辞には多いとは言えず、外観も年季の入った木造建築で、お客なんて滅多に来ない。そして俺の予想は狙い通り、アルバイトという形で勤務をしているが実際には店に並んでいる本で読書をしている時間の方が長い。そのためアルバイトではなく、お手伝いに近いだろう。
二つ目は、お客が滅多に来ないことと少し被る部分はあるが、同じ学校の生徒がみせに訪れないことだ。弓道部に属していた時は毎日のように告白をされていた。部活を辞めた今でも告白をしてくる連中はいるが、正直不愉快極まりない。
告白は決まって「ずっと前から好きでした。付き合ってください。」だ。
告白してくる連中には悪いが、俺からしたら”初めまして”の連中ばかりだ。それもいきなり付き合ってくださいなどと図々しいと来た。向こうも俺と面識がないことくらいわかっているだろうにと思うが、向こうはそんなこと一切気にしないのだ。
腹が立つ。
そのため俺は利用客の少ないこの店でアルバイトをすることにした。そのおかげか現状誰にもこの書店でバイトをしていることはバレていない。
そもそもの話ここでバイトを始めて四か月以上経つが、客が入ったのは月に片手で数える程度だ。本当にこんな楽なバイトで給料をもらってもいいのかと不安になるレベルだ。
そんなことを考えながらゆっくりと歩いていると時間は思ったいてよりもかかっていた様で、普段は通ることのない裏路地を使ってショートカットを計ろう思い立った。この裏路地は駅への近道でもある。この裏路地を知っている人が少なくはないのだが、あまりの狭さにほとんどの人が使うことはない。
本来であれば俺だって使いたくはないのだが、この日はバイトに遅刻しそうになっているので致し方がない。
そんなときだった。
「お前のせいでオレは沙耶と別れたんだぞ!」
俺が行こうとしている裏路地の先で怒号が響き渡った。その声量に俺の身体が震えあがるのを感じた。怖いわけではなく、急な怒号に身体が驚いてしまったのだ。身動きが取れずにいると次はドンッと何かを叩きつけるような鈍い音がした。
俺はそこで初めて同じ制服を着た鮫島高等学校の生徒が他校である水科高等学校の生徒に暴行を受けているのだということを理解した。
普段の俺であれば、こんなめんどくさいイベントは無視するだろう。
しかし今日はそういうわけにはいかなかった。なぜだかはわからないが、ここで助けなければ後悔すると心のどこかでそう感じたからだ。
それは俺が今暴行を受けている男子生徒のコトを見たことがあったからかもしれない。知り合いというわけでもなく、話したこともない。そもそも学年が違うため、同じ制服というだけで俺の勘違いかもしれないと思ったが、俺はそいつのコトを確実に知っていた。
——鮫島高等学校の占い師。
鮫島高等学校に通っていてその存在を知らない者はいないだろう。俺も鮫島高等学校ではなかなかの有名人な部類だと思うが、占い師は俺の比にならないくらいの有名人だ。
それは俺とは違い、女性だけではなく男性からの支持もあるからだ。
しかし今はそんなことはどうでもいい。
気が付くと俺は、今にも占い師を殴りつけようとしている他校の男子生徒の腕を掴み、占い師の安否を確認していた。
「鮫島高校の子、大丈夫?もうすぐ警察来るから。」
咄嗟に出た嘘は他校の男子生徒にはひどくめんどくさい存在だったらしく、俺に大きな舌打ちをして、俺が掴んでいる手を振りほどくと、大きなため息を付きながらこの狭い路地から去っていった。
きっと彼は何度か警察のお世話になったことがあるのだろう。そうでなければ警察という単語を聞いただけで逃げ出すことはない。そんなこと思いながら、走り去っていく男子生徒の背中が見えなくなるまで目で追い続けた。
「あ、ありがとうございます。危ないところを助けていただいて。」
俺は占い師に言われてそこで初めて”人助け”をしたのだと認識した。身体が勝手に動いたとはいえまさか自分が人助けなんて行為をするなんて思ってもみなかった。つまり自分で自分の行動に驚いているのだ。
「……全然。怪我は大丈夫そう?」
驚きで返事が遅れてしまったが、とりあえず叩きつけられたであろうあの鈍い音を心配して声を掛けた。大丈夫というのでその場を立ち去ろうとしたが「同じ高校ですよね?」と呼び止められてしまった。
正直めんどくさかったが、ここで無言で立ち去るのも後味が悪いと感じ、少しだけ会話をすることにした。まあすぐこの場を離れて、またあの他校の男子生徒が来ても心配だしなと思いながら。
「そうだけど。お前あれだろ?占いやってる子。」
「あ、はい……そうです。えっと先輩ですよね?」
「俺?三年の人見だ。」
俺はプラスで驚いた。どうやらこの占い師は俺のコトを知らないらしい。
そもそも鮫島高等学校は制服だけでは生徒の学年を判別することはできないが、あれだけ全校集会などで壇上にあがっているんだ。ほとんどの生徒が俺が三年であることは知っているはずだ。そのためこの占い師は俺に気を使ってくれているのだろう。
……正直話しやすかった。
✂ ——— ✂ ——— ✂ ——— ✂ ——— ✂
翌日、昼休みに自販機から戻ってくると教室の前が何やら人だかりが出来ていた。教室に戻りたいのに邪魔だなと思っていたが、人だかりの中心には昨日俺が気の迷いで助けた占い師の新島の姿があった。
おそらく三年の誰かしらにようがあったのだろう。それこそ占いをやってると聞いたことがあるから、三年の誰かを占いに来たに違いない。しかし今の状況では多くの女子生徒に囲まれている。あれでは身動きが取れないだろう。
助ける義理は無いが、昨日の今日で見捨てるような真似をするのは良心が痛む。
俺は自身の心が乱されたことに苛立ちを覚えながらも、新島を助けるために声を掛けた。
「新島に何か用?」
俺の呼びかけに、新島を取り囲んでいた女たちはたじろぎはじめた。どこかで見たことがあると思ったが、俺に告白をしたことがある女が紛れていたようだ。俺の声にたじろいでいたのはそのせいだろう。あまり記憶にないが、きっとよくない振り方だったに違いない。
そんな女は怯えるような声でよくわからない理由を述べたが、興味が無かったので「じゃあ新島借りていくから」とだけ告げ、新島の手を取り、屋上へと向かった。
屋上へ来たのはいいが、このあとはどうすればいいのだろうか。助けるためとはいえ、正直屋上まで来る必要はなかったはずだ。一階から屋上までは割と距離がある。夏ということもあるが、階段で一気に駆けあがってきたため、体感温度は体温の上昇も相まって思っている以上に暑くて熱い。
しかしここまで新島を連れてきてしまった以上、声を掛けないわけにはいかない。正直気は乗らなかったが、話かけることにした。結果は予想外のことに俺に用があったようだ。
昨日のお礼をしたくて、わざわざ三年の教室まで出向き俺を探していたらしい。新島は右手で大事そうに持っていた紙袋を俺に手渡してきた。中身はこれからの季節に活躍しそうなタオル生地のハンカチに香料付きの汗拭きシート。それからクッキーもあった。
「……クッキーは手作りだったりする?」
「あ、いえ……市販です。出来合いのものですみません。」
「いや全然。その方が嬉しいよ。」
これは本音だ。俺はクッキーや手作りの食べ物にいい思い出を持っていない。それは以前女から貰ったクッキーから髪の毛が生えていたからだ。嫌だからせなのか、そういう愛情表現なのかは分からないが、俺には到底理解することのできない気色の悪いクッキーを機に俺は手作りを食べることができない。
それを知ってか知らずか、新島は俺に市販のクッキーを買ってきたようだ。
新島はそんな俺のことを気にしたのか、「不快にさせましたか?」「女性が苦手なんですか?」なんて聞いてきた。俺のことを気にするような素振りをされたのは久しぶりで思いがけず話が弾んだ。
その際に面白いことも聞いた。
新島への占いの大半は俺と付き合えるかどうかを占いに来ているということ。そして俺と相性が良いという占い結果が出たことがある人は今のところいないということだ。
俺は正直に相性が良くないって分かってても告白してくるんだなと若干愚痴をこぼすが、新島から返ってきた言葉は予想外のものだった。
「まぁあくまで占いですから。」
「え?占いやってる奴がそんなこと言っていいの?」
「はい、全然言います。占いは当たるも八卦当たらぬも八卦と言ってますので。占いは当たることもあれば外れることもあるって感じですね。」
正直驚いた。まさか占い師が占いを軽んじているだなんて思ってもみなかったからだ。噂では九十五パーセントの確率で新島の占いは当たると聞いたことがあるが、逆にそんな気持ちで占っているからこそ当たるのかもしれない。
俺が驚いていると、新島は徐々に表情が柔らかくなっていき、ついには笑い始めた。俺はそんな新島に釣られるように笑ってしまった。
「いやぁ久々に学校で笑ったわ。」
「え、そうなんですか?」
「まぁお互いいろいろとあるだろ?」
「そ、そうですね……。」
その時鮫島高等学校の敷地内全体にチャイムが鳴り響いた。それは昼休みの終了の合図でもあり、残り十分足らずで次の授業が始まることを意味していた。俺は久々に学校で笑えたことをもう少し噛みしめていたかったが、チャイムが鳴っては仕方がない。俺は小さく溜息を吐き出し、新島にお礼のお礼を告げ教室に戻る。
……新島としゃべるときは楽でいいな。
俺はそんなことを思いながらゆっくりと階段を降りる。
✂ ——— ✂ ——— ✂ ——— ✂ ——— ✂
数日後、学食で新島とバッタリ出くわした。
いつもあれば購買で出来合いの総菜パンを買ったりしているのだが、今日に限ってはかなり購買が混んでいたため、仕方なく学食に足を運んだ結果だった。
普段学食なんて来ないため、そもそも学食のあたりメニューが分からない。
どれにしようか悩んでいると、新島から予想もしていなかったことを言われた。
「……あの、もしよければお菓子の消費手伝ってくれませんか?」
「え?」
どうやら占いのお礼で貰うお菓子の消費を手伝ってほしいというものだ。正直占いのお礼なら新島自身が食べるべきではないかと思ったが、一人では食べきれないとのことなんでありがたく貰うことにした。
そもそも俺は菓子などの甘いものが好きだ。
あの女のせいで手作りやクッキーが苦手になっただけで本当であれば毎日でも食べたい。
そんな俺にとって新島からの提案は素晴らしいものだった。
俺は「どもっ」と少しの恥ずかしさを紛らわすかのようにぶっきらぼうな態度を取りながら、新島が俺の取りやすい位置に置いてくれた紙袋から無作為に個包装の菓子を取り出す。
そんな俺の行動を新島はずっと目で追っていた。正面ということもあるが、ここまで見られていれば誰だって気が付くだろう。
「見すぎ。」
「え、あ、ごめんなさい!」
「別にいいけど。新島は食べないの?」
「た、食べます。」
そういって新島も菓子を紙袋からいくつか取り出し、食べ始めた。
しかしそんな時間はすぐに終わりを迎えた。おそらく俺目当てだろう下級生が話掛けてきたからだ。気持ちの悪い猫なで声でしゃべるその女二人は空気が読めないのか単純に馬鹿なのか分からないが、相席しようと席に座り、それでも無視を続けると今度は新島の菓子を食べようとし始めた。
新島は戸惑っていたが、流石にこれは容認できないものだった。
この菓子を貰っている俺が言えた立場じゃないが、これは新島が占いをしてそのお礼に貰っているモノだ。つまりこの不躾な女たちは人が労働で得たものを勝手に持っていこうとしているわけだ。何度もいうがこれは容認できるものではない。
女が話掛けているのは俺のため、新島は言いづらいのだろうか?それとも新島の同級生で関係を崩さないために、言いたくても言いづらい雰囲気になっているのかは分からないが、何か言いたげな表情をしているが、身体が動かないようだ。
まぁ俺もこれには不快であることを示す必要がある。
「うぜぇよ。新島と飯食ってんだろ。見てわかんねぇのか。」
俺は掴み慣れた新島の手を取り、ついでに女に菓子を取られないように紙袋をちょっとだけ雑に取り上げると、先日のように屋上へと足を進めた。
屋上へと足を進めていたが、先日の屋上の暑さを思い出し、屋上に出入りできる踊り場で足を止めた。女たちへの苛立ちもあったからか、それともただ暑いだけかは分からないが俺の手は汗ばんでおり、その若干の恥ずかしさと申し訳なさから俺はゆっくりと新島から手を離し、申し訳なさをアピールしながら声を掛けた。
「……痛くなかったか?」
「は、はい。大丈夫です。せ……先輩こそ大丈夫ですか?」
新島は自分の心配より先に、俺の心配をしてくれているらしい。普段なら俺に近寄ってくる奴らの心配は、本当に心配しているわけではなく、俺と話すための口実に過ぎないが新島の場合は違う。本気で俺のことを心配してくれている。
……人に心配されて悪い気がしなかったのは初めてかもしれない。
俺は少し呼吸を整えてから、屋上は暑いからこの踊り場で続きを食べようと提案をし、ゆっくりと腰を落とす。踊り場の床は思っていた以上に冷たく、下手に教室で食べるよりも快適に食事をすることができるかもしれない。
そんなことを考えていたが、新島はなかなか座ろうとしないので、軽く床を叩き座るように指示を出す。新島が座ったことを確認してから俺たちはまた菓子を食べ進めた。
今思い返してみれば、誰かと昼食を共にするのは本当に久しぶりかもしれない。普段であれば購買でかった総菜パンをパパッと一人で食べ終え、どこかで時間を潰してから教室に戻る。そんな一種のルーティンを続けてきたのだが、今日は新島とその時間を過ごしている。そんな普段とは違う環境に俺自身が少し浮かれていたのかもしれない。
それは新島とLINEを交換したからだ。
「それじゃあ今度僕とカフェとか行きませんか?僕が『お菓子食べませんか?』なんて言ったから、せっかくのお昼でしたのに気分を害されたので……そのお詫びということで……。どうですか?」
新島からカフェに行かないかと提案を受けた。いつもなら無視するか御断りをするのだが、今回の相手は新島だ。こいつはおそらく俺に媚を売るためにこんなことを言ってきているわけじゃないだろう。そう考えて俺はカフェに行くことを了承し、そのまま勢いでLINEまで交換した。
新島はあまり深く考えてないなさそうだったので、俺からLINEの交換提案をしたのだが、俺は初めてこの学校でLINEを交換したかもしれない。
まあ、新島ならいいか。
✂ ——— ✂ ——— ✂ ——— ✂ ——— ✂
日曜日。普段の俺であれば、バイトに行ったりしたり家で勉強や課題に手を付けていることだと思うが、今日は駅に来ている。
新島とカフェに行くためだ。
新島からは控えめな文章でLINEが来たときは思わず笑ってしまったが、俺のことを考えて時間を掛けて考えた文章を送ってくれたと考えると途端に嬉しくなった。
一応服装など気を使った方がいいのだろうかと考えたが、新島といるときは自然体でいることの方が多いことを思い出し、俺はいつも通りの白のTシャツにジーンズというラフな恰好で新島との待ち合わせに向かった。この服装は俺がバイトをするときの格好だ。楽な仕事とはいえ、本の整理などで割と身体を動かすことがあるため、あえて動きやすいラフな恰好でバイトをしている。
待ち合わせ場所に着くと、既に新島がいた。約束の時間より早く着いたと思っていたのだが少し申し訳ないことをしたかもしれない。俺は足早に新島と合流し、そのままカフェへと向かう。
カフェは想像していたものとは異なっており、隠れ家的な場所にあるそんなカフェだった。きっとチェーン店にでも行くのだと思っていたが、そうではなかったらしい。
俺は来たこともない隠れ家のカフェにテンションがあがりながらも、新島にお勧めのメニューを聞く。
「ここは何がおいしいんだ?」
「聞いたところによると、パフェがおいしいらしいです。チョコとイチゴとマンゴーがあるみたいです。」
「そうなんだ。新島はもう何にするか決まってるの?」
「僕はパフェにいいなとは思うんですけど、シンプルにお腹も空いているのでホットサンドでも頼もうかと思ってます。」
「俺もホットサンド食べたい。シェアするか?」
「いいですね!それならパフェも頼んじゃおうかな。先輩はどの味にします?」
「……チョコ。」
「わかりました!」
そう言うと新島は右手を上げ店員を呼び注文をした。新島の右手を見て気になったのだが、湿布は取れているようだった。きっと痛みは引いたのだろうと安心した。
新島の注文から数分後、俺たちのテーブルには予想よりもでかいパフェと帆とサンドであるクロックムッシュが運ばれてきた。ぶっちゃけ腹はかなり減っている。朝食を抜いた自分が悪いのだが、正直カフェが少し楽しみだったことは新島にはナイショだ。
俺は運ばれてきたクロックムッシュをお腹が空いていたこともあり、一口で食べきる勢いで頬張る。流石にこの大きなクロックムッシュを一口で食べきることは出来なかったが、四分の一はすでに俺の胃に納まっている。
新島とご飯を食べるようになって気が付いたが、新島は俺が食事をするときに俺のコトをずっと見ている。
「……また見てる。」
「あ、ご、ごめんなさい。」
「いいけど。新島よく俺の食べるところ見てるよな?もしかして食べ方汚い?」
「そんなことないです!いつも豪快に食べる感じが好きで……ついつい見ちゃうんです。」
「……そ、不快に感じてないならいいや。」
どうやら食べ方が汚くて凝視しているわけではないらしい。少し不安だったが新島がいうならそうなのだろう。俺は続けてクロックムッシュを食べ進める。しかし豪快に食べる感じが好きとはどういうことだろうか。それが気になり今度は俺が新島の食べるところを凝視する。
新島は俺のようにクロックムッシュを口いっぱいに頬張るが、あまりのチーズの量とあまりの分厚さに噛み切れなかったハムがクロックムッシュから一気に零れ落ちる。
そんな姿を見て、俺は思わず微笑んでしまった。
新島は笑われたと勘違いして、両手で持っていたクロックムッシュで顔を覆い隠すが、その姿にかわいさを覚え「もう遅いって」と思わずツッコミを入れてしまった。
俺はきっとどんどん新島といるのが楽しくなっていたんだと思う。
だからこうやって笑えているんだろ思う。
だから俺は少し新島に期待していたのかもしれない。
「新島はさ、俺が弓道辞めた理由知ってる?」
✂ ——— ✂ ——— ✂ ——— ✂ ——— ✂
弓道を始めた理由。
始めた結果どんな扱いをされていたのか。
そしてどうして弓道を辞めるに至ったのか。
そのすべてを新島は質問を交えながら真剣に聞いてくれた。
そして俺の新島への第一印象もここで話した。
最初の印象は最悪だったこと。今はそんなこと思ってないことを。全部話した。
「印象が最悪な奴とカフェとかいかねーだろ。少なくとも今は好印象だよ。そうだな。あえて言うなら弟的なそんな存在かな。」
「お、弟?」
「ん。放っておけない感じ?俺一人っ子だからわかんないけど、弟がいたらこんな感じなのかなって。」
そうだ。新島は俺にとって弟のような存在なんだ。
新島としゃべるのは楽で良いなと思うにも、LINEを交換しても良いと思えるのも全て。
きっと新島が俺にとって弟のような存在だからだ。
それを聞いた新島は徐々に顔が俯き始めた。新島はきっと恥ずかしがり屋だから真っ赤な顔を隠すために俯いているのだろうと考えていた。
「大丈夫か?」
「え、あ、はい!大丈夫です。弟的な存在……嬉しいです!先輩が誰かと仲良くしているところなんて見たことなかったので。そうすると僕は人見先輩の中じゃだいぶ上位に入るくらいの人間ってことですか?」
「……俺、学校じゃ新島以外と喋んねーよ。」
「そうなんですか?」
「他学年だと声を掛けられることはあっても、同学年だとねーな。誰かと学校で昼食食ったりしたのだってそれこそ一年ぶりとかじゃねーかな。」
「それは……光栄ですね。」
「なんだそれ。そういえばこうやって休日家族以外とどこか出かけたりするのは初めてかもな。」
「え!!!!!」
「うるさっ!」
「す、すみません。取り乱しました。」
「いやいいけどさ。そんなに驚くことか?」
「いえ、先輩ならいろんな方とデートとか行かれてるでしょうから、お出かけとかは慣れてるんだと思ってました。」
「デートねぇ……。なら今日の新島とのデートが初デートだな。」
それ見たことか。やっぱり新島はすぐに顔を赤くする。かわいい弟だ。
実際に兄弟のいない俺は、弟とどのように過ごせばいいかは分からないが、もしいたらこんなことをするのだろうかと考えながら、俺は新島に向かって口を大きく開けた。
「あーん、して。」
「え?」
「新島のイチゴのパフェも食べたいから交換しねえ?だからあーんして。」
新島は動揺の末、イチゴパフェを俺に食べさせた。
兄弟なら御返しもするだろうと、俺も自分のチョコパフェを新島に食べさせる。
「んまぁ。」
「……満足そうで何よりです。」
「新島は?美味かったか?」
「は、はい!めちゃくちゃおいしいです!」
「そ、ならいいよ。」
その後イチゴパフェの美味しさと弟へのいたずらに魔が差し、何度か新島のパフェを盗み食いしていたが、案の定新島にはバレていたらしい。
カフェデートの後は、俺の提案で先日新島が助けたお礼にくれたクッキーを購入した店に連れてってもらうことにした。実は新島に貰ったクッキーは最初かなり警戒していたのだが、食べてみると本当に美味かった。そのためどこであのクッキーが買えるのか気になっていたのだ。
店はクッキーだけではなく、紅茶の販売もしているそうで、新島のおすすめを購入することにした。新島に何か買うかと問うと先日俺にくれたクッキーのセットだというのでそれも買った。
「ん。」
「……これって?」
「今日のお礼的なやつ。」
「お、お礼?」
「デートが楽しかったお礼。」
「え、いや、いただけませんよ!お金払います。」
「じゃあ次一緒に行くための対価ってことで。」
新島はほんとに弟のような存在だ。
弟の欲しがっていたものをあげるなんて、本当に兄みたいだ。
✂ ——— ✂ ——— ✂ ——— ✂ ——— ✂
新島とは、あの日のデートを境に関係値が変わった。
まず昼食は基本的に共に過ごすし、放課後は新島と一緒にどこかに寄ったりすることも増えた。
こんなにも楽しい学生生活は初めてかもしれない。
実際俺は心のどこかでこんな生活を夢見ていたし、期待に胸を膨らませていた。今までは俺に近づこうとする女や、俺と仲良くなり女にモテたいとかいう男から誘いを受けることはあったが、それが求めていたものかと言われればそうではない。
もっと本当の友達や恋人といった関係の人とすることに意味があった。それが叶うことはないと思っていたが、それは新島との出会いによって変わっていった。
今日も俺は新島と下校を共にするために、新島の占いが終わるのを待つ。
最初こそ、俺が新島と一緒に帰っていることを目撃した誰かが、噂を広めたようで、始めはそれなりに校内で話題になったようだが、今ではそれが普通になったようで変に勘ぐってくるような輩はいなくなった。
「終わったか?」
「わ!人見先輩!待っててくれたんですか?」
俺は新島の占いが終わるのを待って今日も声をかけた。
今日は占いのお礼として、スタバのギフトカードをもらったようで、一緒にスタバに行くことになった。スタバはしょっちゅう行くわけではないが、バイト前後の時間潰しに少し寄ったりする。常連というわけではないが、ある程度のメニューには心得がある。そんな感じだ。
「流石に暑いな。」
「ですね……。そろそろ夏休みですね。人見先輩は何か予定あるんですか?」
「んー。何度かは学校に行く予定。これでも受験生なんで。」
「あ、そうじゃないですか!どこ受けるんですか?」
「……ナイショ。」
「……ケチだ。」
「冗談だよ。誰にも言ってねーからなあ。」
「そうなんですか?……あぁ、なるほど。そうですよね。」
「まぁ新島には言ってもいいか。」
「え、いいんですか?」
「まぁ……弟だし?」
「……なんすかそれ」
夏休みが近いということもあってか、お互いの予定を確認する。しかし俺は一応受験生なわけでそれとなくそのことを伝えると、意外にも食いついてきた。実を言うと俺は教師以外にはどこの学校を受験するつもりかなど話したことはない。
別に将来の夢を語ることが恥ずかしいとかそういうわけではないのだが、そうベラベラと言いふらすものでもないとも考えている。ぶっちゃけ新島以外の生徒に俺の進学先をうっかり漏らしてしまった場合は次の日には全校生徒が俺の進学先を知ることになるだろう。
しかし新島はそんなことはしない。それだけ信用を置いているのだ。
スタバに着き、注文を進めていく。新島の分も一緒に注文するため、新島にフラペチーノのサイズを確認する。すると新島は「Lサイズ」と回答した。
面白さより驚きが勝ったね。
まさか高校生でスタバのサイズ形式を知らない者がいるなんて思ってもみなかったからだ。
「新島ってもしかしてスタバ初めて?」
「いえ、何度かは来たことはありますよ?」
「……一人で?」
「友達とですけど……。」
「そ。スタバのサイズはSMLじゃないぞ。ショート、トール、ベンティが基本のサイズ構成だ。」
「え?そうなんですか?」
俺はスタバ店内であることを忘れ、馬鹿笑いした。店員も微笑んでいたしまあいいだろう。新島は俺が笑ってしまったことで顔を真っ赤にし、プルプル震えている。きっと恥ずかしさに押しつぶされそうなのだろう。
「はあー。お前かわいいな。笑ってごめんな。驕るから許して。」
「かわっ……。かわいくないですよ!」
「かわいいよ。新島は。」
これは本心だ。
新島はかわいい。これは俺が新島のことを弟のように思っているからだと思う。
注文を済ませ、バニラフラペチーノを受け取り、店内に空いていた席に座る。
俺はバニラフラペチーノを思いきいり吸ったが、出来立てでまだ凍っているのか一切吸うことはできなかった。溶けるのを待っている間、俺は新島に聞いてみたかったことを質問する。
「俺も新島に占ってもらえるの?」
「……え?」
「占いだよ。新島がいつも放課後やってるやつ。あれ俺も占ってほしいんだけど、お菓子とか持ってくればいいわけ?」
「え、人見先輩って占いに興味があるんですか……?てっきり占いなんて興味無いんだと思ってました。」
「んー。そこまで興味は無いよ。でも新島の占いは九十五パーセントの確率で当たるんだろ?そこまで高いんだったら少しは気になるよ。」
おかしい。明らかに新島は動揺している。もしかして何か変なことを言ってしまったのだろうか。しかし思い返してみてもただ単に占ってほしいと言っただけに過ぎない。
俺が少し疑問に思っていると、新島は占いは予約制である旨を伝えてきた。
ならどこで予約ができるのかを聞いたが、現在は先まで予約で埋まっているため予約は受けていないとのことだった。
俺個人としては占ってほしいことがあるわけではないので、別にそれでもいいかと思い、予約ができるようになったら教えてくれとだけ伝えておいた。
✂ ——— ✂ ——— ✂ ——— ✂ ——— ✂
夏休みに入り、俺はバイトと勉強の毎日を送っている。一応すでに滑り止めとして推薦はもらっているのだが、俺としては専門に行きたいと思っているため、推薦は断ろうと思っている。そうなってくると必然的に受験勉強をしなくてはならない。
バイト先である個人経営の古書店は客も来ないため、店長に許可をもらって、店番をしながら参考書を眺めたりしている。
正直身が入らない。
勉強は別に苦ではないのだが、集中ができないのだ。
ここのところ俺はどうかしてしまったのかもしれない。
趣味が瞑想で精神統一であることを自称しているが、それができていない。本来の俺は集中なら誰にも負けない自信があったが今は気になることがずっとあり、一切集中することができない。
原因は新島だ。
新島が今、何をしているのか。そんなことばかり考えてしまう。
きっと今まで休日などで遊んだ経験がほとんどなく、新島に依存してしまっているのだろう。
自己分析はできている。できているが、気になってしまったものはしょうがない。俺は新島に連絡を取るための口実を探すため、バイト終わりにキョロキョロと周りを見渡しながら帰る。
そこで気づいたのだが、今日はどうも人が多い。夏休みのため人が多いことはわかっているがそうではない。浴衣姿の女が多いのだ。——今日は夏祭りか!
これで新島に連絡を取る口実ができた。家に帰り着き自室のベッドで横になりながら新島にどう連絡をしようかと考えるため新島のLINEを開いたところで、タイミングよく新島から連絡がきた。
——気分転換に僕とどこか遊びに行きませんか?
これはお誘いだ。そしてこのタイミング。嬉しくないわけがない。
LINEを続けていると、新島は今日が夏祭りであることを知らずにお誘いをしたらしい。そうなればもっとうれしい。だって夏祭りという口実がなくとも、新島は俺と遊びたいと思ってくれているのだから。
そうとなれば俺はこの嬉しさのお礼をするために、今日は存分に弟を甘やかさなくてはならない。十九時に駅集合という間に合わせの約束を取り付けた。
俺はATMに寄るため、約束の時間より早めに駅に着いたのだが、そこにはすでに新島の姿があった。
「新島?はやくねーか?」
「人見先輩!こんばんは!」
「ん。まだ時間までだいぶあるぞ?」
「いつも先輩を待たせてしまっているので、今日くらいはと思いまして。それに今日はバイト早上がりだったんです。だから時間に余裕が出来てしまいまして……」
やはり新島といると楽しい。まだ祭りの会場にすらたどり着いていないのにすでに楽しい。さっきまで一切集中できなかったのに、今なら集中出来る気がする。
俺はATMでちゃっちゃと現金を引き出し、新島と祭り会場へと向かった。
聞くところによると新島は夏祭りに来るのが初めてらしい。俺もぶっちゃけくるのは初めてだが、ここは兄としてしっかり今日の夏祭りデートをエスコートしなければならない。俺はいつものように新島の手を取り、祭り会場へと向かう。
祭り会場はすでに賑わいを見せており、はぐれないように新島の手を強く握り直す。
新島に好き嫌いはないかと問いかけ、ないと返事をもらったため目に入った屋台を次々に周っていった。両手で持ちきれないほど買い込み、近くの公園のベンチで一息ついた。
他愛もない話をしながら買い込んだご飯を食べ進めていく。話は俺がやりたいことについての話に変わった。新島が言うには俺が今までできなかったことは全部やりましょうとのこと。しかし俺がやりたかったことはすべて新島のおかげで叶えることができている。
それを聞いた新島は嬉しそうにもしたが、反対に少し悲しげな表情もした。きっともっと俺のためにしたいことがあったのだろう。このままでは新島が悲しんでしまうかもしれないと考え、その結果一つやってもらいたいことを思い出した。
占いだ。
新島に占ってほしい。そのことを伝えると、新島の表情はどんどん曇っていった。俺は言葉の選択を間違ってしまったのだと感じた。以前占ってほしい旨を聞いたときは準場があるからと断られたが、おそらくあれは本心ではない。きっと新島は俺を占いたくないのだ。
……なぜだ?
その疑問は俺の中で膨れ上がり、怒りへと変わっていった。
俺はその勢いのまま新島を攻めるように問いかけた。
「俺のこと占うなって誰かに止められてんの?」
「……違います。」
「じゃあ新島の意志で俺を占いたくないってことね。」
「……はい。」
「その理由は教えてくれねーの?」
「……言ってしまったらもう、人見先輩は俺と話してくれなくなります。」
「俺がその理由を聞いたら、俺から新島と距離を置くような、そんな内容なの?」
「……はい。」
「俺の嫌いなコト知ってるよな?」
「こ、心を乱されることです。」
「まさに今、この状況がそうだよ。」
「ごめん……なさい。」
「……今日は夏祭りデートに付き合ってもらってどーも。」
俺はコントロールできない自身の怒りを抑えきれなくなり、新島とのデートを中断して帰路につく。
俺は最低だと思う。自分から占ってほしいなんて聞いておいて、いざ占いを断られただけでこんな態度を取るなんて。
本当は前から気づいていたんだ。俺の新島に対する気持ちに。これは弟に向けるような気持ちではない。俺が自分の気持ちに気づきたくなくて、そんな気持ちを上書きするためについたのが新島は弟のような存在であるという嘘だ。
わかっていた。自分がなぜ新島といるとこんなにも楽しいのか。なぜ新島のことを考えてしまうのか。全部わかっていた。
この怒りも新島が占ってくれなかったことに対するものじゃない。これは”嫉妬”だ。
新島に占ってもらったやつが羨ましい。それなのに俺は占ってもらえない。嫉妬で狂いそうになる。それが今表に出てしまった。
俺は最低だ。
新島………………好きだ。
✂ ——— ✂ ——— ✂ ——— ✂ ——— ✂
夏休みが終わり、新学期が始まり二週間が経過していた。
あの一件以来、俺は新島と連絡を取っていない。
本来であれば俺が素直に謝罪をするべきなのだが、俺にはその勇気がなかった。ほんとにしょうもない。さっさと謝ってまた一緒に昼食を取りたいし、下校時も一緒に帰りたい。
自分の不甲斐なさに、もっと自分が嫌いになっていく。
俺は大きなため息を吐きながら、教室の隅で一人、机に顔を伏せながら休み時間が終わるのを待っていた。
「ねぇ、占い師の話聞いた?」
「聞いた!あれでしょ。占いが全く当たらなくなったってやつ!」
「そうそう!高校最後に占ってもらおうと思ってたけど、辞めとこうかなー。」
「うわ薄情じゃん。でももともとは九十五パーセントの確率で当たってたんでしょ?最近何かあったんじゃない?」
「どうなんだろうね。あ、でも挙動不審だったって聞いたよ?」
「挙動不審?なにそれ?」
「なんか、なにかに怯えてるっていうか?」
「え、大丈夫なんそれ?」
「わかんない。今度差し入れでも持っていってあげる?」
「いいね。ついでに占ってもらお!」
「結局占ってほしいんじゃん!」
「バレたか……」
盗み聴くつもりはなかったが、聞こえてしまったものはしょうがない。
しかし今はそんなことはどうでもいい。
新島の占いが当たらなくなった?いつも何かに怯えている?
どういうことだ?今すぐ新島に会って確認したい。新島が困っているなら助けたい。
でも俺にはその資格はない。
俺は机に伏せた状態で小さく「くそっ……」と呟いた。
俺があの日、あの路地裏を通りかかったのは本当に偶然だった。
部活を辞めたことで放課後はかなり時間に余裕が出来たことで始めたアルバイト先に向かっている最中の出来事だった。アルバイトと言っても高校生の初めてのアルバイト先で確実に上位TOP3には入るであろうコンビニとかではなく、駅の近くにある個人経営の古い書店だ。
アルバイト先にこの書店を選んだ理由は二つ。
一つは業務内容が楽そうだったからだ。個人経営の書店なだけあって、本の品揃えも御世辞には多いとは言えず、外観も年季の入った木造建築で、お客なんて滅多に来ない。そして俺の予想は狙い通り、アルバイトという形で勤務をしているが実際には店に並んでいる本で読書をしている時間の方が長い。そのためアルバイトではなく、お手伝いに近いだろう。
二つ目は、お客が滅多に来ないことと少し被る部分はあるが、同じ学校の生徒がみせに訪れないことだ。弓道部に属していた時は毎日のように告白をされていた。部活を辞めた今でも告白をしてくる連中はいるが、正直不愉快極まりない。
告白は決まって「ずっと前から好きでした。付き合ってください。」だ。
告白してくる連中には悪いが、俺からしたら”初めまして”の連中ばかりだ。それもいきなり付き合ってくださいなどと図々しいと来た。向こうも俺と面識がないことくらいわかっているだろうにと思うが、向こうはそんなこと一切気にしないのだ。
腹が立つ。
そのため俺は利用客の少ないこの店でアルバイトをすることにした。そのおかげか現状誰にもこの書店でバイトをしていることはバレていない。
そもそもの話ここでバイトを始めて四か月以上経つが、客が入ったのは月に片手で数える程度だ。本当にこんな楽なバイトで給料をもらってもいいのかと不安になるレベルだ。
そんなことを考えながらゆっくりと歩いていると時間は思ったいてよりもかかっていた様で、普段は通ることのない裏路地を使ってショートカットを計ろう思い立った。この裏路地は駅への近道でもある。この裏路地を知っている人が少なくはないのだが、あまりの狭さにほとんどの人が使うことはない。
本来であれば俺だって使いたくはないのだが、この日はバイトに遅刻しそうになっているので致し方がない。
そんなときだった。
「お前のせいでオレは沙耶と別れたんだぞ!」
俺が行こうとしている裏路地の先で怒号が響き渡った。その声量に俺の身体が震えあがるのを感じた。怖いわけではなく、急な怒号に身体が驚いてしまったのだ。身動きが取れずにいると次はドンッと何かを叩きつけるような鈍い音がした。
俺はそこで初めて同じ制服を着た鮫島高等学校の生徒が他校である水科高等学校の生徒に暴行を受けているのだということを理解した。
普段の俺であれば、こんなめんどくさいイベントは無視するだろう。
しかし今日はそういうわけにはいかなかった。なぜだかはわからないが、ここで助けなければ後悔すると心のどこかでそう感じたからだ。
それは俺が今暴行を受けている男子生徒のコトを見たことがあったからかもしれない。知り合いというわけでもなく、話したこともない。そもそも学年が違うため、同じ制服というだけで俺の勘違いかもしれないと思ったが、俺はそいつのコトを確実に知っていた。
——鮫島高等学校の占い師。
鮫島高等学校に通っていてその存在を知らない者はいないだろう。俺も鮫島高等学校ではなかなかの有名人な部類だと思うが、占い師は俺の比にならないくらいの有名人だ。
それは俺とは違い、女性だけではなく男性からの支持もあるからだ。
しかし今はそんなことはどうでもいい。
気が付くと俺は、今にも占い師を殴りつけようとしている他校の男子生徒の腕を掴み、占い師の安否を確認していた。
「鮫島高校の子、大丈夫?もうすぐ警察来るから。」
咄嗟に出た嘘は他校の男子生徒にはひどくめんどくさい存在だったらしく、俺に大きな舌打ちをして、俺が掴んでいる手を振りほどくと、大きなため息を付きながらこの狭い路地から去っていった。
きっと彼は何度か警察のお世話になったことがあるのだろう。そうでなければ警察という単語を聞いただけで逃げ出すことはない。そんなこと思いながら、走り去っていく男子生徒の背中が見えなくなるまで目で追い続けた。
「あ、ありがとうございます。危ないところを助けていただいて。」
俺は占い師に言われてそこで初めて”人助け”をしたのだと認識した。身体が勝手に動いたとはいえまさか自分が人助けなんて行為をするなんて思ってもみなかった。つまり自分で自分の行動に驚いているのだ。
「……全然。怪我は大丈夫そう?」
驚きで返事が遅れてしまったが、とりあえず叩きつけられたであろうあの鈍い音を心配して声を掛けた。大丈夫というのでその場を立ち去ろうとしたが「同じ高校ですよね?」と呼び止められてしまった。
正直めんどくさかったが、ここで無言で立ち去るのも後味が悪いと感じ、少しだけ会話をすることにした。まあすぐこの場を離れて、またあの他校の男子生徒が来ても心配だしなと思いながら。
「そうだけど。お前あれだろ?占いやってる子。」
「あ、はい……そうです。えっと先輩ですよね?」
「俺?三年の人見だ。」
俺はプラスで驚いた。どうやらこの占い師は俺のコトを知らないらしい。
そもそも鮫島高等学校は制服だけでは生徒の学年を判別することはできないが、あれだけ全校集会などで壇上にあがっているんだ。ほとんどの生徒が俺が三年であることは知っているはずだ。そのためこの占い師は俺に気を使ってくれているのだろう。
……正直話しやすかった。
✂ ——— ✂ ——— ✂ ——— ✂ ——— ✂
翌日、昼休みに自販機から戻ってくると教室の前が何やら人だかりが出来ていた。教室に戻りたいのに邪魔だなと思っていたが、人だかりの中心には昨日俺が気の迷いで助けた占い師の新島の姿があった。
おそらく三年の誰かしらにようがあったのだろう。それこそ占いをやってると聞いたことがあるから、三年の誰かを占いに来たに違いない。しかし今の状況では多くの女子生徒に囲まれている。あれでは身動きが取れないだろう。
助ける義理は無いが、昨日の今日で見捨てるような真似をするのは良心が痛む。
俺は自身の心が乱されたことに苛立ちを覚えながらも、新島を助けるために声を掛けた。
「新島に何か用?」
俺の呼びかけに、新島を取り囲んでいた女たちはたじろぎはじめた。どこかで見たことがあると思ったが、俺に告白をしたことがある女が紛れていたようだ。俺の声にたじろいでいたのはそのせいだろう。あまり記憶にないが、きっとよくない振り方だったに違いない。
そんな女は怯えるような声でよくわからない理由を述べたが、興味が無かったので「じゃあ新島借りていくから」とだけ告げ、新島の手を取り、屋上へと向かった。
屋上へ来たのはいいが、このあとはどうすればいいのだろうか。助けるためとはいえ、正直屋上まで来る必要はなかったはずだ。一階から屋上までは割と距離がある。夏ということもあるが、階段で一気に駆けあがってきたため、体感温度は体温の上昇も相まって思っている以上に暑くて熱い。
しかしここまで新島を連れてきてしまった以上、声を掛けないわけにはいかない。正直気は乗らなかったが、話かけることにした。結果は予想外のことに俺に用があったようだ。
昨日のお礼をしたくて、わざわざ三年の教室まで出向き俺を探していたらしい。新島は右手で大事そうに持っていた紙袋を俺に手渡してきた。中身はこれからの季節に活躍しそうなタオル生地のハンカチに香料付きの汗拭きシート。それからクッキーもあった。
「……クッキーは手作りだったりする?」
「あ、いえ……市販です。出来合いのものですみません。」
「いや全然。その方が嬉しいよ。」
これは本音だ。俺はクッキーや手作りの食べ物にいい思い出を持っていない。それは以前女から貰ったクッキーから髪の毛が生えていたからだ。嫌だからせなのか、そういう愛情表現なのかは分からないが、俺には到底理解することのできない気色の悪いクッキーを機に俺は手作りを食べることができない。
それを知ってか知らずか、新島は俺に市販のクッキーを買ってきたようだ。
新島はそんな俺のことを気にしたのか、「不快にさせましたか?」「女性が苦手なんですか?」なんて聞いてきた。俺のことを気にするような素振りをされたのは久しぶりで思いがけず話が弾んだ。
その際に面白いことも聞いた。
新島への占いの大半は俺と付き合えるかどうかを占いに来ているということ。そして俺と相性が良いという占い結果が出たことがある人は今のところいないということだ。
俺は正直に相性が良くないって分かってても告白してくるんだなと若干愚痴をこぼすが、新島から返ってきた言葉は予想外のものだった。
「まぁあくまで占いですから。」
「え?占いやってる奴がそんなこと言っていいの?」
「はい、全然言います。占いは当たるも八卦当たらぬも八卦と言ってますので。占いは当たることもあれば外れることもあるって感じですね。」
正直驚いた。まさか占い師が占いを軽んじているだなんて思ってもみなかったからだ。噂では九十五パーセントの確率で新島の占いは当たると聞いたことがあるが、逆にそんな気持ちで占っているからこそ当たるのかもしれない。
俺が驚いていると、新島は徐々に表情が柔らかくなっていき、ついには笑い始めた。俺はそんな新島に釣られるように笑ってしまった。
「いやぁ久々に学校で笑ったわ。」
「え、そうなんですか?」
「まぁお互いいろいろとあるだろ?」
「そ、そうですね……。」
その時鮫島高等学校の敷地内全体にチャイムが鳴り響いた。それは昼休みの終了の合図でもあり、残り十分足らずで次の授業が始まることを意味していた。俺は久々に学校で笑えたことをもう少し噛みしめていたかったが、チャイムが鳴っては仕方がない。俺は小さく溜息を吐き出し、新島にお礼のお礼を告げ教室に戻る。
……新島としゃべるときは楽でいいな。
俺はそんなことを思いながらゆっくりと階段を降りる。
✂ ——— ✂ ——— ✂ ——— ✂ ——— ✂
数日後、学食で新島とバッタリ出くわした。
いつもあれば購買で出来合いの総菜パンを買ったりしているのだが、今日に限ってはかなり購買が混んでいたため、仕方なく学食に足を運んだ結果だった。
普段学食なんて来ないため、そもそも学食のあたりメニューが分からない。
どれにしようか悩んでいると、新島から予想もしていなかったことを言われた。
「……あの、もしよければお菓子の消費手伝ってくれませんか?」
「え?」
どうやら占いのお礼で貰うお菓子の消費を手伝ってほしいというものだ。正直占いのお礼なら新島自身が食べるべきではないかと思ったが、一人では食べきれないとのことなんでありがたく貰うことにした。
そもそも俺は菓子などの甘いものが好きだ。
あの女のせいで手作りやクッキーが苦手になっただけで本当であれば毎日でも食べたい。
そんな俺にとって新島からの提案は素晴らしいものだった。
俺は「どもっ」と少しの恥ずかしさを紛らわすかのようにぶっきらぼうな態度を取りながら、新島が俺の取りやすい位置に置いてくれた紙袋から無作為に個包装の菓子を取り出す。
そんな俺の行動を新島はずっと目で追っていた。正面ということもあるが、ここまで見られていれば誰だって気が付くだろう。
「見すぎ。」
「え、あ、ごめんなさい!」
「別にいいけど。新島は食べないの?」
「た、食べます。」
そういって新島も菓子を紙袋からいくつか取り出し、食べ始めた。
しかしそんな時間はすぐに終わりを迎えた。おそらく俺目当てだろう下級生が話掛けてきたからだ。気持ちの悪い猫なで声でしゃべるその女二人は空気が読めないのか単純に馬鹿なのか分からないが、相席しようと席に座り、それでも無視を続けると今度は新島の菓子を食べようとし始めた。
新島は戸惑っていたが、流石にこれは容認できないものだった。
この菓子を貰っている俺が言えた立場じゃないが、これは新島が占いをしてそのお礼に貰っているモノだ。つまりこの不躾な女たちは人が労働で得たものを勝手に持っていこうとしているわけだ。何度もいうがこれは容認できるものではない。
女が話掛けているのは俺のため、新島は言いづらいのだろうか?それとも新島の同級生で関係を崩さないために、言いたくても言いづらい雰囲気になっているのかは分からないが、何か言いたげな表情をしているが、身体が動かないようだ。
まぁ俺もこれには不快であることを示す必要がある。
「うぜぇよ。新島と飯食ってんだろ。見てわかんねぇのか。」
俺は掴み慣れた新島の手を取り、ついでに女に菓子を取られないように紙袋をちょっとだけ雑に取り上げると、先日のように屋上へと足を進めた。
屋上へと足を進めていたが、先日の屋上の暑さを思い出し、屋上に出入りできる踊り場で足を止めた。女たちへの苛立ちもあったからか、それともただ暑いだけかは分からないが俺の手は汗ばんでおり、その若干の恥ずかしさと申し訳なさから俺はゆっくりと新島から手を離し、申し訳なさをアピールしながら声を掛けた。
「……痛くなかったか?」
「は、はい。大丈夫です。せ……先輩こそ大丈夫ですか?」
新島は自分の心配より先に、俺の心配をしてくれているらしい。普段なら俺に近寄ってくる奴らの心配は、本当に心配しているわけではなく、俺と話すための口実に過ぎないが新島の場合は違う。本気で俺のことを心配してくれている。
……人に心配されて悪い気がしなかったのは初めてかもしれない。
俺は少し呼吸を整えてから、屋上は暑いからこの踊り場で続きを食べようと提案をし、ゆっくりと腰を落とす。踊り場の床は思っていた以上に冷たく、下手に教室で食べるよりも快適に食事をすることができるかもしれない。
そんなことを考えていたが、新島はなかなか座ろうとしないので、軽く床を叩き座るように指示を出す。新島が座ったことを確認してから俺たちはまた菓子を食べ進めた。
今思い返してみれば、誰かと昼食を共にするのは本当に久しぶりかもしれない。普段であれば購買でかった総菜パンをパパッと一人で食べ終え、どこかで時間を潰してから教室に戻る。そんな一種のルーティンを続けてきたのだが、今日は新島とその時間を過ごしている。そんな普段とは違う環境に俺自身が少し浮かれていたのかもしれない。
それは新島とLINEを交換したからだ。
「それじゃあ今度僕とカフェとか行きませんか?僕が『お菓子食べませんか?』なんて言ったから、せっかくのお昼でしたのに気分を害されたので……そのお詫びということで……。どうですか?」
新島からカフェに行かないかと提案を受けた。いつもなら無視するか御断りをするのだが、今回の相手は新島だ。こいつはおそらく俺に媚を売るためにこんなことを言ってきているわけじゃないだろう。そう考えて俺はカフェに行くことを了承し、そのまま勢いでLINEまで交換した。
新島はあまり深く考えてないなさそうだったので、俺からLINEの交換提案をしたのだが、俺は初めてこの学校でLINEを交換したかもしれない。
まあ、新島ならいいか。
✂ ——— ✂ ——— ✂ ——— ✂ ——— ✂
日曜日。普段の俺であれば、バイトに行ったりしたり家で勉強や課題に手を付けていることだと思うが、今日は駅に来ている。
新島とカフェに行くためだ。
新島からは控えめな文章でLINEが来たときは思わず笑ってしまったが、俺のことを考えて時間を掛けて考えた文章を送ってくれたと考えると途端に嬉しくなった。
一応服装など気を使った方がいいのだろうかと考えたが、新島といるときは自然体でいることの方が多いことを思い出し、俺はいつも通りの白のTシャツにジーンズというラフな恰好で新島との待ち合わせに向かった。この服装は俺がバイトをするときの格好だ。楽な仕事とはいえ、本の整理などで割と身体を動かすことがあるため、あえて動きやすいラフな恰好でバイトをしている。
待ち合わせ場所に着くと、既に新島がいた。約束の時間より早く着いたと思っていたのだが少し申し訳ないことをしたかもしれない。俺は足早に新島と合流し、そのままカフェへと向かう。
カフェは想像していたものとは異なっており、隠れ家的な場所にあるそんなカフェだった。きっとチェーン店にでも行くのだと思っていたが、そうではなかったらしい。
俺は来たこともない隠れ家のカフェにテンションがあがりながらも、新島にお勧めのメニューを聞く。
「ここは何がおいしいんだ?」
「聞いたところによると、パフェがおいしいらしいです。チョコとイチゴとマンゴーがあるみたいです。」
「そうなんだ。新島はもう何にするか決まってるの?」
「僕はパフェにいいなとは思うんですけど、シンプルにお腹も空いているのでホットサンドでも頼もうかと思ってます。」
「俺もホットサンド食べたい。シェアするか?」
「いいですね!それならパフェも頼んじゃおうかな。先輩はどの味にします?」
「……チョコ。」
「わかりました!」
そう言うと新島は右手を上げ店員を呼び注文をした。新島の右手を見て気になったのだが、湿布は取れているようだった。きっと痛みは引いたのだろうと安心した。
新島の注文から数分後、俺たちのテーブルには予想よりもでかいパフェと帆とサンドであるクロックムッシュが運ばれてきた。ぶっちゃけ腹はかなり減っている。朝食を抜いた自分が悪いのだが、正直カフェが少し楽しみだったことは新島にはナイショだ。
俺は運ばれてきたクロックムッシュをお腹が空いていたこともあり、一口で食べきる勢いで頬張る。流石にこの大きなクロックムッシュを一口で食べきることは出来なかったが、四分の一はすでに俺の胃に納まっている。
新島とご飯を食べるようになって気が付いたが、新島は俺が食事をするときに俺のコトをずっと見ている。
「……また見てる。」
「あ、ご、ごめんなさい。」
「いいけど。新島よく俺の食べるところ見てるよな?もしかして食べ方汚い?」
「そんなことないです!いつも豪快に食べる感じが好きで……ついつい見ちゃうんです。」
「……そ、不快に感じてないならいいや。」
どうやら食べ方が汚くて凝視しているわけではないらしい。少し不安だったが新島がいうならそうなのだろう。俺は続けてクロックムッシュを食べ進める。しかし豪快に食べる感じが好きとはどういうことだろうか。それが気になり今度は俺が新島の食べるところを凝視する。
新島は俺のようにクロックムッシュを口いっぱいに頬張るが、あまりのチーズの量とあまりの分厚さに噛み切れなかったハムがクロックムッシュから一気に零れ落ちる。
そんな姿を見て、俺は思わず微笑んでしまった。
新島は笑われたと勘違いして、両手で持っていたクロックムッシュで顔を覆い隠すが、その姿にかわいさを覚え「もう遅いって」と思わずツッコミを入れてしまった。
俺はきっとどんどん新島といるのが楽しくなっていたんだと思う。
だからこうやって笑えているんだろ思う。
だから俺は少し新島に期待していたのかもしれない。
「新島はさ、俺が弓道辞めた理由知ってる?」
✂ ——— ✂ ——— ✂ ——— ✂ ——— ✂
弓道を始めた理由。
始めた結果どんな扱いをされていたのか。
そしてどうして弓道を辞めるに至ったのか。
そのすべてを新島は質問を交えながら真剣に聞いてくれた。
そして俺の新島への第一印象もここで話した。
最初の印象は最悪だったこと。今はそんなこと思ってないことを。全部話した。
「印象が最悪な奴とカフェとかいかねーだろ。少なくとも今は好印象だよ。そうだな。あえて言うなら弟的なそんな存在かな。」
「お、弟?」
「ん。放っておけない感じ?俺一人っ子だからわかんないけど、弟がいたらこんな感じなのかなって。」
そうだ。新島は俺にとって弟のような存在なんだ。
新島としゃべるのは楽で良いなと思うにも、LINEを交換しても良いと思えるのも全て。
きっと新島が俺にとって弟のような存在だからだ。
それを聞いた新島は徐々に顔が俯き始めた。新島はきっと恥ずかしがり屋だから真っ赤な顔を隠すために俯いているのだろうと考えていた。
「大丈夫か?」
「え、あ、はい!大丈夫です。弟的な存在……嬉しいです!先輩が誰かと仲良くしているところなんて見たことなかったので。そうすると僕は人見先輩の中じゃだいぶ上位に入るくらいの人間ってことですか?」
「……俺、学校じゃ新島以外と喋んねーよ。」
「そうなんですか?」
「他学年だと声を掛けられることはあっても、同学年だとねーな。誰かと学校で昼食食ったりしたのだってそれこそ一年ぶりとかじゃねーかな。」
「それは……光栄ですね。」
「なんだそれ。そういえばこうやって休日家族以外とどこか出かけたりするのは初めてかもな。」
「え!!!!!」
「うるさっ!」
「す、すみません。取り乱しました。」
「いやいいけどさ。そんなに驚くことか?」
「いえ、先輩ならいろんな方とデートとか行かれてるでしょうから、お出かけとかは慣れてるんだと思ってました。」
「デートねぇ……。なら今日の新島とのデートが初デートだな。」
それ見たことか。やっぱり新島はすぐに顔を赤くする。かわいい弟だ。
実際に兄弟のいない俺は、弟とどのように過ごせばいいかは分からないが、もしいたらこんなことをするのだろうかと考えながら、俺は新島に向かって口を大きく開けた。
「あーん、して。」
「え?」
「新島のイチゴのパフェも食べたいから交換しねえ?だからあーんして。」
新島は動揺の末、イチゴパフェを俺に食べさせた。
兄弟なら御返しもするだろうと、俺も自分のチョコパフェを新島に食べさせる。
「んまぁ。」
「……満足そうで何よりです。」
「新島は?美味かったか?」
「は、はい!めちゃくちゃおいしいです!」
「そ、ならいいよ。」
その後イチゴパフェの美味しさと弟へのいたずらに魔が差し、何度か新島のパフェを盗み食いしていたが、案の定新島にはバレていたらしい。
カフェデートの後は、俺の提案で先日新島が助けたお礼にくれたクッキーを購入した店に連れてってもらうことにした。実は新島に貰ったクッキーは最初かなり警戒していたのだが、食べてみると本当に美味かった。そのためどこであのクッキーが買えるのか気になっていたのだ。
店はクッキーだけではなく、紅茶の販売もしているそうで、新島のおすすめを購入することにした。新島に何か買うかと問うと先日俺にくれたクッキーのセットだというのでそれも買った。
「ん。」
「……これって?」
「今日のお礼的なやつ。」
「お、お礼?」
「デートが楽しかったお礼。」
「え、いや、いただけませんよ!お金払います。」
「じゃあ次一緒に行くための対価ってことで。」
新島はほんとに弟のような存在だ。
弟の欲しがっていたものをあげるなんて、本当に兄みたいだ。
✂ ——— ✂ ——— ✂ ——— ✂ ——— ✂
新島とは、あの日のデートを境に関係値が変わった。
まず昼食は基本的に共に過ごすし、放課後は新島と一緒にどこかに寄ったりすることも増えた。
こんなにも楽しい学生生活は初めてかもしれない。
実際俺は心のどこかでこんな生活を夢見ていたし、期待に胸を膨らませていた。今までは俺に近づこうとする女や、俺と仲良くなり女にモテたいとかいう男から誘いを受けることはあったが、それが求めていたものかと言われればそうではない。
もっと本当の友達や恋人といった関係の人とすることに意味があった。それが叶うことはないと思っていたが、それは新島との出会いによって変わっていった。
今日も俺は新島と下校を共にするために、新島の占いが終わるのを待つ。
最初こそ、俺が新島と一緒に帰っていることを目撃した誰かが、噂を広めたようで、始めはそれなりに校内で話題になったようだが、今ではそれが普通になったようで変に勘ぐってくるような輩はいなくなった。
「終わったか?」
「わ!人見先輩!待っててくれたんですか?」
俺は新島の占いが終わるのを待って今日も声をかけた。
今日は占いのお礼として、スタバのギフトカードをもらったようで、一緒にスタバに行くことになった。スタバはしょっちゅう行くわけではないが、バイト前後の時間潰しに少し寄ったりする。常連というわけではないが、ある程度のメニューには心得がある。そんな感じだ。
「流石に暑いな。」
「ですね……。そろそろ夏休みですね。人見先輩は何か予定あるんですか?」
「んー。何度かは学校に行く予定。これでも受験生なんで。」
「あ、そうじゃないですか!どこ受けるんですか?」
「……ナイショ。」
「……ケチだ。」
「冗談だよ。誰にも言ってねーからなあ。」
「そうなんですか?……あぁ、なるほど。そうですよね。」
「まぁ新島には言ってもいいか。」
「え、いいんですか?」
「まぁ……弟だし?」
「……なんすかそれ」
夏休みが近いということもあってか、お互いの予定を確認する。しかし俺は一応受験生なわけでそれとなくそのことを伝えると、意外にも食いついてきた。実を言うと俺は教師以外にはどこの学校を受験するつもりかなど話したことはない。
別に将来の夢を語ることが恥ずかしいとかそういうわけではないのだが、そうベラベラと言いふらすものでもないとも考えている。ぶっちゃけ新島以外の生徒に俺の進学先をうっかり漏らしてしまった場合は次の日には全校生徒が俺の進学先を知ることになるだろう。
しかし新島はそんなことはしない。それだけ信用を置いているのだ。
スタバに着き、注文を進めていく。新島の分も一緒に注文するため、新島にフラペチーノのサイズを確認する。すると新島は「Lサイズ」と回答した。
面白さより驚きが勝ったね。
まさか高校生でスタバのサイズ形式を知らない者がいるなんて思ってもみなかったからだ。
「新島ってもしかしてスタバ初めて?」
「いえ、何度かは来たことはありますよ?」
「……一人で?」
「友達とですけど……。」
「そ。スタバのサイズはSMLじゃないぞ。ショート、トール、ベンティが基本のサイズ構成だ。」
「え?そうなんですか?」
俺はスタバ店内であることを忘れ、馬鹿笑いした。店員も微笑んでいたしまあいいだろう。新島は俺が笑ってしまったことで顔を真っ赤にし、プルプル震えている。きっと恥ずかしさに押しつぶされそうなのだろう。
「はあー。お前かわいいな。笑ってごめんな。驕るから許して。」
「かわっ……。かわいくないですよ!」
「かわいいよ。新島は。」
これは本心だ。
新島はかわいい。これは俺が新島のことを弟のように思っているからだと思う。
注文を済ませ、バニラフラペチーノを受け取り、店内に空いていた席に座る。
俺はバニラフラペチーノを思いきいり吸ったが、出来立てでまだ凍っているのか一切吸うことはできなかった。溶けるのを待っている間、俺は新島に聞いてみたかったことを質問する。
「俺も新島に占ってもらえるの?」
「……え?」
「占いだよ。新島がいつも放課後やってるやつ。あれ俺も占ってほしいんだけど、お菓子とか持ってくればいいわけ?」
「え、人見先輩って占いに興味があるんですか……?てっきり占いなんて興味無いんだと思ってました。」
「んー。そこまで興味は無いよ。でも新島の占いは九十五パーセントの確率で当たるんだろ?そこまで高いんだったら少しは気になるよ。」
おかしい。明らかに新島は動揺している。もしかして何か変なことを言ってしまったのだろうか。しかし思い返してみてもただ単に占ってほしいと言っただけに過ぎない。
俺が少し疑問に思っていると、新島は占いは予約制である旨を伝えてきた。
ならどこで予約ができるのかを聞いたが、現在は先まで予約で埋まっているため予約は受けていないとのことだった。
俺個人としては占ってほしいことがあるわけではないので、別にそれでもいいかと思い、予約ができるようになったら教えてくれとだけ伝えておいた。
✂ ——— ✂ ——— ✂ ——— ✂ ——— ✂
夏休みに入り、俺はバイトと勉強の毎日を送っている。一応すでに滑り止めとして推薦はもらっているのだが、俺としては専門に行きたいと思っているため、推薦は断ろうと思っている。そうなってくると必然的に受験勉強をしなくてはならない。
バイト先である個人経営の古書店は客も来ないため、店長に許可をもらって、店番をしながら参考書を眺めたりしている。
正直身が入らない。
勉強は別に苦ではないのだが、集中ができないのだ。
ここのところ俺はどうかしてしまったのかもしれない。
趣味が瞑想で精神統一であることを自称しているが、それができていない。本来の俺は集中なら誰にも負けない自信があったが今は気になることがずっとあり、一切集中することができない。
原因は新島だ。
新島が今、何をしているのか。そんなことばかり考えてしまう。
きっと今まで休日などで遊んだ経験がほとんどなく、新島に依存してしまっているのだろう。
自己分析はできている。できているが、気になってしまったものはしょうがない。俺は新島に連絡を取るための口実を探すため、バイト終わりにキョロキョロと周りを見渡しながら帰る。
そこで気づいたのだが、今日はどうも人が多い。夏休みのため人が多いことはわかっているがそうではない。浴衣姿の女が多いのだ。——今日は夏祭りか!
これで新島に連絡を取る口実ができた。家に帰り着き自室のベッドで横になりながら新島にどう連絡をしようかと考えるため新島のLINEを開いたところで、タイミングよく新島から連絡がきた。
——気分転換に僕とどこか遊びに行きませんか?
これはお誘いだ。そしてこのタイミング。嬉しくないわけがない。
LINEを続けていると、新島は今日が夏祭りであることを知らずにお誘いをしたらしい。そうなればもっとうれしい。だって夏祭りという口実がなくとも、新島は俺と遊びたいと思ってくれているのだから。
そうとなれば俺はこの嬉しさのお礼をするために、今日は存分に弟を甘やかさなくてはならない。十九時に駅集合という間に合わせの約束を取り付けた。
俺はATMに寄るため、約束の時間より早めに駅に着いたのだが、そこにはすでに新島の姿があった。
「新島?はやくねーか?」
「人見先輩!こんばんは!」
「ん。まだ時間までだいぶあるぞ?」
「いつも先輩を待たせてしまっているので、今日くらいはと思いまして。それに今日はバイト早上がりだったんです。だから時間に余裕が出来てしまいまして……」
やはり新島といると楽しい。まだ祭りの会場にすらたどり着いていないのにすでに楽しい。さっきまで一切集中できなかったのに、今なら集中出来る気がする。
俺はATMでちゃっちゃと現金を引き出し、新島と祭り会場へと向かった。
聞くところによると新島は夏祭りに来るのが初めてらしい。俺もぶっちゃけくるのは初めてだが、ここは兄としてしっかり今日の夏祭りデートをエスコートしなければならない。俺はいつものように新島の手を取り、祭り会場へと向かう。
祭り会場はすでに賑わいを見せており、はぐれないように新島の手を強く握り直す。
新島に好き嫌いはないかと問いかけ、ないと返事をもらったため目に入った屋台を次々に周っていった。両手で持ちきれないほど買い込み、近くの公園のベンチで一息ついた。
他愛もない話をしながら買い込んだご飯を食べ進めていく。話は俺がやりたいことについての話に変わった。新島が言うには俺が今までできなかったことは全部やりましょうとのこと。しかし俺がやりたかったことはすべて新島のおかげで叶えることができている。
それを聞いた新島は嬉しそうにもしたが、反対に少し悲しげな表情もした。きっともっと俺のためにしたいことがあったのだろう。このままでは新島が悲しんでしまうかもしれないと考え、その結果一つやってもらいたいことを思い出した。
占いだ。
新島に占ってほしい。そのことを伝えると、新島の表情はどんどん曇っていった。俺は言葉の選択を間違ってしまったのだと感じた。以前占ってほしい旨を聞いたときは準場があるからと断られたが、おそらくあれは本心ではない。きっと新島は俺を占いたくないのだ。
……なぜだ?
その疑問は俺の中で膨れ上がり、怒りへと変わっていった。
俺はその勢いのまま新島を攻めるように問いかけた。
「俺のこと占うなって誰かに止められてんの?」
「……違います。」
「じゃあ新島の意志で俺を占いたくないってことね。」
「……はい。」
「その理由は教えてくれねーの?」
「……言ってしまったらもう、人見先輩は俺と話してくれなくなります。」
「俺がその理由を聞いたら、俺から新島と距離を置くような、そんな内容なの?」
「……はい。」
「俺の嫌いなコト知ってるよな?」
「こ、心を乱されることです。」
「まさに今、この状況がそうだよ。」
「ごめん……なさい。」
「……今日は夏祭りデートに付き合ってもらってどーも。」
俺はコントロールできない自身の怒りを抑えきれなくなり、新島とのデートを中断して帰路につく。
俺は最低だと思う。自分から占ってほしいなんて聞いておいて、いざ占いを断られただけでこんな態度を取るなんて。
本当は前から気づいていたんだ。俺の新島に対する気持ちに。これは弟に向けるような気持ちではない。俺が自分の気持ちに気づきたくなくて、そんな気持ちを上書きするためについたのが新島は弟のような存在であるという嘘だ。
わかっていた。自分がなぜ新島といるとこんなにも楽しいのか。なぜ新島のことを考えてしまうのか。全部わかっていた。
この怒りも新島が占ってくれなかったことに対するものじゃない。これは”嫉妬”だ。
新島に占ってもらったやつが羨ましい。それなのに俺は占ってもらえない。嫉妬で狂いそうになる。それが今表に出てしまった。
俺は最低だ。
新島………………好きだ。
✂ ——— ✂ ——— ✂ ——— ✂ ——— ✂
夏休みが終わり、新学期が始まり二週間が経過していた。
あの一件以来、俺は新島と連絡を取っていない。
本来であれば俺が素直に謝罪をするべきなのだが、俺にはその勇気がなかった。ほんとにしょうもない。さっさと謝ってまた一緒に昼食を取りたいし、下校時も一緒に帰りたい。
自分の不甲斐なさに、もっと自分が嫌いになっていく。
俺は大きなため息を吐きながら、教室の隅で一人、机に顔を伏せながら休み時間が終わるのを待っていた。
「ねぇ、占い師の話聞いた?」
「聞いた!あれでしょ。占いが全く当たらなくなったってやつ!」
「そうそう!高校最後に占ってもらおうと思ってたけど、辞めとこうかなー。」
「うわ薄情じゃん。でももともとは九十五パーセントの確率で当たってたんでしょ?最近何かあったんじゃない?」
「どうなんだろうね。あ、でも挙動不審だったって聞いたよ?」
「挙動不審?なにそれ?」
「なんか、なにかに怯えてるっていうか?」
「え、大丈夫なんそれ?」
「わかんない。今度差し入れでも持っていってあげる?」
「いいね。ついでに占ってもらお!」
「結局占ってほしいんじゃん!」
「バレたか……」
盗み聴くつもりはなかったが、聞こえてしまったものはしょうがない。
しかし今はそんなことはどうでもいい。
新島の占いが当たらなくなった?いつも何かに怯えている?
どういうことだ?今すぐ新島に会って確認したい。新島が困っているなら助けたい。
でも俺にはその資格はない。
俺は机に伏せた状態で小さく「くそっ……」と呟いた。