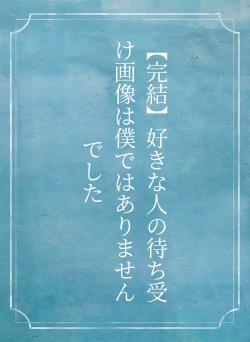夏休みに入り、毎日ではないものの僕と人見先輩は変わらず連絡を取り合っていた。人見先輩は受験勉強で忙しいのか前ほど時間に余裕がないようで、今のところ夏休み前に約束していた一緒に遊びに行こうといこうというのが実現できないでいた。
しかし、それでもお互いに学校のある日が被ったりすると下校時は一緒に帰って、先日のようにスタバに寄ったり、駅のクッキー屋さんに寄ったりとそれなりに充実した時間を過ごしていた。
また僕にはもう一つ夏休みが充実していると実感できる理由があった。
「爽≪そう≫くんがいてくれて助かるわ。あ、次はこっちの資料室の整理をお願いできるかした。」
「そういってもらえると嬉しいです。ありがとうございます。資料室の整理ですね。分かりました!やっておきますね。」
それは夏休み期間中限定で始めたアルバイトだ。
アルバイトは担任でもあり顧問でもある澤村先生が紹介してくれたもので、心理カウンセラーとしての労働はできないが、それを間近で見ることができるというもので、澤村先生の知り合いが運営しているという会社に常駐しているという産業カウンセラーさんの元で様々な経験ができるというものであった。
お給料は高校生ということもあってか、最低賃金での勤務となり正直物足りなさは感じているが、それと同時に高校生の自分が将来就きたい職業に近い、産業カウンセラーさんの元で学ばせてもらえる機会はほとんどゼロに等しく、このような体験をさせてもらえている環境に感謝をしていた。
僕は産業カウンセラーの海野さんに言われた通り、資料室へ向かい書類の整理を行う。
カウンセラーということもあってか、取り扱い情報はほぼすべてが個人情報につながるようなモノのため取り扱いには注意しながら作業を進めていく。
アルバイト初日はそういった個人情報の観点からか、いろんな書類にサインを書かされたことを今でも覚えている。一日の内に自分の名前をあんなにも書いたのは入学式で配布された教科書に名前を書いたとき以来だ。
そんなことを思い出しながら書類の整理を行っていると、海野さんが声を掛けてきた。
「爽くんは学校がない日はって言っていつも手伝いに来てくれてるけど、学生の本業は学ぶことと遊ぶことよ?どこかにお出かけしたりしないの?」
「あー……。予定が無いわけではないんですが、まだその日程が決まってなくて。」
「あら。どこに行く予定?」
「実はそれもまだ決まってなくてですね……。」
それを聞いた海野さんは少し困惑したような表情を浮かべた後、僕を少し叱るような声のトーンで話し始めた。
「決まってないって、それ、爽くんから連絡した?」
「いえ……相手はその、受験生でして……。連絡頻度は落とした方がいいかと思いまして。」
「受験生ね……。それならなおさら爽くんから連絡入れなさい!受験勉強は大事だけど、めり込み過ぎると、自分でもどのタイミングで辞めたらいいかとか分からなくなるの。そうなる前に、爽くんから連絡して相手さんの気分転換の相手をしてあげなさい!」
「わ、分かりました。」
「ならよし!じゃあ今すぐ連絡して。」
「え?今ですか?」
「何よ。善は急げよ?」
「そうかもですが……。」
「爽くんが送らないなら、私が送るけど?」
「止めてくださいよ!自分で送りますから!」
僕は渋々ポケットからスマホを取り出し、LINEを起動する。当然のようにトーク欄の一番上には人見先輩のアイコンがあり、それをタップして送る文章を考える。
人見先輩には行きたいところをピックアップしておけと言われていたが、正直人見先輩とどこかに遊びに行けるだけで十分な僕はそれを怠っていたため、すぐに遊びに行きたいところが思いつかない。
そんな僕に痺れを切らしたのか、見かねた海野さんが「遊びに行くなら基本室内にすること。祭りとか夜のイベントであれば野外でも良いけど」とアドバイスをくれた。僕はくれたアドバイスに従って、人見先輩にメッセージを送る。
【新島】:人見先輩、こんにちは!
【新島】:勉強の進み具合はいかがですか?
【新島】:気分転換に僕とどこか遊びに行きませんか?
僕がLINEを送るとすぐに返信が来た。
【人見】:おつかれ
【人見】:勉強は進んでない
【人見】:新島は今どこ?
【新島】:今はバイト先に来てます
【人見】:そういやバイトするとか言ってたな
【人見】:夜とか空いてるか?
【新島】:空いてます!
【新島】:行きたいところあるんですか?
【人見】:今日夏祭りな
【人見】:十九時に駅集合ね
【新島】:え!今日夏祭りなんですか?
【人見】:知らなかったのか?
【新島】:お恥ずかしながら……
【人見】:知ってて今日連絡してきたんだと思ってたわ
【人見】:まあいいわ。とりあえず十九時に駅集合な
【人見】:じゃ
僕は人見先輩から送られてきたLINEをみて、反射的に海野さんの方を見る。そこには二ヤつきながら僕を見る海野さんの姿があった。きっと海野さんは今日夏祭りが行われることを知っていたのだろう。急に遊びに行かないのか?と聞いてきたり、善は急げとか言って人見先輩へ送るLINEの催促をしたりとした理由はこれだったのかと、少ししてやられた気分だ。
「今日が夏祭りだって知ってましたね?」
「何のことかなー?それで今日はその夏祭りに行くの?」
「……たった今行くことになりました。」
「良かったじゃない!なら今日はもうあがっていいわよ。」
「え?」
「何時からなの?」
「十九時に駅集合です……。」
「じゃあ尚更あがっていいわよ。浴衣着るのは意外と時間かかるものよ。」
「いやいや!僕浴衣とか持ってませんから。」
僕のその発言に海野さんは大層困惑した表情を浮かべていた。おそらくは浴衣を持っていないことへの驚きだろう。しかしながら浴衣を持っていないのは事実である。そもそも女子高校生は兎も角、男子高校生が浴衣を持っているなんて、そんなアニメやマンガの中の話だ。いや持っている人は一定数いるかも知れないが、一般家庭の出で浴衣を持っている男子高校生は珍しい部類だろう。
「イマドキの男子高校生は浴衣なんて持ってませんよ。女性なら兎も角男子高校生で持ってる人は少ないんじゃないですか?」
「えー、持ってないの?爽くんの浴衣姿見たかったなー。」
「持ってたとしても海野さんには見せませんよ。」
「私のおかげでデートにいけるようになったのに?」
「デートってそんなんじゃないですよ。ただ遊びに行くだけです……。」
「その割にはすごく嬉しそうだけど?」
海野さんの職業をすっかり忘れていたが、彼女は産業カウンセラー。心理学においてはプロフェッショナルなのだ。そんな海野さんに僕が勝てるわけもなく、彼女の手のひらで転がされていたにすぎない。
僕はその悔しさと恥ずかしさに、顔が徐々に熱くなっていく。
「で、デートですよ!」
「はい、よろしい。」
僕はきっとこの先、海野さんに勝てることは無いのだろう。
✂ ——— ✂ ——— ✂ ——— ✂ ——— ✂
本当にバイトを早上がりさせてもらえた僕は一度家に帰り、動きやすくそして涼し目な服装に着替えてから駅へと向かった。
今までは夏祭りがあったとしても、実は行くことはなかった。友達から誘われることは何度かあったが、正直にお金がないからと断っていた。しかし今年の夏休みはアルバイトをしている。さらに言えばなんと海野さんが「私の分まで楽しんできなさい!」と二千円を握らせてくれた。
さすがにと思って断ったのだが、「じゃあ澤村先生に爽くんがデート行ってましたって報告しておくね」という謎の脅しを掛けられたため、渋々二千円を受け取る羽目になった。
「新島?はやくねーか?」
「人見先輩!こんばんは!」
「ん。まだ時間までだいぶあるぞ?」
「いつも先輩を待たせてしまっているので、今日くらいはと思いまして。それに今日はバイト早上がりだったんです。だから時間に余裕が出来てしまいまして……」
現在の時刻は十八時二十八分。約束の時間まではあと三十分以上も残っていた。
「と、いうかそれは先輩もですよ!まだ約束の時間まで三十分以上もありますよ?」
「……いや俺は駅のATMでお金下ろそうと思って早く来ただけ。」
「ATM……僕なんてこの間両親から自分の口座があることを聞かされたばっかりなのに。」
「まぁ親が定期預金とかしてくれてる家庭あるって聞くもんな。それにバイトも始めたんだし、今後使う機会も増えるからいい機会じゃねーか。」
「そうなんですけど……。え、先輩ってアルバイトとかしたことあるんですか?ずっと部活されてましたよね?」
「部活引退してからは、何度かやったぞ。まぁ全部手伝いって感じだったけどな。」
「そうなんですね。知らなかったです!」
「ま、誰にも言ったことなかったしな。」
人見先輩はそう言うと、「ちょっとここで待ってろ」と告げ、駅構内にあるコンビニに行きATMでお金を下ろしに行った。
そんな人見先輩の後ろ姿を目で追いかけながら僕の顔は先ほど海野さんに言い負かされたとき以上に熱くなっていた。
(待て待て待て待て待て!人見先輩最近おかしくないか?僕のコトをかわいいっていったり、誰にも言ってないって言ってたバイトをしていたことや進学のことも僕には教えてくれた……。人見先輩は本当に僕のことを弟としか見てないのだろうか?)
「お待たせ。行こうか。」
「え、あ、はい!よろしくお願いします!」
「なんだそれ。祭りで何か食いたいもん決まってんの?」
「実は夏祭り来るの初めてでして……。何売ってるか知らないです。」
「マジか?」
「お恥ずかしながら……。」
「……そ。なら今日のデートは俺がエスコートしねーとな。」
そんなことをなんてことない顔で言ってくるこの人は本当にずるいと思う。実は人見先輩は僕の気持ちを知ってて、揶揄かっているんじゃないかとすら思えてくる。実は前にも同じようなことを思ったのだが、今回はその比じゃない。
うれしい気持ちの反面、恥ずかしさがこみあげてくる。
しかし人見先輩は僕がどう思っているかなどお構いなしに、僕の手を取りお祭り会場へと足を進めた。手を取られ更に動揺していると「人混みすげーから、はぐれないよーにな」と微笑みながら語りかけてきた。その笑顔は本当に嬉しそうで、きっと人見先輩はこのお祭りを楽しみにしていたのかもしれない。そんなことを思いながら僕は手を引かれるまま人見先輩の後をついていった。
お祭り会場は駅からさほど離れてはおらず、時間にして十分ほどで着くことができた。会場は既に賑わっており、多くの人で溢れかえっていた。
人見先輩はというと、会場に着いても僕の手を話すことはなく子どものように目を輝かせながら「新島は食べれないものはあるか?」と質問され「無いです」と回答。人見先輩はその回答を待っていたかのように、手を引く勢いが強くなった。
たこ焼きや焼きそば、箸巻きにリンゴ飴とお祭りの定番中の定番に加え、炭火焼や餃子、わたあめにチョコバナナなど、両手では持ちきれないほどの大量の食べ物を人見先輩に連れられるがまま買い込んだ。
一番驚いたことは、買い込んだ量もさることながら、会計は全て人見先輩が支払ってくれたことだ。「僕も払います」と言ったのだが、「新島の今日の仕事は俺から離れないことと食材持ちな!」といって聞く耳をもってもらえなかった。
しかし「俺から離れるな」という人見先輩の言葉に、その嬉しさからか思わず口角があがってしまった。
「めちゃくちゃ買いましたね。これ食べきれるんですか?」
「ん。食べきる。」
「すごいですね……。重すぎて、僕の両手千切れそうですよ。」
「なんだそれ。てか新島もコレ食べるんだからな。」
「いや、二人でもこの量は厳しくないですか?」
「絶対食う。」
買い込みが終わると、お祭り会場から少し離れたところにある公園のベンチに二人で座り、買い込んだものを一緒に食べることになった。
僕の左手はたくさんの袋を握っていたせいか、真っ赤になっており、それを見た人見先輩は「流石に買いすぎたか?」と少し申し訳なさそうにしながら微笑んだ。
「それにしても意外でした。人見先輩もお祭りになるとテンションあがるんですね。」
その問いかけに対し、人見先輩は焼きそばを頬張りながら、少し恥ずかしそうに答えた。
「……俺もさ。実は祭り初めてなんだよね。」
「え?そうなんですか?」
「いや、正確に言えば来たことはあるんだけどこうやって買って食べるのは初めて。」
「……意外です。先輩モテるしきっと彼女さんとかと来たことあるんだと思っていました。」
「俺、彼女いたことないよ。」
「いや、それは嘘「嘘じゃねーよ」」
人見先輩は僕が言い終わる前に、被せるようにして彼女がいたことを否定した。
そこまで否定するということは本当のことなのだろう。しかしあんなにもモテる人見先輩がお祭りが初めてというのがどういうことなのだろうか。
そんなことを疑問に思っていると、人見先輩はゆっくりと自分の話をしてくれた。
「……俺さ、自分で言いたくないけど、割とモテる方だろ?ほぼ毎日告白されてた時期があったからさ、嫌でも自覚するよ。でも前にそういうのが嫌いって話しただろ?気分的には最悪だよ。それもさ告白だけじゃないんだよね。」
「どういうことですか?」
「『思い出だけでいいので、祭りに一緒にいきませんか?』だって。もちろん断ったよ。でも断った祭りに俺が行ってるとするだろ?そうすると女って俺を囲んで『一日でいいんだからデートくらいしてあげなよ』だってさ。俺は自分の好きなように祭りを楽しむことすらできないんだと思ったよ。」
そう語る人見先輩は悲しげな表情で、でもそれを感じさせないようにまた焼きそばを口いっぱいに頬張る。それを食べ終えると次は大きく口を開けて、僕の方を向いた。
「あ!」
「え?」
「たこ焼きくれ」
「あ、はい!」
そういって僕は人見先輩の口元にたこ焼きを運ぶ。それを本当においしそうに先輩は食べる。
「だからさ。今日新島から連絡がきて本当に嬉しかった。俺返信早かっただろ?」
「はい……びっくりしました。」
「それな俺が新島を祭りに誘おうとしたタイミングで新島から連絡が来たからなんだよ。」
「えっ!」
その回答は僕は予想もしていなかったものだった。確かに返信が早いとは思ったが、僕に連絡しようとしていたとは思っていなかった。それと同時に人見先輩には本当に友人と呼べるような人がいないのだと悟った。
「……人見先輩!もっと楽しみましょう!」
「ん?」
「今までできなかったこと全部しましょ!手伝います!」
「お、おう……。でもまぁ新島のおかげでほぼ叶ったぞ?」
「……え?」
「昼食一緒に食ったり、放課後買い食いしたり、こうやって夏祭りデートしたり。俺がやりたかったことはほぼほぼ新島と一緒にいることで叶ったかな。」
「そ、そうですか……。それは良かったです。」
それは本当に良かった。良かったのだが、これ以上僕が人見先輩にしてやれることはないということだ。それはそれでさみしい。きっと人見先輩はそこまで深く考えずに発言したのだろうが、僕にとってはひどく心を痛めるような内容だった。
しかし人見先輩は思い出したかのように告げた。
「あ、あるわ。新島にやってほしいこと。」
「ほ、本当ですか?」
「ん。」
「なんですか?僕先輩のために頑張りますよ。」
「占い。」
「…………………………え?」
「占いだよ。新島やってほしいこと。」
「あっ……。」
夏休みに入り、すっかり忘れていたが人見先輩は僕に占いをしてほしいと言ってきたことがあった。そのときは予約だの、順番があるだの言い訳を並べて回避したが、今はそうもいかない。
「夏休み中でも順番守らないとダメか?」
「いや、えっと……。」
「もしかして、俺のこと占いたくない?」
「そ、そんなことは……無い……です。」
「じゃあ今占ってよ。」
「い、今はタロットカード持ってないので……。」
「じゃあ持ってたら占ってた?」
「それは……。」
先ほどまで上機嫌だった人見先輩の声のトーンがだんだんと低くなっていくのが分かる。これはきっと怒っているわけじゃない。不安なときの声のトーンだ。
「俺は新島と仲良いと思ってたけど、新島は違ったわけ?」
「違います!」
「じゃあ何?どうして占ってくれねーの?」
「それは……えっと……その……。」
言えない。言えるわけがない。僕が先輩のコトが好きで、もし先輩の占いたいコトが恋愛だった場合、僕は素直に占うことができないからだと。そんなこと言えるわけがない。
ただ座っているだけなのに、息が上がっていく。
「ひ、人見先輩は何を占ってほしいんですか?」
「……それが新島が俺を占ってくれないことと関係あんの?」
「………………。」
「無言は肯定と受け取るぞ?」
「…………………………。」
「そ。」
人見先輩はそれだけ言うと立ち上がった。そのままゆっくりと歩みを進め公園の中央で立ち止まる。ゆっくりと振り返り、僕に質問する。
「俺のこと占うなって誰かに止められてんの?」
「……違います。」
「じゃあ新島の意志で俺を占いたくないってことね。」
「……はい。」
「その理由は教えてくれねーの?」
「……言ってしまったらもう、人見先輩は俺と話してくれなくなります。」
「俺がその理由を聞いたら、俺から新島と距離を置くような、そんな内容なの?」
「……はい。」
「俺の嫌いなコト知ってるよな?」
「こ、心を乱されることです。」
「まさに今、この状況がそうだよ。」
「ごめん……なさい。」
「……今日は夏祭りデートに付き合ってもらってどーも。」
人見先輩は先ほどまでの僕に歩幅を合わせてくれていた時とは違って、大股でズカズカと大きな音を立てながら一人で公園から出て行った。
人見先輩の後ろ姿が見えなくなるまで、僕はその後ろ姿をただ眺めることしかできなかった。公園にはすすり泣く僕の声と、一人では到底食べきることのできないたくさんの食べ物が鎮座していた。
今日は月が見えそうにない。
しかし、それでもお互いに学校のある日が被ったりすると下校時は一緒に帰って、先日のようにスタバに寄ったり、駅のクッキー屋さんに寄ったりとそれなりに充実した時間を過ごしていた。
また僕にはもう一つ夏休みが充実していると実感できる理由があった。
「爽≪そう≫くんがいてくれて助かるわ。あ、次はこっちの資料室の整理をお願いできるかした。」
「そういってもらえると嬉しいです。ありがとうございます。資料室の整理ですね。分かりました!やっておきますね。」
それは夏休み期間中限定で始めたアルバイトだ。
アルバイトは担任でもあり顧問でもある澤村先生が紹介してくれたもので、心理カウンセラーとしての労働はできないが、それを間近で見ることができるというもので、澤村先生の知り合いが運営しているという会社に常駐しているという産業カウンセラーさんの元で様々な経験ができるというものであった。
お給料は高校生ということもあってか、最低賃金での勤務となり正直物足りなさは感じているが、それと同時に高校生の自分が将来就きたい職業に近い、産業カウンセラーさんの元で学ばせてもらえる機会はほとんどゼロに等しく、このような体験をさせてもらえている環境に感謝をしていた。
僕は産業カウンセラーの海野さんに言われた通り、資料室へ向かい書類の整理を行う。
カウンセラーということもあってか、取り扱い情報はほぼすべてが個人情報につながるようなモノのため取り扱いには注意しながら作業を進めていく。
アルバイト初日はそういった個人情報の観点からか、いろんな書類にサインを書かされたことを今でも覚えている。一日の内に自分の名前をあんなにも書いたのは入学式で配布された教科書に名前を書いたとき以来だ。
そんなことを思い出しながら書類の整理を行っていると、海野さんが声を掛けてきた。
「爽くんは学校がない日はって言っていつも手伝いに来てくれてるけど、学生の本業は学ぶことと遊ぶことよ?どこかにお出かけしたりしないの?」
「あー……。予定が無いわけではないんですが、まだその日程が決まってなくて。」
「あら。どこに行く予定?」
「実はそれもまだ決まってなくてですね……。」
それを聞いた海野さんは少し困惑したような表情を浮かべた後、僕を少し叱るような声のトーンで話し始めた。
「決まってないって、それ、爽くんから連絡した?」
「いえ……相手はその、受験生でして……。連絡頻度は落とした方がいいかと思いまして。」
「受験生ね……。それならなおさら爽くんから連絡入れなさい!受験勉強は大事だけど、めり込み過ぎると、自分でもどのタイミングで辞めたらいいかとか分からなくなるの。そうなる前に、爽くんから連絡して相手さんの気分転換の相手をしてあげなさい!」
「わ、分かりました。」
「ならよし!じゃあ今すぐ連絡して。」
「え?今ですか?」
「何よ。善は急げよ?」
「そうかもですが……。」
「爽くんが送らないなら、私が送るけど?」
「止めてくださいよ!自分で送りますから!」
僕は渋々ポケットからスマホを取り出し、LINEを起動する。当然のようにトーク欄の一番上には人見先輩のアイコンがあり、それをタップして送る文章を考える。
人見先輩には行きたいところをピックアップしておけと言われていたが、正直人見先輩とどこかに遊びに行けるだけで十分な僕はそれを怠っていたため、すぐに遊びに行きたいところが思いつかない。
そんな僕に痺れを切らしたのか、見かねた海野さんが「遊びに行くなら基本室内にすること。祭りとか夜のイベントであれば野外でも良いけど」とアドバイスをくれた。僕はくれたアドバイスに従って、人見先輩にメッセージを送る。
【新島】:人見先輩、こんにちは!
【新島】:勉強の進み具合はいかがですか?
【新島】:気分転換に僕とどこか遊びに行きませんか?
僕がLINEを送るとすぐに返信が来た。
【人見】:おつかれ
【人見】:勉強は進んでない
【人見】:新島は今どこ?
【新島】:今はバイト先に来てます
【人見】:そういやバイトするとか言ってたな
【人見】:夜とか空いてるか?
【新島】:空いてます!
【新島】:行きたいところあるんですか?
【人見】:今日夏祭りな
【人見】:十九時に駅集合ね
【新島】:え!今日夏祭りなんですか?
【人見】:知らなかったのか?
【新島】:お恥ずかしながら……
【人見】:知ってて今日連絡してきたんだと思ってたわ
【人見】:まあいいわ。とりあえず十九時に駅集合な
【人見】:じゃ
僕は人見先輩から送られてきたLINEをみて、反射的に海野さんの方を見る。そこには二ヤつきながら僕を見る海野さんの姿があった。きっと海野さんは今日夏祭りが行われることを知っていたのだろう。急に遊びに行かないのか?と聞いてきたり、善は急げとか言って人見先輩へ送るLINEの催促をしたりとした理由はこれだったのかと、少ししてやられた気分だ。
「今日が夏祭りだって知ってましたね?」
「何のことかなー?それで今日はその夏祭りに行くの?」
「……たった今行くことになりました。」
「良かったじゃない!なら今日はもうあがっていいわよ。」
「え?」
「何時からなの?」
「十九時に駅集合です……。」
「じゃあ尚更あがっていいわよ。浴衣着るのは意外と時間かかるものよ。」
「いやいや!僕浴衣とか持ってませんから。」
僕のその発言に海野さんは大層困惑した表情を浮かべていた。おそらくは浴衣を持っていないことへの驚きだろう。しかしながら浴衣を持っていないのは事実である。そもそも女子高校生は兎も角、男子高校生が浴衣を持っているなんて、そんなアニメやマンガの中の話だ。いや持っている人は一定数いるかも知れないが、一般家庭の出で浴衣を持っている男子高校生は珍しい部類だろう。
「イマドキの男子高校生は浴衣なんて持ってませんよ。女性なら兎も角男子高校生で持ってる人は少ないんじゃないですか?」
「えー、持ってないの?爽くんの浴衣姿見たかったなー。」
「持ってたとしても海野さんには見せませんよ。」
「私のおかげでデートにいけるようになったのに?」
「デートってそんなんじゃないですよ。ただ遊びに行くだけです……。」
「その割にはすごく嬉しそうだけど?」
海野さんの職業をすっかり忘れていたが、彼女は産業カウンセラー。心理学においてはプロフェッショナルなのだ。そんな海野さんに僕が勝てるわけもなく、彼女の手のひらで転がされていたにすぎない。
僕はその悔しさと恥ずかしさに、顔が徐々に熱くなっていく。
「で、デートですよ!」
「はい、よろしい。」
僕はきっとこの先、海野さんに勝てることは無いのだろう。
✂ ——— ✂ ——— ✂ ——— ✂ ——— ✂
本当にバイトを早上がりさせてもらえた僕は一度家に帰り、動きやすくそして涼し目な服装に着替えてから駅へと向かった。
今までは夏祭りがあったとしても、実は行くことはなかった。友達から誘われることは何度かあったが、正直にお金がないからと断っていた。しかし今年の夏休みはアルバイトをしている。さらに言えばなんと海野さんが「私の分まで楽しんできなさい!」と二千円を握らせてくれた。
さすがにと思って断ったのだが、「じゃあ澤村先生に爽くんがデート行ってましたって報告しておくね」という謎の脅しを掛けられたため、渋々二千円を受け取る羽目になった。
「新島?はやくねーか?」
「人見先輩!こんばんは!」
「ん。まだ時間までだいぶあるぞ?」
「いつも先輩を待たせてしまっているので、今日くらいはと思いまして。それに今日はバイト早上がりだったんです。だから時間に余裕が出来てしまいまして……」
現在の時刻は十八時二十八分。約束の時間まではあと三十分以上も残っていた。
「と、いうかそれは先輩もですよ!まだ約束の時間まで三十分以上もありますよ?」
「……いや俺は駅のATMでお金下ろそうと思って早く来ただけ。」
「ATM……僕なんてこの間両親から自分の口座があることを聞かされたばっかりなのに。」
「まぁ親が定期預金とかしてくれてる家庭あるって聞くもんな。それにバイトも始めたんだし、今後使う機会も増えるからいい機会じゃねーか。」
「そうなんですけど……。え、先輩ってアルバイトとかしたことあるんですか?ずっと部活されてましたよね?」
「部活引退してからは、何度かやったぞ。まぁ全部手伝いって感じだったけどな。」
「そうなんですね。知らなかったです!」
「ま、誰にも言ったことなかったしな。」
人見先輩はそう言うと、「ちょっとここで待ってろ」と告げ、駅構内にあるコンビニに行きATMでお金を下ろしに行った。
そんな人見先輩の後ろ姿を目で追いかけながら僕の顔は先ほど海野さんに言い負かされたとき以上に熱くなっていた。
(待て待て待て待て待て!人見先輩最近おかしくないか?僕のコトをかわいいっていったり、誰にも言ってないって言ってたバイトをしていたことや進学のことも僕には教えてくれた……。人見先輩は本当に僕のことを弟としか見てないのだろうか?)
「お待たせ。行こうか。」
「え、あ、はい!よろしくお願いします!」
「なんだそれ。祭りで何か食いたいもん決まってんの?」
「実は夏祭り来るの初めてでして……。何売ってるか知らないです。」
「マジか?」
「お恥ずかしながら……。」
「……そ。なら今日のデートは俺がエスコートしねーとな。」
そんなことをなんてことない顔で言ってくるこの人は本当にずるいと思う。実は人見先輩は僕の気持ちを知ってて、揶揄かっているんじゃないかとすら思えてくる。実は前にも同じようなことを思ったのだが、今回はその比じゃない。
うれしい気持ちの反面、恥ずかしさがこみあげてくる。
しかし人見先輩は僕がどう思っているかなどお構いなしに、僕の手を取りお祭り会場へと足を進めた。手を取られ更に動揺していると「人混みすげーから、はぐれないよーにな」と微笑みながら語りかけてきた。その笑顔は本当に嬉しそうで、きっと人見先輩はこのお祭りを楽しみにしていたのかもしれない。そんなことを思いながら僕は手を引かれるまま人見先輩の後をついていった。
お祭り会場は駅からさほど離れてはおらず、時間にして十分ほどで着くことができた。会場は既に賑わっており、多くの人で溢れかえっていた。
人見先輩はというと、会場に着いても僕の手を話すことはなく子どものように目を輝かせながら「新島は食べれないものはあるか?」と質問され「無いです」と回答。人見先輩はその回答を待っていたかのように、手を引く勢いが強くなった。
たこ焼きや焼きそば、箸巻きにリンゴ飴とお祭りの定番中の定番に加え、炭火焼や餃子、わたあめにチョコバナナなど、両手では持ちきれないほどの大量の食べ物を人見先輩に連れられるがまま買い込んだ。
一番驚いたことは、買い込んだ量もさることながら、会計は全て人見先輩が支払ってくれたことだ。「僕も払います」と言ったのだが、「新島の今日の仕事は俺から離れないことと食材持ちな!」といって聞く耳をもってもらえなかった。
しかし「俺から離れるな」という人見先輩の言葉に、その嬉しさからか思わず口角があがってしまった。
「めちゃくちゃ買いましたね。これ食べきれるんですか?」
「ん。食べきる。」
「すごいですね……。重すぎて、僕の両手千切れそうですよ。」
「なんだそれ。てか新島もコレ食べるんだからな。」
「いや、二人でもこの量は厳しくないですか?」
「絶対食う。」
買い込みが終わると、お祭り会場から少し離れたところにある公園のベンチに二人で座り、買い込んだものを一緒に食べることになった。
僕の左手はたくさんの袋を握っていたせいか、真っ赤になっており、それを見た人見先輩は「流石に買いすぎたか?」と少し申し訳なさそうにしながら微笑んだ。
「それにしても意外でした。人見先輩もお祭りになるとテンションあがるんですね。」
その問いかけに対し、人見先輩は焼きそばを頬張りながら、少し恥ずかしそうに答えた。
「……俺もさ。実は祭り初めてなんだよね。」
「え?そうなんですか?」
「いや、正確に言えば来たことはあるんだけどこうやって買って食べるのは初めて。」
「……意外です。先輩モテるしきっと彼女さんとかと来たことあるんだと思っていました。」
「俺、彼女いたことないよ。」
「いや、それは嘘「嘘じゃねーよ」」
人見先輩は僕が言い終わる前に、被せるようにして彼女がいたことを否定した。
そこまで否定するということは本当のことなのだろう。しかしあんなにもモテる人見先輩がお祭りが初めてというのがどういうことなのだろうか。
そんなことを疑問に思っていると、人見先輩はゆっくりと自分の話をしてくれた。
「……俺さ、自分で言いたくないけど、割とモテる方だろ?ほぼ毎日告白されてた時期があったからさ、嫌でも自覚するよ。でも前にそういうのが嫌いって話しただろ?気分的には最悪だよ。それもさ告白だけじゃないんだよね。」
「どういうことですか?」
「『思い出だけでいいので、祭りに一緒にいきませんか?』だって。もちろん断ったよ。でも断った祭りに俺が行ってるとするだろ?そうすると女って俺を囲んで『一日でいいんだからデートくらいしてあげなよ』だってさ。俺は自分の好きなように祭りを楽しむことすらできないんだと思ったよ。」
そう語る人見先輩は悲しげな表情で、でもそれを感じさせないようにまた焼きそばを口いっぱいに頬張る。それを食べ終えると次は大きく口を開けて、僕の方を向いた。
「あ!」
「え?」
「たこ焼きくれ」
「あ、はい!」
そういって僕は人見先輩の口元にたこ焼きを運ぶ。それを本当においしそうに先輩は食べる。
「だからさ。今日新島から連絡がきて本当に嬉しかった。俺返信早かっただろ?」
「はい……びっくりしました。」
「それな俺が新島を祭りに誘おうとしたタイミングで新島から連絡が来たからなんだよ。」
「えっ!」
その回答は僕は予想もしていなかったものだった。確かに返信が早いとは思ったが、僕に連絡しようとしていたとは思っていなかった。それと同時に人見先輩には本当に友人と呼べるような人がいないのだと悟った。
「……人見先輩!もっと楽しみましょう!」
「ん?」
「今までできなかったこと全部しましょ!手伝います!」
「お、おう……。でもまぁ新島のおかげでほぼ叶ったぞ?」
「……え?」
「昼食一緒に食ったり、放課後買い食いしたり、こうやって夏祭りデートしたり。俺がやりたかったことはほぼほぼ新島と一緒にいることで叶ったかな。」
「そ、そうですか……。それは良かったです。」
それは本当に良かった。良かったのだが、これ以上僕が人見先輩にしてやれることはないということだ。それはそれでさみしい。きっと人見先輩はそこまで深く考えずに発言したのだろうが、僕にとってはひどく心を痛めるような内容だった。
しかし人見先輩は思い出したかのように告げた。
「あ、あるわ。新島にやってほしいこと。」
「ほ、本当ですか?」
「ん。」
「なんですか?僕先輩のために頑張りますよ。」
「占い。」
「…………………………え?」
「占いだよ。新島やってほしいこと。」
「あっ……。」
夏休みに入り、すっかり忘れていたが人見先輩は僕に占いをしてほしいと言ってきたことがあった。そのときは予約だの、順番があるだの言い訳を並べて回避したが、今はそうもいかない。
「夏休み中でも順番守らないとダメか?」
「いや、えっと……。」
「もしかして、俺のこと占いたくない?」
「そ、そんなことは……無い……です。」
「じゃあ今占ってよ。」
「い、今はタロットカード持ってないので……。」
「じゃあ持ってたら占ってた?」
「それは……。」
先ほどまで上機嫌だった人見先輩の声のトーンがだんだんと低くなっていくのが分かる。これはきっと怒っているわけじゃない。不安なときの声のトーンだ。
「俺は新島と仲良いと思ってたけど、新島は違ったわけ?」
「違います!」
「じゃあ何?どうして占ってくれねーの?」
「それは……えっと……その……。」
言えない。言えるわけがない。僕が先輩のコトが好きで、もし先輩の占いたいコトが恋愛だった場合、僕は素直に占うことができないからだと。そんなこと言えるわけがない。
ただ座っているだけなのに、息が上がっていく。
「ひ、人見先輩は何を占ってほしいんですか?」
「……それが新島が俺を占ってくれないことと関係あんの?」
「………………。」
「無言は肯定と受け取るぞ?」
「…………………………。」
「そ。」
人見先輩はそれだけ言うと立ち上がった。そのままゆっくりと歩みを進め公園の中央で立ち止まる。ゆっくりと振り返り、僕に質問する。
「俺のこと占うなって誰かに止められてんの?」
「……違います。」
「じゃあ新島の意志で俺を占いたくないってことね。」
「……はい。」
「その理由は教えてくれねーの?」
「……言ってしまったらもう、人見先輩は俺と話してくれなくなります。」
「俺がその理由を聞いたら、俺から新島と距離を置くような、そんな内容なの?」
「……はい。」
「俺の嫌いなコト知ってるよな?」
「こ、心を乱されることです。」
「まさに今、この状況がそうだよ。」
「ごめん……なさい。」
「……今日は夏祭りデートに付き合ってもらってどーも。」
人見先輩は先ほどまでの僕に歩幅を合わせてくれていた時とは違って、大股でズカズカと大きな音を立てながら一人で公園から出て行った。
人見先輩の後ろ姿が見えなくなるまで、僕はその後ろ姿をただ眺めることしかできなかった。公園にはすすり泣く僕の声と、一人では到底食べきることのできないたくさんの食べ物が鎮座していた。
今日は月が見えそうにない。