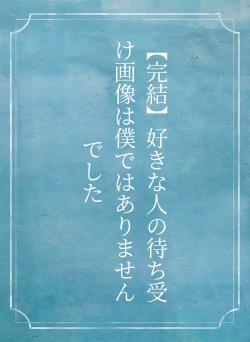あの日のデート(?)を境に、僕と人見先輩の関係は少し変わりつつあった。
一つ目は昼食をともに取ることが増えたということだ。お互いに用事のないときは学食に集合して、占いのお礼でいただいたお菓子を食べたり、売店や食堂で買ったご飯を一緒に食べたりしている。
最初こそ学食で人見先輩を食事をともにすることで先日の女子生徒のように声を掛けてくる輩が増えるのではないかと想像していたが、人見先輩の明らかな話しかけてくるなオーラに加え、先日の騒動を目撃していた生徒から他の生徒へと噂が広まり、食事中に声を掛けてくる生徒はほぼゼロに等しい状態になっていた。
とどのつまり二人で静かに食事をすることができている。
二つ目は下校時は一緒に帰るようになったことだ。これは本当にたまたまだったのだが、昼食を食べている最中に人見先輩から「今日も駅のクッキー買いに行くけど、一緒に行くか?」と提案されたコトがきっかけだった。人見先輩はあのクッキーが相当気に入ったらしい。
もちろん僕は二つ返事で回答したのだが、問題は放課後に僕は占いの依頼をこなさなければならないことであった。僕が回答後におどおどするもんだから、人見先輩もそれを察したのだろう。占いが終わるのを待つと言ってくれたのだ。申し訳ないと思ったが構わないと言うので、甘えることにしたのがつい先日の出来事だ。
「——『未来』のカードは皇帝の正位置ですね。これは責任を表しています。松浦先生は今後責任感が強くなるコトを意味していますね。それに伴って個人をまとめる能力が向上するといったところでしょうか。今後松浦先生は副担任ではなく、主担任として自身の生徒を持つ可能性があるかもしれません。それに伴って責任感が強くなるようなことがあるかもしれません。」
「なるほど……噂には聞いてましたが新島くんの占いはすごいですね。君に占ってもらってよかったよ。」
「そういってもらえてよかったです。」
「あ、お礼だよね。好きなお菓子とかジュースが何かわからなかったから、下手なものあげるよりこっちの方が嬉しいんじゃないかなって思ったんだけど、これでいいかな?」
そういって松浦先生が差し出してきたのはスタバのカードであった。
「え?いいんですか?」
「あ、もしかして何か問題だった?」
「いえ、高すぎませんか?なんかこう缶コーヒーとかでも良かったんですけど……。」
「そうなの?でも買っちゃったから受け取ってくれると嬉しいな。」
「では、ありがたく……。」
僕は松浦先生からスタバカードを受け取ると、先生は満足そうに微笑み、再度僕に占いのお礼を告げた後、教室を後にした。それを見届けた澤村先生は「今日はここまで」と一言。その合図を皮切りに占いを一目見ようと集まっていた生徒や先生方は蜘蛛の子のように散り散りに教室から出ていく。
「終わったか?」
「わ!人見先輩!待っててくれたんですか?」
教室から出ていく生徒と入れ違うように人見先輩が占いをしている二年の教室に入って来た。人見先輩は僕の占いが終わるのを待ってくれているようで、スクールバッグを肩に掛け、すぐに帰ることができる状態であった。
「今日もお待たせしてすみません。」
「いや、俺が好きで待ってるんだから気にすんな。」
「気にしますよ……。」
「……今日はどっか寄りたいことあるか?」
「あ、松浦先生からスタバカードいただいたんですよ!なのでスタバに寄ろうかと思います。」
「俺も行くわ。おすすめあんの?」
僕はタロットカードや教科書などを引き出しからスクールバッグへと移しながら、人見先輩からのその問いかけの回答を考えていた。
スタバに行ったことがないわけではないが、一人で行ったことはなく、基本的に一緒に行った人と同じものを頼んでいたため具体的にどんなメニューがあるかすらわからず、知っているとすればフラペチーノという夏にぴったりの冷たい飲み物があるということだけだ。
「ふ、フラペチーノですかね……?」
「ああ、まあそうだよな。俺はバニラにしようかな。」
「いいですね。僕も人見先輩と同じものにします。」
「ん。行けるか?」
「はい!」
僕は少し駆け足で人見先輩に近づき、先輩と横並びでそのまま駅近くにあるスタバへ向かった。
このようにして一緒に帰ることが増えたのだが、帰りはいつも今日のようにどこかに寄っているわけではなく、駅で解散することもあれば今日のようにどこかに寄ってからそこで解散することもある。
スタバに行くまでの間、僕と先輩は他愛もない話をする。
「流石に暑いな。」
「ですね……。そろそろ夏休みですね。人見先輩は何か予定あるんですか?」
「んー。何度かは学校に行く予定。これでも受験生なんで。」
「あ、そうじゃないですか!どこ受けるんですか?」
「……ナイショ。」
「……ケチだ。」
「冗談だよ。誰にも言ってねーからなあ。」
「そうなんですか?……あぁ、なるほど。そうですよね。」
僕はなんとなく察しがついた。おそらく女子生徒を警戒しているのだろう。同じ大学受けるだの。それがバレたら一緒に勉強する口実になり、声を掛けてくるだの。人見先輩はやはりいろいろ大変らしい。
「まぁ新島には言ってもいいか。」
「え、いいんですか?」
「まぁ……弟だし?」
「……なんすかそれ」
僕は人見先輩からの弟発言を笑って躱す。
嬉しくないわけじゃない。ただ弟では恋愛対象として見てもらうことができないからしんどいのだ。しかもそれを面と向かって伝えてくるあたり、そもそも恋愛対象でもなんでもなくシンプルに僕のコトを弟か何かだと思っているのだろう。
そんな何とも言えない気持ちになっていたが、人見先輩はそんな僕の状態には気付かずに淡々と話を続ける。
「ゆーても専門なんだけどね。将来やりたいことあって。」
「やりたいこと?」
「そ。それはまだ言わねーけど。いつか言うよ。新島はもう進路決めてんの?」
「僕は心理カウンセラーになりたいので、心理学が学べる大学に進学しようと思ってます。」
「いい夢じゃん。絶対に叶えろよ。」
「はい。ありがとうございます。」
正直なところ両親と教員以外に初めて自分の夢を語った。自分の夢を語るという行為は決して恥ずかしいことではないのだけれど、高校生という思春期真っ只中な僕にとってそれを第三者に話すと言う行為はとても勇気のいるものであった。
しかし僕の夢を人見先輩は笑うことなく、いい夢だと言ってくれた。
僕はそのたったそれだけの言葉で心が温かくなった。
ほどなくしてスタバに着いたのだが、人見先輩は事前に注文するものをバニラのフラペチーノと決めていたからだろうか、スタバに着くなりレジに並んだ。
僕は人見先輩の後ろについて並んでいたが、人見先輩は何を考えているのかバニラフラペチーノを二つと店員さんに注文をした。
二つも飲みたくなるほど暑かったのだろうかと考えていると、人見先輩は振り返り僕に向かってサイズは何にするかと問いかけてきた。
「え?」
突然のことに困惑していると、人見先輩はもう一度僕に向かって告げた。
「サイズだよ。バニラフラペチーノのサイズ。何にする?」
「え、先輩が二つ飲むのかと思ってました。」
「いくら俺でもこれ二つも飲めねーよ。てか太るわ。」
「人見先輩スタイルいいですもんね。腹筋とか割れてるんですか?」
「いや今はいいから。サイズは?」
「え、あ、えっとLサイズですかね……?」
僕のその回答に人見先輩と後ろで会話を聞いていて店員さんの表情が少し驚いたものへと変わった。何か変なことを言ってしまっただろうかと疑問に思ったが、その疑問はすぐに人見先輩によって解決した。
「新島ってもしかしてスタバ初めて?」
「いえ、何度かは来たことはありますよ?」
「……一人で?」
「友達とですけど……。」
「そ。スタバのサイズはSMLじゃないぞ。ショート、トール、ベンティが基本のサイズ構成だ。」
「え?そうなんですか?」
僕はそれを聞いて途端に恥ずかしくなってきた。確かに今までは一緒に来た人と同じものを注文していたため、サイズなど気にしたことはなかったが、まさかサイズ表記が通常とは異なっているなどとは思ってもいなかった。
恥ずかしいのはサイズの認識が間違っていたからだけではない。店員さんがその会話を聞いて微笑んでいるからでもない。人見先輩がそれを聞いて大笑いしていることだ。
人見先輩は僕と話すときはよく笑ってくれるのだが、それでもこんなに大笑いをしているのを見るのは初めてだ。そんなに恥ずかしいことだったのかと、余計に恥ずかしくなる。
「はあー。お前かわいいな。笑ってごめんな。驕るから許して。」
「かわっ……。かわいくないですよ!」
「かわいいよ。新島は。」
「もっー。……それでショートとトールとベンティでしたっけ?どれがどのサイズに当てはまるんですか?」
「ショートがS、トールがM、ベンティがLって感じかな。俺はベンティにするけど、新島はどうする?」
人見先輩は僕を茶化しながらも、サイズについて教えてくれた。人見先輩でベンティと言うことはそれはかなりの量だろう。ここ最近一緒に昼食を共にしたり、放課後買い食いしたりすることで人見先輩の大体の食事量は分かってきているつもりだった。端的に言えば僕の約倍はたやすく平らげることができるようだ。そう考えると僕はMサイズであるトールが丁度いいかもしれない。
「と、トールでお願いします。」
「Mじゃなくていいのか?」
「バカにしないでください!」
人見先輩はそんな会話にまた大きく口を開けて笑いながら、店員さんに注文をしていた。人見先輩はスタバに慣れているのか、スマホを取り出し慣れた手つきで会計を済ませる。
ここで初めて知ったのだが、スタバカードはスマホのアプリと連動させることができるらしく、カードを持ち歩かずともスマホだけで決済が可能らしい。
ちなみにこの知識はレジ横に掲げてあったパネルに記載のあった情報だ。
会計を済ませ、人見先輩と僕は商品を受け取りカウンターで受け取った後、店内に空いていた席に腰を下ろす。
「お、驕っていただきありがとうございます。」
「ん。」
人見先輩はいつも通りちょっとぶっきらぼうな返事をしたのち、まだ出来立てでほぼ溶けていないフラペチーノをストローで勢いよく吸う。
「吸えねえわ。」
「まぁ今作っていただきましたしね。暑いですしすぐ溶けますよ。」
「だなー。そういえばさ……」
「はい、なんですか?」
人見先輩は何やら改まって僕に何かを伝えようとしているのだろうか。いつもとは違って少しもじもじとした感じで僕に相談するような声のトーンで話を続けた。
「俺も新島に占ってもらえるの?」
「……え?」
「占いだよ。新島がいつも放課後やってるやつ。あれ俺も占ってほしいんだけど、お菓子とか持ってくればいいわけ?」
ぶっちゃけ人見先輩は占いなど興味が無いと思っていた。その理由は人見先輩は心を乱されるのが嫌いであると自身の口から語られていたからである。
占いは当たるも八卦当たらぬも八卦と伝えてはいるが、結果次第で人は一喜一憂する。占いとはそういうものである。人見先輩にも何度か説明しているため、今まで人見先輩から占ってほしいなどと言う発言は無かったのだと思っていた。
しかしたった今それが覆ってしまった。
「え、人見先輩って占いに興味があるんですか……?てっきり占いなんて興味無いんだと思ってました。」
「んー。そこまで興味は無いよ。でも新島の占いは九十五パーセントの確率で当たるんだろ?そこまで高いんだったら少しは気になるよ。」
九十五パーセントの確率で当たる占い。それは単純に占いをはじめて二十人を占った際にそのうち十九人が的中。残り一人も外れたわけではなく、未来だけを占ってほしいという的中の有無がすぐには分からないものだったからという形だった。そのためそれを見ていた一人の生徒が新島の占いは九十五パーセントの確率で当たるなんて話を広めてしまったがために噂が独り歩きしたに過ぎない。
何度も言う通り、占いは当たるも八卦当たらぬも八卦だ。当たるときは当たるし、外れるときは外れる。
しかしそんな噂のおかげで今では多くの人が僕の占いを見に来たり、実際に占ってほしいと占いをしに訪れたりもしている。ありがたいことだとは思うが、それとこれとは話が違うのだ。
「占いは当たるも八卦当たらぬも八卦ですよ……。」
「ん。新島がいつも言ってるやつだよな。分かってるよ。それで?どうすれば占ってもらえるの?」
人見先輩はどうしても占ってほしいらしい。
実際のところ占うのはさほど大きな問題ではない。問題は何を占うかだ。
僕は人見先輩のコトが好きだ。しかし人見先輩が占ってほしい内容が恋愛に関係するものだった場合どうする。僕は素直にその結果を伝えることができるだろうか。
占いの結果で最近食事を共にしている人とは関わらない方がいいといったような僕にとってマイナスな結果の占いが出た場合どうしたらいいか。
占いは当たるも八卦当たらぬも八卦と自分で言っておきながら、マイナスな結果が出たら正直落ち込むモノである。
しかし現状では人見先輩がどんなことを占いたいのかは分からない。生徒からの占いは恋愛相談なものが大半を占めているが、大人からは今後のアドバイスを求めるようなモノが多い。実際に松浦先生からの占いの希望は、大学を卒業して一年目で副担任を任せてもらっているが、今のまま突き進んでも良いのか?といったような未来に対するアドバイスを求めるモノであった。
そのため恋愛以外を占う可能性は大いにある。しかし実際のところ何を占ってほしいかは人見先輩だけが知るところだ。だがそれを聞いてしまったら確実に人見先輩を占わなければならない。
——それだけは避けなくてはならない。
「えっと……今は占いの希望が結構埋まっておりまして、だいぶ先になってしまうんですよね。」
「だよなー。いつも教室にすげぇ人集まってるもんな。」
「そ、そうなんですよ。なのでいくら先輩でも順番を抜かすと、僕は兎も角先輩までいろいろ言われそうなので……。」
「ん。じゃあどこで予約できんの?」
まずいことになってしまった。人見先輩は予約をしてまで僕に占ってほしいらしい。ちなみに僕の占いに予約などは存在しない。いや厳密に言えば存在はしている。それは直接僕にこの日に占ってほしいと連絡をすることだ。
そうすればその日はその人を優先的に占い、予約分を捌いた後で時間があれば集まってきている生徒や教師から抽選する形で占いを行っている。ただ最近は事前に連絡をしてくる生徒も増えてきたため抽選はせず、定員の五人を占ってその日は終了することがほとんどだ。
しかしこの場でそのことを伝えてしまうと、人見先輩は即予約をするだろう。そうなってしまえば本末転倒だ。そうとなればここで嘘をつくしかない。
「…………今は予約も取ってないんですよ。先まで埋まってしまうと、僕の予定が立てられなくなってしまうので。」
「なるほどな……新島も大変なんだな。じゃあ予約できるようになったら教えてくれ。」
「わ、分かりました。」
「そういや新島は夏休み何すんの?」
僕は人見先輩の予約を上手く躱し、先輩からの質問の回答を考える。
「そうですね……。一応同好会という形ではありますが存続のために活動しないといけないので、先輩と同じく何日かは学校に行きますかね。それ以外だったら特に予定が埋まっているわけではないので、いけそうだったら短期バイトとか入れようかなと思ってます。」
「ふーん。じゃあ空いてる日は俺とどっか遊び行くか?」
「え?いいんですか?でも先輩受験ですよね……?」
「受験生にも息抜きが必要なの。嫌ならいいけど。」
「いや行きます!行かせてください!」
僕の必死な感じに人見先輩はまたも大きな口を開けて笑っていた。
「じゃあ約束な。行きたいところあればピックアップしとけよ?」
「はい!人見先輩も行きたいところあれば遠慮なく言ってくださいね!」
「ん。」
バニラフラペチーノが注がれたカップの周りには水滴が付き、ストローで吸えるほど程よく溶けだしていた。
人見先輩は僕と遊びの約束をしたのに満足したのか、頬をつきながら片手でカップを持ち上げ、微笑みながらバニラフラペチーノを飲んだ。
一つ目は昼食をともに取ることが増えたということだ。お互いに用事のないときは学食に集合して、占いのお礼でいただいたお菓子を食べたり、売店や食堂で買ったご飯を一緒に食べたりしている。
最初こそ学食で人見先輩を食事をともにすることで先日の女子生徒のように声を掛けてくる輩が増えるのではないかと想像していたが、人見先輩の明らかな話しかけてくるなオーラに加え、先日の騒動を目撃していた生徒から他の生徒へと噂が広まり、食事中に声を掛けてくる生徒はほぼゼロに等しい状態になっていた。
とどのつまり二人で静かに食事をすることができている。
二つ目は下校時は一緒に帰るようになったことだ。これは本当にたまたまだったのだが、昼食を食べている最中に人見先輩から「今日も駅のクッキー買いに行くけど、一緒に行くか?」と提案されたコトがきっかけだった。人見先輩はあのクッキーが相当気に入ったらしい。
もちろん僕は二つ返事で回答したのだが、問題は放課後に僕は占いの依頼をこなさなければならないことであった。僕が回答後におどおどするもんだから、人見先輩もそれを察したのだろう。占いが終わるのを待つと言ってくれたのだ。申し訳ないと思ったが構わないと言うので、甘えることにしたのがつい先日の出来事だ。
「——『未来』のカードは皇帝の正位置ですね。これは責任を表しています。松浦先生は今後責任感が強くなるコトを意味していますね。それに伴って個人をまとめる能力が向上するといったところでしょうか。今後松浦先生は副担任ではなく、主担任として自身の生徒を持つ可能性があるかもしれません。それに伴って責任感が強くなるようなことがあるかもしれません。」
「なるほど……噂には聞いてましたが新島くんの占いはすごいですね。君に占ってもらってよかったよ。」
「そういってもらえてよかったです。」
「あ、お礼だよね。好きなお菓子とかジュースが何かわからなかったから、下手なものあげるよりこっちの方が嬉しいんじゃないかなって思ったんだけど、これでいいかな?」
そういって松浦先生が差し出してきたのはスタバのカードであった。
「え?いいんですか?」
「あ、もしかして何か問題だった?」
「いえ、高すぎませんか?なんかこう缶コーヒーとかでも良かったんですけど……。」
「そうなの?でも買っちゃったから受け取ってくれると嬉しいな。」
「では、ありがたく……。」
僕は松浦先生からスタバカードを受け取ると、先生は満足そうに微笑み、再度僕に占いのお礼を告げた後、教室を後にした。それを見届けた澤村先生は「今日はここまで」と一言。その合図を皮切りに占いを一目見ようと集まっていた生徒や先生方は蜘蛛の子のように散り散りに教室から出ていく。
「終わったか?」
「わ!人見先輩!待っててくれたんですか?」
教室から出ていく生徒と入れ違うように人見先輩が占いをしている二年の教室に入って来た。人見先輩は僕の占いが終わるのを待ってくれているようで、スクールバッグを肩に掛け、すぐに帰ることができる状態であった。
「今日もお待たせしてすみません。」
「いや、俺が好きで待ってるんだから気にすんな。」
「気にしますよ……。」
「……今日はどっか寄りたいことあるか?」
「あ、松浦先生からスタバカードいただいたんですよ!なのでスタバに寄ろうかと思います。」
「俺も行くわ。おすすめあんの?」
僕はタロットカードや教科書などを引き出しからスクールバッグへと移しながら、人見先輩からのその問いかけの回答を考えていた。
スタバに行ったことがないわけではないが、一人で行ったことはなく、基本的に一緒に行った人と同じものを頼んでいたため具体的にどんなメニューがあるかすらわからず、知っているとすればフラペチーノという夏にぴったりの冷たい飲み物があるということだけだ。
「ふ、フラペチーノですかね……?」
「ああ、まあそうだよな。俺はバニラにしようかな。」
「いいですね。僕も人見先輩と同じものにします。」
「ん。行けるか?」
「はい!」
僕は少し駆け足で人見先輩に近づき、先輩と横並びでそのまま駅近くにあるスタバへ向かった。
このようにして一緒に帰ることが増えたのだが、帰りはいつも今日のようにどこかに寄っているわけではなく、駅で解散することもあれば今日のようにどこかに寄ってからそこで解散することもある。
スタバに行くまでの間、僕と先輩は他愛もない話をする。
「流石に暑いな。」
「ですね……。そろそろ夏休みですね。人見先輩は何か予定あるんですか?」
「んー。何度かは学校に行く予定。これでも受験生なんで。」
「あ、そうじゃないですか!どこ受けるんですか?」
「……ナイショ。」
「……ケチだ。」
「冗談だよ。誰にも言ってねーからなあ。」
「そうなんですか?……あぁ、なるほど。そうですよね。」
僕はなんとなく察しがついた。おそらく女子生徒を警戒しているのだろう。同じ大学受けるだの。それがバレたら一緒に勉強する口実になり、声を掛けてくるだの。人見先輩はやはりいろいろ大変らしい。
「まぁ新島には言ってもいいか。」
「え、いいんですか?」
「まぁ……弟だし?」
「……なんすかそれ」
僕は人見先輩からの弟発言を笑って躱す。
嬉しくないわけじゃない。ただ弟では恋愛対象として見てもらうことができないからしんどいのだ。しかもそれを面と向かって伝えてくるあたり、そもそも恋愛対象でもなんでもなくシンプルに僕のコトを弟か何かだと思っているのだろう。
そんな何とも言えない気持ちになっていたが、人見先輩はそんな僕の状態には気付かずに淡々と話を続ける。
「ゆーても専門なんだけどね。将来やりたいことあって。」
「やりたいこと?」
「そ。それはまだ言わねーけど。いつか言うよ。新島はもう進路決めてんの?」
「僕は心理カウンセラーになりたいので、心理学が学べる大学に進学しようと思ってます。」
「いい夢じゃん。絶対に叶えろよ。」
「はい。ありがとうございます。」
正直なところ両親と教員以外に初めて自分の夢を語った。自分の夢を語るという行為は決して恥ずかしいことではないのだけれど、高校生という思春期真っ只中な僕にとってそれを第三者に話すと言う行為はとても勇気のいるものであった。
しかし僕の夢を人見先輩は笑うことなく、いい夢だと言ってくれた。
僕はそのたったそれだけの言葉で心が温かくなった。
ほどなくしてスタバに着いたのだが、人見先輩は事前に注文するものをバニラのフラペチーノと決めていたからだろうか、スタバに着くなりレジに並んだ。
僕は人見先輩の後ろについて並んでいたが、人見先輩は何を考えているのかバニラフラペチーノを二つと店員さんに注文をした。
二つも飲みたくなるほど暑かったのだろうかと考えていると、人見先輩は振り返り僕に向かってサイズは何にするかと問いかけてきた。
「え?」
突然のことに困惑していると、人見先輩はもう一度僕に向かって告げた。
「サイズだよ。バニラフラペチーノのサイズ。何にする?」
「え、先輩が二つ飲むのかと思ってました。」
「いくら俺でもこれ二つも飲めねーよ。てか太るわ。」
「人見先輩スタイルいいですもんね。腹筋とか割れてるんですか?」
「いや今はいいから。サイズは?」
「え、あ、えっとLサイズですかね……?」
僕のその回答に人見先輩と後ろで会話を聞いていて店員さんの表情が少し驚いたものへと変わった。何か変なことを言ってしまっただろうかと疑問に思ったが、その疑問はすぐに人見先輩によって解決した。
「新島ってもしかしてスタバ初めて?」
「いえ、何度かは来たことはありますよ?」
「……一人で?」
「友達とですけど……。」
「そ。スタバのサイズはSMLじゃないぞ。ショート、トール、ベンティが基本のサイズ構成だ。」
「え?そうなんですか?」
僕はそれを聞いて途端に恥ずかしくなってきた。確かに今までは一緒に来た人と同じものを注文していたため、サイズなど気にしたことはなかったが、まさかサイズ表記が通常とは異なっているなどとは思ってもいなかった。
恥ずかしいのはサイズの認識が間違っていたからだけではない。店員さんがその会話を聞いて微笑んでいるからでもない。人見先輩がそれを聞いて大笑いしていることだ。
人見先輩は僕と話すときはよく笑ってくれるのだが、それでもこんなに大笑いをしているのを見るのは初めてだ。そんなに恥ずかしいことだったのかと、余計に恥ずかしくなる。
「はあー。お前かわいいな。笑ってごめんな。驕るから許して。」
「かわっ……。かわいくないですよ!」
「かわいいよ。新島は。」
「もっー。……それでショートとトールとベンティでしたっけ?どれがどのサイズに当てはまるんですか?」
「ショートがS、トールがM、ベンティがLって感じかな。俺はベンティにするけど、新島はどうする?」
人見先輩は僕を茶化しながらも、サイズについて教えてくれた。人見先輩でベンティと言うことはそれはかなりの量だろう。ここ最近一緒に昼食を共にしたり、放課後買い食いしたりすることで人見先輩の大体の食事量は分かってきているつもりだった。端的に言えば僕の約倍はたやすく平らげることができるようだ。そう考えると僕はMサイズであるトールが丁度いいかもしれない。
「と、トールでお願いします。」
「Mじゃなくていいのか?」
「バカにしないでください!」
人見先輩はそんな会話にまた大きく口を開けて笑いながら、店員さんに注文をしていた。人見先輩はスタバに慣れているのか、スマホを取り出し慣れた手つきで会計を済ませる。
ここで初めて知ったのだが、スタバカードはスマホのアプリと連動させることができるらしく、カードを持ち歩かずともスマホだけで決済が可能らしい。
ちなみにこの知識はレジ横に掲げてあったパネルに記載のあった情報だ。
会計を済ませ、人見先輩と僕は商品を受け取りカウンターで受け取った後、店内に空いていた席に腰を下ろす。
「お、驕っていただきありがとうございます。」
「ん。」
人見先輩はいつも通りちょっとぶっきらぼうな返事をしたのち、まだ出来立てでほぼ溶けていないフラペチーノをストローで勢いよく吸う。
「吸えねえわ。」
「まぁ今作っていただきましたしね。暑いですしすぐ溶けますよ。」
「だなー。そういえばさ……」
「はい、なんですか?」
人見先輩は何やら改まって僕に何かを伝えようとしているのだろうか。いつもとは違って少しもじもじとした感じで僕に相談するような声のトーンで話を続けた。
「俺も新島に占ってもらえるの?」
「……え?」
「占いだよ。新島がいつも放課後やってるやつ。あれ俺も占ってほしいんだけど、お菓子とか持ってくればいいわけ?」
ぶっちゃけ人見先輩は占いなど興味が無いと思っていた。その理由は人見先輩は心を乱されるのが嫌いであると自身の口から語られていたからである。
占いは当たるも八卦当たらぬも八卦と伝えてはいるが、結果次第で人は一喜一憂する。占いとはそういうものである。人見先輩にも何度か説明しているため、今まで人見先輩から占ってほしいなどと言う発言は無かったのだと思っていた。
しかしたった今それが覆ってしまった。
「え、人見先輩って占いに興味があるんですか……?てっきり占いなんて興味無いんだと思ってました。」
「んー。そこまで興味は無いよ。でも新島の占いは九十五パーセントの確率で当たるんだろ?そこまで高いんだったら少しは気になるよ。」
九十五パーセントの確率で当たる占い。それは単純に占いをはじめて二十人を占った際にそのうち十九人が的中。残り一人も外れたわけではなく、未来だけを占ってほしいという的中の有無がすぐには分からないものだったからという形だった。そのためそれを見ていた一人の生徒が新島の占いは九十五パーセントの確率で当たるなんて話を広めてしまったがために噂が独り歩きしたに過ぎない。
何度も言う通り、占いは当たるも八卦当たらぬも八卦だ。当たるときは当たるし、外れるときは外れる。
しかしそんな噂のおかげで今では多くの人が僕の占いを見に来たり、実際に占ってほしいと占いをしに訪れたりもしている。ありがたいことだとは思うが、それとこれとは話が違うのだ。
「占いは当たるも八卦当たらぬも八卦ですよ……。」
「ん。新島がいつも言ってるやつだよな。分かってるよ。それで?どうすれば占ってもらえるの?」
人見先輩はどうしても占ってほしいらしい。
実際のところ占うのはさほど大きな問題ではない。問題は何を占うかだ。
僕は人見先輩のコトが好きだ。しかし人見先輩が占ってほしい内容が恋愛に関係するものだった場合どうする。僕は素直にその結果を伝えることができるだろうか。
占いの結果で最近食事を共にしている人とは関わらない方がいいといったような僕にとってマイナスな結果の占いが出た場合どうしたらいいか。
占いは当たるも八卦当たらぬも八卦と自分で言っておきながら、マイナスな結果が出たら正直落ち込むモノである。
しかし現状では人見先輩がどんなことを占いたいのかは分からない。生徒からの占いは恋愛相談なものが大半を占めているが、大人からは今後のアドバイスを求めるようなモノが多い。実際に松浦先生からの占いの希望は、大学を卒業して一年目で副担任を任せてもらっているが、今のまま突き進んでも良いのか?といったような未来に対するアドバイスを求めるモノであった。
そのため恋愛以外を占う可能性は大いにある。しかし実際のところ何を占ってほしいかは人見先輩だけが知るところだ。だがそれを聞いてしまったら確実に人見先輩を占わなければならない。
——それだけは避けなくてはならない。
「えっと……今は占いの希望が結構埋まっておりまして、だいぶ先になってしまうんですよね。」
「だよなー。いつも教室にすげぇ人集まってるもんな。」
「そ、そうなんですよ。なのでいくら先輩でも順番を抜かすと、僕は兎も角先輩までいろいろ言われそうなので……。」
「ん。じゃあどこで予約できんの?」
まずいことになってしまった。人見先輩は予約をしてまで僕に占ってほしいらしい。ちなみに僕の占いに予約などは存在しない。いや厳密に言えば存在はしている。それは直接僕にこの日に占ってほしいと連絡をすることだ。
そうすればその日はその人を優先的に占い、予約分を捌いた後で時間があれば集まってきている生徒や教師から抽選する形で占いを行っている。ただ最近は事前に連絡をしてくる生徒も増えてきたため抽選はせず、定員の五人を占ってその日は終了することがほとんどだ。
しかしこの場でそのことを伝えてしまうと、人見先輩は即予約をするだろう。そうなってしまえば本末転倒だ。そうとなればここで嘘をつくしかない。
「…………今は予約も取ってないんですよ。先まで埋まってしまうと、僕の予定が立てられなくなってしまうので。」
「なるほどな……新島も大変なんだな。じゃあ予約できるようになったら教えてくれ。」
「わ、分かりました。」
「そういや新島は夏休み何すんの?」
僕は人見先輩の予約を上手く躱し、先輩からの質問の回答を考える。
「そうですね……。一応同好会という形ではありますが存続のために活動しないといけないので、先輩と同じく何日かは学校に行きますかね。それ以外だったら特に予定が埋まっているわけではないので、いけそうだったら短期バイトとか入れようかなと思ってます。」
「ふーん。じゃあ空いてる日は俺とどっか遊び行くか?」
「え?いいんですか?でも先輩受験ですよね……?」
「受験生にも息抜きが必要なの。嫌ならいいけど。」
「いや行きます!行かせてください!」
僕の必死な感じに人見先輩はまたも大きな口を開けて笑っていた。
「じゃあ約束な。行きたいところあればピックアップしとけよ?」
「はい!人見先輩も行きたいところあれば遠慮なく言ってくださいね!」
「ん。」
バニラフラペチーノが注がれたカップの周りには水滴が付き、ストローで吸えるほど程よく溶けだしていた。
人見先輩は僕と遊びの約束をしたのに満足したのか、頬をつきながら片手でカップを持ち上げ、微笑みながらバニラフラペチーノを飲んだ。