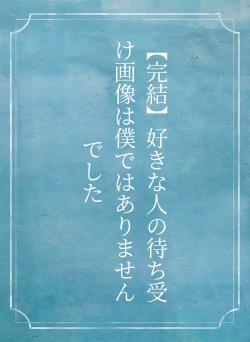人見先輩はクロックムッシュを食べ終え、細長い先割れのスプーンを持ち、パフェの先端にある生クリームを上手にすくってそれをパクリと頬張る。何口か食べた後、次はどの部分を食べようかと考えるそぶりをしながら人見先輩は自身の身の上話を聞かせてくれた。
「俺さ、弓道がやりたかったわけじゃないんだよ。」
「……そうなんですか?」
「そ。俺さ自分の心が乱されるのめちゃくちゃ嫌なんだよね。まぁそれは俺の心が弱いのが悪いんだけどさ。例えば誰かに告白されたり。そうするとさ、嫌でもその告白してきたやつの事意識するだろ。それが恋愛感情があろうとなかろうと。」
「たしかにそうですね。何かと気まずかったりしますよね。」
「だろ?そういうしょーもないことで気を使ったりしないといけないのが俺苦手なんだよね。だから俺の趣味って言うかよくやってることがあって、それが精神統一とか瞑想なんだよね。」
「……メンタル面を鍛えるってことですか?」
「ん。で、その延長線で弓道をはじめたんだよね。だから弓道やりたくて始めたわけじゃなくて、メンタル鍛えるために弓道始めたんだよ。でもさ精神統一とかそういう面では弓道は良かったけど、鍛えられるわけじゃなかったよ。」
「……弓道は集中力を高めるのには向いていたけど、メンタルを鍛えられるわけじゃなかったってことですか?」
人見先輩はその長い先割れスプーンで何口か食べた後に僕の質問に対して肯定するようにぶっきらぼうな返事をする。そんな人見先輩は自分自身の話をするときは恥ずかしいのか、はたまたパフェに集中しているのか、僕と視線が合うことはなくずっとパフェを見ながら僕と会話をしている。
「あ、でも弓道自体は楽しかったよ。でもその楽しさが仇になったんだよ。」
「仇……ですか……。先輩は全国大会でも優勝するくらいの実力なんですから、仇とかないと思うんですけど。」
「いやその優勝がダメだったんだよね。会場で表彰されるとかは別に良かったけど、校舎に弾幕掛けたり、優勝したことを全校集会とかで表彰したりさ。そのせいで今までの比にならないくらい声を掛けられたよ。毎日顔も知らない女子生徒に話しかけられたり、話したこともない同学年の男からも勝手に友達認定されたり。耐えきれなかった。」
「………………。」
「だから辞めたんだ。全部。」
「……全部?それって……。」
そこまで聞いて、僕はなんとなく察していた。学校での人見先輩のあの冷ややかな視線に刺すような口調。それはきっと人見先輩なりの防衛だったのだろう。僕が学校で感じていた違和感はこれだったのだ。男子生徒はわからないが、多くの女子生徒はきっと人見先輩に告白をして、こっぴどく振られたのだろう。だから三年の先輩たちは人見先輩への態度がよそよそしかったのだと思う。それを知らない生徒、それこそ先日学食で声を掛けてきた一年の女子生徒はかっこいい先輩という噂だけを聞いて、ああいう感じで先輩に声をかけて怒らせるのだろう。
人見先輩が僕が何を考えているのか大方の想像が付いたようで、少し微笑みながら僕を怖がらせないように呟いた。
「そ。弓道も友人関係も何もかも。正直楽になったよ。でもここ直近でそんな楽な時間は終わりを迎えたよ。」
「……もしかして僕のせいですか?」
「……最初の印象は最悪だったよ。」
「……。」
「あの路地は偶然通りかかったんだ。普段なら路地裏で誰かが暴行受けていても気にも留めないと思うよ。いや気にはするだろうけど、それでもわざわざ助けに行こうという正義感は生まれないかな。だから新島を助けたときは自分でも驚いたよ。」
人見先輩は笑いながら淡々と会話を続けた。
「最初はさそれこそ同じ学校の制服だったし、困ってそうだったってのもあるけど、どこかで見たことある気がして声かけたんだよね。てかそこで声かけなかったから、なんか俺って結構最低な人間じゃん?精神的にもよくないなって思って助けた。そしたら次の日俺のクラスの前でそいつが女子生徒に囲まれて困ってんの。こいつどんだけ俺の心を乱してくるんだよって思った。でもまあ助けたよ。困ってたし。」
「……。」
「でもだんだんと、そんな考えは変わっていったよ。」
僕は驚いて俯きつつあった顔を思いっきり上げた。
「え?」
「印象が最悪な奴とカフェとかいかねーだろ。少なくとも今は好印象だよ。そうだな。あえて言うなら弟的なそんな存在かな。」
「お、弟?」
「ん。放っておけない感じ?俺一人っ子だからわかんないけど、弟がいたらこんな感じなのかなって。」
それは僕にとってあまりにも残酷なモノだった。弟のような存在。つまりこれは恋愛対象にはならないと言うことを意味していた。よく言う男女間で男性が女性に対して、こいつは妹みたいな存在だから恋愛には発展しないのと同じ。もしくはそれ以上の効果を持つ言葉だ。
そもそも先輩の性対象を知らないが、これでは先輩の性対象が女性でもたとえ男性であっても、僕のことを好きになることは無いだろう。
上げた顔がだんだんとまた俯き始める。
人見先輩はそれに何かを察したのだろう、心配そうな声で僕に声を掛けた。
「大丈夫か?」
「え、あ、はい!大丈夫です。弟的な存在……嬉しいです!先輩が誰かと仲良くしているところなんて見たことなかったので。そうすると僕は人見先輩の中じゃだいぶ上位に入るくらいの人間ってことですか?」
人見先輩は僕の問いかけに対して、右斜め上を見上げ数秒考え込んだ。
「……俺、学校じゃ新島以外と喋んねーよ。」
「そうなんですか?」
「他学年だと声を掛けられることはあっても、同学年だとねーな。誰かと学校で昼食食ったりしたのだってそれこそ一年ぶりとかじゃねーかな。」
「それは……光栄ですね。」
「なんだそれ。そういえばこうやって休日家族以外とどこか出かけたりするのは初めてかもな。」
「え!!!!!」
「うるさっ!」
僕はその衝撃的な発言に驚き、人見先輩を驚かせただけではなく、お店のスタッフさんの視線までもを集めることとなった。
「す、すみません。取り乱しました。」
「いやいいけどさ。そんなに驚くことか?」
「いえ、先輩ならいろんな方とデートとか行かれてるでしょうから、お出かけとかは慣れてるんだと思ってました。」
「デートねぇ……。なら今日の新島とのデートが初デートだな。」
「なっ!」
僕は顔が一気に赤くなる。それを見た人見先輩はそれが面白かったのか、単に僕をからかいたかったのか分からないが、楽しそうにしながら残りのパフェを頬張っていた。
惚れた弱みだろうか。僕は何も言い返せないまま、人見先輩と同じくパフェを頬張った。
その後数口食べ進めていると、急に僕の目の前にチョコがたっぷりかかった生クリームがすくってるスプーンが差し出された。突然のことに動揺していると人見先輩は口を開いた。
「あーん、して。」
「え?」
「新島のイチゴのパフェも食べたいから交換しねえ?だからあーんして。」
「………………。」
これは俗に言う間接キスではないのだろうか。
人見先輩は僕のことを弟のような存在としか思っていないため、きっとこれは何の感情も無い、ただ単に本当に僕の食べているイチゴのパフェを食べたかったが故の行動なのだろう。しかし僕にはそんなこと関係ない。僕は人見先輩のことが好きなのだ。
今まで恋人がいない歴イコール年齢の僕にとってこれは一大イベントである。
そんな僕をお構いなしに人見先輩はスプーンを更に僕に近づけ、顎を使い食べるように指示を出す。そんなイケメンに僕は逆らえるわけもなく、ゆっくり。ほんとにゆっくりと口を大きく開けて、人見先輩が差し出しているスプーンを頬張った。
今度はそれを確認した人見先輩が「あーん」と大きく口を開けて待機していた。これは食べさせろということだろうが、これまた覚悟のいるイベントが今まさに始まろうとしていた。
僕はパフェで一番大きなイチゴが載っている部分を何の躊躇もなくすくうと、震える手を抑えながら人見先輩の口の中へとスプーンを入れる。先輩は目で笑い、スプーンにかじりつく勢いで大きなイチゴをおいしそうに頬張った。
「んまぁ。」
「……満足そうで何よりです。」
「新島は?美味かったか?」
「は、はい!めちゃくちゃおいしいです!」
「そ、ならいいよ。」
人見先輩は満足したのか、黙々と食べ進め、たまに僕に断りもなくイチゴパフェをちょくちょくつまんでいた。そんなにおいしかったのかと「もう一つ頼みますか?」と聞いたところ、「え、つまみ食いしてたのバレてた?」と茶目っ気のある笑顔に続けて「今日はいいや。また今度来た時食おうぜ。」と目尻に綺麗なシワを寄せながらそう言った。
僕は次があるのかと少し二ヤつきが止まらなかった。
✂ ——— ✂ ——— ✂ ——— ✂ ——— ✂
「ほんとに驕ってもらってよかったのか?」
「もちろんです!お詫びも兼ねてでしたので。」
人見先輩は会計時まで財布を出して俺が出すの一点張りであったが、流石に先日のお詫びと、そもそも今日のデート(?)に誘ったのは僕のため、誘った側が出すと言い続け、渋々ながらも財布をしまってもらうことに成功した。
今日の要件も終わったので、カフェを出たらもう帰路に就くだけだと思っていたが、予想に反し人見先輩から声を掛けてきた。
「腹ごしらえすんだし、どっか行くか?」
「え?いいんですか?」
「……逆にカフェだけなんか?」
「いえ、カフェ行きましょうって誘ったのでカフェで解散だと思ってました。」
「ふーん……。新島はこの後時間あるの?」
「いえ、特に予定も無いので、空いてますけど……。」
「じゃあきまり、デートの続きしよっか。」
「………………はい?」
人見先輩はそう言うと、僕の手を掴み駅に向かって歩き始めた。駅に向かうということはどこかに電車で向かうもんだと思っていたがそうではないみたいだ。
駅に着いた人見先輩は一言。
「この間くれたクッキーが売ってる店どこ?」
となかなかに端的に要件を伝えてきた。思い返してみればクッキーは喜んで食べてくれていたが、そのときに変なことを聞かれた気がする。当時はそれが何を意味するのかは分からなかったが、今ならその意味が多少なりとも分かる気がした。
「あのクッキーならこっちの店ですよ。あの……言いづらいかもしれませんがこのクッキーをあげたとき先輩、手作りかどうか聞いてきたじゃないですか。それってもしかして過去に何か変なもの入れられてたりしてたんじゃないですか?」
「……ん。マジで怖いよ。クッキーから毛とか生えてたら。」
「…………すみません。想像して気持ち悪くなってきました。」
「大丈夫か?」
人見先輩はそういって僕を心配するように、僕の顔を覗き込んできた。その優しさに惚れ惚れすると共に、好きな人の顔が至近距離にあることに動揺してしまい、更に人見先輩を心配させてしまうことになった。
人見先輩はそんな僕の態度に焦ったのか、近くの自動販売機に走り、水を買って戻って来てくれた。
「飲め!」
「あ、ありがとうございます。すみません。僕から聞いておいて……。」
「全然。むしろ急に話してすまん。」
「いえ、聞いたのは僕ですから……。だから人見先輩は出来合いのものしか口にしない感じなんですか?」
「ん。」
人見先輩のその短く端的な回答はすごく悲しげに聞こえた。
きっとそのコトがトラウマで食べたいものも食べることができなかったことがあるんじゃないかと思った。そうなれば人見先輩がわざわざクッキーの売り場を聞いてきたのも納得が行く。
「もう大丈夫です!クッキー見に行きましょうか!」
「ん。」
日曜日の駅は午後となり、今朝見たときよりかは明らかに人の数が多くなっていた。それでもどこかのお店が混んでいるとかそういうわけではなく、単に電車を使う人口が多いだけという印象で、人の流れに身を任せれば案外すぐに目的のクッキーが売っている店にたどり着いた。
「たくさん種類あんのね。」
「そうなんですよ。人見先輩にあげたのがこのチョコとバタークッキーのセットだったんですけど、生姜が苦手でなければジンジャークッキーがおいしいのでお勧めです。」
「へぇ。ん、ここ紅茶のティーパックも売ってんのね。なら新島おすすめのジンジャークッキーと適当な紅茶買おうかな。」
「いいですね!ここは紅茶もすっごくおいしいんですよ。」
「ん。新島は何か買う?」
「そうですね……まだまだ占いでもらったお菓子があるのであまりお菓子は増やしたくないのですが、少しならいいですよね。先輩にあげたチョコとバタークッキーのセットを買おうと思います。」
「そ。すみません。ジンジャークッキーと紅茶の組み合わせ。それとチョコとバタークッキーのセットもください。あ、セットで袋わけでください。」
人見先輩は何の躊躇もなく、店員さんに注文をしたかと思えば、僕が注文する予定だったものも一緒に注文をした。僕は単に聞き間違えたのかと思ったが、そうではないらしい。どういうことかと聞こうとしたがその前に、スマホの電子決済を使用し、スマートに会計を終わらせると二つの袋を受け取り、そのうち一つを僕に手渡してきた。
「ん。」
「……これって?」
「今日のお礼的なやつ。」
「お、お礼?」
「デートが楽しかったお礼。」
「え、いや、いただけませんよ!お金払います。」
「じゃあ次一緒に行くための対価ってことで。」
そう言われてしまったら受け取らないわけにはいかない。
何せ好きな人から次も一緒にデートに行こうと誘われているようなものだ。
僕は渋々人見先輩からチョコとバタークッキーのセットが入った袋を受け取ると、お礼を告げる。先輩は左側の口角だけを上げ、ドヤ顔のような笑みを浮かべながら小さく「ん」と呟いた。
「今日はありがとうございました。」
「こちらこそ。カフェのパフェも良かったし、クッキーの店も知れて良かった。」
「人見先輩が良かったなら、僕も良かったです!」
「ん。じゃあ今日はこれで。」
「はい、また学校で。」
「ん。」
人見先輩は去り際、またその大きな背中で語りながら、右手だけをあげ僕に合図を送る。
僕はその後ろ姿が見えなくなるまで見送ると、大きな深呼吸でもするように溜息をついた。
「かっこよすぎるだろ……。」
突如駅構内でしゃがみ込んでしまったからか、駅を行き交う人の視線は僕に必然的に集まった。しかし僕はそれを気にする余裕が無いほど、人見先輩との次のデートを楽しみに浮かれていた。
「俺さ、弓道がやりたかったわけじゃないんだよ。」
「……そうなんですか?」
「そ。俺さ自分の心が乱されるのめちゃくちゃ嫌なんだよね。まぁそれは俺の心が弱いのが悪いんだけどさ。例えば誰かに告白されたり。そうするとさ、嫌でもその告白してきたやつの事意識するだろ。それが恋愛感情があろうとなかろうと。」
「たしかにそうですね。何かと気まずかったりしますよね。」
「だろ?そういうしょーもないことで気を使ったりしないといけないのが俺苦手なんだよね。だから俺の趣味って言うかよくやってることがあって、それが精神統一とか瞑想なんだよね。」
「……メンタル面を鍛えるってことですか?」
「ん。で、その延長線で弓道をはじめたんだよね。だから弓道やりたくて始めたわけじゃなくて、メンタル鍛えるために弓道始めたんだよ。でもさ精神統一とかそういう面では弓道は良かったけど、鍛えられるわけじゃなかったよ。」
「……弓道は集中力を高めるのには向いていたけど、メンタルを鍛えられるわけじゃなかったってことですか?」
人見先輩はその長い先割れスプーンで何口か食べた後に僕の質問に対して肯定するようにぶっきらぼうな返事をする。そんな人見先輩は自分自身の話をするときは恥ずかしいのか、はたまたパフェに集中しているのか、僕と視線が合うことはなくずっとパフェを見ながら僕と会話をしている。
「あ、でも弓道自体は楽しかったよ。でもその楽しさが仇になったんだよ。」
「仇……ですか……。先輩は全国大会でも優勝するくらいの実力なんですから、仇とかないと思うんですけど。」
「いやその優勝がダメだったんだよね。会場で表彰されるとかは別に良かったけど、校舎に弾幕掛けたり、優勝したことを全校集会とかで表彰したりさ。そのせいで今までの比にならないくらい声を掛けられたよ。毎日顔も知らない女子生徒に話しかけられたり、話したこともない同学年の男からも勝手に友達認定されたり。耐えきれなかった。」
「………………。」
「だから辞めたんだ。全部。」
「……全部?それって……。」
そこまで聞いて、僕はなんとなく察していた。学校での人見先輩のあの冷ややかな視線に刺すような口調。それはきっと人見先輩なりの防衛だったのだろう。僕が学校で感じていた違和感はこれだったのだ。男子生徒はわからないが、多くの女子生徒はきっと人見先輩に告白をして、こっぴどく振られたのだろう。だから三年の先輩たちは人見先輩への態度がよそよそしかったのだと思う。それを知らない生徒、それこそ先日学食で声を掛けてきた一年の女子生徒はかっこいい先輩という噂だけを聞いて、ああいう感じで先輩に声をかけて怒らせるのだろう。
人見先輩が僕が何を考えているのか大方の想像が付いたようで、少し微笑みながら僕を怖がらせないように呟いた。
「そ。弓道も友人関係も何もかも。正直楽になったよ。でもここ直近でそんな楽な時間は終わりを迎えたよ。」
「……もしかして僕のせいですか?」
「……最初の印象は最悪だったよ。」
「……。」
「あの路地は偶然通りかかったんだ。普段なら路地裏で誰かが暴行受けていても気にも留めないと思うよ。いや気にはするだろうけど、それでもわざわざ助けに行こうという正義感は生まれないかな。だから新島を助けたときは自分でも驚いたよ。」
人見先輩は笑いながら淡々と会話を続けた。
「最初はさそれこそ同じ学校の制服だったし、困ってそうだったってのもあるけど、どこかで見たことある気がして声かけたんだよね。てかそこで声かけなかったから、なんか俺って結構最低な人間じゃん?精神的にもよくないなって思って助けた。そしたら次の日俺のクラスの前でそいつが女子生徒に囲まれて困ってんの。こいつどんだけ俺の心を乱してくるんだよって思った。でもまあ助けたよ。困ってたし。」
「……。」
「でもだんだんと、そんな考えは変わっていったよ。」
僕は驚いて俯きつつあった顔を思いっきり上げた。
「え?」
「印象が最悪な奴とカフェとかいかねーだろ。少なくとも今は好印象だよ。そうだな。あえて言うなら弟的なそんな存在かな。」
「お、弟?」
「ん。放っておけない感じ?俺一人っ子だからわかんないけど、弟がいたらこんな感じなのかなって。」
それは僕にとってあまりにも残酷なモノだった。弟のような存在。つまりこれは恋愛対象にはならないと言うことを意味していた。よく言う男女間で男性が女性に対して、こいつは妹みたいな存在だから恋愛には発展しないのと同じ。もしくはそれ以上の効果を持つ言葉だ。
そもそも先輩の性対象を知らないが、これでは先輩の性対象が女性でもたとえ男性であっても、僕のことを好きになることは無いだろう。
上げた顔がだんだんとまた俯き始める。
人見先輩はそれに何かを察したのだろう、心配そうな声で僕に声を掛けた。
「大丈夫か?」
「え、あ、はい!大丈夫です。弟的な存在……嬉しいです!先輩が誰かと仲良くしているところなんて見たことなかったので。そうすると僕は人見先輩の中じゃだいぶ上位に入るくらいの人間ってことですか?」
人見先輩は僕の問いかけに対して、右斜め上を見上げ数秒考え込んだ。
「……俺、学校じゃ新島以外と喋んねーよ。」
「そうなんですか?」
「他学年だと声を掛けられることはあっても、同学年だとねーな。誰かと学校で昼食食ったりしたのだってそれこそ一年ぶりとかじゃねーかな。」
「それは……光栄ですね。」
「なんだそれ。そういえばこうやって休日家族以外とどこか出かけたりするのは初めてかもな。」
「え!!!!!」
「うるさっ!」
僕はその衝撃的な発言に驚き、人見先輩を驚かせただけではなく、お店のスタッフさんの視線までもを集めることとなった。
「す、すみません。取り乱しました。」
「いやいいけどさ。そんなに驚くことか?」
「いえ、先輩ならいろんな方とデートとか行かれてるでしょうから、お出かけとかは慣れてるんだと思ってました。」
「デートねぇ……。なら今日の新島とのデートが初デートだな。」
「なっ!」
僕は顔が一気に赤くなる。それを見た人見先輩はそれが面白かったのか、単に僕をからかいたかったのか分からないが、楽しそうにしながら残りのパフェを頬張っていた。
惚れた弱みだろうか。僕は何も言い返せないまま、人見先輩と同じくパフェを頬張った。
その後数口食べ進めていると、急に僕の目の前にチョコがたっぷりかかった生クリームがすくってるスプーンが差し出された。突然のことに動揺していると人見先輩は口を開いた。
「あーん、して。」
「え?」
「新島のイチゴのパフェも食べたいから交換しねえ?だからあーんして。」
「………………。」
これは俗に言う間接キスではないのだろうか。
人見先輩は僕のことを弟のような存在としか思っていないため、きっとこれは何の感情も無い、ただ単に本当に僕の食べているイチゴのパフェを食べたかったが故の行動なのだろう。しかし僕にはそんなこと関係ない。僕は人見先輩のことが好きなのだ。
今まで恋人がいない歴イコール年齢の僕にとってこれは一大イベントである。
そんな僕をお構いなしに人見先輩はスプーンを更に僕に近づけ、顎を使い食べるように指示を出す。そんなイケメンに僕は逆らえるわけもなく、ゆっくり。ほんとにゆっくりと口を大きく開けて、人見先輩が差し出しているスプーンを頬張った。
今度はそれを確認した人見先輩が「あーん」と大きく口を開けて待機していた。これは食べさせろということだろうが、これまた覚悟のいるイベントが今まさに始まろうとしていた。
僕はパフェで一番大きなイチゴが載っている部分を何の躊躇もなくすくうと、震える手を抑えながら人見先輩の口の中へとスプーンを入れる。先輩は目で笑い、スプーンにかじりつく勢いで大きなイチゴをおいしそうに頬張った。
「んまぁ。」
「……満足そうで何よりです。」
「新島は?美味かったか?」
「は、はい!めちゃくちゃおいしいです!」
「そ、ならいいよ。」
人見先輩は満足したのか、黙々と食べ進め、たまに僕に断りもなくイチゴパフェをちょくちょくつまんでいた。そんなにおいしかったのかと「もう一つ頼みますか?」と聞いたところ、「え、つまみ食いしてたのバレてた?」と茶目っ気のある笑顔に続けて「今日はいいや。また今度来た時食おうぜ。」と目尻に綺麗なシワを寄せながらそう言った。
僕は次があるのかと少し二ヤつきが止まらなかった。
✂ ——— ✂ ——— ✂ ——— ✂ ——— ✂
「ほんとに驕ってもらってよかったのか?」
「もちろんです!お詫びも兼ねてでしたので。」
人見先輩は会計時まで財布を出して俺が出すの一点張りであったが、流石に先日のお詫びと、そもそも今日のデート(?)に誘ったのは僕のため、誘った側が出すと言い続け、渋々ながらも財布をしまってもらうことに成功した。
今日の要件も終わったので、カフェを出たらもう帰路に就くだけだと思っていたが、予想に反し人見先輩から声を掛けてきた。
「腹ごしらえすんだし、どっか行くか?」
「え?いいんですか?」
「……逆にカフェだけなんか?」
「いえ、カフェ行きましょうって誘ったのでカフェで解散だと思ってました。」
「ふーん……。新島はこの後時間あるの?」
「いえ、特に予定も無いので、空いてますけど……。」
「じゃあきまり、デートの続きしよっか。」
「………………はい?」
人見先輩はそう言うと、僕の手を掴み駅に向かって歩き始めた。駅に向かうということはどこかに電車で向かうもんだと思っていたがそうではないみたいだ。
駅に着いた人見先輩は一言。
「この間くれたクッキーが売ってる店どこ?」
となかなかに端的に要件を伝えてきた。思い返してみればクッキーは喜んで食べてくれていたが、そのときに変なことを聞かれた気がする。当時はそれが何を意味するのかは分からなかったが、今ならその意味が多少なりとも分かる気がした。
「あのクッキーならこっちの店ですよ。あの……言いづらいかもしれませんがこのクッキーをあげたとき先輩、手作りかどうか聞いてきたじゃないですか。それってもしかして過去に何か変なもの入れられてたりしてたんじゃないですか?」
「……ん。マジで怖いよ。クッキーから毛とか生えてたら。」
「…………すみません。想像して気持ち悪くなってきました。」
「大丈夫か?」
人見先輩はそういって僕を心配するように、僕の顔を覗き込んできた。その優しさに惚れ惚れすると共に、好きな人の顔が至近距離にあることに動揺してしまい、更に人見先輩を心配させてしまうことになった。
人見先輩はそんな僕の態度に焦ったのか、近くの自動販売機に走り、水を買って戻って来てくれた。
「飲め!」
「あ、ありがとうございます。すみません。僕から聞いておいて……。」
「全然。むしろ急に話してすまん。」
「いえ、聞いたのは僕ですから……。だから人見先輩は出来合いのものしか口にしない感じなんですか?」
「ん。」
人見先輩のその短く端的な回答はすごく悲しげに聞こえた。
きっとそのコトがトラウマで食べたいものも食べることができなかったことがあるんじゃないかと思った。そうなれば人見先輩がわざわざクッキーの売り場を聞いてきたのも納得が行く。
「もう大丈夫です!クッキー見に行きましょうか!」
「ん。」
日曜日の駅は午後となり、今朝見たときよりかは明らかに人の数が多くなっていた。それでもどこかのお店が混んでいるとかそういうわけではなく、単に電車を使う人口が多いだけという印象で、人の流れに身を任せれば案外すぐに目的のクッキーが売っている店にたどり着いた。
「たくさん種類あんのね。」
「そうなんですよ。人見先輩にあげたのがこのチョコとバタークッキーのセットだったんですけど、生姜が苦手でなければジンジャークッキーがおいしいのでお勧めです。」
「へぇ。ん、ここ紅茶のティーパックも売ってんのね。なら新島おすすめのジンジャークッキーと適当な紅茶買おうかな。」
「いいですね!ここは紅茶もすっごくおいしいんですよ。」
「ん。新島は何か買う?」
「そうですね……まだまだ占いでもらったお菓子があるのであまりお菓子は増やしたくないのですが、少しならいいですよね。先輩にあげたチョコとバタークッキーのセットを買おうと思います。」
「そ。すみません。ジンジャークッキーと紅茶の組み合わせ。それとチョコとバタークッキーのセットもください。あ、セットで袋わけでください。」
人見先輩は何の躊躇もなく、店員さんに注文をしたかと思えば、僕が注文する予定だったものも一緒に注文をした。僕は単に聞き間違えたのかと思ったが、そうではないらしい。どういうことかと聞こうとしたがその前に、スマホの電子決済を使用し、スマートに会計を終わらせると二つの袋を受け取り、そのうち一つを僕に手渡してきた。
「ん。」
「……これって?」
「今日のお礼的なやつ。」
「お、お礼?」
「デートが楽しかったお礼。」
「え、いや、いただけませんよ!お金払います。」
「じゃあ次一緒に行くための対価ってことで。」
そう言われてしまったら受け取らないわけにはいかない。
何せ好きな人から次も一緒にデートに行こうと誘われているようなものだ。
僕は渋々人見先輩からチョコとバタークッキーのセットが入った袋を受け取ると、お礼を告げる。先輩は左側の口角だけを上げ、ドヤ顔のような笑みを浮かべながら小さく「ん」と呟いた。
「今日はありがとうございました。」
「こちらこそ。カフェのパフェも良かったし、クッキーの店も知れて良かった。」
「人見先輩が良かったなら、僕も良かったです!」
「ん。じゃあ今日はこれで。」
「はい、また学校で。」
「ん。」
人見先輩は去り際、またその大きな背中で語りながら、右手だけをあげ僕に合図を送る。
僕はその後ろ姿が見えなくなるまで見送ると、大きな深呼吸でもするように溜息をついた。
「かっこよすぎるだろ……。」
突如駅構内でしゃがみ込んでしまったからか、駅を行き交う人の視線は僕に必然的に集まった。しかし僕はそれを気にする余裕が無いほど、人見先輩との次のデートを楽しみに浮かれていた。