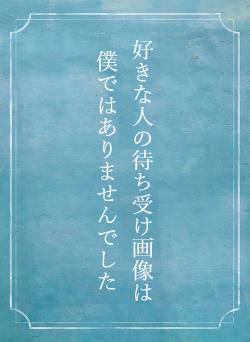「ん?あぁ、新島か。」
「わ!人見先輩こんにちは。先輩も学食なんですね。」
「いや今日はたまたま。いつもは購買なんだけど混んでたから。新島はいつも学食なの?」
「いつもってわけじゃないです。お弁当の日と学食の日があるって感じです。まぁお弁当の日でも学食には来ちゃうんですけどね……。」
昼休みの時間になったため僕はいつも通り学食へ足を運んだところ、食券の前で考え込んでいる人見先輩を発見した。普段なかなか見ることのできない人見先輩の考え込む姿に目を奪われていると、その視線に気づいたのか、人見先輩から声を掛けてくれた。
「そうなんだ。あ、もしかして食券買いたかった?」
「いえ!持ってきているので大丈夫です。」
「偉いね。自分で作ってるの?」
「実は……」
僕はそう言いながら、左手で持っていた紙袋の中身を見せた。紙袋の中身はお弁当箱が入っているわけではなく、到底一人で食べる量とは思えないほど大量のお菓子が入っていた。お菓子は大袋ではなく、個包装になっているお菓子であり、それは一度ですべてを食べ終える気がないことを示していた。
「……これは弁当ではなくないか?」
「そう……なんですよね。」
「どうしたんだ?こんな大量の菓子。」
「これは占いのお礼でいただいたものですね。」
それを聞いた人見先輩は「あぁ〜」と大きな声を上げ、納得したかのように左手の掌に右手で作った拳を振りかざす。
「それ聞いたことあるわ。新島に占ってもらうにはジュースか菓子を対価にするってやつだろ?」
「対価って……そんな大応なものじゃないですよ。」
「なんで菓子なんだ?金取ればいいじゃねーか。」
「流石に学生間でのお金を使ったやり取りは問題になりますからね。それに最初はお菓子とかなくても占ってたんですけど、ある時占ってくれたお礼って言われてお菓子をいただいたことが始まりで、いつしかそのような噂が広まってしまいました。」
「なるほど……。やっぱり新島も大変なんだな。」
「……あの、もしよければお菓子の消費手伝ってくれませんか?」
「え?」
✂ ——— ✂ ——— ✂ ——— ✂ ——— ✂
学食の奥にある四人がけのテーブルに僕と人見先輩は向かい合わせで座っている。この鮫島高等学校で一二を争うほどの有名人(?)である僕と人見先輩が同じ席に座っているからか、学食の入口から一番遠い席にも関わらず、ほぼすべての席から視線を感じる。
正直言って多くの人に見られるのは慣れているとは言え恥ずかしいという感情はある。それは人見先輩も同じなのだろう。多くの視線を感じることには慣れているのか、そのことには一切触れることなく、目の前に座っている僕に話しかける。
「ほんとにもらっていいの?占いのお礼の菓子なんだろ?」
「え?はい!そもそも僕一人じゃ食べきれないので……。むしろ先輩こそお菓子だけで大丈夫ですか?別に好きなもの食べてもいいんですよ?」
「そんなに食べたいものもなかったし大丈夫。」
僕は「どうぞ」と紙袋を席の真ん中に置き、人見先輩がお菓子を取りやすいようにする。人見先輩はほんとに軽い会釈のような形で首を動かし「どもっ」と小さく呟くと、紙袋から個包装のお菓子を無作為に何個か取り出し、袋を開けそれを口へと運ぶ。
その一連の流れを僕は瞬きすることなく目で追っていた。
人見先輩のことを好きだと自覚してから、僕も自分の知らない一面があることに驚いている。好きな人はどんな歩き方をするのか。どんな食べ方をするのか。どんな話し方をするのか。その一挙手一投足が気になって仕方がない。僕は意外にも溺愛するタイプかもしれない。しかしこれが行き過ぎてしまうと重いと感じられる原因になるかもしれないので、気をつけなければならないポイントでもあるだろう。そんなことを考えていると人見先輩がチラッと僕に視線を向けると、短い単語を呟いた。
「見すぎ。」
「え、あ、ごめんなさい!」
「別にいいけど。新島は食べないの?」
「た、食べます。」
流石に見すぎてしまっていたのだろう。人見先輩も僕の視線に気づき僕にそのことを告げる。それに動揺を隠せずどもった返事としてしまったが、僕も昼食と言うよりお菓子を消費するために紙袋の中からいくつかのお菓子を人見先輩と同様無作為に取り出し、食べ始める。
お菓子は塩気のあるものからチョコ系の甘いお菓子など僕と人見先輩を簡単に飽きさせることはなかった。人見先輩は食事中は特に口を開くことはないのか、それとも僕と離すことがないのかはわからないが口数少ない。そもそも人見先輩自体が口数が少ないタイプのため、それがあっているかどうかはわからない。
「あの人見せんぱ……」
「ご一緒していいですかぁ?」
僕が人見先輩に話しかけようとしたとき、頭上からした女性の声に僕の話し声はかき消されてしまった。見上げるとそこには髪にカールをかけ、スカートは膝よりかなり上の位置で履いている女子生徒とこれまた長い黒髪をツインテールにし、校則違反だろうミニスカートに加え、ニーハイソックスを履いて明らかに太ももを見せに来ている女子生徒の二人がいた。
僕にはわかる。十中八九人見先輩目当てで声をかけてきたのだろう。甘えるような猫なで声で声を掛けた時点で察しはついていたが、ここまで露骨だとさすがの僕も少し笑ってしまいそうになる。僕はチラッと人見先輩の表情を確認すると、一切彼女たちの方を向くことなく、パクパクとお菓子に全集中していた。
彼女たちはそれを気にしてないのか、気づいていないのか。はたまた空気が読めないのかわからないが、僕や人見先輩が返事をする前に同じテーブルに座った。
「え、人見先輩って昼食お菓子なんですかぁ。よかったら私の食べます?」
「そうですよぉ!いっぱい食べてください。」
彼女たちはそう言うと、先程買ってきたであろうトレーの上にのった日替わり定食を人見先輩に差し出した。が、それにも一切触れることなくモクモクとお菓子を食べ進める。するとさすがの彼女たちも気がついたのか、声掛けの志向を変えてきた。
「先輩ってお菓子好きなんですかぁ?」
「えー、ウチらもらっていいですか?先輩と同じお菓子もらっちゃおーっと。」
どうしても彼女たちは人見先輩と話したいのだろう。今度は人見先輩の食べているお菓子に興味を示し、僕と人見先輩の間に置かれた紙袋の中からなんの断りもなく、今人見先輩が食べているお菓子と同じモノを探し出すべく物色し始める。
僕もこれはチョットと感じていたところ、人見先輩は急に勢いよく立ち上がった。椅子こそ倒れることはなかったが、その勢いからして倒れなかったのは奇跡だろう。急に立ち上がったことに対して僕と彼女らは今度は人見先輩を見上げる。そんな視線を気にすることなく、人見先輩は彼女らが物色しているお菓子が大量に入った紙袋を左手で奪い取るようにガサツに掴むと、右手で僕の左手を掴み強制的に僕を立たせた。
「うぜぇよ。新島と飯食ってんだろ。見てわかんねぇのか。」
先日は見ることのなかった人見先輩の冷ややかな視線に加え、刺すような低い声で非常識な女子高生二人を黙らせるだけではなく、学食全体の体感温度を三度ほど下げると、人見先輩はそのまま僕の手を引いて、先日屋上へ上がったときと同じ道をたどる。その間人見先輩は僕の手を離すことはなかった。
屋上へ向かっていたと思ったが、屋上に出入りできる扉の前で人見先輩は足を止めた。夏だからなのか少し汗ばんだ手で握っていた僕の手を解放すると、ほんの少しだけ申し訳なさそうな声で僕に声を掛けた。
「……痛くなかったか?」
「は、はい。大丈夫です。せ……先輩こそ大丈夫ですか?」
「……ん。てかごめん。」
「え、そんな謝らないでください!僕もなにかうまい返しができればよかったんですけど……。」
「全然。屋上は暑いからここで食べようか。」
そう言って人見先輩は屋上の出入り口前にある踊り場のような場所に腰を掛け、僕も座れと言わんばかりに素早く二度、自身の横を叩いた。僕はなんだかかわいいなと感じながら人見先輩と向かい合うように座り込む。
実際に座ってみるとわかるが、踊り場の床は思っていた以上に冷たく、夏場であってもそれなりに快適に過ごせるくらいには体温を下げてくれる。学食は冷房が効いていて快適であったが、僕個人としては踊り場の温度もなかなかに適温だと感じていた。人見先輩も踊り場の涼しさが気に入ったのだろう。ペタペタと踊り場のいろんな箇所を触って確かめていた。
人見先輩は握りしめていた紙袋をまた僕との間に置くと、個包装のお菓子を無作為に取り出し、黙々と食べ進めていく。こう見ると人見先輩は案外お菓子とかそういう甘いものが好きなのだろうか。そんなことを考えていると人見先輩が口を開いた。
「また見てる。」
「あ、ごめんなさい。」
「いや、いいんだけどね。てかさっきの女は同級生?」
「あぁ……どうなんでしょう。人見先輩のことを先輩呼びしていたので一年か二年かで確定だと思うんですけど、同級生に先程の二人がいたかは……ごめんなさい。覚えてないです。」
「謝らなくていいよ。図々しかったし、なかなかに失礼な態度だったからてっきり知り合いかなにかだと思ったよ。」
「まさか……。あの態度を知り合いがしてたら流石に注意しますよ。」
「まぁそうだよな。」
そういいながら人見先輩はまた黙々とお菓子を食べ進める。
このままでは人見先輩を不快にさせたまま終わってしまう。そう考えた僕は思い切って自分から話を振ることにした。
「人見先輩はお菓子好きなんですか……?」
「……どちらかと言えば好き。糖分取るといろいろ満たされるし。」
「そうなんですね!それじゃあ今度僕とカフェとか行きませんか?僕が『お菓子食べませんか?』なんて言ったから、せっかくのお昼でしたのに気分を害されたので……そのお詫びということで……。どうですか?」
「……………………いいよ。でも新島のせいじゃないから気にしなくていい。たぶん俺が普通に食券買って食べててもあいつらは声かけてきたよ。」
人見先輩はそう言うと、まっすぐ胡座をかいていた状態から少しだけ重心を左に寄せ、パンツのポケットからスマホを取り出すと、慣れた手つきで画面を操作しQRコードを僕に見せてきた。
「んっ」
「……え?」
「いや連絡先。カフェ行くんだろ?LINE知らねーと連絡取れねーじゃん。」
「あ!はい!ありがとうございます。」
僕もスマホを取り出し、QRコードを読み取ると挨拶としてタロットカードをモチーフにしたデザインのキャラクターで、その中から恋人の正位置のスタンプを送った。そのスタンプを確認したのか、人見先輩はふふっと顔を隠しながら笑い、次は先輩からスタンプが送られてきた。それは猫が土下座をしているようなスタンプで一言「よろしく」とだけ書かれていた。
するとタイミングよくまた昼休みの終了を知らせるチャイムが校舎全体に響き渡るように鳴る。それを聞いた人見先輩は「菓子ありがと。カフェ楽しみにしてるよ。」と言い残し、自身の教室がある一階へと階段を降りて行った。
僕はというと、好きな人と連絡先を交換できるとは思っておらず、嬉しさのあまり舞い上がって恋人の正位置のスタンプを送ってしまったことへの若干の後悔と恥ずかしさ。そして今度人見先輩とカフェに行けることへの喜びで顔は夕日よりも赤くなっていた。
「……カフェ調べとこ。」
僕はそう呟くと、ゆっくりとしたペースで階段を降り自分の教室へと戻った。
「わ!人見先輩こんにちは。先輩も学食なんですね。」
「いや今日はたまたま。いつもは購買なんだけど混んでたから。新島はいつも学食なの?」
「いつもってわけじゃないです。お弁当の日と学食の日があるって感じです。まぁお弁当の日でも学食には来ちゃうんですけどね……。」
昼休みの時間になったため僕はいつも通り学食へ足を運んだところ、食券の前で考え込んでいる人見先輩を発見した。普段なかなか見ることのできない人見先輩の考え込む姿に目を奪われていると、その視線に気づいたのか、人見先輩から声を掛けてくれた。
「そうなんだ。あ、もしかして食券買いたかった?」
「いえ!持ってきているので大丈夫です。」
「偉いね。自分で作ってるの?」
「実は……」
僕はそう言いながら、左手で持っていた紙袋の中身を見せた。紙袋の中身はお弁当箱が入っているわけではなく、到底一人で食べる量とは思えないほど大量のお菓子が入っていた。お菓子は大袋ではなく、個包装になっているお菓子であり、それは一度ですべてを食べ終える気がないことを示していた。
「……これは弁当ではなくないか?」
「そう……なんですよね。」
「どうしたんだ?こんな大量の菓子。」
「これは占いのお礼でいただいたものですね。」
それを聞いた人見先輩は「あぁ〜」と大きな声を上げ、納得したかのように左手の掌に右手で作った拳を振りかざす。
「それ聞いたことあるわ。新島に占ってもらうにはジュースか菓子を対価にするってやつだろ?」
「対価って……そんな大応なものじゃないですよ。」
「なんで菓子なんだ?金取ればいいじゃねーか。」
「流石に学生間でのお金を使ったやり取りは問題になりますからね。それに最初はお菓子とかなくても占ってたんですけど、ある時占ってくれたお礼って言われてお菓子をいただいたことが始まりで、いつしかそのような噂が広まってしまいました。」
「なるほど……。やっぱり新島も大変なんだな。」
「……あの、もしよければお菓子の消費手伝ってくれませんか?」
「え?」
✂ ——— ✂ ——— ✂ ——— ✂ ——— ✂
学食の奥にある四人がけのテーブルに僕と人見先輩は向かい合わせで座っている。この鮫島高等学校で一二を争うほどの有名人(?)である僕と人見先輩が同じ席に座っているからか、学食の入口から一番遠い席にも関わらず、ほぼすべての席から視線を感じる。
正直言って多くの人に見られるのは慣れているとは言え恥ずかしいという感情はある。それは人見先輩も同じなのだろう。多くの視線を感じることには慣れているのか、そのことには一切触れることなく、目の前に座っている僕に話しかける。
「ほんとにもらっていいの?占いのお礼の菓子なんだろ?」
「え?はい!そもそも僕一人じゃ食べきれないので……。むしろ先輩こそお菓子だけで大丈夫ですか?別に好きなもの食べてもいいんですよ?」
「そんなに食べたいものもなかったし大丈夫。」
僕は「どうぞ」と紙袋を席の真ん中に置き、人見先輩がお菓子を取りやすいようにする。人見先輩はほんとに軽い会釈のような形で首を動かし「どもっ」と小さく呟くと、紙袋から個包装のお菓子を無作為に何個か取り出し、袋を開けそれを口へと運ぶ。
その一連の流れを僕は瞬きすることなく目で追っていた。
人見先輩のことを好きだと自覚してから、僕も自分の知らない一面があることに驚いている。好きな人はどんな歩き方をするのか。どんな食べ方をするのか。どんな話し方をするのか。その一挙手一投足が気になって仕方がない。僕は意外にも溺愛するタイプかもしれない。しかしこれが行き過ぎてしまうと重いと感じられる原因になるかもしれないので、気をつけなければならないポイントでもあるだろう。そんなことを考えていると人見先輩がチラッと僕に視線を向けると、短い単語を呟いた。
「見すぎ。」
「え、あ、ごめんなさい!」
「別にいいけど。新島は食べないの?」
「た、食べます。」
流石に見すぎてしまっていたのだろう。人見先輩も僕の視線に気づき僕にそのことを告げる。それに動揺を隠せずどもった返事としてしまったが、僕も昼食と言うよりお菓子を消費するために紙袋の中からいくつかのお菓子を人見先輩と同様無作為に取り出し、食べ始める。
お菓子は塩気のあるものからチョコ系の甘いお菓子など僕と人見先輩を簡単に飽きさせることはなかった。人見先輩は食事中は特に口を開くことはないのか、それとも僕と離すことがないのかはわからないが口数少ない。そもそも人見先輩自体が口数が少ないタイプのため、それがあっているかどうかはわからない。
「あの人見せんぱ……」
「ご一緒していいですかぁ?」
僕が人見先輩に話しかけようとしたとき、頭上からした女性の声に僕の話し声はかき消されてしまった。見上げるとそこには髪にカールをかけ、スカートは膝よりかなり上の位置で履いている女子生徒とこれまた長い黒髪をツインテールにし、校則違反だろうミニスカートに加え、ニーハイソックスを履いて明らかに太ももを見せに来ている女子生徒の二人がいた。
僕にはわかる。十中八九人見先輩目当てで声をかけてきたのだろう。甘えるような猫なで声で声を掛けた時点で察しはついていたが、ここまで露骨だとさすがの僕も少し笑ってしまいそうになる。僕はチラッと人見先輩の表情を確認すると、一切彼女たちの方を向くことなく、パクパクとお菓子に全集中していた。
彼女たちはそれを気にしてないのか、気づいていないのか。はたまた空気が読めないのかわからないが、僕や人見先輩が返事をする前に同じテーブルに座った。
「え、人見先輩って昼食お菓子なんですかぁ。よかったら私の食べます?」
「そうですよぉ!いっぱい食べてください。」
彼女たちはそう言うと、先程買ってきたであろうトレーの上にのった日替わり定食を人見先輩に差し出した。が、それにも一切触れることなくモクモクとお菓子を食べ進める。するとさすがの彼女たちも気がついたのか、声掛けの志向を変えてきた。
「先輩ってお菓子好きなんですかぁ?」
「えー、ウチらもらっていいですか?先輩と同じお菓子もらっちゃおーっと。」
どうしても彼女たちは人見先輩と話したいのだろう。今度は人見先輩の食べているお菓子に興味を示し、僕と人見先輩の間に置かれた紙袋の中からなんの断りもなく、今人見先輩が食べているお菓子と同じモノを探し出すべく物色し始める。
僕もこれはチョットと感じていたところ、人見先輩は急に勢いよく立ち上がった。椅子こそ倒れることはなかったが、その勢いからして倒れなかったのは奇跡だろう。急に立ち上がったことに対して僕と彼女らは今度は人見先輩を見上げる。そんな視線を気にすることなく、人見先輩は彼女らが物色しているお菓子が大量に入った紙袋を左手で奪い取るようにガサツに掴むと、右手で僕の左手を掴み強制的に僕を立たせた。
「うぜぇよ。新島と飯食ってんだろ。見てわかんねぇのか。」
先日は見ることのなかった人見先輩の冷ややかな視線に加え、刺すような低い声で非常識な女子高生二人を黙らせるだけではなく、学食全体の体感温度を三度ほど下げると、人見先輩はそのまま僕の手を引いて、先日屋上へ上がったときと同じ道をたどる。その間人見先輩は僕の手を離すことはなかった。
屋上へ向かっていたと思ったが、屋上に出入りできる扉の前で人見先輩は足を止めた。夏だからなのか少し汗ばんだ手で握っていた僕の手を解放すると、ほんの少しだけ申し訳なさそうな声で僕に声を掛けた。
「……痛くなかったか?」
「は、はい。大丈夫です。せ……先輩こそ大丈夫ですか?」
「……ん。てかごめん。」
「え、そんな謝らないでください!僕もなにかうまい返しができればよかったんですけど……。」
「全然。屋上は暑いからここで食べようか。」
そう言って人見先輩は屋上の出入り口前にある踊り場のような場所に腰を掛け、僕も座れと言わんばかりに素早く二度、自身の横を叩いた。僕はなんだかかわいいなと感じながら人見先輩と向かい合うように座り込む。
実際に座ってみるとわかるが、踊り場の床は思っていた以上に冷たく、夏場であってもそれなりに快適に過ごせるくらいには体温を下げてくれる。学食は冷房が効いていて快適であったが、僕個人としては踊り場の温度もなかなかに適温だと感じていた。人見先輩も踊り場の涼しさが気に入ったのだろう。ペタペタと踊り場のいろんな箇所を触って確かめていた。
人見先輩は握りしめていた紙袋をまた僕との間に置くと、個包装のお菓子を無作為に取り出し、黙々と食べ進めていく。こう見ると人見先輩は案外お菓子とかそういう甘いものが好きなのだろうか。そんなことを考えていると人見先輩が口を開いた。
「また見てる。」
「あ、ごめんなさい。」
「いや、いいんだけどね。てかさっきの女は同級生?」
「あぁ……どうなんでしょう。人見先輩のことを先輩呼びしていたので一年か二年かで確定だと思うんですけど、同級生に先程の二人がいたかは……ごめんなさい。覚えてないです。」
「謝らなくていいよ。図々しかったし、なかなかに失礼な態度だったからてっきり知り合いかなにかだと思ったよ。」
「まさか……。あの態度を知り合いがしてたら流石に注意しますよ。」
「まぁそうだよな。」
そういいながら人見先輩はまた黙々とお菓子を食べ進める。
このままでは人見先輩を不快にさせたまま終わってしまう。そう考えた僕は思い切って自分から話を振ることにした。
「人見先輩はお菓子好きなんですか……?」
「……どちらかと言えば好き。糖分取るといろいろ満たされるし。」
「そうなんですね!それじゃあ今度僕とカフェとか行きませんか?僕が『お菓子食べませんか?』なんて言ったから、せっかくのお昼でしたのに気分を害されたので……そのお詫びということで……。どうですか?」
「……………………いいよ。でも新島のせいじゃないから気にしなくていい。たぶん俺が普通に食券買って食べててもあいつらは声かけてきたよ。」
人見先輩はそう言うと、まっすぐ胡座をかいていた状態から少しだけ重心を左に寄せ、パンツのポケットからスマホを取り出すと、慣れた手つきで画面を操作しQRコードを僕に見せてきた。
「んっ」
「……え?」
「いや連絡先。カフェ行くんだろ?LINE知らねーと連絡取れねーじゃん。」
「あ!はい!ありがとうございます。」
僕もスマホを取り出し、QRコードを読み取ると挨拶としてタロットカードをモチーフにしたデザインのキャラクターで、その中から恋人の正位置のスタンプを送った。そのスタンプを確認したのか、人見先輩はふふっと顔を隠しながら笑い、次は先輩からスタンプが送られてきた。それは猫が土下座をしているようなスタンプで一言「よろしく」とだけ書かれていた。
するとタイミングよくまた昼休みの終了を知らせるチャイムが校舎全体に響き渡るように鳴る。それを聞いた人見先輩は「菓子ありがと。カフェ楽しみにしてるよ。」と言い残し、自身の教室がある一階へと階段を降りて行った。
僕はというと、好きな人と連絡先を交換できるとは思っておらず、嬉しさのあまり舞い上がって恋人の正位置のスタンプを送ってしまったことへの若干の後悔と恥ずかしさ。そして今度人見先輩とカフェに行けることへの喜びで顔は夕日よりも赤くなっていた。
「……カフェ調べとこ。」
僕はそう呟くと、ゆっくりとしたペースで階段を降り自分の教室へと戻った。