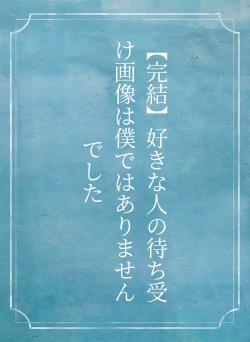「お前が鮫島の占い師か?」
そう告げる目の前の男子高校生は鮫島高等学校の制服ではない。鮫島高等学校は夏場は水色のカッターシャツに青と紺のストライプのネクタイ。グレーのベストにチェックのパンツという制服なのだが、男は違っていた。制服ではあるのだが、全体的に色が違う。清潔感のある白のカッターシャツなのだが、ネクタイはしておらずベストも身に着けていない。何なら前のボタンはすべて空いており、カッターシャツの下に着ていたオレンジのTシャツが見えているような状態だ。パンツは黒のスラックスであり、その制服から近くにあるもう一つの高校である水科《みずしな》高等学校であることがわかった。
そこまではわかったのだが、なぜこの男子高校生が僕に声をかけたかは理解できないでいた。そもそも僕は水科高等学校に友人や知り合いはおらず、占いのことが外部生徒に漏れている可能性もあるが、その場合男子高校生の殺意に満ちた表情と冷ややかな視線にはならないだろう。となれば他校の男子高校生が僕に声を掛ける理由は一つしかない。
「えっと……人違いですかね?」
「ああそうですか……とはならねえよ。お前が鮫島の占い師だろ?」
「な、何か御用ですか?占い希望であればまた後日でお願いしたいのですが……。」
「お前のせいでオレは沙耶《さや》と別れたんだぞ!」
彼の怒号は僕の声をかき消すように響き渡った。ここが裏路地でなければ数多くの通行人の視線を一斉に集めることになっただろう。しかしここは人通りもなく、ましてや近道するためにしか使わない人が一人通れるくらいの幅しかない。つまり僕と目の前の男子高校生以外この場にはいないということだ。
彼の手は血が滴るのではないかと思うほど強く握りしめられており、あまりの怒りに脚が震えているようにも見える。僕は知っている。この状態の人間と会話が成立することはない。つまりこの状況で僕が取るべき行動は逃げる一択だ。僕はその瞬間踵を返し、来た道を走って戻ろうとするが、突如右半身に強烈な痛みが走り、僕は裏路地の壁に吹き飛ばされた。壁に押し当てられた左半身にも痛みが走った。
喧嘩など無縁の人生を送ってきた僕にとってその衝撃はまるで骨が折れたかのような痛みを伴った。実際に骨折した経験はなく完全に感覚でしかないが、それと同等の痛みだと思う。路地裏の壁に押し付けられその場に倒れ込む僕に男子高校生は馬乗りになり、僕を逃さないように拘束すると、拳を振りかざした。
この男子高校生の口ぶりからして、彼はきっと僕の占いが原因で彼女と別れたのだろう。沙耶と言っていたが、正直覚えていない。ここ半年以上ほぼ毎日五人以上の占いをし続けているのだ。何度も占いを依頼する生徒もいるが一回しか占っていない生徒ももちろんいる。男女問わず占いは行っているが、比率で言えば明らかに女性の方が多い。それこそ鮫島高等学校のほとんどの女子生徒は占った気がする。体感のため実際には違うかもしれないが、鮫島高等学校は男女合わせて千人を超える生徒数だ。単純計算で女子生徒が五百人いることになるのだが、五百人すべての名前を覚えているわけがない。それは教師であっても難しいだろう。
「何ボサッとしてんだよ!」
そんなことを走馬灯のように瞬時に振り返っていると、男子高校生の振り上げられた拳は一直線に僕の顔面めがけて速度を上げた。僕は目を強く瞑り、少しでも防御をしようと手を前にかざす。ある程度の痛みを覚悟したのだが、五秒ほど経過しても痛みを感じることはなかった。僕は恐る恐る目を開けると、振り上げられた拳は誰かに腕を掴まれる形で宙に浮いた状態になっていた。
「何だよてめぇ!邪魔すんな!」
「鮫島高校の子、大丈夫?もうすぐ警察来るから。」
「はぁ?何警察とか呼んでんだよ!ふざけんなよ!」
拳を振りかざした男子高校生は警察という自身が当事者になると途端に面倒な存在に変わるそれの名前を聞き、大きな舌打ちをしながら掴まれた腕を振りほどき、ゆっくりと僕の上からその大きな体を退かすと、これまた大きなため息を付きながら去っていった。
僕と僕を助けてくれた同じ制服の男子高校生は走り去る男の背中を追い、見えなくなるとそこで初めて僕達は顔を合わせた。
「あ、ありがとうございます。危ないところを助けていただいて。」
「……全然。怪我は大丈夫そう?」
「は、はい。全身が痛いですが、打撲程度だと思うので、大丈夫だと思います。」
「そ。痛くなったら病院いきなよ。」
「はい!ありがとうございます。えっと警察まで呼んでいただいて、すみません。」
「あぁ警察は嘘だよ。警察って聞けば大抵は逃げ出すでしょ。」
「そうだったんですね。本当に助かりました。あの、同じ高校ですよね?」
「そうだけど。お前あれだろ?占いやってる子。」
「あ、はい……そうです。えっと先輩ですよね?」
「俺?三年の人見だ。」
「僕は二年の新島です。新島爽《にいじまそう》っていいます。あの人見先輩は僕の事知ってるんですか?」
「そりゃ知ってるだろ。鮫島高校に通ってるやつで新島のこと知らない奴の方が少ないだろ。それじゃ気を付けて帰れよ。」
人見先輩はそう言い残し、足早に去ってしまった。僕個人としては助けてもらったお礼をちゃんとしたかったし、もう少しお話をしてみたかった。
実というと僕は人見先輩のことを前から知っていた。自分の口からはあまり言いたくはないのだが、僕は鮫島高等学校ではそれなりに有名人である。それは先ほど人見先輩が言っていた通りで、僕のことを知らない人の方が少ないほどだ。そして鮫島高等学校にはもう一人、僕と同じくらい鮫島高等学校には知らない人の方が少ない有名人がいる。それが人見先輩だ。
人見孝仁《ひとみたかと》先輩は百八十センチという高身長に加え、女性だけではなく男性もが惚れ惚れするルックス。そして人見先輩の最大の魅力は弓道にある。弓道部のエースを務めていた人見先輩は試合中的を外したことはなく、全国大会で優勝するほどの腕前だ。全国大会優勝後は校舎に弾幕が降ろされ、かつ全校集会でも全校生徒の前で表彰されたため、基本的には全校生徒が人見先輩のことを知ってるだろう。
高身長とルックスに加え、スポーツも万能とくれば女子生徒が放っておくわけがなく、何人もの生徒が人見先輩に告白したという噂を聞いたことがある。実際僕に占いを依頼しに来る女子生徒のほとんどの片想いの相手が人見先輩であり、相性であったり、どうすれば付き合えるのか。実際に付き合うことは可能かなどの占いをしにくる女子生徒が多い。それだけ人見先輩は人気があるのだが、実際のところ人見先輩と付き合えた女子生徒はいないらしい。
僕がなぜこんなにも人見先輩のことに詳しいか。それは僕自身が人見先輩のことを前から気になっていたからである。それは恋愛対象とかそういう感情ではなく、女子生徒のほとんどが人見先輩との相性を占いに来るほどの人がどういう人なのかという、単純に人見先輩を人として気になっていたという話だ。
しかし僕の感情は今日この瞬間変化した。
「かっこいい……。」
この感情はテレビに映る俳優を見てかっこいいなと感じるものとは似て非なるものだ。心が暖かくなるのがわかる。そんな感情だ。僕を助け足早に去っていく人見先輩の背中は大きく、頼もしく思えた。
人見先輩にちゃんとお礼を言いたい。もっと話したい。
僕は自覚した。きっとこの感情は恋なのだと。
✂ ——— ✂ ——— ✂ ——— ✂ ——— ✂
翌日僕は昼休みの時間を使って、三年生の教室がある校舎の一階に脚を運んでいた。その理由はただ一つ。人見先輩に会いに行くためだ。
昨日、人見先輩への気持ちに気づいてから、人見先輩に少しでも近づくために駅の中にある少しお高めの雑貨屋で助けてもらったお礼の品と称して、オシャレなクッキーの詰め合わせと無難なところでタオル生地のハンカチに、これからの季節である夏をすぎて秋でも使用できるようないい匂いのする汗ふきシートを購入した。それらを紙袋に詰めて、僕は今一階をうろうろしている。
(……そもそも人見先輩って、何組なんだ?)
僕は自分の事前準備のなさにショックを受けつつも、人見先輩に会うために三年生の教室を少し覗いて人見先輩がいないことを確認すると、すぐに隣りの教室に移動するというのを何回か繰り返していた。すべての教室を回り終えたのだが、目当ての人見先輩を見つけることはできなかった。もしかしたら今日はお休みしているのかもしれないとガッカリしながら二階にある自分の教室に戻ろうとしたとき、僕は複数の女子生徒に取り囲まれていることに気がついた。
「あれ?新島くんだ。三年の教室に何か用?」
「あ、もしかして誰か探してる?占いの依頼?」
「放課後じゃなくても、占ってくれるの?え、ウチ占ってよ!」
「今お菓子持ってない!学食奢るとかでもいい?」
「え、てか右手どうしたの?湿布?怪我した感じ?」
「ホントだ。右足首にも湿布貼ってあるじゃん!怪我したの?大丈夫そ?」
「ウチ痛み止め持ってるよ!もらっとく?」
「いやそれロキソニンでしょ?怪我の痛みにも効くの?」
「え、わかんない。でも痛み止めだし?」
「あーね。ウチもその辺詳しくないからなぁ。」
「その辺って……サクラって詳しい分野あったっけ?」
「それは言わない約束だからぁ!」
僕を取り囲んだ三年の先輩は、三年の教室を見て回る僕に興味を示しつつも、僕にそんなに干渉するわけでもなく、仲間内で話を進めていく。取り囲まれてしまった僕は逃げることもできず、ましてや先輩たちの会話に入ることもできず、どうしようもできずただただ立ち尽くすことしかできないでいた。
正直僕は女性と話すことがそんなに得意ではない。多くの女性を占ってきておいて何を言っているんだと思われるかもしれないが、僕のする占いは会話をすると言うより、占いの結果を伝え、今後どうするべきかというアドバイスをするという形のため、基本一方的に話すことが多い。追加で言うとすれば占いは基本一対一でするものだ。そのため話せても一対一でなら多少なら可能なのだが、今のような一対多の状況には慣れておらず、どうしても自分から何かを切り出すということはできない。
そんなどうにもできない状況で一人たじろいでいると、突如として背後から左手を掴まれた。僕は昨日の体験もあり、若干の恐怖で表情が歪みながらも、勢いよく振り返り僕の手を掴んだ人間を確認する。そこは顔を見上げなければ表情を確認することができない程の高身長に加え、筋肉質な大きな体にゴツゴツとした男らしい手で僕の左手を掴んでいる人見先輩の姿がそこにはあった。
「新島に何か用?」
昨日僕を助けたときの声とは違う、低くそして若干冷たくも聞こえる声が僕の頭上から降り注いだ。その感じに僕を取り囲んでいた先輩たちが今度はたじろぐ形となった。僕はその状況に若干の違和感を覚えていると、女子生徒の一人が口を開いた。
「ひ、人見くん……。いや新島くんが三年の教室を見て回ってたから声かけただけだよ。」
「そ……。じゃあ新島借りていくから。」
「う、うん……。」
そう言うと人見先輩は掴んだ僕の左手を離すことはなく、そのまま僕を引っ張り階段を駆け上がった。その間人見先輩は声を掛けることはなかったが、その背中に優しさと温かさを感じながら僕は人見先輩に引かれるがままに、後をついていく。
到着したのは校舎の屋上であった。春やもう少し秋が深まった季節になれば屋上も多くの生徒で賑わっているのだが、夏真っ盛りのこの時期は直射日光に当てられる屋上の利用頻度は極端に下がるわけで、要するに僕と人見先輩以外、屋上に来ている生徒はいなかった。
「……新島はいつもああなの?」
「え、あ、いや。あのまた助けていただいてありがとうございます!」
「いや、いいけど。新島の大変だな。」
「そんな……人見先輩も大変なんじゃないですか?」
「まぁ……。と、いうか新島は俺のこと知ってたの?」
「先輩のこと知らない生徒の方が少ないですよ。」
「どこかで聞いたことのあるようなセリフだな。それで?三年の誰かに用だったのか?なんか女に囲まれて困ってそうだったから声かけたけど。」
僕はそれを聞いて人見先輩に用があったことを思い出す。持っていた紙袋を人見先輩に差し出し、「昨日はありがとうございました。これはお礼です!」となかなかに大きな声でそれを伝えた。
「え?俺に用だったの?わざわざごめん。昨日はあの後大丈夫だった?」
「はい、お陰様で無事先輩へのお礼の品を買いに行けるくらいには安全でした。」
「そう?うわぁ、いっぱい入ってるじゃん。ハンカチと汗拭きシートと……クッキー?」
「はい。お口に合えばいいのですが……。ダメだったら捨てちゃってください。」
「……クッキーは手作りだったりする?」
「あ、いえ……市販です。出来合いのものですみません。」
「いや全然。その方が嬉しいよ。」
「あの……何かあったんですか?」
僕のその質問にため息をつきながら視線をそらし、人見先輩はめんどくさそうに頭を掻き始めた。何かまずいことを聞いてしまったのかもしれないと感じながらも、一度口から出てしまった言葉はもうしまうことはできない。
「すみません。不快にさせてしまいましたか?」
こんなときは謝るに限る。これは僕の今までの経験で培ってきたものの一つだ。自分が悪いことをしたらすぐに謝る。個人的にはこれができる人は少ないが、出来ると人生が生きやすくなる気がする。
頭を深く下げる僕に人見先輩は「気にしないでくれ」と優しく接してくれた。それに僕はまた若干の違和感を覚えた。先ほども僕が先輩方に囲まれている最中に助けてくれたときもそうだったのだが、僕に対しての態度と女子生徒に対しての態度が大きく違う気がしてならない。
「人見先輩ってもしかして、女性が苦手なんですか?」
「……なんで?」
「先輩、僕には優しいじゃないですか。昨日もさっきだって助けてくれましたし。でも僕を取り囲んでいた女性の先輩に対しては若干冷たさを感じたので、苦手なのかなと……。」
僕の質問に対し、人見先輩は少し考えた後「新島も同じだろ?」と共感を求めてきた。それに対しすぐに共感ができずにいると、人見先輩は続けて口を開いた。
「占いをするのはいいけど、別に女と話したいわけじゃないだろ?」
「まぁ…そうですね。」
「だろ?俺も別にモテたくて弓道やってたわけじゃないし。それなのにそれが原因でたくさんの人から声を掛けられる。正直不快だよ。」
「……よく告白されてますもんね。」
「え、そんなことまで知ってるの?」
「あ、いえ!知ってるといいますか……。僕の占いを受けに来る女子生徒の大半が人見先輩と付き合えるかを占いに来るので……。でも今まで人見先輩と相性が良いって結果が出た人いないんですよね。」
「へぇ。それなのにあんなに告白してくるんだ。」
「まぁあくまで占いですから。」
「え?占いやってる奴がそんなこと言っていいの?」
「はい、全然言います。占いは当たるも八卦当たらぬも八卦と言ってますので。占いは当たることもあれば外れることもあるって感じですね。」
それを聞いた人見先輩は驚きの表情を見せた。僕個人としてはよくある反応だったのだが、先ほどまで少しつんけんしていた人見先輩からは想像も付かない表情だったため僕は思わず声を出して笑ってしまった。
そんな僕を見て「そんなに笑うなよ」と若干不貞腐れたような表情を浮かべていたが、最終的には僕に釣られて人見先輩も笑顔になっていた。
「いやぁ久々に学校で笑ったわ。」
「え、そうなんですか?」
「まぁお互いいろいろとあるだろ?」
「そ、そうですね……。」
その時鮫島高等学校の敷地内全体にチャイムが鳴り響いた。それは昼休みの終了の合図でもあり、残り十分足らずで次の授業が始まることを意味していた。それを聞いた人見先輩は小さめの溜息を吐き出すと口を開いた。
「わざわざクッキーとかハンカチとかありがとう。俺教室戻るから。またね。」
「あ、はい!長々とお話してしまいすみません。昨日も助けていただいたのに、本日も助けていただきありがとうございました!」
それを聞き終えた人見先輩はこちらを振り返ることなく軽く右手を挙げ「ケガ、お大事に。」とだけ呟き、屋上から校舎内に戻る扉を潜り、階段を降りて行った。
僕は昨日も見たその大きな背中を見てやはり人見先輩のことが好きなんだと感じつつ、昨日に引き続き、今日も助けてもらったことへの罪悪感で胸を詰まらせていた。
そう告げる目の前の男子高校生は鮫島高等学校の制服ではない。鮫島高等学校は夏場は水色のカッターシャツに青と紺のストライプのネクタイ。グレーのベストにチェックのパンツという制服なのだが、男は違っていた。制服ではあるのだが、全体的に色が違う。清潔感のある白のカッターシャツなのだが、ネクタイはしておらずベストも身に着けていない。何なら前のボタンはすべて空いており、カッターシャツの下に着ていたオレンジのTシャツが見えているような状態だ。パンツは黒のスラックスであり、その制服から近くにあるもう一つの高校である水科《みずしな》高等学校であることがわかった。
そこまではわかったのだが、なぜこの男子高校生が僕に声をかけたかは理解できないでいた。そもそも僕は水科高等学校に友人や知り合いはおらず、占いのことが外部生徒に漏れている可能性もあるが、その場合男子高校生の殺意に満ちた表情と冷ややかな視線にはならないだろう。となれば他校の男子高校生が僕に声を掛ける理由は一つしかない。
「えっと……人違いですかね?」
「ああそうですか……とはならねえよ。お前が鮫島の占い師だろ?」
「な、何か御用ですか?占い希望であればまた後日でお願いしたいのですが……。」
「お前のせいでオレは沙耶《さや》と別れたんだぞ!」
彼の怒号は僕の声をかき消すように響き渡った。ここが裏路地でなければ数多くの通行人の視線を一斉に集めることになっただろう。しかしここは人通りもなく、ましてや近道するためにしか使わない人が一人通れるくらいの幅しかない。つまり僕と目の前の男子高校生以外この場にはいないということだ。
彼の手は血が滴るのではないかと思うほど強く握りしめられており、あまりの怒りに脚が震えているようにも見える。僕は知っている。この状態の人間と会話が成立することはない。つまりこの状況で僕が取るべき行動は逃げる一択だ。僕はその瞬間踵を返し、来た道を走って戻ろうとするが、突如右半身に強烈な痛みが走り、僕は裏路地の壁に吹き飛ばされた。壁に押し当てられた左半身にも痛みが走った。
喧嘩など無縁の人生を送ってきた僕にとってその衝撃はまるで骨が折れたかのような痛みを伴った。実際に骨折した経験はなく完全に感覚でしかないが、それと同等の痛みだと思う。路地裏の壁に押し付けられその場に倒れ込む僕に男子高校生は馬乗りになり、僕を逃さないように拘束すると、拳を振りかざした。
この男子高校生の口ぶりからして、彼はきっと僕の占いが原因で彼女と別れたのだろう。沙耶と言っていたが、正直覚えていない。ここ半年以上ほぼ毎日五人以上の占いをし続けているのだ。何度も占いを依頼する生徒もいるが一回しか占っていない生徒ももちろんいる。男女問わず占いは行っているが、比率で言えば明らかに女性の方が多い。それこそ鮫島高等学校のほとんどの女子生徒は占った気がする。体感のため実際には違うかもしれないが、鮫島高等学校は男女合わせて千人を超える生徒数だ。単純計算で女子生徒が五百人いることになるのだが、五百人すべての名前を覚えているわけがない。それは教師であっても難しいだろう。
「何ボサッとしてんだよ!」
そんなことを走馬灯のように瞬時に振り返っていると、男子高校生の振り上げられた拳は一直線に僕の顔面めがけて速度を上げた。僕は目を強く瞑り、少しでも防御をしようと手を前にかざす。ある程度の痛みを覚悟したのだが、五秒ほど経過しても痛みを感じることはなかった。僕は恐る恐る目を開けると、振り上げられた拳は誰かに腕を掴まれる形で宙に浮いた状態になっていた。
「何だよてめぇ!邪魔すんな!」
「鮫島高校の子、大丈夫?もうすぐ警察来るから。」
「はぁ?何警察とか呼んでんだよ!ふざけんなよ!」
拳を振りかざした男子高校生は警察という自身が当事者になると途端に面倒な存在に変わるそれの名前を聞き、大きな舌打ちをしながら掴まれた腕を振りほどき、ゆっくりと僕の上からその大きな体を退かすと、これまた大きなため息を付きながら去っていった。
僕と僕を助けてくれた同じ制服の男子高校生は走り去る男の背中を追い、見えなくなるとそこで初めて僕達は顔を合わせた。
「あ、ありがとうございます。危ないところを助けていただいて。」
「……全然。怪我は大丈夫そう?」
「は、はい。全身が痛いですが、打撲程度だと思うので、大丈夫だと思います。」
「そ。痛くなったら病院いきなよ。」
「はい!ありがとうございます。えっと警察まで呼んでいただいて、すみません。」
「あぁ警察は嘘だよ。警察って聞けば大抵は逃げ出すでしょ。」
「そうだったんですね。本当に助かりました。あの、同じ高校ですよね?」
「そうだけど。お前あれだろ?占いやってる子。」
「あ、はい……そうです。えっと先輩ですよね?」
「俺?三年の人見だ。」
「僕は二年の新島です。新島爽《にいじまそう》っていいます。あの人見先輩は僕の事知ってるんですか?」
「そりゃ知ってるだろ。鮫島高校に通ってるやつで新島のこと知らない奴の方が少ないだろ。それじゃ気を付けて帰れよ。」
人見先輩はそう言い残し、足早に去ってしまった。僕個人としては助けてもらったお礼をちゃんとしたかったし、もう少しお話をしてみたかった。
実というと僕は人見先輩のことを前から知っていた。自分の口からはあまり言いたくはないのだが、僕は鮫島高等学校ではそれなりに有名人である。それは先ほど人見先輩が言っていた通りで、僕のことを知らない人の方が少ないほどだ。そして鮫島高等学校にはもう一人、僕と同じくらい鮫島高等学校には知らない人の方が少ない有名人がいる。それが人見先輩だ。
人見孝仁《ひとみたかと》先輩は百八十センチという高身長に加え、女性だけではなく男性もが惚れ惚れするルックス。そして人見先輩の最大の魅力は弓道にある。弓道部のエースを務めていた人見先輩は試合中的を外したことはなく、全国大会で優勝するほどの腕前だ。全国大会優勝後は校舎に弾幕が降ろされ、かつ全校集会でも全校生徒の前で表彰されたため、基本的には全校生徒が人見先輩のことを知ってるだろう。
高身長とルックスに加え、スポーツも万能とくれば女子生徒が放っておくわけがなく、何人もの生徒が人見先輩に告白したという噂を聞いたことがある。実際僕に占いを依頼しに来る女子生徒のほとんどの片想いの相手が人見先輩であり、相性であったり、どうすれば付き合えるのか。実際に付き合うことは可能かなどの占いをしにくる女子生徒が多い。それだけ人見先輩は人気があるのだが、実際のところ人見先輩と付き合えた女子生徒はいないらしい。
僕がなぜこんなにも人見先輩のことに詳しいか。それは僕自身が人見先輩のことを前から気になっていたからである。それは恋愛対象とかそういう感情ではなく、女子生徒のほとんどが人見先輩との相性を占いに来るほどの人がどういう人なのかという、単純に人見先輩を人として気になっていたという話だ。
しかし僕の感情は今日この瞬間変化した。
「かっこいい……。」
この感情はテレビに映る俳優を見てかっこいいなと感じるものとは似て非なるものだ。心が暖かくなるのがわかる。そんな感情だ。僕を助け足早に去っていく人見先輩の背中は大きく、頼もしく思えた。
人見先輩にちゃんとお礼を言いたい。もっと話したい。
僕は自覚した。きっとこの感情は恋なのだと。
✂ ——— ✂ ——— ✂ ——— ✂ ——— ✂
翌日僕は昼休みの時間を使って、三年生の教室がある校舎の一階に脚を運んでいた。その理由はただ一つ。人見先輩に会いに行くためだ。
昨日、人見先輩への気持ちに気づいてから、人見先輩に少しでも近づくために駅の中にある少しお高めの雑貨屋で助けてもらったお礼の品と称して、オシャレなクッキーの詰め合わせと無難なところでタオル生地のハンカチに、これからの季節である夏をすぎて秋でも使用できるようないい匂いのする汗ふきシートを購入した。それらを紙袋に詰めて、僕は今一階をうろうろしている。
(……そもそも人見先輩って、何組なんだ?)
僕は自分の事前準備のなさにショックを受けつつも、人見先輩に会うために三年生の教室を少し覗いて人見先輩がいないことを確認すると、すぐに隣りの教室に移動するというのを何回か繰り返していた。すべての教室を回り終えたのだが、目当ての人見先輩を見つけることはできなかった。もしかしたら今日はお休みしているのかもしれないとガッカリしながら二階にある自分の教室に戻ろうとしたとき、僕は複数の女子生徒に取り囲まれていることに気がついた。
「あれ?新島くんだ。三年の教室に何か用?」
「あ、もしかして誰か探してる?占いの依頼?」
「放課後じゃなくても、占ってくれるの?え、ウチ占ってよ!」
「今お菓子持ってない!学食奢るとかでもいい?」
「え、てか右手どうしたの?湿布?怪我した感じ?」
「ホントだ。右足首にも湿布貼ってあるじゃん!怪我したの?大丈夫そ?」
「ウチ痛み止め持ってるよ!もらっとく?」
「いやそれロキソニンでしょ?怪我の痛みにも効くの?」
「え、わかんない。でも痛み止めだし?」
「あーね。ウチもその辺詳しくないからなぁ。」
「その辺って……サクラって詳しい分野あったっけ?」
「それは言わない約束だからぁ!」
僕を取り囲んだ三年の先輩は、三年の教室を見て回る僕に興味を示しつつも、僕にそんなに干渉するわけでもなく、仲間内で話を進めていく。取り囲まれてしまった僕は逃げることもできず、ましてや先輩たちの会話に入ることもできず、どうしようもできずただただ立ち尽くすことしかできないでいた。
正直僕は女性と話すことがそんなに得意ではない。多くの女性を占ってきておいて何を言っているんだと思われるかもしれないが、僕のする占いは会話をすると言うより、占いの結果を伝え、今後どうするべきかというアドバイスをするという形のため、基本一方的に話すことが多い。追加で言うとすれば占いは基本一対一でするものだ。そのため話せても一対一でなら多少なら可能なのだが、今のような一対多の状況には慣れておらず、どうしても自分から何かを切り出すということはできない。
そんなどうにもできない状況で一人たじろいでいると、突如として背後から左手を掴まれた。僕は昨日の体験もあり、若干の恐怖で表情が歪みながらも、勢いよく振り返り僕の手を掴んだ人間を確認する。そこは顔を見上げなければ表情を確認することができない程の高身長に加え、筋肉質な大きな体にゴツゴツとした男らしい手で僕の左手を掴んでいる人見先輩の姿がそこにはあった。
「新島に何か用?」
昨日僕を助けたときの声とは違う、低くそして若干冷たくも聞こえる声が僕の頭上から降り注いだ。その感じに僕を取り囲んでいた先輩たちが今度はたじろぐ形となった。僕はその状況に若干の違和感を覚えていると、女子生徒の一人が口を開いた。
「ひ、人見くん……。いや新島くんが三年の教室を見て回ってたから声かけただけだよ。」
「そ……。じゃあ新島借りていくから。」
「う、うん……。」
そう言うと人見先輩は掴んだ僕の左手を離すことはなく、そのまま僕を引っ張り階段を駆け上がった。その間人見先輩は声を掛けることはなかったが、その背中に優しさと温かさを感じながら僕は人見先輩に引かれるがままに、後をついていく。
到着したのは校舎の屋上であった。春やもう少し秋が深まった季節になれば屋上も多くの生徒で賑わっているのだが、夏真っ盛りのこの時期は直射日光に当てられる屋上の利用頻度は極端に下がるわけで、要するに僕と人見先輩以外、屋上に来ている生徒はいなかった。
「……新島はいつもああなの?」
「え、あ、いや。あのまた助けていただいてありがとうございます!」
「いや、いいけど。新島の大変だな。」
「そんな……人見先輩も大変なんじゃないですか?」
「まぁ……。と、いうか新島は俺のこと知ってたの?」
「先輩のこと知らない生徒の方が少ないですよ。」
「どこかで聞いたことのあるようなセリフだな。それで?三年の誰かに用だったのか?なんか女に囲まれて困ってそうだったから声かけたけど。」
僕はそれを聞いて人見先輩に用があったことを思い出す。持っていた紙袋を人見先輩に差し出し、「昨日はありがとうございました。これはお礼です!」となかなかに大きな声でそれを伝えた。
「え?俺に用だったの?わざわざごめん。昨日はあの後大丈夫だった?」
「はい、お陰様で無事先輩へのお礼の品を買いに行けるくらいには安全でした。」
「そう?うわぁ、いっぱい入ってるじゃん。ハンカチと汗拭きシートと……クッキー?」
「はい。お口に合えばいいのですが……。ダメだったら捨てちゃってください。」
「……クッキーは手作りだったりする?」
「あ、いえ……市販です。出来合いのものですみません。」
「いや全然。その方が嬉しいよ。」
「あの……何かあったんですか?」
僕のその質問にため息をつきながら視線をそらし、人見先輩はめんどくさそうに頭を掻き始めた。何かまずいことを聞いてしまったのかもしれないと感じながらも、一度口から出てしまった言葉はもうしまうことはできない。
「すみません。不快にさせてしまいましたか?」
こんなときは謝るに限る。これは僕の今までの経験で培ってきたものの一つだ。自分が悪いことをしたらすぐに謝る。個人的にはこれができる人は少ないが、出来ると人生が生きやすくなる気がする。
頭を深く下げる僕に人見先輩は「気にしないでくれ」と優しく接してくれた。それに僕はまた若干の違和感を覚えた。先ほども僕が先輩方に囲まれている最中に助けてくれたときもそうだったのだが、僕に対しての態度と女子生徒に対しての態度が大きく違う気がしてならない。
「人見先輩ってもしかして、女性が苦手なんですか?」
「……なんで?」
「先輩、僕には優しいじゃないですか。昨日もさっきだって助けてくれましたし。でも僕を取り囲んでいた女性の先輩に対しては若干冷たさを感じたので、苦手なのかなと……。」
僕の質問に対し、人見先輩は少し考えた後「新島も同じだろ?」と共感を求めてきた。それに対しすぐに共感ができずにいると、人見先輩は続けて口を開いた。
「占いをするのはいいけど、別に女と話したいわけじゃないだろ?」
「まぁ…そうですね。」
「だろ?俺も別にモテたくて弓道やってたわけじゃないし。それなのにそれが原因でたくさんの人から声を掛けられる。正直不快だよ。」
「……よく告白されてますもんね。」
「え、そんなことまで知ってるの?」
「あ、いえ!知ってるといいますか……。僕の占いを受けに来る女子生徒の大半が人見先輩と付き合えるかを占いに来るので……。でも今まで人見先輩と相性が良いって結果が出た人いないんですよね。」
「へぇ。それなのにあんなに告白してくるんだ。」
「まぁあくまで占いですから。」
「え?占いやってる奴がそんなこと言っていいの?」
「はい、全然言います。占いは当たるも八卦当たらぬも八卦と言ってますので。占いは当たることもあれば外れることもあるって感じですね。」
それを聞いた人見先輩は驚きの表情を見せた。僕個人としてはよくある反応だったのだが、先ほどまで少しつんけんしていた人見先輩からは想像も付かない表情だったため僕は思わず声を出して笑ってしまった。
そんな僕を見て「そんなに笑うなよ」と若干不貞腐れたような表情を浮かべていたが、最終的には僕に釣られて人見先輩も笑顔になっていた。
「いやぁ久々に学校で笑ったわ。」
「え、そうなんですか?」
「まぁお互いいろいろとあるだろ?」
「そ、そうですね……。」
その時鮫島高等学校の敷地内全体にチャイムが鳴り響いた。それは昼休みの終了の合図でもあり、残り十分足らずで次の授業が始まることを意味していた。それを聞いた人見先輩は小さめの溜息を吐き出すと口を開いた。
「わざわざクッキーとかハンカチとかありがとう。俺教室戻るから。またね。」
「あ、はい!長々とお話してしまいすみません。昨日も助けていただいたのに、本日も助けていただきありがとうございました!」
それを聞き終えた人見先輩はこちらを振り返ることなく軽く右手を挙げ「ケガ、お大事に。」とだけ呟き、屋上から校舎内に戻る扉を潜り、階段を降りて行った。
僕は昨日も見たその大きな背中を見てやはり人見先輩のことが好きなんだと感じつつ、昨日に引き続き、今日も助けてもらったことへの罪悪感で胸を詰まらせていた。