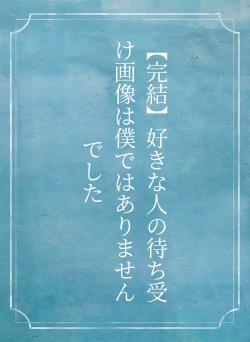「追いかけなくていいの?」
「……村田先輩でしたっけ?いつから見てたんですか?」
一人駐輪場に残された松本に声を掛けたのは、本日新島に人見との相性を占ってもらっていた村田であった。
「人聞きが悪い後輩ね。駐輪場に自転車置いてるから取りに来ただけよ。」
「それはすみませんでした。」
村田は自分の自転車を駐輪場から見つけ出し、自転車のワイヤーロックを解除しながら松本に話し続ける。それはまるで松本のことを気遣っているようであった。
「それで?追いかけないの?」
「いや無理でしょ。俺振られたんですよ?村田先輩こそ、人見先輩を追いかけなくていいんですか?好きなんですよね?」
「……私の占い結果、人見先輩に寄り添った接し方をするのがいいんですって。」
「はぁ……。」
「人見先輩が新島くんのこと好きなら、それに寄り添うべきじゃない?だから占い結果を聞いた時点で私は人見先輩とは付き合えないなって思ったのよ。てゆうか後輩くんは新島くんのこと、振られたくらいで諦めるの?」
「……俺の占い結果、現在が”夢中になりすぎる”。未来が”身勝手な自分”って結果だったんすよ。結果は占い通りって感じですね。」
「そ、じゃあ。新島くんの占いはやっぱり当たるんだ。」
「ほんとすごいっすよ。新島先輩も人見先輩も。……俺は最初っから新島先輩と付き合えなかったんですかね?」
村田はスクールバッグを雑に自転車のカゴに入れ、そのまま自転車に跨ると松本の方向を見ることなく、独り言のように呟く。
「新島くんは占いは当たるも八卦当たらぬも八卦って言ってたよ。あくまで今度自分がどう行動するべきかのアドバイスに過ぎないってさ。占ってもらった私がいえたセリフじゃないけどさ、信じない方がいい夢は見れたのかもしれないね。」
村田は松本からの返事を聞くことなく「それじゃ」とだけ言い残し、颯爽と自転車に乗って帰っていった。
駐輪場に一人残された松本はただただ、霞んで見えなくなった目を瞑ることはなく、何かを我慢するかのように唇を噛みしめていた。
✂ ——— ✂ ——— ✂ ——— ✂ ——— ✂
ここ最近僕は自分自身では理解が追いつかないことが多々あったのだが、今日の今まさに発生しているこのイベントに関しては本当に理解が出来ずに困惑するしかなかった。
松本くんからの告白をお断りしたかと思えば、あの夏祭りの日を境に連絡を取ることも、話しをすることもなくなった僕の好きな人が、僕の腕をさも当然のように掴み、そのまま僕を連れまわしている。
見慣れたその大きな背中は少し怒っているようにも思えるし、何か焦っているようにも思える。
そんなことを思いながらも、それすらを凌駕するほどの疑問が僕の脳内を占領していた。
なぜ人見先輩があの場にいたのか。どこから聞いていたのか。そして、なぜ人見先輩は僕の腕を掴み、さらにはどこへ行こうとしているのか。
徐々に僕の腕を掴む人見先輩の握力が強くなっていくのが分かる。
「ひ、人見先輩、い、痛いです!」
考えに考え抜いた結果、僕の口から出た言葉がそれだった。
それを聞いた人見先輩はピタッと動くのを止め、僕の腕を掴んでいた手が徐々に解けていく。
「ごめん。」
「いえ、僕の方こそすみません。」
「……なんで新島が謝るんだ?」
「え、えっと……。」
僕が回答に困っていると、人見先輩は僕の返事を待つことなく続けて話しをする。
「腕、大丈夫か?痕になったりしてないか?」
「はい、大丈夫です。」
「そっか。よかった。」
安堵する人見先輩の表情に若干和んでしまった僕は人見先輩に疑問に思っていたことをぶつけるように聞いた。
「あの、人見先輩はどうして駐輪場にいたんですか……?」
「最初は普通に帰るつもりだったけど、新島の姿が見えたから後を付けたんだよ。もしかして占いの結果が原因でまた誰かに暴行でもされんのかと思って、心配で。」
人見先輩は優しい目で僕にそう告げた。
あの日確かに僕は人見先輩を怒らせたはずだ。だから連絡もなかったし話すこともなくなった。そんな人見先輩が僕のことを気にかけてくれているだけでうれしいのに、僕はそれを深堀するように人見先輩に問いただす。
「僕のこと心配してくれるんですか?」
「しちゃだめか?」
「人見先輩は僕のこと嫌いになったんじゃないですか?」
「……なんで?」
「夏祭りの日に先輩を怒らせたから……。」
「怒らせた?」
「え、違うんですか?」
人見先輩から返ってきた答えは予想もしていないものであった。
怒らせたことに疑問を抱くということは、人見先輩は怒っていないということだ。
しかしあの日、人見先輩はキレていたように思える。
僕のその疑問は次の人見先輩のセリフで解決することとなった。
「……あれは嫉妬だよ。」
「嫉妬、ですか?」
「ん。他の奴は占ってもらえるのに、俺は占ってもらえないことへの嫉妬。嫉妬であんな態度取ってしまった。ごめん。」
なぜ人見先輩が占いをしてもらえないだけで嫉妬する必要があるのだろうか。新たなる疑問が僕の中で生まれようとしていたが、その疑問が確立されるよりも先に人見先輩はあの優しい目をしながら、僕に微笑みかけながらゆっくりと口を開いた。
「新島は弟なんかじゃない。これは弟に抱いてもいい感情なんかじゃない。最初っから分かってた。他校の生徒に絡まれていたところを助けたのはほんとに偶然だったが、それ以外は違う。全部自分の意志でやったことだ。新島のことが好きだから放っておけなかった。」
「え……?」
「さっき後輩に告白されてたとき、他に好きな人がいるって言って断ってたよな?その好きな人って俺か?もしそうなら俺の手を取ってほしい。いつもは俺が新島の手を取りに行くけど、この瞬間だけは新島から手を取ってほしい。俺と新島のことを占ってくれ。」
そう言って人見先輩は右手を僕に差し出してきた。
そのゴツゴツとした男らしい手は何度も僕の手を取り、いろんなところへと連れて行ってくれた手だ。
他校の生徒に因縁をつけられ暴行を受けていた時に助けてもらったことから始まり、翌日お礼を伝えに三年の教室を訪れ女子生徒の囲まれてしまったときも、学食で後輩に絡まれたときも、デートと称してカフェに行ったときも、そして夏祭りに行ったときも、僕の腕を優しく引っ張ってくれたその大好きな手。
そんな手が、今まで見たことないくらいに震えている。
緊張してくれている。
それをみて確信する。本気なんだと。
僕はその震えている大好きな手を包み込むように握る。
「あの日。人見先輩に初めて助けられたあの日からずっと人見先輩のことが好きでした。僕に手を握らせてもらえませんか?」
それを聞いた人見先輩は空いていた左手で僕の腕を掴むを自身に引き寄せる。
好きな人とハグをするのはこんなにも温かくて気持ちの良いものなのだと僕は初めて知った。
「すっげぇ嬉しい。」
「僕もです。」
「心臓の音、すっげぇうるせーの。聞こえる?」
「僕の音もすごくて、先輩の心音聞く余裕ないですよ。」
「ん。」
「でも人見先輩は心を乱されるのが嫌いだから誰も好きになんてならないと思ってました。だから僕は気持ちを告げなかったのに。」
「今でも乱されるのは嫌。でも新島が俺以外の誰かにとられるのはもっと嫌。新島のそばが一番落ち着くよ。」
「は、恥ずかしいです……。」
「一緒に慣れていこーな。」
「はい!」
ハグをしていた僕と人見先輩だが、人見先輩に身体を剥がされると、次はゆっくりと人見先輩の顔が僕に近づいてきた。
そして僕の唇に人見先輩の唇が重なった。
僕は驚きのあまり目を見開いてしまったが、人見先輩は目を閉じており、その距離はまつ毛の本数を数えることが出来るほどであった。
「こーゆーのも一緒に慣れていこうな。」
「は、はひぃ……。」
少し照れながらも決めるところは決めてくる人見先輩のかっこよさに僕は声が裏返り、変な返事をするだけで精一杯だった。
✂ ——— ✂ ——— ✂ ——— ✂ ——— ✂
翌日から僕と人見先輩は昼食は学食で共に食事をし、帰宅するときのタイミングも合わせるようになった。
言ってしまえば一学期の後半のようなスタイルに戻ったとも言える。
お互い高校生ということもあり、更にお互いに初めての恋人ということもあってか変なテンションになっていた僕らは、学食でさまざまな人が見ている前で「あーん」をかましてしまい、付き合い始めてまだ数日しか経っていないのにも関わらず、僕と人見先輩が付き合っているということは鮫島高等学校の全生徒が知ることとなった。
僕はまだその恥ずかしさに慣れていないのだが、人見先輩は周りなんてどうでもいいと思っているようで、割とどこでもいちゃついてくる。
「あ、あの人見先輩、ここ学食ですよ?」
「ん?何?爽は俺といちゃつくことに何の問題があんの?てか、また苗字に戻ってるんだけど?」
「え、あ、えっと……孝仁《たかひと》先輩。」
「ん。」
僕と人見先輩が付き合い始めて決めたルールが存在する。
まずは昼食は学食で一緒に食べること。帰宅するときは一緒に帰ること。この二つがメインだ。
しかし人見先輩の案はそれだけではなく、名前で呼び合おうというものであった。
もちろん世間一般的に見ればお付き合いをされているほぼ全てのカップルがお互いを苗字ではなく、ファーストネームで呼び合うだろうから、何もおかしなところはない。
だからと言ってそれが全てのカップルで成立するわけではないと思う。
端的に言うとめちゃくちゃ恥ずかしいのだ。
これでは僕たち付き合ってますと周りに公言しているのと変わらない。それが学校外であれば多少なりとも僕の気も楽だったかもしれない。しかしここは鮫島高等学校内にある学食。利用者はこの学校の生徒なわけで、その視線が痛い。
だが人見先輩はそんなことは全くといっていいほど気にしていない。
実は人見先輩はこのためにメンタル面を鍛えていたのではないかと思うほどだ。
「また考えゴト?」
「あ、いえ。えっと今日は何食べます?占いのお礼で貰ったお菓子もありますけど、ブランダルのクッキーもありますよ。」
「ん。じゃあクッキーで。」
「ホント好きですよね。」
「爽が教えてくれたクッキーだからな。」
やはりこういった恥ずかしいことを平気で言うなんて、人見先輩のメンタルの鍛え方は正しかったのかもしれない。そんなことを思いながら僕は今日も人見先輩の口元にクッキーを運ぶ。
✂ ——— ✂ ——— ✂ ——— ✂ ——— ✂
「爽ぉ、準備出来たか?」
「ちょっとまって孝仁。もう終わる!」
「ん。」
孝仁と付き合い始めてから十年が経過しようとしていた。
僕は夢であったスクールカウンセラーとして、母校である鮫島高等学校に勤務をしている。孝仁はというとスポーツ整体師として自分の店を持ちつつ、出張で弓道関連の整体師を行っているようだ。
孝仁が進学先として考えていたのは、弓道をやっていた知識を他でも活かせないかと考え、そう言ったことが学べる専門学校に進んだのであった。
最初は大変なことも多かったようだが、今はとても安定しているようだ。
そんな僕と孝仁は付き合って十年目になる大きな節目で、高級レストランを予約していた。
お互いに忙しい職場環境であるが、今日この日だけはゆっくりしようと九年目を祝ったときには既に決めており、今日のために様々な調整を行ってきた。
レストランはホテルレストランになっており、食事を楽しんだ後は、ゆっくりホテルでくつろぐことができるようになっている。
「爽に出会えたことに。」
「孝仁とのこれからに。」
そういって僕と孝仁はワイングラスで乾杯をする。
お互いの仕事で気にお酒を飲む頻度はかなり低いのだが、今日だけは飲もうと二人で決めていたのだ。
次々と運ばれてくる豪華なディナーに感動しつつ、楽しい時間を過ごしていく。
「そういえばさ、爽にずっと聞きたかったことあるんだけど。」
「え、なに?」
「結局さ、俺は今まで一度も爽に占ってもらったことないんだけど。」
「えぇ……そりゃ占わないよ。」
「え!?なんで?俺と爽のこと占ってよ!」
「いやだよ。」
「なんで……?」
あ、これはちょっと不機嫌になるやつだ。
十年も一緒にいれば、お互いのことは割と分かるようになってくる。それこそ今の孝仁はやっぱり自分は僕に好かれていないんじゃないかと不安になり、不機嫌になる手前の状態だ。
こうなった孝仁はひどくめんどくさい。
そもそも付き合い始めたときからなんとなく察してはいたが、孝仁は無自覚に僕のことを溺愛している。たまにその溺愛ぶりが束縛に近いものになるときもあるためめんどくさいのだが、今のところ本人にはそれを伝えていない。
「占わないよ。だって占いなんてなくても十年も一緒にいるんだよ。絶対にこれから先も一緒にいるよ。それに、孝仁との恋愛は占いに頼らず、一緒に正解を見つけたいな。」
「……爽って俺のことめちゃくちゃ好きだよな?」
「それは孝仁もでしょ。」
「ん。」
占いは当たるも八卦当たらぬも八卦。僕個人の見解としてはあくまでアドバイス程度の認識だ。
今まで自分の人生や生き方を占いで決めたことはないが、それは今後も変わることはないだろう。
僕と孝仁の未来が視えるのは、僕らだけだから。
—fin—
「……村田先輩でしたっけ?いつから見てたんですか?」
一人駐輪場に残された松本に声を掛けたのは、本日新島に人見との相性を占ってもらっていた村田であった。
「人聞きが悪い後輩ね。駐輪場に自転車置いてるから取りに来ただけよ。」
「それはすみませんでした。」
村田は自分の自転車を駐輪場から見つけ出し、自転車のワイヤーロックを解除しながら松本に話し続ける。それはまるで松本のことを気遣っているようであった。
「それで?追いかけないの?」
「いや無理でしょ。俺振られたんですよ?村田先輩こそ、人見先輩を追いかけなくていいんですか?好きなんですよね?」
「……私の占い結果、人見先輩に寄り添った接し方をするのがいいんですって。」
「はぁ……。」
「人見先輩が新島くんのこと好きなら、それに寄り添うべきじゃない?だから占い結果を聞いた時点で私は人見先輩とは付き合えないなって思ったのよ。てゆうか後輩くんは新島くんのこと、振られたくらいで諦めるの?」
「……俺の占い結果、現在が”夢中になりすぎる”。未来が”身勝手な自分”って結果だったんすよ。結果は占い通りって感じですね。」
「そ、じゃあ。新島くんの占いはやっぱり当たるんだ。」
「ほんとすごいっすよ。新島先輩も人見先輩も。……俺は最初っから新島先輩と付き合えなかったんですかね?」
村田はスクールバッグを雑に自転車のカゴに入れ、そのまま自転車に跨ると松本の方向を見ることなく、独り言のように呟く。
「新島くんは占いは当たるも八卦当たらぬも八卦って言ってたよ。あくまで今度自分がどう行動するべきかのアドバイスに過ぎないってさ。占ってもらった私がいえたセリフじゃないけどさ、信じない方がいい夢は見れたのかもしれないね。」
村田は松本からの返事を聞くことなく「それじゃ」とだけ言い残し、颯爽と自転車に乗って帰っていった。
駐輪場に一人残された松本はただただ、霞んで見えなくなった目を瞑ることはなく、何かを我慢するかのように唇を噛みしめていた。
✂ ——— ✂ ——— ✂ ——— ✂ ——— ✂
ここ最近僕は自分自身では理解が追いつかないことが多々あったのだが、今日の今まさに発生しているこのイベントに関しては本当に理解が出来ずに困惑するしかなかった。
松本くんからの告白をお断りしたかと思えば、あの夏祭りの日を境に連絡を取ることも、話しをすることもなくなった僕の好きな人が、僕の腕をさも当然のように掴み、そのまま僕を連れまわしている。
見慣れたその大きな背中は少し怒っているようにも思えるし、何か焦っているようにも思える。
そんなことを思いながらも、それすらを凌駕するほどの疑問が僕の脳内を占領していた。
なぜ人見先輩があの場にいたのか。どこから聞いていたのか。そして、なぜ人見先輩は僕の腕を掴み、さらにはどこへ行こうとしているのか。
徐々に僕の腕を掴む人見先輩の握力が強くなっていくのが分かる。
「ひ、人見先輩、い、痛いです!」
考えに考え抜いた結果、僕の口から出た言葉がそれだった。
それを聞いた人見先輩はピタッと動くのを止め、僕の腕を掴んでいた手が徐々に解けていく。
「ごめん。」
「いえ、僕の方こそすみません。」
「……なんで新島が謝るんだ?」
「え、えっと……。」
僕が回答に困っていると、人見先輩は僕の返事を待つことなく続けて話しをする。
「腕、大丈夫か?痕になったりしてないか?」
「はい、大丈夫です。」
「そっか。よかった。」
安堵する人見先輩の表情に若干和んでしまった僕は人見先輩に疑問に思っていたことをぶつけるように聞いた。
「あの、人見先輩はどうして駐輪場にいたんですか……?」
「最初は普通に帰るつもりだったけど、新島の姿が見えたから後を付けたんだよ。もしかして占いの結果が原因でまた誰かに暴行でもされんのかと思って、心配で。」
人見先輩は優しい目で僕にそう告げた。
あの日確かに僕は人見先輩を怒らせたはずだ。だから連絡もなかったし話すこともなくなった。そんな人見先輩が僕のことを気にかけてくれているだけでうれしいのに、僕はそれを深堀するように人見先輩に問いただす。
「僕のこと心配してくれるんですか?」
「しちゃだめか?」
「人見先輩は僕のこと嫌いになったんじゃないですか?」
「……なんで?」
「夏祭りの日に先輩を怒らせたから……。」
「怒らせた?」
「え、違うんですか?」
人見先輩から返ってきた答えは予想もしていないものであった。
怒らせたことに疑問を抱くということは、人見先輩は怒っていないということだ。
しかしあの日、人見先輩はキレていたように思える。
僕のその疑問は次の人見先輩のセリフで解決することとなった。
「……あれは嫉妬だよ。」
「嫉妬、ですか?」
「ん。他の奴は占ってもらえるのに、俺は占ってもらえないことへの嫉妬。嫉妬であんな態度取ってしまった。ごめん。」
なぜ人見先輩が占いをしてもらえないだけで嫉妬する必要があるのだろうか。新たなる疑問が僕の中で生まれようとしていたが、その疑問が確立されるよりも先に人見先輩はあの優しい目をしながら、僕に微笑みかけながらゆっくりと口を開いた。
「新島は弟なんかじゃない。これは弟に抱いてもいい感情なんかじゃない。最初っから分かってた。他校の生徒に絡まれていたところを助けたのはほんとに偶然だったが、それ以外は違う。全部自分の意志でやったことだ。新島のことが好きだから放っておけなかった。」
「え……?」
「さっき後輩に告白されてたとき、他に好きな人がいるって言って断ってたよな?その好きな人って俺か?もしそうなら俺の手を取ってほしい。いつもは俺が新島の手を取りに行くけど、この瞬間だけは新島から手を取ってほしい。俺と新島のことを占ってくれ。」
そう言って人見先輩は右手を僕に差し出してきた。
そのゴツゴツとした男らしい手は何度も僕の手を取り、いろんなところへと連れて行ってくれた手だ。
他校の生徒に因縁をつけられ暴行を受けていた時に助けてもらったことから始まり、翌日お礼を伝えに三年の教室を訪れ女子生徒の囲まれてしまったときも、学食で後輩に絡まれたときも、デートと称してカフェに行ったときも、そして夏祭りに行ったときも、僕の腕を優しく引っ張ってくれたその大好きな手。
そんな手が、今まで見たことないくらいに震えている。
緊張してくれている。
それをみて確信する。本気なんだと。
僕はその震えている大好きな手を包み込むように握る。
「あの日。人見先輩に初めて助けられたあの日からずっと人見先輩のことが好きでした。僕に手を握らせてもらえませんか?」
それを聞いた人見先輩は空いていた左手で僕の腕を掴むを自身に引き寄せる。
好きな人とハグをするのはこんなにも温かくて気持ちの良いものなのだと僕は初めて知った。
「すっげぇ嬉しい。」
「僕もです。」
「心臓の音、すっげぇうるせーの。聞こえる?」
「僕の音もすごくて、先輩の心音聞く余裕ないですよ。」
「ん。」
「でも人見先輩は心を乱されるのが嫌いだから誰も好きになんてならないと思ってました。だから僕は気持ちを告げなかったのに。」
「今でも乱されるのは嫌。でも新島が俺以外の誰かにとられるのはもっと嫌。新島のそばが一番落ち着くよ。」
「は、恥ずかしいです……。」
「一緒に慣れていこーな。」
「はい!」
ハグをしていた僕と人見先輩だが、人見先輩に身体を剥がされると、次はゆっくりと人見先輩の顔が僕に近づいてきた。
そして僕の唇に人見先輩の唇が重なった。
僕は驚きのあまり目を見開いてしまったが、人見先輩は目を閉じており、その距離はまつ毛の本数を数えることが出来るほどであった。
「こーゆーのも一緒に慣れていこうな。」
「は、はひぃ……。」
少し照れながらも決めるところは決めてくる人見先輩のかっこよさに僕は声が裏返り、変な返事をするだけで精一杯だった。
✂ ——— ✂ ——— ✂ ——— ✂ ——— ✂
翌日から僕と人見先輩は昼食は学食で共に食事をし、帰宅するときのタイミングも合わせるようになった。
言ってしまえば一学期の後半のようなスタイルに戻ったとも言える。
お互い高校生ということもあり、更にお互いに初めての恋人ということもあってか変なテンションになっていた僕らは、学食でさまざまな人が見ている前で「あーん」をかましてしまい、付き合い始めてまだ数日しか経っていないのにも関わらず、僕と人見先輩が付き合っているということは鮫島高等学校の全生徒が知ることとなった。
僕はまだその恥ずかしさに慣れていないのだが、人見先輩は周りなんてどうでもいいと思っているようで、割とどこでもいちゃついてくる。
「あ、あの人見先輩、ここ学食ですよ?」
「ん?何?爽は俺といちゃつくことに何の問題があんの?てか、また苗字に戻ってるんだけど?」
「え、あ、えっと……孝仁《たかひと》先輩。」
「ん。」
僕と人見先輩が付き合い始めて決めたルールが存在する。
まずは昼食は学食で一緒に食べること。帰宅するときは一緒に帰ること。この二つがメインだ。
しかし人見先輩の案はそれだけではなく、名前で呼び合おうというものであった。
もちろん世間一般的に見ればお付き合いをされているほぼ全てのカップルがお互いを苗字ではなく、ファーストネームで呼び合うだろうから、何もおかしなところはない。
だからと言ってそれが全てのカップルで成立するわけではないと思う。
端的に言うとめちゃくちゃ恥ずかしいのだ。
これでは僕たち付き合ってますと周りに公言しているのと変わらない。それが学校外であれば多少なりとも僕の気も楽だったかもしれない。しかしここは鮫島高等学校内にある学食。利用者はこの学校の生徒なわけで、その視線が痛い。
だが人見先輩はそんなことは全くといっていいほど気にしていない。
実は人見先輩はこのためにメンタル面を鍛えていたのではないかと思うほどだ。
「また考えゴト?」
「あ、いえ。えっと今日は何食べます?占いのお礼で貰ったお菓子もありますけど、ブランダルのクッキーもありますよ。」
「ん。じゃあクッキーで。」
「ホント好きですよね。」
「爽が教えてくれたクッキーだからな。」
やはりこういった恥ずかしいことを平気で言うなんて、人見先輩のメンタルの鍛え方は正しかったのかもしれない。そんなことを思いながら僕は今日も人見先輩の口元にクッキーを運ぶ。
✂ ——— ✂ ——— ✂ ——— ✂ ——— ✂
「爽ぉ、準備出来たか?」
「ちょっとまって孝仁。もう終わる!」
「ん。」
孝仁と付き合い始めてから十年が経過しようとしていた。
僕は夢であったスクールカウンセラーとして、母校である鮫島高等学校に勤務をしている。孝仁はというとスポーツ整体師として自分の店を持ちつつ、出張で弓道関連の整体師を行っているようだ。
孝仁が進学先として考えていたのは、弓道をやっていた知識を他でも活かせないかと考え、そう言ったことが学べる専門学校に進んだのであった。
最初は大変なことも多かったようだが、今はとても安定しているようだ。
そんな僕と孝仁は付き合って十年目になる大きな節目で、高級レストランを予約していた。
お互いに忙しい職場環境であるが、今日この日だけはゆっくりしようと九年目を祝ったときには既に決めており、今日のために様々な調整を行ってきた。
レストランはホテルレストランになっており、食事を楽しんだ後は、ゆっくりホテルでくつろぐことができるようになっている。
「爽に出会えたことに。」
「孝仁とのこれからに。」
そういって僕と孝仁はワイングラスで乾杯をする。
お互いの仕事で気にお酒を飲む頻度はかなり低いのだが、今日だけは飲もうと二人で決めていたのだ。
次々と運ばれてくる豪華なディナーに感動しつつ、楽しい時間を過ごしていく。
「そういえばさ、爽にずっと聞きたかったことあるんだけど。」
「え、なに?」
「結局さ、俺は今まで一度も爽に占ってもらったことないんだけど。」
「えぇ……そりゃ占わないよ。」
「え!?なんで?俺と爽のこと占ってよ!」
「いやだよ。」
「なんで……?」
あ、これはちょっと不機嫌になるやつだ。
十年も一緒にいれば、お互いのことは割と分かるようになってくる。それこそ今の孝仁はやっぱり自分は僕に好かれていないんじゃないかと不安になり、不機嫌になる手前の状態だ。
こうなった孝仁はひどくめんどくさい。
そもそも付き合い始めたときからなんとなく察してはいたが、孝仁は無自覚に僕のことを溺愛している。たまにその溺愛ぶりが束縛に近いものになるときもあるためめんどくさいのだが、今のところ本人にはそれを伝えていない。
「占わないよ。だって占いなんてなくても十年も一緒にいるんだよ。絶対にこれから先も一緒にいるよ。それに、孝仁との恋愛は占いに頼らず、一緒に正解を見つけたいな。」
「……爽って俺のことめちゃくちゃ好きだよな?」
「それは孝仁もでしょ。」
「ん。」
占いは当たるも八卦当たらぬも八卦。僕個人の見解としてはあくまでアドバイス程度の認識だ。
今まで自分の人生や生き方を占いで決めたことはないが、それは今後も変わることはないだろう。
僕と孝仁の未来が視えるのは、僕らだけだから。
—fin—