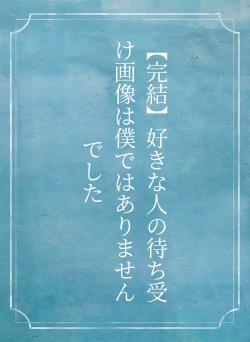月曜日がこんなにも憂鬱に感じたのは初めてかもしれない。
人見先輩に合わないように気を使わないといけないし、松本くんからの告白に対しても答えを出してあげないといけない。
最初こそ、このまま松本くんと付き合ってしまえば、人見先輩のことを忘れられるかもしれないなんて考えがあったが、それはあまりにも松本くんに失礼過ぎる。きっと松本くんならそれでもいいと言ってきそうではあるが、それは本当に避けたい。少しでもそんな考えにいたった自分を殴ってやりたい気分だ。
土日の二日間の休みで僕は真剣に考えた結果、松本くんにはきちんと付き合えない旨を伝えることにした。
しかしいざ伝えるとなると、気持ち的にも重いものがある。振られる方もキツいと思うが、振る方も案外心にくるものがあるらしい。
僕はそんなことを感じながら、今日も鮫島高等学校へと向かう。
一時限目から四時限目までの午前の授業は難なく過ごすことができた。それは移動教室をしなければならない授業もなく、教室で待機しているだけでよかったからである。
問題はここからだ。
昼休みはやらなければならないことが多数ある。そのうちの一つが昼食だ。以前までであれば学食を使っていたが、人見先輩を避けるようになってからは一度も使っていない。それなら屋上かと言われるとそうではない。ならば教室かと問われればそうかもしれが、生憎教室で食べると貰ったお菓子を見せびらかしているようで気が引けてしまい、自分のクラスの教室では食べることはせず、今は占い同好会が使用させてもらっている空き教室でこっそり一人で食べている。
正直今までは人見先輩と昼食を取っていたこともあり、一人で食事をすることに多少なりとも寂しさを感じているが、四の五の言ってられない。じゃあその前の人見先輩と昼食を取る前はどうしていたのかと聞かれると、学食で食べていたという回答になる。
鮫島高等学校でも割と有名な方の僕は、学食で一人で食べていると、いろんな人が物珍しさに相席の許可を求めてくる。それは同級生や後輩だけではなく、先輩もそうだ。相席をしたからと言って、そこで占ってほしいとは言われることはないが、そこでもなぜかお菓子をいただいたり、学食で買ったものをくれたりとよくしてくれてもらっていた。
だからといって一人で食べる昼食が嫌なわけではない。これもそれはそれでいい。
学校内に一人になれるプライベートスペースがあるというのは本当にラッキーだと思う。同好会ではあるが、占いの活動は今はほとんど教室で行っていることもあり、そもそも占い同好会に部室が存在していることを知っている生徒はほぼいない。
僕は部室にたどり着き、大きなため息を吐きながら椅子に腰掛ける。いつものように紙袋に入ったお菓子を広げ、少しずつつまんでいく。
「人見先輩と食べてたときはあんなに美味しく感じていたのに……」
僕はそんなことを呟きながら、ただ甘いだけのお菓子を頬張っていくが、美味しいと思うことはできず、数口食べただけで紙袋に手を伸ばすのを止めた。そしてまた大きな溜息を吐く。
✂ ——— ✂ ——— ✂ ——— ✂ ——— ✂
放課後になり、いつものように占いを行っていく。
最近占いが当たらなくなってきたとは言え、僕にまだまだ占ってほしいという生徒は大勢いることに感謝しつつ、今日も一人ひとり親身になって占いをしていく。
「えっと……れ、恋愛相談ということでよろしいでしょうか?」
「はい。私と人見先輩との相性を占ってください!」
「あ、相性ですか……?」
「……新島くんって人見先輩と別れたのよね?なら占ってくれるわよね?」
「え、えっと、そもそも人見先輩と僕はそういう関係じゃなくてですね……。」
「ただ仲がいいだけってこと?でも夏休み前と後では明らかに接点減ったよね。それって何かあったからよね?」
今日の依頼主は同じクラスの女子生徒である村田さんだ。
別にクラスメイトを占うことは珍しくないのだが、まさかこんなにもグイグイ来るような子だとは思っていなかった。よっぽど人見先輩と付き合いたいのだろう。
夏休み前に僕と人見先輩に学食で声を掛けてきた女子生徒とは違い、かなり清潔感を感じる子だったため、特に問題視はしていなかったが、ここまで質問攻めにされると若干の恐怖すら覚える。
というか、松本くんもそうだったが、なぜみんな僕と人見先輩が付き合っていると勘違いをしているのだろうか。確かに人見先輩とは何度かデート(?)に行ったし、昼食だって学食でいつも二人で共に食事をしていた。しかしなぜそれだけで僕が人見先輩と付き合っていると誤解するのだろうかと疑問に思う。
「……ほんとに付き合ってないの?」
「え、あ、はい。そうですけど……。どうしてそう思うんですか?」
「人見先輩があんなに優しい目をするのは新島くんだけだからよ。」
「優しい……目?」
「好きな人でも見るような目ってこと。一学期の後半は結構話題になってたのよ。」
「そう……ですか。」
「それで、占ってくれるんですか?」
「い、依頼なので。」
「そ、ならお願い。」
正直この占いはやりたくない。人見先輩を好きだと自覚してからこの手の占い依頼は今までも何度か受けては来たが、その度にやりたくないと心の何処かで思っていた。やはり人見先輩はモテるのだと再度実感するとともに、僕なんかより可愛い女の子の方が人見先輩には合っていると思う。
そう思うと徐々に自分のテンションが下がっているのがわかる。
「村田さんは現在人見先輩とお付き合いをしているわけではないので、相性を見ることは難しいです。なので村田さんが人見先輩にお近づきになるには。という視点でなら占うことはできますが、どうですか?」
「……そうなんだ。じゃあそれで。」
「わかりました。では。」
僕はタロットカードを一枚だけめくる。
緊張が走る。
もしもこのカードの結果次第で、人見先輩が村田さんと付き合うかもしれない。
心拍数が上がっていくのを感じる。
「………………。」
「ど、どういう意味なの?」
「えっと、女教皇の正位置のカードですね。大きく言えば理解者であることを示すカードになります。」
「理解者?」
「はい。好き好きアピールをするよりは、相手の気持ちに寄り添ったりする方がいい方向に進むかもって感じでしょうか?」
「それって、すでに接点がないとダメってこと?」
「いえ、そうではないです。今後接点を持つときにも生きてきます。ガツガツ行き過ぎるより、ゆとりを感じさせるくらいの距離感を意識した方がよさそうですって感じでしょうか。」
「なるほどね。……ねぇ、新島くんはほんとにそれでいいの?」
「え?」
「私、人見先輩にアプローチかけるけど?」
「え、えっと、それは個人の自由なので……。」
村田さんの言いたいことはなんとなく分かる気がするが、今は占いをしている最中であり、多くの生徒が占いを見に来ている状態だ。
この状況で”人見先輩にアプローチ掛けないで!”なんて言えるわけがない。
言ってしまえば、それは告白も同然であり、翌日には学校中がそれを知ることになるだろう。
なら恋愛系占いの依頼者は全員翌日には学校中に広まっていることになるが、問題ないのかと聞かれそうだが、僕に依頼をしてくる人は全員それを承知の上で僕に占ってほしいと依頼をしてくる。
そのため、僕に恋愛系の占いを依頼しに来る時点で一種の告白をしているのと同等なのだ。
「そ。まあいいや。私、別に人見先輩に告白しないから。」
「え?」
「今の占いで十分。私は人見先輩とは付き合えない。」
「え、いや、最初にもお伝えしましたが、占いはあくまで占いです。当たるも八卦当たらぬも八卦なので、占いの結果だけでどうこうと決めるものではないです。それは女教皇は悪いカードではありません。付き合える・付き合えないの前に挑戦してみないと結果は分からないですよ。」
「いいの。付き合えないってわかってるから。」
「……じゃあどうして、占いを依頼したんですか?」
これは素朴な疑問だ。
正直に言って占いの結果は悪くなかった。
これから徐々に人見先輩との距離を縮めるといった点ではこれ以上にないほど良いカードが出ただろう。
それなのにも関わらず、どうして村田さんは告白しないという選択を選んでいるのかが分からない。
そもそも付き合う気がないのならどうして占いの依頼をしてきたのだろうか。高校生などの盛んな時期は少しでも期待を得たいという一心で占いを受けに来るようなものじゃないのだろうか。
「それは新島くんが自分で考えて。じゃこれお礼のお菓子だから。」
村田さんはそう言うと、僕に手提げバッグと同じ大きさの紙袋いっぱいに入ったお菓子を手渡してきた。占いのお礼をしっかりと用意していたということは、やはり占いは受けたかったのだろう。しかしそれは人見先輩と付き合うためではなく、人見先輩と付き合えないことを確認するためだったということだろうか。
自分で考えてと告げた村田さんは占いを見に集まっていた人だかりをモーセのごとく切り開くと、そそくさと教室から出て行ってしまった。
「ゴホンッ。えー、じゃあ今日の占いは以上で終わりか?なら教室閉めるぞー。」
澤村先生は図ったかのように終了の合図をする。
その合図を皮切りに占いを一目見ようと集まっていた生徒たちは散り散りになり、教室を後にしていく。
僕はそんな生徒たちの後ろ姿を眺めながら、今日の占いが上手くいったことに安堵しつつも、何か胸に引っ掛かりを感じるそんな気分のまま、身支度を整えていた。
その時、教室の扉がガラッと開く。
生徒の誰かが忘れ物を取りに帰って来たのだと思い、扉の方に視線を向けると、そこに立っていたのは、先日僕に告白をしてきた松本くんだった。
「え、あ、松本くん……ど、どうしたの?」
「占いは終わりましたか?」
「う、うん……。」
「このあと時間貰ってもいいですか?」
「え……。」
「金曜日の答え、聞きたいです。」
✂ ——— ✂ ——— ✂ ——— ✂ ——— ✂
体育館と鮫島高等学校を取り囲むように建てられたフェンスとの間にある駐輪場へ向かう道中、松本くんは一切口を開くことはなかった。
会話はないが、松本くんの背中からは後をついてくるように言われているような気がして、僕も黙って松本くんを追いかける。
この時間はまだ部活中であり、部活動を行っている生徒は駐輪場に来ないし、部活を行っていない生徒はすでに帰宅済みの時間だ。
つまり今この時間に駐輪場に訪れるものはいない。
無言のこの状況に耐えかねた僕は、松本くんよりも先に口を開いた。
「えっと、返事は急がないって話じゃなかったっけ?」
「そう……だったんですけど、やっぱり聞きたくて。すみません。」
「いや、僕も返事しなきゃって思ってたから。それでさ、少し聞きたいんだけど、松本くんはどうして僕のことを好きになったの?今まで接点とかってなかったよね?」
「先輩は気付いてないと思うんですが俺、新島先輩と何度か話したことあるんですよ?」
「え?」
松本くんには申し訳ないが、僕には一切記憶になかった。
占いをしたあの日が初対面だと思っていたが、そうではないようだ。
しかしそれ以前にどこで話したかなんて、本当に分からない。
松本くんは僕の困惑度合いに気が付き、少し微笑みながら話をしてくれた。
「新島先輩って駅にある”ブランダル”っていうお店によく来ますよね?」
ブランダルとは僕がよくいっているクッキーや紅茶を購入することができるお店の名前で、人見先輩とデートするときにも行ったことがあるほどお気に入りのお店だ。
そんなブランダルの名前が出てくるということは、松本くんはそこでアルバイトをしているのかもしれない。
そう疑問に思ったタイミングで松本くんはそれを肯定するように告げた。
「俺、ブランダルでバイトしているんですよ。毎日じゃないですけどタイミングが合う日があればシフト入ってるって感じです。……俺が初めて新島先輩と話したのは店員と客の関係値の状態で話したんですよ。最初は”同じ高校の生徒だ”くらいの認識しかなかったんですけど、相当クッキーが気に入っているのか、週一くらいのペースで買いに来てたじゃないですか。いつも俺がレジだったわけじゃないですけど、選んでる表情とかはいつも見えてました。」
やはり松本くんは、ブランダルでアルバイトをしているらしい。
そして松本くんがアルバイト中に僕が何度かクッキーを買いに足を運んでいたとのことだった。
「そ、それで僕を好きになってくれたの?」
「はい。いつも楽しそうにクッキー選んでる新島先輩に徐々に魅かれていきました。一回人見先輩ともお店来ましたよね?その時もいたんですよ俺。あの時デートなんだと思いました。」
「いやあれはデートとかじゃなくて……。」
「あれはデートですよ。そして新島先輩の隣にいるのは俺じゃないんだって思いました。それが本当に嫌だった。でも新島先輩は二学期が始まってから人見先輩と距離取ってるじゃないですか。喧嘩したんだ。別れたんだって思いました。不謹慎だとは思いましたが、チャンスだとも思いました。新島先輩の隣にいることが出来るチャンスだと。だから思い切って告白しちゃいました……。」
「……。」
「……俺じゃダメですか?」
松本くんは真剣なんだ。
それなら尚更、僕の”松本くんと付き合えば人見先輩のことを忘れられるかも知れない”という最低な感情のまま松本くんの想いに答えることは出来ない。
松本くんが差し伸べてくれた手を僕は取ることなく、ゆっくりと自分の気持ちを伝える。
「松本くん。まずは僕を好きになってくれてありがとう。人から好意を向けられることなんてほとんどないから、こうやって気持ちを伝えてくれたこと。本当に嬉しいよ。本当にありがとう。そしてごめんなさい。松本くんの手を取ることは出来ません。」
「……そう……ですか。理由を聞いてもいいですか?」
松本くんは僕に向かって差し伸べてくれた手をゆっくりと降ろし、声を震わせながら僕に理由を尋ねた。きっと松本くんは自分が振られることが分かっていたのかもしれない。触れると分かったうえで、自分の気持ちを僕に伝えてくれたのだ。
その想いに答えるために、僕は松本くんからの問いかけに答える。
「好きな人がいるから、その気持ちには答えることができない……です。」
そう告げた瞬間、僕の腕は大きな手に握られ、無理やり引っ張られる。
動揺している僕を余所に、僕の腕を掴み慣れてるであろう大きな手の主は松本くんに向かって一言告げる。
「そういうことだから。」
僕はあの日のように、人見先輩の背中を追いかけるように、そして引っ張られるようにして駐輪場を後にした。
人見先輩に合わないように気を使わないといけないし、松本くんからの告白に対しても答えを出してあげないといけない。
最初こそ、このまま松本くんと付き合ってしまえば、人見先輩のことを忘れられるかもしれないなんて考えがあったが、それはあまりにも松本くんに失礼過ぎる。きっと松本くんならそれでもいいと言ってきそうではあるが、それは本当に避けたい。少しでもそんな考えにいたった自分を殴ってやりたい気分だ。
土日の二日間の休みで僕は真剣に考えた結果、松本くんにはきちんと付き合えない旨を伝えることにした。
しかしいざ伝えるとなると、気持ち的にも重いものがある。振られる方もキツいと思うが、振る方も案外心にくるものがあるらしい。
僕はそんなことを感じながら、今日も鮫島高等学校へと向かう。
一時限目から四時限目までの午前の授業は難なく過ごすことができた。それは移動教室をしなければならない授業もなく、教室で待機しているだけでよかったからである。
問題はここからだ。
昼休みはやらなければならないことが多数ある。そのうちの一つが昼食だ。以前までであれば学食を使っていたが、人見先輩を避けるようになってからは一度も使っていない。それなら屋上かと言われるとそうではない。ならば教室かと問われればそうかもしれが、生憎教室で食べると貰ったお菓子を見せびらかしているようで気が引けてしまい、自分のクラスの教室では食べることはせず、今は占い同好会が使用させてもらっている空き教室でこっそり一人で食べている。
正直今までは人見先輩と昼食を取っていたこともあり、一人で食事をすることに多少なりとも寂しさを感じているが、四の五の言ってられない。じゃあその前の人見先輩と昼食を取る前はどうしていたのかと聞かれると、学食で食べていたという回答になる。
鮫島高等学校でも割と有名な方の僕は、学食で一人で食べていると、いろんな人が物珍しさに相席の許可を求めてくる。それは同級生や後輩だけではなく、先輩もそうだ。相席をしたからと言って、そこで占ってほしいとは言われることはないが、そこでもなぜかお菓子をいただいたり、学食で買ったものをくれたりとよくしてくれてもらっていた。
だからといって一人で食べる昼食が嫌なわけではない。これもそれはそれでいい。
学校内に一人になれるプライベートスペースがあるというのは本当にラッキーだと思う。同好会ではあるが、占いの活動は今はほとんど教室で行っていることもあり、そもそも占い同好会に部室が存在していることを知っている生徒はほぼいない。
僕は部室にたどり着き、大きなため息を吐きながら椅子に腰掛ける。いつものように紙袋に入ったお菓子を広げ、少しずつつまんでいく。
「人見先輩と食べてたときはあんなに美味しく感じていたのに……」
僕はそんなことを呟きながら、ただ甘いだけのお菓子を頬張っていくが、美味しいと思うことはできず、数口食べただけで紙袋に手を伸ばすのを止めた。そしてまた大きな溜息を吐く。
✂ ——— ✂ ——— ✂ ——— ✂ ——— ✂
放課後になり、いつものように占いを行っていく。
最近占いが当たらなくなってきたとは言え、僕にまだまだ占ってほしいという生徒は大勢いることに感謝しつつ、今日も一人ひとり親身になって占いをしていく。
「えっと……れ、恋愛相談ということでよろしいでしょうか?」
「はい。私と人見先輩との相性を占ってください!」
「あ、相性ですか……?」
「……新島くんって人見先輩と別れたのよね?なら占ってくれるわよね?」
「え、えっと、そもそも人見先輩と僕はそういう関係じゃなくてですね……。」
「ただ仲がいいだけってこと?でも夏休み前と後では明らかに接点減ったよね。それって何かあったからよね?」
今日の依頼主は同じクラスの女子生徒である村田さんだ。
別にクラスメイトを占うことは珍しくないのだが、まさかこんなにもグイグイ来るような子だとは思っていなかった。よっぽど人見先輩と付き合いたいのだろう。
夏休み前に僕と人見先輩に学食で声を掛けてきた女子生徒とは違い、かなり清潔感を感じる子だったため、特に問題視はしていなかったが、ここまで質問攻めにされると若干の恐怖すら覚える。
というか、松本くんもそうだったが、なぜみんな僕と人見先輩が付き合っていると勘違いをしているのだろうか。確かに人見先輩とは何度かデート(?)に行ったし、昼食だって学食でいつも二人で共に食事をしていた。しかしなぜそれだけで僕が人見先輩と付き合っていると誤解するのだろうかと疑問に思う。
「……ほんとに付き合ってないの?」
「え、あ、はい。そうですけど……。どうしてそう思うんですか?」
「人見先輩があんなに優しい目をするのは新島くんだけだからよ。」
「優しい……目?」
「好きな人でも見るような目ってこと。一学期の後半は結構話題になってたのよ。」
「そう……ですか。」
「それで、占ってくれるんですか?」
「い、依頼なので。」
「そ、ならお願い。」
正直この占いはやりたくない。人見先輩を好きだと自覚してからこの手の占い依頼は今までも何度か受けては来たが、その度にやりたくないと心の何処かで思っていた。やはり人見先輩はモテるのだと再度実感するとともに、僕なんかより可愛い女の子の方が人見先輩には合っていると思う。
そう思うと徐々に自分のテンションが下がっているのがわかる。
「村田さんは現在人見先輩とお付き合いをしているわけではないので、相性を見ることは難しいです。なので村田さんが人見先輩にお近づきになるには。という視点でなら占うことはできますが、どうですか?」
「……そうなんだ。じゃあそれで。」
「わかりました。では。」
僕はタロットカードを一枚だけめくる。
緊張が走る。
もしもこのカードの結果次第で、人見先輩が村田さんと付き合うかもしれない。
心拍数が上がっていくのを感じる。
「………………。」
「ど、どういう意味なの?」
「えっと、女教皇の正位置のカードですね。大きく言えば理解者であることを示すカードになります。」
「理解者?」
「はい。好き好きアピールをするよりは、相手の気持ちに寄り添ったりする方がいい方向に進むかもって感じでしょうか?」
「それって、すでに接点がないとダメってこと?」
「いえ、そうではないです。今後接点を持つときにも生きてきます。ガツガツ行き過ぎるより、ゆとりを感じさせるくらいの距離感を意識した方がよさそうですって感じでしょうか。」
「なるほどね。……ねぇ、新島くんはほんとにそれでいいの?」
「え?」
「私、人見先輩にアプローチかけるけど?」
「え、えっと、それは個人の自由なので……。」
村田さんの言いたいことはなんとなく分かる気がするが、今は占いをしている最中であり、多くの生徒が占いを見に来ている状態だ。
この状況で”人見先輩にアプローチ掛けないで!”なんて言えるわけがない。
言ってしまえば、それは告白も同然であり、翌日には学校中がそれを知ることになるだろう。
なら恋愛系占いの依頼者は全員翌日には学校中に広まっていることになるが、問題ないのかと聞かれそうだが、僕に依頼をしてくる人は全員それを承知の上で僕に占ってほしいと依頼をしてくる。
そのため、僕に恋愛系の占いを依頼しに来る時点で一種の告白をしているのと同等なのだ。
「そ。まあいいや。私、別に人見先輩に告白しないから。」
「え?」
「今の占いで十分。私は人見先輩とは付き合えない。」
「え、いや、最初にもお伝えしましたが、占いはあくまで占いです。当たるも八卦当たらぬも八卦なので、占いの結果だけでどうこうと決めるものではないです。それは女教皇は悪いカードではありません。付き合える・付き合えないの前に挑戦してみないと結果は分からないですよ。」
「いいの。付き合えないってわかってるから。」
「……じゃあどうして、占いを依頼したんですか?」
これは素朴な疑問だ。
正直に言って占いの結果は悪くなかった。
これから徐々に人見先輩との距離を縮めるといった点ではこれ以上にないほど良いカードが出ただろう。
それなのにも関わらず、どうして村田さんは告白しないという選択を選んでいるのかが分からない。
そもそも付き合う気がないのならどうして占いの依頼をしてきたのだろうか。高校生などの盛んな時期は少しでも期待を得たいという一心で占いを受けに来るようなものじゃないのだろうか。
「それは新島くんが自分で考えて。じゃこれお礼のお菓子だから。」
村田さんはそう言うと、僕に手提げバッグと同じ大きさの紙袋いっぱいに入ったお菓子を手渡してきた。占いのお礼をしっかりと用意していたということは、やはり占いは受けたかったのだろう。しかしそれは人見先輩と付き合うためではなく、人見先輩と付き合えないことを確認するためだったということだろうか。
自分で考えてと告げた村田さんは占いを見に集まっていた人だかりをモーセのごとく切り開くと、そそくさと教室から出て行ってしまった。
「ゴホンッ。えー、じゃあ今日の占いは以上で終わりか?なら教室閉めるぞー。」
澤村先生は図ったかのように終了の合図をする。
その合図を皮切りに占いを一目見ようと集まっていた生徒たちは散り散りになり、教室を後にしていく。
僕はそんな生徒たちの後ろ姿を眺めながら、今日の占いが上手くいったことに安堵しつつも、何か胸に引っ掛かりを感じるそんな気分のまま、身支度を整えていた。
その時、教室の扉がガラッと開く。
生徒の誰かが忘れ物を取りに帰って来たのだと思い、扉の方に視線を向けると、そこに立っていたのは、先日僕に告白をしてきた松本くんだった。
「え、あ、松本くん……ど、どうしたの?」
「占いは終わりましたか?」
「う、うん……。」
「このあと時間貰ってもいいですか?」
「え……。」
「金曜日の答え、聞きたいです。」
✂ ——— ✂ ——— ✂ ——— ✂ ——— ✂
体育館と鮫島高等学校を取り囲むように建てられたフェンスとの間にある駐輪場へ向かう道中、松本くんは一切口を開くことはなかった。
会話はないが、松本くんの背中からは後をついてくるように言われているような気がして、僕も黙って松本くんを追いかける。
この時間はまだ部活中であり、部活動を行っている生徒は駐輪場に来ないし、部活を行っていない生徒はすでに帰宅済みの時間だ。
つまり今この時間に駐輪場に訪れるものはいない。
無言のこの状況に耐えかねた僕は、松本くんよりも先に口を開いた。
「えっと、返事は急がないって話じゃなかったっけ?」
「そう……だったんですけど、やっぱり聞きたくて。すみません。」
「いや、僕も返事しなきゃって思ってたから。それでさ、少し聞きたいんだけど、松本くんはどうして僕のことを好きになったの?今まで接点とかってなかったよね?」
「先輩は気付いてないと思うんですが俺、新島先輩と何度か話したことあるんですよ?」
「え?」
松本くんには申し訳ないが、僕には一切記憶になかった。
占いをしたあの日が初対面だと思っていたが、そうではないようだ。
しかしそれ以前にどこで話したかなんて、本当に分からない。
松本くんは僕の困惑度合いに気が付き、少し微笑みながら話をしてくれた。
「新島先輩って駅にある”ブランダル”っていうお店によく来ますよね?」
ブランダルとは僕がよくいっているクッキーや紅茶を購入することができるお店の名前で、人見先輩とデートするときにも行ったことがあるほどお気に入りのお店だ。
そんなブランダルの名前が出てくるということは、松本くんはそこでアルバイトをしているのかもしれない。
そう疑問に思ったタイミングで松本くんはそれを肯定するように告げた。
「俺、ブランダルでバイトしているんですよ。毎日じゃないですけどタイミングが合う日があればシフト入ってるって感じです。……俺が初めて新島先輩と話したのは店員と客の関係値の状態で話したんですよ。最初は”同じ高校の生徒だ”くらいの認識しかなかったんですけど、相当クッキーが気に入っているのか、週一くらいのペースで買いに来てたじゃないですか。いつも俺がレジだったわけじゃないですけど、選んでる表情とかはいつも見えてました。」
やはり松本くんは、ブランダルでアルバイトをしているらしい。
そして松本くんがアルバイト中に僕が何度かクッキーを買いに足を運んでいたとのことだった。
「そ、それで僕を好きになってくれたの?」
「はい。いつも楽しそうにクッキー選んでる新島先輩に徐々に魅かれていきました。一回人見先輩ともお店来ましたよね?その時もいたんですよ俺。あの時デートなんだと思いました。」
「いやあれはデートとかじゃなくて……。」
「あれはデートですよ。そして新島先輩の隣にいるのは俺じゃないんだって思いました。それが本当に嫌だった。でも新島先輩は二学期が始まってから人見先輩と距離取ってるじゃないですか。喧嘩したんだ。別れたんだって思いました。不謹慎だとは思いましたが、チャンスだとも思いました。新島先輩の隣にいることが出来るチャンスだと。だから思い切って告白しちゃいました……。」
「……。」
「……俺じゃダメですか?」
松本くんは真剣なんだ。
それなら尚更、僕の”松本くんと付き合えば人見先輩のことを忘れられるかも知れない”という最低な感情のまま松本くんの想いに答えることは出来ない。
松本くんが差し伸べてくれた手を僕は取ることなく、ゆっくりと自分の気持ちを伝える。
「松本くん。まずは僕を好きになってくれてありがとう。人から好意を向けられることなんてほとんどないから、こうやって気持ちを伝えてくれたこと。本当に嬉しいよ。本当にありがとう。そしてごめんなさい。松本くんの手を取ることは出来ません。」
「……そう……ですか。理由を聞いてもいいですか?」
松本くんは僕に向かって差し伸べてくれた手をゆっくりと降ろし、声を震わせながら僕に理由を尋ねた。きっと松本くんは自分が振られることが分かっていたのかもしれない。触れると分かったうえで、自分の気持ちを僕に伝えてくれたのだ。
その想いに答えるために、僕は松本くんからの問いかけに答える。
「好きな人がいるから、その気持ちには答えることができない……です。」
そう告げた瞬間、僕の腕は大きな手に握られ、無理やり引っ張られる。
動揺している僕を余所に、僕の腕を掴み慣れてるであろう大きな手の主は松本くんに向かって一言告げる。
「そういうことだから。」
僕はあの日のように、人見先輩の背中を追いかけるように、そして引っ張られるようにして駐輪場を後にした。