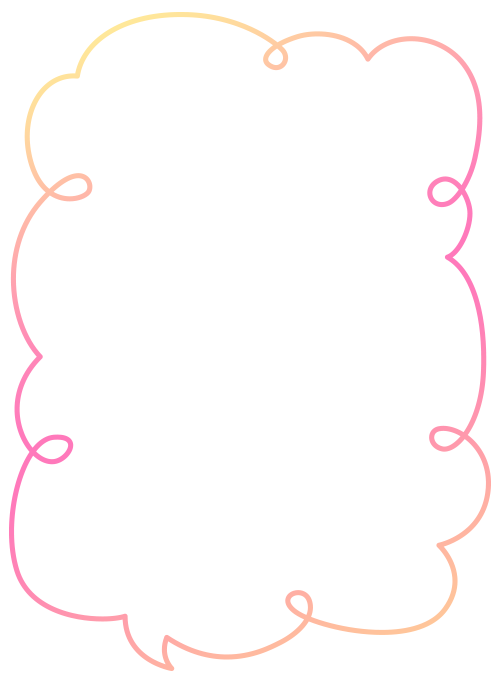仕事終わり、外に見えるイルミネーションに何となく目を惹かれて、気づけばタクシーから降りていた。そんな俺に呆れることなく一緒にいた光輝くんは嫌な顔一つせずに俺に付き合って寒空の下、電飾に彩られた街路樹の下を歩いてくれている。夜遅いことや外が寒いことからか人通りはまばらだ。
ふと、ガラスに映る光輝くんのキラキラと輝いている髪がイルミネーションの光を浴びてとても綺麗に見えた。
「奏?」
無意識だった。
呼びかけられてようやく俺は自分がしたことに気づいた。
俺の手は光輝くんの綺麗な髪に触れている。指通りが良くて艶々の光輝くんの髪は触り心地抜群だ。冬の寒さを纏っていても光を浴びてより美しいと思えてしまうほどだ。
むしろ寒々としているからこそ光が際立って見える。
名前の通り、光り輝いている。
「どうした?」
「あ……ごめん」
「何かあったか?」
「ううん、何もない」
俺の答えに光輝くんは少し笑ってくれる。
色白な光輝くんの頬がほんのりと赤く染まっていて、それが何だか胸を締めつける。
好きだなぁ……なんて気持ちが込み上げてきて、思わず見つめてしまう。
「綺麗だな」
「え?」
「奏の瞳にイルミネーションの光が映って綺麗だ」
すっ、と光輝くんの手が俺の顔に伸びて来たかと思えば優しく頬を撫でられる。
街中だから誰に見られるのかわからないけれど、触れてくる光輝くんの手の温度が心地良いから離れがたい。
「……そんな顔しないでくれ」
「……どんな顔?」
「可愛い顔だ」
頬を撫でていた手の動きは止まり、唇に何かが触れる。それは光輝くんの指で、俺の唇の形をなぞるように弄ぶ。このまま細い指先を喰んでみようか? なんて悪戯心がむくむくと大きくなってきた。夜中と呼ぶのが近い時間帯かつ人通りは少ないとは言え此処は街中だ。誰かに見られるかもしれないけれど触れ合っているのは“仲良し”と言われている俺達だ。誰も気に留めない可能性のほうが大きい。
そう思ったら好奇心には勝てなかった。
「……っ」
唇を突き出し、俺の唇に触れている光輝くんの指先にキスを落とせば光輝くんが息を呑んだのがわかった。さっきまで穏やかだった瞳が色を秘めたのを理解したけれど気づかないふりをする。
それすらも光輝くんには見透かされてそうな気もするけど。
「光輝くん」
光輝くんにだけ聞こえるように囁くように名前を呼べば、ふにっ、と唇を押し潰される。そして優しくなぞり、光輝くんは笑う。
「奏は本当に俺を煽るのが上手いな?」
「そんなことないよ」
「あるから困っているんだ」
多分部屋の中ならキスされてたと思うし、俺もそれを受け入れていた。
唇に触れた光輝くんの体温が離れていく感覚にキスに似た名残惜しさを覚えて胸が締めつけられてしまう。
好きだなぁ、なんてこう言う瞬間に再認識してしまうけど、何年経っても慣れることはない。
お互いに見つめ合い、どちらともなく笑い合う。
「帰ろうか、奏」
「うん。ありがとね」
「何がだ?」
「俺に付き合ってくれて」
「俺も奏と見たかったからな」
手は繋げないけれど、気持ちは繋がっていると思えるから寂しくはない。それでも触れ合いたいと一度思ってしまえばその気持ちを抑えられる気がしないので、自分からタクシーを降りたわけだけれど今は寮に帰りたい気持ちが大きくなっている。都合が良いのはわかっているし我儘だと言うこともわかっている。わかっているけど、でも。
これも全部、冬の所為だ。
そんなことを思いながら深い溜息を吐けば息は白く染まった。