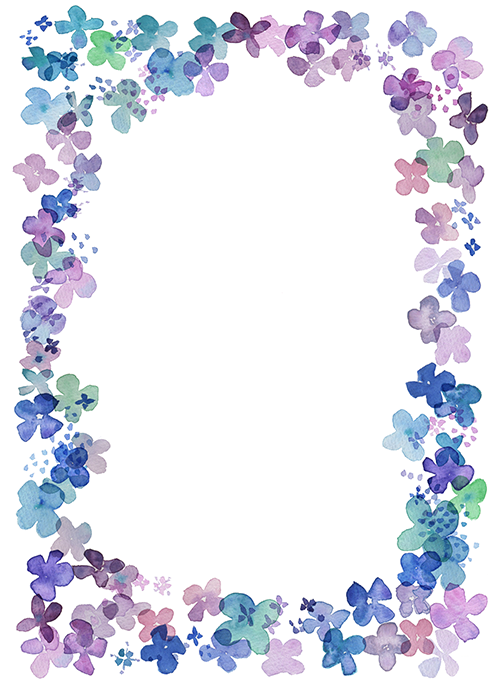その日は朝から曇天が広がっていて風が強く吹いていた。
微かに雨の匂いもして、降られるのは時間の問題だと少女は幼いながらに勘ぐる。
地面を蹴って駆け出したとき、どこからか呻き声が聞こえた。
足を止めて耳をすませるとそれは近くの洞窟から発せられているものだと分かる。
獣かもしれないと一度は後ずさるが再び聞こえたのは明確な言葉だった。
「──しい。くる、しい」
「えっ……?」
聞き間違いなどではない。
はっきりと『苦しい』と言った。
低音の声からしてその人物は男性だろう。
必死に誰かを呼んで助けを求めているのだと思い、気がつけば少女は洞窟へと向かっていた。
「あの、誰かいますか?」
昼間とはいえ洞窟の中はまるで夜のように薄暗く不気味な雰囲気に先ほどまでの勢いが萎んでいく。
しかし、人の声は確実にここから聞こえた。
恐怖に負けて逃げてしまえば助けることは叶わない。
普段なら両親に叱られるような小さな声を精いっぱい張らせながら呼びかけていく。
進むたび暗くなる周囲に目をこらしたとき。
「まだ、俺は……」
そのかき消されそうなひとりごとのような声を少女は聞き逃さなかった。
そして彼はそう遠くない場所にいる。
こちらに訴えかけるような強い意思を感じて不思議と確信を得た。
「待っていて、すぐに行くから!」
息を切らしながら迷うことなく心のままに走る。
すると辿り着いた先に驚きの光景が広がっていた。
「りゅ、龍……?」
少女はあまりの衝撃に目を見開き、言葉を失った。
自分の身体の何倍もある巨大な龍が地面に倒れているのだ。
それも大量の血を流しながら。
あまりにも残酷な姿にひゅっと息を吸い込み、足が震え始める。
龍は立ち尽くす少女に気がつくと、こちらを威嚇するように口を開けて歯を剥き出しにした。
「今すぐここから去れ!」
「……っ」
洞窟の中ということもあってか龍の怒号は反響し思わず耳を塞ぎそうになった。
命令に素直に従うべきなのだろうか。
しかし、こうしている間にも息は絶え絶えになり地面は真っ赤な血で染まっていく。
それでもなお、ここから離れない少女に苛立つように龍は最後の力を振り絞るように尾を高く上げると勢いよく叩きつけた。
まるで地震のように辺りが凄まじい揺れに襲われ、とても立ってはいられず、その場に倒れ込んでしまった。
小さな身体に強い衝撃に受け、さすがにすぐには起き上がれない。
うぅっと小さく声をあげると歯を食いしばって上半身だけを持ち上げた。
「でも貴方をこのまま放っておくわけにはいかない……」
「何を呑気に言っている!早くしないとお前も邪神の呪いを受けてしまうぞ!」
「邪神……? も、もしかして」
少女の予想は的中した。
本でしか見たことがなく伝説の存在として認識していた龍に先ほどの『神』という言葉。
そう、間違いなく目の前にいるのは龍神だ。
龍神と分かればやるべきことはただ一つ。
呪いに恐れて逃げている場合ではない。
少女は打ちつけた痛みなど忘れ、すぐに立ち上がると龍神の元へ走った。
そして出血している身体の箇所へと手をかざす。
(お父さまとお母さまには選定の儀式が終わるまで勝手に力を使うなって言われていたけれど)
「お前、まさか」
「はい。わたしは巫女の家系の者です。だから今すぐ龍神さまの傷を治します」
だが方法は知っていても実際に力を使うのは初めてで小さく細い手が震える。
少女のその姿を見て龍神はふんと小さく鼻を鳴らした。
「幼きお前に何が出来るというのだ。見るからにまだ位など判明もしていないのだろう」
「そ、それは……」
「図星か。……もう俺は疲れた。勝手にすれば良いが呪われても知らないぞ」
ゆっくりと目を閉じようとする龍神に少女は慌てて声をかけた。
このままでは彼は確実に死んでしまう。
「駄目です、龍神さま!諦めてはいけません!どうか希望をもってください!」
「もう遅い。抗ったところでこの身体は闇に蝕まれている」
視線を顔から全身へ移すと白く輝いていた鱗は中心から徐々に黒く染まっていき、その神々しさは消えていく。
「それならわたしが貴方を照らします!光を取り戻すまでずっと……!」
その少女の言葉に龍神は僅かに目を見開いたあともう何も言わなかった。
諦めて死を待っているのか彼女を信じたいと思ったのか分からない。
きっと力を使えば両親にこっぴどく叱られる。
それに儀式の前に龍神と関わったとなれば前代未聞。
だが儀式が終わってからではこの命は助からない。
少女は意を決してかざした手に強く想いを込めて祈る。
(もしわたしに癒しの力が本当にあるのならばどうかお願い。希望の光が龍神さまに届きますように)
すると手から柔らかな光が溢れ、龍神の身体全体を包み込んでいく。
そして目を開いているのもやっとなほどの眩さに思わず細めると光は粒となって弾けた。
まるで雪のような幻想的な光景に息をするのも忘れるほど。
降りそそぐ光は黒く染まりつつあった身体を元の美しい白へと戻していく。
傷が癒えて力も復活させた龍神は鋭い爪が特徴の足を使い、起き上がった。
「この力はもしや……」
「わあ……!龍神さま、とっても綺麗!」
彼の呟きは少女の喜びに満ち溢れ、弾んだ声にかき消されてしまった。
きらきらと目を輝かせる姿に先ほどの出来事が悪い夢のように思えてきた龍神は呆気にとられる。
その間にもお構いなしに彼女は本来の優美で迫力のある龍神を間近でまじまじと見ている。
そしてよほど興奮しているのか頬を赤く染めていた。
まるで観察でもしているかのようで思わず龍神はふっと吹き出してしまった。
頭上で小さく笑う彼に気がつき、少女は顔を上げる。
「龍神さま?」
「お前は面白いな」
「えっ? そ、そうでしょうか。そのようなこと初めて言われました」
「真剣な表情をしたかと思えば今のように嬉しそうに顔を綻ばす……。ころころと変わって見ていて飽きない」
そう言うと龍神はその身体から溢れるほどの光を放った。
傷を癒したときよりも強い眩しさに少女は反射的にぎゅっと固く目を閉じる。
そして眩さが消えるのを感じるとゆっくりと開く。
そこに立っていたのは龍ではなく──。
「りゅ、龍神さまが人間に……」
それはそれは麗しいほどの一人の男だった。
絹と見間違えるほどさらりとした銀髪にシミ一つない陶器のような肌。
藍色が特徴的の瞳は宝石と匹敵する。
突然目の前に現れた美丈夫にぽかんとしていると彼にとってはそんな少女の方が可笑しいのか喉をくくっと鳴らした。
「口が開きっぱなしだぞ」
「あ……」
慌てて口元を手で隠すがもうすでに遅い。
恥ずかしさで顔を真っ赤にさせる少女に男は優しく目を細めた。
「助けてくれたこと感謝する。そして怪我をしていたとはいえ、君にきつく言い過ぎた。すまなかった」
頭を下げる男に少女は慌てふためく。
龍神はこの国で最も尊ばれる存在。
比にはならないほどの高貴な彼に謝られるなんて思ってもおらず、ただ首を一生懸命、横に振ることしか出来ない。
呼び方も『お前』から『君』に変わっていて本当は優しい心の持ち主なのだと理解した。
「いえ!澄宮家の人間として当然のことをしたまでです!」
「澄宮……。ああ君はその家の娘なのか」
「わたし、澄宮撫子と言います。わたしの家をご存じなのですか?」
「ああ。優秀な巫女を輩出する名家だと。過去には龍神の花嫁に選ばれた者もいると耳にしたことがある」
「……あ!」
「急にどうした、そんな大声を出して」
会話の途中で突然、何かを思い出したように慌てふためく少女に龍神は不思議そうに見つめた。
顔を真っ青にしている様子からただ事ではないことが窺えた。
「せ、選定の儀式のことすっかり忘れてました……!」
「まさか今日なのか?」
「は、はい。おそらくもう始まっている時間のはずです。急いで帰らないと……!龍神さま、失礼いたします!」
深く頭を下げてくるりと背を向ける。
そして走り出そうとしたとき背後から声がかかった。
「待ってくれ。君に渡したいものがある」
「渡したいもの?」
振り返ると頷いた龍神は一歩近づき、自らの手のひらに握っていたものをこちらに見せた。
そこにはため息が出るほど美しい装飾が施された指輪があった。
中央にはダイヤのように煌めく宝石が埋められている。
「この指輪を君に。受け取ってくれ」
「ええっ!? こ、こんな素敵な指輪いただけません!」
きっと助けたお礼なのだろうが、こんな豪華な指輪をとても貰うことなんて出来ない。
何か対価が欲しいから傷を癒したわけではない。
ただ彼に生きてほしかった、それだけだ。
断る撫子だったが龍神も差し出す手を引くことはなかった。
薄暗いこの空間で指輪はきらりと光を放つ。
「恐れることなくまっすぐな眼差しでこちらを見てくれる君に俺は救われた。だからこそこの指輪は君にふさわしい」
「で、でもこんな大人っぽい指輪、地味なわたしには似合いません。綺麗なお姉さまやお母さまの方がよっぽど……」
「俺からすればどんな女性よりも君が一番輝いていて眩しいと思う」
「……本当にいただいてよろしいのですか?」
「ああ」
頷く龍神に断る意思はすっかり萎んでしまった。
撫子は吸い寄せられるように彼の手のひらに置かれている指輪へと手を伸ばす。
そして煌めきを小さな手の中に閉じ込めた。
「ありがとうございます。ずっと、ずっと大切にします。……あの、また会えますか」
「君が望めばきっと。その祈りはいつか再会へと導くはずだ。さあ、もう時間だ。行きなさい」
「はい」
未来でまた会える。
そう思えば心が高鳴って世界が明るくなったような気がした。
そして撫子は頭を下げて龍神に背を向けると洞窟の外へと走り出す。
屋敷での選定の儀式が終われば巫女としての日々が始まって今のように困っている龍神たちを助けられる。
精いっぱい頑張ろう、そう決意した撫子だったがすぐに絶望へと叩き落とされるのをまだ知らないのだった──。
*
「邪魔よ、お姉さま!さっさと退いてくださる?」
「ご、ごめんなさい……」
青い空が広がり白い雲が穏やかに流れ浮かぶ昼下がり。
ふわりとした栗色の長い髪を赤色のリボンで結った妹が床掃除をしていた貧相な姉を鋭い目つきで睨みつける。
広大な敷地内に建つ純和風の屋敷中に響き渡るような甲高い声にここに住む家族も仕えている使用人も一度動きを止めた。
『お姉さま』と呼ばれた娘、澄宮撫子は雑巾を握りしめたまま廊下の端へと移動する。
顔色を悪くさせながら俯く姉に妹の葵は満足げにふんと鼻を鳴らした。
「言わないと分からないなんて本当にとろいんだから。これだから無能のごみくずは困るわ」
そう言って、白色のレースが付いている制服のスカートを翻しながら一瞥し廊下の真ん中を歩いていく。
「今度は気をつけるから……」
「何度、同じことを言わせれば気が済むの? どうすれば私の機嫌を損なわないかちゃんと学びなさいよ」
「ええ……」
今にも消えそうなか細い返事に苛ついたのか葵は足を止めて腕を組んだ。
こんな状況でも彼女のつり上がる眉も怒りに染まる瞳も恐ろしく美しい。
「この星巫女の私に何か不満でもあるの?」
「そんなこと……!葵は何も間違っていない。すべて正しいわ」
「だったら澄宮の人間としてまともに返事をして。ただでさえ一週間後の龍夜の儀の準備で忙しいのだからこれ以上迷惑をかけないでくださる?」
「気をつけるわ。本当にごめんなさい」
「まったく……。こんな姉がいるなんて恥ずかしくてたまらないわ」
なぜだろう。
今のような言葉は何度も耳にしたはずなのにいっこうに慣れる気配はない。
こちらの気持ちなど気にする様子もなく、葵は古い雑巾を持ち、地味で暗い格好をしている撫子を軽蔑するかのように見下した。
そしてため息をつくと髪をなびかせながらその場をあとにしていく。
「なんて愚かなお姉さま。嘆けば嘆くほどその負の感情は私の巫女としての力を強化させるというのに」
去り際にほくそ笑みながら呟いたその言葉は悲しみに暮れている撫子の耳には届かない。
(……こんなこと今日が初めてじゃないのに。しっかりしなさい、澄宮撫子)
忘れて仕事に没頭したいのだが、がつんと殴られたような衝撃を受けて足がすくんだままだった。
ふと視界に入ったのは廊下の壁に飾られている一枚の絵画。
そこには空を舞う白龍が描かれていた。
撫子が暮らしているこの国は古来より龍神が統べている。
遙か大昔に突如として呪霊が現れ、人々を襲った。
壊滅的な被害を受けて絶望していた人間を救ったのは天界に住まう龍神だった。
そしてかつてより龍神を信仰していた巫女も立ち上がり共に豊かな世界へと導いたのだ。
その偉大な力で荒れた大地は緑が溢れ、黒く汚れた川は清らかな水に。
呪霊に襲われ怪我をした人々はたちまち回復し笑顔を取り戻した。
世界を闇から守った龍神はのちに巫女を花嫁として迎え平和な世を築いていった。
時を経ていくにつれ巫女の血を受け継ぐ者が増え宿す力によって位を与えられるようになる。
下から巫女、花巫女、星巫女、姫巫女。
澄宮家はかつて姫巫女を輩出したこともある国内でも有数の名家。
撫子の妹、葵と母のすみれは上から二番目の星巫女だ。
星巫女の存在も現代の世にとっては貴重で人々から敬われている。
そして力が強ければ強いほど龍神の花嫁に選ばれる確率が高くなる。
中には数多いる龍神たちを従える龍王に見初められる巫女もいる。
記録には昔、星巫女が龍王の花嫁として迎えられたとあるため、次は澄宮家の次女である葵ではないかと噂が囁かれているのだ。
特に天界に住む龍神たちに舞で祈りを捧げる儀式、『龍夜の儀』で月光を渡って運命の花嫁に会いにくることも多いので最近は周囲が期待で高まっていた。
彼女は歴代の中でも強い力を秘めていていずれ姫巫女に覚醒するのではという話も上がっている。
(葵もお母さまも立派な巫女なのにどうしてわたしだけ無能なの。確かにあの日、力が発現したはずなのに)
先ほどの傷が癒えないまま撫子はぼんやりと濡れた雑巾で廊下の床を拭いていく。
十年前、巫女としての力を見定める儀式で撫子は父親から無能という判断を下された。
すぐには到底、受け入れられなかった。
なぜなら撫子は儀式が始まる直前、家の近くの洞窟で瀕死状態の龍神を助けたからだ。
当時はまだ八歳だったため記憶はうろ覚えですべてを覚えているわけではないが、その事実だけは確信があった。
その出来事を話しても誰一人信じてくれなかった。
子供のただの作り話だと。
龍神から貰った指輪を見せたら信じてくれるだろうかと一瞬考えが過った。
しかし、見せてしまえば傲慢な両親に取られてしまうかもしれないと幼いながらに分かったので今日まで大切に保管したきりだ。
(葵もお母さまも高価なアクセサリーをたくさん持っているけれどあの指輪に勝るものは何も無かったわ。間違えて見られてしまっては必ず盗まれてしまう。もしそんなことがあったら龍神さまとの大切な思い出さえもきっと消えてしまうもの)
途端に懐かしくなって青白い頬に一筋の涙が伝う。
優しい彼から貰った指輪だけが撫子の心のよりどころで唯一残った希望だった。
*
龍夜の儀の当日。
年に一度の大切な儀式とあって朝早くから澄宮家は皆がせわしなく動いていた。
名前の通り儀式は夜に開かれるが準備はかなりの時間が要されるため家の中はまるで戦場のよう。
参加出来るのは巫女とその家族のみだが無能の撫子は当たり前のように外されている。
だからといって休めるわけではない。
使用人として早朝から深夜まで働き詰めだ。
巫女の力も持たない娘は我が澄宮家の娘には値しないと八歳のあの日から両親に教え込まれ、それが彼女にとっても常となった。
せめて誰かの必要になれるように。
星巫女の妹の支えになれるよう影の存在として。
「何を呆けているの、この役立たず」
「……っ!お、お母さま」
食器を片づけていた手を止めていた撫子に一喝したのはこの家の女主人であるすみれだった。
艶やかな黒髪を蝶の意匠が美しい簪で留めており、牡丹の花が存在感を放つ藤色の着物を身に纏っている。
葵と似ている眼光で睨みつけられ、ただならぬ空気にすぐに背筋が伸びた。
「呑気に休んでいるなんて何て良い御身分だこと。儀式に影響が出てしまったらどうするの? 貴女に責任がとれるのかしら」
「も、申し訳ありません」
すみれは撫子を選定の儀式から名前で呼ばなくなり自分の娘として認識しなくなった。
無能の撫子を消耗品のように、そしてその代わりに次女の葵をそれはそれは愛で宝物のように扱った。
深々と頭を下げて謝罪する撫子にすみれはため息をついて口を開いた。
「いい? 何があっても貴女は神楽殿には近づかないでちょうだい。神聖な場に巫女でもない娘がいれば儀式は台無しよ。今夜は部屋から出ないこと、分かったわね?」
「かしこまりました」
「まったく……。本当に可愛くない女ね。その背負った運命を恨むのなら自分を恨みなさい。わたくしからこの無能が生まれたかと思うとぞっとするわ」
すみれはそう吐き捨てるように言うと居間から出て行く。
そして襖がぴしゃりと閉まる音を確認してようやく撫子はそっと頭を上げた。
辺りはシンと静まり返り、微かに遠くで準備に勤しむ使用人たちの物音が聞こえる。
(お母さまのおっしゃる通りだわ。わたしのせいで儀式が失敗したら謝るだけでは済まないもの。仕事に集中しないと……)
余計な考えを振り払うように頭を左右に数回動かすと再び後片づけを始める撫子だった。
*
「もうそろそろ儀式が始まる時間ね」
部屋にいるよう母親から命じられた撫子は勉強していた手を止めて机の上に置かれている時計へと視線を向けた。
針は間もなく予定されている時刻を指そうとしている。
そして何気なくその隣にある小さな卓上カレンダーを見て気がついた。
「今日ってわたしの……」
最近は毎日、目が回るような忙しくてすっかり忘れていた。
今日は龍夜の儀であり、そして撫子の十八歳の誕生日である。
誰かに『おめでとう』と言われたらもちろん思い出すだろうけれど僅かな興味でさえ抱かれていない撫子など誰一人として祝わない。
きっと葵ならたくさんのプレゼントを贈られ祝福の言葉を降るようにかけられる。
最後に誕生日ケーキを食べたのはいつだっただろうか。
もう思い出せないほど遠い記憶になってしまったような気がする。
撫子は深く息を吐き出すと机の引き出しを開けて奥底から小さな箱を取り出す。
白色の蓋を持ち上げると中にはあの龍神から贈られた指輪が収められていた。
それを無意識に左手の薬指にはめる。
ふと外からしゃんしゃんという鈴の音が耳朶を撫でた。
葵が祭司舞を踊り始めたのだろう。
撫子の部屋からは神楽殿の一部しか見えないがその空気を少しでも感じたくて椅子から立ち上がり障子を開けた。
それと同時にひんやりとした冷たい風が身体に吹きつける。
震わせながら空を見上げると眩い輝きを放つ大きな満月が浮かんでいた。
龍夜の儀に見える満月は普段より一段と大きく異彩を放つ。
幻想的な景色に魅入っていると不思議とあの日の思い出がよみがえってきた。
もう顔も思い出せないけれど優しくしてくれたことも笑いかけてくれたことも撫子にとって永遠に特別だ。
昔も今もそして未来も。
「また会えるかな……」
思いを馳せるように指輪をはめた左手を上げて満月と重ね合わせる。
すると突然、中央に埋められた宝石から眩いほどの光が溢れ出した。
「きゃっ!」
強く、そして勢いよく放たれる光にとても目など開けてはいられず、とっさに瞑る。
この状況がまったく理解出来ず、ただ治まるのを待つことしか今の撫子には無理だった。
風も巻き上がり、障子はガタガタと揺れて机の上に置いてあったノートは早いスピードでめくれていく。
しばらくすると徐々に光と風が止む気配を感じておそるおそる目を開いた。
次の瞬間、撫子は目の前に広がる光景に驚きを隠せなかった。
「これは……?」
漆黒の夜空に浮かぶ満月の神秘的な月光がまっすぐに伸びて地上にある撫子の部屋まで繋がっていた。
うっすらとした色ではなく、はっきりと濃い色でそれはまるで道のよう。
困惑しているとふと、はめていた指輪もやわらかく輝いていることに気がつく。
不思議と目の前に現れた道に反応を示しているようにも見えた。
撫子は無能のはず。
だとしたらこれは龍夜の儀の影響なのか、それとも龍神から贈られたこの指輪に秘密があるのか──。
もう一度、視線を空へと戻すと満月の前に一体の龍が飛んでいるのに気がついた。
遠すぎて身体の色は分からないけれどかなりの大きさであることは確認出来た。
「もしかして龍神さま……? で、でもどうして人間界に?」
龍夜の儀を執り行った十八歳の娘はごく稀だが龍神の花嫁に選ばれる場合がある。
しかし葵はまだ十六歳。
強い力を宿しているとはいえ、定められている年齢には達していない。
どれだけ力を捧げようとも花嫁になるためには最低でもあと二年は待たないといけないはず。
すると龍はふわりと舞いながら地上へと降りてくる。
(こっちに来るわ……!)
逃げるのも違う気がするし、誰かを呼びに行く余裕はなく、一体どうすれば良いのか撫子は珍しく慌てふためいた。
間違いない、龍は葵がいる神楽殿ではなく撫子の部屋に一直線に向かって来ている。
そして混乱しているうちに月光の道を渡って庭へと降り立った。
同時に吹き荒れていた風は止み、静寂が訪れる。
「貴方は……」
撫子は目の前に現れた白き龍の姿に瞠目すると小さな声で呟く。
消えてしまいそうな彼女の音を龍は聞き逃さず、反対に嬉しそうに藍色の瞳を細めた。
「きっとまた会えると言っただろう? ──撫子」
彼女の名前を呼ぶと龍の身体は光に包まれ、すぐに治まったかと思えば、人間の男へと姿を変えていた。
さらりとした銀髪に長い睫毛に縁取られた藍色の瞳は撫子の中に眠る記憶を確かなものへと結びつける。
まるで奇跡のような出来事に驚きと喜びで気づけば裸足のまま庭へ降りて彼の元に駆け寄った。
辺りに転がる小石が足裏に当たるけれど今はそんなことはどうでも良かった。
「龍神さま……!」
「こら、撫子。駆け寄ってくれるのは嬉しいけれど裸足は危ないよ。大切な君の身体に傷がついたら大変だ」
(あっ、わたしったらつい……)
足元を見ると血は出てないけれど土で薄く汚れており、恥ずかしさで顔に熱が集まるのが分かった。
これではまるで外を駆けずり回る子供のようだ。
深く考えず溢れる思いのまま行動してしまったことに反省した瞬間──。
「ひゃっ!?」
身体がふわりとしたかと思えば一瞬のうちに龍神に抱き上げられていた。
彼の分厚い胸板が右耳に当たり、心臓がどくんと高鳴った。
「な、何をなさっているのですか」
「何って、いつまでも裸足のままというわけにもいかないだろう。それにあの状態ではゆっくり話も出来ないからな」
「だからって何も抱き上げなくても……!龍神さま、降ろしてくださいませ」
「桜河」
「え?」
『おうが』という言葉をすぐには理解出来ず、撫子は不思議そうに首を傾げる。
その様子を見て彼は愛おしそうに微笑みながらしっかりと頷いた。
「そういえばまだ名前を言っていなかったな。俺は白龍の桜河。龍神たちを統べる龍王だ」
「ええっ!?」
まさかあの時助けた彼が龍王だとは夢にも思わず大声を出してしまう。
慌てて口元を押さえる撫子に桜河は可笑しそうに喉をくくっと鳴らした。
「龍王である貴方さまがなぜこちらに?」
撫子の問いかけに耳を傾け、そして色香漂う唇を開いたかと思えば耳を疑う衝撃の一言を放った。
「撫子。君を俺の花嫁として迎えたい」
指輪に導かれた運命がこの日から始まるのだった──。
微かに雨の匂いもして、降られるのは時間の問題だと少女は幼いながらに勘ぐる。
地面を蹴って駆け出したとき、どこからか呻き声が聞こえた。
足を止めて耳をすませるとそれは近くの洞窟から発せられているものだと分かる。
獣かもしれないと一度は後ずさるが再び聞こえたのは明確な言葉だった。
「──しい。くる、しい」
「えっ……?」
聞き間違いなどではない。
はっきりと『苦しい』と言った。
低音の声からしてその人物は男性だろう。
必死に誰かを呼んで助けを求めているのだと思い、気がつけば少女は洞窟へと向かっていた。
「あの、誰かいますか?」
昼間とはいえ洞窟の中はまるで夜のように薄暗く不気味な雰囲気に先ほどまでの勢いが萎んでいく。
しかし、人の声は確実にここから聞こえた。
恐怖に負けて逃げてしまえば助けることは叶わない。
普段なら両親に叱られるような小さな声を精いっぱい張らせながら呼びかけていく。
進むたび暗くなる周囲に目をこらしたとき。
「まだ、俺は……」
そのかき消されそうなひとりごとのような声を少女は聞き逃さなかった。
そして彼はそう遠くない場所にいる。
こちらに訴えかけるような強い意思を感じて不思議と確信を得た。
「待っていて、すぐに行くから!」
息を切らしながら迷うことなく心のままに走る。
すると辿り着いた先に驚きの光景が広がっていた。
「りゅ、龍……?」
少女はあまりの衝撃に目を見開き、言葉を失った。
自分の身体の何倍もある巨大な龍が地面に倒れているのだ。
それも大量の血を流しながら。
あまりにも残酷な姿にひゅっと息を吸い込み、足が震え始める。
龍は立ち尽くす少女に気がつくと、こちらを威嚇するように口を開けて歯を剥き出しにした。
「今すぐここから去れ!」
「……っ」
洞窟の中ということもあってか龍の怒号は反響し思わず耳を塞ぎそうになった。
命令に素直に従うべきなのだろうか。
しかし、こうしている間にも息は絶え絶えになり地面は真っ赤な血で染まっていく。
それでもなお、ここから離れない少女に苛立つように龍は最後の力を振り絞るように尾を高く上げると勢いよく叩きつけた。
まるで地震のように辺りが凄まじい揺れに襲われ、とても立ってはいられず、その場に倒れ込んでしまった。
小さな身体に強い衝撃に受け、さすがにすぐには起き上がれない。
うぅっと小さく声をあげると歯を食いしばって上半身だけを持ち上げた。
「でも貴方をこのまま放っておくわけにはいかない……」
「何を呑気に言っている!早くしないとお前も邪神の呪いを受けてしまうぞ!」
「邪神……? も、もしかして」
少女の予想は的中した。
本でしか見たことがなく伝説の存在として認識していた龍に先ほどの『神』という言葉。
そう、間違いなく目の前にいるのは龍神だ。
龍神と分かればやるべきことはただ一つ。
呪いに恐れて逃げている場合ではない。
少女は打ちつけた痛みなど忘れ、すぐに立ち上がると龍神の元へ走った。
そして出血している身体の箇所へと手をかざす。
(お父さまとお母さまには選定の儀式が終わるまで勝手に力を使うなって言われていたけれど)
「お前、まさか」
「はい。わたしは巫女の家系の者です。だから今すぐ龍神さまの傷を治します」
だが方法は知っていても実際に力を使うのは初めてで小さく細い手が震える。
少女のその姿を見て龍神はふんと小さく鼻を鳴らした。
「幼きお前に何が出来るというのだ。見るからにまだ位など判明もしていないのだろう」
「そ、それは……」
「図星か。……もう俺は疲れた。勝手にすれば良いが呪われても知らないぞ」
ゆっくりと目を閉じようとする龍神に少女は慌てて声をかけた。
このままでは彼は確実に死んでしまう。
「駄目です、龍神さま!諦めてはいけません!どうか希望をもってください!」
「もう遅い。抗ったところでこの身体は闇に蝕まれている」
視線を顔から全身へ移すと白く輝いていた鱗は中心から徐々に黒く染まっていき、その神々しさは消えていく。
「それならわたしが貴方を照らします!光を取り戻すまでずっと……!」
その少女の言葉に龍神は僅かに目を見開いたあともう何も言わなかった。
諦めて死を待っているのか彼女を信じたいと思ったのか分からない。
きっと力を使えば両親にこっぴどく叱られる。
それに儀式の前に龍神と関わったとなれば前代未聞。
だが儀式が終わってからではこの命は助からない。
少女は意を決してかざした手に強く想いを込めて祈る。
(もしわたしに癒しの力が本当にあるのならばどうかお願い。希望の光が龍神さまに届きますように)
すると手から柔らかな光が溢れ、龍神の身体全体を包み込んでいく。
そして目を開いているのもやっとなほどの眩さに思わず細めると光は粒となって弾けた。
まるで雪のような幻想的な光景に息をするのも忘れるほど。
降りそそぐ光は黒く染まりつつあった身体を元の美しい白へと戻していく。
傷が癒えて力も復活させた龍神は鋭い爪が特徴の足を使い、起き上がった。
「この力はもしや……」
「わあ……!龍神さま、とっても綺麗!」
彼の呟きは少女の喜びに満ち溢れ、弾んだ声にかき消されてしまった。
きらきらと目を輝かせる姿に先ほどの出来事が悪い夢のように思えてきた龍神は呆気にとられる。
その間にもお構いなしに彼女は本来の優美で迫力のある龍神を間近でまじまじと見ている。
そしてよほど興奮しているのか頬を赤く染めていた。
まるで観察でもしているかのようで思わず龍神はふっと吹き出してしまった。
頭上で小さく笑う彼に気がつき、少女は顔を上げる。
「龍神さま?」
「お前は面白いな」
「えっ? そ、そうでしょうか。そのようなこと初めて言われました」
「真剣な表情をしたかと思えば今のように嬉しそうに顔を綻ばす……。ころころと変わって見ていて飽きない」
そう言うと龍神はその身体から溢れるほどの光を放った。
傷を癒したときよりも強い眩しさに少女は反射的にぎゅっと固く目を閉じる。
そして眩さが消えるのを感じるとゆっくりと開く。
そこに立っていたのは龍ではなく──。
「りゅ、龍神さまが人間に……」
それはそれは麗しいほどの一人の男だった。
絹と見間違えるほどさらりとした銀髪にシミ一つない陶器のような肌。
藍色が特徴的の瞳は宝石と匹敵する。
突然目の前に現れた美丈夫にぽかんとしていると彼にとってはそんな少女の方が可笑しいのか喉をくくっと鳴らした。
「口が開きっぱなしだぞ」
「あ……」
慌てて口元を手で隠すがもうすでに遅い。
恥ずかしさで顔を真っ赤にさせる少女に男は優しく目を細めた。
「助けてくれたこと感謝する。そして怪我をしていたとはいえ、君にきつく言い過ぎた。すまなかった」
頭を下げる男に少女は慌てふためく。
龍神はこの国で最も尊ばれる存在。
比にはならないほどの高貴な彼に謝られるなんて思ってもおらず、ただ首を一生懸命、横に振ることしか出来ない。
呼び方も『お前』から『君』に変わっていて本当は優しい心の持ち主なのだと理解した。
「いえ!澄宮家の人間として当然のことをしたまでです!」
「澄宮……。ああ君はその家の娘なのか」
「わたし、澄宮撫子と言います。わたしの家をご存じなのですか?」
「ああ。優秀な巫女を輩出する名家だと。過去には龍神の花嫁に選ばれた者もいると耳にしたことがある」
「……あ!」
「急にどうした、そんな大声を出して」
会話の途中で突然、何かを思い出したように慌てふためく少女に龍神は不思議そうに見つめた。
顔を真っ青にしている様子からただ事ではないことが窺えた。
「せ、選定の儀式のことすっかり忘れてました……!」
「まさか今日なのか?」
「は、はい。おそらくもう始まっている時間のはずです。急いで帰らないと……!龍神さま、失礼いたします!」
深く頭を下げてくるりと背を向ける。
そして走り出そうとしたとき背後から声がかかった。
「待ってくれ。君に渡したいものがある」
「渡したいもの?」
振り返ると頷いた龍神は一歩近づき、自らの手のひらに握っていたものをこちらに見せた。
そこにはため息が出るほど美しい装飾が施された指輪があった。
中央にはダイヤのように煌めく宝石が埋められている。
「この指輪を君に。受け取ってくれ」
「ええっ!? こ、こんな素敵な指輪いただけません!」
きっと助けたお礼なのだろうが、こんな豪華な指輪をとても貰うことなんて出来ない。
何か対価が欲しいから傷を癒したわけではない。
ただ彼に生きてほしかった、それだけだ。
断る撫子だったが龍神も差し出す手を引くことはなかった。
薄暗いこの空間で指輪はきらりと光を放つ。
「恐れることなくまっすぐな眼差しでこちらを見てくれる君に俺は救われた。だからこそこの指輪は君にふさわしい」
「で、でもこんな大人っぽい指輪、地味なわたしには似合いません。綺麗なお姉さまやお母さまの方がよっぽど……」
「俺からすればどんな女性よりも君が一番輝いていて眩しいと思う」
「……本当にいただいてよろしいのですか?」
「ああ」
頷く龍神に断る意思はすっかり萎んでしまった。
撫子は吸い寄せられるように彼の手のひらに置かれている指輪へと手を伸ばす。
そして煌めきを小さな手の中に閉じ込めた。
「ありがとうございます。ずっと、ずっと大切にします。……あの、また会えますか」
「君が望めばきっと。その祈りはいつか再会へと導くはずだ。さあ、もう時間だ。行きなさい」
「はい」
未来でまた会える。
そう思えば心が高鳴って世界が明るくなったような気がした。
そして撫子は頭を下げて龍神に背を向けると洞窟の外へと走り出す。
屋敷での選定の儀式が終われば巫女としての日々が始まって今のように困っている龍神たちを助けられる。
精いっぱい頑張ろう、そう決意した撫子だったがすぐに絶望へと叩き落とされるのをまだ知らないのだった──。
*
「邪魔よ、お姉さま!さっさと退いてくださる?」
「ご、ごめんなさい……」
青い空が広がり白い雲が穏やかに流れ浮かぶ昼下がり。
ふわりとした栗色の長い髪を赤色のリボンで結った妹が床掃除をしていた貧相な姉を鋭い目つきで睨みつける。
広大な敷地内に建つ純和風の屋敷中に響き渡るような甲高い声にここに住む家族も仕えている使用人も一度動きを止めた。
『お姉さま』と呼ばれた娘、澄宮撫子は雑巾を握りしめたまま廊下の端へと移動する。
顔色を悪くさせながら俯く姉に妹の葵は満足げにふんと鼻を鳴らした。
「言わないと分からないなんて本当にとろいんだから。これだから無能のごみくずは困るわ」
そう言って、白色のレースが付いている制服のスカートを翻しながら一瞥し廊下の真ん中を歩いていく。
「今度は気をつけるから……」
「何度、同じことを言わせれば気が済むの? どうすれば私の機嫌を損なわないかちゃんと学びなさいよ」
「ええ……」
今にも消えそうなか細い返事に苛ついたのか葵は足を止めて腕を組んだ。
こんな状況でも彼女のつり上がる眉も怒りに染まる瞳も恐ろしく美しい。
「この星巫女の私に何か不満でもあるの?」
「そんなこと……!葵は何も間違っていない。すべて正しいわ」
「だったら澄宮の人間としてまともに返事をして。ただでさえ一週間後の龍夜の儀の準備で忙しいのだからこれ以上迷惑をかけないでくださる?」
「気をつけるわ。本当にごめんなさい」
「まったく……。こんな姉がいるなんて恥ずかしくてたまらないわ」
なぜだろう。
今のような言葉は何度も耳にしたはずなのにいっこうに慣れる気配はない。
こちらの気持ちなど気にする様子もなく、葵は古い雑巾を持ち、地味で暗い格好をしている撫子を軽蔑するかのように見下した。
そしてため息をつくと髪をなびかせながらその場をあとにしていく。
「なんて愚かなお姉さま。嘆けば嘆くほどその負の感情は私の巫女としての力を強化させるというのに」
去り際にほくそ笑みながら呟いたその言葉は悲しみに暮れている撫子の耳には届かない。
(……こんなこと今日が初めてじゃないのに。しっかりしなさい、澄宮撫子)
忘れて仕事に没頭したいのだが、がつんと殴られたような衝撃を受けて足がすくんだままだった。
ふと視界に入ったのは廊下の壁に飾られている一枚の絵画。
そこには空を舞う白龍が描かれていた。
撫子が暮らしているこの国は古来より龍神が統べている。
遙か大昔に突如として呪霊が現れ、人々を襲った。
壊滅的な被害を受けて絶望していた人間を救ったのは天界に住まう龍神だった。
そしてかつてより龍神を信仰していた巫女も立ち上がり共に豊かな世界へと導いたのだ。
その偉大な力で荒れた大地は緑が溢れ、黒く汚れた川は清らかな水に。
呪霊に襲われ怪我をした人々はたちまち回復し笑顔を取り戻した。
世界を闇から守った龍神はのちに巫女を花嫁として迎え平和な世を築いていった。
時を経ていくにつれ巫女の血を受け継ぐ者が増え宿す力によって位を与えられるようになる。
下から巫女、花巫女、星巫女、姫巫女。
澄宮家はかつて姫巫女を輩出したこともある国内でも有数の名家。
撫子の妹、葵と母のすみれは上から二番目の星巫女だ。
星巫女の存在も現代の世にとっては貴重で人々から敬われている。
そして力が強ければ強いほど龍神の花嫁に選ばれる確率が高くなる。
中には数多いる龍神たちを従える龍王に見初められる巫女もいる。
記録には昔、星巫女が龍王の花嫁として迎えられたとあるため、次は澄宮家の次女である葵ではないかと噂が囁かれているのだ。
特に天界に住む龍神たちに舞で祈りを捧げる儀式、『龍夜の儀』で月光を渡って運命の花嫁に会いにくることも多いので最近は周囲が期待で高まっていた。
彼女は歴代の中でも強い力を秘めていていずれ姫巫女に覚醒するのではという話も上がっている。
(葵もお母さまも立派な巫女なのにどうしてわたしだけ無能なの。確かにあの日、力が発現したはずなのに)
先ほどの傷が癒えないまま撫子はぼんやりと濡れた雑巾で廊下の床を拭いていく。
十年前、巫女としての力を見定める儀式で撫子は父親から無能という判断を下された。
すぐには到底、受け入れられなかった。
なぜなら撫子は儀式が始まる直前、家の近くの洞窟で瀕死状態の龍神を助けたからだ。
当時はまだ八歳だったため記憶はうろ覚えですべてを覚えているわけではないが、その事実だけは確信があった。
その出来事を話しても誰一人信じてくれなかった。
子供のただの作り話だと。
龍神から貰った指輪を見せたら信じてくれるだろうかと一瞬考えが過った。
しかし、見せてしまえば傲慢な両親に取られてしまうかもしれないと幼いながらに分かったので今日まで大切に保管したきりだ。
(葵もお母さまも高価なアクセサリーをたくさん持っているけれどあの指輪に勝るものは何も無かったわ。間違えて見られてしまっては必ず盗まれてしまう。もしそんなことがあったら龍神さまとの大切な思い出さえもきっと消えてしまうもの)
途端に懐かしくなって青白い頬に一筋の涙が伝う。
優しい彼から貰った指輪だけが撫子の心のよりどころで唯一残った希望だった。
*
龍夜の儀の当日。
年に一度の大切な儀式とあって朝早くから澄宮家は皆がせわしなく動いていた。
名前の通り儀式は夜に開かれるが準備はかなりの時間が要されるため家の中はまるで戦場のよう。
参加出来るのは巫女とその家族のみだが無能の撫子は当たり前のように外されている。
だからといって休めるわけではない。
使用人として早朝から深夜まで働き詰めだ。
巫女の力も持たない娘は我が澄宮家の娘には値しないと八歳のあの日から両親に教え込まれ、それが彼女にとっても常となった。
せめて誰かの必要になれるように。
星巫女の妹の支えになれるよう影の存在として。
「何を呆けているの、この役立たず」
「……っ!お、お母さま」
食器を片づけていた手を止めていた撫子に一喝したのはこの家の女主人であるすみれだった。
艶やかな黒髪を蝶の意匠が美しい簪で留めており、牡丹の花が存在感を放つ藤色の着物を身に纏っている。
葵と似ている眼光で睨みつけられ、ただならぬ空気にすぐに背筋が伸びた。
「呑気に休んでいるなんて何て良い御身分だこと。儀式に影響が出てしまったらどうするの? 貴女に責任がとれるのかしら」
「も、申し訳ありません」
すみれは撫子を選定の儀式から名前で呼ばなくなり自分の娘として認識しなくなった。
無能の撫子を消耗品のように、そしてその代わりに次女の葵をそれはそれは愛で宝物のように扱った。
深々と頭を下げて謝罪する撫子にすみれはため息をついて口を開いた。
「いい? 何があっても貴女は神楽殿には近づかないでちょうだい。神聖な場に巫女でもない娘がいれば儀式は台無しよ。今夜は部屋から出ないこと、分かったわね?」
「かしこまりました」
「まったく……。本当に可愛くない女ね。その背負った運命を恨むのなら自分を恨みなさい。わたくしからこの無能が生まれたかと思うとぞっとするわ」
すみれはそう吐き捨てるように言うと居間から出て行く。
そして襖がぴしゃりと閉まる音を確認してようやく撫子はそっと頭を上げた。
辺りはシンと静まり返り、微かに遠くで準備に勤しむ使用人たちの物音が聞こえる。
(お母さまのおっしゃる通りだわ。わたしのせいで儀式が失敗したら謝るだけでは済まないもの。仕事に集中しないと……)
余計な考えを振り払うように頭を左右に数回動かすと再び後片づけを始める撫子だった。
*
「もうそろそろ儀式が始まる時間ね」
部屋にいるよう母親から命じられた撫子は勉強していた手を止めて机の上に置かれている時計へと視線を向けた。
針は間もなく予定されている時刻を指そうとしている。
そして何気なくその隣にある小さな卓上カレンダーを見て気がついた。
「今日ってわたしの……」
最近は毎日、目が回るような忙しくてすっかり忘れていた。
今日は龍夜の儀であり、そして撫子の十八歳の誕生日である。
誰かに『おめでとう』と言われたらもちろん思い出すだろうけれど僅かな興味でさえ抱かれていない撫子など誰一人として祝わない。
きっと葵ならたくさんのプレゼントを贈られ祝福の言葉を降るようにかけられる。
最後に誕生日ケーキを食べたのはいつだっただろうか。
もう思い出せないほど遠い記憶になってしまったような気がする。
撫子は深く息を吐き出すと机の引き出しを開けて奥底から小さな箱を取り出す。
白色の蓋を持ち上げると中にはあの龍神から贈られた指輪が収められていた。
それを無意識に左手の薬指にはめる。
ふと外からしゃんしゃんという鈴の音が耳朶を撫でた。
葵が祭司舞を踊り始めたのだろう。
撫子の部屋からは神楽殿の一部しか見えないがその空気を少しでも感じたくて椅子から立ち上がり障子を開けた。
それと同時にひんやりとした冷たい風が身体に吹きつける。
震わせながら空を見上げると眩い輝きを放つ大きな満月が浮かんでいた。
龍夜の儀に見える満月は普段より一段と大きく異彩を放つ。
幻想的な景色に魅入っていると不思議とあの日の思い出がよみがえってきた。
もう顔も思い出せないけれど優しくしてくれたことも笑いかけてくれたことも撫子にとって永遠に特別だ。
昔も今もそして未来も。
「また会えるかな……」
思いを馳せるように指輪をはめた左手を上げて満月と重ね合わせる。
すると突然、中央に埋められた宝石から眩いほどの光が溢れ出した。
「きゃっ!」
強く、そして勢いよく放たれる光にとても目など開けてはいられず、とっさに瞑る。
この状況がまったく理解出来ず、ただ治まるのを待つことしか今の撫子には無理だった。
風も巻き上がり、障子はガタガタと揺れて机の上に置いてあったノートは早いスピードでめくれていく。
しばらくすると徐々に光と風が止む気配を感じておそるおそる目を開いた。
次の瞬間、撫子は目の前に広がる光景に驚きを隠せなかった。
「これは……?」
漆黒の夜空に浮かぶ満月の神秘的な月光がまっすぐに伸びて地上にある撫子の部屋まで繋がっていた。
うっすらとした色ではなく、はっきりと濃い色でそれはまるで道のよう。
困惑しているとふと、はめていた指輪もやわらかく輝いていることに気がつく。
不思議と目の前に現れた道に反応を示しているようにも見えた。
撫子は無能のはず。
だとしたらこれは龍夜の儀の影響なのか、それとも龍神から贈られたこの指輪に秘密があるのか──。
もう一度、視線を空へと戻すと満月の前に一体の龍が飛んでいるのに気がついた。
遠すぎて身体の色は分からないけれどかなりの大きさであることは確認出来た。
「もしかして龍神さま……? で、でもどうして人間界に?」
龍夜の儀を執り行った十八歳の娘はごく稀だが龍神の花嫁に選ばれる場合がある。
しかし葵はまだ十六歳。
強い力を宿しているとはいえ、定められている年齢には達していない。
どれだけ力を捧げようとも花嫁になるためには最低でもあと二年は待たないといけないはず。
すると龍はふわりと舞いながら地上へと降りてくる。
(こっちに来るわ……!)
逃げるのも違う気がするし、誰かを呼びに行く余裕はなく、一体どうすれば良いのか撫子は珍しく慌てふためいた。
間違いない、龍は葵がいる神楽殿ではなく撫子の部屋に一直線に向かって来ている。
そして混乱しているうちに月光の道を渡って庭へと降り立った。
同時に吹き荒れていた風は止み、静寂が訪れる。
「貴方は……」
撫子は目の前に現れた白き龍の姿に瞠目すると小さな声で呟く。
消えてしまいそうな彼女の音を龍は聞き逃さず、反対に嬉しそうに藍色の瞳を細めた。
「きっとまた会えると言っただろう? ──撫子」
彼女の名前を呼ぶと龍の身体は光に包まれ、すぐに治まったかと思えば、人間の男へと姿を変えていた。
さらりとした銀髪に長い睫毛に縁取られた藍色の瞳は撫子の中に眠る記憶を確かなものへと結びつける。
まるで奇跡のような出来事に驚きと喜びで気づけば裸足のまま庭へ降りて彼の元に駆け寄った。
辺りに転がる小石が足裏に当たるけれど今はそんなことはどうでも良かった。
「龍神さま……!」
「こら、撫子。駆け寄ってくれるのは嬉しいけれど裸足は危ないよ。大切な君の身体に傷がついたら大変だ」
(あっ、わたしったらつい……)
足元を見ると血は出てないけれど土で薄く汚れており、恥ずかしさで顔に熱が集まるのが分かった。
これではまるで外を駆けずり回る子供のようだ。
深く考えず溢れる思いのまま行動してしまったことに反省した瞬間──。
「ひゃっ!?」
身体がふわりとしたかと思えば一瞬のうちに龍神に抱き上げられていた。
彼の分厚い胸板が右耳に当たり、心臓がどくんと高鳴った。
「な、何をなさっているのですか」
「何って、いつまでも裸足のままというわけにもいかないだろう。それにあの状態ではゆっくり話も出来ないからな」
「だからって何も抱き上げなくても……!龍神さま、降ろしてくださいませ」
「桜河」
「え?」
『おうが』という言葉をすぐには理解出来ず、撫子は不思議そうに首を傾げる。
その様子を見て彼は愛おしそうに微笑みながらしっかりと頷いた。
「そういえばまだ名前を言っていなかったな。俺は白龍の桜河。龍神たちを統べる龍王だ」
「ええっ!?」
まさかあの時助けた彼が龍王だとは夢にも思わず大声を出してしまう。
慌てて口元を押さえる撫子に桜河は可笑しそうに喉をくくっと鳴らした。
「龍王である貴方さまがなぜこちらに?」
撫子の問いかけに耳を傾け、そして色香漂う唇を開いたかと思えば耳を疑う衝撃の一言を放った。
「撫子。君を俺の花嫁として迎えたい」
指輪に導かれた運命がこの日から始まるのだった──。