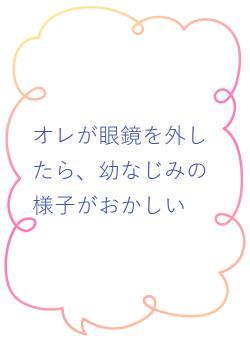八月に入った。今日も3年は課外授業。午前中から、普段と変わらない授業を受けている。外からは運動部の練習している声が時折聞こえてくる。汗を拭いながら、テニスコートでラケットを振っていた日々が遠い昔のように思える。
昼食を終え、アイスが食べたいという朝比奈と気分転換に購買へ行く。
渡り廊下に足を踏み入れると、アブラゼミのけたたましい鳴き声が聞こえてきた。容赦ない日差しに熱せられた空気が、体にまとわりつく。
「あっつ」
ハンディファンを顔に当てながら、隣りを歩く朝比奈が顔をしかめる。
「これだけ熱いと熱風だよね」
「それな」
ブツブツ文句を言いながら自動販売機に来た。
朝比奈は、クリーム系から鮮やかなシャーベットまでが揃うアイスを吟味し始めた。俺はいつものカフェオレを求めて奥へ進む。
「……まじか」
いつものボタンに点く赤ランプに、がっかり感が半端ない。アイスを手にした朝比奈が近寄ってきた。
「あ、航平の好きな濃いめカフェオレ売り切れじゃん」
「もう、ついてねー、帰りたくなってきた」
アレがないと眠気覚ましができない。それなら、レモンティーにしようと見ると、それも売り切れだった。
「アイスにカフェオレ味あるよ」
朝比奈がぺりぺりと緑色の包装を剥き、ミントグリーンのアイスを舐め始めた。
「今、ここで食べるの?」
「中庭のベンチで食べればいいじゃん」
さっきあれだけ暑いと文句を言っていたのに、外で食べるなんて矛盾している。
とりあえず、朝比奈の提案に従いアイスのボタンを押した。
ゴトンと音をたてて、カフェオレ色に包まれた棒アイスが出てくる。
「あー、航平ダメだ。カップルがいる」
こんなに暑いのに、よくもまあと朝比奈が手招きをした。外で食べようと思っていた朝比奈だって変わらないだろうと、中庭を見て全身の血の気が引くのを感じた。
そこには後ろ姿でもわかるほど、親しいふたりが並んで座っていた。
「新旧生徒会長カップルか……」
朝比奈の言葉が、ぐさりと音を立てて胸に突き刺さる。
「行こう、朝比奈」
「あ、ちょっと待ってよ」
足早に購買を後にすると、ふたたび渡り廊下を抜ける熱風に当てられた。
――好きです。
昨日、清瀬が言いかけた言葉の続きが頭に響いた。言われてないのに、熱を持った清瀬の声がリアルに響く。目の奥がじわじわ熱くなってきて、まだ手を付けていない冷たいアイスを頬に強く押さえつけた。
*
中庭で清瀬たちを見た日から、3日が過ぎた。俺はさりげなく清瀬を避けている。
夕食後、自習室へ行こうとドアを開けようとした時、清瀬と鉢合わせをしてしまった。
「あ、ごめん」
「待って」
清瀬の脇をすり抜けようとすると、手をつかまれ息を呑んだ。
「先輩、俺のこと避けてますよね」
「避けてない。自習室に行くから、手離して」
「イヤだ」
清瀬のつかんだ手が、さらにぎゅっと握られる。
「早く起きて自習室に行くし、朝食も夕食の時間も少しずらしてる。それに、部屋にいてもベッドに籠ってカーテンをずっと閉めてる。俺を避けてますよ」
図星だった。
図星過ぎて、目を合わせることができない。
「なんでですか。俺、何か嫌われるようなことしましたか?」
切羽詰まったような声色に、もう誤魔化せないと観念した。
「桜井さんのこと、好きなんだろ」
「えっ、なんでそうなるんですか」
「昼休み、ベンチで一緒にいるところを見た」
清瀬が、あっと何かを思い出したようだった。
「おまえに『可愛い』とか『ワンチャン』とか言われて、意識した俺がバカだった。最初から言えよ。必死になって生徒会室に連れて行くくらい、好きなんだろう……」
うつむいたまま、絞り出すように言った。
「それは、先輩が桜井先輩と話しているのを見て俺、嫉妬して、我慢できなくて――」
「もういいから。これ以上、俺を揺らさないでくれ」
「え、まだ話が」
清瀬の言葉を遮り、つかまれた手を強引に解く。清瀬の顔には、今まで見たことのないような困惑が滲んでいる。
「勝手に俺が勘違いしただけだから。一瞬でも清瀬が好きなのは俺かもって期待した。馬鹿みたいだよな」
恥ずかしさに顔も見ずに、そのまま部屋を出た。
ちょうど通りかかった井上が「おいおいどうした」と心配げに声をかけてきた。
「ちょっとケンカ」
「なんだよ、話聞くから」
談話室を覗くと誰もいなかった。がらんとした部屋の畳に、井上と腰を下ろした。
でも、本当のことなんて話せない。井上には悪いが、最近清瀬とケンカが多いと話した。
「なるほどね。それならすぐ部屋、替えてもらったら?」
「いや、それは」
「なんで? ちょうどいい時期じゃん。夏休みが終われば、3年は強制的にひとり部屋になるんだから。それを少し早めてもらえば」
希望すれば、3年は春からでも個室を選択できた。でも寮費が少し高くなるし、個室にこだわりはなかった。それに、清瀬との部屋は心地が良かった。
「清瀬って、とっつきにくいところがあるよな。なに考えてるかわかんないって感じ」
俺を励まそうとしているのか、清瀬が悪いとでも言いたげな口調に違和感を感じる。井上は、からかったりするところはあるが、人の悪口を言ったりしない。
「いや、そんなことない。たしかにクールに見えるけど」
「ふーん。でも生徒会長になったけど、あれはほとんど女子票だろ? 顔も頭もいいけど、つかみどころがないんだよな」
「清瀬は優しいし、何でも卒なくこなせるように見えて、でも実はすごく努力していて。一緒にいて心地がいいんだ」
「航平は、その清瀬と今まさにケンカして悩んでるんだろ? それは、清瀬が何を考えてるかわからないからじゃないの? ああ、それだけじゃないか。航平、ミスター鈍感だから」
「はあ? 今それ関係ある?」
「あるんじゃない? いつだったか和香と航平が教室出て行った後、清瀬が来て『航平先輩、どこですか』って聞いてきたんだ。和香と出て行ったって言ったら、顔色変えて追いかけて行ったから」
「え……っ」
ワークを回収に行ったあの日のことだ。
清瀬は桜井さんを連れ戻したのではなく、俺を追いかけていた?
「そして、後ろ」
井上の声に、反射的に振り返った。ドアのところに清瀬が立っていた。
「あとは、ちゃんと仲直りしろよ」
井上が去り際に清瀬の肩を叩いて談話室を出て行った。
部屋に戻り、テーブルに向かい合わせで座った。清瀬の焦燥に満ちた目に、胸がズキズキと痛む。
「今度こそ、ちゃんと話を聞いてください。俺は、和香先輩のことが好きなんて、ひとことも言ってません」
「うん」
「俺が必死に追いかけたあの日、和香先輩が告白しようとしていたことに、気づいてないんですか?」
「え?」
やっぱり、と清瀬が息を吐いた。
「今まで何度も聞かれましたよ、航平先輩のこと。だから、和香先輩の気持ちに、俺は気づいてました」
そういえば、ミスター鈍感と井上にいじられたとき、「わかる気がする」と桜井さんは笑っていた。
「どうしても、あの言葉の続きを言わせるわけにはいかなかった。本当は今だって、和香先輩の話なんてしたくないです」
「どういう意味?」
「意識して欲しくないからですよ! ただでさえ同じクラスなのに」
「いやいや、それはお前のほうだろ? いつも教室に来て。ベンチで楽しげに桜井さんと話してるの、俺見てるからな!」
「それは、桜井先輩が告白しようとしてるから、必死で止めてたんですよ」
「はっ?」
「まだわからないですか? 好きだからですよ! 俺は航平先輩のことがずっと好きだった。でも、和香先輩が告白したら、俺に勝ち目はないと思ってた。だから引き離すのに必死だったんです」
清瀬の目に涙が溜まっていく。みんなの前で見せるクールさは微塵もない。
「あの夜、先輩が電話で話してるのを聞いて、チャンスだと思いました。でも、好きだと伝えるのをためらったのも事実です。拒絶されて、一緒に居られなくなるかもしれないって思ったら怖かった」
なんだよ、もう! 早く言ってくれ! このイケメンのせいで、俺の心臓はどれだけ振り回されたんだ。
でも、俺だって清瀬に何度も聞くタイミングはあったのに、できなかった。
痛いほどわかるよ、おまえの気持ち。
ずっと我慢していた涙が、目の縁からあふれ頬を伝う。
「俺が好きなのは、優しくて、ちょっと頼りないところがあって。でも、いざとなったら誰よりも頼れる人です。そんなの、航平先輩しかいないじゃないですか」
いつもは涼し気なイケメンが、泣きそうな顔でほほえんだ。
「俺、頼れるところなんてないと思うけど」
「そんな謙虚なところも好きです。俺が寮に来た頃のこと覚えてますか?」
「うん、覚えてるよ」
「俺は冷たくみられるせいであんまり話しかけてもらえないし、先輩たちの当たりもきつくて。けれど、航平先輩がいつも輪の中に入れてくれました。そんな優しいところも好きです。それに――」
「え、まだあんの?」
「ありますよ、まだ」
「清瀬、もう十分だから。清瀬の気持ち、よくわかったから」
これ以上、清瀬にほめられたら心臓が爆発しそうだ。
「ところで先輩」
「ん?」
「先輩の気持ちはどうなんですか?」
一気に距離を近づけてきた清瀬の顔は真剣で、だけど不安が透けて見える。
同室で後輩。平凡な俺とは違うハイスペックさに気づかないふりをしていた。
清瀬のスッとした顎のラインが好きだ。クールな目も、柔らかく笑った顔も好きだ。清瀬の持つ全てが、こんなにも俺を揺らしてくる。
「好きだよ。すごく」
俺は躊躇なく眼鏡を外し、清瀬の瞳を覗き込んだ。わずかに揺れる瞳に、この想いが伝われと、ゆっくりと触れるだけのキスをした。
*
お盆を目の前に、高校のある北乃から車で2時間の西乃沢へ帰って来た。
俺の家は「深見亭」という旅館を営んでいる。決して大きな旅館ではないが、敷地内に蛍を見られるスポットがあり、この時期はリピートのお客さんが多い。
清瀬は、オープンキャンパスと帰省で、俺よりも先に寮を出ていた。離ればなれになって数日しか経っていないのに、メッセージが清瀬で埋め尽くされている。
夜も深くなり、課題に疲れて裏庭に出た。
ここには、お客さんも来ない。風になびく葉音とかすかに流れる水の音が聞こえる中、足音を立てないように秘密の場所へ静かに歩く。
腰を下ろし、青々とした茂みを見つめていると、ふわりと薄緑色の光が舞い始めた。その儚げな光に手を差し伸べてしばらく待つと、その光が手のひらに止まった。
反対の手でスマートフォンを操作し、瞬く淡い光にレンズを向けた。
『うちの裏庭』
送信した途端に既読がついて思わず頬が緩む。最初は、その速さにビビったが、もう慣れた。
「会いたいです」
清瀬のストレートな返信に胸が温かくなる。
『電話してもいい?』
「もちろんです」
通話ボタンを押すと、ワンコールもしないうちに清瀬が出た。
「俺、今から先輩のところに行きたいです」
「嬉しいけど、無理だね。めちゃくちゃ田舎だからな」
「知ってます」
「まぁ、西乃沢っていったら、とんでもない田舎だってみんな思ってるよな」
「そうじゃなくて。俺、今の時期でも蛍が見られる貴重な場所を知ってるんです」
「もしかして、ここに来たことあるの?」
「はい」
「それなら言ってくれればよかったのに」
「言おうとしましたよ、この間、先輩が熱いキスをしてくれた日に」
一瞬で、あの夜のキスを思い出し、顔が火照る。
「熱いなんて大げさだな。欧米では、あいさつでよくするぐらいの軽ーいやつだったろ」
「ここ日本だし。ちゃんと先輩の唇の感触覚えてますよ。柔らかくて――」
「はいはい、そこまで。もうやめて」
なぜ、俺があんなに大胆な行動に出られたのか、自分でもよくわからない。
「ところで、清瀬が西乃沢に来た時、ウチの旅館に泊まったの?」
「はい、小学生の頃ですけど。蛍を見てるうちに親と離れて、泣きそうになってたところを助けてもらいました。先輩に」
「俺が? ごめん。全然覚えてない」
「いいんです。俺は覚えてますから」
それから清瀬は、入寮した時、俺がいることを知って嬉しかったとか、先輩たちの冷たさにも俺がいたから耐えられたとか、最後は「運命ですね」なんて甘さの極みみたいな言葉を残して長い通話を終えた。
――早く会いたい……。
生徒会の活動で、ひと足先に寮に戻る清瀬にメッセージを送った。
*
普段なら運動部の掛け声や球の音が響く校庭も、お盆が明けたばかりの今日は静かだ。
俺は帰寮を1日早め、夕方の渡り廊下に清瀬を呼び出した。
「航平先輩」
清瀬が笑顔で走って来た。1週間ぶりの再会に思わず頬が緩む。
「久しぶり。もう、やること終わった?」
「はい。帰って来るの明日だと思ってたから、メッセージ見て嬉しくて」
「今日ならいいかと思ってさ」
「俺も、一緒に飲みたいと思ってました。好きですよ、先輩」
「おいおい、早くねぇ?」
間髪入れずに告白してくる清瀬に面食らう。
「だって、吹奏楽部が練習終わったら来ますよ、ここに」
あ、そうかと校舎から響く吹奏楽部の音に納得した。
「だから、先輩、早く」
「うん、好きだよ」
「じゃあ、早くレモンティー飲みましょう」
「ちょっと、清瀬。なんかこう、余韻とかないの?」
清瀬を見上げると、俺の問いにニンマリと笑って耳打ちをした。
「ハグは部屋で」
甘くささやかれ、ぼっと顔が熱くなる。
「余韻って、そういう意味じゃねぇよ。じんとするとかないの?」
「それならあとで。とにかく人が来る前に、レモンティーを――」
清瀬が言いかけたところで、背後から声がした。
「おーい、そこのふたりー! そろそろここの戸、鍵締めるよ」
ヤベっと声の方を向くと、手にレモンティーを持った冬月先生がいた。
「すいません。買ったら帰ります」
先生にそう言い自動販売機の赤ランプを見て、清瀬と固まった。
「あ、私のが最後だったみたい」
ごめんねーと冬月先生が言う。
冬月先生に背を向けて、小声で清瀬とどうする? と話す。
「こんなことなら、俺買ってくれば良かった。ごめん」
「先輩のせいじゃないです。お盆明けで業者が――」
「何ひそひそ話してるの?」
冬月先生の声にどきりと肩が上がった。
「もしかして、ベンチで飲みたかった?」
冬月先生の鋭い突っ込みにふたりしてたじろぐ。
なんせ、この女性教師は厳しいで有名だ。特に時間と提出物。
でも、相談事に乗ってくれるし、先生に会いに来る卒業生は多いのも、担任だったから知っている。
清瀬は担任になったことが無いから、厳しいところしか知らないかもしれない。
「はい。ベンチで飲もうと思って、清瀬くんを呼び出しました」
「え……っ」
清瀬がびっくりした顔で俺を見る。
「でも、無いのでレモンシャーベットで手を打とうと思います」
「あー、それは効果が期待できないわ」
「えっ」
清瀬と顔を見合わせた。
「レモンティー伝説は最強だから。これ譲るわ。半分こしたら?」
ふふっと笑って、先生は缶コーヒーを買い直す。
「大人は黙ってこれ飲むわ。早くしないと来るよ、吹奏楽部。あと帰る時は別ルートで帰って。渡り廊下の戸は鍵閉めるから」
ありがたく先生から譲ってもらったレモンティーにストローを差した。
「清瀬から飲めよ」
「いえ、先輩から」
「いいの?」
「はい、その方が早く間接キスできるんで」
まったく、このイケメンの甘さはどんどん強くなっていく。清瀬の思いに包まれながら冷えたレモンティーを吸い込んで、空を見上げた。
「青いな、空」
「そうですね、初めて先輩とここで見た時よりも青いですね」
パックを渡すと、清瀬もストローに口をつける。清瀬の喉仏がこくりと上下に動いた。その仕草に見惚れてしまう。
なかなか暮れない夏の空の下で、ずっと一緒にいられますようにとレモンティーをふたりで飲み干した。
昼食を終え、アイスが食べたいという朝比奈と気分転換に購買へ行く。
渡り廊下に足を踏み入れると、アブラゼミのけたたましい鳴き声が聞こえてきた。容赦ない日差しに熱せられた空気が、体にまとわりつく。
「あっつ」
ハンディファンを顔に当てながら、隣りを歩く朝比奈が顔をしかめる。
「これだけ熱いと熱風だよね」
「それな」
ブツブツ文句を言いながら自動販売機に来た。
朝比奈は、クリーム系から鮮やかなシャーベットまでが揃うアイスを吟味し始めた。俺はいつものカフェオレを求めて奥へ進む。
「……まじか」
いつものボタンに点く赤ランプに、がっかり感が半端ない。アイスを手にした朝比奈が近寄ってきた。
「あ、航平の好きな濃いめカフェオレ売り切れじゃん」
「もう、ついてねー、帰りたくなってきた」
アレがないと眠気覚ましができない。それなら、レモンティーにしようと見ると、それも売り切れだった。
「アイスにカフェオレ味あるよ」
朝比奈がぺりぺりと緑色の包装を剥き、ミントグリーンのアイスを舐め始めた。
「今、ここで食べるの?」
「中庭のベンチで食べればいいじゃん」
さっきあれだけ暑いと文句を言っていたのに、外で食べるなんて矛盾している。
とりあえず、朝比奈の提案に従いアイスのボタンを押した。
ゴトンと音をたてて、カフェオレ色に包まれた棒アイスが出てくる。
「あー、航平ダメだ。カップルがいる」
こんなに暑いのに、よくもまあと朝比奈が手招きをした。外で食べようと思っていた朝比奈だって変わらないだろうと、中庭を見て全身の血の気が引くのを感じた。
そこには後ろ姿でもわかるほど、親しいふたりが並んで座っていた。
「新旧生徒会長カップルか……」
朝比奈の言葉が、ぐさりと音を立てて胸に突き刺さる。
「行こう、朝比奈」
「あ、ちょっと待ってよ」
足早に購買を後にすると、ふたたび渡り廊下を抜ける熱風に当てられた。
――好きです。
昨日、清瀬が言いかけた言葉の続きが頭に響いた。言われてないのに、熱を持った清瀬の声がリアルに響く。目の奥がじわじわ熱くなってきて、まだ手を付けていない冷たいアイスを頬に強く押さえつけた。
*
中庭で清瀬たちを見た日から、3日が過ぎた。俺はさりげなく清瀬を避けている。
夕食後、自習室へ行こうとドアを開けようとした時、清瀬と鉢合わせをしてしまった。
「あ、ごめん」
「待って」
清瀬の脇をすり抜けようとすると、手をつかまれ息を呑んだ。
「先輩、俺のこと避けてますよね」
「避けてない。自習室に行くから、手離して」
「イヤだ」
清瀬のつかんだ手が、さらにぎゅっと握られる。
「早く起きて自習室に行くし、朝食も夕食の時間も少しずらしてる。それに、部屋にいてもベッドに籠ってカーテンをずっと閉めてる。俺を避けてますよ」
図星だった。
図星過ぎて、目を合わせることができない。
「なんでですか。俺、何か嫌われるようなことしましたか?」
切羽詰まったような声色に、もう誤魔化せないと観念した。
「桜井さんのこと、好きなんだろ」
「えっ、なんでそうなるんですか」
「昼休み、ベンチで一緒にいるところを見た」
清瀬が、あっと何かを思い出したようだった。
「おまえに『可愛い』とか『ワンチャン』とか言われて、意識した俺がバカだった。最初から言えよ。必死になって生徒会室に連れて行くくらい、好きなんだろう……」
うつむいたまま、絞り出すように言った。
「それは、先輩が桜井先輩と話しているのを見て俺、嫉妬して、我慢できなくて――」
「もういいから。これ以上、俺を揺らさないでくれ」
「え、まだ話が」
清瀬の言葉を遮り、つかまれた手を強引に解く。清瀬の顔には、今まで見たことのないような困惑が滲んでいる。
「勝手に俺が勘違いしただけだから。一瞬でも清瀬が好きなのは俺かもって期待した。馬鹿みたいだよな」
恥ずかしさに顔も見ずに、そのまま部屋を出た。
ちょうど通りかかった井上が「おいおいどうした」と心配げに声をかけてきた。
「ちょっとケンカ」
「なんだよ、話聞くから」
談話室を覗くと誰もいなかった。がらんとした部屋の畳に、井上と腰を下ろした。
でも、本当のことなんて話せない。井上には悪いが、最近清瀬とケンカが多いと話した。
「なるほどね。それならすぐ部屋、替えてもらったら?」
「いや、それは」
「なんで? ちょうどいい時期じゃん。夏休みが終われば、3年は強制的にひとり部屋になるんだから。それを少し早めてもらえば」
希望すれば、3年は春からでも個室を選択できた。でも寮費が少し高くなるし、個室にこだわりはなかった。それに、清瀬との部屋は心地が良かった。
「清瀬って、とっつきにくいところがあるよな。なに考えてるかわかんないって感じ」
俺を励まそうとしているのか、清瀬が悪いとでも言いたげな口調に違和感を感じる。井上は、からかったりするところはあるが、人の悪口を言ったりしない。
「いや、そんなことない。たしかにクールに見えるけど」
「ふーん。でも生徒会長になったけど、あれはほとんど女子票だろ? 顔も頭もいいけど、つかみどころがないんだよな」
「清瀬は優しいし、何でも卒なくこなせるように見えて、でも実はすごく努力していて。一緒にいて心地がいいんだ」
「航平は、その清瀬と今まさにケンカして悩んでるんだろ? それは、清瀬が何を考えてるかわからないからじゃないの? ああ、それだけじゃないか。航平、ミスター鈍感だから」
「はあ? 今それ関係ある?」
「あるんじゃない? いつだったか和香と航平が教室出て行った後、清瀬が来て『航平先輩、どこですか』って聞いてきたんだ。和香と出て行ったって言ったら、顔色変えて追いかけて行ったから」
「え……っ」
ワークを回収に行ったあの日のことだ。
清瀬は桜井さんを連れ戻したのではなく、俺を追いかけていた?
「そして、後ろ」
井上の声に、反射的に振り返った。ドアのところに清瀬が立っていた。
「あとは、ちゃんと仲直りしろよ」
井上が去り際に清瀬の肩を叩いて談話室を出て行った。
部屋に戻り、テーブルに向かい合わせで座った。清瀬の焦燥に満ちた目に、胸がズキズキと痛む。
「今度こそ、ちゃんと話を聞いてください。俺は、和香先輩のことが好きなんて、ひとことも言ってません」
「うん」
「俺が必死に追いかけたあの日、和香先輩が告白しようとしていたことに、気づいてないんですか?」
「え?」
やっぱり、と清瀬が息を吐いた。
「今まで何度も聞かれましたよ、航平先輩のこと。だから、和香先輩の気持ちに、俺は気づいてました」
そういえば、ミスター鈍感と井上にいじられたとき、「わかる気がする」と桜井さんは笑っていた。
「どうしても、あの言葉の続きを言わせるわけにはいかなかった。本当は今だって、和香先輩の話なんてしたくないです」
「どういう意味?」
「意識して欲しくないからですよ! ただでさえ同じクラスなのに」
「いやいや、それはお前のほうだろ? いつも教室に来て。ベンチで楽しげに桜井さんと話してるの、俺見てるからな!」
「それは、桜井先輩が告白しようとしてるから、必死で止めてたんですよ」
「はっ?」
「まだわからないですか? 好きだからですよ! 俺は航平先輩のことがずっと好きだった。でも、和香先輩が告白したら、俺に勝ち目はないと思ってた。だから引き離すのに必死だったんです」
清瀬の目に涙が溜まっていく。みんなの前で見せるクールさは微塵もない。
「あの夜、先輩が電話で話してるのを聞いて、チャンスだと思いました。でも、好きだと伝えるのをためらったのも事実です。拒絶されて、一緒に居られなくなるかもしれないって思ったら怖かった」
なんだよ、もう! 早く言ってくれ! このイケメンのせいで、俺の心臓はどれだけ振り回されたんだ。
でも、俺だって清瀬に何度も聞くタイミングはあったのに、できなかった。
痛いほどわかるよ、おまえの気持ち。
ずっと我慢していた涙が、目の縁からあふれ頬を伝う。
「俺が好きなのは、優しくて、ちょっと頼りないところがあって。でも、いざとなったら誰よりも頼れる人です。そんなの、航平先輩しかいないじゃないですか」
いつもは涼し気なイケメンが、泣きそうな顔でほほえんだ。
「俺、頼れるところなんてないと思うけど」
「そんな謙虚なところも好きです。俺が寮に来た頃のこと覚えてますか?」
「うん、覚えてるよ」
「俺は冷たくみられるせいであんまり話しかけてもらえないし、先輩たちの当たりもきつくて。けれど、航平先輩がいつも輪の中に入れてくれました。そんな優しいところも好きです。それに――」
「え、まだあんの?」
「ありますよ、まだ」
「清瀬、もう十分だから。清瀬の気持ち、よくわかったから」
これ以上、清瀬にほめられたら心臓が爆発しそうだ。
「ところで先輩」
「ん?」
「先輩の気持ちはどうなんですか?」
一気に距離を近づけてきた清瀬の顔は真剣で、だけど不安が透けて見える。
同室で後輩。平凡な俺とは違うハイスペックさに気づかないふりをしていた。
清瀬のスッとした顎のラインが好きだ。クールな目も、柔らかく笑った顔も好きだ。清瀬の持つ全てが、こんなにも俺を揺らしてくる。
「好きだよ。すごく」
俺は躊躇なく眼鏡を外し、清瀬の瞳を覗き込んだ。わずかに揺れる瞳に、この想いが伝われと、ゆっくりと触れるだけのキスをした。
*
お盆を目の前に、高校のある北乃から車で2時間の西乃沢へ帰って来た。
俺の家は「深見亭」という旅館を営んでいる。決して大きな旅館ではないが、敷地内に蛍を見られるスポットがあり、この時期はリピートのお客さんが多い。
清瀬は、オープンキャンパスと帰省で、俺よりも先に寮を出ていた。離ればなれになって数日しか経っていないのに、メッセージが清瀬で埋め尽くされている。
夜も深くなり、課題に疲れて裏庭に出た。
ここには、お客さんも来ない。風になびく葉音とかすかに流れる水の音が聞こえる中、足音を立てないように秘密の場所へ静かに歩く。
腰を下ろし、青々とした茂みを見つめていると、ふわりと薄緑色の光が舞い始めた。その儚げな光に手を差し伸べてしばらく待つと、その光が手のひらに止まった。
反対の手でスマートフォンを操作し、瞬く淡い光にレンズを向けた。
『うちの裏庭』
送信した途端に既読がついて思わず頬が緩む。最初は、その速さにビビったが、もう慣れた。
「会いたいです」
清瀬のストレートな返信に胸が温かくなる。
『電話してもいい?』
「もちろんです」
通話ボタンを押すと、ワンコールもしないうちに清瀬が出た。
「俺、今から先輩のところに行きたいです」
「嬉しいけど、無理だね。めちゃくちゃ田舎だからな」
「知ってます」
「まぁ、西乃沢っていったら、とんでもない田舎だってみんな思ってるよな」
「そうじゃなくて。俺、今の時期でも蛍が見られる貴重な場所を知ってるんです」
「もしかして、ここに来たことあるの?」
「はい」
「それなら言ってくれればよかったのに」
「言おうとしましたよ、この間、先輩が熱いキスをしてくれた日に」
一瞬で、あの夜のキスを思い出し、顔が火照る。
「熱いなんて大げさだな。欧米では、あいさつでよくするぐらいの軽ーいやつだったろ」
「ここ日本だし。ちゃんと先輩の唇の感触覚えてますよ。柔らかくて――」
「はいはい、そこまで。もうやめて」
なぜ、俺があんなに大胆な行動に出られたのか、自分でもよくわからない。
「ところで、清瀬が西乃沢に来た時、ウチの旅館に泊まったの?」
「はい、小学生の頃ですけど。蛍を見てるうちに親と離れて、泣きそうになってたところを助けてもらいました。先輩に」
「俺が? ごめん。全然覚えてない」
「いいんです。俺は覚えてますから」
それから清瀬は、入寮した時、俺がいることを知って嬉しかったとか、先輩たちの冷たさにも俺がいたから耐えられたとか、最後は「運命ですね」なんて甘さの極みみたいな言葉を残して長い通話を終えた。
――早く会いたい……。
生徒会の活動で、ひと足先に寮に戻る清瀬にメッセージを送った。
*
普段なら運動部の掛け声や球の音が響く校庭も、お盆が明けたばかりの今日は静かだ。
俺は帰寮を1日早め、夕方の渡り廊下に清瀬を呼び出した。
「航平先輩」
清瀬が笑顔で走って来た。1週間ぶりの再会に思わず頬が緩む。
「久しぶり。もう、やること終わった?」
「はい。帰って来るの明日だと思ってたから、メッセージ見て嬉しくて」
「今日ならいいかと思ってさ」
「俺も、一緒に飲みたいと思ってました。好きですよ、先輩」
「おいおい、早くねぇ?」
間髪入れずに告白してくる清瀬に面食らう。
「だって、吹奏楽部が練習終わったら来ますよ、ここに」
あ、そうかと校舎から響く吹奏楽部の音に納得した。
「だから、先輩、早く」
「うん、好きだよ」
「じゃあ、早くレモンティー飲みましょう」
「ちょっと、清瀬。なんかこう、余韻とかないの?」
清瀬を見上げると、俺の問いにニンマリと笑って耳打ちをした。
「ハグは部屋で」
甘くささやかれ、ぼっと顔が熱くなる。
「余韻って、そういう意味じゃねぇよ。じんとするとかないの?」
「それならあとで。とにかく人が来る前に、レモンティーを――」
清瀬が言いかけたところで、背後から声がした。
「おーい、そこのふたりー! そろそろここの戸、鍵締めるよ」
ヤベっと声の方を向くと、手にレモンティーを持った冬月先生がいた。
「すいません。買ったら帰ります」
先生にそう言い自動販売機の赤ランプを見て、清瀬と固まった。
「あ、私のが最後だったみたい」
ごめんねーと冬月先生が言う。
冬月先生に背を向けて、小声で清瀬とどうする? と話す。
「こんなことなら、俺買ってくれば良かった。ごめん」
「先輩のせいじゃないです。お盆明けで業者が――」
「何ひそひそ話してるの?」
冬月先生の声にどきりと肩が上がった。
「もしかして、ベンチで飲みたかった?」
冬月先生の鋭い突っ込みにふたりしてたじろぐ。
なんせ、この女性教師は厳しいで有名だ。特に時間と提出物。
でも、相談事に乗ってくれるし、先生に会いに来る卒業生は多いのも、担任だったから知っている。
清瀬は担任になったことが無いから、厳しいところしか知らないかもしれない。
「はい。ベンチで飲もうと思って、清瀬くんを呼び出しました」
「え……っ」
清瀬がびっくりした顔で俺を見る。
「でも、無いのでレモンシャーベットで手を打とうと思います」
「あー、それは効果が期待できないわ」
「えっ」
清瀬と顔を見合わせた。
「レモンティー伝説は最強だから。これ譲るわ。半分こしたら?」
ふふっと笑って、先生は缶コーヒーを買い直す。
「大人は黙ってこれ飲むわ。早くしないと来るよ、吹奏楽部。あと帰る時は別ルートで帰って。渡り廊下の戸は鍵閉めるから」
ありがたく先生から譲ってもらったレモンティーにストローを差した。
「清瀬から飲めよ」
「いえ、先輩から」
「いいの?」
「はい、その方が早く間接キスできるんで」
まったく、このイケメンの甘さはどんどん強くなっていく。清瀬の思いに包まれながら冷えたレモンティーを吸い込んで、空を見上げた。
「青いな、空」
「そうですね、初めて先輩とここで見た時よりも青いですね」
パックを渡すと、清瀬もストローに口をつける。清瀬の喉仏がこくりと上下に動いた。その仕草に見惚れてしまう。
なかなか暮れない夏の空の下で、ずっと一緒にいられますようにとレモンティーをふたりで飲み干した。