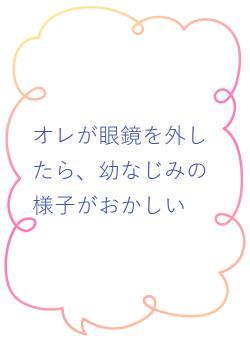テーブルで一緒に眠り込んだあの日から、二週間が経った。夏の日差しは強くなり、カーテン越しでも燦燦と部屋に降り注ぐ。
顔を合わせれば、「暑いね」が口癖になるのと同じくらい、「可愛いですね」が清瀬の口癖になっている。
「おはようございます。可愛い寝ぐせですね」
洗面所で顔を洗っていると背後から爽やかな声がした。
「もう、部屋の外ではやめてくれよ」
「じゃあ、部屋の中ならいいんですね」
清瀬がいたずらっぽく笑った。
「照れてる先輩も可愛いですね」
顔をタオルに押し当てていると、今度は耳元でささやいてくる。とろけるような甘い声に心臓が小さく跳ねる。
清瀬がどれほど本気なのか、未だにわからない。でも、俺は清瀬の言葉ひとつに感情が揺さぶられ、落ち着かない毎日を過ごしている。
その一方で、学校での清瀬は変わらない。
爽やか生徒会長の顔は崩さないし、昼休みは相変わらずウチの教室まで来て、桜井さんと廊下で話し込んでいる。桜井さんが俺に話しかけてくれば、すかさず割り込んで来て、そのまま生徒会室に連れて行ってしまう。
――勘違いするな。
やっぱり清瀬は桜井さんのことが好きだ。
あの甘くて熱っぽい言葉の数々は、きっと頼りない俺に対する面倒見のいい後輩の思いやりに過ぎない。
明日で一学期が終わり、夏休みに入る。 だから、揺さぶられる日々は、案外早く終わるのかもしれない。
「ところで先輩。相談したいことがあるんですけど、いいですか?」
夕方、帰って来た清瀬の改まった口調に、思わずドキリとする。
「相談したいことって何?」
「明日、全校集会で話さなければならないんです」
「そっか。今度からは清瀬が話すんだな」
テーブルを挟んだ向かいで清瀬がこくりと頷く。あの真夜中の勉強会以来、テーブルは出したままになっている。ふたりで話す時の定位置だ。
終業式の全校集会では、生徒会長がまとめと来学期への抱負を話す。新しく生徒会長になった清瀬にとっては、生徒の前でする初めての大仕事だ。
「それで原稿を書いてみたんですけど、しっくりこないというか」
「見ていいの? ていうか、どうして俺に?」
「先輩、国語得意じゃないですか」
「いや、そんなことないよ」
「知ってますよ。先輩がいろいろ書いて賞を取ってるの」
「え?」
「それに、今日、冬月先生に原稿を見せたら『深見くんと同じ部屋なんでしょ? 相談したら良いアドバイスもらえると思う』と言われて」
なるほど、そういうことか。
国語の冬月先生は、俺が1年の時の担任で「推薦入試に有利だから」と読書感想文やら課題を出されることが多かった。そのうちのいくつかが、たまたま賞に入っただけだ。ちなみに今、冬月先生は生徒会担当だ。
「まぐれだよ、まぐれ。でも、俺でよかったら」
「ありがとうございます」
清瀬がにこっと笑う。口元にうっすらできるえくぼ。あんまりみんな知らないんじゃないか。
早速、清瀬の几帳面さが見える、きれいな文字で書かれた原稿に目を通し始める。
「何分で話すの?」
「四分から五分です」
「ちょっと待って」
スマートフォンを取り出して、四分から五分のスピーチの文字数を調べる。
「この原稿だと少し時間が余るね。ほら、見て」
検索した画面を清瀬に見せようとすると、清瀬がスッとテーブルの脇を回り込み、航平の真横に座り直した。
「この方が見やすいんで」
「………………」
隣に座られ、膝と膝が触れ合うほどの距離に、航平の心臓が早鐘を打ち始める。
「本当ですね。一分間に三百字。五分だとして千五百字……」
「話すスピードにもよるみたいだけど」
「俺、緊張するんで字数が多くない方がいいです」
「清瀬でも緊張するの?」
「しますよ。メチャクチャ緊張しいなんで、完全に準備しないと心配で。だから、今こうして先輩に相談できて嬉しいです」
素直な笑顔を向けられ、画面を見るふりをして視線を逸らした。これ以上、目を合わせていたら心臓がどうにかなってしまいそうだ。
「いつも何かを書く時は、とりあえず調べるから」
「そうなんですね」
「どうせ書くならいいの書きたいじゃん。だから――」
スマートフォンを持つ航平の手に清瀬がそっと触れた。
「えっ……どうした?」
「ありがとうございます。俺、すげー嬉しいです」
もしかして、あの壁ドンの意味を聞くのは今なんじゃないか。
「清瀬、あのさ……」
言いかけて頭の中が真っ白になる。手から清瀬の熱が伝わり、体温が上がっていく。
「……先輩?」
ダメだ。聞けない。
じわじわと頬が熱くなってくる。手に触れたまま俺の言葉を待つ清瀬の頬も桃色に染まっていく。何かを言いたそうに清瀬の唇がわずかに開いた。けれど、無言のまま見つめ合うばかりだ。
この胸のドキドキが清瀬に届いてしまうのではないかと、俺は無意識に息を止めていた。
張り詰めた沈黙の中、俺が耐えきれずに息を吐いた瞬間、「先輩、もう限界です。考えられない」と顔を赤らめた清瀬が言った。
「そ、そうか。じゃ、一緒に考えるか」
コクッと清瀬が頷く。
「それなら一学期の行事、たとえば体育祭に触れても良いんじゃないかな? 大雨の次の日で、グラウンドの水を処理するの大変だったこととか。皆さんの協力があって無事できました、みたいな」
「いいですね」
俺の意見を清瀬は熱心に原稿に書き込んでいく。何でも卒なくこなしているように見えるが、見えないところで努力するやつだ。ちょっと加減がバグってるところはあるけれど。
それにしても、このテーブルは男ふたりで使うのには小さすぎる。同時に原稿を覗き込むと頭がぶつかりそうになって慌てて身体を引いた。
「ごめん」
「すみません。やっぱり先輩は頼りになります」
「そう?」
「はい。あと可愛いです」
とろけるような顔でささやかれ、また息が止まりそうになった。
一学期終業式。
全校集会は校長の長々としたありがたいお話から始まる。いつもなら夢の中に行く者が多数出るが、今日は暑すぎて無理だ。体育館の窓を全開にした所で、外から入ってくる風は熱されている。ただ座っているだけで額に汗が滲む。
「あっちー」
隣りに座る井上が扇子を仰いでいる。
「おいおい、それはマズくない? 結構目立ってるよ」
小声で話しかける。
「え、大丈夫だって。あれよりはいいでしょ」
回りを見ると、女子の中にハンディファンを回している人がちらほらいる。
まあ、確かにハンディファンよりはマシか。
「――次は新生徒会長の清瀬くん。一学期の総括です」
教師によるアナウンスが流れると、ざわめきの中に待ち望んでいたような歓声が混じった。
いつものクールな表情を崩さず、清瀬が登壇する。マイクの前に立つと、一呼吸置いて発声した。
「おはようございます。今日で一学期の授業が終了し、いよいよ明日から楽しみにしていた夏休みが始まります」
体育館はシーンと静まり返り、胸の前で手を組んでステージの清瀬を食い入るように見つめる女子さえいる。
――マジか……。
清瀬はいっさい原稿を見ていない。クールな表情のまま、昨日一緒に考えた原稿を淀みなく話していく。あれだけ緊張しいだと言っていたのが嘘のようだ。
「それでは、事故や怪我のないよう有意義な夏休みを過ごしてください」
最後の締めの言葉に、思わず拍手を送りたくなる。
清瀬が生徒たちを見渡した最後の瞬間、清瀬と目が合ったように感じた。そして一瞬だけ、ふわっと優しい笑顔になった。
でも、俺の斜め前には桜井さんがいる。
目が悪い俺は、それが誰に向けられたものか、判断がつかない。桜井さんの表情も見えず、あの笑顔が自分に向けられたものなのか、考え込んでしまう。
――って、俺、何を期待しているんだ……。
心臓がドクンと音を立てた。
この期待がどこから来るものなのか、熱された空気の中で、はっきりと自覚した。
*
夏休みが始まって一週間が過ぎた、七月最後の土曜日。3回目のアラームを止めると、備え付けのカーテンが開いた。
「おはようございます」
「お、おはよう」
体を起こすと、砂糖を溶かしたような甘い笑顔を向けられ、居心地の悪さに頭を搔いた。
「寝ぐせ、直しましょうか」
また始まった。
「あのさ……」
「なんですか?」
「自分で起きられるから、カーテンも開けないで」
「わかりました。でも、『なんで起こしてくれなかった』って、いつだか泣きそうになったのは、どこの誰でしたっけ」
「な、泣きそうになんかなってないだろ!」
「そうやって、むきになるのも可愛いです。とりあえず早く起きてください」
俺の抵抗をするりと躱し、清瀬は涼しい顔で準備を始める。
一時は、清瀬より早く起きて、起こされることに抵抗してみた。けれど長くは続かず、こうして起こされることが当たり前になりつつある。
夏休みでも清瀬は忙しそうだ。オープンスクールの手伝いに、夏休み明けにある文化祭の準備で、生徒会の仕事があるらしい。
結局、未だに壁ドンの真意を聞けていない。
ベッドを抜け、ジャージに着替えた。今日は中学生向けのオープンスクールがあり、課外授業は休みだ。
「今日のオープンスクール、先輩はテニス部に行くんですか?」
「うん。田舎から後輩とか、あとペア組んでたヤツの弟も来るから」
そういえば、こんな風に清瀬と距離が近くなったのは榎田の電話があった日からだ。あれから、1か月が過ぎた。
「へぇ、後輩ですか。久しぶりにテニス、やるんですか?」
「うん、少し。いつも夏休みに帰省すると、中学生たちとテニスしてるんだけど、今年はできないし。そういえば清瀬は、いつ帰るの?」
「まだ決めてないんですけど、まずは東京の大学のオープンキャンパスに行くつもりで。来週、1つ行こうか迷っている学校があって」
「そっか」
あと一週間で、しばらく会えなくなるんだ……。
(寂しいな……)
「寂しいですか?」
「え……っ」
「漏れてますよ。ね? 無自覚に漏らしてる」
「だから、言い方!」
ふわりと清瀬の口元が弧を描く。まるで俺の心の内を見透かしているかのように、優しくて少し意地悪にほほえんだ。
「先輩も寂しいんですね。俺も寂しいです。行ってきます」
甘い言葉を残して、軽やかに清瀬が部屋を出て行った。
まったく、無自覚なのはどっちだよ。
毎日、俺はアイツの言動に揺さぶられっぱなしだ。
夏の日差しが照り付けるテニスコートに、少しずつ中学生が集まり始めた。数名の後輩部員たちは、ウチの部に来てもらおうと、中学生の呼び込みに行っている。
俺はやって来た中学生に、普段の部活の様子を見せようと久しぶりにラケットを握った。
「航平せんぱーいっ!」
一段と威勢のいい男子二人がやって来た。
「コート、きれい! すげえ!」
「四面もある!」
「久しぶり!、海斗、蓮」
榎田の弟とその友達だ。いい具合に人数が集まり、早速始める。
後輩部員とのラリーを見せ、経験者の中学生にはラリーを体験してもらう。予想通り、中学生のほとんどは経験者で、軽くボールを打ち合う。
それに混じって少しだけ、海斗と蓮のふたりと乱打をする。春休みよりも、彼らが打つ球は速く力強くなっていた。
「ふたりとも上手くなってるな!」
海斗と蓮を褒めると誇らしげだ。
「でしょ? だって俺たち、県大会まで行ったんだよ」
「そうそう。俺たち、高校入ってからも続けるんだ、テニス」
「それは楽しみだな」
海斗が腕を上げ、俺は自然にハイタッチで応じた。
「またな」
ハイタッチした手を強めに握り合う。最後の一握りは、ウチの中学校のお決まりだ。続けざまに蓮ともハイタッチをして見送った。
炎天下の下、熱くなった顔の汗を拭おうと校舎に顔を向けた。それをしっかり校舎二階の窓から見ているヤツがいることに、俺は少しも気づいていなかった。
*
「先輩。手、絡ませてた」
「は!?」
清瀬が帰って来るなり、机に向かっていた航平へ拗ねたように言う。
「ずいぶんと仲がいいんですね、後輩たちと」
清瀬は、背負っていたリュックを下ろすとカーテンを閉めた。何のことかと振り返り、海斗と蓮のことかと思い出した。カーテン越しにも機嫌の悪さが滲み出ている。
「何にもしてないよ。ていうか、見てたの?」
「ハイタッチしたと思ったら、そのまま恋人つなぎしてました」
「は? そんなことしてないって。俺の住んでるところ、子供が少ないんだよ。だから年が離れていても、必然的に仲良くなるっていうか」
清瀬の声に困惑していると、シャッとカーテンが開いた。Tシャツ、短パンに着替えた清瀬が航平のそばに自分の椅子を寄せた。航平が清瀬の方を向いた瞬間、清瀬の大きな手のひらが航平の右手をぎゅっと握って来た。
「こんな風に握ってた。はっきりこの目で見ました」
「いや、ハイタッチしただけだよ」
「うそだ。触れたと思ったら、こうしてた」
清瀬が握っている航平の手を恋人つなぎに変えた。はっとして息を呑んだ。
「俺だって、したことないのに」
真っ黒に染まった清瀬の瞳から、怒りがひしひしと伝わってきた。
――嫉妬……?
浮かんだ言葉を打ち消すように、桜井さんと清瀬が廊下で楽しそうに話す姿が浮かんだ。
「離せ、清瀬。汗かくから」
「イヤです」
「なんでだよ!」
「俺は、先輩が他の誰かと親密にしているのが堪らなくイヤなんです」
「どうして」
清瀬はため息をつくと、焼け付くような目で俺を見た。
「先輩は、自分がどれだけ魅力的な人かわかってない。俺はずっと前から先輩を――」
その瞬間、201号室のドアがガンッ! と勢いよく開いた。
「清瀬~! ちょっと、これどうなってんだよ! 俺マジでわかんねえ!」
乱入してきたのは、またしても遠藤だ。
清瀬は、一瞬の舌打ちを呑み込み、即座に手を離すと、いつもの「優等生の顔」に戻った。
「遠藤。落ち着け。どうせ問題文を読んでいないんだろう」
「え、読んでるよ! でも解けねぇー」
航平は凍り付いたまま動けない。顔は火照り、心臓はドクドクと強く鼓動を続けている。
清瀬が言いかけた言葉の続きが、脳内で勝手に再生される。
――好きです。
胸が高鳴る感じも、ときどき感じる胸の痛みも味わってみたかった。
なのに、味わいたくなかったと、すぐ後に思い知らされるなんて、この夜はまだわからなかった。
顔を合わせれば、「暑いね」が口癖になるのと同じくらい、「可愛いですね」が清瀬の口癖になっている。
「おはようございます。可愛い寝ぐせですね」
洗面所で顔を洗っていると背後から爽やかな声がした。
「もう、部屋の外ではやめてくれよ」
「じゃあ、部屋の中ならいいんですね」
清瀬がいたずらっぽく笑った。
「照れてる先輩も可愛いですね」
顔をタオルに押し当てていると、今度は耳元でささやいてくる。とろけるような甘い声に心臓が小さく跳ねる。
清瀬がどれほど本気なのか、未だにわからない。でも、俺は清瀬の言葉ひとつに感情が揺さぶられ、落ち着かない毎日を過ごしている。
その一方で、学校での清瀬は変わらない。
爽やか生徒会長の顔は崩さないし、昼休みは相変わらずウチの教室まで来て、桜井さんと廊下で話し込んでいる。桜井さんが俺に話しかけてくれば、すかさず割り込んで来て、そのまま生徒会室に連れて行ってしまう。
――勘違いするな。
やっぱり清瀬は桜井さんのことが好きだ。
あの甘くて熱っぽい言葉の数々は、きっと頼りない俺に対する面倒見のいい後輩の思いやりに過ぎない。
明日で一学期が終わり、夏休みに入る。 だから、揺さぶられる日々は、案外早く終わるのかもしれない。
「ところで先輩。相談したいことがあるんですけど、いいですか?」
夕方、帰って来た清瀬の改まった口調に、思わずドキリとする。
「相談したいことって何?」
「明日、全校集会で話さなければならないんです」
「そっか。今度からは清瀬が話すんだな」
テーブルを挟んだ向かいで清瀬がこくりと頷く。あの真夜中の勉強会以来、テーブルは出したままになっている。ふたりで話す時の定位置だ。
終業式の全校集会では、生徒会長がまとめと来学期への抱負を話す。新しく生徒会長になった清瀬にとっては、生徒の前でする初めての大仕事だ。
「それで原稿を書いてみたんですけど、しっくりこないというか」
「見ていいの? ていうか、どうして俺に?」
「先輩、国語得意じゃないですか」
「いや、そんなことないよ」
「知ってますよ。先輩がいろいろ書いて賞を取ってるの」
「え?」
「それに、今日、冬月先生に原稿を見せたら『深見くんと同じ部屋なんでしょ? 相談したら良いアドバイスもらえると思う』と言われて」
なるほど、そういうことか。
国語の冬月先生は、俺が1年の時の担任で「推薦入試に有利だから」と読書感想文やら課題を出されることが多かった。そのうちのいくつかが、たまたま賞に入っただけだ。ちなみに今、冬月先生は生徒会担当だ。
「まぐれだよ、まぐれ。でも、俺でよかったら」
「ありがとうございます」
清瀬がにこっと笑う。口元にうっすらできるえくぼ。あんまりみんな知らないんじゃないか。
早速、清瀬の几帳面さが見える、きれいな文字で書かれた原稿に目を通し始める。
「何分で話すの?」
「四分から五分です」
「ちょっと待って」
スマートフォンを取り出して、四分から五分のスピーチの文字数を調べる。
「この原稿だと少し時間が余るね。ほら、見て」
検索した画面を清瀬に見せようとすると、清瀬がスッとテーブルの脇を回り込み、航平の真横に座り直した。
「この方が見やすいんで」
「………………」
隣に座られ、膝と膝が触れ合うほどの距離に、航平の心臓が早鐘を打ち始める。
「本当ですね。一分間に三百字。五分だとして千五百字……」
「話すスピードにもよるみたいだけど」
「俺、緊張するんで字数が多くない方がいいです」
「清瀬でも緊張するの?」
「しますよ。メチャクチャ緊張しいなんで、完全に準備しないと心配で。だから、今こうして先輩に相談できて嬉しいです」
素直な笑顔を向けられ、画面を見るふりをして視線を逸らした。これ以上、目を合わせていたら心臓がどうにかなってしまいそうだ。
「いつも何かを書く時は、とりあえず調べるから」
「そうなんですね」
「どうせ書くならいいの書きたいじゃん。だから――」
スマートフォンを持つ航平の手に清瀬がそっと触れた。
「えっ……どうした?」
「ありがとうございます。俺、すげー嬉しいです」
もしかして、あの壁ドンの意味を聞くのは今なんじゃないか。
「清瀬、あのさ……」
言いかけて頭の中が真っ白になる。手から清瀬の熱が伝わり、体温が上がっていく。
「……先輩?」
ダメだ。聞けない。
じわじわと頬が熱くなってくる。手に触れたまま俺の言葉を待つ清瀬の頬も桃色に染まっていく。何かを言いたそうに清瀬の唇がわずかに開いた。けれど、無言のまま見つめ合うばかりだ。
この胸のドキドキが清瀬に届いてしまうのではないかと、俺は無意識に息を止めていた。
張り詰めた沈黙の中、俺が耐えきれずに息を吐いた瞬間、「先輩、もう限界です。考えられない」と顔を赤らめた清瀬が言った。
「そ、そうか。じゃ、一緒に考えるか」
コクッと清瀬が頷く。
「それなら一学期の行事、たとえば体育祭に触れても良いんじゃないかな? 大雨の次の日で、グラウンドの水を処理するの大変だったこととか。皆さんの協力があって無事できました、みたいな」
「いいですね」
俺の意見を清瀬は熱心に原稿に書き込んでいく。何でも卒なくこなしているように見えるが、見えないところで努力するやつだ。ちょっと加減がバグってるところはあるけれど。
それにしても、このテーブルは男ふたりで使うのには小さすぎる。同時に原稿を覗き込むと頭がぶつかりそうになって慌てて身体を引いた。
「ごめん」
「すみません。やっぱり先輩は頼りになります」
「そう?」
「はい。あと可愛いです」
とろけるような顔でささやかれ、また息が止まりそうになった。
一学期終業式。
全校集会は校長の長々としたありがたいお話から始まる。いつもなら夢の中に行く者が多数出るが、今日は暑すぎて無理だ。体育館の窓を全開にした所で、外から入ってくる風は熱されている。ただ座っているだけで額に汗が滲む。
「あっちー」
隣りに座る井上が扇子を仰いでいる。
「おいおい、それはマズくない? 結構目立ってるよ」
小声で話しかける。
「え、大丈夫だって。あれよりはいいでしょ」
回りを見ると、女子の中にハンディファンを回している人がちらほらいる。
まあ、確かにハンディファンよりはマシか。
「――次は新生徒会長の清瀬くん。一学期の総括です」
教師によるアナウンスが流れると、ざわめきの中に待ち望んでいたような歓声が混じった。
いつものクールな表情を崩さず、清瀬が登壇する。マイクの前に立つと、一呼吸置いて発声した。
「おはようございます。今日で一学期の授業が終了し、いよいよ明日から楽しみにしていた夏休みが始まります」
体育館はシーンと静まり返り、胸の前で手を組んでステージの清瀬を食い入るように見つめる女子さえいる。
――マジか……。
清瀬はいっさい原稿を見ていない。クールな表情のまま、昨日一緒に考えた原稿を淀みなく話していく。あれだけ緊張しいだと言っていたのが嘘のようだ。
「それでは、事故や怪我のないよう有意義な夏休みを過ごしてください」
最後の締めの言葉に、思わず拍手を送りたくなる。
清瀬が生徒たちを見渡した最後の瞬間、清瀬と目が合ったように感じた。そして一瞬だけ、ふわっと優しい笑顔になった。
でも、俺の斜め前には桜井さんがいる。
目が悪い俺は、それが誰に向けられたものか、判断がつかない。桜井さんの表情も見えず、あの笑顔が自分に向けられたものなのか、考え込んでしまう。
――って、俺、何を期待しているんだ……。
心臓がドクンと音を立てた。
この期待がどこから来るものなのか、熱された空気の中で、はっきりと自覚した。
*
夏休みが始まって一週間が過ぎた、七月最後の土曜日。3回目のアラームを止めると、備え付けのカーテンが開いた。
「おはようございます」
「お、おはよう」
体を起こすと、砂糖を溶かしたような甘い笑顔を向けられ、居心地の悪さに頭を搔いた。
「寝ぐせ、直しましょうか」
また始まった。
「あのさ……」
「なんですか?」
「自分で起きられるから、カーテンも開けないで」
「わかりました。でも、『なんで起こしてくれなかった』って、いつだか泣きそうになったのは、どこの誰でしたっけ」
「な、泣きそうになんかなってないだろ!」
「そうやって、むきになるのも可愛いです。とりあえず早く起きてください」
俺の抵抗をするりと躱し、清瀬は涼しい顔で準備を始める。
一時は、清瀬より早く起きて、起こされることに抵抗してみた。けれど長くは続かず、こうして起こされることが当たり前になりつつある。
夏休みでも清瀬は忙しそうだ。オープンスクールの手伝いに、夏休み明けにある文化祭の準備で、生徒会の仕事があるらしい。
結局、未だに壁ドンの真意を聞けていない。
ベッドを抜け、ジャージに着替えた。今日は中学生向けのオープンスクールがあり、課外授業は休みだ。
「今日のオープンスクール、先輩はテニス部に行くんですか?」
「うん。田舎から後輩とか、あとペア組んでたヤツの弟も来るから」
そういえば、こんな風に清瀬と距離が近くなったのは榎田の電話があった日からだ。あれから、1か月が過ぎた。
「へぇ、後輩ですか。久しぶりにテニス、やるんですか?」
「うん、少し。いつも夏休みに帰省すると、中学生たちとテニスしてるんだけど、今年はできないし。そういえば清瀬は、いつ帰るの?」
「まだ決めてないんですけど、まずは東京の大学のオープンキャンパスに行くつもりで。来週、1つ行こうか迷っている学校があって」
「そっか」
あと一週間で、しばらく会えなくなるんだ……。
(寂しいな……)
「寂しいですか?」
「え……っ」
「漏れてますよ。ね? 無自覚に漏らしてる」
「だから、言い方!」
ふわりと清瀬の口元が弧を描く。まるで俺の心の内を見透かしているかのように、優しくて少し意地悪にほほえんだ。
「先輩も寂しいんですね。俺も寂しいです。行ってきます」
甘い言葉を残して、軽やかに清瀬が部屋を出て行った。
まったく、無自覚なのはどっちだよ。
毎日、俺はアイツの言動に揺さぶられっぱなしだ。
夏の日差しが照り付けるテニスコートに、少しずつ中学生が集まり始めた。数名の後輩部員たちは、ウチの部に来てもらおうと、中学生の呼び込みに行っている。
俺はやって来た中学生に、普段の部活の様子を見せようと久しぶりにラケットを握った。
「航平せんぱーいっ!」
一段と威勢のいい男子二人がやって来た。
「コート、きれい! すげえ!」
「四面もある!」
「久しぶり!、海斗、蓮」
榎田の弟とその友達だ。いい具合に人数が集まり、早速始める。
後輩部員とのラリーを見せ、経験者の中学生にはラリーを体験してもらう。予想通り、中学生のほとんどは経験者で、軽くボールを打ち合う。
それに混じって少しだけ、海斗と蓮のふたりと乱打をする。春休みよりも、彼らが打つ球は速く力強くなっていた。
「ふたりとも上手くなってるな!」
海斗と蓮を褒めると誇らしげだ。
「でしょ? だって俺たち、県大会まで行ったんだよ」
「そうそう。俺たち、高校入ってからも続けるんだ、テニス」
「それは楽しみだな」
海斗が腕を上げ、俺は自然にハイタッチで応じた。
「またな」
ハイタッチした手を強めに握り合う。最後の一握りは、ウチの中学校のお決まりだ。続けざまに蓮ともハイタッチをして見送った。
炎天下の下、熱くなった顔の汗を拭おうと校舎に顔を向けた。それをしっかり校舎二階の窓から見ているヤツがいることに、俺は少しも気づいていなかった。
*
「先輩。手、絡ませてた」
「は!?」
清瀬が帰って来るなり、机に向かっていた航平へ拗ねたように言う。
「ずいぶんと仲がいいんですね、後輩たちと」
清瀬は、背負っていたリュックを下ろすとカーテンを閉めた。何のことかと振り返り、海斗と蓮のことかと思い出した。カーテン越しにも機嫌の悪さが滲み出ている。
「何にもしてないよ。ていうか、見てたの?」
「ハイタッチしたと思ったら、そのまま恋人つなぎしてました」
「は? そんなことしてないって。俺の住んでるところ、子供が少ないんだよ。だから年が離れていても、必然的に仲良くなるっていうか」
清瀬の声に困惑していると、シャッとカーテンが開いた。Tシャツ、短パンに着替えた清瀬が航平のそばに自分の椅子を寄せた。航平が清瀬の方を向いた瞬間、清瀬の大きな手のひらが航平の右手をぎゅっと握って来た。
「こんな風に握ってた。はっきりこの目で見ました」
「いや、ハイタッチしただけだよ」
「うそだ。触れたと思ったら、こうしてた」
清瀬が握っている航平の手を恋人つなぎに変えた。はっとして息を呑んだ。
「俺だって、したことないのに」
真っ黒に染まった清瀬の瞳から、怒りがひしひしと伝わってきた。
――嫉妬……?
浮かんだ言葉を打ち消すように、桜井さんと清瀬が廊下で楽しそうに話す姿が浮かんだ。
「離せ、清瀬。汗かくから」
「イヤです」
「なんでだよ!」
「俺は、先輩が他の誰かと親密にしているのが堪らなくイヤなんです」
「どうして」
清瀬はため息をつくと、焼け付くような目で俺を見た。
「先輩は、自分がどれだけ魅力的な人かわかってない。俺はずっと前から先輩を――」
その瞬間、201号室のドアがガンッ! と勢いよく開いた。
「清瀬~! ちょっと、これどうなってんだよ! 俺マジでわかんねえ!」
乱入してきたのは、またしても遠藤だ。
清瀬は、一瞬の舌打ちを呑み込み、即座に手を離すと、いつもの「優等生の顔」に戻った。
「遠藤。落ち着け。どうせ問題文を読んでいないんだろう」
「え、読んでるよ! でも解けねぇー」
航平は凍り付いたまま動けない。顔は火照り、心臓はドクドクと強く鼓動を続けている。
清瀬が言いかけた言葉の続きが、脳内で勝手に再生される。
――好きです。
胸が高鳴る感じも、ときどき感じる胸の痛みも味わってみたかった。
なのに、味わいたくなかったと、すぐ後に思い知らされるなんて、この夜はまだわからなかった。