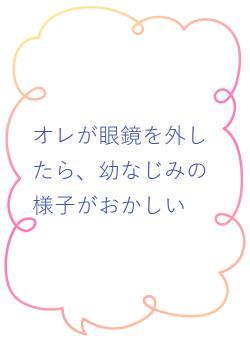「……先輩、……起きて……。起きてください、航平先輩」
スッとカーテンが引かれ、朝の光が差し込んだ。
急な眩しさに重いまぶたをうっすら開けると、光を背にした清瀬と目が合った。心臓が大きく跳ね、ビクッとした。
「おはようございます」
「お、おはよう……清瀬」
朝から爽やかな笑顔を向けられ、目をすがめた。イケメン過ぎて眩しいなんて、一体どうなってんだ。いや、それより昨日のことがあったのに、なんで清瀬は平然としてるんだ。
「朝ご飯の時間まで10分もないんで、急いでください。俺は生徒会があるんで、行きますね」
手を差し出され、思わず手をつかむとゆっくり引き上げられた。
――はっ!?
反射的に手をつかんでしまった。
何をやってるんだ俺は! 違う、違う! 反射、これは断じて反射!
「ふふっ、可愛いです」
急に手が伸びてきて、頭の後ろを撫でられた。びっくりして固まる俺に近づいた清瀬からは、いい香りがする。
「寝ぐせ、俺の机にあるミスト使ってください。本当は俺が直してあげたかったけど」
「え……っ」
「行ってきます」
あっけにとられた木曜日。
新生徒会長の清瀬は、いつもより早く部屋を出ていった。
清瀬のミストのおかげで、手ごわい寝ぐせは何とか収まった。爆速で朝食をとり、正門を目指す。
(なんで同じ敷地にあるのに、南からぐるっと回って北側の正門まで走らないといけないんだよ……)
息を切らしながら駆け足で校門をくぐると、向こうで生徒会役員が定例のあいさつ運動をしているのが見えた。
清瀬は、登校してくる生徒に爽やかな笑みを向けている。その完璧な「生徒会長の顔」は、昨夜、壁に追い込まれながら見た表情とは、まるで違う。
爽やか清瀬の隣には、前生徒会長の桜井和香がいる。きりりとした目元を緩ませて挨拶すると、肩にかかるボブの髪が軽やかに弾んだ。
「あ、ふかみん!」
俺を見るなり桜井さんが走って来た。途端に、後ろで清瀬の表情が曇った。
「おはよう。ふかみんに頼みたいことがあって」
聞けば、朝のうちに古典のワークを集めて、冬月先生に持っていかなければならないのに、急に生徒会の活動に駆り出されたという。冬月先生は時間に厳しい人で、提出が遅れるとクラス全員に迷惑がかかる。
「途中まで集めたワーク、教卓の上にあるから」
「わかった。あとはやっておく」
「ありがとう、ほんと助かる」
「たいしたことないよ。じゃ、急ぐね」
決して余裕のある時間ではないところに仕事が増えた。このやり取りを見て、さらに引きつった表情になっている清瀬を敢えて見ないふりをして、俺は急ぎ足で昇降口へ入った。
*
昼休み。
教室で井上と朝比奈の三人で弁当を食べ始める。
「今日、カツじゃん」
目の前で、テンション高めにカツを頬張るのは井上遼介。バスケの特待生で、俺と同じ寮生だ。その隣で涼やかに購買のパンを食べているのが朝比奈奏斗。中性的な顔立ちで、柔らかそうな髪は明るい栗色をしている。
弁当の蓋を開けた途端、後ろから声をかけられた。
「ふかみん、ちょっといい?」
振り向くと桜井さんだった。
「どうしたの?」
「お昼食べ終わったら、ワークを取りに行くの手伝ってもらえないかな?」
「それなら、俺行こうか? 和香の頼みなら、いくらでも聞くよ!」
すかさず井上が言うと、桜井さんは少し困ったような曖昧な笑みを浮かべた。
「ごめん、井上くん。できれば、ふかみんにお願いしたいんだけど……」
井上と朝比奈の視線が俺に向く。
――今朝、持って行ったのが俺だからか。
「いいよ。行くとき声かけて」
「ありがとう」
にこっと笑みを向けて席に戻った。
「あのさ……」
井上の手招きに、朝比奈とふたりで顔を寄せた。
「和香って、航平のこと好きなんじゃね?」
「は?」
「あー、俺もそう思う。結構前からじゃない?」
「だよな」
俺は、ふたりの指摘を即座に否定する。
「なんで? そんなことないって」
「いやいや、和香ってひとりで何でもやってのけるタイプじゃん。会長やるぐらいだし。でも、その和香が何かを頼むのは、いつも航平だよな」
「そう! 他の奴には頼まないよね」
朝比奈が井上に同調した。
「それは、単に頼みやすいからじゃない? 俺、今までもずっとそういう役回りだし」
「まったく、航平は『ミスター鈍感』だな」
「はあ? なんだよそれ、いやだな。変な称号付けるのやめてくれ」
でも、井上の言うことには、いつも鋭いところがある。バスケ部では主将を務め、部員にも慕われている。複数の大学から推薦のオファーがくるほどプレーも上手い。
その日の弁当の時間は「なぁ、ミスター鈍感どう思う?」「そういえばミスター鈍感、今日は寝ぐせついてないね」と、ありがたくもない称号でふたりに何度もいじられた。
「もういいって!」
笑いながらそう言ったとき、ちょうど弁当を食べ終えた桜井さんが声をかけてきた。席から立ち上がり廊下へ足を向ける。
「いってらっしゃい! ミスター鈍感」
後ろから井上の声がした。
「まだ言ってんのかよ、やめてくれ」
笑いながら向き直ると、隣の桜井さんがクスクス笑っている。
「ふかみんのあだ名、ミスター鈍感になったの?」
「まったく井上のヤツ。いつも変なあだ名付けてくるんだよ」
「でも、ちょっとわかる気がする」
「えっ、桜井さんまで……。俺ってそんなに鈍感?」
「うん」
「そうなの?」
「うん、だって私――」
一瞬、桜井さんは何かを言いかけて口をつぐんだ。
「ん?」
「ううん、何でもない」
いつもきりっとしている桜井さんは、話してみるとほんわかしている。生徒会長として活動している時と、ふたりで話す時にギャップがある。
――清瀬もそうだ。
渡り廊下を通ると、夏風が桜井さんの肩にかかる髪をふわりと揺らした。甘くていい香りが、かすかに漂う。
――そういえば、今朝、清瀬もいい香りがした。
「……ふかみん?」
「あっ、ごめん。何だっけ」
「昨日、私がここで告白している人を見たって話」
ああ、そうだった。話の途中で昨夜のことを思い出して、ぼおっとしてしまった。
「桜井さんも見てたの?」
「え、ふかみんも見たの? 昼休み、ウチのクラスの――」
「いや、昼休みなら違う。俺は放課後だから」
そんなにここで告白するのがいいのか?
そもそも、「渡り廊下レモンティー伝説」って誰が言い出したんだろう。
「ふかみんは、好きな人いるの?」
「えっ」
唐突な問いに足が止まった。
上目遣いの桜井さんと視線がぶつかり、真剣な瞳にどう答えればいいのか、言葉に詰まった。
「ふかみん、あのね、私――」
桜井さんが何かを言いかけたとき、突然聞き慣れた声が、その言葉を遮るように渡り廊下に響いた。
「和香先輩!」
険しい表情の清瀬が走って来た。航平をチラリとも見ず、まっすぐ桜井さんだけを見ている。
「清瀬くん、どうしたの?」
「ちょっと先輩に聞きたいことがあって、教室に行ったら国語科準備室へ行ったと聞いたので。できれば昼休みのうちに集計の仕方を教えて欲しくて」
機嫌が悪そうにも見えるが、単純に切羽詰まった仕事なのかもしれない。
「じゃ、俺が取りに行ってくるから、桜井さんは清瀬と行って」
「え、でも、朝もふかみんに頼んだから。清瀬くん、悪いけど放課後にしてくれる?」
戸惑っている桜井さんを目の前にして、清瀬の眉間にしわが寄る。張り詰めた空気に、居たたまれなくなる。
「桜井さん、早く行ってやって。急ぎの仕事なんでしょ? こっちは俺が行ってくるから」
「いや、でも……」
「大丈夫、行ってきて」
「……ごめんね。ふかみん」
桜井さんは航平に軽く手を振ると、清瀬の隣を歩き出す。こうして美男美女のふたりが並ぶと絵になる。
清瀬の視線は、最後まで俺を捉えることはなかった。
――清瀬は、桜井さんが好きなんだ……。
それにしても、必死過ぎるだろ。
朝も、清瀬は俺が桜井さんと話すのを見て不機嫌になっていた。今だって、渡り廊下まで追いかけてくるなんて。
――清瀬、スマートに見えて少し不器用なやつなのかもしれない。
*
夕方、部屋で課題をやっていると、いつもより早く清瀬が帰って来た。清瀬が航平の机の上に、冷たいカフェオレのパックをそっと置いた。
「ん?」
「昼休み、すみませんでした。本当は和香先輩の仕事だったのに、俺が無理やり連れて行ってしまって。あのあと、和香先輩にすごく怒られました」
「ごめんなさい」と眉を下げる清瀬が、なんだか幼くて可愛く見える。桜井さんが怒るなんて、よほど仲がいいんだろう。
「なんか清瀬って、スマートに見えて不器用なところもあるんだな。これ、ありがとう」
カフェオレを受け取ると、清瀬は口角を上げて嬉しそうにほほえんだ。自分の机から椅子を引いて、航平の向かいに座った。カーテンの隙間から差し込む西日が、彼の整った横顔を照らしていた。本当に目を奪われるほど男前だ。
冷えたカフェオレのストローに口をつけ、一気に喉に流し込んだ。
「沁みる〜。ちょうど飲みたいと思ってたんだ」
「先輩、それ好きですよね」
「うん、好きだよ」
一瞬、清瀬がかすかに息を呑んだ。
「ん?」
「いえ、本当は迷ったんです。先輩にもレモンティーにするか。でも、カフェオレの方が喜ぶかなと思って」
「やっぱり清瀬って優しいね。今朝も、ヘアミストありがとう。清瀬って、髪サラサラだよね。俺も同じヘアミスト使ったら、少しは清瀬みたいになれるかな」
清瀬はふっと軽く息を吐き出し、ふわりと笑みを浮かべた。
「先輩は俺みたいにならなくていいです。寝ぐせも、この部屋で見せる黒縁メガネ姿も可愛いです」
穏やかな笑みの中に、砂糖菓子のような甘さを感じたのは気のせいだろうか。
「か、可愛いって、おかしいだろ」
「そんな風に、赤くなるのも可愛いです」
「もう、先輩をからかうんじゃないよ」
清瀬の視線から逃げるように背を向けた。壁際に置かれた自分の机に向かえば、もう清瀬と目が合うことはない。
「……先輩?」
「…………」
「ねえ、航平先輩?」
しばらく黙っていると、きぃっとイスの軋む音がして清瀬の指先が軽く肩に触れた。
「怒っちゃいましたか?」
「怒ってない。そういうんじゃなくて、ただ……」
「ただ?」
「褒められることに慣れてないから、くすぐったいだけ!」
「こんなにいいところばっかりなのに?」
清瀬は無垢な瞳で俺の目を覗き込んでくる。吐き出された清瀬のセリフに、俺はあんぐりと口を開けたまま固まった。
「先輩はそのままでいてください。できれば、メガネは俺の前だけにして欲しいけど」
ハチミツみたいにとろけるような甘い視線に、もう心臓が限界だった。
「ヤバッ。もうこんな時間だ。井上と勉強する約束してたの忘れてた。清瀬、カフェオレありがとうな!」
すばやく課題をつかむと清瀬の言葉を待たず、逃げるように部屋を飛び出す。
なんなんだ、これは。
自習室へ続く階段を駆け下りても、頬の熱が引かない。清瀬の「可愛いです」という言葉が、耳から離れなかった。
そして夜。二十四時を過ぎても、数学の課題が終わらない。
自習室から戻って来ると清瀬はすでに眠りの中にいた。いっそのこと、井上みたいに解答を写そうかという考えが頭をよぎる。
いやいや、駄目だ。俺は受験で数学を使うんだから。そう思いながらも、手も足も出ず頭を抱えていると、かすかに布の擦れるような音がした。
マズい。清瀬を起こしてしまった。
「まだ寝ないんですか?」
「ごめん。ライト、まぶしかった?」
「いえ、唸ってる声がしたんで、どうしたのかなと思って」
「マジか、ごめん。心の中で唸ってたんだけど」
「漏れてましたよ」
清瀬はふふっと笑いながら軽く背伸びをすると、航平の机の横に立った。
「ちょっと見せてもらえますか」
テキストを覗き込む清瀬の息遣いを耳元に感じた。シャンプーの香りが、強く鼻をくすぐった。
清瀬の細くて長い指が、シャーペンを握る航平の手の上から伸びてきた。
「貸してください」
柔らかく手が重なるように触れた瞬間、ドクンと心臓が大きく跳ねた。航平のシャーペンを握ると、清瀬はさらさらと問題を解いていく。
「ここは、この公式を使って、こういう流れで解くと早いですよ」
「清瀬、なんでもできるんだな。理系って聞いてたけど、改めてすごい」
3年の俺が、こんな風に2年の清瀬に頼ってしまって恥ずかしい。
「この通りやると、スムーズに次の問題も解けます。やってみて下さい」
「あ、う、うん」
カリカリとノートを走るシャープペンの音が、静かな夜に優しく響く。時折、航平の筆跡を清瀬がなぞる。目が合うと、清瀬が航平のペンを取り、解いて見せる。
そんなことを何度も繰り返しているうちに、あまりの申し訳なさから、先に眠るように促した。
「俺なら大丈夫です。航平先輩、一緒に最後までやりましょう」
部屋の真ん中に折り畳みのテーブルを出した。
斜め前で見据えている視線は温かなもので、いつもなら諦めてしまいそうなものも、まったくそんな気にならなかった。
最後の問題を解く頃には、立ち上がるのも億劫で、ほとんど無意識に、ふたりでそのまま突っ伏して眠った。
どれぐらい眠っただろうか。
カーテンから差す朝の日差しに目をこすり、体を起こすと、清瀬はまだテーブルに突っ伏して眠っていた。
すやすやと寝息を立てる寝顔をこっそりと覗き見た。少し乱れた前髪の下にある無防備な額に、そっと指先で触れてしまった。長いまつ毛に、スッと通った鼻筋。完璧すぎる寝顔に見惚れていると、閉じられていたまぶたがゆっくり開いていく。
「おはよう、清瀬」
「おはようございます」
清瀬はふわっと力なく笑うと、ふたたびまぶたが閉じていく。こんなに無防備な清瀬を見るのは、初めてだ。
「可愛い」
思わず口から零れた。
自分が発した言葉の熱が顔を熱くする。窺うように見ると、しっかり目は閉じていて、ほっと胸を撫で下ろす。
穏やかな寝息を立て始めた清瀬を起こさないよう、静かにテーブルから抜け出した。
昨夜、眠りに落ちる瞬間を思い出す。清瀬の肩の温もり、すぐ隣にあったシャンプーの匂いの心地よさ。
――やばい、意識しすぎだ。
熱くなった頬を両手でぱちんと叩いた。顔を洗い、制服に着替えても、まだ清瀬に起きる気配がない。
「清瀬、そろそろ起きないと。朝ご飯、間に合わなくなるから」
声をかけても清瀬は小さく唸るだけで起きない。仕方なく、そばにしゃがんで少し強めに肩を揺すった。
「ん……先輩……?」
目を開けた清瀬の視線が、一瞬、ぼんやりとテーブルを捉えた。
「……おはようございます。俺たち、一緒に寝ちゃったんですね」
清瀬が照れたように笑う。
「ごめん。完全に俺のせいだ」
「いえ、幸せな目覚めです」
そのストレートな言葉が、昨夜からの記憶と合わさって、ふたたび俺の頬を熱くさせる。
「早く準備しろよ」
赤くなった顔を隠すように、俺は清瀬に背を向けた。
スッとカーテンが引かれ、朝の光が差し込んだ。
急な眩しさに重いまぶたをうっすら開けると、光を背にした清瀬と目が合った。心臓が大きく跳ね、ビクッとした。
「おはようございます」
「お、おはよう……清瀬」
朝から爽やかな笑顔を向けられ、目をすがめた。イケメン過ぎて眩しいなんて、一体どうなってんだ。いや、それより昨日のことがあったのに、なんで清瀬は平然としてるんだ。
「朝ご飯の時間まで10分もないんで、急いでください。俺は生徒会があるんで、行きますね」
手を差し出され、思わず手をつかむとゆっくり引き上げられた。
――はっ!?
反射的に手をつかんでしまった。
何をやってるんだ俺は! 違う、違う! 反射、これは断じて反射!
「ふふっ、可愛いです」
急に手が伸びてきて、頭の後ろを撫でられた。びっくりして固まる俺に近づいた清瀬からは、いい香りがする。
「寝ぐせ、俺の机にあるミスト使ってください。本当は俺が直してあげたかったけど」
「え……っ」
「行ってきます」
あっけにとられた木曜日。
新生徒会長の清瀬は、いつもより早く部屋を出ていった。
清瀬のミストのおかげで、手ごわい寝ぐせは何とか収まった。爆速で朝食をとり、正門を目指す。
(なんで同じ敷地にあるのに、南からぐるっと回って北側の正門まで走らないといけないんだよ……)
息を切らしながら駆け足で校門をくぐると、向こうで生徒会役員が定例のあいさつ運動をしているのが見えた。
清瀬は、登校してくる生徒に爽やかな笑みを向けている。その完璧な「生徒会長の顔」は、昨夜、壁に追い込まれながら見た表情とは、まるで違う。
爽やか清瀬の隣には、前生徒会長の桜井和香がいる。きりりとした目元を緩ませて挨拶すると、肩にかかるボブの髪が軽やかに弾んだ。
「あ、ふかみん!」
俺を見るなり桜井さんが走って来た。途端に、後ろで清瀬の表情が曇った。
「おはよう。ふかみんに頼みたいことがあって」
聞けば、朝のうちに古典のワークを集めて、冬月先生に持っていかなければならないのに、急に生徒会の活動に駆り出されたという。冬月先生は時間に厳しい人で、提出が遅れるとクラス全員に迷惑がかかる。
「途中まで集めたワーク、教卓の上にあるから」
「わかった。あとはやっておく」
「ありがとう、ほんと助かる」
「たいしたことないよ。じゃ、急ぐね」
決して余裕のある時間ではないところに仕事が増えた。このやり取りを見て、さらに引きつった表情になっている清瀬を敢えて見ないふりをして、俺は急ぎ足で昇降口へ入った。
*
昼休み。
教室で井上と朝比奈の三人で弁当を食べ始める。
「今日、カツじゃん」
目の前で、テンション高めにカツを頬張るのは井上遼介。バスケの特待生で、俺と同じ寮生だ。その隣で涼やかに購買のパンを食べているのが朝比奈奏斗。中性的な顔立ちで、柔らかそうな髪は明るい栗色をしている。
弁当の蓋を開けた途端、後ろから声をかけられた。
「ふかみん、ちょっといい?」
振り向くと桜井さんだった。
「どうしたの?」
「お昼食べ終わったら、ワークを取りに行くの手伝ってもらえないかな?」
「それなら、俺行こうか? 和香の頼みなら、いくらでも聞くよ!」
すかさず井上が言うと、桜井さんは少し困ったような曖昧な笑みを浮かべた。
「ごめん、井上くん。できれば、ふかみんにお願いしたいんだけど……」
井上と朝比奈の視線が俺に向く。
――今朝、持って行ったのが俺だからか。
「いいよ。行くとき声かけて」
「ありがとう」
にこっと笑みを向けて席に戻った。
「あのさ……」
井上の手招きに、朝比奈とふたりで顔を寄せた。
「和香って、航平のこと好きなんじゃね?」
「は?」
「あー、俺もそう思う。結構前からじゃない?」
「だよな」
俺は、ふたりの指摘を即座に否定する。
「なんで? そんなことないって」
「いやいや、和香ってひとりで何でもやってのけるタイプじゃん。会長やるぐらいだし。でも、その和香が何かを頼むのは、いつも航平だよな」
「そう! 他の奴には頼まないよね」
朝比奈が井上に同調した。
「それは、単に頼みやすいからじゃない? 俺、今までもずっとそういう役回りだし」
「まったく、航平は『ミスター鈍感』だな」
「はあ? なんだよそれ、いやだな。変な称号付けるのやめてくれ」
でも、井上の言うことには、いつも鋭いところがある。バスケ部では主将を務め、部員にも慕われている。複数の大学から推薦のオファーがくるほどプレーも上手い。
その日の弁当の時間は「なぁ、ミスター鈍感どう思う?」「そういえばミスター鈍感、今日は寝ぐせついてないね」と、ありがたくもない称号でふたりに何度もいじられた。
「もういいって!」
笑いながらそう言ったとき、ちょうど弁当を食べ終えた桜井さんが声をかけてきた。席から立ち上がり廊下へ足を向ける。
「いってらっしゃい! ミスター鈍感」
後ろから井上の声がした。
「まだ言ってんのかよ、やめてくれ」
笑いながら向き直ると、隣の桜井さんがクスクス笑っている。
「ふかみんのあだ名、ミスター鈍感になったの?」
「まったく井上のヤツ。いつも変なあだ名付けてくるんだよ」
「でも、ちょっとわかる気がする」
「えっ、桜井さんまで……。俺ってそんなに鈍感?」
「うん」
「そうなの?」
「うん、だって私――」
一瞬、桜井さんは何かを言いかけて口をつぐんだ。
「ん?」
「ううん、何でもない」
いつもきりっとしている桜井さんは、話してみるとほんわかしている。生徒会長として活動している時と、ふたりで話す時にギャップがある。
――清瀬もそうだ。
渡り廊下を通ると、夏風が桜井さんの肩にかかる髪をふわりと揺らした。甘くていい香りが、かすかに漂う。
――そういえば、今朝、清瀬もいい香りがした。
「……ふかみん?」
「あっ、ごめん。何だっけ」
「昨日、私がここで告白している人を見たって話」
ああ、そうだった。話の途中で昨夜のことを思い出して、ぼおっとしてしまった。
「桜井さんも見てたの?」
「え、ふかみんも見たの? 昼休み、ウチのクラスの――」
「いや、昼休みなら違う。俺は放課後だから」
そんなにここで告白するのがいいのか?
そもそも、「渡り廊下レモンティー伝説」って誰が言い出したんだろう。
「ふかみんは、好きな人いるの?」
「えっ」
唐突な問いに足が止まった。
上目遣いの桜井さんと視線がぶつかり、真剣な瞳にどう答えればいいのか、言葉に詰まった。
「ふかみん、あのね、私――」
桜井さんが何かを言いかけたとき、突然聞き慣れた声が、その言葉を遮るように渡り廊下に響いた。
「和香先輩!」
険しい表情の清瀬が走って来た。航平をチラリとも見ず、まっすぐ桜井さんだけを見ている。
「清瀬くん、どうしたの?」
「ちょっと先輩に聞きたいことがあって、教室に行ったら国語科準備室へ行ったと聞いたので。できれば昼休みのうちに集計の仕方を教えて欲しくて」
機嫌が悪そうにも見えるが、単純に切羽詰まった仕事なのかもしれない。
「じゃ、俺が取りに行ってくるから、桜井さんは清瀬と行って」
「え、でも、朝もふかみんに頼んだから。清瀬くん、悪いけど放課後にしてくれる?」
戸惑っている桜井さんを目の前にして、清瀬の眉間にしわが寄る。張り詰めた空気に、居たたまれなくなる。
「桜井さん、早く行ってやって。急ぎの仕事なんでしょ? こっちは俺が行ってくるから」
「いや、でも……」
「大丈夫、行ってきて」
「……ごめんね。ふかみん」
桜井さんは航平に軽く手を振ると、清瀬の隣を歩き出す。こうして美男美女のふたりが並ぶと絵になる。
清瀬の視線は、最後まで俺を捉えることはなかった。
――清瀬は、桜井さんが好きなんだ……。
それにしても、必死過ぎるだろ。
朝も、清瀬は俺が桜井さんと話すのを見て不機嫌になっていた。今だって、渡り廊下まで追いかけてくるなんて。
――清瀬、スマートに見えて少し不器用なやつなのかもしれない。
*
夕方、部屋で課題をやっていると、いつもより早く清瀬が帰って来た。清瀬が航平の机の上に、冷たいカフェオレのパックをそっと置いた。
「ん?」
「昼休み、すみませんでした。本当は和香先輩の仕事だったのに、俺が無理やり連れて行ってしまって。あのあと、和香先輩にすごく怒られました」
「ごめんなさい」と眉を下げる清瀬が、なんだか幼くて可愛く見える。桜井さんが怒るなんて、よほど仲がいいんだろう。
「なんか清瀬って、スマートに見えて不器用なところもあるんだな。これ、ありがとう」
カフェオレを受け取ると、清瀬は口角を上げて嬉しそうにほほえんだ。自分の机から椅子を引いて、航平の向かいに座った。カーテンの隙間から差し込む西日が、彼の整った横顔を照らしていた。本当に目を奪われるほど男前だ。
冷えたカフェオレのストローに口をつけ、一気に喉に流し込んだ。
「沁みる〜。ちょうど飲みたいと思ってたんだ」
「先輩、それ好きですよね」
「うん、好きだよ」
一瞬、清瀬がかすかに息を呑んだ。
「ん?」
「いえ、本当は迷ったんです。先輩にもレモンティーにするか。でも、カフェオレの方が喜ぶかなと思って」
「やっぱり清瀬って優しいね。今朝も、ヘアミストありがとう。清瀬って、髪サラサラだよね。俺も同じヘアミスト使ったら、少しは清瀬みたいになれるかな」
清瀬はふっと軽く息を吐き出し、ふわりと笑みを浮かべた。
「先輩は俺みたいにならなくていいです。寝ぐせも、この部屋で見せる黒縁メガネ姿も可愛いです」
穏やかな笑みの中に、砂糖菓子のような甘さを感じたのは気のせいだろうか。
「か、可愛いって、おかしいだろ」
「そんな風に、赤くなるのも可愛いです」
「もう、先輩をからかうんじゃないよ」
清瀬の視線から逃げるように背を向けた。壁際に置かれた自分の机に向かえば、もう清瀬と目が合うことはない。
「……先輩?」
「…………」
「ねえ、航平先輩?」
しばらく黙っていると、きぃっとイスの軋む音がして清瀬の指先が軽く肩に触れた。
「怒っちゃいましたか?」
「怒ってない。そういうんじゃなくて、ただ……」
「ただ?」
「褒められることに慣れてないから、くすぐったいだけ!」
「こんなにいいところばっかりなのに?」
清瀬は無垢な瞳で俺の目を覗き込んでくる。吐き出された清瀬のセリフに、俺はあんぐりと口を開けたまま固まった。
「先輩はそのままでいてください。できれば、メガネは俺の前だけにして欲しいけど」
ハチミツみたいにとろけるような甘い視線に、もう心臓が限界だった。
「ヤバッ。もうこんな時間だ。井上と勉強する約束してたの忘れてた。清瀬、カフェオレありがとうな!」
すばやく課題をつかむと清瀬の言葉を待たず、逃げるように部屋を飛び出す。
なんなんだ、これは。
自習室へ続く階段を駆け下りても、頬の熱が引かない。清瀬の「可愛いです」という言葉が、耳から離れなかった。
そして夜。二十四時を過ぎても、数学の課題が終わらない。
自習室から戻って来ると清瀬はすでに眠りの中にいた。いっそのこと、井上みたいに解答を写そうかという考えが頭をよぎる。
いやいや、駄目だ。俺は受験で数学を使うんだから。そう思いながらも、手も足も出ず頭を抱えていると、かすかに布の擦れるような音がした。
マズい。清瀬を起こしてしまった。
「まだ寝ないんですか?」
「ごめん。ライト、まぶしかった?」
「いえ、唸ってる声がしたんで、どうしたのかなと思って」
「マジか、ごめん。心の中で唸ってたんだけど」
「漏れてましたよ」
清瀬はふふっと笑いながら軽く背伸びをすると、航平の机の横に立った。
「ちょっと見せてもらえますか」
テキストを覗き込む清瀬の息遣いを耳元に感じた。シャンプーの香りが、強く鼻をくすぐった。
清瀬の細くて長い指が、シャーペンを握る航平の手の上から伸びてきた。
「貸してください」
柔らかく手が重なるように触れた瞬間、ドクンと心臓が大きく跳ねた。航平のシャーペンを握ると、清瀬はさらさらと問題を解いていく。
「ここは、この公式を使って、こういう流れで解くと早いですよ」
「清瀬、なんでもできるんだな。理系って聞いてたけど、改めてすごい」
3年の俺が、こんな風に2年の清瀬に頼ってしまって恥ずかしい。
「この通りやると、スムーズに次の問題も解けます。やってみて下さい」
「あ、う、うん」
カリカリとノートを走るシャープペンの音が、静かな夜に優しく響く。時折、航平の筆跡を清瀬がなぞる。目が合うと、清瀬が航平のペンを取り、解いて見せる。
そんなことを何度も繰り返しているうちに、あまりの申し訳なさから、先に眠るように促した。
「俺なら大丈夫です。航平先輩、一緒に最後までやりましょう」
部屋の真ん中に折り畳みのテーブルを出した。
斜め前で見据えている視線は温かなもので、いつもなら諦めてしまいそうなものも、まったくそんな気にならなかった。
最後の問題を解く頃には、立ち上がるのも億劫で、ほとんど無意識に、ふたりでそのまま突っ伏して眠った。
どれぐらい眠っただろうか。
カーテンから差す朝の日差しに目をこすり、体を起こすと、清瀬はまだテーブルに突っ伏して眠っていた。
すやすやと寝息を立てる寝顔をこっそりと覗き見た。少し乱れた前髪の下にある無防備な額に、そっと指先で触れてしまった。長いまつ毛に、スッと通った鼻筋。完璧すぎる寝顔に見惚れていると、閉じられていたまぶたがゆっくり開いていく。
「おはよう、清瀬」
「おはようございます」
清瀬はふわっと力なく笑うと、ふたたびまぶたが閉じていく。こんなに無防備な清瀬を見るのは、初めてだ。
「可愛い」
思わず口から零れた。
自分が発した言葉の熱が顔を熱くする。窺うように見ると、しっかり目は閉じていて、ほっと胸を撫で下ろす。
穏やかな寝息を立て始めた清瀬を起こさないよう、静かにテーブルから抜け出した。
昨夜、眠りに落ちる瞬間を思い出す。清瀬の肩の温もり、すぐ隣にあったシャンプーの匂いの心地よさ。
――やばい、意識しすぎだ。
熱くなった頬を両手でぱちんと叩いた。顔を洗い、制服に着替えても、まだ清瀬に起きる気配がない。
「清瀬、そろそろ起きないと。朝ご飯、間に合わなくなるから」
声をかけても清瀬は小さく唸るだけで起きない。仕方なく、そばにしゃがんで少し強めに肩を揺すった。
「ん……先輩……?」
目を開けた清瀬の視線が、一瞬、ぼんやりとテーブルを捉えた。
「……おはようございます。俺たち、一緒に寝ちゃったんですね」
清瀬が照れたように笑う。
「ごめん。完全に俺のせいだ」
「いえ、幸せな目覚めです」
そのストレートな言葉が、昨夜からの記憶と合わさって、ふたたび俺の頬を熱くさせる。
「早く準備しろよ」
赤くなった顔を隠すように、俺は清瀬に背を向けた。