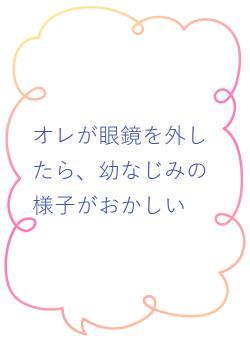「清瀬くん、私と付き合って下さい」
課外授業が終わった夕方。
購買へ行く途中、聞こえてきた声に足が止まった。ひとけのない渡り廊下で告白されているのは、寮で同室の清瀬だ。
「ごめん。俺、好きな人いるから」
「そっか、わかった。ごめんね、時間取らせちゃって」
「いや、俺の方こそ。今まで通りに話してくれたら嬉しい」
告白していた女の子がこっちを振り返る。足早にすれ違うと、目にうっすら涙が浮かんでいた。
このまま清瀬の方へ歩いて行くのは気まず過ぎると引き返そうとした時、「航平先輩!」と後ろから呼び止められた。
「ごめん、見るつもりはなかったんだけど」
「いえ、課外終わりですか?」
「うん。眠け覚ましに飲みもの買おうと思って」
「俺も一緒にいいですか?」
隣を歩く清瀬は1つ後輩だ。180センチ近い長身で、黙っていると冷たく見えるほどに整った顔立ちをしている。ぎりぎり170センチの俺は、清瀬と並ぶと野暮ったく見えてしまう。
購買前の自動販売機でカフェオレを買い、ふたりで中庭のベンチに腰掛けた。梅雨明けの空は透き通っていて、初夏の爽やかな風が首筋を撫でる。
「清瀬はレモンティーか」
「好きなんで」
「ふーん」
きっと、告白したさっきの女の子は、清瀬と一緒に飲みたかったんだろうな。
告白現場を目撃したせいで、授業中に感じていた強い眠気は、とっくに消えていた。
冷えた四角いパックにプスッとストローを差し、濃いめのカフェオレを吸い込んだ。ほどよい苦味が口の中に広がる。
清瀬は、まだ暮れない空を見上げて目を細めている。
――カッコいいな。
すっとした鼻筋と顎のラインは、男の俺が見ても綺麗だと思う。
「清瀬、知ってる? そのレモンティーの話」
「知ってます。渡り廊下で告白して、このベンチで一緒にレモンティーを飲んだら別れないっていう、この学校の言い伝えですよね」
「なーんだ、知ってたか」
「知ってますよ」
頬を緩めた清瀬と目が合った。
「モテるのも大変だね」
「あんまり嬉しくないです。好きな人にモテないと意味ないんで」
清瀬はモテる。でも、そのせいで気の毒なこともあった。
去年の夏の終わり。
清瀬は父親の転勤で途中入寮した。すると聞きつけた女の子たちが、寮の周りをうろうろするようになった。それをよく思わなかった先輩たちの冷ややかな言葉や態度を、清瀬は黙って受け入れていた。
「清瀬って、どんな人が好きなの?」
思わず口を突いて出た言葉に、はっとした。
清瀬とは同じ部屋というだけで、気軽に恋愛相談できるような関係ではないと思う。
「そうですね。優しくて、ちょっと頼りないところがあって。でも、いざとなったら誰よりも頼れる人です」
淀みのない具体的な答えに驚いた。
「へぇ~。そういう人、2年にいるんだ」
「いえ、3年です」
意外だった。
好きな人と言えば、同じクラスとか部活とか。そんな接点しか思い浮かばない俺は、あまりにも恋愛経験がないからか。
――誰だろう、清瀬の好きな人……。
部活に入っていない清瀬の接点を考えると、すぐにピンと来た。
ついこの間まで生徒会長だった、ウチのクラスの桜井和香。
清瀬はこの間の選挙で生徒会長になった。思い返すとウチの教室に来て、桜井さんとよく話している。
(桜井さん、人気あるもんな……)
「え?」
「あ、ごめん。つい心の声が漏れた」
「違います!」
力のこもった否定に思わず肩がびくりと上がった。
これは図星だったか……。
「すみません。大きい声出して」
「ううん」
「でも先輩、よく漏らしてますよ」
「おいおい、言い方! 漏らしてるって、おまえが言うと俺がおねしょしてるみたいじゃん」
「たしかに」
ぷはっと吹き出した清瀬に「勘弁してくれ、同じ部屋なんだからさー」とぼやいても、まだ笑っている。
「でも先輩、結構部屋で漏らしてますよ」
「本当にやめてくれよ。それを言うなら『漏れてます』だからっ! ほら、会長さんは生徒会室に行かないと! 俺も教室戻って勉強する」
*
その日の夜、夕食を食べ終わり、部屋にひとりでいると幼なじみの榎田から電話がかかってきた。
『航平、元気~? この夏、みんなで会おうって話が出てるんだけど、いつ西乃沢に帰る?』
「ごめん。今回はお盆だけだと思う。課外授業とかオープンスクールとか何かと忙しくて」
航平と榎田の故郷である西乃沢は、今住んでいる北乃市から車で2時間ほどの山間の温泉地にある。自宅から通える高校はなく、寮があるうちの高校か、榎田の通う高校へ進学する。
榎田と高校は離れてしまったが、一番仲が良く中学ではテニス部でペアを組んでいた。
『そっか。海斗たち、航平が帰ってきたら、一緒にテニスやりたいって言ってたんだけど』
「ごめん。悪いけど今回は無理かな。でも、海斗くんたち、ウチのオープンスクールに来るんじゃない? 部活動見学の時間もあるから、テニス部に来たら俺いるし」
海斗くんは榎田の弟だ。帰省すると、中学生のテニス部員たちと一緒にテニスをしている。
『わかった。海斗たちにテニス部、見に行けって言っとくわ。ところで、航平に聞いて欲しいことがあって電話したんだけど、いま少し時間いい?』
カラッとした性格の榎田が、妙に改まった口調で胸がざわつく。
「どうした? 何かあった?」
実は……で始まった話は「下宿先で、気になる人ができた」という内容だった。要は恋愛話を聞いて欲しいということなのかと「へぇ~、榎田の好きな人ってどんな人なの?」と軽い気持ちで聞いた。
『航平にしか話せないんだけど、俺、理解してもらえないかもしれない人を好きになっちゃって――』
榎田の声には、不安が透けていて胸が苦しくなった。
「そっか。別にいいじゃん。俺は好きになるのに、男とか女とか、性別なんて関係ないと思うよ」
好きな人すらできたことのない俺からすれば、誰かを好きになれる気持ち自体が、羨ましい。単なる励ましではなく、本当にそう思う。だから、いつもより声が大きくなっていたかもしれない。
ほっとした声に戻った榎田とは、お盆で帰省した時に会う約束して電話を切った。
今日はなんだか恋愛絡みの話が多いな。
そう思いながら椅子から立ち上がると、ドアのそばに、唖然とした表情の清瀬が立っていた。
「いつからそこにいたんだよ!」
「さっき、ただいまって言いましたよ」
ぜんぜん聞こえなかった。いったい、どこから話を聞いていただろうか。入り口にいた清瀬が勢いよく航平へ近づいて来た。
「もしかして、今の話、聞いてた?」
「俺も先輩と全く同意見です」
「そ、そうか。良かった」
胸を射抜くような鋭い眼差しを向けられ、たじろいだ。
「清瀬、心配しなくて大丈夫だから。今のは俺の話じゃなくて、友達の話で――」
「本当は違うってことですか?」
「いや、嘘じゃない。俺の場合、好きになるっていうのがどういうことなのか、イマイチわからないって言った方がいいかもだけど」
「俺も、人を好きになるのに性別は関係ないと思ってます」
なんだなんだと思っているうちに、ジリジリと壁に追いやられ、顔の左側に清瀬が手をついた。距離が一気にゼロに等しくなる。
――なんで俺、清瀬に壁ドンされてるんだ?
「ちょっと、顔、近い」
「なら、俺にもワンチャンあるってことですよね?」
「へ……っ?」
思わず変な声が出た。
いま清瀬、なんて言った?
ワンチャン……、ワンチャン……ワンチャン……?
眉間に力をいれた清瀬を目の前にして、うまく頭が回らない。
「ごめん。それ、どういう意味?」
「俺、先輩とレモンティー飲みたいです」
「え、あ、うん。わかった。今度な」
「本当に意味、わかってますか? まぁわからなくても、そのうちわかるようにしますけど」
クールな顔立ちの清瀬にまっすぐ見つめられ、息を詰める。壁に背をつけたまま、清瀬から目を逸らせないでいると、ドアをノックする音が聞こえた。ふっと空気が緩むとすかさず清瀬が入り口を一瞥し、チッと舌打ちをした。
「あっ、どうぞー」
航平が上ずった声でドアに向かって返事をすると、2年の遠藤が「助けて清瀬~!」とノート片手に勢いよく入ってきた。
一瞬で苦い顔になった清瀬が、遠藤の質問に答え始めた。航平は、混乱した頭で机に広げていたやりかけの課題を雑にまとめる。
――何だったんだ、今の……。
清瀬は一体、何を言いたかったんだ?
うるさい心臓を押さえ、自習室に逃げ込んだ。
逃げ込んでも、あの衝撃が強すぎて、全く勉強に集中できなかった。
真夜中の二十四時。
自習室の利用可能時間が過ぎ、部屋に戻る。 そっと201のドアを開けると、すでに清瀬は寝ているようだ。
寮の部屋は中央に通路があり、空間が分けられている。左が清瀬、右が航平のスペースだ。眠る時は備え付けのカーテンを引くと、互いのプライバシーが守られる造りになっている。
足音を立てないように部屋の奥へ進み、机の上に勉強道具を置いた。Tシャツに短パンのままベッドに潜りこむと、シンとした部屋の中に清瀬の規則的な寝息が聞こえる。
今まで寝息なんて、気にしたことがなかった。
――まぁわからなくても、そのうちわかるようにしますけど。
さっきの熱っぽい声が耳に響いた。
あの言い方は、冗談なんかじゃなかった。イケメンで優等生を絵に描いたような清瀬が俺を好き?……いやいや、平凡な俺を好きになる理由がない。
俺の取り柄と言えば、「とりあえず話を聞いて欲しい」と友人に言われることが多いことぐらいだ。それも大半は相談ではなく「単に聞いて欲しい」だけでアドバイスは求めていない。そもそも、求められたところで上手いアドバイスができるわけもないんだけど……。
今日の榎田がいい例だ。
それに、ベンチで「違います」と否定した時の清瀬は、まるで言い当てられたかのように動揺していた。
カーテンをゆっくり引き、灯りが漏れないように読書灯の角度を調整した。手のひらサイズの単語帳を手にすると、集中力は続かず、いつの間にか眠っていた。
課外授業が終わった夕方。
購買へ行く途中、聞こえてきた声に足が止まった。ひとけのない渡り廊下で告白されているのは、寮で同室の清瀬だ。
「ごめん。俺、好きな人いるから」
「そっか、わかった。ごめんね、時間取らせちゃって」
「いや、俺の方こそ。今まで通りに話してくれたら嬉しい」
告白していた女の子がこっちを振り返る。足早にすれ違うと、目にうっすら涙が浮かんでいた。
このまま清瀬の方へ歩いて行くのは気まず過ぎると引き返そうとした時、「航平先輩!」と後ろから呼び止められた。
「ごめん、見るつもりはなかったんだけど」
「いえ、課外終わりですか?」
「うん。眠け覚ましに飲みもの買おうと思って」
「俺も一緒にいいですか?」
隣を歩く清瀬は1つ後輩だ。180センチ近い長身で、黙っていると冷たく見えるほどに整った顔立ちをしている。ぎりぎり170センチの俺は、清瀬と並ぶと野暮ったく見えてしまう。
購買前の自動販売機でカフェオレを買い、ふたりで中庭のベンチに腰掛けた。梅雨明けの空は透き通っていて、初夏の爽やかな風が首筋を撫でる。
「清瀬はレモンティーか」
「好きなんで」
「ふーん」
きっと、告白したさっきの女の子は、清瀬と一緒に飲みたかったんだろうな。
告白現場を目撃したせいで、授業中に感じていた強い眠気は、とっくに消えていた。
冷えた四角いパックにプスッとストローを差し、濃いめのカフェオレを吸い込んだ。ほどよい苦味が口の中に広がる。
清瀬は、まだ暮れない空を見上げて目を細めている。
――カッコいいな。
すっとした鼻筋と顎のラインは、男の俺が見ても綺麗だと思う。
「清瀬、知ってる? そのレモンティーの話」
「知ってます。渡り廊下で告白して、このベンチで一緒にレモンティーを飲んだら別れないっていう、この学校の言い伝えですよね」
「なーんだ、知ってたか」
「知ってますよ」
頬を緩めた清瀬と目が合った。
「モテるのも大変だね」
「あんまり嬉しくないです。好きな人にモテないと意味ないんで」
清瀬はモテる。でも、そのせいで気の毒なこともあった。
去年の夏の終わり。
清瀬は父親の転勤で途中入寮した。すると聞きつけた女の子たちが、寮の周りをうろうろするようになった。それをよく思わなかった先輩たちの冷ややかな言葉や態度を、清瀬は黙って受け入れていた。
「清瀬って、どんな人が好きなの?」
思わず口を突いて出た言葉に、はっとした。
清瀬とは同じ部屋というだけで、気軽に恋愛相談できるような関係ではないと思う。
「そうですね。優しくて、ちょっと頼りないところがあって。でも、いざとなったら誰よりも頼れる人です」
淀みのない具体的な答えに驚いた。
「へぇ~。そういう人、2年にいるんだ」
「いえ、3年です」
意外だった。
好きな人と言えば、同じクラスとか部活とか。そんな接点しか思い浮かばない俺は、あまりにも恋愛経験がないからか。
――誰だろう、清瀬の好きな人……。
部活に入っていない清瀬の接点を考えると、すぐにピンと来た。
ついこの間まで生徒会長だった、ウチのクラスの桜井和香。
清瀬はこの間の選挙で生徒会長になった。思い返すとウチの教室に来て、桜井さんとよく話している。
(桜井さん、人気あるもんな……)
「え?」
「あ、ごめん。つい心の声が漏れた」
「違います!」
力のこもった否定に思わず肩がびくりと上がった。
これは図星だったか……。
「すみません。大きい声出して」
「ううん」
「でも先輩、よく漏らしてますよ」
「おいおい、言い方! 漏らしてるって、おまえが言うと俺がおねしょしてるみたいじゃん」
「たしかに」
ぷはっと吹き出した清瀬に「勘弁してくれ、同じ部屋なんだからさー」とぼやいても、まだ笑っている。
「でも先輩、結構部屋で漏らしてますよ」
「本当にやめてくれよ。それを言うなら『漏れてます』だからっ! ほら、会長さんは生徒会室に行かないと! 俺も教室戻って勉強する」
*
その日の夜、夕食を食べ終わり、部屋にひとりでいると幼なじみの榎田から電話がかかってきた。
『航平、元気~? この夏、みんなで会おうって話が出てるんだけど、いつ西乃沢に帰る?』
「ごめん。今回はお盆だけだと思う。課外授業とかオープンスクールとか何かと忙しくて」
航平と榎田の故郷である西乃沢は、今住んでいる北乃市から車で2時間ほどの山間の温泉地にある。自宅から通える高校はなく、寮があるうちの高校か、榎田の通う高校へ進学する。
榎田と高校は離れてしまったが、一番仲が良く中学ではテニス部でペアを組んでいた。
『そっか。海斗たち、航平が帰ってきたら、一緒にテニスやりたいって言ってたんだけど』
「ごめん。悪いけど今回は無理かな。でも、海斗くんたち、ウチのオープンスクールに来るんじゃない? 部活動見学の時間もあるから、テニス部に来たら俺いるし」
海斗くんは榎田の弟だ。帰省すると、中学生のテニス部員たちと一緒にテニスをしている。
『わかった。海斗たちにテニス部、見に行けって言っとくわ。ところで、航平に聞いて欲しいことがあって電話したんだけど、いま少し時間いい?』
カラッとした性格の榎田が、妙に改まった口調で胸がざわつく。
「どうした? 何かあった?」
実は……で始まった話は「下宿先で、気になる人ができた」という内容だった。要は恋愛話を聞いて欲しいということなのかと「へぇ~、榎田の好きな人ってどんな人なの?」と軽い気持ちで聞いた。
『航平にしか話せないんだけど、俺、理解してもらえないかもしれない人を好きになっちゃって――』
榎田の声には、不安が透けていて胸が苦しくなった。
「そっか。別にいいじゃん。俺は好きになるのに、男とか女とか、性別なんて関係ないと思うよ」
好きな人すらできたことのない俺からすれば、誰かを好きになれる気持ち自体が、羨ましい。単なる励ましではなく、本当にそう思う。だから、いつもより声が大きくなっていたかもしれない。
ほっとした声に戻った榎田とは、お盆で帰省した時に会う約束して電話を切った。
今日はなんだか恋愛絡みの話が多いな。
そう思いながら椅子から立ち上がると、ドアのそばに、唖然とした表情の清瀬が立っていた。
「いつからそこにいたんだよ!」
「さっき、ただいまって言いましたよ」
ぜんぜん聞こえなかった。いったい、どこから話を聞いていただろうか。入り口にいた清瀬が勢いよく航平へ近づいて来た。
「もしかして、今の話、聞いてた?」
「俺も先輩と全く同意見です」
「そ、そうか。良かった」
胸を射抜くような鋭い眼差しを向けられ、たじろいだ。
「清瀬、心配しなくて大丈夫だから。今のは俺の話じゃなくて、友達の話で――」
「本当は違うってことですか?」
「いや、嘘じゃない。俺の場合、好きになるっていうのがどういうことなのか、イマイチわからないって言った方がいいかもだけど」
「俺も、人を好きになるのに性別は関係ないと思ってます」
なんだなんだと思っているうちに、ジリジリと壁に追いやられ、顔の左側に清瀬が手をついた。距離が一気にゼロに等しくなる。
――なんで俺、清瀬に壁ドンされてるんだ?
「ちょっと、顔、近い」
「なら、俺にもワンチャンあるってことですよね?」
「へ……っ?」
思わず変な声が出た。
いま清瀬、なんて言った?
ワンチャン……、ワンチャン……ワンチャン……?
眉間に力をいれた清瀬を目の前にして、うまく頭が回らない。
「ごめん。それ、どういう意味?」
「俺、先輩とレモンティー飲みたいです」
「え、あ、うん。わかった。今度な」
「本当に意味、わかってますか? まぁわからなくても、そのうちわかるようにしますけど」
クールな顔立ちの清瀬にまっすぐ見つめられ、息を詰める。壁に背をつけたまま、清瀬から目を逸らせないでいると、ドアをノックする音が聞こえた。ふっと空気が緩むとすかさず清瀬が入り口を一瞥し、チッと舌打ちをした。
「あっ、どうぞー」
航平が上ずった声でドアに向かって返事をすると、2年の遠藤が「助けて清瀬~!」とノート片手に勢いよく入ってきた。
一瞬で苦い顔になった清瀬が、遠藤の質問に答え始めた。航平は、混乱した頭で机に広げていたやりかけの課題を雑にまとめる。
――何だったんだ、今の……。
清瀬は一体、何を言いたかったんだ?
うるさい心臓を押さえ、自習室に逃げ込んだ。
逃げ込んでも、あの衝撃が強すぎて、全く勉強に集中できなかった。
真夜中の二十四時。
自習室の利用可能時間が過ぎ、部屋に戻る。 そっと201のドアを開けると、すでに清瀬は寝ているようだ。
寮の部屋は中央に通路があり、空間が分けられている。左が清瀬、右が航平のスペースだ。眠る時は備え付けのカーテンを引くと、互いのプライバシーが守られる造りになっている。
足音を立てないように部屋の奥へ進み、机の上に勉強道具を置いた。Tシャツに短パンのままベッドに潜りこむと、シンとした部屋の中に清瀬の規則的な寝息が聞こえる。
今まで寝息なんて、気にしたことがなかった。
――まぁわからなくても、そのうちわかるようにしますけど。
さっきの熱っぽい声が耳に響いた。
あの言い方は、冗談なんかじゃなかった。イケメンで優等生を絵に描いたような清瀬が俺を好き?……いやいや、平凡な俺を好きになる理由がない。
俺の取り柄と言えば、「とりあえず話を聞いて欲しい」と友人に言われることが多いことぐらいだ。それも大半は相談ではなく「単に聞いて欲しい」だけでアドバイスは求めていない。そもそも、求められたところで上手いアドバイスができるわけもないんだけど……。
今日の榎田がいい例だ。
それに、ベンチで「違います」と否定した時の清瀬は、まるで言い当てられたかのように動揺していた。
カーテンをゆっくり引き、灯りが漏れないように読書灯の角度を調整した。手のひらサイズの単語帳を手にすると、集中力は続かず、いつの間にか眠っていた。