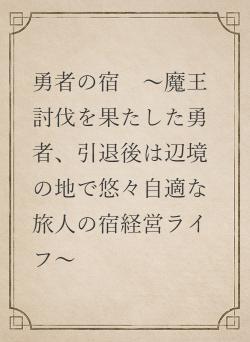「アルト皇子だ!」
誰かがそう叫ぶと町中の人がその人物を一目でも見ようとこぞって集まってくる。
もはやアイドルのような存在である少年アルト・アンドレアルは公務の帰りに気まぐれで城下町を通っていた。
王族として民草に定期的に姿を見せることは、もはや習慣化されたアルトの行動の一つだが、今日は街を歩きたい気分だった。
「馬車、止めてもらえる?」
「皇子?王城はまだ先ですが……」
「先と言ったってもう目と鼻の先ほどの距離じゃないか。ちょっと歩きたい気分なんだ」
「左様にございますか……ルート、皇子をお守りしろ!」
「はっ」
俺の乗る馬車を引いていた二人のうち一人が俺と一緒に馬車を降りる。
「ルート、アルト様に万が一のことがないように。くれぐれも注意するのだぞ!」
「この命に替えましても!」
ルートと呼ばれた騎士が上司と思われる騎士に敬礼をするとすぐにアルトの方を向いて跪いた。
「王城までの護衛をさせていただきます」
「ああ、悪いね。少し歩きたい気分でさ」
「お気になさらず、皇子の命ならばこの命であろうと簡単に捧げましょう」
「それはダメだよ。俺の騎士ならば、俺の命と自分の命を同時に守れなきゃね」
「はっ!このルート、肝に銘じます!」
11歳の子供の足でも半刻とかからない距離を歩くだけでこの大げさっぷり。
この国アスガルドにおける第一皇子にして、誰もが次期国王と信じて疑わないこの少年は名をアルト・アンドレアルと言った。
若干11歳にして国王の代理を務めて公務をこなし、傍らで立ち寄った村での水害を機転により解決、前王の時代から国中に名を轟かせた大盗賊団の根城の発見及び掃討など、数々の功績を積み上げている彼は、その才を認められているからこそ、このように王族という身分をも超えたような扱いを受けていた。
「今の、見たわよね!」
「ええ、まだ覚醒もされていないのにあのカリスマ! 一体どんなスキルを覚醒されるのかしら」
そんなアルトと騎士たちのやり取りを固唾を呑んで見つめていた民衆から集まる視線も憧れや羨望、忠誠のようなものばかりだった。
だが、その中に一人アルトの目に留まった女性がいた。
「そこのあなた……酷く憔悴しているように見える。何かあったのか?」
そんな視線ばかりを受けている俺は、道中にへたり込む女性が気になり声をかけた。
その女性は自分の母より少し年上ほどの年齢だと見受けられるが、髪には艶が全くなく、頬がこけ、目はうつろだった。
「あ、あぁっアルト様! 申し訳ありません。……その……む、娘が世界樹様の元へ、行くことになりまして……いえもちろん、光栄なことであるということは承知しているのです! ですが……」
ああ、そうだったのか。
我が母と年が近いのならば、娘の年齢もまた俺と近いのだろう。
「良い、身内が手から離れていくのはそれが世界樹との一体化だとしてもつらかろう。娘の名は?」
俺がそう問うと、女性はボロボロと涙をこぼしながら答えた。
「ルミネ……ルミネにございます」
「ルミネか。良き名だな」
名前を聞くと俺はこの国を望む、あり得ない程巨大な樹……世界樹に向かって膝をつき胸に手を当てた。
「――私はアスガルド第一皇子アルト・アンドレアル。ここに世界樹となったルミネへ感謝と敬意を表す! その命、大義であった!」
声を張りながら低い姿勢で首を垂れる。
「あ゙あぁっ……ああぁ……。ルミネ、良かったわね。あなたはアルト様に……」
ルミネの母は泣き崩れ、周りに居た民衆は俺と同じように世界樹に向かって膝をつき胸に手を当てた。
この国アスガルドでは、時折このように世界樹となる者たちがいる。
世界樹となる、とはつまり、呼吸以外のすべての身体機能が停止してしまった者たちを指し、そうなったものは世界樹の根元へ埋葬される。
しばらくすると、そうなった者たちは実際に世界樹に吸収されるのだ。
「ルミネの母よ、あなたもまた大義である。今後はさらなる世界樹の加護があなたを守るだろう」
俺は世界樹への祈りを終えると最後にそう伝え、咽び泣く声を背に受けながら王城に向けて歩き出す。
「毅然とされた態度、流石にございました。このルート感服仕りました」
「俺は王族だからな。国を治めるものとして民への感謝を忘れないのは当然だ」
何かと反応の大きいルートに内心少し辟易しつつも共に王城まで歩いた。
◇◇◇
「兄様! おかえりなさい! 村の様子はどうでしたか?」
アルトが城へと戻ると妹のテナーが食い入るように聞いてきた。
「ただいまテナー。調子は良さそうだったよ。水害でダメになった家もしっかり建て直されてきてたし、次に川が決壊したときのための対応もちゃんと指示通り行われていた。またあの大雨が降っても大丈夫だと思うよ」
「さすが兄様! 『浮力付与』のスキルを村全ての家に使うなんてどうやったら思いつくのですか!?」
「はははっ! そうだね、自分でも思いついたときは馬鹿げてると思ったさ。でもスキルは組み合わせ次第で色々なことができるからね。この村の件だって確かに『浮力付与』が一番目立ってはいるけど、水害があった時に浮いた家が流されないようにするための『固定の鎖』とか他にもいろいろなスキルが使われてる。俺はスキルについて少し詳しいから思いつけただけさ。テナーも勉強を頑張ればこのくらいすぐに思いつけるようになるよ」
「はぁい……でも勉強かぁ……兄様が言うなら、私ももう少し頑張ってみます!」
意気込むテナーの頭を撫でながら思う。
やはり、スキルの力や詳細を王族だけが有して民衆に公表しないのはよくないと。
世界においてスキルの持つ力は圧倒的だ。
だからこそ、どの国であろうと何らかの方法で自分以外のスキル詳細は秘匿されるようになっている。
我が国アスガルドでは、『誓いの約因』という初代国王のスキルによる誓いを12歳となりスキルを覚醒した者全員に行わせ、自分のスキルの効果や能力を他人に教えてはならないという誓いを立てさせている。
仕組みとしては『誓いの約因』が付与されたスキルの書と呼ばれる本に名前と覚醒したスキルを書かせると言った単純なものだが、このスキルの書には偽造や嘘を防ぐ『真実の目』や限定された者にしか公開されないようにするための『隠者の約定』などのスキルが使われている。
「あ、にいさま! ねえさまばかりずるい! 僕もにいさまによしよししてもらう!」
考え事をしている間、ずっとテナーの頭を撫でていたところを弟に見つかってしまった。
「いいぞ! カイも来なさい。ほら」
テナーを撫でる手とは逆側に弟のカイを呼んでやると、とてもうれしそうに飛び込んできた。
俺とテナーは年子だが、カイは少し離れているためどうにも甘えん坊に育ってしまっているようだ。
まあ、かわいいからいいのだけど、テナーも含めて二人にはもう少し王族としての振る舞いを身に着けて欲しいという思いもあった。
「にいさま! ねえさまとは何のお話をしてたんですか?」
「今日視察に行った村の話だよ。カイもスキルについてはちゃんと学んでおくんだぞ?」
「うぅ……勉強は嫌いだよぉ……」
「ダメよカイ! ねえさまと一緒に頑張りましょう?」
カイがいるとテナーも少しは大人になる様だ。
◇
「そういえば、もうすぐ兄様も覚醒ですね! 兄様は一体どんなスキルを覚醒されるのでしょう!?」
「にいさまのスキルだよ! 絶対すごいやつだよ!」
俺の部屋までついてきた二人は今度の俺の誕生日に授けられるスキルについてで盛り上がっていた。
「でも、兄様なら一見用途が難しそうなスキルでもすごい活用法を思いつきそう! それこそ初代国王様みたいに!」
「えー、きっとまだ誰も知らないようなすごいやつだよ!」
「「兄さまはどうなると思いますか!?」」
結論に詰まったからか、二人は同時に俺の方を向いてそう聞いてきた。
「どうだろうね? でも、どんなスキルでもやることは変わらないさ。この世界には全く無駄なスキルはないんだから」
俺の答えに一応納得はするも、やはり気になってしまうようで二人による俺のスキル予想はさらに盛り上がっていた。
俺としても王族のスキルは『誓いの約定』の能力で全国民に公開されるため、それなりのものであることを願った。
「ついに明日なのね! 一体アルトはどんなスキルを覚醒するのかしら!」
少しの月日が流れ、ついに今日はアルトの誕生日前日となっていた。
目の前の母だけでなく、国中がお祭りのような雰囲気を醸し出しており、国民がアルトへ向ける期待や羨望の眼差しがまるで空気にまで作用している様だった。
「母さん、はしゃぎすぎだよ。それに俺はどんなスキルでも王族としての務めを果たすだけさ!」
アルトの母ラーノ・アンドレアルは子煩悩だが、とくにアルトを溺愛しており、人生における最重要ポイントともとれるスキル覚醒を前にして興奮を抑えられない様子だった。
「もう! そんな固いことばかり考えなくていいのよ? 私はまだ三十五だし、コントラスもまだ四十手前だから、いきなりアルトに国を任せたりはしないわ。アルトは賢いのだからもっと好きに生きてね?」
「ははっ、ありがとう母さん。もう十分好きに生きてるよ。スキルの勉強をして、それを国民の生活に役立てて国を豊かにする。俺のやりたいことはたくさんやらせてもらってるよ!」
「アルトがそれでいいならいいけど……他にやりたいことがあればいつでも、なんでも言ってね?私、なんでも応援するから!」
「じゃあ、呼び方を母様に戻しても……」
「それはダメよ!」
……母さんも名家の出身のはずなのだが、俺たち兄弟にはこんな感じなのだ。
これで母さんのスキルは『氷結の刃』という冷酷無比な戦闘系のスキルなのだからスキルというものは本当にわからない。
二十歳の頃に他国との戦争で大戦功をあげ、その圧倒的な力に惚れ込んだ父が粘り落したらしい。
ちなみに当時の二つ名は麗氷だったと父が言っていた。冷たい氷と氷のように美しい様をよく表現した二つ名だとニヤニヤ語る父には少し引いたというのはここだけの話だ。
「まあ、スキルについては明日になれば嫌でも分かるし、やりたいことも十分できてるから大丈夫だよ母さん」
「そう? アルトが満足してるならいいわ! それよりスキルの後はお嫁さんね! コントラスみたいに二十を過ぎても決まった相手がいないなんて真似はさせないから安心してね? あ、でも、どうしても気に入る子がいなかったら、私がアルトのお嫁さんになってあげるから!」
「母さん! その話はやめてよ! 恥ずかしいから!」
頭を撫でながら懐かしい昔の話を持ち出され、照れ隠しに母さんを押しのけようとするも、麗氷の異名を持つ武人な母さんにはなすすべもなく、そのまま抱きしめられた。
「ふふっ、良いじゃない。テナーもカイもいないんだから! 私には甘えてくれていいのよ? どんなに優秀で賢くてもアルトはまだ十二歳なんだから」
「……うん、ありがとう母さん」
圧倒的なまでの母性に包まれ、その温かい優しさを噛み締めるように俺も抱きしめ返すのだった。
◇◇◇
夕食の時間になった。
これを食べて、眠りに着けば明日にはスキルが覚醒している……そう考えると緊張と不安や期待など様々な感情が自分の中で渦巻いた。
「アルト、体調はどうだ? 万全か?」
「もちろん! 若干緊張はしてるけど、体調は問題ないよ!」
父に聞かれ、そんな複雑な感情を打ち払うように少しだけ気丈に振る舞って見せる。
「はははっ! そうか、お前でも緊張するか!」
「ちょっとコントラス! 当たり前でしょう? アルトだって普通の十二歳なのよ?」
「そうは言っても母さん、兄様が緊張するって言葉にするのは珍しいよ!」
「たしかに、にいさまでも緊張するんだね!」
「テナーもカイも俺を何だと思ってるんだ? 当たり前だろう?」
これでも気丈に振る舞ったつもりだったが、それでも驚かせてしまったようだ。
だがこれも俺に向けられる期待の表れなんだ。
弱気になっている場合じゃない。
俺は今一度気を引き締めた。
「ねえ、とおさまはにいさまのスキルはどんなスキルだと思う?」
「そうだな……ラーノみたいに戦闘寄りのスキルもいいが、賢いアルトには本当にどんなスキルでも似合いそうだな」
「やっぱりとおさまもそう思うよね! あ~明日が楽しみだな~」
「ほら、あんまりプレッシャーをかけすぎちゃダメよ。……アルト? そんなに緊張しなくて大丈夫よ? スキルは選べるものじゃないわ。それにあなたにはこれまでたくさん勉強して蓄えた知識があるもの! 明日だって普段通りに寝て起きたらいいのよ」
「母さん……。そうだね。今変に気負ってもしょうがないか」
「まあ、ラーノの言う通りだ。どんなスキルだろうと、アルトは上手く使うだろうさ。さて、じゃあ、今日はもう寝ておくか?」
皆、楽しみにしてくれているのと同時に心配してくれているんだ。
……そうだ、どんなスキルだろうと役に立たないものはない。
貰ったスキルで胸を張って行けばいいんだ。
「うん、そうするよ。じゃあみんな、一足先におやすみ」
「ああ、おやすみアルト」
「「兄様! おやすみなさい」」
「おやすみ、アルト」
四人の家族に見送られ、俺は自室へ戻る。
見送られながら自室に戻るというのは中々不思議な感覚で少し気恥しかったが、それと同時に誇らしくもあった。
これでもっと俺も国のために尽くすことが出来る。
何だか明日が楽しみになって来た。
◇◇◇
ナイトルーティーンと言うほどではないが、変に身構えないように、努めていつも通りに過ごし、ベッドに入る。
緊張や興奮で寝られないかもしれないという俺の心配はどこへやら、気付けば俺は深い眠りに落ちていた。
どれくらい眠ったのだろうか?
それは不思議な感覚だった。
身体は完全に眠っていると言うのに、意識だけはまるではっきりとしているような、そんな感覚。
そこにその声が響いた。
「あなたが私の王なのね!」
全身を優しく包み込む様な柔らかく、温かい声。
聞いたことがないのに、まるで生まれた頃からずっと、共に在ったかのようなその声はスッと頭に入ってくる。
「君は……一体?」
「ふふ、私はロロ。あなたのスキルだよ」
俺が控えめに正体を聞くと目の前に姿を現した同年代か少し年上くらいの少女はロロと名乗った。
「俺のスキルが君? スキルは自我を持っているのか?」
とんでもない現象を目の前にしていると言うのに、どういう訳か不思議と受け入れている自分がいる。
俺は冷静にそう聞いた。
「ふふっ、違うよ。私とあなたが特別なの。だってあなたは……この世界樹に抱かれた国で最も、世界樹に愛された子なんだから」
柔らかく微笑み、優しく胸に抱かれる。
母以外の女性に抱きしめられるというのは少し気恥しい。
しかし、ロロの抱きしめる手からは俺を思いやる感情が伝わって来てすぐに受け入れられた。
「そっか。ロロ、これからよろしくね」
俺は彼女を抱きしめ返し、そう告げる。
「ええ。よろしくねアルト」
こうして再び俺の意識は身体に戻っていった。
◇◇◇
翌日、王城は騒乱に包まれた。
「アルトッ! アルトッッ!! どうしちゃったの! ねぇ、アルトッ! お願いっ! 起きて!」
その日、アルト・アンドレアルの12歳の誕生日は確かに訪れた。
しかし……その日にアルト・アンドレアルが目を覚ますことはなかった。
「兄様? もう、お昼ですよ。勉強を見てください。兄様、このスキルについてなのですが……兄様? 兄様、兄様兄様、兄様兄様兄様っっっ!!!」
穏やかな顔をして、呼吸も安定している。
しかし、彼の身体はピクリとも動かない。
「にいさまがおねぼうなんてめずらしい。……でも、もう夜だよ? にいさま、どうしたの?」
まるで、この国を遥か高みから見下ろす世界樹のように、彼は静かに横たわっていた。
「クソっ! クソっ!! 何が世界樹だ! 俺の息子を……アルトを……ふざけるな! ふざけるなぁぁぁ!!!」
その慟哭は一日を過ぎても止むことはなかった。
そしてまた一日、二日、一週間と時間は過ぎていく。
「これは……コントラス陛下。……おめでとう……ございます。あ、アルト、皇子は……世界樹に、なられました」
国随一と呼ばれる名医、スキル『治癒の光』を持つ医者が遂にそれを告げた。
その顔は酷く怯え、引きつっている。
「ふ、ふざける――」
「貴方……!」
アルトの世界樹化を告げた医者にコントラスが掴みかかろうとするのを、すっかり憔悴してしまったラーノが何とか引き留めた。
アスガルドにおいて世界樹になるということは悲しくもあり、最大の名誉でもある。
「兄様……」
「うっ……うぅぅ……」
この国を高くから見守り、支え、象徴としてそびえ立つ。
それが世界樹だからだ。
「……あの子は……アルトはきっと今も私たちを見てくれている。……恥ずかしいところを見せるわけにはいかないわ」
目は泣き腫らし、頬はこけ、髪の艶がなくなっても、ラーノは家族を奮い立たせる。
「ちゃんと、見送ってあげましょう」
こうして、アルト・アンドレアルの誕生日から二週間と一日、ちょうど半月の期間を擁してその事実を受け入れたアンドレアル皇家によって、アルト・アンドレアルは世界樹の根元で眠らされることになった。
その発表は大いに国を混乱させた。
嘆き、悲しみくれる者、彼の代わりに自分を世界樹にしてくれと昼夜問わずに世界樹へ祈りを捧げ続ける者、実際に後を追ってしまう者までもが現れた。
民からのアルトへの信頼は、まさに世界樹へ向けられるようなものだった。
◇◇◇
ずいぶん長く眠っていた気がする。
少し、寝坊をしてしまっただろうか?
うっすらと目を開けてみればそこは暗がりの中に仄かな光だけが広がる空間だった。
「……ここは? 一体?」
「あ、アルト、おはよう。良く寝てたね」
すると俺の真横から優しい声が聞こえて来る。
「……君は……もしかしてロロ?」
そちらを振り向けば夢の中で出会ったあの少女の姿があった。
「ええ、私はあなたのスキル『世界樹の王』のロロ。改めてこれからよろしくね」
「うん、よろしくロロ。……え? 『世界樹の王』?」
俺は差し出された手を取りながら、ロロの言った言葉を反芻し、思わず疑問符を浮かべる。
「そうよ。私はこの世界樹ユグドラシルの精霊であり、世界樹の王となる資格を持つ者の元へ現れる。そういうスキルなの」
「それってつまり……俺が世界樹の王ってこと?」
「そう、アルトは世界樹の王になったのよ!」
……どうやら俺が覚醒したスキルはすごいモノのようだ。
「そうなんだ。それで、俺はどんなことが出来るの? アスガルドの役に立てる?」
しかし、俺にとって重要なことはスキルの優劣ではない。
そのスキルを用いてどのように国の役に立つかと言う所だ。
「……そうね」
だが、俺の質問にロロは少しだけ表情を暗くした。
「アルト……あなたにはアスガルドの前にこの世界樹を救ってもらう必要があります」
「それは……一体どういうこと?」
「それは……」
悲し気な眼差しで俺を見つめたロロはその理由を語りだした。
誰かがそう叫ぶと町中の人がその人物を一目でも見ようとこぞって集まってくる。
もはやアイドルのような存在である少年アルト・アンドレアルは公務の帰りに気まぐれで城下町を通っていた。
王族として民草に定期的に姿を見せることは、もはや習慣化されたアルトの行動の一つだが、今日は街を歩きたい気分だった。
「馬車、止めてもらえる?」
「皇子?王城はまだ先ですが……」
「先と言ったってもう目と鼻の先ほどの距離じゃないか。ちょっと歩きたい気分なんだ」
「左様にございますか……ルート、皇子をお守りしろ!」
「はっ」
俺の乗る馬車を引いていた二人のうち一人が俺と一緒に馬車を降りる。
「ルート、アルト様に万が一のことがないように。くれぐれも注意するのだぞ!」
「この命に替えましても!」
ルートと呼ばれた騎士が上司と思われる騎士に敬礼をするとすぐにアルトの方を向いて跪いた。
「王城までの護衛をさせていただきます」
「ああ、悪いね。少し歩きたい気分でさ」
「お気になさらず、皇子の命ならばこの命であろうと簡単に捧げましょう」
「それはダメだよ。俺の騎士ならば、俺の命と自分の命を同時に守れなきゃね」
「はっ!このルート、肝に銘じます!」
11歳の子供の足でも半刻とかからない距離を歩くだけでこの大げさっぷり。
この国アスガルドにおける第一皇子にして、誰もが次期国王と信じて疑わないこの少年は名をアルト・アンドレアルと言った。
若干11歳にして国王の代理を務めて公務をこなし、傍らで立ち寄った村での水害を機転により解決、前王の時代から国中に名を轟かせた大盗賊団の根城の発見及び掃討など、数々の功績を積み上げている彼は、その才を認められているからこそ、このように王族という身分をも超えたような扱いを受けていた。
「今の、見たわよね!」
「ええ、まだ覚醒もされていないのにあのカリスマ! 一体どんなスキルを覚醒されるのかしら」
そんなアルトと騎士たちのやり取りを固唾を呑んで見つめていた民衆から集まる視線も憧れや羨望、忠誠のようなものばかりだった。
だが、その中に一人アルトの目に留まった女性がいた。
「そこのあなた……酷く憔悴しているように見える。何かあったのか?」
そんな視線ばかりを受けている俺は、道中にへたり込む女性が気になり声をかけた。
その女性は自分の母より少し年上ほどの年齢だと見受けられるが、髪には艶が全くなく、頬がこけ、目はうつろだった。
「あ、あぁっアルト様! 申し訳ありません。……その……む、娘が世界樹様の元へ、行くことになりまして……いえもちろん、光栄なことであるということは承知しているのです! ですが……」
ああ、そうだったのか。
我が母と年が近いのならば、娘の年齢もまた俺と近いのだろう。
「良い、身内が手から離れていくのはそれが世界樹との一体化だとしてもつらかろう。娘の名は?」
俺がそう問うと、女性はボロボロと涙をこぼしながら答えた。
「ルミネ……ルミネにございます」
「ルミネか。良き名だな」
名前を聞くと俺はこの国を望む、あり得ない程巨大な樹……世界樹に向かって膝をつき胸に手を当てた。
「――私はアスガルド第一皇子アルト・アンドレアル。ここに世界樹となったルミネへ感謝と敬意を表す! その命、大義であった!」
声を張りながら低い姿勢で首を垂れる。
「あ゙あぁっ……ああぁ……。ルミネ、良かったわね。あなたはアルト様に……」
ルミネの母は泣き崩れ、周りに居た民衆は俺と同じように世界樹に向かって膝をつき胸に手を当てた。
この国アスガルドでは、時折このように世界樹となる者たちがいる。
世界樹となる、とはつまり、呼吸以外のすべての身体機能が停止してしまった者たちを指し、そうなったものは世界樹の根元へ埋葬される。
しばらくすると、そうなった者たちは実際に世界樹に吸収されるのだ。
「ルミネの母よ、あなたもまた大義である。今後はさらなる世界樹の加護があなたを守るだろう」
俺は世界樹への祈りを終えると最後にそう伝え、咽び泣く声を背に受けながら王城に向けて歩き出す。
「毅然とされた態度、流石にございました。このルート感服仕りました」
「俺は王族だからな。国を治めるものとして民への感謝を忘れないのは当然だ」
何かと反応の大きいルートに内心少し辟易しつつも共に王城まで歩いた。
◇◇◇
「兄様! おかえりなさい! 村の様子はどうでしたか?」
アルトが城へと戻ると妹のテナーが食い入るように聞いてきた。
「ただいまテナー。調子は良さそうだったよ。水害でダメになった家もしっかり建て直されてきてたし、次に川が決壊したときのための対応もちゃんと指示通り行われていた。またあの大雨が降っても大丈夫だと思うよ」
「さすが兄様! 『浮力付与』のスキルを村全ての家に使うなんてどうやったら思いつくのですか!?」
「はははっ! そうだね、自分でも思いついたときは馬鹿げてると思ったさ。でもスキルは組み合わせ次第で色々なことができるからね。この村の件だって確かに『浮力付与』が一番目立ってはいるけど、水害があった時に浮いた家が流されないようにするための『固定の鎖』とか他にもいろいろなスキルが使われてる。俺はスキルについて少し詳しいから思いつけただけさ。テナーも勉強を頑張ればこのくらいすぐに思いつけるようになるよ」
「はぁい……でも勉強かぁ……兄様が言うなら、私ももう少し頑張ってみます!」
意気込むテナーの頭を撫でながら思う。
やはり、スキルの力や詳細を王族だけが有して民衆に公表しないのはよくないと。
世界においてスキルの持つ力は圧倒的だ。
だからこそ、どの国であろうと何らかの方法で自分以外のスキル詳細は秘匿されるようになっている。
我が国アスガルドでは、『誓いの約因』という初代国王のスキルによる誓いを12歳となりスキルを覚醒した者全員に行わせ、自分のスキルの効果や能力を他人に教えてはならないという誓いを立てさせている。
仕組みとしては『誓いの約因』が付与されたスキルの書と呼ばれる本に名前と覚醒したスキルを書かせると言った単純なものだが、このスキルの書には偽造や嘘を防ぐ『真実の目』や限定された者にしか公開されないようにするための『隠者の約定』などのスキルが使われている。
「あ、にいさま! ねえさまばかりずるい! 僕もにいさまによしよししてもらう!」
考え事をしている間、ずっとテナーの頭を撫でていたところを弟に見つかってしまった。
「いいぞ! カイも来なさい。ほら」
テナーを撫でる手とは逆側に弟のカイを呼んでやると、とてもうれしそうに飛び込んできた。
俺とテナーは年子だが、カイは少し離れているためどうにも甘えん坊に育ってしまっているようだ。
まあ、かわいいからいいのだけど、テナーも含めて二人にはもう少し王族としての振る舞いを身に着けて欲しいという思いもあった。
「にいさま! ねえさまとは何のお話をしてたんですか?」
「今日視察に行った村の話だよ。カイもスキルについてはちゃんと学んでおくんだぞ?」
「うぅ……勉強は嫌いだよぉ……」
「ダメよカイ! ねえさまと一緒に頑張りましょう?」
カイがいるとテナーも少しは大人になる様だ。
◇
「そういえば、もうすぐ兄様も覚醒ですね! 兄様は一体どんなスキルを覚醒されるのでしょう!?」
「にいさまのスキルだよ! 絶対すごいやつだよ!」
俺の部屋までついてきた二人は今度の俺の誕生日に授けられるスキルについてで盛り上がっていた。
「でも、兄様なら一見用途が難しそうなスキルでもすごい活用法を思いつきそう! それこそ初代国王様みたいに!」
「えー、きっとまだ誰も知らないようなすごいやつだよ!」
「「兄さまはどうなると思いますか!?」」
結論に詰まったからか、二人は同時に俺の方を向いてそう聞いてきた。
「どうだろうね? でも、どんなスキルでもやることは変わらないさ。この世界には全く無駄なスキルはないんだから」
俺の答えに一応納得はするも、やはり気になってしまうようで二人による俺のスキル予想はさらに盛り上がっていた。
俺としても王族のスキルは『誓いの約定』の能力で全国民に公開されるため、それなりのものであることを願った。
「ついに明日なのね! 一体アルトはどんなスキルを覚醒するのかしら!」
少しの月日が流れ、ついに今日はアルトの誕生日前日となっていた。
目の前の母だけでなく、国中がお祭りのような雰囲気を醸し出しており、国民がアルトへ向ける期待や羨望の眼差しがまるで空気にまで作用している様だった。
「母さん、はしゃぎすぎだよ。それに俺はどんなスキルでも王族としての務めを果たすだけさ!」
アルトの母ラーノ・アンドレアルは子煩悩だが、とくにアルトを溺愛しており、人生における最重要ポイントともとれるスキル覚醒を前にして興奮を抑えられない様子だった。
「もう! そんな固いことばかり考えなくていいのよ? 私はまだ三十五だし、コントラスもまだ四十手前だから、いきなりアルトに国を任せたりはしないわ。アルトは賢いのだからもっと好きに生きてね?」
「ははっ、ありがとう母さん。もう十分好きに生きてるよ。スキルの勉強をして、それを国民の生活に役立てて国を豊かにする。俺のやりたいことはたくさんやらせてもらってるよ!」
「アルトがそれでいいならいいけど……他にやりたいことがあればいつでも、なんでも言ってね?私、なんでも応援するから!」
「じゃあ、呼び方を母様に戻しても……」
「それはダメよ!」
……母さんも名家の出身のはずなのだが、俺たち兄弟にはこんな感じなのだ。
これで母さんのスキルは『氷結の刃』という冷酷無比な戦闘系のスキルなのだからスキルというものは本当にわからない。
二十歳の頃に他国との戦争で大戦功をあげ、その圧倒的な力に惚れ込んだ父が粘り落したらしい。
ちなみに当時の二つ名は麗氷だったと父が言っていた。冷たい氷と氷のように美しい様をよく表現した二つ名だとニヤニヤ語る父には少し引いたというのはここだけの話だ。
「まあ、スキルについては明日になれば嫌でも分かるし、やりたいことも十分できてるから大丈夫だよ母さん」
「そう? アルトが満足してるならいいわ! それよりスキルの後はお嫁さんね! コントラスみたいに二十を過ぎても決まった相手がいないなんて真似はさせないから安心してね? あ、でも、どうしても気に入る子がいなかったら、私がアルトのお嫁さんになってあげるから!」
「母さん! その話はやめてよ! 恥ずかしいから!」
頭を撫でながら懐かしい昔の話を持ち出され、照れ隠しに母さんを押しのけようとするも、麗氷の異名を持つ武人な母さんにはなすすべもなく、そのまま抱きしめられた。
「ふふっ、良いじゃない。テナーもカイもいないんだから! 私には甘えてくれていいのよ? どんなに優秀で賢くてもアルトはまだ十二歳なんだから」
「……うん、ありがとう母さん」
圧倒的なまでの母性に包まれ、その温かい優しさを噛み締めるように俺も抱きしめ返すのだった。
◇◇◇
夕食の時間になった。
これを食べて、眠りに着けば明日にはスキルが覚醒している……そう考えると緊張と不安や期待など様々な感情が自分の中で渦巻いた。
「アルト、体調はどうだ? 万全か?」
「もちろん! 若干緊張はしてるけど、体調は問題ないよ!」
父に聞かれ、そんな複雑な感情を打ち払うように少しだけ気丈に振る舞って見せる。
「はははっ! そうか、お前でも緊張するか!」
「ちょっとコントラス! 当たり前でしょう? アルトだって普通の十二歳なのよ?」
「そうは言っても母さん、兄様が緊張するって言葉にするのは珍しいよ!」
「たしかに、にいさまでも緊張するんだね!」
「テナーもカイも俺を何だと思ってるんだ? 当たり前だろう?」
これでも気丈に振る舞ったつもりだったが、それでも驚かせてしまったようだ。
だがこれも俺に向けられる期待の表れなんだ。
弱気になっている場合じゃない。
俺は今一度気を引き締めた。
「ねえ、とおさまはにいさまのスキルはどんなスキルだと思う?」
「そうだな……ラーノみたいに戦闘寄りのスキルもいいが、賢いアルトには本当にどんなスキルでも似合いそうだな」
「やっぱりとおさまもそう思うよね! あ~明日が楽しみだな~」
「ほら、あんまりプレッシャーをかけすぎちゃダメよ。……アルト? そんなに緊張しなくて大丈夫よ? スキルは選べるものじゃないわ。それにあなたにはこれまでたくさん勉強して蓄えた知識があるもの! 明日だって普段通りに寝て起きたらいいのよ」
「母さん……。そうだね。今変に気負ってもしょうがないか」
「まあ、ラーノの言う通りだ。どんなスキルだろうと、アルトは上手く使うだろうさ。さて、じゃあ、今日はもう寝ておくか?」
皆、楽しみにしてくれているのと同時に心配してくれているんだ。
……そうだ、どんなスキルだろうと役に立たないものはない。
貰ったスキルで胸を張って行けばいいんだ。
「うん、そうするよ。じゃあみんな、一足先におやすみ」
「ああ、おやすみアルト」
「「兄様! おやすみなさい」」
「おやすみ、アルト」
四人の家族に見送られ、俺は自室へ戻る。
見送られながら自室に戻るというのは中々不思議な感覚で少し気恥しかったが、それと同時に誇らしくもあった。
これでもっと俺も国のために尽くすことが出来る。
何だか明日が楽しみになって来た。
◇◇◇
ナイトルーティーンと言うほどではないが、変に身構えないように、努めていつも通りに過ごし、ベッドに入る。
緊張や興奮で寝られないかもしれないという俺の心配はどこへやら、気付けば俺は深い眠りに落ちていた。
どれくらい眠ったのだろうか?
それは不思議な感覚だった。
身体は完全に眠っていると言うのに、意識だけはまるではっきりとしているような、そんな感覚。
そこにその声が響いた。
「あなたが私の王なのね!」
全身を優しく包み込む様な柔らかく、温かい声。
聞いたことがないのに、まるで生まれた頃からずっと、共に在ったかのようなその声はスッと頭に入ってくる。
「君は……一体?」
「ふふ、私はロロ。あなたのスキルだよ」
俺が控えめに正体を聞くと目の前に姿を現した同年代か少し年上くらいの少女はロロと名乗った。
「俺のスキルが君? スキルは自我を持っているのか?」
とんでもない現象を目の前にしていると言うのに、どういう訳か不思議と受け入れている自分がいる。
俺は冷静にそう聞いた。
「ふふっ、違うよ。私とあなたが特別なの。だってあなたは……この世界樹に抱かれた国で最も、世界樹に愛された子なんだから」
柔らかく微笑み、優しく胸に抱かれる。
母以外の女性に抱きしめられるというのは少し気恥しい。
しかし、ロロの抱きしめる手からは俺を思いやる感情が伝わって来てすぐに受け入れられた。
「そっか。ロロ、これからよろしくね」
俺は彼女を抱きしめ返し、そう告げる。
「ええ。よろしくねアルト」
こうして再び俺の意識は身体に戻っていった。
◇◇◇
翌日、王城は騒乱に包まれた。
「アルトッ! アルトッッ!! どうしちゃったの! ねぇ、アルトッ! お願いっ! 起きて!」
その日、アルト・アンドレアルの12歳の誕生日は確かに訪れた。
しかし……その日にアルト・アンドレアルが目を覚ますことはなかった。
「兄様? もう、お昼ですよ。勉強を見てください。兄様、このスキルについてなのですが……兄様? 兄様、兄様兄様、兄様兄様兄様っっっ!!!」
穏やかな顔をして、呼吸も安定している。
しかし、彼の身体はピクリとも動かない。
「にいさまがおねぼうなんてめずらしい。……でも、もう夜だよ? にいさま、どうしたの?」
まるで、この国を遥か高みから見下ろす世界樹のように、彼は静かに横たわっていた。
「クソっ! クソっ!! 何が世界樹だ! 俺の息子を……アルトを……ふざけるな! ふざけるなぁぁぁ!!!」
その慟哭は一日を過ぎても止むことはなかった。
そしてまた一日、二日、一週間と時間は過ぎていく。
「これは……コントラス陛下。……おめでとう……ございます。あ、アルト、皇子は……世界樹に、なられました」
国随一と呼ばれる名医、スキル『治癒の光』を持つ医者が遂にそれを告げた。
その顔は酷く怯え、引きつっている。
「ふ、ふざける――」
「貴方……!」
アルトの世界樹化を告げた医者にコントラスが掴みかかろうとするのを、すっかり憔悴してしまったラーノが何とか引き留めた。
アスガルドにおいて世界樹になるということは悲しくもあり、最大の名誉でもある。
「兄様……」
「うっ……うぅぅ……」
この国を高くから見守り、支え、象徴としてそびえ立つ。
それが世界樹だからだ。
「……あの子は……アルトはきっと今も私たちを見てくれている。……恥ずかしいところを見せるわけにはいかないわ」
目は泣き腫らし、頬はこけ、髪の艶がなくなっても、ラーノは家族を奮い立たせる。
「ちゃんと、見送ってあげましょう」
こうして、アルト・アンドレアルの誕生日から二週間と一日、ちょうど半月の期間を擁してその事実を受け入れたアンドレアル皇家によって、アルト・アンドレアルは世界樹の根元で眠らされることになった。
その発表は大いに国を混乱させた。
嘆き、悲しみくれる者、彼の代わりに自分を世界樹にしてくれと昼夜問わずに世界樹へ祈りを捧げ続ける者、実際に後を追ってしまう者までもが現れた。
民からのアルトへの信頼は、まさに世界樹へ向けられるようなものだった。
◇◇◇
ずいぶん長く眠っていた気がする。
少し、寝坊をしてしまっただろうか?
うっすらと目を開けてみればそこは暗がりの中に仄かな光だけが広がる空間だった。
「……ここは? 一体?」
「あ、アルト、おはよう。良く寝てたね」
すると俺の真横から優しい声が聞こえて来る。
「……君は……もしかしてロロ?」
そちらを振り向けば夢の中で出会ったあの少女の姿があった。
「ええ、私はあなたのスキル『世界樹の王』のロロ。改めてこれからよろしくね」
「うん、よろしくロロ。……え? 『世界樹の王』?」
俺は差し出された手を取りながら、ロロの言った言葉を反芻し、思わず疑問符を浮かべる。
「そうよ。私はこの世界樹ユグドラシルの精霊であり、世界樹の王となる資格を持つ者の元へ現れる。そういうスキルなの」
「それってつまり……俺が世界樹の王ってこと?」
「そう、アルトは世界樹の王になったのよ!」
……どうやら俺が覚醒したスキルはすごいモノのようだ。
「そうなんだ。それで、俺はどんなことが出来るの? アスガルドの役に立てる?」
しかし、俺にとって重要なことはスキルの優劣ではない。
そのスキルを用いてどのように国の役に立つかと言う所だ。
「……そうね」
だが、俺の質問にロロは少しだけ表情を暗くした。
「アルト……あなたにはアスガルドの前にこの世界樹を救ってもらう必要があります」
「それは……一体どういうこと?」
「それは……」
悲し気な眼差しで俺を見つめたロロはその理由を語りだした。