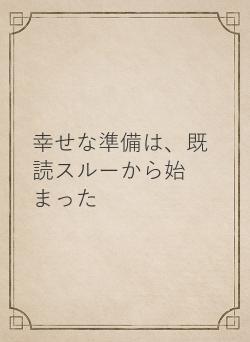幸せな日々が続いた。
薬はまだ3粒残っていたけれど、私はしばらく使わなかった。
由香里とは毎週のように会うようになった。拓也のことも、もう心を痛めることはなくなった。祖母の愛を知って、私は少しだけ強くなれた気がした。
仕事も順調だった。レオの毒舌アドバイスのおかげで、自信を持って振る舞えるようになった私を、上司も認めてくれるようになった。
そして何より、レオがいた。
毎日、帰宅すると出迎えてくれるレオ。薬を使わなくても、その存在だけで十分だった。
でも、幸せは突然終わった。
ある朝のことだった。
いつものようにレオに朝ごはんをあげようとすると、レオは食べなかった。
「どうしたの、レオ? お腹空いてないの?」
レオは弱々しく鳴いただけだった。
その日は仕事があったから、様子を見ることにした。帰ったら元気になっているだろうと思った。
でも、帰宅すると、レオはソファの上で丸くなったまま動かなかった。
「レオ?」
近づくと、レオが突然体を震わせた。
そして、吐いた。
透明な液体と、少しの血が混じっていた。
「レオ!」
私は慌ててレオを抱き上げた。体が、いつもより軽い気がした。
すぐに動物病院に電話をかけた。
「今から行きます。お願いします、診てください」
タクシーを呼んで、レオを抱えて病院に駆け込んだ。
待合室で待つ時間が、永遠のように長かった。
レオは私の腕の中で、ぐったりとしていた。いつもの活発さは、どこにもなかった。
「飼い主さん」
獣医師が呼んだ。
診察室に入ると、獣医師は深刻な顔をしていた。
「検査の結果ですが......悪性リンパ腫です」
頭が真っ白になった。
「悪性......リンパ腫?」
「猫の血液の癌です。進行が早く、既にかなり進んでいます」
獣医師は、レントゲン写真を見せてくれた。
でも、私には何も理解できなかった。
「治療は......できないんですか?」
「抗がん剤治療という選択肢はあります。ただ、レオちゃんの年齢と進行度を考えると......」
獣医師は言葉を濁した。
「どのくらい......どのくらい生きられますか?」
私の声が震えた。
獣医師は、静かに答えた。
「治療をしても、恐らく数週間から、長くて2ヶ月程度かと思います」
世界が崩れた。
数週間。2ヶ月。
そんな短い時間しか、残されていないなんて。
「今は、痛みを和らげる治療と、できるだけ穏やかに過ごせるようにすることが大切です」
獣医師の声が、遠くに聞こえた。
私は、ただ頷くことしかできなかった。
帰りのタクシーの中で、私はレオを抱きしめた。
レオは、静かに目を閉じていた。
「ごめんね、レオ。気づいてあげられなくて」
涙が溢れた。
もっと早く気づいていれば。
もっと早く病院に連れて行っていれば。
でも、もう遅かった。
レオの時間は、もう残り少ない。
家に着いても、私は何も手につかなかった。
ただ、レオの横に座って、その体を撫で続けた。
温かい体温。柔らかい毛並み。
これが、もうすぐ失われてしまう。
「嫌だ......嫌だよ、レオ」
私は泣きながら、レオに語りかけた。
レオは、小さく鳴いた。
まるで「大丈夫だよ」と言っているような、優しい声だった。
でも、大丈夫じゃない。
何も、大丈夫じゃなかった。
残された時間は、あまりにも短すぎた。
翌日、私は仕事を休んだ。
レオの側を離れられなかった。
レオは、ほとんど動かなくなっていた。水も餌も、ほとんど口にしない。
私は、ふと思い出した。
薬だ。
まだ3粒残っている。レオと話せる薬。
「レオ、今どんな気持ちなの? どこが痛い? 何が食べたい?」
聞きたいことが、山ほどあった。
私は震える手で薬を取り出した。
レオの餌に混ぜる。でも、レオは食べない。
「お願い、レオ。食べて」
私は無理やり、薬を溶かした水をレオの口に含ませた。
レオは嫌がったけれど、少しだけ飲み込んでくれた。
数分後。
薬の効果が現れるはずだった。
「レオ? 聞こえる? 私の声」
レオは、ゆっくりと目を開けた。
いつもの、鋭い目。
「レオ、教えて。どこが痛いの? 何かしてほしいことある?」
でも、レオは何も言わなかった。
口を閉ざしたまま、ただ私を見ている。
「レオ? 薬、ちゃんと飲んだよね? 効いてるはずなのに......」
私は焦った。
薬が効いていないのか。それとも、レオはもう喋る力もないのか。
「お願い、何か言って。苦しいなら苦しいって言って。痛いなら痛いって言って!」
私の声が、金切り声になった。
レオは、ただ静かに私を見つめていた。
そして、ゆっくりと目を閉じた。
「嫌だ......嫌だよ、レオ」
私は泣き崩れた。
どうして。
どうして何も言ってくれないの。
次の日も、私は薬を使った。残り2粒。
「レオ、お願い。今日は話して。何でもいいから」
でも、レオはやはり沈黙を貫いた。
薬は効いている。レオの目を見ればわかる。私の言葉を、ちゃんと理解している。
それなのに、何も言わない。
「どうして......どうして黙ってるの?」
私は、レオの体を揺さぶった。
「前はあんなに喋ってくれたのに。毒舌でもいい、悪態でもいいから、何か言ってよ!」
レオは、ただじっと私を見ていた。
その目は、悲しそうだった。
そして、私は気づいた。
レオは、喋れるのに喋らない。
なぜ?
答えは、すぐにわかった。
レオは、私を守ろうとしている。
「痛い」と言えば、私は苦しむ。
「苦しい」と言えば、私は壊れる。
だから、黙っている。
何も言わずに、ただ耐えている。
「レオ......」
私の涙が、レオの体に落ちた。
「バカ......バカだよ、レオ」
私は震える声で言った。
「我慢しなくていいのに。痛いなら痛いって言ってよ。私、何でもするから。できることなら何でも」
でも、レオは首を横に振った。
小さく、ゆっくりと。
まるで「大丈夫」と言っているように。
私は、レオを抱きしめた。
「ごめんね......ごめんね、レオ」
レオは、私の腕の中で静かに目を閉じた。
その体は、日に日に軽くなっていく。
私は、自分の無力さに打ちのめされた。
レオは、最期の瞬間まで私を思いやっている。
自分の痛みよりも、私の心を優先している。
それなのに、私は何もできない。
レオの痛みを取り除くことも、苦しみを和らげることもできない。
ただ、見守ることしかできない。
「レオ、あんたは優しすぎるよ」
私は泣きながら囁いた。
「もっとわがまま言ってよ。もっと頼ってよ」
でも、レオは何も言わなかった。
ただ、私の腕の中で、小さく喉を鳴らした。
ゴロゴロという音。
それは、レオなりの「大丈夫」だった。
私は、その音を聞きながら、ずっとレオを抱きしめていた。
言葉はなくても、伝わってくるものがあった。
レオの温もり。
レオの優しさ。
レオの、私への愛。
「ありがとう、レオ」
私は何度も何度も囁いた。
「あんたに出会えて、本当によかった」
レオは、また小さく鳴いた。
まるで「俺もだよ」と言っているように。
その夜、私は薬を使わなかった。
残り1粒。
最後の1粒は、いつ使おう。
私は、まだ決められなかった。
でも、一つだけわかったことがあった。
言葉がなくても、レオと私は通じ合っている。
薬がなくても、レオの気持ちはわかる。
レオの目を見れば。
レオの体温を感じれば。
レオの小さな仕草を見れば。
全部、伝わってくる。
私は、レオの隣で眠った。
レオの呼吸に合わせて、自分の呼吸を整える。
一緒に生きている。
この瞬間を、大切にしたい。
たとえ、それがあとどれだけ続くかわからなくても。
数日後、私は決意した。
薬を探しに行く。
残りは1粒。これでは足りない。
もっと欲しい。もっとレオと話したい。
いや、話したいわけじゃない。
ただ、レオの声が聞きたい。
あの毒舌でもいい。悪態でもいい。
レオが生きている証が欲しかった。
私は、あの公園に向かった。
露天商の男を探して、公園中を歩き回った。
ベンチ、木の陰、遊具の近く。
でも、男の姿はどこにもなかった。
「どこにいるの......お願い、出てきて」
私は必死だった。
毎日、仕事が終わると公園に通った。
朝早く行ってみたり、夜遅く行ってみたり。
でも、男は現れなかった。
1週間が過ぎた。
レオの容態は、日に日に悪化していた。
もう、ほとんど動かない。
「レオ......待ってて。薬、必ず見つけるから」
私は、焦っていた。
時間がない。
レオとの時間が、刻一刻と減っていく。
そして、ある夕暮れのこと。
私がいつものように公園に来ると、ベンチに誰かが座っていた。
古びたコート。片手に木箱。
あの男だ。
「あなた!」
私は駆け寄った。
男は、ゆっくりと顔を上げた。
「やあ、お嬢さん。また会ったね」
「薬を売ってください。お願いします」
私は頭を下げた。
「いくらでも払います。だから、薬を」
男は、静かに首を横に振った。
「売れない」
「どうして? お金なら......」
「お金の問題じゃないんだよ」
男は、木箱を開けた。
中には、あの虹色の薬が並んでいた。
「薬はある。でも、お嬢さんには売らない」
「お願いします! レオが、私の猫が死にかけてるんです。最期に、もう一度声が聞きたいんです」
私の声が震えた。
「だから、お願い。薬を売ってください」
男は、じっと私を見た。
「お嬢さん、猫の声が聞きたいのかい? それとも、猫の気持ちが知りたいのかい?」
「......え?」
「この薬は、猫の言葉を人間の言葉に変換する。便利だ。でもね、言葉って不思議なもので」
男は、空を見上げた。
夕焼けが、空を赤く染めていた。
「言葉は便利なようで、一番大事なものを隠すことがある」
「どういう......」
「お嬢さんの猫は、今何も喋らないんだろう?」
私は、息を呑んだ。
どうして、それを。
「猫が黙っているのは、喋れないからじゃない。喋らない選択をしてるんだ。お嬢さんを守るために」
男の言葉が、胸に刺さった。
「その優しさ、その想い。言葉にしたら、逆に安っぽくなる。わかるかい?」
私は、何も言えなかった。
「お嬢さんは、もう猫の気持ちがわかってるはずだ。言葉なしでも。目を見れば、体温を感じれば、呼吸を聞けば。全部、伝わってくるだろう?」
そうだった。
レオが何も言わなくても、私にはわかる。
レオが私を愛していること。
レオが私を心配していること。
レオが、最期まで私の側にいたいと思っていること。
「言葉は、時に嘘をつく。でも、心は嘘をつけない」
男は立ち上がった。
「お嬢さん、薬に頼るのはもうやめな。お嬢さんにできることは、猫の隣にいて、その温もりを感じて、最期まで一緒にいることだ」
男は、木箱を閉じた。
「猫は、お嬢さんの声を聞きたがってる。薬で聞こえる声じゃなくて、お嬢さん自身の声を」
「私の......声?」
「そうだ。ありがとうって。愛してるって。一緒にいてくれて嬉しかったって。そういう言葉を、猫は待ってるんだよ」
男は、ゆっくりと歩き出した。
「待って!」
私は呼び止めた。
でも、男は振り向かなかった。
「もう会うことはないだろう。猫を、大切にな」
男の姿が、夕暮れの中に消えていった。
私は、その場に立ち尽くした。
薬は、手に入らなかった。
でも、何かもっと大切なものを、手に入れた気がした。
言葉なんて、いらない。
レオの気持ちは、もうわかっている。
そして、私の気持ちも、レオに伝えなきゃいけない。
薬に頼らずに。
自分の声で。
私は、走り出した。
家に帰らなきゃ。
レオの側に、戻らなきゃ。
残された時間は、わずかかもしれない。
でも、その時間を、言葉に頼らずに過ごそう。
レオと、ちゃんと向き合おう。
夕焼けの空の下、私は必死で走った。
家に着くと、息を切らしながらドアを開けた。
「レオ!」
リビングに駆け込む。
レオは、ソファの上で丸くなっていた。
私の声に、ゆっくりと目を開けた。
「レオ......ごめん、遅くなった」
私は、レオの隣に座った。
薬の袋を見る。残り1粒。
でも、私はそれを使わなかった。
代わりに、そっとレオの前足を握った。
小さくて、細くて、温かい足。
「レオ、聞いて」
私は、静かに語りかけた。
「もう薬は使わない。言葉で聞くんじゃなくて、ちゃんと感じたいから」
レオは、じっと私を見た。
「レオの気持ち、わかるよ。ちゃんと伝わってる」
私は、レオの頭を優しく撫でた。
柔らかい毛並み。指先に伝わる、小さな温もり。
レオは、ゆっくりと瞬きをした。
1回、2回。
猫のキス。
愛情表現だと、どこかで読んだことがある。
「私も、レオが大好きだよ」
私は微笑んだ。
レオの尻尾が、わずかに動いた。
ほんの少しだけ、左に揺れた。
それだけで、十分だった。
レオは、私の言葉を聞いている。
わかってくれている。
私は、レオの体を優しく撫で続けた。
背中、首、頬。
レオの体は、以前よりずっと痩せていた。
骨が浮き出ている。
でも、まだ温かい。
まだ、生きている。
レオが、小さく喉を鳴らした。
ゴロゴロという音。
か細くて、途切れ途切れだけれど、確かに聞こえた。
「嬉しいの?」
私は聞いた。
レオは、また瞬きをした。
ゆっくりと、優しく。
涙が溢れた。
でも、悲しい涙じゃなかった。
「ありがとう、レオ。私の側にいてくれて」
私は、レオの体を包み込むように抱きしめた。
レオの心臓の音が聞こえる。
小さくて、弱々しいけれど、確かに鼓動している。
トクン、トクン、トクン。
その音に、私は耳を澄ませた。
「レオ、あのね」
私は囁いた。
「レオと過ごした時間、全部宝物だよ。毎日帰ってきて、レオがいてくれるだけで、私は幸せだった」
レオの尻尾が、また少し動いた。
「最初は、レオの毒舌にびっくりしたけど」
私は笑った。
「でも、あれは全部、私のためだったんだよね。わかってるよ」
レオの呼吸が、私の腕に当たる。
温かい吐息。
生きている証。
「レオは、いつも私を見ていてくれた。私が泣いてる時も、笑ってる時も。誰よりも、私のことを知っていてくれた」
レオが、小さく鳴いた。
「ん......」
か細い声。
でも、確かにレオの声だった。
「レオ、痛い? 苦しい?」
私は心配になった。
でも、レオはゆっくりと首を横に振った。
わずかな動きだけれど、はっきりと「違う」と言っていた。
「そっか。よかった」
私は安堵した。
そして、また撫で続けた。
時間が、ゆっくりと流れていく。
外は、もう暗くなっていた。
部屋の明かりを消して、月明かりだけにした。
静寂の中で、私とレオは寄り添っていた。
言葉はいらなかった。
レオの瞬き。
レオの尻尾の動き。
レオの喉のゴロゴロ音。
レオの体温。
レオの呼吸。
その全てが、言葉だった。
「愛してる」という言葉。
「ありがとう」という言葉。
「一緒にいて幸せ」という言葉。
それが、音のない声となって、私の心に響いていた。
「私も、レオのこと、大好きだよ」
私は何度も囁いた。
「一緒にいてくれて、ありがとう」
レオは、私の腕の中で静かに目を閉じた。
その顔は、穏やかだった。
苦しそうでも、悲しそうでもなく。
ただ、安心しているような、優しい表情。
私は、レオを抱きしめたまま、じっと見つめた。
このまま、時間が止まればいいのに。
そう願った。
でも、時間は止まらない。
それでも、この瞬間を、心に刻もう。
レオの温もり。
レオの重み。
レオの存在。
全部、忘れない。
「レオ、愛してるよ」
私は、最後にもう一度囁いた。
レオの尻尾が、ほんの少しだけ動いた。
まるで「俺もだよ」と言っているように。
静寂の中で、私たちの魂は完全に通じ合っていた。
言葉なんて、もう必要なかった。
ただ、この温もりがあれば。
それだけで、十分だった。
薬はまだ3粒残っていたけれど、私はしばらく使わなかった。
由香里とは毎週のように会うようになった。拓也のことも、もう心を痛めることはなくなった。祖母の愛を知って、私は少しだけ強くなれた気がした。
仕事も順調だった。レオの毒舌アドバイスのおかげで、自信を持って振る舞えるようになった私を、上司も認めてくれるようになった。
そして何より、レオがいた。
毎日、帰宅すると出迎えてくれるレオ。薬を使わなくても、その存在だけで十分だった。
でも、幸せは突然終わった。
ある朝のことだった。
いつものようにレオに朝ごはんをあげようとすると、レオは食べなかった。
「どうしたの、レオ? お腹空いてないの?」
レオは弱々しく鳴いただけだった。
その日は仕事があったから、様子を見ることにした。帰ったら元気になっているだろうと思った。
でも、帰宅すると、レオはソファの上で丸くなったまま動かなかった。
「レオ?」
近づくと、レオが突然体を震わせた。
そして、吐いた。
透明な液体と、少しの血が混じっていた。
「レオ!」
私は慌ててレオを抱き上げた。体が、いつもより軽い気がした。
すぐに動物病院に電話をかけた。
「今から行きます。お願いします、診てください」
タクシーを呼んで、レオを抱えて病院に駆け込んだ。
待合室で待つ時間が、永遠のように長かった。
レオは私の腕の中で、ぐったりとしていた。いつもの活発さは、どこにもなかった。
「飼い主さん」
獣医師が呼んだ。
診察室に入ると、獣医師は深刻な顔をしていた。
「検査の結果ですが......悪性リンパ腫です」
頭が真っ白になった。
「悪性......リンパ腫?」
「猫の血液の癌です。進行が早く、既にかなり進んでいます」
獣医師は、レントゲン写真を見せてくれた。
でも、私には何も理解できなかった。
「治療は......できないんですか?」
「抗がん剤治療という選択肢はあります。ただ、レオちゃんの年齢と進行度を考えると......」
獣医師は言葉を濁した。
「どのくらい......どのくらい生きられますか?」
私の声が震えた。
獣医師は、静かに答えた。
「治療をしても、恐らく数週間から、長くて2ヶ月程度かと思います」
世界が崩れた。
数週間。2ヶ月。
そんな短い時間しか、残されていないなんて。
「今は、痛みを和らげる治療と、できるだけ穏やかに過ごせるようにすることが大切です」
獣医師の声が、遠くに聞こえた。
私は、ただ頷くことしかできなかった。
帰りのタクシーの中で、私はレオを抱きしめた。
レオは、静かに目を閉じていた。
「ごめんね、レオ。気づいてあげられなくて」
涙が溢れた。
もっと早く気づいていれば。
もっと早く病院に連れて行っていれば。
でも、もう遅かった。
レオの時間は、もう残り少ない。
家に着いても、私は何も手につかなかった。
ただ、レオの横に座って、その体を撫で続けた。
温かい体温。柔らかい毛並み。
これが、もうすぐ失われてしまう。
「嫌だ......嫌だよ、レオ」
私は泣きながら、レオに語りかけた。
レオは、小さく鳴いた。
まるで「大丈夫だよ」と言っているような、優しい声だった。
でも、大丈夫じゃない。
何も、大丈夫じゃなかった。
残された時間は、あまりにも短すぎた。
翌日、私は仕事を休んだ。
レオの側を離れられなかった。
レオは、ほとんど動かなくなっていた。水も餌も、ほとんど口にしない。
私は、ふと思い出した。
薬だ。
まだ3粒残っている。レオと話せる薬。
「レオ、今どんな気持ちなの? どこが痛い? 何が食べたい?」
聞きたいことが、山ほどあった。
私は震える手で薬を取り出した。
レオの餌に混ぜる。でも、レオは食べない。
「お願い、レオ。食べて」
私は無理やり、薬を溶かした水をレオの口に含ませた。
レオは嫌がったけれど、少しだけ飲み込んでくれた。
数分後。
薬の効果が現れるはずだった。
「レオ? 聞こえる? 私の声」
レオは、ゆっくりと目を開けた。
いつもの、鋭い目。
「レオ、教えて。どこが痛いの? 何かしてほしいことある?」
でも、レオは何も言わなかった。
口を閉ざしたまま、ただ私を見ている。
「レオ? 薬、ちゃんと飲んだよね? 効いてるはずなのに......」
私は焦った。
薬が効いていないのか。それとも、レオはもう喋る力もないのか。
「お願い、何か言って。苦しいなら苦しいって言って。痛いなら痛いって言って!」
私の声が、金切り声になった。
レオは、ただ静かに私を見つめていた。
そして、ゆっくりと目を閉じた。
「嫌だ......嫌だよ、レオ」
私は泣き崩れた。
どうして。
どうして何も言ってくれないの。
次の日も、私は薬を使った。残り2粒。
「レオ、お願い。今日は話して。何でもいいから」
でも、レオはやはり沈黙を貫いた。
薬は効いている。レオの目を見ればわかる。私の言葉を、ちゃんと理解している。
それなのに、何も言わない。
「どうして......どうして黙ってるの?」
私は、レオの体を揺さぶった。
「前はあんなに喋ってくれたのに。毒舌でもいい、悪態でもいいから、何か言ってよ!」
レオは、ただじっと私を見ていた。
その目は、悲しそうだった。
そして、私は気づいた。
レオは、喋れるのに喋らない。
なぜ?
答えは、すぐにわかった。
レオは、私を守ろうとしている。
「痛い」と言えば、私は苦しむ。
「苦しい」と言えば、私は壊れる。
だから、黙っている。
何も言わずに、ただ耐えている。
「レオ......」
私の涙が、レオの体に落ちた。
「バカ......バカだよ、レオ」
私は震える声で言った。
「我慢しなくていいのに。痛いなら痛いって言ってよ。私、何でもするから。できることなら何でも」
でも、レオは首を横に振った。
小さく、ゆっくりと。
まるで「大丈夫」と言っているように。
私は、レオを抱きしめた。
「ごめんね......ごめんね、レオ」
レオは、私の腕の中で静かに目を閉じた。
その体は、日に日に軽くなっていく。
私は、自分の無力さに打ちのめされた。
レオは、最期の瞬間まで私を思いやっている。
自分の痛みよりも、私の心を優先している。
それなのに、私は何もできない。
レオの痛みを取り除くことも、苦しみを和らげることもできない。
ただ、見守ることしかできない。
「レオ、あんたは優しすぎるよ」
私は泣きながら囁いた。
「もっとわがまま言ってよ。もっと頼ってよ」
でも、レオは何も言わなかった。
ただ、私の腕の中で、小さく喉を鳴らした。
ゴロゴロという音。
それは、レオなりの「大丈夫」だった。
私は、その音を聞きながら、ずっとレオを抱きしめていた。
言葉はなくても、伝わってくるものがあった。
レオの温もり。
レオの優しさ。
レオの、私への愛。
「ありがとう、レオ」
私は何度も何度も囁いた。
「あんたに出会えて、本当によかった」
レオは、また小さく鳴いた。
まるで「俺もだよ」と言っているように。
その夜、私は薬を使わなかった。
残り1粒。
最後の1粒は、いつ使おう。
私は、まだ決められなかった。
でも、一つだけわかったことがあった。
言葉がなくても、レオと私は通じ合っている。
薬がなくても、レオの気持ちはわかる。
レオの目を見れば。
レオの体温を感じれば。
レオの小さな仕草を見れば。
全部、伝わってくる。
私は、レオの隣で眠った。
レオの呼吸に合わせて、自分の呼吸を整える。
一緒に生きている。
この瞬間を、大切にしたい。
たとえ、それがあとどれだけ続くかわからなくても。
数日後、私は決意した。
薬を探しに行く。
残りは1粒。これでは足りない。
もっと欲しい。もっとレオと話したい。
いや、話したいわけじゃない。
ただ、レオの声が聞きたい。
あの毒舌でもいい。悪態でもいい。
レオが生きている証が欲しかった。
私は、あの公園に向かった。
露天商の男を探して、公園中を歩き回った。
ベンチ、木の陰、遊具の近く。
でも、男の姿はどこにもなかった。
「どこにいるの......お願い、出てきて」
私は必死だった。
毎日、仕事が終わると公園に通った。
朝早く行ってみたり、夜遅く行ってみたり。
でも、男は現れなかった。
1週間が過ぎた。
レオの容態は、日に日に悪化していた。
もう、ほとんど動かない。
「レオ......待ってて。薬、必ず見つけるから」
私は、焦っていた。
時間がない。
レオとの時間が、刻一刻と減っていく。
そして、ある夕暮れのこと。
私がいつものように公園に来ると、ベンチに誰かが座っていた。
古びたコート。片手に木箱。
あの男だ。
「あなた!」
私は駆け寄った。
男は、ゆっくりと顔を上げた。
「やあ、お嬢さん。また会ったね」
「薬を売ってください。お願いします」
私は頭を下げた。
「いくらでも払います。だから、薬を」
男は、静かに首を横に振った。
「売れない」
「どうして? お金なら......」
「お金の問題じゃないんだよ」
男は、木箱を開けた。
中には、あの虹色の薬が並んでいた。
「薬はある。でも、お嬢さんには売らない」
「お願いします! レオが、私の猫が死にかけてるんです。最期に、もう一度声が聞きたいんです」
私の声が震えた。
「だから、お願い。薬を売ってください」
男は、じっと私を見た。
「お嬢さん、猫の声が聞きたいのかい? それとも、猫の気持ちが知りたいのかい?」
「......え?」
「この薬は、猫の言葉を人間の言葉に変換する。便利だ。でもね、言葉って不思議なもので」
男は、空を見上げた。
夕焼けが、空を赤く染めていた。
「言葉は便利なようで、一番大事なものを隠すことがある」
「どういう......」
「お嬢さんの猫は、今何も喋らないんだろう?」
私は、息を呑んだ。
どうして、それを。
「猫が黙っているのは、喋れないからじゃない。喋らない選択をしてるんだ。お嬢さんを守るために」
男の言葉が、胸に刺さった。
「その優しさ、その想い。言葉にしたら、逆に安っぽくなる。わかるかい?」
私は、何も言えなかった。
「お嬢さんは、もう猫の気持ちがわかってるはずだ。言葉なしでも。目を見れば、体温を感じれば、呼吸を聞けば。全部、伝わってくるだろう?」
そうだった。
レオが何も言わなくても、私にはわかる。
レオが私を愛していること。
レオが私を心配していること。
レオが、最期まで私の側にいたいと思っていること。
「言葉は、時に嘘をつく。でも、心は嘘をつけない」
男は立ち上がった。
「お嬢さん、薬に頼るのはもうやめな。お嬢さんにできることは、猫の隣にいて、その温もりを感じて、最期まで一緒にいることだ」
男は、木箱を閉じた。
「猫は、お嬢さんの声を聞きたがってる。薬で聞こえる声じゃなくて、お嬢さん自身の声を」
「私の......声?」
「そうだ。ありがとうって。愛してるって。一緒にいてくれて嬉しかったって。そういう言葉を、猫は待ってるんだよ」
男は、ゆっくりと歩き出した。
「待って!」
私は呼び止めた。
でも、男は振り向かなかった。
「もう会うことはないだろう。猫を、大切にな」
男の姿が、夕暮れの中に消えていった。
私は、その場に立ち尽くした。
薬は、手に入らなかった。
でも、何かもっと大切なものを、手に入れた気がした。
言葉なんて、いらない。
レオの気持ちは、もうわかっている。
そして、私の気持ちも、レオに伝えなきゃいけない。
薬に頼らずに。
自分の声で。
私は、走り出した。
家に帰らなきゃ。
レオの側に、戻らなきゃ。
残された時間は、わずかかもしれない。
でも、その時間を、言葉に頼らずに過ごそう。
レオと、ちゃんと向き合おう。
夕焼けの空の下、私は必死で走った。
家に着くと、息を切らしながらドアを開けた。
「レオ!」
リビングに駆け込む。
レオは、ソファの上で丸くなっていた。
私の声に、ゆっくりと目を開けた。
「レオ......ごめん、遅くなった」
私は、レオの隣に座った。
薬の袋を見る。残り1粒。
でも、私はそれを使わなかった。
代わりに、そっとレオの前足を握った。
小さくて、細くて、温かい足。
「レオ、聞いて」
私は、静かに語りかけた。
「もう薬は使わない。言葉で聞くんじゃなくて、ちゃんと感じたいから」
レオは、じっと私を見た。
「レオの気持ち、わかるよ。ちゃんと伝わってる」
私は、レオの頭を優しく撫でた。
柔らかい毛並み。指先に伝わる、小さな温もり。
レオは、ゆっくりと瞬きをした。
1回、2回。
猫のキス。
愛情表現だと、どこかで読んだことがある。
「私も、レオが大好きだよ」
私は微笑んだ。
レオの尻尾が、わずかに動いた。
ほんの少しだけ、左に揺れた。
それだけで、十分だった。
レオは、私の言葉を聞いている。
わかってくれている。
私は、レオの体を優しく撫で続けた。
背中、首、頬。
レオの体は、以前よりずっと痩せていた。
骨が浮き出ている。
でも、まだ温かい。
まだ、生きている。
レオが、小さく喉を鳴らした。
ゴロゴロという音。
か細くて、途切れ途切れだけれど、確かに聞こえた。
「嬉しいの?」
私は聞いた。
レオは、また瞬きをした。
ゆっくりと、優しく。
涙が溢れた。
でも、悲しい涙じゃなかった。
「ありがとう、レオ。私の側にいてくれて」
私は、レオの体を包み込むように抱きしめた。
レオの心臓の音が聞こえる。
小さくて、弱々しいけれど、確かに鼓動している。
トクン、トクン、トクン。
その音に、私は耳を澄ませた。
「レオ、あのね」
私は囁いた。
「レオと過ごした時間、全部宝物だよ。毎日帰ってきて、レオがいてくれるだけで、私は幸せだった」
レオの尻尾が、また少し動いた。
「最初は、レオの毒舌にびっくりしたけど」
私は笑った。
「でも、あれは全部、私のためだったんだよね。わかってるよ」
レオの呼吸が、私の腕に当たる。
温かい吐息。
生きている証。
「レオは、いつも私を見ていてくれた。私が泣いてる時も、笑ってる時も。誰よりも、私のことを知っていてくれた」
レオが、小さく鳴いた。
「ん......」
か細い声。
でも、確かにレオの声だった。
「レオ、痛い? 苦しい?」
私は心配になった。
でも、レオはゆっくりと首を横に振った。
わずかな動きだけれど、はっきりと「違う」と言っていた。
「そっか。よかった」
私は安堵した。
そして、また撫で続けた。
時間が、ゆっくりと流れていく。
外は、もう暗くなっていた。
部屋の明かりを消して、月明かりだけにした。
静寂の中で、私とレオは寄り添っていた。
言葉はいらなかった。
レオの瞬き。
レオの尻尾の動き。
レオの喉のゴロゴロ音。
レオの体温。
レオの呼吸。
その全てが、言葉だった。
「愛してる」という言葉。
「ありがとう」という言葉。
「一緒にいて幸せ」という言葉。
それが、音のない声となって、私の心に響いていた。
「私も、レオのこと、大好きだよ」
私は何度も囁いた。
「一緒にいてくれて、ありがとう」
レオは、私の腕の中で静かに目を閉じた。
その顔は、穏やかだった。
苦しそうでも、悲しそうでもなく。
ただ、安心しているような、優しい表情。
私は、レオを抱きしめたまま、じっと見つめた。
このまま、時間が止まればいいのに。
そう願った。
でも、時間は止まらない。
それでも、この瞬間を、心に刻もう。
レオの温もり。
レオの重み。
レオの存在。
全部、忘れない。
「レオ、愛してるよ」
私は、最後にもう一度囁いた。
レオの尻尾が、ほんの少しだけ動いた。
まるで「俺もだよ」と言っているように。
静寂の中で、私たちの魂は完全に通じ合っていた。
言葉なんて、もう必要なかった。
ただ、この温もりがあれば。
それだけで、十分だった。