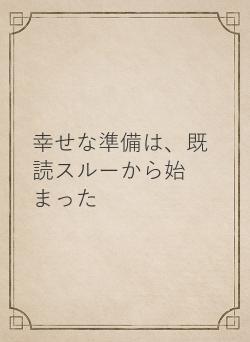それから数日、私とレオの奇妙な共同生活は続いた。薬を使うたびにレオは毒舌を吐き、私はそれに従って少しずつ生活を変えていった。
ある夜のことだった。
いつものように薬を混ぜた餌をレオに与え、効果が現れるのを待っていた。レオが餌を食べ終わり、口を開く。
「おい、独身女。今日は......」
レオの声が、途切れた。
「......レオ?」
私は不安になって、レオに近づいた。レオは立ったまま、じっと固まっている。
そして、また口が動いた。
「......咲......美咲......」
その声は、レオではなかった。
女性の声。どこか聞き覚えのある、懐かしい声。
「え......?」
私の心臓が跳ねた。
レオの口から、別の誰かの声が聞こえている。
「美咲、ごめんね......本当は......」
声はすぐに途切れ、また別の声に変わった。今度は男性の声。
「......弱くて......すまなかった......」
そして、ノイズのような音が混じり、レオの声に戻った。
「おい、何だこれ......俺の口が勝手に......」
レオ自身も混乱しているようだった。
私は震える手で、薬の袋を探した。あの怪しげな薬。何か説明書きのようなものはなかっただろうか。
バッグの中を探る。財布、ハンカチ、鍵。そして、小さな紙切れ。
薬の袋の底に、折り畳まれた紙が入っていた。小さな文字でびっしりと書かれている。
私は震える指で紙を広げた。
『ご使用上の注意:この薬には副作用があります。猫の鋭敏な聴覚と記憶が、飼い主の周囲の残留思念を再生することがあります。猫は人間が思っている以上に、多くのことを聞き、覚えています。特に、強い感情を伴った言葉や想いは、猫の記憶に深く刻まれます。驚かれるかもしれませんが、これも薬の効果の一部です。どうぞ、大切にお使いください』
残留思念。
強い感情を伴った言葉。
私の周囲の、誰かの想い。
レオは、それを全部聞いていた。そして、記憶していた。
「レオ......」
私はレオを見た。レオは戸惑ったように私を見返した。
「おい、今のは何だ。俺が喋ったのか? でも、俺じゃねえ声だった......」
「多分、レオが覚えてる、誰かの声なんだと思う」
私は震える声で答えた。
あの女性の声は、誰だったのだろう。
あの男性の声は。
そして、彼らは私に何を伝えようとしているのだろう。
レオの中に、私の知らない誰かの想いが眠っている。
薬は、ただレオの言葉を翻訳するだけじゃなかった。レオの記憶に刻まれた、過去の声まで呼び起こしてしまう。
私は、その事実に震えた。
翌日の夜、私は恐る恐る5粒目の薬をレオに与えた。また、あの声が聞こえるのだろうか。
レオが餌を食べ終わる。私は息を呑んで待った。
「おい、独身女。今日は......」
レオの声が、また途切れた。
そして、変わった。
「美咲」
女性の声。今度ははっきりと聞こえた。
「......ゆ、由香里?」
私は思わず声を上げた。
その声は、間違いなく親友だった由香里の声だった。大学時代、いつも一緒にいた親友。でも、3年前に喧嘩別れして以来、連絡を取っていない。
「美咲、ごめんね」
レオの口から、由香里の声が続いた。
「あの時、ひどいこと言っちゃって。あんたの夢、馬鹿にするようなこと言って」
私の胸が痛んだ。
あの日のことを、思い出す。
私が「小説家になりたい」と話した時、由香里は笑った。「現実見なよ」と。
私は傷ついて、怒って、「もう会いたくない」と言ってしまった。
「でもね、本当は違うの」
由香里の声は、震えていた。
「私、美咲のこと、すごいって思ってた。いつも夢に向かって頑張ってて、文章も上手で、キラキラしてて。羨ましかった。憧れてた」
「由香里......」
「でも、私は何もなかった。就活もうまくいかなくて、焦ってて。美咲が輝いてるのを見るのが、辛くなっちゃったの。だから、あんな言い方しちゃった」
レオの体が、小刻みに震えている。まるで、由香里の感情がレオを通して溢れ出しているようだった。
「本当は、応援したかった。美咲の小説、一番最初に読みたかった。でも、素直になれなくて。ごめんね、美咲。本当に、ごめん」
声が途切れた。
レオは、ゆっくりと私を見上げた。いつものレオの目に戻っている。
「......おい、今のは......」
「由香里だった。私の、親友だった人」
私は涙を拭った。いつの間にか、泣いていた。
由香里は、私を嫌いになったんじゃなかった。
嫉妬でも、軽蔑でもなく、ただ自分の弱さに押し潰されそうになっていただけだった。
そして、私はそれに気づけなかった。
私は立ち上がって、スマートフォンを手に取った。
由香里の連絡先は、まだ残っている。3年間、一度も開いていない連絡先。
指が震える。
でも、かけなきゃいけない。
今、かけなきゃ。
私は、通話ボタンを押した。
コール音が響く。1回、2回、3回。
そして、繋がった。
「......もしもし?」
由香里の声。レオの口から聞こえた声と同じ、懐かしい声。
「由香里、私」
「美咲......? 美咲なの?」
驚きと、戸惑いと、そして少しの喜びが混じった声。
「ごめん、突然電話して。でも、話したくて」
「私も......私も、ずっと話したかった」
由香里の声が震えた。
「あの時のこと、ずっと後悔してた。謝りたかった。でも、勇気が出なくて......」
「私もごめん。由香里の気持ち、わかってあげられなくて」
二人とも、泣いていた。
電話越しに聞こえる、由香里のすすり泣く声。
「美咲、小説、書いてる?」
「......少しだけ。でも、なかなか進まなくて」
「書いてよ。絶対に。私、美咲の小説、読みたいから」
「うん。頑張る」
私は笑った。涙で顔がぐちゃぐちゃなのに、笑えた。
「今度、会える?」
「会いたい。すごく会いたい」
「じゃあ、来週の土曜日は?」
「いいよ。絶対行く」
電話を切った後も、私の手は震えていた。
でも、それは恐怖や悲しみの震えじゃなかった。
喜びで、震えていた。
レオは、私の足元で丸くなっていた。私はレオを抱き上げて、ぎゅっと抱きしめた。
「ありがとう、レオ。ありがとう」
レオは少し迷惑そうに鳴いたけれど、逃げようとはしなかった。
私の腕の中で、温かい体温を感じながら、静かに目を閉じていた。
失ったと思っていた友情が、レオを通して戻ってきた。
レオは、ずっとあの日の由香里の言葉を、覚えていてくれたのだ。私に届けるために。
それから数日後。
由香里と再会した帰り道、私は軽い足取りで家に帰った。久しぶりに笑い合って、思い出話をして、心が満たされていた。
家に着くと、レオは窓辺で外を眺めていた。夕暮れの光が、レオの黒い毛並みを照らしている。
「ただいま、レオ」
レオは振り向いて、小さく鳴いた。
私は6粒目の薬を取り出した。まだ、誰かの声が聞こえるのだろうか。
いつものように餌に混ぜて、レオに与える。
レオが食べ終わると、また口が開いた。
「おい、独身女。今日は機嫌がいいな」
レオの声。いつもの毒舌。
「うん。由香里と会ってきたの。すごく楽しかった」
「そうか。よかったじゃねえか」
レオは素っ気なく答えた。でも、その目は優しかった。
そして、また声が変わった。
今度は、男性の声。
低く、少しだけ震えた声。
私の心臓が、止まりそうになった。
「......美咲」
知っている。この声を知っている。
「拓也......」
元カレの名前が、自然に口から出た。
1年前に別れた彼。最後に会った時、彼は言った。「お前、重いんだよ」と。
その言葉が、ずっと私を縛っていた。
私は重い。愛情が重い。だから、嫌われるのだと。
「美咲、ごめん」
拓也の声は、苦しそうだった。
「あの時、ひどいこと言った。『重い』なんて。あれは、嘘だ」
「......嘘?」
「お前は重くなんかなかった。むしろ、お前の愛情が、眩しすぎたんだ」
レオの体が、また震え始めた。拓也の感情が、波のように押し寄せてくる。
「お前は、いつも俺のことを考えてくれた。誕生日も、記念日も、全部覚えてて。俺が疲れてる時は、そっと寄り添ってくれて。手作りの弁当を作ってくれて」
拓也の声が、途切れそうになる。
「でも、俺は応えられなかった。お前の優しさに、愛情に、何一つ応えられなかった。仕事が忙しいって言い訳して、お前を放っておいて。デートもドタキャンして」
私は、胸が苦しくなった。
そうだった。拓也は、いつも忙しかった。私は、いつも待っていた。
「お前が笑顔で『いいよ、仕事頑張ってね』って言うたびに、俺は自分が情けなくなった。こんな俺のために、お前は時間を使ってくれているのに」
「拓也......」
「俺は、お前に釣り合わない人間だった。だから、逃げたんだ。『重い』なんて言葉で、お前を傷つけて、逃げた」
拓也の声が、震えた。
「本当は、お前が大好きだった。お前の笑顔も、優しさも、全部。でも、そんなお前を幸せにできない自分が、許せなかった」
涙が溢れた。
拓也は、私を嫌いになったんじゃなかった。
私が重かったんじゃなかった。
ただ、彼は自分を責めていただけだった。
「ごめん、美咲。お前を傷つけて、ごめん。お前は、誰かにとって大切な人になれる。俺じゃない、もっといい奴に、愛される資格がある」
声が途切れた。
レオは、ゆっくりと目を開けた。いつものレオに戻っている。
「......泣いてんのか」
レオの呆れた声。
「うん......泣いてる」
私は涙を拭った。でも、止まらなかった。
「バカだな。過去の男のことで泣くなよ」
「違うの。これは、悲しい涙じゃない」
私は笑った。
「楽になったの。ずっと、自分が悪いんだと思ってた。私が重いから、嫌われたんだって。でも、違ったんだね」
拓也は、私を愛してくれていた。
ただ、それに応えられない自分を責めて、逃げただけだった。
私は、悪くなかった。
私の愛情は、重くなんかなかった。
「レオ、ありがとう」
私は、またレオを抱きしめた。
レオは相変わらず迷惑そうだったけれど、でも私の腕の中で、静かに喉を鳴らした。
過去の恋愛の呪縛が、解けていく。
拓也の言葉は、私を縛るものじゃなかった。
彼の弱さが、私を傷つけただけだった。
そして今、レオを通して、彼の本当の気持ちを知ることができた。
私は、もう自由だった。
次に誰かを愛する時、私は怖がらなくていい。
私の愛情を、恥じなくていい。
窓の外では、夕暮れが深い夜に変わろうとしていた。
レオの温もりが、私の心を静かに満たしていく。
「レオ、あと何人の声が、聞こえるんだろうね」
私は呟いた。
レオは答えなかった。
ただ、私の腕の中で、目を細めていた。
その答えは、すぐに訪れた。
翌々日の夜、私は7粒目の薬をレオに与えた。残りは、あと3粒。
レオが餌を食べ終わる。そして、口を開く。
「おい、独身女......」
また、声が変わった。
今度は、年老いた女性の声。
穏やかで、優しくて、懐かしい声。
「......おばあちゃん?」
私の声が震えた。
祖母は、5年前に亡くなった。私が23歳の時。最期は病院のベッドの上で、静かに眠るように逝った。
「美咲」
祖母の声が、レオの口から響いた。
「元気にしてるかい」
涙が溢れた。
会いたかった。もう一度、声が聞きたかった。
「おばあちゃん......」
「美咲、あんたに謝らなきゃいけないことがあるんだよ」
祖母の声は、申し訳なさそうだった。
「謝る? 何を?」
「あの時のこと。あんたが小学生の時、覚えてるかい」
小学生の時。
私の胸に、古い記憶が蘇った。
嫌な記憶。ずっと忘れたかった記憶。
「財布のこと......?」
「そう。私の財布から、お金を取ったこと」
私は息を呑んだ。
あれは、小学校5年生の時だった。
友達が持っている可愛い文房具が欲しくて、でもお小遣いでは買えなくて。
魔が差して、祖母の財布から千円札を抜き取った。
祖母は、何も言わなかった。気づいていないのだと思った。
でも、あの後、私はその千円で何も買えなかった。罪悪感で、胸が苦しくて。
結局、その千円は使わずに、こっそり財布に戻した。
「おばあちゃんは、気づいてなかったと思ってた......」
「気づいてたよ」
祖母の声は、静かだった。
「あんたが財布を開けた時も、お金を取った時も、全部見てた」
「......」
「でもね、何も言わなかった。言えなかった」
レオの体が震えている。祖母の感情が、波のように伝わってくる。
「あんたは、すぐに後悔してたから。顔を見ればわかった。泣きそうな顔して、ずっと下を向いてた」
そうだった。
あの日から数日間、私は祖母の顔をまともに見られなかった。
「もし私が『盗ったでしょ』って言ったら、あんたはどれだけ傷つくか。もう十分反省してるあんたを、さらに傷つけることになる」
祖母の声が、優しく続く。
「だから、黙ってた。お金が戻ってきた時も、何も言わなかった。あんたが自分で間違いに気づいて、自分で正せたこと。それが何より嬉しかった」
涙が止まらなかった。
「でもね、美咲。一つだけ、後悔してることがある」
「何......?」
「あの時、あんたを抱きしめてあげればよかった。『大丈夫だよ』って、言ってあげればよかった」
祖母の声が震えた。
「人間は誰だって間違える。大事なのは、それに気づいて正せること。あんたは、ちゃんとそれができた。偉かったよ、美咲」
「おばあちゃん......」
「あんたはいい子だ。昔も、今も。だから、自分を責めすぎちゃダメだよ」
声が途切れた。
レオは、じっと私を見上げた。
私は、もう我慢できなかった。
レオを抱きしめて、声を上げて泣いた。
子供みたいに、わんわんと泣いた。
ずっと、ずっと謝りたかった。
おばあちゃん、ごめんなさい。悪いことをしてごめんなさい。
でも、祖母は知っていた。
全部知っていて、それでも黙って許してくれていた。
傷つけないように。愛してくれていたから。
「おばあちゃん......ありがとう......ごめんなさい......」
私は泣きながら、何度も何度も呟いた。
レオは、文句を言わなかった。
いつもなら「うるせえ」とか「離せよ」とか言うのに、今日は何も言わない。
ただ、私の腕の中で、静かに背中を預けていた。
温かかった。
レオの体温が、祖母の温もりのように感じられた。
私は、愛されていた。
祖母に。由香里に。拓也にも。
みんな、不器用で、うまく伝えられなかっただけで、私を愛してくれていた。
そして今、レオがそれを教えてくれた。
私は孤独じゃなかった。
ずっと、誰かに見守られていた。
「ありがとう、レオ」
私は涙で濡れた顔のまま、レオに囁いた。
「あんたがいてくれて、本当によかった」
レオは、小さく鳴いた。
そして、ゆっくりと目を閉じた。
その横顔は、まるで微笑んでいるようだった。
ある夜のことだった。
いつものように薬を混ぜた餌をレオに与え、効果が現れるのを待っていた。レオが餌を食べ終わり、口を開く。
「おい、独身女。今日は......」
レオの声が、途切れた。
「......レオ?」
私は不安になって、レオに近づいた。レオは立ったまま、じっと固まっている。
そして、また口が動いた。
「......咲......美咲......」
その声は、レオではなかった。
女性の声。どこか聞き覚えのある、懐かしい声。
「え......?」
私の心臓が跳ねた。
レオの口から、別の誰かの声が聞こえている。
「美咲、ごめんね......本当は......」
声はすぐに途切れ、また別の声に変わった。今度は男性の声。
「......弱くて......すまなかった......」
そして、ノイズのような音が混じり、レオの声に戻った。
「おい、何だこれ......俺の口が勝手に......」
レオ自身も混乱しているようだった。
私は震える手で、薬の袋を探した。あの怪しげな薬。何か説明書きのようなものはなかっただろうか。
バッグの中を探る。財布、ハンカチ、鍵。そして、小さな紙切れ。
薬の袋の底に、折り畳まれた紙が入っていた。小さな文字でびっしりと書かれている。
私は震える指で紙を広げた。
『ご使用上の注意:この薬には副作用があります。猫の鋭敏な聴覚と記憶が、飼い主の周囲の残留思念を再生することがあります。猫は人間が思っている以上に、多くのことを聞き、覚えています。特に、強い感情を伴った言葉や想いは、猫の記憶に深く刻まれます。驚かれるかもしれませんが、これも薬の効果の一部です。どうぞ、大切にお使いください』
残留思念。
強い感情を伴った言葉。
私の周囲の、誰かの想い。
レオは、それを全部聞いていた。そして、記憶していた。
「レオ......」
私はレオを見た。レオは戸惑ったように私を見返した。
「おい、今のは何だ。俺が喋ったのか? でも、俺じゃねえ声だった......」
「多分、レオが覚えてる、誰かの声なんだと思う」
私は震える声で答えた。
あの女性の声は、誰だったのだろう。
あの男性の声は。
そして、彼らは私に何を伝えようとしているのだろう。
レオの中に、私の知らない誰かの想いが眠っている。
薬は、ただレオの言葉を翻訳するだけじゃなかった。レオの記憶に刻まれた、過去の声まで呼び起こしてしまう。
私は、その事実に震えた。
翌日の夜、私は恐る恐る5粒目の薬をレオに与えた。また、あの声が聞こえるのだろうか。
レオが餌を食べ終わる。私は息を呑んで待った。
「おい、独身女。今日は......」
レオの声が、また途切れた。
そして、変わった。
「美咲」
女性の声。今度ははっきりと聞こえた。
「......ゆ、由香里?」
私は思わず声を上げた。
その声は、間違いなく親友だった由香里の声だった。大学時代、いつも一緒にいた親友。でも、3年前に喧嘩別れして以来、連絡を取っていない。
「美咲、ごめんね」
レオの口から、由香里の声が続いた。
「あの時、ひどいこと言っちゃって。あんたの夢、馬鹿にするようなこと言って」
私の胸が痛んだ。
あの日のことを、思い出す。
私が「小説家になりたい」と話した時、由香里は笑った。「現実見なよ」と。
私は傷ついて、怒って、「もう会いたくない」と言ってしまった。
「でもね、本当は違うの」
由香里の声は、震えていた。
「私、美咲のこと、すごいって思ってた。いつも夢に向かって頑張ってて、文章も上手で、キラキラしてて。羨ましかった。憧れてた」
「由香里......」
「でも、私は何もなかった。就活もうまくいかなくて、焦ってて。美咲が輝いてるのを見るのが、辛くなっちゃったの。だから、あんな言い方しちゃった」
レオの体が、小刻みに震えている。まるで、由香里の感情がレオを通して溢れ出しているようだった。
「本当は、応援したかった。美咲の小説、一番最初に読みたかった。でも、素直になれなくて。ごめんね、美咲。本当に、ごめん」
声が途切れた。
レオは、ゆっくりと私を見上げた。いつものレオの目に戻っている。
「......おい、今のは......」
「由香里だった。私の、親友だった人」
私は涙を拭った。いつの間にか、泣いていた。
由香里は、私を嫌いになったんじゃなかった。
嫉妬でも、軽蔑でもなく、ただ自分の弱さに押し潰されそうになっていただけだった。
そして、私はそれに気づけなかった。
私は立ち上がって、スマートフォンを手に取った。
由香里の連絡先は、まだ残っている。3年間、一度も開いていない連絡先。
指が震える。
でも、かけなきゃいけない。
今、かけなきゃ。
私は、通話ボタンを押した。
コール音が響く。1回、2回、3回。
そして、繋がった。
「......もしもし?」
由香里の声。レオの口から聞こえた声と同じ、懐かしい声。
「由香里、私」
「美咲......? 美咲なの?」
驚きと、戸惑いと、そして少しの喜びが混じった声。
「ごめん、突然電話して。でも、話したくて」
「私も......私も、ずっと話したかった」
由香里の声が震えた。
「あの時のこと、ずっと後悔してた。謝りたかった。でも、勇気が出なくて......」
「私もごめん。由香里の気持ち、わかってあげられなくて」
二人とも、泣いていた。
電話越しに聞こえる、由香里のすすり泣く声。
「美咲、小説、書いてる?」
「......少しだけ。でも、なかなか進まなくて」
「書いてよ。絶対に。私、美咲の小説、読みたいから」
「うん。頑張る」
私は笑った。涙で顔がぐちゃぐちゃなのに、笑えた。
「今度、会える?」
「会いたい。すごく会いたい」
「じゃあ、来週の土曜日は?」
「いいよ。絶対行く」
電話を切った後も、私の手は震えていた。
でも、それは恐怖や悲しみの震えじゃなかった。
喜びで、震えていた。
レオは、私の足元で丸くなっていた。私はレオを抱き上げて、ぎゅっと抱きしめた。
「ありがとう、レオ。ありがとう」
レオは少し迷惑そうに鳴いたけれど、逃げようとはしなかった。
私の腕の中で、温かい体温を感じながら、静かに目を閉じていた。
失ったと思っていた友情が、レオを通して戻ってきた。
レオは、ずっとあの日の由香里の言葉を、覚えていてくれたのだ。私に届けるために。
それから数日後。
由香里と再会した帰り道、私は軽い足取りで家に帰った。久しぶりに笑い合って、思い出話をして、心が満たされていた。
家に着くと、レオは窓辺で外を眺めていた。夕暮れの光が、レオの黒い毛並みを照らしている。
「ただいま、レオ」
レオは振り向いて、小さく鳴いた。
私は6粒目の薬を取り出した。まだ、誰かの声が聞こえるのだろうか。
いつものように餌に混ぜて、レオに与える。
レオが食べ終わると、また口が開いた。
「おい、独身女。今日は機嫌がいいな」
レオの声。いつもの毒舌。
「うん。由香里と会ってきたの。すごく楽しかった」
「そうか。よかったじゃねえか」
レオは素っ気なく答えた。でも、その目は優しかった。
そして、また声が変わった。
今度は、男性の声。
低く、少しだけ震えた声。
私の心臓が、止まりそうになった。
「......美咲」
知っている。この声を知っている。
「拓也......」
元カレの名前が、自然に口から出た。
1年前に別れた彼。最後に会った時、彼は言った。「お前、重いんだよ」と。
その言葉が、ずっと私を縛っていた。
私は重い。愛情が重い。だから、嫌われるのだと。
「美咲、ごめん」
拓也の声は、苦しそうだった。
「あの時、ひどいこと言った。『重い』なんて。あれは、嘘だ」
「......嘘?」
「お前は重くなんかなかった。むしろ、お前の愛情が、眩しすぎたんだ」
レオの体が、また震え始めた。拓也の感情が、波のように押し寄せてくる。
「お前は、いつも俺のことを考えてくれた。誕生日も、記念日も、全部覚えてて。俺が疲れてる時は、そっと寄り添ってくれて。手作りの弁当を作ってくれて」
拓也の声が、途切れそうになる。
「でも、俺は応えられなかった。お前の優しさに、愛情に、何一つ応えられなかった。仕事が忙しいって言い訳して、お前を放っておいて。デートもドタキャンして」
私は、胸が苦しくなった。
そうだった。拓也は、いつも忙しかった。私は、いつも待っていた。
「お前が笑顔で『いいよ、仕事頑張ってね』って言うたびに、俺は自分が情けなくなった。こんな俺のために、お前は時間を使ってくれているのに」
「拓也......」
「俺は、お前に釣り合わない人間だった。だから、逃げたんだ。『重い』なんて言葉で、お前を傷つけて、逃げた」
拓也の声が、震えた。
「本当は、お前が大好きだった。お前の笑顔も、優しさも、全部。でも、そんなお前を幸せにできない自分が、許せなかった」
涙が溢れた。
拓也は、私を嫌いになったんじゃなかった。
私が重かったんじゃなかった。
ただ、彼は自分を責めていただけだった。
「ごめん、美咲。お前を傷つけて、ごめん。お前は、誰かにとって大切な人になれる。俺じゃない、もっといい奴に、愛される資格がある」
声が途切れた。
レオは、ゆっくりと目を開けた。いつものレオに戻っている。
「......泣いてんのか」
レオの呆れた声。
「うん......泣いてる」
私は涙を拭った。でも、止まらなかった。
「バカだな。過去の男のことで泣くなよ」
「違うの。これは、悲しい涙じゃない」
私は笑った。
「楽になったの。ずっと、自分が悪いんだと思ってた。私が重いから、嫌われたんだって。でも、違ったんだね」
拓也は、私を愛してくれていた。
ただ、それに応えられない自分を責めて、逃げただけだった。
私は、悪くなかった。
私の愛情は、重くなんかなかった。
「レオ、ありがとう」
私は、またレオを抱きしめた。
レオは相変わらず迷惑そうだったけれど、でも私の腕の中で、静かに喉を鳴らした。
過去の恋愛の呪縛が、解けていく。
拓也の言葉は、私を縛るものじゃなかった。
彼の弱さが、私を傷つけただけだった。
そして今、レオを通して、彼の本当の気持ちを知ることができた。
私は、もう自由だった。
次に誰かを愛する時、私は怖がらなくていい。
私の愛情を、恥じなくていい。
窓の外では、夕暮れが深い夜に変わろうとしていた。
レオの温もりが、私の心を静かに満たしていく。
「レオ、あと何人の声が、聞こえるんだろうね」
私は呟いた。
レオは答えなかった。
ただ、私の腕の中で、目を細めていた。
その答えは、すぐに訪れた。
翌々日の夜、私は7粒目の薬をレオに与えた。残りは、あと3粒。
レオが餌を食べ終わる。そして、口を開く。
「おい、独身女......」
また、声が変わった。
今度は、年老いた女性の声。
穏やかで、優しくて、懐かしい声。
「......おばあちゃん?」
私の声が震えた。
祖母は、5年前に亡くなった。私が23歳の時。最期は病院のベッドの上で、静かに眠るように逝った。
「美咲」
祖母の声が、レオの口から響いた。
「元気にしてるかい」
涙が溢れた。
会いたかった。もう一度、声が聞きたかった。
「おばあちゃん......」
「美咲、あんたに謝らなきゃいけないことがあるんだよ」
祖母の声は、申し訳なさそうだった。
「謝る? 何を?」
「あの時のこと。あんたが小学生の時、覚えてるかい」
小学生の時。
私の胸に、古い記憶が蘇った。
嫌な記憶。ずっと忘れたかった記憶。
「財布のこと......?」
「そう。私の財布から、お金を取ったこと」
私は息を呑んだ。
あれは、小学校5年生の時だった。
友達が持っている可愛い文房具が欲しくて、でもお小遣いでは買えなくて。
魔が差して、祖母の財布から千円札を抜き取った。
祖母は、何も言わなかった。気づいていないのだと思った。
でも、あの後、私はその千円で何も買えなかった。罪悪感で、胸が苦しくて。
結局、その千円は使わずに、こっそり財布に戻した。
「おばあちゃんは、気づいてなかったと思ってた......」
「気づいてたよ」
祖母の声は、静かだった。
「あんたが財布を開けた時も、お金を取った時も、全部見てた」
「......」
「でもね、何も言わなかった。言えなかった」
レオの体が震えている。祖母の感情が、波のように伝わってくる。
「あんたは、すぐに後悔してたから。顔を見ればわかった。泣きそうな顔して、ずっと下を向いてた」
そうだった。
あの日から数日間、私は祖母の顔をまともに見られなかった。
「もし私が『盗ったでしょ』って言ったら、あんたはどれだけ傷つくか。もう十分反省してるあんたを、さらに傷つけることになる」
祖母の声が、優しく続く。
「だから、黙ってた。お金が戻ってきた時も、何も言わなかった。あんたが自分で間違いに気づいて、自分で正せたこと。それが何より嬉しかった」
涙が止まらなかった。
「でもね、美咲。一つだけ、後悔してることがある」
「何......?」
「あの時、あんたを抱きしめてあげればよかった。『大丈夫だよ』って、言ってあげればよかった」
祖母の声が震えた。
「人間は誰だって間違える。大事なのは、それに気づいて正せること。あんたは、ちゃんとそれができた。偉かったよ、美咲」
「おばあちゃん......」
「あんたはいい子だ。昔も、今も。だから、自分を責めすぎちゃダメだよ」
声が途切れた。
レオは、じっと私を見上げた。
私は、もう我慢できなかった。
レオを抱きしめて、声を上げて泣いた。
子供みたいに、わんわんと泣いた。
ずっと、ずっと謝りたかった。
おばあちゃん、ごめんなさい。悪いことをしてごめんなさい。
でも、祖母は知っていた。
全部知っていて、それでも黙って許してくれていた。
傷つけないように。愛してくれていたから。
「おばあちゃん......ありがとう......ごめんなさい......」
私は泣きながら、何度も何度も呟いた。
レオは、文句を言わなかった。
いつもなら「うるせえ」とか「離せよ」とか言うのに、今日は何も言わない。
ただ、私の腕の中で、静かに背中を預けていた。
温かかった。
レオの体温が、祖母の温もりのように感じられた。
私は、愛されていた。
祖母に。由香里に。拓也にも。
みんな、不器用で、うまく伝えられなかっただけで、私を愛してくれていた。
そして今、レオがそれを教えてくれた。
私は孤独じゃなかった。
ずっと、誰かに見守られていた。
「ありがとう、レオ」
私は涙で濡れた顔のまま、レオに囁いた。
「あんたがいてくれて、本当によかった」
レオは、小さく鳴いた。
そして、ゆっくりと目を閉じた。
その横顔は、まるで微笑んでいるようだった。