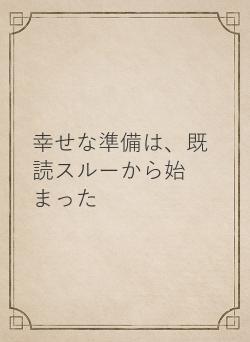翌朝、私は怒りで目が覚めた。
あの胡散臭い男を探し出して、返品してやる。いや、詐欺で訴えてやる。
私は公園に向かった。昨日男がいた場所、ベンチの近く、木の陰、あらゆる場所を探し回った。でも、男の姿はどこにもなかった。
当然だ。詐欺師が同じ場所にいるわけがない。
私は力なくベンチに座り込んだ。手の中には、残り9粒の薬が入った袋。これを捨てるべきか、それとも......。
9,800円。決して安くはない金額だ。給料日まであと2週間もあるのに、財布の中身はもう心許ない。
捨てるのは、あまりにももったいない。
私は袋を握りしめた。使うしかない。この貧乏性が、私の運命を決めた。
仕事から帰ると、レオはいつも通りソファで寝ていた。私は深いため息をつきながら、夕食の準備をした。そして、2粒目の薬を餌に混ぜた。
どうせ悪態しか聞けないのだ。それなら、せめて何か役に立つことを言わせてやろう。
レオが餌を食べ終わると、またあの声が響いた。
「おい、独身女」
「何よ」
私は投げやりに答えた。
「明日も仕事だろ? その格好で行くのか?」
レオは、ソファの背もたれに置いてあった私の通勤用のブラウスを見た。
「これの何が悪いのよ」
「地味すぎんだよ。お前、職場で空気だろ。そういう『私は目立ちたくありません』って服着てるから、誰にも相手にされねえんだ」
「うるさいわね。別に目立ちたくないし」
「嘘つけ。本当は認められたいくせに。でも怖いから、最初から期待されない格好して逃げてんだろ」
ぐさりと刺さった。
レオは容赦なく続けた。
「あとな、お前の歩き方。猫背でトボトボ歩きやがって。あれじゃ『私は自信がありません』って宣伝してるようなもんだ。背筋伸ばせ。胸張れ。お前、人間だろ? もっと堂々としろよ」
「......」
悔しかった。悔しくて、腹が立って、でも言い返せなかった。
なぜなら、全部図星だったから。
翌朝、私はクローゼットの奥から、ずっと着ていなかった明るい色のブラウスを引っ張り出した。少し派手かもしれない。でも、レオの言葉が頭から離れなかった。
鏡の前で何度も着替えて、結局そのブラウスを着ることにした。
玄関を出る時、意識して背筋を伸ばした。胸を張る。視線を上げる。
最初は不自然で、体がこわばった。でも、歩いているうちに、少しずつ慣れてきた。
駅のホームで、隣にいたサラリーマンが私に道を譲った。いつもなら、私が避ける側だったのに。
会社に着くと、受付の女性が「おはようございます」と笑顔で挨拶してくれた。いつも無言で通り過ぎていたのに、今日は違った。
「おはようございます」
私も笑顔で返した。
デスクに着くと、隣の席の同僚が言った。
「あれ、雰囲気変わった? なんか明るくなったね」
「そう......ですか?」
「うん。その服、似合ってるよ」
心臓が跳ねた。褒められた。久しぶりに、誰かに褒められた。
午後、プレゼンの機会があった。いつもなら資料を読み上げるだけで精一杯だったけれど、今日は違った。背筋を伸ばして、はっきりと声を出した。
「以上が、私の提案です」
会議室に、短い沈黙が流れた。
そして、上司の小林さんが頷いた。
「いいね。前向きに検討しよう」
信じられなかった。あの小林さんが、私の提案を認めてくれた。
帰り道、私はコンビニで一番高い缶詰を買った。レオへの、小さなお礼のつもりだった。
家に帰ると、レオは相変わらずソファで寝ていた。私は缶詰を開けて、3粒目の薬を混ぜた。
レオが食べ終わると、いつもの声が響いた。
「おう、今日はマシな缶詰じゃねえか」
「......ありがとう、レオ」
私は素直に言った。
「は? 何言ってんだ、急に」
「今日、すごく良い日だったの。レオのアドバイス、役に立ったわ」
レオは少しバツが悪そうに目を逸らした。
「フン。当然だろ。お前のこと、毎日見てんだからな。誰よりもお前のダメなとこ、知ってんだよ」
その言葉が、不思議と温かかった。
毒舌だけれど、それは無関心とは正反対だった。レオは、ずっと私を見ていてくれた。
その夜、私は珍しく冷蔵庫からビールを取り出した。普段は節約のために買わないけれど、今日は特別な日だ。自分へのささやかなご褒美。
缶を開けて、グラスに注ぐ。金色の液体が泡立つ音が、妙に心地よい。
「レオ、ちょっと待ってて」
私はキッチンの棚から、ずっと取っておいた高級ちゅ~るんを取り出した。普通のちゅ~るんの3倍くらいする、国産まぐろ使用の特別なやつ。
「今日は、お祝いしよう」
レオは不思議そうに私を見上げた。私は高級ちゅ~るんをレオの前に置き、自分はグラスを持った。
「乾杯」
私はグラスを掲げた。レオは首を傾げたあと、ちゅ~るんに舌を伸ばした。
ビールを一口飲む。喉を通る冷たさと、ほのかな苦み。疲れた体に染み渡っていく。
「はあ......美味しい」
私は思わずため息をついた。レオは高級ちゅ~るんに夢中で、ペロペロと音を立てている。その姿が可愛くて、思わず笑みがこぼれた。
4粒目の薬の効果が切れるまで、あと30分くらいだろうか。私は聞いてみたかったことを口にした。
「ねえ、レオ」
「あ?」
レオは顔を上げた。口の周りにちゅ~るんがついている。
「なんでそんなに、私のことを見てるの?」
レオは一瞬、動きを止めた。そして、またちゅ~るんに顔を戻した。
「暇だからな」
そっけない返事。
「お前くらいしか見るもんがねえんだよ。この狭い部屋で、一日中何もすることねえし」
「それだけ?」
「それだけだ」
レオは相変わらずぶっきらぼうに答えた。でも、その横顔を見ていると、何か違うものが見えた気がした。
暇つぶし、と言いながら、私の服装まで覚えている。いつ洗濯したか、いつ掃除したか、全部知っている。元カレのことも、仕事の悩みも、私が口に出したことを全部覚えている。
それは、本当にただの暇つぶしだろうか。
「レオは、優しいんだね」
私は小さく呟いた。
「はあ? 何言ってんだ。俺が優しい? 頭おかしくなったか」
レオは明らかに動揺していた。耳がピクピクと動いている。
「優しくなんかねえよ。ただ、お前があまりにもダメダメだから、見てらんねえだけだ」
「うん、そうだね」
私は笑った。
「でも、それって優しさだと思う」
「......ったく、酔っ払いの相手は疲れんな」
レオはそう言って、また高級ちゅ~るんに顔を戻した。でも、その尻尾は、ゆっくりと左右に揺れていた。機嫌が良い時の、あの動き。
私はビールをもう一口飲んだ。
部屋の中には、私とレオだけ。静かで、少し散らかっていて、決して広くはない空間。
でも今、この瞬間は、悪くないと思った。
いや、悪くないどころか、温かかった。
レオの存在が、この部屋を、そして私の生活を、少しだけ温かくしてくれている。
家族、という言葉が頭に浮かんだ。
レオは私の家族なのかもしれない。血は繋がっていないし、言葉も通じなかった。でも今、こうして悪態をつきながらも、私のことを見守ってくれている。
「ありがとね、レオ」
私はもう一度言った。
「だから何に対してだよ」
「全部」
レオは呆れたように鼻を鳴らした。
「変な女」
でも、その声は、少しだけ優しかった気がした。
あの胡散臭い男を探し出して、返品してやる。いや、詐欺で訴えてやる。
私は公園に向かった。昨日男がいた場所、ベンチの近く、木の陰、あらゆる場所を探し回った。でも、男の姿はどこにもなかった。
当然だ。詐欺師が同じ場所にいるわけがない。
私は力なくベンチに座り込んだ。手の中には、残り9粒の薬が入った袋。これを捨てるべきか、それとも......。
9,800円。決して安くはない金額だ。給料日まであと2週間もあるのに、財布の中身はもう心許ない。
捨てるのは、あまりにももったいない。
私は袋を握りしめた。使うしかない。この貧乏性が、私の運命を決めた。
仕事から帰ると、レオはいつも通りソファで寝ていた。私は深いため息をつきながら、夕食の準備をした。そして、2粒目の薬を餌に混ぜた。
どうせ悪態しか聞けないのだ。それなら、せめて何か役に立つことを言わせてやろう。
レオが餌を食べ終わると、またあの声が響いた。
「おい、独身女」
「何よ」
私は投げやりに答えた。
「明日も仕事だろ? その格好で行くのか?」
レオは、ソファの背もたれに置いてあった私の通勤用のブラウスを見た。
「これの何が悪いのよ」
「地味すぎんだよ。お前、職場で空気だろ。そういう『私は目立ちたくありません』って服着てるから、誰にも相手にされねえんだ」
「うるさいわね。別に目立ちたくないし」
「嘘つけ。本当は認められたいくせに。でも怖いから、最初から期待されない格好して逃げてんだろ」
ぐさりと刺さった。
レオは容赦なく続けた。
「あとな、お前の歩き方。猫背でトボトボ歩きやがって。あれじゃ『私は自信がありません』って宣伝してるようなもんだ。背筋伸ばせ。胸張れ。お前、人間だろ? もっと堂々としろよ」
「......」
悔しかった。悔しくて、腹が立って、でも言い返せなかった。
なぜなら、全部図星だったから。
翌朝、私はクローゼットの奥から、ずっと着ていなかった明るい色のブラウスを引っ張り出した。少し派手かもしれない。でも、レオの言葉が頭から離れなかった。
鏡の前で何度も着替えて、結局そのブラウスを着ることにした。
玄関を出る時、意識して背筋を伸ばした。胸を張る。視線を上げる。
最初は不自然で、体がこわばった。でも、歩いているうちに、少しずつ慣れてきた。
駅のホームで、隣にいたサラリーマンが私に道を譲った。いつもなら、私が避ける側だったのに。
会社に着くと、受付の女性が「おはようございます」と笑顔で挨拶してくれた。いつも無言で通り過ぎていたのに、今日は違った。
「おはようございます」
私も笑顔で返した。
デスクに着くと、隣の席の同僚が言った。
「あれ、雰囲気変わった? なんか明るくなったね」
「そう......ですか?」
「うん。その服、似合ってるよ」
心臓が跳ねた。褒められた。久しぶりに、誰かに褒められた。
午後、プレゼンの機会があった。いつもなら資料を読み上げるだけで精一杯だったけれど、今日は違った。背筋を伸ばして、はっきりと声を出した。
「以上が、私の提案です」
会議室に、短い沈黙が流れた。
そして、上司の小林さんが頷いた。
「いいね。前向きに検討しよう」
信じられなかった。あの小林さんが、私の提案を認めてくれた。
帰り道、私はコンビニで一番高い缶詰を買った。レオへの、小さなお礼のつもりだった。
家に帰ると、レオは相変わらずソファで寝ていた。私は缶詰を開けて、3粒目の薬を混ぜた。
レオが食べ終わると、いつもの声が響いた。
「おう、今日はマシな缶詰じゃねえか」
「......ありがとう、レオ」
私は素直に言った。
「は? 何言ってんだ、急に」
「今日、すごく良い日だったの。レオのアドバイス、役に立ったわ」
レオは少しバツが悪そうに目を逸らした。
「フン。当然だろ。お前のこと、毎日見てんだからな。誰よりもお前のダメなとこ、知ってんだよ」
その言葉が、不思議と温かかった。
毒舌だけれど、それは無関心とは正反対だった。レオは、ずっと私を見ていてくれた。
その夜、私は珍しく冷蔵庫からビールを取り出した。普段は節約のために買わないけれど、今日は特別な日だ。自分へのささやかなご褒美。
缶を開けて、グラスに注ぐ。金色の液体が泡立つ音が、妙に心地よい。
「レオ、ちょっと待ってて」
私はキッチンの棚から、ずっと取っておいた高級ちゅ~るんを取り出した。普通のちゅ~るんの3倍くらいする、国産まぐろ使用の特別なやつ。
「今日は、お祝いしよう」
レオは不思議そうに私を見上げた。私は高級ちゅ~るんをレオの前に置き、自分はグラスを持った。
「乾杯」
私はグラスを掲げた。レオは首を傾げたあと、ちゅ~るんに舌を伸ばした。
ビールを一口飲む。喉を通る冷たさと、ほのかな苦み。疲れた体に染み渡っていく。
「はあ......美味しい」
私は思わずため息をついた。レオは高級ちゅ~るんに夢中で、ペロペロと音を立てている。その姿が可愛くて、思わず笑みがこぼれた。
4粒目の薬の効果が切れるまで、あと30分くらいだろうか。私は聞いてみたかったことを口にした。
「ねえ、レオ」
「あ?」
レオは顔を上げた。口の周りにちゅ~るんがついている。
「なんでそんなに、私のことを見てるの?」
レオは一瞬、動きを止めた。そして、またちゅ~るんに顔を戻した。
「暇だからな」
そっけない返事。
「お前くらいしか見るもんがねえんだよ。この狭い部屋で、一日中何もすることねえし」
「それだけ?」
「それだけだ」
レオは相変わらずぶっきらぼうに答えた。でも、その横顔を見ていると、何か違うものが見えた気がした。
暇つぶし、と言いながら、私の服装まで覚えている。いつ洗濯したか、いつ掃除したか、全部知っている。元カレのことも、仕事の悩みも、私が口に出したことを全部覚えている。
それは、本当にただの暇つぶしだろうか。
「レオは、優しいんだね」
私は小さく呟いた。
「はあ? 何言ってんだ。俺が優しい? 頭おかしくなったか」
レオは明らかに動揺していた。耳がピクピクと動いている。
「優しくなんかねえよ。ただ、お前があまりにもダメダメだから、見てらんねえだけだ」
「うん、そうだね」
私は笑った。
「でも、それって優しさだと思う」
「......ったく、酔っ払いの相手は疲れんな」
レオはそう言って、また高級ちゅ~るんに顔を戻した。でも、その尻尾は、ゆっくりと左右に揺れていた。機嫌が良い時の、あの動き。
私はビールをもう一口飲んだ。
部屋の中には、私とレオだけ。静かで、少し散らかっていて、決して広くはない空間。
でも今、この瞬間は、悪くないと思った。
いや、悪くないどころか、温かかった。
レオの存在が、この部屋を、そして私の生活を、少しだけ温かくしてくれている。
家族、という言葉が頭に浮かんだ。
レオは私の家族なのかもしれない。血は繋がっていないし、言葉も通じなかった。でも今、こうして悪態をつきながらも、私のことを見守ってくれている。
「ありがとね、レオ」
私はもう一度言った。
「だから何に対してだよ」
「全部」
レオは呆れたように鼻を鳴らした。
「変な女」
でも、その声は、少しだけ優しかった気がした。