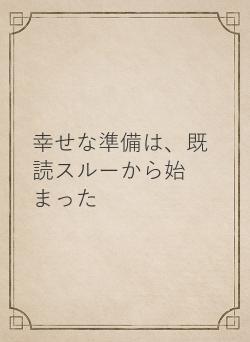私の人生で一番長い一日は、水曜日だった。
朝から企画書のデータが飛び、午後のプレゼンは散々で、上司の小林さんには会議室に呼び出された。「君ね、もう少し危機感持ってくれないと困るんだよ」。そう言われても、私だって必死だった。ただ、必死さが空回りしているだけで。
「すみません」と頭を下げる私の声は、もう何度目かわからないくらい擦り切れていた。どうせ私なんて、会社の歯車としても不良品なのだろう。
退社時刻にはもう外は暗くなっていて、改札を出た途端に雨が降り出した。傘は、もちろん家に置いてきた。コンビニで買うのも癪だったから、私はそのまま濡れながら歩いた。冷たい雨粒が頬を叩く。泣いているみたいだ、と思ったけれど、実際に泣くほどの元気も残っていなかった。
アパートに着く頃には、髪も服もびしょ濡れだった。築30年を超えているこの建物のドアは、湿気を吸って開けにくくなっている。力任せに押し開けると、玄関の奥から小さな鳴き声が聞こえた。
「ただいま、レオ」
私は靴を脱ぎ捨てて、狭い廊下を抜けてリビングに入った。
黒猫のレオは、いつもの定位置であるソファの肘掛けに丸まっていた。私が近づいても、ゆっくりと片目を開けるだけ。まるで「遅いな」とでも言いたげに、大きな欠伸をした。ピンク色の舌がちらりと見えて、また口を閉じる。
「ねえ、聞いてよ。今日ね、最悪だったの」
私はレオの隣にどさりと座り込んだ。濡れた服のまま、レオの背中をそっと撫でる。温かい。生きている温度。この部屋で、私以外に温度を持っているのはレオだけだ。
「企画、全然ダメだって言われちゃって。私、もう向いてないのかな。仕事も恋愛も何もかも、全部うまくいかなくて......」
レオは私の言葉に反応することなく、ただ目を細めた。気持ちよさそうに喉を鳴らす。ゴロゴロという振動が、私の指先に伝わってくる。
「レオはいいよね。何も考えなくていいんだもん」
そう呟いた瞬間、レオは私の手から顔をそらして、また欠伸をした。無関心。完全に、無関心だった。
私は力なく笑った。そうだ、猫に愚痴を聞いてもらおうなんて、そもそも間違っているのだ。レオは私の話なんて聞いていない。ただ、撫でられて気持ちいいから喉を鳴らしているだけ。それ以上でも以下でもない。
それでも、と私は思う。それでも、レオがいてくれるだけで、この部屋に帰る理由ができる。
窓の外では雨が強くなっていた。私は濡れた服を着替えることも忘れて、ただレオの隣でぼんやりと座り続けた。孤独が、部屋の隅から静かに這い寄ってくる。レオの体温だけが、唯一の救いだった。
翌日は休日だった。昨日の疲れを引きずったまま、私は近所の公園まで散歩に出た。気分転換のつもりだったけれど、結局ベンチに座ってぼんやりと木々を眺めているだけだった。
背後から、いきなり声がかけられた。
「猫、飼ってる?」
振り向くと、年齢不詳の男が立っていた。古びたコートを着て、片手には小さな木箱を抱えている。行商人か何かだろうか。胡散臭さが全身から滲み出ていた。
「ええ、まあ......」
私は警戒しながら答えた。怪しい。明らかに怪しい。
「猫ちゃんと、ちゃんとお話しできてる?」
男はにやりと笑った。その笑みに、背筋が少し寒くなる。
「お話? 普通に話しかけてますけど」
「いやいや、そうじゃなくてね。本当の意味での『会話』さ。猫の言葉が、人間の言葉として聞こえたら、素敵だと思わない?」
男は木箱を開けた。中には、小さなカプセル状の薬が並んでいる。透明なカプセルの中に、虹色に光る粉末が入っていた。
「これはね、猫と話せる薬なんだ。飲ませると、猫の言葉が人間の言葉として聞こえるようになる」
私は思わず鼻で笑った。
「はあ? 何それ、詐欺ですか?」
「詐欺だなんて人聞きが悪い。これは正真正銘、本物さ。まあ、信じられないのも無理はないけどね」
男は肩をすくめた。
「特別価格、3万円。どうだい?」
3万円。バカバカしい。そんな金額を、怪しげな薬に払う人間がいるわけがない。私は立ち上がろうとした。
「やっぱり興味ないか。そうだよね、普通は信じないよね」
男は残念そうに木箱を閉じかけた。その瞬間、私の中で何かが引っかかった。
もし本当だったら。
もしレオの本音が聞けたら。
「私のこと、好き?」って聞いて、「大好きだよ」って返ってきたら。それだけで、この孤独は少しは癒えるんじゃないだろうか。
「......いくらって言いました?」
私の声に、男の顔がぱっと明るくなった。
「3万円。でもお嬢さん、ちょっと迷ってるね。わかるよ、その気持ち。じゃあ特別に、今なら9,800円でいいよ」
急に値下げされて、逆に怪しさが増した。でも、9,800円なら......。給料日前でギリギリだけど、出せない金額じゃない。
「本当に効くんですか?」
「保証はできないけどね。ただ、試してみる価値はあると思うよ。猫ちゃんの本音、聞きたくない?」
聞きたい。
レオが私のことをどう思っているのか、本当は知りたい。
「......買います」
私は財布から1万円札を取り出した。手が少し震えている。
男は満足そうに笑って、カプセルを10粒、小さな袋に入れて私に手渡した。
「1粒で約1時間効くからね。大事に使いな」
そして男は、釣り銭の200円を渡すと、あっという間に公園を去っていった。
私の手の中には、虹色に光る怪しげな薬と、残り少ない現金が残された。
これは、間違いなく詐欺だ。
そう頭ではわかっているのに、胸の奥では小さな期待が灯り始めていた。キャリーバッグの中でレオが小さく鳴いた。まるで「バカなことしたな」と呆れているようで、私は苦笑いを浮かべた。
でも、もしかしたら。
その「もしかしたら」に、私は9,800円を賭けてしまったのだった。
家に帰ると、レオは相変わらずソファで丸くなっていた。私は台所でレオの夕食を準備した。いつもの缶詰を開けて、皿に盛る。そして、震える手で薬のカプセルを1粒取り出した。
虹色の粉末がキラキラと光っている。本当に効くのだろうか。いや、効くわけがない。でも......。
私はカプセルを開けて、中身をレオの餌に混ぜ込んだ。粉末はすぐに餌に溶け込んで、見た目には何も変わらなくなった。
「レオ、ごはんだよ」
皿を床に置くと、レオはのそのそと近づいてきた。期待と不安で、胸が苦しい。
もし本当に話せたら、レオは何て言ってくれるだろう。
「大好き」。
「いつもありがとう」。
そんな言葉を期待している自分が、少し恥ずかしかった。でも、聞きたかった。誰かに必要とされている実感が、今の私には必要だった。
レオは餌に顔を近づけて、匂いを嗅いだ。そして、ゆっくりと食べ始めた。
私は固唾を呑んで見守った。心臓の音が、やけに大きく聞こえる。
レオが餌を半分ほど食べた時、それは起こった。
レオがゆっくりと顔を上げた。そして、私を見た。
口が、動いた。
「おい」
私の全身が凍りついた。
今、レオが喋った。確かに、喋った。
「今日の缶詰、安物に変えただろ」
低く、ドスの効いた声だった。まるでヤンキーか不良のような口調。期待していた可愛らしい声とは、まるで違う。
「マズくて食えねえよ、万年独身女」
「えっ......」
私は言葉を失った。いや、違う。これは何かの間違いだ。
「お、おい、レオ?」
「誰がレオだ。俺の名前、お前が勝手につけたんだろうが」
レオは餌から完全に顔を離して、私を見上げた。その目には、明らかに知性が宿っている。
「ったく、いつもいつも、特売の缶詰ばっかり買いやがって。たまには国産の高いやつ買えよ。お前の昼飯より俺の飯のほうが安いってどういうことだよ」
「ちょ、ちょっと待って......」
私は腰を抜かして、その場にへたり込んだ。現実感が完全に崩壊している。
「待つも何も、言いたいことは山ほどあんだよ。まずこの部屋、汚ねえ。洗濯物は溜まってるし、床には髪の毛落ちてるし。お前、掃除って概念知ってんのか?」
レオは尻尾をパタパタと振りながら、容赦なく言葉を続けた。
「あとな、夜中にスマホ見ながら泣くのやめろ。うるせえんだよ。元カレのSNS見て何になるんだ。あんなクズ、とっとと忘れろ」
「な、何で知って......」
「お前が全部喋ってんだろうが。俺に愚痴りながら泣いてたの、忘れたのか? 鳥頭かよ」
私は頭が真っ白になった。
これが、レオの本音。
「大好き」でも「ありがとう」でもなく、ただの悪態と文句。
癒やしを求めて買った薬が、絶望しか与えてくれなかった。私は両手で顔を覆った。9,800円を、ドブに捨てた。
朝から企画書のデータが飛び、午後のプレゼンは散々で、上司の小林さんには会議室に呼び出された。「君ね、もう少し危機感持ってくれないと困るんだよ」。そう言われても、私だって必死だった。ただ、必死さが空回りしているだけで。
「すみません」と頭を下げる私の声は、もう何度目かわからないくらい擦り切れていた。どうせ私なんて、会社の歯車としても不良品なのだろう。
退社時刻にはもう外は暗くなっていて、改札を出た途端に雨が降り出した。傘は、もちろん家に置いてきた。コンビニで買うのも癪だったから、私はそのまま濡れながら歩いた。冷たい雨粒が頬を叩く。泣いているみたいだ、と思ったけれど、実際に泣くほどの元気も残っていなかった。
アパートに着く頃には、髪も服もびしょ濡れだった。築30年を超えているこの建物のドアは、湿気を吸って開けにくくなっている。力任せに押し開けると、玄関の奥から小さな鳴き声が聞こえた。
「ただいま、レオ」
私は靴を脱ぎ捨てて、狭い廊下を抜けてリビングに入った。
黒猫のレオは、いつもの定位置であるソファの肘掛けに丸まっていた。私が近づいても、ゆっくりと片目を開けるだけ。まるで「遅いな」とでも言いたげに、大きな欠伸をした。ピンク色の舌がちらりと見えて、また口を閉じる。
「ねえ、聞いてよ。今日ね、最悪だったの」
私はレオの隣にどさりと座り込んだ。濡れた服のまま、レオの背中をそっと撫でる。温かい。生きている温度。この部屋で、私以外に温度を持っているのはレオだけだ。
「企画、全然ダメだって言われちゃって。私、もう向いてないのかな。仕事も恋愛も何もかも、全部うまくいかなくて......」
レオは私の言葉に反応することなく、ただ目を細めた。気持ちよさそうに喉を鳴らす。ゴロゴロという振動が、私の指先に伝わってくる。
「レオはいいよね。何も考えなくていいんだもん」
そう呟いた瞬間、レオは私の手から顔をそらして、また欠伸をした。無関心。完全に、無関心だった。
私は力なく笑った。そうだ、猫に愚痴を聞いてもらおうなんて、そもそも間違っているのだ。レオは私の話なんて聞いていない。ただ、撫でられて気持ちいいから喉を鳴らしているだけ。それ以上でも以下でもない。
それでも、と私は思う。それでも、レオがいてくれるだけで、この部屋に帰る理由ができる。
窓の外では雨が強くなっていた。私は濡れた服を着替えることも忘れて、ただレオの隣でぼんやりと座り続けた。孤独が、部屋の隅から静かに這い寄ってくる。レオの体温だけが、唯一の救いだった。
翌日は休日だった。昨日の疲れを引きずったまま、私は近所の公園まで散歩に出た。気分転換のつもりだったけれど、結局ベンチに座ってぼんやりと木々を眺めているだけだった。
背後から、いきなり声がかけられた。
「猫、飼ってる?」
振り向くと、年齢不詳の男が立っていた。古びたコートを着て、片手には小さな木箱を抱えている。行商人か何かだろうか。胡散臭さが全身から滲み出ていた。
「ええ、まあ......」
私は警戒しながら答えた。怪しい。明らかに怪しい。
「猫ちゃんと、ちゃんとお話しできてる?」
男はにやりと笑った。その笑みに、背筋が少し寒くなる。
「お話? 普通に話しかけてますけど」
「いやいや、そうじゃなくてね。本当の意味での『会話』さ。猫の言葉が、人間の言葉として聞こえたら、素敵だと思わない?」
男は木箱を開けた。中には、小さなカプセル状の薬が並んでいる。透明なカプセルの中に、虹色に光る粉末が入っていた。
「これはね、猫と話せる薬なんだ。飲ませると、猫の言葉が人間の言葉として聞こえるようになる」
私は思わず鼻で笑った。
「はあ? 何それ、詐欺ですか?」
「詐欺だなんて人聞きが悪い。これは正真正銘、本物さ。まあ、信じられないのも無理はないけどね」
男は肩をすくめた。
「特別価格、3万円。どうだい?」
3万円。バカバカしい。そんな金額を、怪しげな薬に払う人間がいるわけがない。私は立ち上がろうとした。
「やっぱり興味ないか。そうだよね、普通は信じないよね」
男は残念そうに木箱を閉じかけた。その瞬間、私の中で何かが引っかかった。
もし本当だったら。
もしレオの本音が聞けたら。
「私のこと、好き?」って聞いて、「大好きだよ」って返ってきたら。それだけで、この孤独は少しは癒えるんじゃないだろうか。
「......いくらって言いました?」
私の声に、男の顔がぱっと明るくなった。
「3万円。でもお嬢さん、ちょっと迷ってるね。わかるよ、その気持ち。じゃあ特別に、今なら9,800円でいいよ」
急に値下げされて、逆に怪しさが増した。でも、9,800円なら......。給料日前でギリギリだけど、出せない金額じゃない。
「本当に効くんですか?」
「保証はできないけどね。ただ、試してみる価値はあると思うよ。猫ちゃんの本音、聞きたくない?」
聞きたい。
レオが私のことをどう思っているのか、本当は知りたい。
「......買います」
私は財布から1万円札を取り出した。手が少し震えている。
男は満足そうに笑って、カプセルを10粒、小さな袋に入れて私に手渡した。
「1粒で約1時間効くからね。大事に使いな」
そして男は、釣り銭の200円を渡すと、あっという間に公園を去っていった。
私の手の中には、虹色に光る怪しげな薬と、残り少ない現金が残された。
これは、間違いなく詐欺だ。
そう頭ではわかっているのに、胸の奥では小さな期待が灯り始めていた。キャリーバッグの中でレオが小さく鳴いた。まるで「バカなことしたな」と呆れているようで、私は苦笑いを浮かべた。
でも、もしかしたら。
その「もしかしたら」に、私は9,800円を賭けてしまったのだった。
家に帰ると、レオは相変わらずソファで丸くなっていた。私は台所でレオの夕食を準備した。いつもの缶詰を開けて、皿に盛る。そして、震える手で薬のカプセルを1粒取り出した。
虹色の粉末がキラキラと光っている。本当に効くのだろうか。いや、効くわけがない。でも......。
私はカプセルを開けて、中身をレオの餌に混ぜ込んだ。粉末はすぐに餌に溶け込んで、見た目には何も変わらなくなった。
「レオ、ごはんだよ」
皿を床に置くと、レオはのそのそと近づいてきた。期待と不安で、胸が苦しい。
もし本当に話せたら、レオは何て言ってくれるだろう。
「大好き」。
「いつもありがとう」。
そんな言葉を期待している自分が、少し恥ずかしかった。でも、聞きたかった。誰かに必要とされている実感が、今の私には必要だった。
レオは餌に顔を近づけて、匂いを嗅いだ。そして、ゆっくりと食べ始めた。
私は固唾を呑んで見守った。心臓の音が、やけに大きく聞こえる。
レオが餌を半分ほど食べた時、それは起こった。
レオがゆっくりと顔を上げた。そして、私を見た。
口が、動いた。
「おい」
私の全身が凍りついた。
今、レオが喋った。確かに、喋った。
「今日の缶詰、安物に変えただろ」
低く、ドスの効いた声だった。まるでヤンキーか不良のような口調。期待していた可愛らしい声とは、まるで違う。
「マズくて食えねえよ、万年独身女」
「えっ......」
私は言葉を失った。いや、違う。これは何かの間違いだ。
「お、おい、レオ?」
「誰がレオだ。俺の名前、お前が勝手につけたんだろうが」
レオは餌から完全に顔を離して、私を見上げた。その目には、明らかに知性が宿っている。
「ったく、いつもいつも、特売の缶詰ばっかり買いやがって。たまには国産の高いやつ買えよ。お前の昼飯より俺の飯のほうが安いってどういうことだよ」
「ちょ、ちょっと待って......」
私は腰を抜かして、その場にへたり込んだ。現実感が完全に崩壊している。
「待つも何も、言いたいことは山ほどあんだよ。まずこの部屋、汚ねえ。洗濯物は溜まってるし、床には髪の毛落ちてるし。お前、掃除って概念知ってんのか?」
レオは尻尾をパタパタと振りながら、容赦なく言葉を続けた。
「あとな、夜中にスマホ見ながら泣くのやめろ。うるせえんだよ。元カレのSNS見て何になるんだ。あんなクズ、とっとと忘れろ」
「な、何で知って......」
「お前が全部喋ってんだろうが。俺に愚痴りながら泣いてたの、忘れたのか? 鳥頭かよ」
私は頭が真っ白になった。
これが、レオの本音。
「大好き」でも「ありがとう」でもなく、ただの悪態と文句。
癒やしを求めて買った薬が、絶望しか与えてくれなかった。私は両手で顔を覆った。9,800円を、ドブに捨てた。