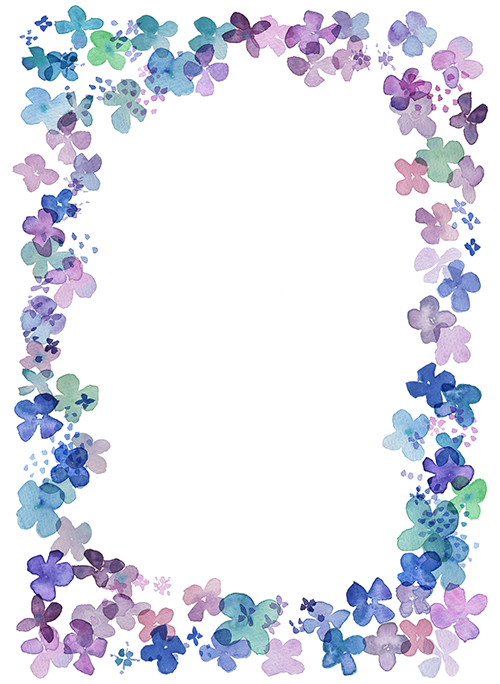カーテンの隙間から、やわらかな乳白色の光がこぼれ落ちている。
まるで世界がまだ半分だけ眠っているような、そんなとろりとした朝の気配。
目覚ましのアラームが騒ぎ出すより少し早く、わたしは意識が覚醒していくのを感じる。でも、身体は動かせない。――いや、正確に言えば、動かしてはいけないのだ。
だって、わたしの胸の上には、ずしりとした重みがのっているのだから。
温もりと、やわらかさと、かすかに香ばしい匂いをまとった、いのちのかたまり。
わたしはそうっと薄目を開けて、その正体を確かめてみる。視界いっぱいに広がるのは、こんがり焼き上がったトーストを思わせる、茶色と黒のしましま模様。キジトラ猫の、まる子だ。
まる子は、わたしの胸を極上のベッドに見立てて、すうすうと気持ちよさそうに寝息を立てている。「すー、すー」という人間みたいな呼吸と、ときおり混じる「ぷすっ」という小さな鼻息。そのリズムに合わせて、わたしの肺もちいさく押されたり、ふっとゆるんだりする。
まるで、しあわせでできた重石だ。
わたしはそっと手を伸ばして、まる子の背中にふれてみる。指先がふかふかと沈んでいく。冬の日に干したてのお布団みたいに、たっぷりと空気をふくんだ毛並みは、触れるだけで指紋のすきまにまで、ぬくもりがしみこんでくる。
「ん……」
まる子がめいわくそうに身じろぎする。ごめんごめん、と心のなかでささやきながら、わたしはもう一度その背中をなでた。ふわふわ、というより、もふもふ。いや、もっと密度のある――なんというか、幸福がぎゅっと詰まったみたいな感触。
まる子は保護猫カフェからやってきた子だ。
出会ったときは、部屋のすみっこでクッションのふりをしながら、気配を消して丸くなっていた。ほかの猫たちが猫じゃらしに夢中で飛びついているなか、ひとりだけ「わたしはここにいませんよ」という顔をして、じっと壁を見つめていたのだ。その背中があまりにもまあるくて、ちいさくて、なんだかほうっておけなくて、わたしは足しげく通いつめた。
それが今ではどうだろう。
わたしの胸の上で、まるで王様のように手足を投げ出して眠りこけている。保護猫カフェ時代の『壁』はどこへやら、今のまる子は「この家の主役はわたし、あなたはお世話係」という確固たる自信にあふれかえっている。
時計を見ると、七時を少し過ぎていた。
「まる子さん、そろそろ起きていただけませんか」
わたしは小声で交渉を持ちかける。
まる子は片目だけうっすらと開けて、黄金色の瞳でちらりとこちらを見た。「人間のスケジュールなんて知らないわ」と言わんばかりの、ひんやりした視線。そして、ふいっと顔をそむけたかと思うと、なんとわたしのアゴの下に頭をねじこんできた。
ぐりぐり、ぐりぐり。
かたい頭蓋骨を押しつけられる感触。これは『拒否』のしるしであり、同時に「もっと撫でなさい」という命令でもある。
わたしは観念して、両手でまる子のあたまを包みこみ、耳のうしろあたりをやさしく掻いてやる。ごろごろ、ごろごろ。喉の奥でちいさなエンジンが始動する音。その振動が胸骨をつたって、わたしの心臓まで直接ひびいてくる。
ああ、もう。会社なんて行きたくないなあ。
このまま、まる子といっしょに布団の海に沈んで、一日じゅう「ごろごろ音」の振動に身をゆだねていたい。
けれど、悲しいかな、わたしは社会人だ。
「よいしょ」
意を決して身体を起こすと、まる子は不満げに「にゃっ」と短く鳴いて、ベッドのはしっこへところりと転がり落ちた。まるで液体のように、とろりと形を変えて、布団のくぼみにすっぽりとおさまる。
わたしは後ろ髪を引かれる思いで、洗面所へと向かった。
◇
その日は、ちょっぴり特別な一日だった。
今日からしばらくのあいだ、完全在宅勤務――いわゆるリモートワークになるのだ。
いつもならバタバタとお化粧をして、パンを口にほおばりながら駅までダッシュするところだけれど、今日はちがう。顔を洗って、ゆったりした部屋着に着替えて、コーヒー豆を挽く余裕さえある。
がりがり、がりがり。
手回しミルの音が、しずかな朝のリビングにやわらかく響きわたる。豆が砕けるかさかさした音と、ふわりと漂いはじめる深煎りの香り。お湯を注ぐと、コーヒーの粉がもこもことふくらんで、茶色いちいさなドームをつくる。
その香りに誘われたのか、まる子がリビングにやってきた。
とことこ、とことこ。
フローリングを叩く肉球の音は、いつ聞いても胸のおくがほどけていくようだ。まる子はわたしの足もとまで来ると、スウェットの裾に爪を立てて、『のび』をした。
ばりばり。
「あーっ、まる子! それお気に入りなのに!」
悲鳴をあげるわたしを見上げて、まる子は「なにか?」と首をかしげる。そして、ごはん皿の前にちょこんとお座りをして、無言の圧力をかけてくる。
はいはい、わかりましたよ。
カリカリのキャットフードを器に入れると、からん、ころんと軽やかな音がした。まる子はそれを待ちかまえていたかのように、がつがつと食べはじめる。
さて、わたしも仕事の準備をしよう。
ダイニングテーブルの上の、読みかけの雑誌やチラシを端っこに寄せて、会社のノートパソコンを開く。マウスをセットして、手帳をひらく。いつもの食卓が、即席のコックピットに早変わりだ。
始業時刻の九時。
Slackの通知音が「しゅっ」と鳴る。チームのメンバーたちが次々と「おはようございます」「業務開始します」と書きこんでいく。
わたしも「おはようございます。本日もよろしくお願いします」と打ちこんで、エンターキーをぽんと押した。
画面の向こうには、数十人の同僚たちがいて、それぞれの場所でそれぞれの仕事を始めている。けれど、この部屋にいるのは、わたしひとりと、いっぴきだけ。
不思議な感覚だ。社会とつながっているような、ふわりと切り離されているような。
かたかた、かたかた。
しずかな部屋に、キーボードを叩く音だけが響く。集中力がすこしずつ研ぎ澄まされていく。メールをチェックして、今日やるべき仕事を整理する。よし、今日は企画書の作成を進めないといけない。
順調な始まりだと思った。
しかし、それは大きなまちがいだった。
ふいに、視界のすみに茶色いかたまりが映りこんだ。
「ん?」
顔を上げると、まる子がテーブルのはじっこに座っている。前足をきちんと揃えて、まるでエジプトの猫神さまのような神妙なおももちで、わたしの手もとをじいっと凝視している。
「まる子、どうしたの?」
声をかけると、まる子は「にゃあ」とちいさく鳴いて、そろり、そろりと近づいてきた。
そして――
どさっ。
なんのためらいもなく、キーボードの上に横たわったのだ。
「ちょ、ちょっと! まる子さん!?」
画面には「あlkjdf;あlkjfdさ」という謎の文字列が爆発的に入力されている。わたしはあわててまる子を抱きあげようとするが、まる子は液状化現象を起こして、テーブルにぺったりへばりついて抵抗する。
「重い、重いよまる子!」
まる子は「ここがいちばん暖かい場所だってこと、わかってるのよ」という顔をしている。ノートパソコンの排熱が、猫にとっては極上の床暖房なのだ。
「どいてー、お仕事できないよー」
わたしは懇願しながら、なんとかまる子をパソコンのよこに移動させる。まる子は不服そうにしっぽをぱたん、ぱたんと揺らしながらも、マウスパッドの半分を占領するかたちで落ち着いた。
カーソルを動かそうとすると、まる子の前足がじゃまをする。マウスを動かすたびに、まる子のひげがわたしの手にくすぐったくふれる。
「……これ、お仕事になるのかな」
不安がよぎる。でも、まる子には悪気なんてこれっぽっちもない。「あなたがおうちにいるなら、わたしの相手をするのが当然でしょう?」という絶対的な正義が、そのまあるい背中からただよっている。
むしろ、まる子にとっては「お仕事のじゃまをしてあげるのが、わたしのお仕事」だと思っている節がある。
わたしがキーボードを叩く指の動きを目で追って、ときおり「えいっ」と猫パンチを繰り出してくる。画面上のカーソルを虫か何かだと思っているらしく、モニターに顔を近づけて「かかかっ」と歯を鳴らす。
かわいい。
くやしいけれど、猛烈にかわいい。
企画書の進捗は亀のあゆみだ。一行書いては、まる子をなで、二行書いては、まる子の猫パンチをかわす。
まるで、やわらかい障害物競走をしているみたいだ。
◇
お昼休み。
わたしは冷蔵庫のあまりもので、かんたんなパスタをこしらえた。
湯気のたつお皿をテーブルに運ぶと、まる子がまたしても「検品」にやってくる。
くんくん、くんくん。
お鼻をひくひくさせて匂いを嗅ぎ、「ふん、人間の食べものか」と興味を失ってさっさと去っていく。その一連の動作が、なんだか気位の高い美食家みたいでおかしい。
窓を開けると、春の風がふわりと吹きこんできた。
レースのカーテンがふうわりと揺れて、床に落ちた光のパッチワークがゆらゆらと踊る。まる子はその光のなかにごろんと寝転んで、おなかを天井に向けて「へそ天」のポーズをとった。
無防備すぎる。
野生の本能なんて、どこかに置き忘れてきたのだろうか。
白いおなかの毛が、光を浴びてきらきらと輝いている。それはまるで、ふわふわの雲を切り取って、そこにそっと置いたみたいだ。
わたしはパスタをくるくる巻き取りながら、その光景をぼんやりと眺める。
会社にいれば、ランチタイムは戦場だ。混みあうエレベーターに乗り、行列のできるお店に並び、時計を気にしながらあわてて食べる。食べた気がしないことも多い。
でも、今日はちがう。
猫がひなたで昼寝をしている、ただそれだけの光景を見ているだけで、心のささくれがひとつずつ、ていねいに削り取られていくような気がする。
「お昼寝日和だねえ」
ひとりごとをつぶやくと、まる子の耳がぴくりと動いた。
猫はいいなあ。
生きているだけで、だれかをしあわせにして、自分も気持ちよくて。
わたしも来世は、いいおうちで飼われる猫になりたい。
◇
午後のお仕事は、すこし緊張感のあるものだった。
三時から、部内のZoom定例会議があるのだ。
この会議には、あの上司が参加する。竹中課長だ。
竹中課長は、絵に描いたような堅物だ。いつも眉間にしわを寄せ、眼鏡の奥の目は笑っていない。口ぐせは「進捗はどうなってる?」「根拠は?」「それ、何の利益につながるの?」。
部下たちは彼を『鉄仮面』と呼んでおそれている。わたしも例外ではない。先週提出した資料も、「論理が甘い」と一蹴されて戻ってきたばかりだ。
時間になり、わたしは緊張した面持ちでZoomに接続した。
画面分割されたモニターに、同僚たちの顔が次々と映しだされる。みんな、自宅だったり、バーチャル背景だったりするけれど、表情は一様にかたい。
最後に、竹中課長が入ってきた。
背景は殺風景な白い壁。着くずすことのないスーツ姿。画面越しでも伝わってくるぴりぴりとしたオーラ。
「では、定例を始める。まずはAチームの報告から」
抑揚のない声がスピーカーから流れる。
空気が重い。まるで深海にいるような圧迫感だ。だれも余計なことは喋らない。必要な数字と事実だけが淡々と報告されていく。
わたしの出番はまだ先だ。手のひらの汗を拭きながら、画面を見つめる。
そのときだった。
足もとで、なにかが動いた気配がした。
いやな予感がした。
視線を落とさずに、足の指先だけで探る。温かい毛玉の感触。
まる子だ。
さっきまでひなたぼっこをしていたはずなのに、なぜこのタイミングで?
まる子は、わたしの膝のうえに前足をかけた。「乗せて」という合図だ。
だめだめ、今はだめ。
わたしは目だけで「ステイ」の合図を送るが、まる子に通じるはずもない。
「にゃっ」
ちいさく、しかしはっきりとした抗議の声。
画面のなかの竹中課長が、眉をひそめた気がした。マイクはオンになっている。
まずい。
わたしは冷や汗をかきながら、そっとマイクをミュートにしようとマウスに手を伸ばした。
その瞬間。
まる子が、ロケットのような瞬発力で膝のうえに飛び乗ってきたのだ。
どすん!
机が揺れる。カメラのアングルがずれる。
そして、わたしの顔の前に、巨大な茶色いおしりが出現した。
画面に映っているのは、わたしの顔ではない。どアップの、猫の肛門と、ふさふさのしっぽだ。
「ああっ!」
思わず声が出る。
まる子は「ふう、やっと落ち着いた」と言わんばかりに、キーボードの上、それもカメラの真ん前で香箱座りを決めこんだ。
画面は完全に、茶色い毛並みで埋めつくされている。まるで突然、カメラが毛皮のコートのなかに突っこんだみたいだ。
「な、なにこれ!」
あわててまる子をどかそうとするが、まる子は「動きませんよ」とばかりに石のようにかたまっている。
スピーカーから、ざわめきが聞こえる。
「え?」「猫?」「こはるさん、だいじょうぶ?」
同僚たちの声。
そして、竹中課長の声がひびいた。
「……おい」
終わった。
神聖なる業務報告の場を、猫のおしりで汚してしまった。こっぴどく怒られる。始末書ものかもしれない。
わたしは震える手で、なんとかまる子を抱きかかえ、画面のわきへと移動させた。
カメラの前に、わたしの青ざめた顔と、抱えられてきょとんとしているまる子の顔がならんで映る。
「す、すみません! 猫が、乱入してしまいまして……すぐにお部屋の外に出しますので!」
わたしは早口で謝罪し、立ちあがろうとした。
そのときだ。
「……ちょっと待って」
竹中課長の声が、いつもより低く、しかしどこか震えていた。
怒られる。
わたしは身をすくめた。
「その猫……キジトラ、か?」
「は、はい?」
予想外の質問に、わたしは固まった。
画面のなかの竹中課長を見る。
いつも鉄仮面のような無表情の課長が、画面に顔を近づけている。眼鏡の位置を直し、目を細めている。
「靴下履いてるみたいな模様だな。足先だけ白くて」
「あ、はい。そうなんです。足袋猫っていうか……」
「……」
沈黙が流れる。
そして、信じられないことが起きた。
あの竹中課長の口もとが、ふにゃりとゆるんだのだ。
「いい毛並みだ。……うちにも、いるんだよ」
「え?」
「黒猫なんだがね。会議中になると、かならずモニターの裏から手を出してくるんだ」
ええええっ!?
Zoomの画面上に、衝撃が走ったのがわかった。全員の目が点になっている。あの竹中課長が? 猫? しかもデレている?
課長はこほんと咳払いをひとつして、すこし照れくさそうにつづけた。
「いや、猫っていうのは、どうしてこう、忙しいときに限って構ってくれと来るんだろうな。……その子、名前は?」
「あ、まる子です」
「まる子か。……いい名前だ」
課長の目が、完全に「猫好きのおじさん」の目になっていた。
その瞬間、張りつめていた空気が一気に弾けた。
「課長、猫飼ってたんですか!?」
「うちも実は犬がいるんです!」
「まる子ちゃん、かわいい〜! カメラ目線ください!」
ミュートを解除して、次々に口を開く同僚たち。
堅苦しい会議の場が、一瞬にしてオンラインペット自慢大会のような温かい空気につつまれた。
まる子はといえば、自分が注目の的であることを理解しているのか、カメラに向かって「にゃーん」とひと鳴きした。
そのあざといほどに完璧な鳴き声に、画面の向こうで数人が「うわぁ……」と悶絶するのが見えた。竹中課長も、口もとを手で覆ってニヤけそうになるのを必死に堪えている。
その後、会議はおどろくほどスムーズに進んだ。
というより、みんなの心がすこしやわらかくなったおかげで、意見交換が活発になり、以前より建設的な議論ができたのだ。
竹中課長も「まあ、そういう視点もありだな」と、いつになく寛容だった。
会議の終わりぎわ、課長は言った。
「……たまには、こういうのも悪くないな。みんな、在宅ワークでストレスも溜まってるだろうが、適度に息抜きするように」
そう言って通信を切る課長の顔は、憑きものが落ちたように穏やかだった。
◇
パソコンを閉じると、窓の外はもう夕焼けに染まっていた。
茜色の光が部屋の奥まで差しこみ、空気中のほこりが金粉のようにきらきらと舞っている。
わたしは大きく息を吐きだして、椅子の背もたれに身体をあずけた。
どっと疲れが出たけれど、それは心地よい疲れだった。心の芯がじんわりとあたたかい。まるで、いい湯加減のお風呂からあがったばかりのような、ほかほかとした感覚。
足もとを見ると、まる子が満足げに毛づくろいをしている。
ピンク色の舌で、ていねいに足をなめ、顔を洗う。くしくし、くしくし。その動作のひとつひとつが、見ているだけで時間を忘れさせる芸術だ。
「まる子」
わたしは床に座りこみ、まる子を抱きあげた。
抵抗せずに、されるがままになっている。重たい身体をあずけてくる、信頼の重み。
「今日はありがとう。まる子のおかげで、救われたよ」
大袈裟じゃなく、ほんとうにそう思う。
あのぴりぴりした空気を変えられるのは、優秀なビジネスマンの弁論でも、的確なデータ分析でもない。
ただそこにいて、「にゃあ」と鳴くだけの、このちいさな生きものの力なのだ。
合理性とか、効率とか、数字とか。
大人はそういうもので世界を測ろうとするけれど、ほんとうに大切なことは、もっとやわらかくて、かたちのない場所にあるのかもしれない。
まる子は「なに言ってるの?」という顔で、わたしの鼻先をぺろりとなめた。
ざりっとした舌の感触。
ちょっと痛くて、くすぐったくて、涙が出るほど愛おしい。
「おなかすいたね」
「にゃっ」
その返事は、今日いちばんの元気よさだった。
わたしは立ちあがり、キッチンへと向かう。
缶詰を開ける「ぱかっ」という音。お皿を置く音。まる子が食べる「はふはふ」という音。
冷蔵庫からビールを取りだし、ぷしゅっと開ける。
ひとくち飲むと、炭酸が喉を弾けて、一日の疲れを洗い流してくれる。
まる子はごはんを食べ終えると、またソファの上に戻り、今度はハリネズミみたいにまあるくなって眠る体勢に入った。
働きもののわたしと、眠りのプロフェッショナルのまる子。
生活のリズムはぜんぜんちがうけれど、こうして同じ空間で、同じ空気を吸っているだけで、パズルのピースがかちっとはまるような安心感がある。
明日もまた、まる子はお仕事のじゃまをするだろう。
キーボードの上に乗るし、大事な書類を枕にするし、Zoom会議でマイクを乗っ取るかもしれない。
でも、それでいい。
それがいい。
スケジュールよりも、予測不能な猫の気まぐれのほうが、人生を豊かにしてくれることを、わたしは今日知ってしまったから。
窓の外では、一番星が光りはじめていた。
今日も、いい一日だった。
そして明日もきっと、お昼寝日和だ。
わたしはソファの上のあたたかい毛玉に顔を埋め、ふかく、ふかく息を吸いこんだ。
お日さまの匂いと、かすかなミルクの匂い。
それは、世界でいちばんやさしい、しあわせの匂いだった。
まるで世界がまだ半分だけ眠っているような、そんなとろりとした朝の気配。
目覚ましのアラームが騒ぎ出すより少し早く、わたしは意識が覚醒していくのを感じる。でも、身体は動かせない。――いや、正確に言えば、動かしてはいけないのだ。
だって、わたしの胸の上には、ずしりとした重みがのっているのだから。
温もりと、やわらかさと、かすかに香ばしい匂いをまとった、いのちのかたまり。
わたしはそうっと薄目を開けて、その正体を確かめてみる。視界いっぱいに広がるのは、こんがり焼き上がったトーストを思わせる、茶色と黒のしましま模様。キジトラ猫の、まる子だ。
まる子は、わたしの胸を極上のベッドに見立てて、すうすうと気持ちよさそうに寝息を立てている。「すー、すー」という人間みたいな呼吸と、ときおり混じる「ぷすっ」という小さな鼻息。そのリズムに合わせて、わたしの肺もちいさく押されたり、ふっとゆるんだりする。
まるで、しあわせでできた重石だ。
わたしはそっと手を伸ばして、まる子の背中にふれてみる。指先がふかふかと沈んでいく。冬の日に干したてのお布団みたいに、たっぷりと空気をふくんだ毛並みは、触れるだけで指紋のすきまにまで、ぬくもりがしみこんでくる。
「ん……」
まる子がめいわくそうに身じろぎする。ごめんごめん、と心のなかでささやきながら、わたしはもう一度その背中をなでた。ふわふわ、というより、もふもふ。いや、もっと密度のある――なんというか、幸福がぎゅっと詰まったみたいな感触。
まる子は保護猫カフェからやってきた子だ。
出会ったときは、部屋のすみっこでクッションのふりをしながら、気配を消して丸くなっていた。ほかの猫たちが猫じゃらしに夢中で飛びついているなか、ひとりだけ「わたしはここにいませんよ」という顔をして、じっと壁を見つめていたのだ。その背中があまりにもまあるくて、ちいさくて、なんだかほうっておけなくて、わたしは足しげく通いつめた。
それが今ではどうだろう。
わたしの胸の上で、まるで王様のように手足を投げ出して眠りこけている。保護猫カフェ時代の『壁』はどこへやら、今のまる子は「この家の主役はわたし、あなたはお世話係」という確固たる自信にあふれかえっている。
時計を見ると、七時を少し過ぎていた。
「まる子さん、そろそろ起きていただけませんか」
わたしは小声で交渉を持ちかける。
まる子は片目だけうっすらと開けて、黄金色の瞳でちらりとこちらを見た。「人間のスケジュールなんて知らないわ」と言わんばかりの、ひんやりした視線。そして、ふいっと顔をそむけたかと思うと、なんとわたしのアゴの下に頭をねじこんできた。
ぐりぐり、ぐりぐり。
かたい頭蓋骨を押しつけられる感触。これは『拒否』のしるしであり、同時に「もっと撫でなさい」という命令でもある。
わたしは観念して、両手でまる子のあたまを包みこみ、耳のうしろあたりをやさしく掻いてやる。ごろごろ、ごろごろ。喉の奥でちいさなエンジンが始動する音。その振動が胸骨をつたって、わたしの心臓まで直接ひびいてくる。
ああ、もう。会社なんて行きたくないなあ。
このまま、まる子といっしょに布団の海に沈んで、一日じゅう「ごろごろ音」の振動に身をゆだねていたい。
けれど、悲しいかな、わたしは社会人だ。
「よいしょ」
意を決して身体を起こすと、まる子は不満げに「にゃっ」と短く鳴いて、ベッドのはしっこへところりと転がり落ちた。まるで液体のように、とろりと形を変えて、布団のくぼみにすっぽりとおさまる。
わたしは後ろ髪を引かれる思いで、洗面所へと向かった。
◇
その日は、ちょっぴり特別な一日だった。
今日からしばらくのあいだ、完全在宅勤務――いわゆるリモートワークになるのだ。
いつもならバタバタとお化粧をして、パンを口にほおばりながら駅までダッシュするところだけれど、今日はちがう。顔を洗って、ゆったりした部屋着に着替えて、コーヒー豆を挽く余裕さえある。
がりがり、がりがり。
手回しミルの音が、しずかな朝のリビングにやわらかく響きわたる。豆が砕けるかさかさした音と、ふわりと漂いはじめる深煎りの香り。お湯を注ぐと、コーヒーの粉がもこもことふくらんで、茶色いちいさなドームをつくる。
その香りに誘われたのか、まる子がリビングにやってきた。
とことこ、とことこ。
フローリングを叩く肉球の音は、いつ聞いても胸のおくがほどけていくようだ。まる子はわたしの足もとまで来ると、スウェットの裾に爪を立てて、『のび』をした。
ばりばり。
「あーっ、まる子! それお気に入りなのに!」
悲鳴をあげるわたしを見上げて、まる子は「なにか?」と首をかしげる。そして、ごはん皿の前にちょこんとお座りをして、無言の圧力をかけてくる。
はいはい、わかりましたよ。
カリカリのキャットフードを器に入れると、からん、ころんと軽やかな音がした。まる子はそれを待ちかまえていたかのように、がつがつと食べはじめる。
さて、わたしも仕事の準備をしよう。
ダイニングテーブルの上の、読みかけの雑誌やチラシを端っこに寄せて、会社のノートパソコンを開く。マウスをセットして、手帳をひらく。いつもの食卓が、即席のコックピットに早変わりだ。
始業時刻の九時。
Slackの通知音が「しゅっ」と鳴る。チームのメンバーたちが次々と「おはようございます」「業務開始します」と書きこんでいく。
わたしも「おはようございます。本日もよろしくお願いします」と打ちこんで、エンターキーをぽんと押した。
画面の向こうには、数十人の同僚たちがいて、それぞれの場所でそれぞれの仕事を始めている。けれど、この部屋にいるのは、わたしひとりと、いっぴきだけ。
不思議な感覚だ。社会とつながっているような、ふわりと切り離されているような。
かたかた、かたかた。
しずかな部屋に、キーボードを叩く音だけが響く。集中力がすこしずつ研ぎ澄まされていく。メールをチェックして、今日やるべき仕事を整理する。よし、今日は企画書の作成を進めないといけない。
順調な始まりだと思った。
しかし、それは大きなまちがいだった。
ふいに、視界のすみに茶色いかたまりが映りこんだ。
「ん?」
顔を上げると、まる子がテーブルのはじっこに座っている。前足をきちんと揃えて、まるでエジプトの猫神さまのような神妙なおももちで、わたしの手もとをじいっと凝視している。
「まる子、どうしたの?」
声をかけると、まる子は「にゃあ」とちいさく鳴いて、そろり、そろりと近づいてきた。
そして――
どさっ。
なんのためらいもなく、キーボードの上に横たわったのだ。
「ちょ、ちょっと! まる子さん!?」
画面には「あlkjdf;あlkjfdさ」という謎の文字列が爆発的に入力されている。わたしはあわててまる子を抱きあげようとするが、まる子は液状化現象を起こして、テーブルにぺったりへばりついて抵抗する。
「重い、重いよまる子!」
まる子は「ここがいちばん暖かい場所だってこと、わかってるのよ」という顔をしている。ノートパソコンの排熱が、猫にとっては極上の床暖房なのだ。
「どいてー、お仕事できないよー」
わたしは懇願しながら、なんとかまる子をパソコンのよこに移動させる。まる子は不服そうにしっぽをぱたん、ぱたんと揺らしながらも、マウスパッドの半分を占領するかたちで落ち着いた。
カーソルを動かそうとすると、まる子の前足がじゃまをする。マウスを動かすたびに、まる子のひげがわたしの手にくすぐったくふれる。
「……これ、お仕事になるのかな」
不安がよぎる。でも、まる子には悪気なんてこれっぽっちもない。「あなたがおうちにいるなら、わたしの相手をするのが当然でしょう?」という絶対的な正義が、そのまあるい背中からただよっている。
むしろ、まる子にとっては「お仕事のじゃまをしてあげるのが、わたしのお仕事」だと思っている節がある。
わたしがキーボードを叩く指の動きを目で追って、ときおり「えいっ」と猫パンチを繰り出してくる。画面上のカーソルを虫か何かだと思っているらしく、モニターに顔を近づけて「かかかっ」と歯を鳴らす。
かわいい。
くやしいけれど、猛烈にかわいい。
企画書の進捗は亀のあゆみだ。一行書いては、まる子をなで、二行書いては、まる子の猫パンチをかわす。
まるで、やわらかい障害物競走をしているみたいだ。
◇
お昼休み。
わたしは冷蔵庫のあまりもので、かんたんなパスタをこしらえた。
湯気のたつお皿をテーブルに運ぶと、まる子がまたしても「検品」にやってくる。
くんくん、くんくん。
お鼻をひくひくさせて匂いを嗅ぎ、「ふん、人間の食べものか」と興味を失ってさっさと去っていく。その一連の動作が、なんだか気位の高い美食家みたいでおかしい。
窓を開けると、春の風がふわりと吹きこんできた。
レースのカーテンがふうわりと揺れて、床に落ちた光のパッチワークがゆらゆらと踊る。まる子はその光のなかにごろんと寝転んで、おなかを天井に向けて「へそ天」のポーズをとった。
無防備すぎる。
野生の本能なんて、どこかに置き忘れてきたのだろうか。
白いおなかの毛が、光を浴びてきらきらと輝いている。それはまるで、ふわふわの雲を切り取って、そこにそっと置いたみたいだ。
わたしはパスタをくるくる巻き取りながら、その光景をぼんやりと眺める。
会社にいれば、ランチタイムは戦場だ。混みあうエレベーターに乗り、行列のできるお店に並び、時計を気にしながらあわてて食べる。食べた気がしないことも多い。
でも、今日はちがう。
猫がひなたで昼寝をしている、ただそれだけの光景を見ているだけで、心のささくれがひとつずつ、ていねいに削り取られていくような気がする。
「お昼寝日和だねえ」
ひとりごとをつぶやくと、まる子の耳がぴくりと動いた。
猫はいいなあ。
生きているだけで、だれかをしあわせにして、自分も気持ちよくて。
わたしも来世は、いいおうちで飼われる猫になりたい。
◇
午後のお仕事は、すこし緊張感のあるものだった。
三時から、部内のZoom定例会議があるのだ。
この会議には、あの上司が参加する。竹中課長だ。
竹中課長は、絵に描いたような堅物だ。いつも眉間にしわを寄せ、眼鏡の奥の目は笑っていない。口ぐせは「進捗はどうなってる?」「根拠は?」「それ、何の利益につながるの?」。
部下たちは彼を『鉄仮面』と呼んでおそれている。わたしも例外ではない。先週提出した資料も、「論理が甘い」と一蹴されて戻ってきたばかりだ。
時間になり、わたしは緊張した面持ちでZoomに接続した。
画面分割されたモニターに、同僚たちの顔が次々と映しだされる。みんな、自宅だったり、バーチャル背景だったりするけれど、表情は一様にかたい。
最後に、竹中課長が入ってきた。
背景は殺風景な白い壁。着くずすことのないスーツ姿。画面越しでも伝わってくるぴりぴりとしたオーラ。
「では、定例を始める。まずはAチームの報告から」
抑揚のない声がスピーカーから流れる。
空気が重い。まるで深海にいるような圧迫感だ。だれも余計なことは喋らない。必要な数字と事実だけが淡々と報告されていく。
わたしの出番はまだ先だ。手のひらの汗を拭きながら、画面を見つめる。
そのときだった。
足もとで、なにかが動いた気配がした。
いやな予感がした。
視線を落とさずに、足の指先だけで探る。温かい毛玉の感触。
まる子だ。
さっきまでひなたぼっこをしていたはずなのに、なぜこのタイミングで?
まる子は、わたしの膝のうえに前足をかけた。「乗せて」という合図だ。
だめだめ、今はだめ。
わたしは目だけで「ステイ」の合図を送るが、まる子に通じるはずもない。
「にゃっ」
ちいさく、しかしはっきりとした抗議の声。
画面のなかの竹中課長が、眉をひそめた気がした。マイクはオンになっている。
まずい。
わたしは冷や汗をかきながら、そっとマイクをミュートにしようとマウスに手を伸ばした。
その瞬間。
まる子が、ロケットのような瞬発力で膝のうえに飛び乗ってきたのだ。
どすん!
机が揺れる。カメラのアングルがずれる。
そして、わたしの顔の前に、巨大な茶色いおしりが出現した。
画面に映っているのは、わたしの顔ではない。どアップの、猫の肛門と、ふさふさのしっぽだ。
「ああっ!」
思わず声が出る。
まる子は「ふう、やっと落ち着いた」と言わんばかりに、キーボードの上、それもカメラの真ん前で香箱座りを決めこんだ。
画面は完全に、茶色い毛並みで埋めつくされている。まるで突然、カメラが毛皮のコートのなかに突っこんだみたいだ。
「な、なにこれ!」
あわててまる子をどかそうとするが、まる子は「動きませんよ」とばかりに石のようにかたまっている。
スピーカーから、ざわめきが聞こえる。
「え?」「猫?」「こはるさん、だいじょうぶ?」
同僚たちの声。
そして、竹中課長の声がひびいた。
「……おい」
終わった。
神聖なる業務報告の場を、猫のおしりで汚してしまった。こっぴどく怒られる。始末書ものかもしれない。
わたしは震える手で、なんとかまる子を抱きかかえ、画面のわきへと移動させた。
カメラの前に、わたしの青ざめた顔と、抱えられてきょとんとしているまる子の顔がならんで映る。
「す、すみません! 猫が、乱入してしまいまして……すぐにお部屋の外に出しますので!」
わたしは早口で謝罪し、立ちあがろうとした。
そのときだ。
「……ちょっと待って」
竹中課長の声が、いつもより低く、しかしどこか震えていた。
怒られる。
わたしは身をすくめた。
「その猫……キジトラ、か?」
「は、はい?」
予想外の質問に、わたしは固まった。
画面のなかの竹中課長を見る。
いつも鉄仮面のような無表情の課長が、画面に顔を近づけている。眼鏡の位置を直し、目を細めている。
「靴下履いてるみたいな模様だな。足先だけ白くて」
「あ、はい。そうなんです。足袋猫っていうか……」
「……」
沈黙が流れる。
そして、信じられないことが起きた。
あの竹中課長の口もとが、ふにゃりとゆるんだのだ。
「いい毛並みだ。……うちにも、いるんだよ」
「え?」
「黒猫なんだがね。会議中になると、かならずモニターの裏から手を出してくるんだ」
ええええっ!?
Zoomの画面上に、衝撃が走ったのがわかった。全員の目が点になっている。あの竹中課長が? 猫? しかもデレている?
課長はこほんと咳払いをひとつして、すこし照れくさそうにつづけた。
「いや、猫っていうのは、どうしてこう、忙しいときに限って構ってくれと来るんだろうな。……その子、名前は?」
「あ、まる子です」
「まる子か。……いい名前だ」
課長の目が、完全に「猫好きのおじさん」の目になっていた。
その瞬間、張りつめていた空気が一気に弾けた。
「課長、猫飼ってたんですか!?」
「うちも実は犬がいるんです!」
「まる子ちゃん、かわいい〜! カメラ目線ください!」
ミュートを解除して、次々に口を開く同僚たち。
堅苦しい会議の場が、一瞬にしてオンラインペット自慢大会のような温かい空気につつまれた。
まる子はといえば、自分が注目の的であることを理解しているのか、カメラに向かって「にゃーん」とひと鳴きした。
そのあざといほどに完璧な鳴き声に、画面の向こうで数人が「うわぁ……」と悶絶するのが見えた。竹中課長も、口もとを手で覆ってニヤけそうになるのを必死に堪えている。
その後、会議はおどろくほどスムーズに進んだ。
というより、みんなの心がすこしやわらかくなったおかげで、意見交換が活発になり、以前より建設的な議論ができたのだ。
竹中課長も「まあ、そういう視点もありだな」と、いつになく寛容だった。
会議の終わりぎわ、課長は言った。
「……たまには、こういうのも悪くないな。みんな、在宅ワークでストレスも溜まってるだろうが、適度に息抜きするように」
そう言って通信を切る課長の顔は、憑きものが落ちたように穏やかだった。
◇
パソコンを閉じると、窓の外はもう夕焼けに染まっていた。
茜色の光が部屋の奥まで差しこみ、空気中のほこりが金粉のようにきらきらと舞っている。
わたしは大きく息を吐きだして、椅子の背もたれに身体をあずけた。
どっと疲れが出たけれど、それは心地よい疲れだった。心の芯がじんわりとあたたかい。まるで、いい湯加減のお風呂からあがったばかりのような、ほかほかとした感覚。
足もとを見ると、まる子が満足げに毛づくろいをしている。
ピンク色の舌で、ていねいに足をなめ、顔を洗う。くしくし、くしくし。その動作のひとつひとつが、見ているだけで時間を忘れさせる芸術だ。
「まる子」
わたしは床に座りこみ、まる子を抱きあげた。
抵抗せずに、されるがままになっている。重たい身体をあずけてくる、信頼の重み。
「今日はありがとう。まる子のおかげで、救われたよ」
大袈裟じゃなく、ほんとうにそう思う。
あのぴりぴりした空気を変えられるのは、優秀なビジネスマンの弁論でも、的確なデータ分析でもない。
ただそこにいて、「にゃあ」と鳴くだけの、このちいさな生きものの力なのだ。
合理性とか、効率とか、数字とか。
大人はそういうもので世界を測ろうとするけれど、ほんとうに大切なことは、もっとやわらかくて、かたちのない場所にあるのかもしれない。
まる子は「なに言ってるの?」という顔で、わたしの鼻先をぺろりとなめた。
ざりっとした舌の感触。
ちょっと痛くて、くすぐったくて、涙が出るほど愛おしい。
「おなかすいたね」
「にゃっ」
その返事は、今日いちばんの元気よさだった。
わたしは立ちあがり、キッチンへと向かう。
缶詰を開ける「ぱかっ」という音。お皿を置く音。まる子が食べる「はふはふ」という音。
冷蔵庫からビールを取りだし、ぷしゅっと開ける。
ひとくち飲むと、炭酸が喉を弾けて、一日の疲れを洗い流してくれる。
まる子はごはんを食べ終えると、またソファの上に戻り、今度はハリネズミみたいにまあるくなって眠る体勢に入った。
働きもののわたしと、眠りのプロフェッショナルのまる子。
生活のリズムはぜんぜんちがうけれど、こうして同じ空間で、同じ空気を吸っているだけで、パズルのピースがかちっとはまるような安心感がある。
明日もまた、まる子はお仕事のじゃまをするだろう。
キーボードの上に乗るし、大事な書類を枕にするし、Zoom会議でマイクを乗っ取るかもしれない。
でも、それでいい。
それがいい。
スケジュールよりも、予測不能な猫の気まぐれのほうが、人生を豊かにしてくれることを、わたしは今日知ってしまったから。
窓の外では、一番星が光りはじめていた。
今日も、いい一日だった。
そして明日もきっと、お昼寝日和だ。
わたしはソファの上のあたたかい毛玉に顔を埋め、ふかく、ふかく息を吸いこんだ。
お日さまの匂いと、かすかなミルクの匂い。
それは、世界でいちばんやさしい、しあわせの匂いだった。